遺品整理
形見分けのお礼の文例を紹介|形見分けの注意点・時期を説明
更新日:2022.02.04 公開日:2022.02.04
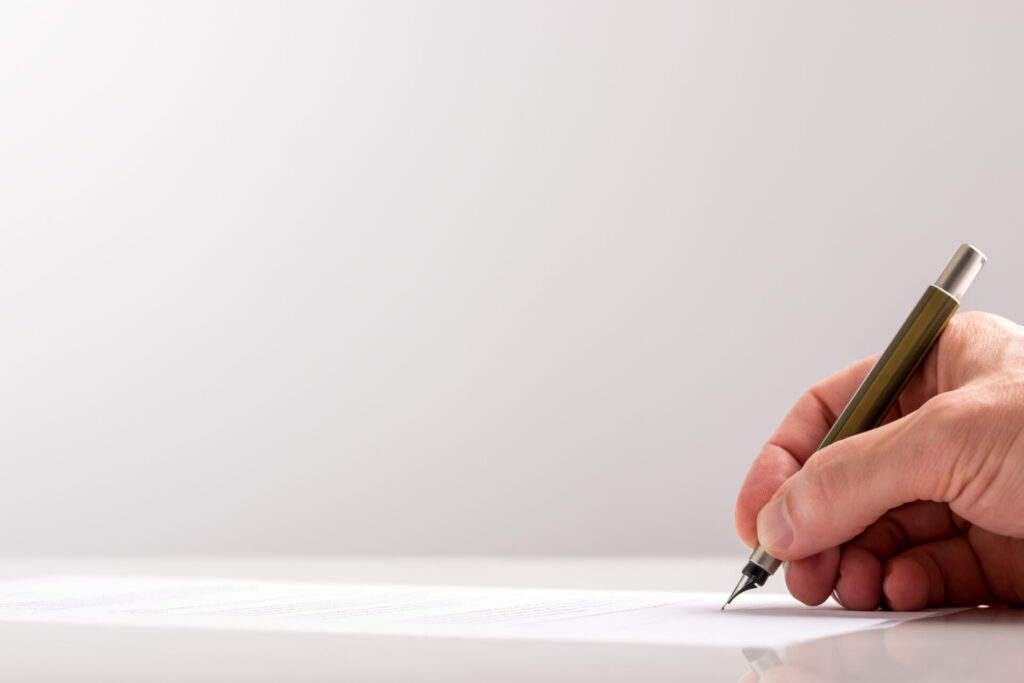
記事のポイントを先取り!
- 形見分けは基本受け取り、お悔やみやお礼の言葉のみを連絡する
- 現金や高価な物は贈与税等の対象になるため注意が必要
- 形見分けは揉めることが多いため慎重に遺族と相談する
- 形見分けを行う時期は宗教によって異なる
個人が亡くなってから四十九日が過ぎたら、そろそろ「形見分け」をする頃合いになってきます。
形見分け時の注意点、受け取った後のお礼や時期などについても知っていきましょう。
そこでこの記事では、形見分けのお礼の文例について詳しく説明していきます。
この機会に、形見分けのお礼の文例を覚えておきましょう。
形見分けでよくあるトラブルについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
形見分けとは
形見分けとは、故人が生前大切に使用していた品物を親族や交友が深かった友人に贈る(分け与える)という、古くから日本にある風習です。
形見を身近に置くことで故人を偲び、供養するという意味の他に、遺品を粗末にしないと言う意味もあります。
形見分けにお礼は必要?
実際に形見分けをいただいた場合、お礼やお返し、またはお悔やみの手紙を書いて送った方がいいかなど、その後の対応がわからない方も多いかと思います。
形見分けをいただいた後にするべき対応を見ていきましょう。
基本的に不要
いただいたらお礼をしたほうがいいと思いがちですが、形見分けでいただく物は元々亡くなった方の遺品となります。
人が亡くなることは喜ばしくないことですので、基本的には特別にお礼を準備する必要はありません。
お礼ではなく連絡をする
形見分けの遺品をいただいたら、無事受け取ったということを連絡するのが一般的です。
会った時にお礼を伝えられるのが一番好ましいですが、遠方の場合は電話で受け取った連絡をしましょう。
もし、仕事などで電話での連絡がなかなかできない場合は、手紙で連絡をしても大丈夫です。
形見分けのお礼の文例
前述した通り、形見分けはプレゼントではないのでお礼を用意する必要はありません。
しかし、一言故人へのお悔やみの言葉や形見分けを受け取ったお礼を遺族へ伝えたほうが、マナーとしてはいいかと思います。
お礼状の書き方は、特に挨拶文などを書く必要はなく、縦書きで結語は敬具にして書きましょう。
文例を載せておきますので、ご参考にしてください。
文例①
先日は形見分けをしていただきまして そのお心遣いに大変恐縮致します
生前ご愛用されていたお品ですので 一生大事にして引き続き使わせて頂きたいと思っております
心から有り難く お礼を申し上げます。
まだまだ寒い日々が続きますが お風邪など召されませんように お体ご自愛くださいませ。
最後になりましたが 謹んでお礼を申し上げますと共に 改めまして故人のご冥福をお祈り申し上げます
文例②
その後 お変わりはございませんでしょうか
○○様が旅立たれてから 随分寂しくなりましたね
生前○○様がご愛用されていた大切なお品を譲り受けて頂き 誠にありがとうございます
大切に使わせて頂きたいと思っております
まだまだお辛い日々を過ごしているかと思いますが どうぞお疲れが出ませんようにお体ご自愛くださいませ
改めて○○様のご冥福を心よりお祈り致します
形見分けの際の注意点
これといった決まりごとなどはありませんが、形見分けを贈る時と受け取る時のマナーがありますので、それぞれご説明します。
現金を受け取る場合には注意が必要
年間で110万円を超えた場合、贈与税が発生してしまいます。
注意したいのは、品物でも価値があると判断された場合、現金と品物の合計が一年の間で110万を超えたとみなされ、贈与税が発生するので注意が必要です。
目上の人には贈らない
形見分けは原則、目上の人が目下の人に贈る習慣となります。希望があった場合にのみ目上の人へ贈りますが、その際は一言無礼をお詫びするようにしましょう。
基本的に受け取る
原則受け取るのがマナーではありますが、もし何らかの理由で受け取れない場合は、丁重にお断りすることもできます。
故人の意思を優先する
もし、遺品の扱い方に対して、故人が生前に残した希望があるならば、故人の意思を優先しましょう。
形見分けはあくまでも習慣なので、故人の意思を尊重することが大切です。
形見分けをする時期
宗教により形見分けをする時期が異なります。
故人が信仰していた宗教にならって行うのが最善だと言えるので、宗教ごとに見ていきましょう。
仏教
仏教では一般的に、四十九日が過ぎてから形見分けを行います。
四十九日の法要は忌明け(きあけ)と言い、故人が仏様のもとへ向かう日であるため、遺族が喪に服す期間が終了します。
しかし地域によっては、必ずしも四十九日が忌明けとは限らず、三十五日で忌明けする場所もあります。
神道
神道の忌明けは五十日祭になるので、それ以降に形見分けをします。
神道では五十日祭を行うと、故人は家を守る守護神になると考えられているため、五十日祭の後に行われます。
キリスト教
キリスト教は大きく分けてカトリックとプロテスタントとありますが、いずれの場合も一ヶ月後を目安に形見分けをします。
形見分けはキリスト教にはない習慣ではありますが、日本では一ヶ月後に形見分けをしていることが多いようです。
スポンサーリンク形見分けでよくあるトラブル
意外かもしれませんが、故人が亡くなった後の形見分けでトラブルになることも少なくはありません。
どんなトラブルが多いのか、見ていきましょう。
遺族との相談不足
一番多いトラブルは、誰が何を貰うかで揉めるケースです。
というのも、遺品の中には貴金属のアクセサリーや故人が収集していたコレクション、着物、書籍など高価なものがある場合があります。
相続権は親族にあるため、友人などへ形見分けする場合は事前にしっかりと、遺族同士で相談してから決めましょう。
また、不要な人に強引に渡してしまってもトラブルの元となるので、希望があるのかどうかも確かめるようにしましょう。
口約束によるトラブル
生前口約束をしていたという場合は、遺族が知らないところで約束をしていることが多い為、トラブルに発展しやすいです。
口約束の場合は、遺族が中心となって慎重に確認することがトラブル回避のポイントです。
税金関係の申告漏れ
貴金属や宝石、絵画などの高価なものを受け取った場合、一年間の間に110万円を超えてしまうと形見分けを貰った側に「贈与税」が課せられてしまいます。
5万円を超える価値がある品物については、「相続税」の対象になり、遺産分割協議書に記載しなくてはいけません。
相続税は合計3千万円までは非課税ですので、気をつけましょう。
一年間で現金、高価な遺品の合計が110万円以下なら非課税ですが、超えた場合は10%の贈与税がかかります。
例えば形見分けが120万だった場合110万は非課税ですが、残りの10万に対して10%の課税が認められ、贈与税は1万円となります。
形見分けのお礼の文例のまとめ

ここまで形見分けをするタイミングや贈る側の注意点についての情報や、受け取る側のお礼や文例などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 形見分けに対して、基本的にはお礼品は不要だが、お礼の言葉等は必要
- 形見分けの際は、基本的に個人の希望に沿った方が良い
- 形見分けでは遺品の分配でトラブルになるため、正式な文書等があると良い
- 形見分けの際には、贈与税や相続税に注意する
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。





