お墓
永代供養とは?費用の相場やメリット・デメリットをわかりやすく解説!
更新日:2023.01.31 公開日:2021.07.03

記事のポイントを先取り!
- 永代供養は寺院や霊園にお墓の管理をしてもらうこと
- 永代供養には様々な埋葬方法がある
- 一般墓より費用が安いことが多い
永代供養とは、故人の供養を自分の代わりに寺院や霊園に管理してもらうことです。
お墓について調べていくとよく目にする言葉ですが、あまり詳しくないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、永代供養の基礎知識からメリット・デメリットを中心にわかりやすく解説していきます。
浄土真宗をはじめとした各宗教ごとの永代供養の費用相場や、お布施は必要かどうかについても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。
- 永代供養とは
- 永代供養のお墓とは
- 永代供養の埋葬方法
- 永代供養の安置する場所
- 永代供養の費用相場
- 永代供養が安い理由
- 各宗派の永代供養の費用相場
- 永代供養のメリット
- 永代供養のデメリット
- 永代供養での法事
- 永代供養にお布施は必要?
- 墓じまいをして「永代供養」する方法
- 一般墓から永代供養に変更は可能?
- 永代供養の選び方のポイント
- 永代供養が向いている人の特徴とは?
- 永代供養が向いていない人の特徴とは?
- 永代供養についてのまとめ
永代供養とは
永代供養とは、日頃からお墓参りをするのが難しい、またはお墓参りすることができない方に代わり、寺院や霊園で供養・管理をしてもらうことを指します。
「永代」と聞くと、依頼した寺院や霊園で永久に供養してもらえるのではないかと考える方も多いのですが、実際は永久に管理してもらえるわけではありません。
永代供養では、33回忌までといったように供養してもらえる期間が定められており、安置期間がすぎると合祀(ごうし)されることになっています。
※合祀とは、他の方の遺骨と合わせて祀ることをいいます。
永代供養は、ライフスタイルの多様化から生まれた制度です。
結婚をせず独身の方や、結婚していても子供がいない方など様々で、従来のお墓の形態で生じる問題を永代供養は解決できます。
年々、このような方々は増加傾向にあり、永代供養も注目を集めています。
永代供養と永代使用の違いとは?
永代供養と似た言葉として永代使用があります。
- 永代供養:寺院や霊園で遺骨の供養・管理をしてもらうこと
- 永代使用:お墓を建立するために購入した土地を永代に使用すること
永代使用では期限を定められておらず、お墓の継承者がいる限りは霊園や寺院から借りている土地を利用し続けることができます。
永代供養は一般的に期間が定められており、その期間を過ぎると合祀される流れになります。
しかし永代使用でも継承者がいなくなった場合は、墓じまいをしその土地の使用権を墓地管理者に返却することになります。
永代使用は、「永代使用権」や「永代使用料」といった形で料金を支払うことになる場合が多く、墓地の価格によっても異なりますが、全国的な相場は70万円ほどとされています。
永代供養のお墓とは
永代供養のお墓は大きく以下の3つに分けることができます。
- 永代供養墓
- 納骨堂
- 樹木葬
永代供養のお墓はそれぞれ特長が異なりますので、以下の内容を参考にしてください。
永代供養墓
永代供養墓は、一般的なお墓に永代供養がついているものです。
永代供養墓では墓石を購入する必要がない場合が多いです。
永代供養墓は、誰と納骨するかという点で合祀墓と個人墓・夫婦墓に分けることができます。
合祀墓
合祀墓は、他の方の遺骨と一緒に納骨するタイプの永代供養墓です。
複数人でお墓を共有しているイメージで、定期的な法要も合同で行われます。
初めから合祀墓に納骨するタイプと、一定期間後に合祀墓に移されるタイプがあります。
費用を抑えることができる点がメリットとしてあげられますが、一度納骨を行うと後から遺骨を取り出すことができない点はデメリットと言えます。
個人墓・夫婦墓
合祀墓とは異なり、個別のスペースに納骨するタイプの永代供養墓です。
1人もしくは夫婦で眠りたいという方向けのお墓で、期限付きのプランが用意されているケースがほとんどです。
期限後も墓地や霊園に管理・供養を任せることができますが、こちらも合祀墓と同様に期限が過ぎると他の遺骨と合祀されます。
納骨堂
納骨堂は、寺院などの一画や、専用のビルなどに設けられていることが多い屋内の墓地・霊園です。
ロッカー型や仏壇型、自動搬送型などさまざまなタイプが用意されています。
納骨堂でも永代供養してくれる場所は多いです。
基本的には個別で遺骨を納めた骨壷を安置できるのと、一般的なお墓に比べ費用が安いのも特徴です。
樹木葬
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を墓標とするタイプのお墓です。
樹木葬の永代供養墓では個別型、集団型、合祀型の3つに分けられます。
個別型では、1つのスペースを利用し、1本の木を植えることができます。集団型や合祀型では、1本の木の周りにスペースを設け、複数の骨壷を埋葬します。
期限付きのプランがほとんどで、17回忌などの節目で合祀される場合が多いです。
自然の中で安らかに眠りたいという方におすすめの永代供養墓です。
樹木葬についてさらに詳しく知りたい方は、「樹木葬とは?樹木葬に関する費用や種類を解説」をご覧ください。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
永代供養の埋葬方法
埋葬方法の違いによって値段が変わることはもちろん、遺骨を埋葬後に分骨・改葬ができるかが変わります。
後に分骨・改葬をしたいとお考えの方は、十分に比較検討しご自身のご希望のプランを選ぶようにしましょう。
個別安置型
個別安置型は遺骨の安置期間が決まっていて、期間中は個別に埋葬され、安置期間がすぎると合祀されるという特徴があります。
安置期間は施設やプランによって異なりますが、33回忌までであることが一般的です。
合祀安置型
合祀安置型は、他の遺骨と合わせて埋葬されるのが特徴です。
費用を安く抑えることができるのがメリットですが、埋葬後に分骨や改葬ができなくなる点がデメリットです。
集合安置型
集合安置型は、安置所を一箇所にまとめられる点は合祀安置型と同じですが、遺骨は別々の骨壷に分ける点が合祀安置型と異なります。
よって、埋葬した後でも遺骨を取り出すことができます。
墓石安置型
墓石安置型は、墓石を建てる一般墓と永代供養の特徴を合わせ持っています。
安置期間内は、墓石の下に遺骨を埋葬し、期間終了後他の方の遺骨と一緒に埋葬されます。
永代供養の安置する場所
永代供養墓は様々な種類がありますが、大きく分けると屋外型と屋内型に分類することができます。
屋外型の永代供養墓
屋外型の永代供養墓は納骨壇型、納骨塔型、墳陵型の3つの種類が存在します。
納骨壇型は、屋外型の永代供養墓の中でもスタンダードな形で、石材で造られた施設にご遺骨を納めます。
納骨塔型は、塔の形や石で作られたモニュメントがあるのが特徴的です。御遺骨は地下に安置することが一般的です。
墳陵型は、前方後円墳や墳丘の形をした大きめの合葬墓です。
屋内型の永代供養墓
屋内型の永代供養墓は霊廟型、納骨塔型、室内ロッカー型の3つの種類が存在します。
霊廟型は、上下の2段に分かれていて、上の段には仏壇、下の段には骨壷を納めるのが一般的です。骨壷が別の所に安置されていて、指定すると移動してくる可動式の物もあります。
納骨塔型は、屋外型の納骨塔型と同様ですが、永代供養墓が屋内にあるか屋外にあるかの差になります。
室内ロッカー型は、個々に区切られたロッカーや店があり、その中に骨壷を納めます。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
永代供養の費用相場
永代供養の費用相場について、各費用の内訳とともに紹介します。
遺骨の埋葬方法別に説明しているので、ぜひお墓選びの参考にしてください。
単独墓
単独墓は一般の墓と同じように、個別で独立しているお墓です。
1つの世帯で持てる専用のお墓になっているため、個人や夫婦、家族で利用できます。
単独墓の費用相場は、全体で40万~300万円と幅が広いです。
主な内訳として永代供養料や永代使用料(区画の使用料)、墓石代が挙げられます。
他にも、管理費が1万~2万円程度かかります。
合祀墓
合祀墓は他のご遺骨と一緒のカロートに納骨されるタイプのお墓を指します。個別のスペースが必要ない点や管理で手間がかからない分、費用も比較的安いです。
合祀墓の一般的な費用相場は、10万~30万円です。
なお管理費や永代使用料、墓石代は発生しません。内訳として、永代供養料のみが発生する仕組みになっています。
集合墓
石碑やプレートは共有しつつ、スペースが個別に設けられているタイプです。一定期間個別のスペースを使用した後、共有のお墓に再納骨されます。
集合墓の費用相場は、20万~70万円程度です。
細かい内訳として、永代使用料やご遺骨の納骨料、戒名の彫刻料が挙げられます。ほかにも管理費も5,000~2万円程度発生するため、チェックが欠かせません。
永代供養が安い理由
永代供養の特徴の1つが費用を大幅に抑えることができる点です。永代供養が費用を安くできる大きな理由が、1つのお墓に複数の遺骨を合祀する点です。
複数の遺骨を合祀するため、その分の墓石や墓標の建立費や敷地の使用料を少なくできます。そのため永代供養の費用は安いプランが数多く用意されています。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
各宗派の永代供養の費用相場
永代供養の費用は宗派によって大きく異なることはありません。
基本的に遺骨をどのように埋葬するかによって、費用は異なります。
各宗派で永代供養をした場合の費用の相場について、合祀墓と集合墓に分けて紹介します。
浄土宗の永代供養の相場
浄土宗は法然を宗祖とし、「南無阿弥陀仏」を唱える宗派になります。
| 合祀墓 | 10万〜30万円 |
| 集合墓 | 20万〜60万円 |
浄土真宗の永代供養の相場
浄土真宗は親鸞を宗祖とし、阿弥陀如来の本願に頼って成仏する「他力本願」という教えがあります。
浄土真宗に永代供養という考え方はないですが、システム的に永代供養と変わらないものは存在します。
| 合祀墓 | 10万〜30万円 |
| 集合墓 | 20万〜120万円 |
浄土真宗では永代供養ができない?
浄土真宗には、阿弥陀如来の本願に頼って死後すぐに極楽浄土に行くことができる「往生即成仏」という考え方があります。
そのため、他の宗教と違い供養を行う必要がありません。
永代供養は「寺院や霊園で遺骨の供養・管理をしてもらうこと」であるという点がこの考えと反するため、まずは菩提寺に相談する必要があります。
曹洞宗の永代供養の相場
曹洞宗は宗から伝わった禅宗で、日本全国に多数の寺院を有しています。
| 合祀墓 | 10万〜30万円 |
| 集合墓 | 50万〜80万円 |
真言宗の永代供養の相場
真言宗は空海を宗祖とし、密教を教える宗派です。
| 合祀墓 | 15万〜45万円 |
| 集合墓 | 50万〜100万円 |
日蓮宗の永代供養の相場
日蓮宗は日蓮を宗祖とし、「南無妙法蓮華経」を唱える宗派になります。
| 合祀墓 | 10万〜20万円 |
| 集合墓 | 15万〜130万円 |
総本山の永代供養
永代供養は各寺院で行うものとは別に、その宗派の総本山で行う本山納骨があります。
本山納骨は遺骨を宗派の総本山に納骨して、供養を行うというものです。
一部地域では、分骨した遺骨を本山納骨するという慣習が残っています。
本山納骨は埋葬方法は合祀となるので、比較的費用を抑えることができます。
| 浄土宗 | 5万円〜 |
| 浄土真宗 | 5万円〜 |
| 曹洞宗 | 3万円〜 |
| 真言宗 | 10万円〜 |
| 日蓮宗 | 5万円〜 |
永代供養のメリット
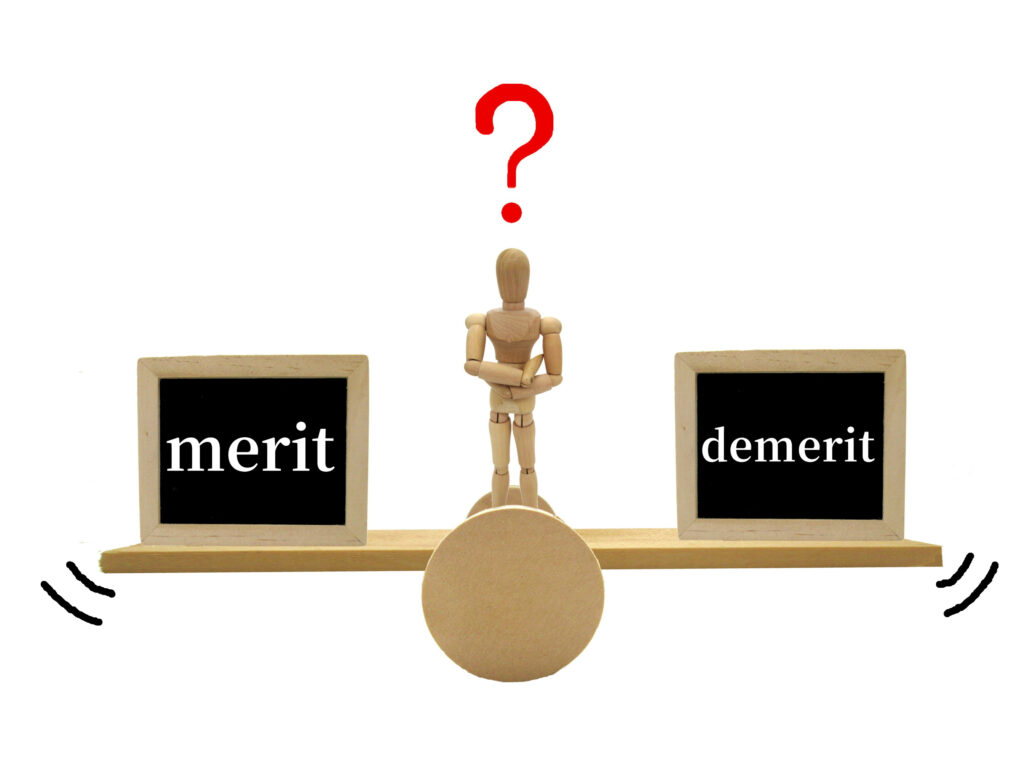
永代供養の主なメリットは以下の4点です。
- 費用が安い
- 維持が簡単
- 宗教・宗派による制限がない
- 生前に購入できる
費用が安い
費用を安く抑えることができる理由は、一般的なお墓のように墓石を建立することがなく、墓石建立のための土地を用意する必要がないためです。
安置期間にもよりますが、一般的な墓石を建立する供養方法に比べて費用を3分の1程度に抑えることも可能です。
お墓の維持が簡単
永代供養は、寺院や霊園などの運営元が管理・供養をしてくれるため、定期的にお墓参りができない方にでも維持することができる方法となっています。
宗教・宗派による制限がない
寺院墓地や霊園の場合は、信仰している宗教や・宗派によっては利用できないということもあります。
しかし、永代供養は宗教・宗派による制限がないため自身の希望に沿った施設を選ぶことができます。
生前に購入できる
生前に寺院や霊園と永代供養の契約を結ぶことができます。
自分の好みに合ったタイプを選ぶことができ、遺族の負担を減らすことが出来ます。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
永代供養のデメリット
永代供養の主なデメリットは以下の4点です。
- 合祀後は遺骨を取り出せない
- お墓の継承ができない
- 周囲の理解を得づらい
- 好きな場所に納骨できない
合祀後は遺骨を取り出せない
永代供養は基本的に、一定期間を過ぎると他の方の遺骨と合祀されるので、後から改葬したいと思っても遺骨を取り出すことができません。
そのため、改葬を考えている方は個別型の永代供養を選び、契約期間内に改葬するかを決める必要があります。
お墓の継承ができない
一般的な墓石を建立するタイプのお墓とは異なり、永代供養では埋葬可能な遺骨の数に制限があります。
また、永代供養では期間終了後は合祀というシステムですので、お墓の継承はできません。
後継者がおり、継承をしていきたいと考えている方には永代供養は不向きです。
周囲の理解を得づらい
永代供養は、近年では一般的な供養形態の1つとなっていますが、墓石を建立する従来のお墓とは見た目の差が大きいため、周囲から反対の声が上がることもあります。
永代供養を検討されている方は、後のトラブルにつなげないためにも事前に周囲の方と相談するようにしましょう。
好きな場所に納骨できない
永代供養では区画が限定されているため、自分が気に入った場所に納骨するのは難しくなります。
スポンサーリンク永代供養での法事
永代供養においては、必ず法事をする必要はありません。
もちろん法事が禁止されているわけではないので、その際のルールやマナーを解説していきます。
法事の際の服装・持ち物
服装に関して、明確な決まりはありませんが、喪服が一番無難となります。
花、お供え物、線香、ろうそく、ゴミ袋などを持参しましょう。
法事の費用
僧侶に読経を依頼する場合は、お布施を持参しましょう。
お布施は、感謝の気持ちを表すものなので、高額を包まなければいけないわけではありません。
無理のない範囲でお布施を包みましょう。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
永代供養にお布施は必要?
永代供養でも納骨の際は通常と変わらず僧侶に読経をしてもらいます。
また、遺骨を管理・供養してもらっている場合でも、三回忌などの年忌法要は行われます。
法要を行う場合、僧侶に読経していただく分のお布施が必要になります。
永代供養で必要になるお布施の相場は、3万~5万円程度です。
墓じまいをして「永代供養」する方法
将来に備えて、墓じまいや永代供養を検討する方もいらっしゃるでしょう。墓じまいをするには、まずご親族や寺院への相談が欠かせません。
特に寺院に相談する際は、墓じまいに至った事情をきちんと伝えるべきです。ご親族や寺院の同意を得たら、カロートの状況を確認します。
ご遺骨が誰のものか、納骨からの年数などが確認すべき項目です。確認が済んだら、永代供養先を決めていきます。
受け入れ先の墓地・霊園が決まったら、改葬許可証の申請も必要です。
まず現在のお墓がある地域の自治体で、改葬許可申請書を入手します。
申請書を記入したら、お墓のある墓地・霊園の管理者に署名・捺印してもらいましょう。なお埋葬証明書を発行してもらうケースも多いです。
次に受け入れ先の墓地・霊園で受入証明書を発行してもらいます。
ほかにも改葬を申請する方とお墓の所有者が異なる場合は、改葬の承諾書も必要です。
以上の書類を揃えて役所に提出すると、改葬許可証が発行されます。
墓じまいの際は、閉眼法要が欠かせません。閉眼法要の準備は、菩提寺や石材店に相談しながら進めていきます。
当日は僧侶に読経していただいたうえで、カロートから骨壺を取り出します。
法要終了後はお墓を解体してもらい、区画も更地にして管理者に返却します。墓じまいが終了すると、永代供養先に納骨する流れです。
すでに使用されているお墓への納骨であれば、納骨式を行うだけで終わります。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
一般墓から永代供養に変更は可能?
結論からいいますと、可能です。
それでは一般墓から永代供養への変更の流れやポイントを見ていきましょう。
- 墓じまいの相談
- 永代供養墓の決定
- 墓じまい
- 変更先に納骨
この流れをもう少し具体的に解説します。
まず、墓じまいの相談や次の永代供養墓を決め、決定でき次第、石材店に頼んで一般墓の墓じまいをします。
墓じまいとは今まで使用していた敷地を更地にして、お寺や霊園に敷地の返却を行うことです。
閉眼法要というお墓から遺骨を取り出す際に魂抜きをした後、墓じまいを行い、それが終わったら永代供養墓に納骨します。
注意点は、やはり大掛かりな作業になるので、墓じまいの作業代や今までお世話になったお寺への感謝代(離壇料など)が多くかかります。
また、元のお寺としてはできる限り離壇してほしくない訳ですから、離壇料を多く請求してきたりなどの問題になることがあるので、相談をする際は慎重になる必要があります。
永代供養の選び方のポイント

永代供養を選ぶポイントとしては、料金、立地、供養方法、納骨方法などが挙げられます。
納骨方法や供養方法は施設ごとによって異なるので、候補となっている施設の方に相談したり、十分に調べてから決定しましょう。
料金に関しては施設によって変わりますが、供養方法によっても大きく変わります。費用の安さだけでなく、供養方法ごとのメリット・デメリットを照らし合わせて後悔のないように判断しましょう。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
永代供養が向いている人の特徴とは?
永代供養がおすすめな方の特徴は、
- 後継者がいない方
- 遺族に負担をかけたくない方
- 先祖とのつながりを重視していない方
などが挙げられます。
お墓の後継者に不安がある場合や、遺族に負担をかけたくないと考えている方にとってはおすすめだと言えます。
後継者がいない方
永代供養墓を選択すると、後継者がいなくなっても寺院や霊園が遺族に代わって供養をしてくれます。
無縁仏になる心配もないため、後継者に不安がある方は永代供養墓を選択するとよいでしょう。
永代供養と無縁仏の違い
永代供養を検討する際、「無縁仏」という言葉も見かけるでしょう。
永代供養と無縁仏は、確かにご遺族が直接管理や供養をしない点では同じです。
ただし無縁仏の場合は、お墓の管理や供養をする方が全くいない状態を指します。一方永代供養の場合は、墓地・霊園の管理者が代行で管理・供養する点が特徴です。
なお、お墓を守る方がいなくて無縁仏になった場合、お墓自体が撤去されます。加えて納骨されていたご遺骨も、他の無縁仏のご遺骨とともに合祀されるのが一般的です。
遺族に負担をかけたくない方
お墓を建立すると、年に数回掃除をし墓石を綺麗に保つ必要があります。
ですので、遺族にお墓の維持や管理の負担をさせたくないという方に向いています。
また遠方でお参りが難しい方や、なんらかの理由で掃除ができない方にとっても永代供養墓を選択することがおすすめです。
先祖とのつながりを重視していない方
一般に、お墓は先祖代々継承していくことになります。
ですが中には個別のお墓にあまり必要性を感じていない方もいると思います。
その場合も、永代供養墓に納骨することがおすすめです。
永代供養が向いていない人の特徴とは?
逆に永代供養をおすすめできない方の特徴は、
- 周りの親族の方から理解を得られない方
- 先祖代々受け継いできたお墓を大事にされたい方
などが挙げられます。
周りの親族の方から理解を得られない方
永代供養は近年浸透し始めている供養方法ではありますが、永代供養は一般的に一定期間を過ぎると合祀される流れになりますので、親族の中には受け入れがたい人もいることが考えられます。
その場合、事前によく理解を得ておかないとのちにトラブルに発展することも考えられます。
親族の中で永代供養に反対している人がいるのであれば、永代供養は避けることが無難です。
先祖代々受け継いできたお墓を大事にされたい方
先祖とのつながりを大事にしたい人には永代供養は向いていません。
永代供養では最終的に他の方の遺骨と共に合祀されますので、先祖代々のつながりは薄れてしまいます。
先祖で受け継いできたお墓を大事にしたい考えのある人は、永代供養には向いていないと言えるでしょう。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
永代供養についてのまとめ

今回は永代供養について多くのことを解説してきました。
記事のポイントをまとめると以下の通りです。
- 永代供養とはお寺や霊園で祭祀や管理を約束してもらうこと
- 永代供養には多くの種類があり、その種類によって費用、埋葬方法、分骨が可能かどうかが大きく変わる
- 永代供養は一般墓に比べて明確な決まりがなく、自由だという特徴がある
永代供養には一般墓に比べて費用を安く抑えられたり、自分の代わりにお墓を大切に管理してもらえたりと魅力的なメリットがある一方、親族からの理解を得られなかったり、安置方法によっては遺骨を取り出せなかったりとデメリットがあることも確かです。
永代供養を選択する際は、きちんと家族や親族と話し合うようにしましょう。
この記事が皆様のお役に立てましたら幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。







