専門家インタビュー
認知症があっても安心して生きられる社会を目指して
更新日:2022.12.28 公開日:2022.12.13

都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
研究内容について
Q1.先生は認知症が言語に与える影響についての研究なさっています。その内容と研究成果について教えてください。
認知症が進行した方でも、若い頃のことはよく覚えている可能性があります。
認知症の方の若い頃の出来事(例えば、学校・卒業・就職・仕事・結婚・育児など)を中心に、ご本人やご家族が持っている写真や、イメージ写真・イラストを使ってアルバム仕立てにしたものを、ライフストーリーブックと言います。
このライフストーリーブックを用いて、介護やリハビリのスタッフが、1か月間・週に5回・1回10分、認知症の方と会話をすることで、軽度の方中心に言葉がよく出てくるようになり、進行した方中心にアパシーという無気力・無為無関心な状態がやや改善されました。
行動心理症状のなかで、特にアパシーは薬物治療が難しい症状であり、意義があります。
Q2.その研究を行った経緯を教えてください。
海外でも、個人的な記憶を治療的な認知刺激として、さまざまな方法で用いる試みが多くなされています。
そのなかにはVR(仮想現実)を用いた大掛かりな研究もあり、アパシーへの効果を言及していました。
VRは有望な介入手段のひとつではありますが、まだまだコストや技術面で普及には乗り越えるべき課題があると考えます。
我々の先の研究では、アパシーにはフォーカスしていませんでしたが、アパシーが改善している感触はありました。
そこで我々が作成したライフストーリーブックの効果について、Q3の研究後に、新たにライフストーリーブックを作成した方の分のデータを加えて、アパシーとアパシーに関連が強いとされる言語流暢性について、再分析したものです。
Q3.「ライフストーリーブックを用いた回想法」についての研究内容とその研究成果について教えてください。
デジタルライフストーリーブックという言葉は2015年当時には一般的でなく、自分はメモリースライドという用語で科研費に応募しました。
つまりメモリースライドは、デジタルライフストーリーブックと同義語です。
認知症の方から若い頃のお話をうかがって、その内容をもとに、介入ツールとしてのデジタルアルバムを作成するのですが、このインタビューにもスキルや対象者の若い頃の時代背景に関する知識が必要です。
アルバムの質を担保するために、インタビューガイド(ライフレビューシート)を作成し、それを用いて、対象者の事を良く知らない学生にインタビューしてもらいました。その結果、対象者を良く知る方にほぼ匹敵するお話を引き出すことができました。
この情報を基に作成したアルバムを用いて、Q1と同じ条件で関わった結果、軽度から中等度の方までは認知機能スコアが改善し、中等度から重度の方の行動心理症状や、介護スタッフの介護負担感は軽減しました。
Q4.浅野様が考える本研究の意義を教えてください。
様々な認知刺激を用いた介入の対象者は、多くが軽度者、せいぜい中等度者です。
しかし私は臨床経験のなかで、中等度以上に進行した方にも関わる意味や必要性を感じており、認知機能の改善は困難だとしても、行動心理症状や介護負担感の改善は可能だと考えていました。
本研究において、対象者に対する本格的介入が開始される以前から行動心理症状や介護負担感の改善が生じたことは、アルバムによる介入効果が本人のみならず、介入したスタッフにも存在した可能性を示唆しています。
つまり介入したスタッフが、インタビューやアルバムの先読みなどで、対象者がどんな人生をおくってきた方なのかがわかり、それにより、対象者への態度が変化した可能性があります。
ご本人が直接変わらなくても、周囲の方が変化することで、全体として良い状況になる、そんな可能性を提示したのが研究の意義と考えます。
今後の目標について
Q1.浅野様の研究における最終的な目標を教えてください。
認知症があっても、安心して生活できる社会の実現です。
それにはICTの利用が不可欠と考えています。
現在、認知症予防に関する研究もかなり進んでいます。
その多くは運動習慣など生活習慣病予防と重なるもので、有望で重要なことと認識しています。
しかし、どんなに予防に気を付けても、発症を完全に抑えることは難しいでしょう。
また、認知症自体の治療薬に関しても、有望な薬剤が出現しています。
しかし、いわば認知症という状態になる前に服用する必要があるとしたら、保険制度の中では扱いが難しくなることが予想されます。
したがって、ある程度は社会が認知症を受け入れる必要があると考えます。
認知症があったとしてもICTを活用して、在宅生活期間の延伸をはかったり、施設に入所したとしても、生活の質を高く保つようにする方策、これについて研究していきます。
Q2.今後はどういった研究を進めていく方針なのでしょうか?
在宅で生活している認知症の方向けには、ご本人の現実見当識の低下を補い、今日やるべきこと(通院、デイサービスへの通所、服薬、ゴミ捨て、買い物)を、遠隔で本人に通知するシステムの研究をしていきます。
施設や病院にいる方、および何らかの事情でデイケアなどの通院や通所が困難な方向けに、遠隔で治療的な認知刺激介入、たとえば先のデジタルアルバムをご家族とご本人とスタッフがお互い離れた場所にいながら同時に見るシステムの開発とその効果を検証します。
また、デジタルアルバムなどを対象者にあわせて1点ずつ手作りすることは、非常に時間と手間がかかることであり、普及の最大の障壁と考えています。
現在、AIを用いてそのような治療コンテンツを生成する研究を企業とおこなっています。
完全な自動生成は難しいかもしれませんが、AIによるアシストがあれば、誰もが質の高い治療コンテンツを楽しめる時代がもうすぐやってくると思います。
みんなが選んだ終活のユーザー様へ一言
Q.みんなが選んだ終活のユーザー様(高齢の方、高齢の親を持つ方)に何かメッセージをお願いいたします。
コミュニケーションを諦めないでほしいです。そして高齢の方や親、は自分の知らない色々な事を知っています。
色々なお話をして、それをまた次代に引き継いでいくことは、文化や歴史の継承という大きな意義があると思います。
また会話をするということは、非常に頭を使う有意義な事と考えます。
残念なことですが、認知症が進行していくと、自分から他者にうまく話しかけることが難しくなってきます。
つまり、周囲の方から話しかけないと、会話が始まりません。
このような状態では、誰かと話す機会が少なくなり、それがさらなる認知機能の低下を招きます。
とはいえ、認知症をもつ方とずっと一緒にいる事は、忍耐力も必要でストレスもかかることです。
そしてそういったネガティブな感情は、認知症の方にも伝わります。
地域包括支援センターの方などに相談して、上手に制度を使う必要があると思います。
また、認知症の家族会など、色々相談できる団体もあります。
自分一人で抱えないで、いろいろなところに繋がってほしいと思います。
スポンサーリンク今回の取材に協力していただいた先生

資格・学会・役職
・作業療法士免許(1998.4)
・日本作業療法学会(1998.4~)
・秋田県作業療法士会 理事(2017.4~)
・日本認知症ケア学会(2013.4~)
・認知症の人の家族の会 秋田県支部世話人(2022.4~)
略歴
システムエンジニアとしてシステムの設計開発に従事(20歳代)
精神病院、介護保険施設などで認知症をもつ方のリハビリテーション業務
(1998.4~2007.3)
新潟リハビリテーション専門学校 専任講師(2007.4~2009.3)
東北文化学園大学 助教・講師(2009.4~2017.3)
秋田大学大学院医学系研究科保健学選考作業療法学講座 准教授(2017.4~)
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
専門家インタビューの関連記事
専門家インタビュー

更新日:2025.02.11
誰もが平等に与えられる最期の時間をより良いものにするために
専門家インタビュー

更新日:2023.01.10
福祉工学の力で人々の幸福を実現し課題解決をしたい
専門家インタビュー
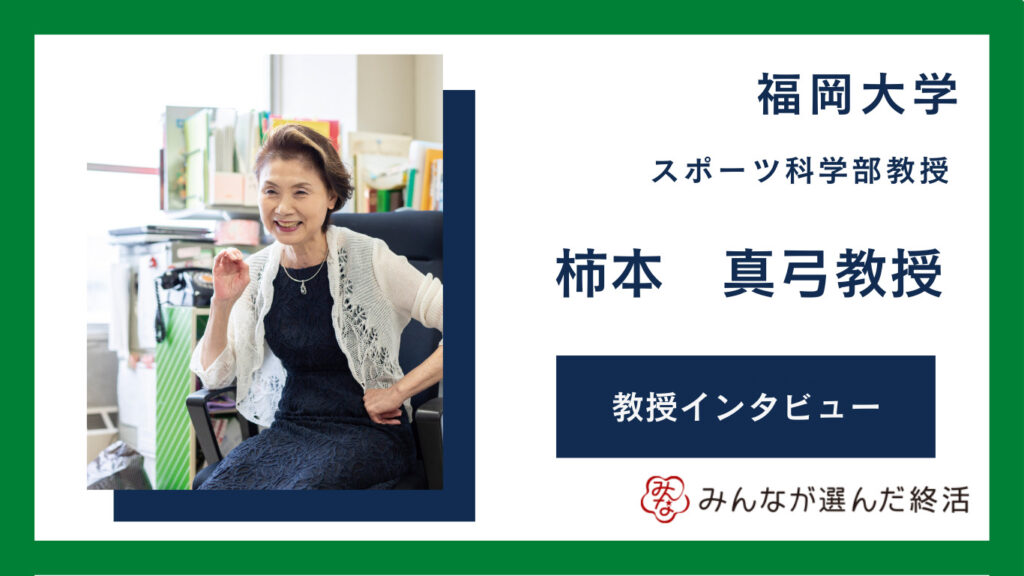
更新日:2023.01.29
運動を通して心身ともに健康な生活を歩んでもらいたい
専門家インタビュー

更新日:2023.03.15
認知症や高齢者になっても安心して暮らせるための看護実践を追究して
専門家インタビュー

更新日:2024.08.28
身寄りのない独居高齢者の身元保証問題に対する 医療ソーシャルワーカーの望ましい支援とは-兵庫県・岡山県の実態調査より-について


