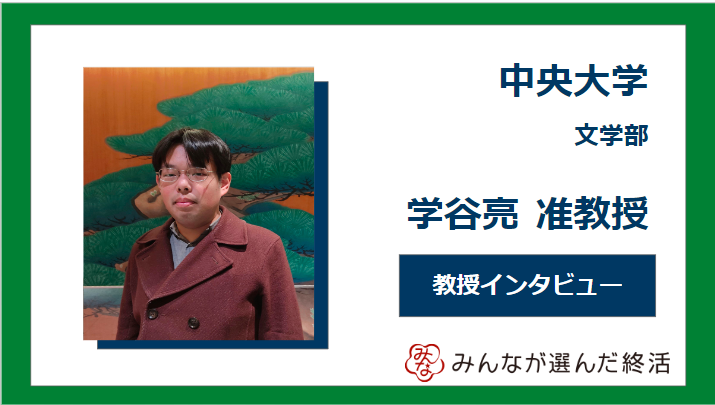専門家インタビュー
認知症高齢者の長期的行動変化について
更新日:2024.10.23 公開日:2024.10.23

都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
研究内容について
Q1.「認知症高齢者の長期的行動変化」の研究を始めたきっかけは何ですか?
20年以上前のことですが、グループホームを経営されている方が学生として入学してこられまして、一緒に介護者を支援するシステムを開発していました。
その中のひとつに入居者を見分け、人と場所に応じて適切に注意喚起するものがありました。たとえばふいに外出することが多い人が玄関に向かっていたら介護者にそのことを伝えるというものです。
いつ誰がどこにいたのかを記録していましたので、二年半経った時点で何か傾向がつかめないだろうかとデータを分析してみました。
Q2.研究対象である、「認知症高齢者の長期的行動変化」とはどのような内容ですか?
ひとつの発見は季節の変化に伴う行動量の変動です。我々は石川県に拠点をおいておりまして、調査したグループホームも同じ県にあるのですが、北陸ですので冬は寒く、雪が降り積もります。冬の寒い時期は活動が低下するだろうと予想していたのですが、実は逆で夏の暑い時期の方が低調でした。入居者6名全員に同じ傾向がみられました。
その当時から夏の暑い時期は体調を崩しやすいので適切に冷房を使いましょうといった指導がされていたのですが、確かに室温管理が重要だとわかりました。
高齢者は暑さに弱く、夏は体力が低下して動きが鈍くなります。それを防ぐには積極的に冷房を使った方がいいわけです。
Q3.本研究の研究成果を教えてください。
季節変動は万人に当てはまることですが、データを収集している期間、亡くなられた方が1名、それから転倒して入院された方が1名いました。これらの方々について詳しくデータ分析したところ、興味深いことがわかりました。ここでは亡くなられた方に焦点をあてて説明します。
この方は老衰で眠るように亡くなられたのですが、行動量をみると亡くなられる3ヶ月前に大きく低下していました。その後、4週間後に少し持ち直したのですがすぐに減少傾向となり、6週間かけて徐々に行動量が減って亡くなられました。
現場の介護者の方々にその間の様子を尋ねたところ、終末期に入ったことは感覚的にわかったとのことでした。あまり動かなくなったとか、食べなくなってきたということは一緒に過ごしているのでわかるようです。終末期が3ヶ月というのは現場の感覚と整合するとのことでした。
その後、同じようなデータを持っている企業の方々と交流する機会がありまして、上の話を紹介したところ、自分たちの持っているデータからも同じようなことがいえるとのことで、やはりそうかと納得した次第です。内容が人の死に関わることなのでなかなか研究しづらいですが、大量にデータを集めれば検証できるでしょう。
Q4.藤波先生が考える本研究の意義を教えてください。
ある人が終末期入ったとき、身近にいる介護者は気づくでしょう。その時点で家族に伝えられたらよいのですが、確証があるわけではないので伝えづらいと思います。データがあれば分析結果を示して、客観的に事態を説明できます。
誰もが肉親の死(の可能性)を否定したいものですが、死期が迫っていることがデータからわかるなら受け入れられるでしょう。そうなればその期間に積極的に会いに行くとか、有意義に過ごせるはずです。
仲のいい家族なら必要ありませんが、グループホームなど介護施設に入居している方は往々にして孤立していて、尋ねてくる人もほとんどいなかったりします。
そういう人であっても、最後に別れを告げたい人はいるでしょう。本人も身辺整理をする気構えができるかもしれません。死の準備を始めるきっかけを提供できることがこういった研究の社会的意義であろうと思います。
スポンサーリンク
今後の目標について
Q5.藤波先生の研究における最終的な目標を教えてください。
このテーマは重要と思うのですが、興味を持つ人が少ないようです。先に言及した同様のデータを持っている企業の人たちも各方面に営業をかけたそうですが、興味を持ってくれたのは葬儀屋さんだけだったそうです。死というのは未だ触れられないテーマなのかもしれません。
技術者目線だと便利なものは使えばいいといった乱暴な話になってしまいますが、死について考えたくないという気持ちも自然なものです。
「余命三ヶ月になったらそのことを知りたいか?」という問いを立ててみましょう。死の準備はその期間をいかに有意義に過ごすかということを含みます。この問いに回答できないことがこの技術が普及する上でのネックとなっています。
病気だったら診断できても治療法がなければ患者を絶望させるだけです。同じことが技術にもいえるでしょう。最期の三ヶ月を有意義に過ごす方法を提案できて、初めて活きてくる技術です。そういったことをこれから研究できるのか定かではありませんが、なんとか取り組んでみたいと考えています。
ほぼ昏睡状態にあってもコミュニケーションがとれる方法とか、そういったことに興味があります。現場をお持ちの方がおられましたら、ぜひお声かけください。よろしくお願いします。
参考文献
屋内位置情報に基づく認知症高齢者の長期的行動変化の分析
藤波努, 杉原太郎, 三浦元喜, 高塚亮三
社会技術研究論文集 Vol.10 pp. 42-53 2013年
先生の経歴について
Q1.先生の略歴を教えてください。
高校卒業後、早稲田大学に行って哲学を学びました。哲学では生活できないなぁと思っていたところ、人工知能で仕事ができそうだとわかり、日立製作所の研究所に入れてもらい、人工知能の研究に携わりました。
その後、理論を突き詰めたいと思い、留学してエディンバラ大学で認知科学を学び、博士論文を書きました。しばらくヨーロッパで仕事したいと考えていたところ、ドイツで仕事があったので移ってStuttgartという町にある大学で研究員として働きました。
そうしているうちに今の大学から声がかかり、帰国して働き出しました。1998年のことです。今に至るまで26年間、同じ所で働いています。
Q2.先生の資格・学会・役職を教えてください。
学会:日本人工知能学会、アートミーツケア学会
役職:マルタ大学客員教授
スポンサーリンク
先生の所属先
スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。