専門家インタビュー
地域高齢者の体力自己評価の関連要因に関する研究について
更新日:2024.10.31 公開日:2024.10.30
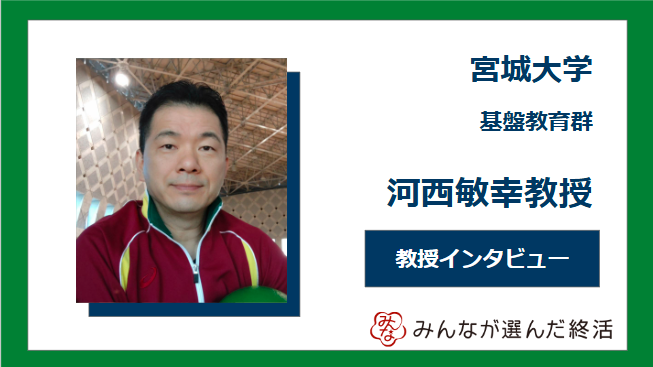
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
研究内容について
Q1.「地域高齢者の体力自己評価の関連要因に関する研究」の研究を始めたきっかけは何ですか?
20年以上前の研究(論文)ですが、現在の研究テーマ『ご当地体操の開発と評価』や、複数地域での介護予防・健康づくり活動にも深くつながっています。
本研究は中部地方の大都市近郊に位置するA村に在住の高齢者を対象としています。同村では1991年から『日本一の健康長寿構想』を推進しており、現在も同村の地域福祉計画などと連動しています。1996年にはこの構想の中核施設として総合保健福祉センターが設立され、大型の温水プールやトレーニングルームも併設されました。本研究のきっかけは、同センターの運動施設を活用した「高齢者対象の健康運動プログラム(試作版)」の作成を担当したことにあります。
当時の運動プログラムは、A村で長期継続している全数調査に基づき、『体力自己評価』(9項目)と、健康状態と関連のあった『日常生活行動』(4項目:友人宅等への訪問、趣味活動、期待役割、健康への気配り)を組み合わせて作成しました。具体的には、“ご自宅でできる運動”と“センターの運動施設を利用したおすすめの運動”を中心に、健康長寿を目指す入門編として32種類のプログラムを作成し、同村在住の高齢者約700名(85%以上)に郵送しました。
その後、体力自己評価に関する一連の研究として、東北や関東の複数の自治体における介護予防事業、例えば「高齢者ボランティアリーダーを中核とした転倒予防体操による介入調査」や「介護予防推進員養成事業の推進とご当地体操の開発」などの活動につながっていきました。
Q2.研究対象である、「地域高齢者の体力自己評価」とはどのような内容ですか?
ある自治体の介護予防事業の一環として実施される転倒予防教室など、特に体力テスト(体力測定)の実施が難しい現場において、適切な運動メニューの検討や運動効果の評価に活用するため、“自分の体力要素”を“自分の感じ方”で評価してもらう質問項目です。本研究では、一般的な体力分類や健康関連体力、新体力テスト種目などを踏まえ、持久力系(全身、脚力、姿勢)、筋力系(腕力、立ち上がり、階段)、調整力系(敏捷性、平衡性、柔軟性)の3領域、計9項目で構成しています。各項目については、「できると思うか」などと尋ね、4段階で回答してもらう形式になっています。
本研究の開始当時、健康や体力の主観的評価や質問紙を使った体力テストなど、すでに一般化している指標はいくつもありました。ただ、本研究の体力自己評価は、私が運動指導者として現場で得た気づきを最大限に反映させ、参加者にとってなるべく理解しやすい表現や尋ね方になるよう工夫しています。そのため、少なくともその地域の高齢者にとっては、既存の指標よりも馴染みやすく、適合性が高いものになっていると考えています。
Q3.本研究の研究成果を教えてください。
本研究のきっかけとなった健康運動プログラム作成時の調査結果として、体力自己評価が高いと「体力テスト値」も高い、あるいは「身体状況」が良好であることが示されました。一方、高齢者が日常生活動作(ADL)レベルの体力を維持するためには、社会との関わりが重要であるという多数の報告がありますので、本研究では高齢者の『社会関連性』に焦点を当て、体力自己評価との関連について検討しました。その結果、体力自己評価が低い方においては、「社会貢献の可能性」に否定的であったり、「趣味活動」や「本・雑誌等の購読」の頻度が低かったりするなど、複数の社会関連性項目が有意に低くなっていました。
本研究の成果としては、これらの直接得られた結果に加え、その後の研究にも発展的につながった点があげられます。具体的には、健康運動プログラムの作成を主目的としていた体力自己評価が、複数の自治体において、転倒予防体操などによる一定期間(半年~2年程度)の介入効果を評価する項目としても有効である可能性が示唆されました。特に注目すべき点は、①運動をしていても、体力自己評価が低下すると立ち上がり能力や平衡性(バランス)が低下する可能性があること、②運動をしていない場合は、体力自己評価が上がっても歩行能力が低下する可能性があること、の2点です。さらに、約300人の高齢者を15年間追跡調査してみたところ、弱い相関ながらも体力自己評価が高いほど15年後に転倒しにくいことや、歩行能力が高くなることも示されました。
これらを踏まえ、私自身、体力テストの実施が困難な現場においては、●体力自己評価が低い方には初回から慎重に対応する(きめ細やかな声かけ、個別サポートなど)、●体力自己評価が高い方には1年くらい前からの運動習慣を確認する、といったアプローチに活かしています。
Q4.河西先生が考える本研究の意義を教えてください。
本研究の意義としては、体力テストが実施できない、あるいは運動指導の専門家がいない現場でも、体力自己評価によって参加者(高齢者)の体力や運動能力、さらに社会との関わりや日常生活の活動量をある程度把握でき、体操やレクリエーションなど、運動を伴う取り組みに活用できる可能性が示唆されたことがあげられます。
また、先行研究では、加齢や運動不足により体力の主観的評価と客観的評価(実際の測定値)が乖離しやすいことが複数報告されています。本研究(および一連の研究)においても、運動習慣が乏しいと一定期間後に体力自己評価と体力テスト値がズレてくることが示唆されました。したがって、本研究は、体力テストが実施できない現場のみならず、体力テストが可能な現場での活用につながる基礎的成果が得られた点でも意義があるものと考えています。実際に、簡易な体力テストが可能な現場では、特に体力自己評価と体力テスト値が逆転している参加者を予め把握し、適切な力加減や体の使い方に関する声かけやデモを可能な限り盛り込むようにしています。
本サイトのメインテーマである『終活』には「人生の最終章を充実させる活動」が含まれると考えられますので、“自分のイメージ通りに体を動かせること”への寄与が期待される本研究は、よりよい終活の基盤を支えるという点でも有意義といえるかもしれません。
スポンサーリンク
今後の目標について
Q5.河西様の研究における最終的な目標を教えてください。
これまでの一連の研究を踏まえた最終的な目標としては、①体力自己評価を様々な現場で使いやすくなるよう洗練していくこと、②体力自己評価を自治体レベルのご当地体操だけでなく、小さなコミュニティのオリジナル体操やダンスの振付に活用すること、③体力自己評価と体力テスト値を組み合わせた評価方法から運動プログラム作成例までをセットにして広く提案・発信すること、の3点を考えています。
私の終活の一環といえるかもしれませんが、大学教員としての定年後は、健康や体力に関連する指標や尺度の科学的根拠を十分に考慮しながらも、自分が蓄積してきた経験的根拠、といいますか “他人には教えたくなかった裏技的なトレーニングやダイエット法”なども惜しみなく公開していく予定です。また、子どもから高齢者まで幅広い方々を対象にしたパーソナルトレーナー的な活動も積極的に展開し、より多くの方と一緒に健康づくりを楽しみたいと思っています。
先生の活動|高齢者向けオリジナル体操
<高齢者向けのご当地体操の一例です。オリジナル体操やダンスの振付などで何かお役に立てることがありましたら、ぜひご連絡ください!>
スポンサーリンク
先生の経歴について
Q1.先生の略歴を教えてください。
・順天堂大学体育学部健康学科卒業
・東洋大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻博士前期課程修了
・東北大学大学院医学系研究科障害科学専攻博士後期課程修了
・国立身体障害者(現・障害者)リハビリテーションセンター研究所非常勤研究員
・東北文化学園大学医療福祉学部保健福祉学科准教授 など
Q2.先生の資格・学会・役職を教えてください。
・博士(障害科学)
・健康運動指導士
・第一種衛生管理者
・日本体育・スポーツ・健康学会
・日本保健福祉学会 など
先生の所属先
スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。



