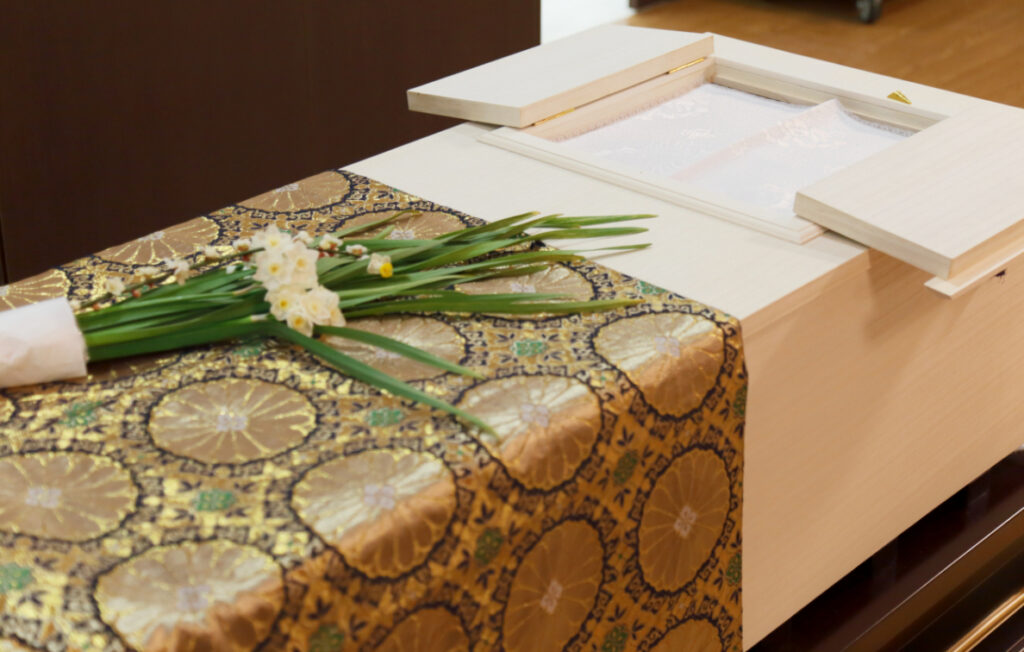死亡後の手続き
死亡診断書とは?死亡診断書の提出先と発行の流れを解説
更新日:2024.02.03 公開日:2022.01.14

記事のポイントを先取り!
- 死亡診断書は医師のみが書ける
- 死亡診断書と死亡届は所定の役所に提出する
- 手続きのためコピーを取っておく
家族や親しい親族が亡くなった場合、死亡診断書が必要になるのですが、どこで入手すればいいのでしょうか。
いざという時に慌てないために、人が亡くなった際の手続きについて、確認しておきたいところです。
そこでこの記事では、死亡診断書について解説していきます。
死亡診断書の費用の相場についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
死亡診断書とは
死亡診断書がどのようなものか、まずは基本から解説していきましょう。
死亡診断書の内容
死亡診断書とは、医学的・法律的に人が死亡したことを証明する書類です。
死亡診断書には以下のような事柄が記されます。
- 死亡者の氏名・性別・生年月日
- 死亡した年月日・時間
- 死亡した場所・その種別
- 死亡の原因
- 死因の種類(病死及び自然死、交通事故等)
- 外因死の追加事項
- 1歳未満で病死した場合の追加事項
- その他特に付言すべきことがら
- 診断医師名・病院名・年月日
死亡診断書は医師だけが書けるもの
死亡診断書は医学的に死亡を証明するもので、死亡者本人の死亡に至るまでの過程を詳細に表します。
死亡診断書を作成できる人は、医師・歯科医師に限られています。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡診断書と死体検案書の書式は同じです。
標題が「死亡診断書(死体検案書)」となっており、どちらの書類に該当するかはもう一方の該当しない方を二重の横線で消すことで示します。
死亡診断書は、医師の診療を受けていた人が、診療を受けていた病気やケガが原因で亡くなった場合の書類です。
例えば昨日まで元気で、診療を受けていなかった人が急に亡くなった場合の書類は死体検案書です。
医師の診療を受けていた人でも、診療を受けていた病気やケガと死因が異なる場合は死体検案書の作成が必要になります。
死亡診断書は役所に提出する
死亡診断書(死体検案書)と死亡届は、一つの書類になっています。
左側半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)として医師が書く欄です。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。
国外で亡くなった場合の期限は、亡くなったことが分かってから3ヶ月以内です。
死亡診断書(死体検案書)と死亡届を提出する場所は役所です。
ただし提出する役所は、以下の3つの場所を管轄する役所に限られます。
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
亡くなった方の住所地の役所は提出先になっていません。
提出しても受理されないので、間違えないようにしましょう。
死亡診断書と死亡届を提出する届出人は、誰でもいいわけではありません。
故人の親族または同居人が届出をするのが基本ですが、その他家主・地主・後見人等も届出ができます。
死亡診断書の発行の流れ
死亡診断書がどのように発行されるのか、その条件と流れを確認しておきましょう。
入院先で亡くなった場合
入院していて亡くなった場合は、ご遺族は特に何もしなくても大丈夫です。
入院していたということは、診療を受けていたことになります。
担当医師が死亡診断書を作成し、病院が発行して渡してくれます。
ご自宅で亡くなった場合
ご自宅で亡くなった場合は、故人が病院の診療を受けていたかどうかで、対応が変わってきます。
病院で診療を受けていて、その病気やケガが死因と認められた場合は、担当医が死亡診断書を作成します。
一方、病院の診療を受けていない場合は、死亡診断書を発行してもらえません。
故人の死因・死亡時刻・死亡場所などを特定するために、死体の検視や検案の手続きが必要になります。
検視とは
検視とは、遺体の外見から事件性の有無を確認する刑事手続きです。
検案とは監察医や警察医が遺体の外表面を検査し、死因や死亡時刻を医学的に判定することで
検案で死因が分かれば、医師によって死体検案書が作成されます。
事故などで亡くなった場合
事故などで病院に運ばれて、病院で死亡が確認された場合には、入院時の対応と同様です。
病院で診療を受けたことになるので、担当医師によって死亡診断書が作成されます。
しかし、医師の診察により不審な点があった場合は事情が変わってきます。
不審な点があれば、医師は24時間以内に管轄の警察署にその旨を届け出なくてはならないとされています。
この場合は検視や必要に応じて司法解剖・行政解剖がおこなわれた後、死体検案書が作成されます。
旅先で亡くなった場合
旅先で亡くなった場合には、現地の医師が死体検案書を発行します。
可能であれば遺体を自宅等へ運びますが、遺体の損傷が大きな場合には、現地で火葬をして、遺骨を持ち帰るケースもあります。
死亡診断書発行の相場費用
死亡診断書の発行費用は、一律に定められているものではありません。
各病院で独自に設定しているので、費用はまちまちです。
病院によって費用に差はありますが、だいたい3,000~1万円が相場と言っていいでしょう。
死亡診断書の費用に対して、死体検案書の場合は比較的高額になります。
これは遺体を搬送する費用や保管費、検視や検案に要する費用などが加算されるからです。
死体検案書費用の相場は、だいたい3万~10万円ほどとなります。
死亡診断書が必要な場面
死亡診断書は、死亡届とともに役所に提出するものです。
しかしそれ以外にも、故人の生活に区切りを付ける手続きのため、様々な場面で必要になります。
では、どのような場面で死亡診断書が必要になるのか、いくつか例を挙げておきましょう。
- 国民年金(遺族基礎年金・寡婦年金)の請求
- 厚生年金(遺族厚生年金)の請求
- 共済年金(遺族共済年金)の請求
- 雇用保険受給者資格証の返還
- 生命保険の死亡保険金の請求
- 健康保険加入者の埋葬料請求
- 自賠責保険の請求
- 携帯電話の解約
- 固定電話の解約
- 証券会社の相続手続き
これはあくまでも一例なので、もっと多くの死亡診断書が必要になるかもしれません。
死亡診断書を発行してもらったら、原本を役所に提出する前に、コピーをできるだけ多く取っておくことをおすすめします。
死亡診断書の再発行はできる?
死亡診断書の原本は、役所に提出します。
しかし死亡診断書は、故人の生活に区切りをつけるための、様々な手続きに必要になるものです。
そのため、ある程度のコピーを取っておくことが必要です。
コピーが無くなってしまった場合、死亡診断書は再発行できるのでしょうか。
病院で再発行できる
病院は遺族の要請があれば、死亡診断書の再発行に応じる義務があると定められています。
そのため死亡診断書の再発行が必要な場合は、以前に死亡診断書を発行した病院に行けば対応してもらえます。
再発行を要請できる人は限られている
再発行を要請できるのは、故人の配偶者と三親等以内の親族のみです。
死亡診断書の再発行は要請すればしてもらえますが、時間がかかる可能性もあるので、事前に病院側とよく相談するようにしてください。
別の方法でも入手可能
役所で死亡診断書の写しを請求できます。
ただし役所に死亡診断書の写しを請求する際には、どこに請求すればいいのか、確認する必要があります。
死亡診断書を提出してからしばらくの間は、管轄の役所に保管されています。
しかしその後は法務局に保管場所が移されます。
死亡診断書が移動されるタイミングは、役所によって異なるので、事前に問い合わせをしたほうがいいでしょう。
再発行に必要な物
死亡診断書の再発行に必要なものは、一般的には以下の通りです。
- 身分証明書
- 故人との関係性を証明する書類(戸籍謄本など)
- 委任者からの署名と捺印のある委任状
- 死亡診断書の再発行費用
あくまでもこれは、一般的な例です。
病院によっては、申請時にさらに別の書類を求められるかもしれません。
再発行の要請をしに行く前に、事前に病院側に確認しておいたほうがいいでしょう。
死亡診断書の再発行は可能ではありますが、手間も時間もかかるものです。
役所に原本を提出する前に、できるだけ多くのコピーを取っておいたほうがいいでしょう。
死亡診断書のまとめ

ここまで死亡診断書の発行や、死体検案書との違いなどを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 死亡診断書とは、医学的・法律的に人の死亡を証明するもの
- 死亡診断書は、故人の本籍地や、死去した場所などを管轄する役所に届け出る
- 入院先で亡くなった場合は、死亡診断書はそのまま病院が発行する
- 死亡診断書は生命保険の死亡保険金の請求等の様々な手続きで必要になる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
葬儀費用の平均相場|内訳や葬儀形式別にかかる費用、費用負担を抑える方法について
スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
死亡後の手続きの関連記事
死亡後の手続き

更新日:2022.04.29
死亡届を出したのに実は生きていた?失踪宣告・認定死亡について解説
死亡後の手続き

更新日:2022.04.30
警察に遺体が引き取られた場合死亡届はどこでもらえる?流れを解説
死亡後の手続き

更新日:2022.04.30
死亡届の提出先はどこになる?手続きや必要な書類、書き方を解説
死亡後の手続き

更新日:2024.12.18
配偶者(夫・妻)が死亡した時にすべき手続きは?時系列ごとに解説