相続
遺産分割協議書の書き方とは?文例や書く時の注意点を徹底解説!
更新日:2025.03.05 公開日:2022.05.12

記事のポイントを先取り!
- 遺産分割協議書に決められた様式はない
- 遺産分割協議書に必要な項目が記載されていると有効
- 遺産分割協議のやり直しができるケースもある
- 遺産分割協議書が不要な場合もある
遺産を分割する際、遺言書などがない場合には、遺産分割協議によって遺産分割を決めます。
遺産分割協議書はどのように書くのが正しいのでしょうか。
そこでこの記事では、遺産分割協議書の書き方について詳しく説明していきます。
遺産分割協議書の作成が必要ない場合についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
- 遺産分割協議書とは
- 遺産分割協議書の書き方
- 遺産分割協議書の文例
- 遺産分割協議書を用意する際の注意点
- 遺産分割協議をやり直しするには
- 遺産分割協議の期限
- 遺産分割協議書が必要とならないケース
- 遺産分割協議書の書き方まとめ
- 不動産売却おススメサイト
遺産分割協議書とは
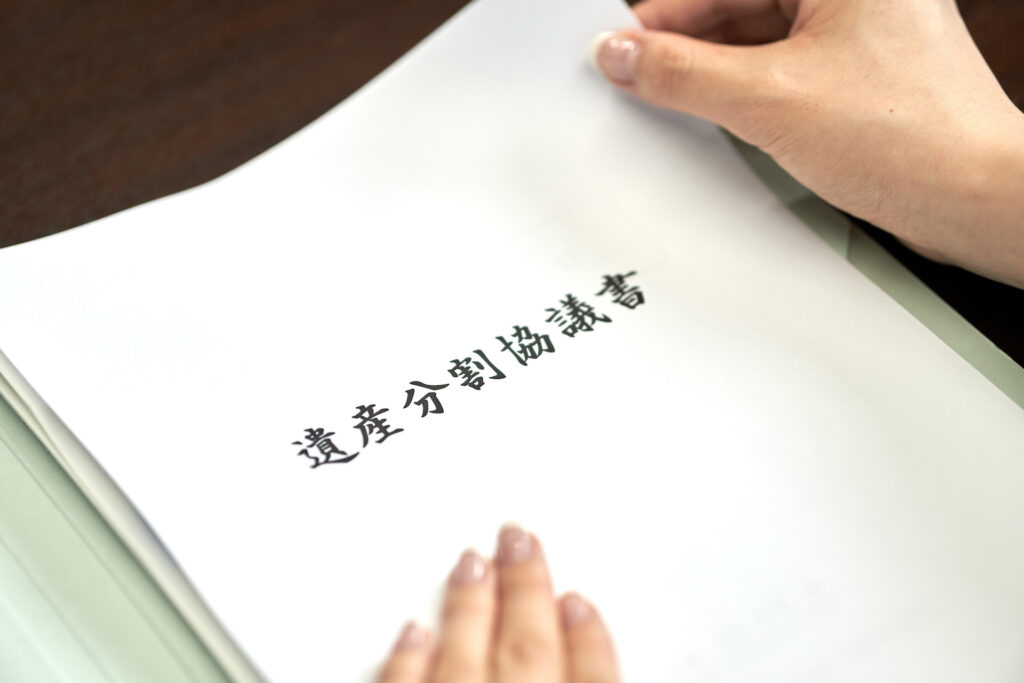
遺産分割する際に、遺言書がない場合もあります。
また、遺言書に記されていない資産が見つかることもあります。
そうした場合、相続する権利のある相続人によって「遺産分割協議」と呼ばれる話し合いが行われることとなります。
遺産分割協議には、法定相続人全員の参加および同意が必須なので、協議を始める前に、漏れのないように徹底的に相続人を調査しておく必要があります。
遺産分割協議で話し合った結果については「遺産分割協議書」と言う書面に残しておくのが良いでしょう。
遺産分割協議書を作成しておくと、相続人全員が同意した内容であることが証明できるため、トラブルを避けられます。
また、相続の手続きの際に、提出が必要な場合もありますので、遺産分割協議で決まった内容は、書き方に注意して遺産分割協議書として残すようにしましょう。
遺産分割協議書の書き方

では、遺産分割協議書はどのように書いたら良いのか、その書き方をご存知でしょうか。
ここではその書き方について、詳しく説明していきます。
遺産分割協議書に形式は存在しない
実は遺産分割協議書の書き方には、決まった形式がありません。
明記すべきポイントを押さえた書き方で作成されていれば、遺産分割協議書として有効となります。
ここからは、遺産分割協議書を書くときのポイントについて解説しますので、作成する際は注意しましょう。
主な項目
意外に見落としがちなのが、書類の主題であるタイトルです。
遺産分割協議書であることが、一目で分かるように「遺産分割協議書」と冒頭に明記しましょう。
被相続人の情報
誰の資産を相続するのか、必ず記載する必要があります。
これらについても、書き方に定めはありませんが、正確さが求められます。
人物について記載する場合は、戸籍謄本に記載されている正式なものを書くようにしましょう。
- 本籍
- 死亡時の住所
- 氏名
- 死亡年月日
これらが記載されていれば差し支えありません。
不動産について
具体的な資産については、「誰が」「どの不動産を」「どれだけ相続する」のかを記載します。
不動産の資産について、登記事項証明書に記載されているとおりに記載しましょう。
不動産の名義変更の際には遺産分割協議書が必要になりますので、不動産の資産がある場合は必ず作成することになります。
書き方を間違えると無効となってしまうので、正しく記載するよう注意しましょう。
自動車について
自動車を名義変更する際にも、遺産分割協議書が必要になります。
資産の特定が出来るように、できる限り詳しく正確に記載しましょう。
預貯金について
どの金融機関に資産があるのかを正確に記載しておく必要がありますが、預貯金の書き方には少し注意が必要です。
金額については詳細を記載しないことをお勧めします。
それは、金額に誤りがあったり、金額が合わなくなったりした場合に無効となる可能性があるからです。
金融機関などでは、利息が付く、手数料がかかる、といった理由で金額が変わってくる可能性があります。
こうした理由から、金額は明記しない書き方を採用しましょう。
有価証券について
こちらは、現金化して相続することは出来ず、証券そのものを相続する形になります。
一旦相続人の口座に移管してから、売却などを進めていく形になります。
家財について
家財については、一般的には遺産分割協議書に記載することはありません。
記載するとしても、通常はひとつひとつの家財を評価するのではなく、「家財道具一式」とする程度です。
家具に資産価値がある場合のみ、個別で記載するのが良いでしょう。
未収入金について
未収入金とは、被相続人が死亡した時点ではまだ回収されていない収益のことで、不動産の家賃などがそれにあたります。
亡くなった後に支払われた家賃については、遺産分割協議が終わるまでは総資産の一部と見なされることを覚えておきましょう。
同意人について
ここまでは、相続する資産についての書き方について説明しましたが、ほかに遺産分割協議書に必ず必要なものがあります。
遺産分割協議は、相続人全員で行うものだということはご理解いただいていると思います。
遺産分割協議で取り決めた内容を記す遺産分割協議書には、同意人として、相続人全員の署名捺印が必要になります。
相続人の氏名、住所を記載の上、実印を押印したものが正式な遺産分割協議書と見なされます。
遺産分割協議書の文例
ここでは、具体的に遺産分割協議書の記載例を紹介します。
ぜひ参考にしていただければと思います。
--------
遺産分割協議書
被相続人:〇〇 〇〇 令和4年〇月〇日死亡
本籍:〇〇県〇〇市〇〇8番8号
死亡時の住所:〇〇県〇〇市〇〇13番8号
上記の者の遺産について、共同相続人全員で遺産分割協議し、記載されている相続人が下記の通り遺産を相続、取得および承継することとする。
記
1、相続人Aが取得する資産
(1)預貯金に関する権利
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号9999999 の2分の1
(2)自動車に関する権利
トヨタ 自動車登録番号 岐阜888れ8888888
型式 BJ40V 車体番号 〇〇-9999999
(3)・・・
2、相続人Bが取得する資産
(1)預貯金に関する権利
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号9999999 の2分の1
(2)未収入金に関する権利
3、・・・
・
・
・
上記の通り分割する遺産の他に、将来にわたり新たな資産や負債が発見された場合には、共同相続人全員によって改めてそれについて遺産分割協議を行なうものとする。
遺産分割協議書に記載されている事項について、共同相続人全員の同意が得られていることを証するために、下記に署名捺印する。
また、この協議書と同様のものを、共同相続人全員が各自1通ずつ保有するものとする。
相続人Aの氏名、本籍地、実印の押印
相続人Bの氏名、本籍地、実印の押印
・
・
・
捨て印も全員分押印
令和4年〇月〇日
--------
必要な事項をもれなく記載し、相続人全員の署名捺印があることを確認し、同じ書類を人数分作成しましょう。
スポンサーリンク遺産分割協議書を用意する際の注意点
遺産分割協議書を作成する際に注意しなければならないことがいくつかあります。
様式に定めはないものの、有効性を持たせるためには覚えておいた方が良いでしょう。
一人で作成はしない
まず、ここまで何度かお伝えしてきましたが、遺産分割協議書は相続人全員で協議した結果を記すものです。
一人で作成することのないようにしましょう。
後ほどトラブルになりそうな場合には、作成そのものを弁護士に依頼するのも良いでしょう。
また、相続人の状況によっては後継人が必要な場合もありますので、覚えておきましょう。
内容は明確に記載する
遺産については、誰が見ても分かるような書き方で、明確に記載する必要があります。
曖昧な表現は避けましょう。
ただし、現金などの場合には、金額は明示しない書き方が良いこともありますので、留意してください。
複数枚になる場合は割印する
分割する遺産が多くある場合、1枚では書き切れないことがあるかも知れません。
相続人が多い場合にも、スペースが足りなくなることがあるでしょう。
複数枚にわたって遺産分割協議書を作成する場合には、全ての用紙が有効となるよう割印しておく方が良いでしょう。
割り印以外の方法として、契印を押す方法もあります。
割印、契印どちらとも、相続人全員の実印で押印することとなります。
基本的にやり直しはできない
遺産分割協議は、相続人全員が話し合い、同意の上で決定するものなので、やり直すということは基本的にありません。
遺産分割協議をやり直しするには
遺産分割協議は、相続人全員で協議し、その結果に同意した上で作成されるものです。
基本的にやり直すことはありませんが、以下のような場合には例外としてやり直しができます。
相続人全員が合意する
相続人全員が、遺産分割協議をやり直すことに同意しているという場合には、やり直しが出来ます。
その際、全ての遺産について分割をやり直す訳ではなく、一部の遺産についてやり直す場合であっても、遺産分割協議書は再度作成する必要があります。
手間はかかりますが、納得いく形で遺産分割協議したいと思えば行いましょう。
協議が無効になった場合
遺産分割協議そのものが、無効であると判断される場合にも、やり直すことができます。
以下のようなケースの時には、遺産分割協議が終わっていても、それを無効とすることが可能です。
遺産分割協議で、相続人本人の意思とは違う結果となってしまった場合がそれにあたり、その事実を証明できれば一度行った遺産分割協議を無効にできます。
例えば、他の相続人に騙された、不利な条件をのむように脅された、間違えて解釈していた、などの場合がそれにあたります。
その場合は、協議の結果は一旦取り消され、再度遺産分割協議をすることとなるでしょう。
新しい遺産が見つかった場合
当初、遺産分割協議書を作成した際には判明していなかった新たな資産が見つかった場合は、その資産について遺産分割協議することが必要です。
やり直す、というよりは、追加で協議するという形になります。
新たに見つかった遺産についてのみ、遺産分割協議ができますので、その場合は遺産分割協議書を新たに追加する形で作成します。
必ずしも1通の遺産分割協議書に全ての遺産を記載しなければならない、ということではありません。
遺産分割協議の期限
法律上、「遺産分割協議をいつまでに終わらせなければいけない」という定めはありません。
ただ、一般的に相続税の支払期限が10ヶ月となっているため、それまでに遺産分割協議を済ませておくと良いでしょう。
遺産分割協議書が必要とならないケース
ここまで、遺産分割協議書が必要となるケースについて説明してきましたが、必要とならないケースもあることを覚えておきましょう。
相続人が一人だけの場合
相続人が複数いない場合には、遺産を分割する必要がないため、遺産分割協議自体が行われません。
そのため、遺産分割協議書の作成もされません。
第三者に示す必要がない場合
遺産分割協議書は、名義を変更する際や相続税の申請などの手続きで必要になります。
相続手続きに該当する資産がない場合には、特に作成する必要はありません。
トラブルなく遺産分割できた場合
相続人全員が、特別な主張をすることなく法定相続分での分割に同意するなど、もめることのないケースでは、遺産分割協議書の作成は必要ないでしょう。
遺産が現金だけの場合
遺産が現金のみの場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
名義変更などもないので、当事者同士で協議をし、その結果に基づいて分割すれば問題ありません。
遺産分割協議書の書き方まとめ

ここまで、遺産分割協議書とその書き方を中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下のとおりです。
- 遺産分割協議書に決められた形式はなく、必要な項目が記されていれば有効となる
- 記載するべき項目の記入を間違えると無効になるので、正確に記入する
- 遺産分割協議は相続人全員で行い、遺産分割協議書を相続人は人数分作成する
- 遺産分割協議のやり直しは原則として行わないが、やり直しができるケースもある
- 遺産分割協議書の作成が不要な場合もある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
不動産売却おススメサイト

エスナレッジ株式会社は、戸建て、分譲マンション、1棟マンション、駐車場など、あらゆる不動産の相続問題に強い不動産売却のエキスパートです。
不動産売却に特化した当社は、相続に関する専門知識も豊富。複雑な相続不動産の売却も、スムーズかつ円満な解決をサポートいたします。
遺産分割協議書についても、司法書士、税理士と連携し、お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案。安心の売却と相続問題解決を実現します。
スポンサーリンク
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。
相続の関連記事
相続

更新日:2022.06.11
遺族年金が非課税である理由と節税方法・確定申告について紹介
相続

更新日:2024.10.27
遺族と相続人の違いは?定義や順位、割合について解説
相続

更新日:2025.05.20
遺産相続とは?手続きの流れ・相続人の範囲など基礎知識を解説
相続
更新日:2026.01.09
相続のお悩みには最適な専門家を|しきサポの相続をご紹介
相続

更新日:2022.04.27
遺産がいらない場合にはどうすれば良い?相続放棄のやり方を紹介
相続

更新日:2025.06.24
遺産分割トラブル、約4分の3が「遺産額5,000万円以下」…専門家が教える、生前の「財産整理」の重要性


