お墓
永代供養墓に遺骨を安置できる期間は?費用や種類も合わせて解説
更新日:2023.11.19 公開日:2021.07.20

2021年現在、少子化や結婚しない方が増えています。
そのため、お墓の管理を寺院などに任せられる永代供養が注目されています。
永代供養という言葉からは、期限を区切らずにお墓が使えるように聞こえます。
しかし、永代供養には期限が定められているのです。
ここでは、永代供養の期間について以下のことを説明します。
- そもそも永代供養とは
- 永代供養墓の期間の定め
- 永代供養墓の期間が過ぎた後はどうなる
永代供養墓の種類や費用説明もしていきます。
ぜひ最後までお読みください。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。
永代供養とは
永代供養とは、家族や遺族に代わって、寺院などの墓地管理者がお墓の管理や供養を行うものになります。
普通のお墓と同じようにお墓参りもでき、特別な供養をお願いすることも可能です。
お墓は先祖代々の遺骨を弔うものであり、その管理は世代を超えて引き継がれます。
例えば、長男の方などが祭祀承継者として引き継ぐことで、お墓は管理されてきました。
しかし、少子化などの影響でお墓を個人で管理することが難しい場合も増えています。
どうしても管理者が見つからない場合は、墓じまいをして墓地管理者にお墓を返すということになります。
こうしたことを背景に、身寄りのない方や後継者が見つからない方などから、永代供養墓が注目を集めています。
また、子供の世代に迷惑をかけたくないという思いから永代供養墓を選択する方も増えているといわれています。
永代供養の期間

お墓を購入するといいますが、お墓は墓地の区画を墓地の管理者から借りているだけです。
この点は、一般のお墓の場合も、永代供養墓の場合も同じです。
永代供養墓と普通のお墓の大きな違いは、お墓の使用期間に関する期限の有無があります。
以下では、使用期間の定めや、期限が来た場合に行うべきことを説明します。
永代供養墓に遺骨を安置する期間
永代供養墓に遺骨を安置できる期間は、永代供養墓を運営管理する墓地や霊園ごとに異なります。
実際には、17回忌、33回忌、50回忌までとされている寺院や霊園が多いようです。
故人を偲び弔うために執り行うために年忌法要を行います。
この年忌法要は、一般的に33回忌までで年忌法要を終えて、弔い上げをすることが多いです。
弔い上げをすると、故人を弔うのではなく、祖先として弔うことになります。
永代供養墓に遺骨を安置できる期間も、33回忌までとするのが平均的なケースです。
永代供養墓に遺骨を安置している間は、供養も行ってくれます。
しかし、どのくらいの頻度でどんな内容で行うかは、各永代供養墓で異なります。
供養について希望がある場合は、各永代供養墓で行われる供養の内容を確認しておくことが必要です。
安置期間が過ぎたら
永代供養墓に安置されている遺骨は、各個人ごとに骨壺に収められており、遺骨を取り出すことができます。
使用期間を過ぎると永代供養墓から取り出されて、他の方の遺骨と合祀されるのが一般的です。
安置期間後に合祀されると、故人の遺骨を取り出すことはできなくなります。
合祀されたからといって、供養が行われないわけではなく、安置期間中と同じように供養されます。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
永代供養の費用の内訳

永代供養の場合に必要な費用は、永代供養料、お布施、刻字料の3種類があります。
永代供養の費用は、永代供養墓の種類によって異なり、数万円単位から100万円単位とかなりの違いがあります。
一般的には、単独墓がもっとも高く、集合墓や合祀墓がそれに続きます。
すなわち、個人に割り当てられるスペースなど、一般のお墓に近くなるほど高くなる傾向にあります。
お布施は遺骨を納骨する際に執り行われる供養で僧侶に渡すものです。
刻字料は、石碑などに個人の名前を刻む場合に必要になる費用です。
なお、戒名を刻む場合は、別途お布施が必要になることに注意しましょう。
永代供養の費用をきちんと知りたい方は下記の記事をお読みください。
永代供養墓の種類
永代供養墓といっても、埋葬方法やお墓の種類などによってさまざまなものがあります。
以下では、主なお墓の種類について説明します。
単独墓
一般的なお墓と同じように、個別に骨壺を収めることができ、墓石を立てることもできるタイプです。
ただし、使用期間が決まっており、使用期間を過ぎると合祀されることに注意が必要です。
集合墓
納骨スペースは個別に確保されますが、墓石を個別に建てられるわけでなく、石碑など共通のものが設置されます。
個別に確保された納骨スペースは使用期間が決まっており、使用期間を過ぎると合祀されることに注意が必要です。
合祀墓
遺骨を最初から他の方と合祀するタイプです。
石碑などは共通のものが用意される場合が多いです。
納骨堂
お墓を持たない方が納骨スペースを確保して安置できる場所です。
都心などに設置されたロッカー型の納骨堂などが利便性の点で注目されています。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
永代供養のメリット・デメリット
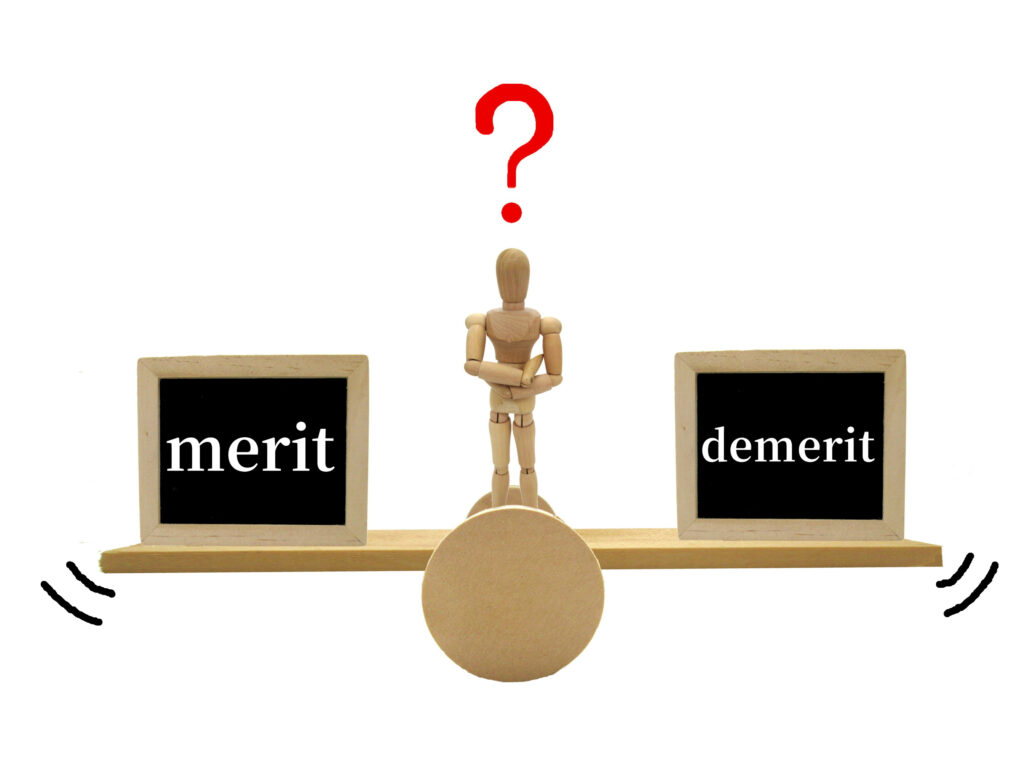
永代供養にもメリットとデメリットがあります。
永代供養のメリット
永代供養のメリットとしては、以下の2点があげられます。
遺骨の管理を任せられる
永代供養の最大のメリットは、遺骨の管理と供養を寺院などの墓地管理者に任せられることです。
お墓の定期的な清掃や維持管理、跡継ぎ問題などを気にすることはありません。
また、供養も行ってくれるので安心です。
宗教・宗派はなんでも良い
お墓を持つ場合は、自分の家の宗教や宗派を受け入れてくれる場所を探す必要があります。
永代供養なら、宗教や宗派を気にする必要はありません。
ただし、寺院の運営する永代供養墓では、その寺院の檀家にならないと申し込めない場合があります。
檀家になる必要があるのかどうかを確認するようにしてください。
永代供養のデメリット
永代供養のデメリットとしては、以下の2点があげられます。
故人のお墓の前で合掌できないことも
永代供養墓では、お参りに行った場合に故人の眠っている場所までいけないことがあります。
永代供養墓全体に共通の香炉や花台などが設定されていて、各個人ごとのお参りをするというわけにはいかない場合があるのです。
その場合は、お花やお供え物はお参りが終わった際に持ち帰るのがマナーなので注意しましょう。
一定の期間が過ぎると合祀される
永代供養墓の単独墓や集合墓の場合、お墓の期間が決まっています。
そのため期間が過ぎると合祀されます。
なお、合祀されてしまうと遺骨は取り出せなくなります。
永代供養の期間についてのまとめ

ここまで永代供養の期間についての情報や、永代供養の種類などを中心にお伝えしてきました。
本記事のまとめは以下の通りです。
- 永代供養は、墓地管理者がお墓の管理や供養を行ってくれる
- 永代供養の期間は一般的には33回忌まで
- 期間が過ぎると合祀される
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。
お墓の関連記事
お墓

更新日:2023.11.19
遺骨を永代供養した場合位牌は位牌堂に?位牌堂について詳しく解説
お墓

更新日:2022.11.17
位牌の永代供養の相場とは?永代供養の際の位牌について詳しく解説
お墓

更新日:2022.10.21
永代供養したら仏壇はどうする?仏壇の役割や処分方法について解説
お墓

更新日:2024.02.03
永代供養にも回向料はかかる?回向料のマナーまで解説
お墓

更新日:2025.05.08
浄土真宗の永代供養の表書きの書き方は?書く時の注意点や永代経についても紹介



