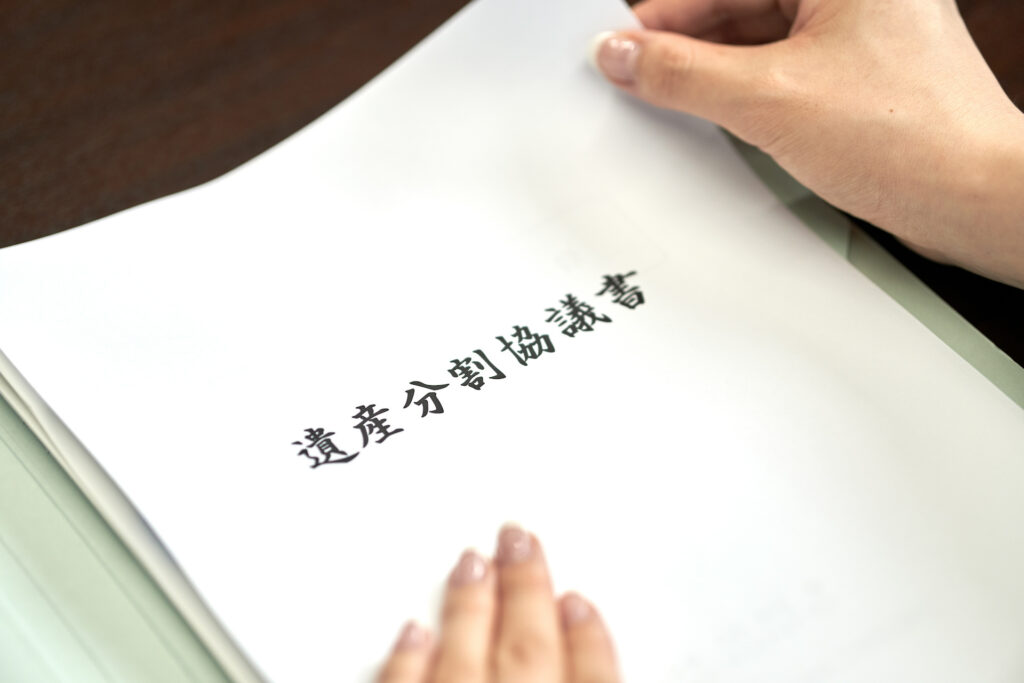相続
祭祀承継者がいない場合はどうなる?継承の破棄や放棄についても紹介
更新日:2024.02.03 公開日:2022.05.25

記事のポイントを先取り!
- 祭祀承継者とは墓や仏壇を継承する人
- 祭祀承継者がいない場合お墓は撤去される
- 祭祀継承者に指定されると拒否できない
- 祭祀継承者をいとこに頼むことも可能
お墓や仏壇などの祭祀財産を承継する祭祀承継者がいない場合、どうすれば良いかご存知でしょうか。
祭祀承継者がいない場合には、どのように祭祀財産を継承するのかについて知っておきましょう。
そこでこの記事では、祭祀承継者がいない場合について詳しく説明していきます。
この機会に祭祀継承者に指定されると拒否できないことを覚えておきましょう。
祭祀承継者がいない場合のお墓選びについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
- 祭祀承継者とは
- 祭祀承継者がいない場合
- 祭祀承継者はいるけど拒否したい場合は?
- 相続放棄すれば継承権も放棄できる?
- 祭祀承継者はいとこなどにお願いできる?
- 祭祀承継者がいない場合のお墓選び
- 祭祀承継者がいないまとめ
祭祀承継者とは
人が亡くなると、その人の残した財産を相続する必要があります。
金銭などの場合は、相続する人に分けるのも簡単です。
ただ、ここで問題になるのは、仏壇やお墓などの死者を弔う際に使うものをどう分けるかです。
こうしたものは、分割することが難しいものになります。
死者を弔うための財産を「祭祀財産」といい、これを受け継ぐ人を「祭祀承継者」といいます。
一般的には、誰が仏壇やお墓を守っていくのかという部分が、この祭祀財産の継承の内容となります。
また、祭祀承継者になるのは基本的に単独の人です。
故人が祭祀承継者を指定していた場合には、その人が祭祀承継者となります。
祭祀承継者が指定されていない場合は、その地域や宗派の慣習で決められることが多いようです。
例えば長男や、故人とずっと一緒に暮らしていた人などが該当します。
慣習がない場合は、家庭裁判所で祭祀承継者決定の調停や審判手続によって決めることになります。
この場合は、祭祀承継者になるべき人物を、故人との関係や一族の中での立場、金銭的余裕などから合理的に妥当な人を選び出す判断がなされます。
祭祀承継者がいない場合
子どもがいなかったり、親戚がいなかったりと、様々な理由で祭祀承継者となる人がいない場合があります。
こうした場合の祭祀財産の扱いについては、いくつかのパターンがあります。
墓地や霊園の場合は、そこで決められている規則に従うことになります。
祭祀承継者が明らかにいない場合にはお墓は撤去され、遺骨などは無縁仏として共同のお墓に合葬される場合が多いようです。
最終的にお墓のあった場所は更地にされ、管理者の判断で別のお墓を売りだしたり、給水場所にしたりして活用されます。
菩提寺の場合は、規則といったものがない場合も多いようです。
明らかに使用されていないお墓があり、祭祀承継者がいないことが分かると、やはり撤去されてしまう場合があります。
お寺や地域の慣習にしたがって、無縁の遺骨は共同の墓に合葬されるなどの措置がとられます。
ただし、霊園やお寺側でもすぐに撤去できるわけではありません。
お墓の整理をする場合は、縁故者に1年以内に申し出なければならないことが法律で定められています。
縁故者が見当たらない場合には、お墓を撤去する旨を立札や官報に掲載した後、1年が経過すれば霊園やお寺側の判断でお墓を撤去できます。
祭祀承継者にはなれない立場の人の中に、お墓の管理の申し出をしてくれた人がいた場合でも、最終的にお墓を管理している霊園などとの話し合いが必要です。
祭祀承継者がどうしてもいない場合には、事前にお墓の管理者に相談しておくことも必要だといえるでしょう。
祭祀承継者はいるけど拒否したい場合は?

祭祀財産はお墓の管理や仏壇の管理など、とても手間のかかる財産でもあります。
そのため、祭祀承継者がいても、祭祀財産を継承することを拒否したい場合もあるでしょう。
では祭祀承継者となったら、祭祀財産の継承を拒否できるのでしょうか。
祭祀承継者は拒否ができない
祭祀承継者は、お墓や仏壇の祭祀財産の継承を拒否することはできません。
金銭や土地などの通常の遺産の場合は、遺産相続の際に「相続放棄」することにより、遺産を受け取らないようにすることが可能です。
しかし、祭祀財産の場合は相続法のルールとは別です。
金銭などの遺産を相続放棄したとしても、祭祀承継者に指定された場合、祭祀財産だけは受け継がなければなりません。
継承が難しい場合はどうすれば良い?
祭祀承継者になったとしても、今後の祭祀財産の継承が難しいといった時にはどうすれば良いのでしょうか。
祭祀承継者になることは拒否できませんが、祭祀財産を手にした後、それをどのように活用するかは祭祀承継者に権利があります。
そのため、祭祀承継者の置かれた環境や金銭的余裕などにあわせて、祭祀財産をどうするかを考えていくことになります。
墓の場合は墓じまいをして、お墓自体を撤去してしまう方法もあります。
お骨は、菩提寺や霊園などに永代供養や散骨などの相談をして、しかるべき方法で供養が可能です。
また、自宅の仏壇に安置しておく手元供養を選択しても良いでしょう。
仏壇や仏具、その他の宗教的な道具も祭祀財産になりますが、こうしたものを処分したり売却したりすることも祭祀承継者に権利があります。
ただし、宗教的な事柄は、勝手なことをしてしまうと親戚などとのトラブルになる可能性もあります。
祭祀承継者に全ての権利があるとはいえ、処分を考えたい場合は、親戚などに一度相談しましょう。
相続放棄すれば継承権も放棄できる?

上記でも少し触れましたが、遺産の相続を放棄した場合でも祭祀承継の権利を放棄することはできません。
祭祀承継者は民法で定められており、遺産を相続するのとは別物とされています。
そのため、遺産の相続放棄をした場合でも、継承の権利は失われません。
ただし、祭祀承継者が遺言などで指定されていない場合や、慣習で決められていない場合は、家庭裁判所で判断してもらうことが可能
です。
家庭裁判所では、死者や先祖に対する気持ちなどを考慮して祭祀承継者を指定します。
祭祀承継者として遺言で指定されていたり、地域の慣習などで決まっていたりする場合は、継承権を放棄することはできません。
祭祀承継者はいとこなどにお願いできる?
祭祀承継者は、家族を指定しなければならないという規定はありません。
家族などがおらず、祭祀承継者が身近にいないという場合もあります。
そうした場合、いとこなどに祭祀承継者をお願いすることもできます。
いとこでも祭祀継承者にはなれる
祭祀承継者が家族にいない場合には、いとこなど、信頼のおける人に祭祀承継者になってもらうことができます。
遺産相続は法定相続人に分けるように決まっていますが、祭祀承継者の場合は生前に指定したり、遺言で指定したりすることが可能です。
法定相続人になる人物ではなくても、血のつながりの濃い親族であるいとこなどは、祭祀承継者になれます。
また、信頼がおけるなら友人や知人でも構いません。
家族がいない場合などは特に、誰が今後、墓や仏壇などを管理してくれるのかをよく考えて祭祀承継者を決める必要があります。
指名する際の注意点
祭祀承継者が家族にいない場合、いとこなどを祭祀承継者に指定することは可能です。
ただし、祭祀承継者に指定されると、祭祀財産の継承を拒否できないことになります。
場合によっては、指定を受けた人に、大きな負担がのしかかるかもしれません。
祭祀承継者をいとこなどに指定する場合は、事前に本人とよく相談しておくことが必要です。
また、金銭的な負担をできるだけ軽くするようにしておくことも大切だといえます。
事前に、自分の入るお墓のある菩提寺や霊園などに、永代供養料を支払っておくこともその一環です。
また、永代供養墓を購入しておくことなども検討すると良いでしょう。
自分が亡くなった場合、いつ、どのようにお参りしてほしいのかをあらかじめ相談しておくのも有効です。
また、祭祀承継者が、金銭的な負担などで将来的に祭祀が難しくなった場合のことまでを含めて、相談しておくとなお良いでしょう。
何より大切なのは、誰もが最小限の負担で、とどこおりなく祭祀承継がなされることです。
祭祀承継者がいない場合のお墓選び
祭祀承継者がどうしてもいない場合、自分が入るお墓が今後どうなってしまうのか、供養はどうなるのか、不安に思うこともあるでしょう。
ここでは、祭祀承継者がいない場合のお墓選びについて解説していきます。
永代供養墓
永代供養墓は、お寺や霊園墓地の管理者がいなくならない限り、永続的に管理してくれるお墓です。
通常のお墓の場合、管理料として少額を月や年単位、もしくは複数年で支払うことになります。
永代供養墓の場合は、お墓の管理者に前もって永代供養料として少し高めの金額を支払って管理してもらいます。
祭祀承継者がいなくても、永代供養墓を用意しておけば、管理者によって供養してもらうことが可能です。
永代供養墓には合祀墓とよばれるものがあり、これは複数の遺骨を一緒のスペースにまとめて供養していくものです。
また、納骨堂として、寺や霊園の建物の中にロッカーのような空間を設置している場合もあります。
納骨堂では、一人一人や家族単位で骨箱を納めて供養してもらうことが可能です。
また、仏壇型になったものや、位牌を置くようになっているものもあります。
樹木葬
墓石ではなく、樹木を祭祀の象徴としたお墓です。
樹木のまわりに遺骨を納めることになります。
自然との調和が取れたお墓として最近は人気も出てきており、祭祀承継者がいるいないにかかわらず、選択する人も増えています。
基本的に合葬の形式をとっている場合は、比較的割安となります。
複数人の区画を用意する場合は、40万円〜100万円程度の金額がかかります。
散骨
遺骨をあらかじめ砕いておき、海や山にまいて供養する方法です。
遺骨はその後残らないので、誰に撒いてもらうのかだけを決めておけば、祭祀承継者など、撒くのを頼まれた人の負担も少なく済みます。
ただし、遺骨は2ミリ以下の粉末にまで砕いたものであることや、撒く場所の土地の所有者に許可をもらっていることが条件になります。
また、撒く土地も、条例や国の指導に反していないことが条件です。
土地の所有者の許可をクリアできたとしても、近隣の人などに嫌がられることもあるかもしれません。
もし散骨を検討するのであれば、事前に現地の情報を集め、土地の所有者をはじめ関係者とよく相談して決める必要があるでしょう。
祭祀承継者がいないまとめ

ここまで祭祀承継者とは何かや、いない場合のお墓選びなどについてお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 祭祀承継者は墓や仏壇などの祭祀財産を受け継ぐ人
- 祭祀継承者に指定されると拒否できない
- 祭祀継承者が家族にいない場合、いとこに頼むことも可能
- 祭祀承継者がいない場合、永代供養墓などの活用を検討
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。