死亡後の手続き
死亡退職後に支給された給与の取り扱いについて。税金はかかる?
更新日:2022.05.17 公開日:2022.06.04

記事のポイントを先取り!
- 死亡退職とは在職中に被相続人が亡くなること
- 死亡後の給与は指定された方または法定相続人に支払われる
- 死亡後の給与も課税対象となる
- 定められた上限を超えた弔慰金は課税対象となる
死亡退職とは在職中に亡くなり退職することをいいますが、死亡退職後の給与の取扱いについてご存知でしょうか。
死亡退職後の給与は、誰に支払われ、税金はどうなるのかを知っておきましょう。
そこでここでは、死亡退職後の給与の取り扱いについて詳しく解説していきます。
この機会に死亡退職後の給与や賞与はどうなるのかについて覚えておきましょう。
弔慰金にかかる税金についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
- 死亡退職とは?
- 死亡退職後に支払われる給与の取り扱い
- 死亡後3年経過後に支給が確定した場合
- 死亡退職金の受取人は?
- 死亡退職金は相続放棄していても受け取れる?
- 他の人はこちらも質問
- 弔慰金には税金がかかる?
- 死亡退職後に支給された給与についてのまとめ
死亡退職とは?

死亡退職とは、働いていた方が在職中に亡くなってしまったことにより、退職扱いになることです。
遺族には、退職金や功労金、これらに準ずる「死亡退職金」が会社などから支払われます。
死亡退職後に支払われる給与の取り扱い
死亡退職後に支払われる給与は原則、以下のようになります。
- 死亡退職後、3年以内に支給が確定した給与、賞与は相続財産として相続税の対象になる
- 死亡前に支給の時期が来た給与、賞与は所得税の対象になる
このように、死亡退職後に支払われる給与は状況によって違ってきます。
ここでは、
- 働いていた方が、8月3日に亡くなった
- 7月分の給与と8月3日までの給与を、8月15日に受け取り予定
- 毎月の給与支給日は25日
という例を基に死亡退職後の給与の取り扱いについて詳しく説明していきます。
死亡前に支給期が到来していた場合
死亡前に支給期限が到来していた場合、支給される給料は生前給与となります。
今回でいうと7月分の給与に関しては、所得税の源泉徴収、かつ、死亡退職時の年末調整が行われます。
死亡時までに支給日が到来していない場合
死亡時までに支給日が到来していない場合、つまり今回でいうと8月分の給与に関しては、相続財産となるため、相続税が課税されます。
一方、所得税は課税されません。
給与以外に、賞与や死亡後に確定した給与アップの差額なども、相続税が課税され、所得税は課税されません。
死亡後3年経過後に支給が確定した場合
死亡後3年が経ってから支給が確定したものに関しては、支給を受けたご遺族の一時所得の扱いになるため、所得税が課税されます。
たとえば、令和2年7月1日に亡くなられた場合、亡くなられてから令和5年6月30日までに支給が確定したものは、相続税の対象になります。
しかし、令和5年7月1日以降に支給が確定したものに関しては、所得税の対象となります。
死亡退職金の受取人は?
死亡退職金の受取人は、原則的には法定相続人になります。
しかし、被相続人(亡くなられた方)が、死亡退職金の受取人を指定した遺言書を用意していたり、会社の就業規則などによって受取人が定められている場合はそちらが優先されます。
法定相続人とは、民法の規定にある相続人のことをいいます。
被相続人の配偶者や、子または孫、兄弟姉妹や甥姪、養親や養子がこれに該当し、この中で受け取れる優先順位が決まっています。
上の順位に該当する相続人がいなかった場合に、次の順位の方に相続対象が移ります。
第一順位は、被相続人の配偶者です。
第二順位は、被相続人の子供になりますが、その子供がすでに亡くなられている場合にはその子供の直系卑属(ちょっけいひぞく)、つまり、被相続人の孫やひ孫が受取人になります。
また、被相続人に養子がいた場合には、実子と対等の相続人となります。
第三順位は、被相続人の直系卑属、つまり、被相続人の両親や祖父母が相続人になります。
被相続人の両親も祖父母もご存命の場合には、被相続人とより世代の近い被相続人の両親が優先されます。
また、被相続人に養親がいた場合、実親と対等の相続人になります。
第四順位は、被相続人の兄弟姉妹になります。
被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなられている場合には、兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥姪が相続人になります。
死亡退職金は相続放棄していても受け取れる?

「相続放棄」とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産、すべての財産を放棄することをいいます。
相続放棄している場合、死亡退職金の受け取りの可否は、状況によって変わります。
死亡退職金を受け取れる場合と、受け取れない場合、それぞれについて詳しく解説していきます。
相続放棄しても死亡退職金を受け取れる場合
死亡退職金の受取人が遺言や規定により決まっている場合は、相続財産の対象ではなく「固有の権利」といった扱いになります。
そのため、相続放棄していても死亡退職金を受け取ることが可能です。
相続放棄したら死亡退職金を受け取れない場合
死亡退職金の受取人が被相続人になっている場合は、相続財産の対象となるため、死亡退職金を受け取ることは不可能になります。
死亡退職金が相続財産の対象であった場合、死亡退職金を受け取ってしまうと、すべて相続する「単純承認」と判断されます。
単純承認と判断されてしまうと、相続放棄はできなくなってしまいますので注意しましょう。
他の人はこちらも質問
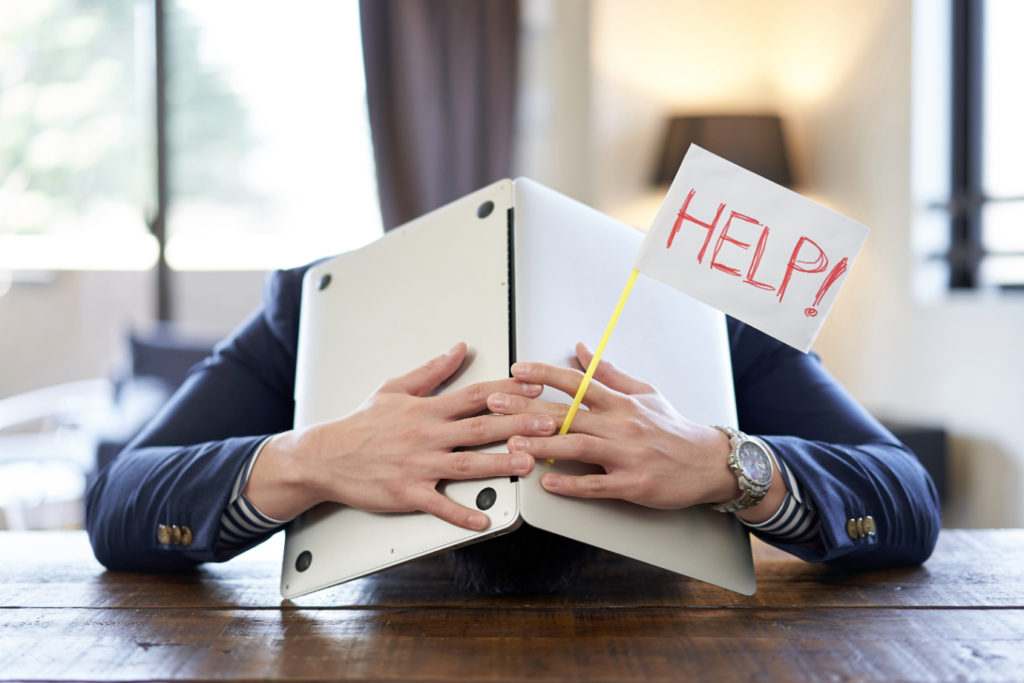
死亡退職の給与と関連した質問についてまとめてみました。
ぜひ参考にしてください。
死亡退職、給与、誰に?
死亡退職された場合の給与は原則的には、相続人への支払いになります。
ただし、被相続人や会社の規定によって、死亡退職後の給与の支払先が指定されている場合には、そちらが優先となります。
また、相続人には優先順位があり、「相続人の配偶者」「相続人の子または孫」「相続人の両親または祖父母」「相続人の兄弟姉妹または甥姪」の順になります。
死んだら退職金はどうなる?
働いていた方が在職中に亡くなってしまった場合、受け取るはずだった退職金は原則ご遺族に支払われることになります。
受け取るはずだった退職金がなかったことにはなりません。
ただし、退職金が支払われるのは、あくまで亡くなられた方が務めていた会社に退職金の制度があった場合です。
退職金の制度がない会社の場合には、退職金は支払われませんので覚えておきましょう。
会社によっては、退職金の制度がなくても「死亡弔慰金」「功労金」などの名目で支給されることもあります。
また、被相続人が遺言によって退職金の受取人を指定していた場合や、会社の規定によって受取人が決まっている場合には、相続人ではなく決められた方に支払われます。
死亡退職、年末調整、還付金は誰に?
還付金とは、年末調整などで源泉所得税を多く納めていたことが分かった場合に、支払いすぎた差額分を納税者に返還するものです。
死亡退職した方に対して行った年末調整で、還付金が生じた場合には相続人に支払います。
この場合の還付金は、受け取った相続人の所得にはならず、相続財産の扱いになるため相続税課税の対象となります。
死亡、年末調整、いつまで?
たとえば、在職者が9月15日に亡くなってしまった場合、亡くなった年の1月1日から8月31日までの年末調整は、亡くなった際に行います。
年末調整は、一般的にはその年の年末に行われますが、この場合には年末まで待つ必要はなく、亡くなった時点で年末調整します。
8月31日までの給与は、亡くなる前に支給される給与になるため、年末調整の対象になります。
しかし、9月1日から9月15日までの給与は亡くなった後に支給される給与のため、相続財産となり相続税の対象になりますので、注意しましょう。
弔慰金には税金がかかる?
弔慰金(ちょういきん)とは、故人様を弔い(とむらい)、ご遺族を慰めることを目的に贈られるお金のことです。
弔慰金は基本的には相続税の課税対象にはなりません。
しかし、弔慰金として取り扱われる金額には上限があるため、その上限を超えてしまった分の金額は相続財産とみなされます。
そのため、超過分の金額に関しては相続税の課税対象となるため、弔慰金をいただいた場合には注意が必要です。
また、故人様(被相続人)の雇用主などから弔慰金として金銭などを受け取った際に、実質上、死亡退職金などと該当された部分に関しては、相続税の課税対象になります。
ここでは、弔慰金の上限や、弔慰金が非課税となった場合の相続税の計算方法について詳しく解説していきます。
相続税が非課税となる弔慰金の額
弔慰金の上限は、被相続人が業務上の理由で亡くなったか、業務上の理由とは関係なく亡くなってしまったかによって違います。
被相続人が業務上の理由で亡くなられた場合の弔慰金
「死亡時の給与×36ヶ月分」
被相続人が業務上とは関係ない理由で亡くなられた場合の弔慰金
「死亡時の給与×6ヶ月」
と、なります。
業務上の理由としては、以下のようなものがあり、
- 業務中の死亡
- 出張中に起きた事故による死亡
- 職業病による死亡
- 通勤途中の災害による死亡、など
被相続人が業務上の理由で亡くなってしまった場合の弔慰金には、ご遺族に対する保証の意味も込められています。
そのため、業務上とは関係のない理由で亡くなられたしまった場合の弔慰金よりも金額が大きくなります。
たとえば、死亡時の給与が20万円であった場合、業務上の理由で亡くなられた場合の弔慰金は720万円、業務上とは関係ない理由の場合には120万円になります。
弔慰金が非課税となった場合の相続税の計算
弔慰金の上限を超えた文の金額に関しては、相続税の課税対象となり、死亡退職金の非課税枠となるのは「法定相続人一人に対して500万円まで」です。
たとえば、法定相続人が5人いる場合の死亡退職金の非課税枠の計算は、「500万円×5人=2,500万円」です。
つまり、死亡時の給与が20万円だった被相続人が、業務上の理由で亡くなられた場合の弔慰金は、720万円が上限金額で、被相続人の法定相続人が5人いる場合は、3,220万円を超えると超えた分の金額が、相続財産の課税対象となります。
死亡退職後に支給された給与についてのまとめ

ここまで死亡退職や、死亡退職後の給与の取り扱いについて触れてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
死亡退職とは、被相続人が在職中に亡くなり退職すること
死亡後の給与は指定がない限り原則的に法定相続人に支払われる
死亡後の給与も課税対象となるため注意が必要
上限を超えた弔慰金は、課税対象となる場合がある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
死亡後の手続きの関連記事
死亡後の手続き

更新日:2022.05.01
死亡退職した社員の年末調整の還付金は誰に?計算方法についても解説
死亡後の手続き

更新日:2024.01.24
死亡退職金の受取人は誰?複数人いる場合の受け取る順位も紹介


