相続
遺産整理ってどうやる?進め方やポイント、費用相場について解説
更新日:2022.04.18 公開日:2022.05.06

記事のポイントを先取り!
- ・遺産整理ではまず遺言書の有無を確認
- ・複雑な遺産整理は専門家に相談
- ・専門家なら節税しながらの整理が可能
- ・弁護士の遺言書検認相場は10万円〜15万円
親族が亡くなると遺産を整理していくことになりますが、遺産整理の進め方はご存じでしょうか。
遺産整理をスムーズに進めるためにも、流れやポイントを知っておきましょう。
そこでこの記事では、遺産整理について詳しく説明していきます。
この機会に、遺産整理の進め方や注意点についても覚えておきましょう。
遺産整理を専門家に依頼するメリットについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
遺産整理の進め方
まずは、遺産整理の進め方について紹介していきます。
遺産整理をスムーズに進めるためにも、流れを知っておきましょう。
遺言書の有無を確認する
遺言書には法的な効力があり、遺産相続においては非常に重要なものです。
遺言書がある場合には、遺言書の通りに遺産分割が行われます。
そのため、まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。
相続人同士で話し合う遺産分割協議で分割内容が決定したあとに遺言書が発見された場合には、再度協議をやり直さなければいけなくなるので、非常に大変です。
遺産整理をスムーズに終わらせるためにも、初めに遺言書の有無を確認するようにしましょう。
相続人を確定する
遺産分割においては、相続人が誰であるのかを確認していくことが重要です。
なぜなら、相続分割する際には相続人全員の承諾が必要になるためです。
相続人を調査するためには、本籍地のある市区町村役場にて故人の死亡から出生までの全ての戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本の取得手続きを行う必要があります。
直接役場の窓口で申請ができるほか、郵送でも可能なので、自分に合った方法を選ぶと良いでしょう。
また、民法により、相続する権利のある人(法定相続人)は定められています。
配偶者はどのようなケースであっても相続人となりますが、その他の相続人の中には優先順位があります。
優先順位が高い順に以下にまとめます。
①故人の子ども
②父母や祖父母などの故人の直系尊属
③故人の兄弟姉妹
相続対象となる財産を確認する
次に、故人の残した財産の中で相続の対象となるものは何なのかを確認していきます。
遺産とは、故人の残した全てのものです。
この中にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。
以下に財産の対象となるものを挙げていきます。
【プラスの財産】
- 預金や貯金
- 不動産
- 有価証券
- 自動車や船舶
- 土地
- 仮想通貨
- 知的財産権
- 保険金
【マイナスの財産】
- 借金
- 未払い金
- ローンの残債
- 保証債務
- 葬儀費用
- 未納の税金
- 損害賠償の責任
遺産分割協議をする
法定相続人が確定し相続財産がどれぐらいあるのかが明確になったら、相続人全員で相続財産の分け方をどうするのかを話し合います。
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要になるので、不参加の人や反対する人が1人でもいると相続分割が成立しません。
また、相続人が全員そろっていないのにもかかわらず、遺産分割協議を行ったケースでは、相続分割が無効となるため注意が必要です。
遺産分割協議で解決しなかった場合は遺産分割調停を行う
遺産分割協議で遺産の分割内容が決まらなかった場合には、遺産分割調停を行います。
遺産分割調停では、家庭裁判所で調停委員が相続人の間に立って話し合いを進めていくことになります。
この遺産分割調停の場合、相続人同士が顔を合わせなくて済むため比較的スムーズに進めやすいでしょう。
調停が成立したあとには調停調書が作成され、内容に従って相続手続きが進められることになります。
遺産分割調停でも解決しなかった場合は遺産分割審判を行う
遺産分割調停でも相続分割の内容が決定しなかった場合には、遺産分割審判に自動的に移行されることになります。
遺産分割審判とは、家庭裁判所で相続人が書類や証拠などを提出して主張や立証を行うことです。
遺産分割調停とは違い、必ず遺産分割の審判が下りるのが特徴といえます。
審判が下りると審判書が作成され、内容に従って相続手続きが進められていきます。
この決定内容には必ず従う義務があり、万が一従わなかった場合は、強制執行などの措置がとられます。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議にて遺産の相続分割が決まったら、遺産分割協議書を作成してその内容を残しておきます。
遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名や押印が必要です。
このことで、相続人全員が納得の上、相続分割をしたという証明になります。
遺産分割協議書は、必ず残さなくてはいけないわけではありません。
しかしあとあとの相続トラブルを防ぐためにも、作成することをおすすめします。
各種名義変更をする
相続した遺産の中には、名義変更が必要なものもあります。
また、期限が設定されているものもあるので、忘れないよう早めに行いましょう。
以下に名義変更が必要な手続きを挙げます。
- 建物や土地などの不動産
- 預貯金
- 株式
- 生命保険
- ゴルフ会員権
- 自動車
- バイク
相続税の申告手続きをする
相続した遺産の中には相続税がかかるものもあります。
相続税には基礎控除制度がありますが、この基礎控除を上回る金額の遺産を相続した場合には相続税を納める必要があります。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
上記の計算式で基礎控除額が出せるので、状況に合わせて計算してみてください。
相続税を納めるときには、まずは申告手続きをする必要があります。
きちんと申告しなければ、加算税や遅滞税が課せられてしまうこともあるため、申告忘れがないように注意しましょう。
遺産整理における主な相談先
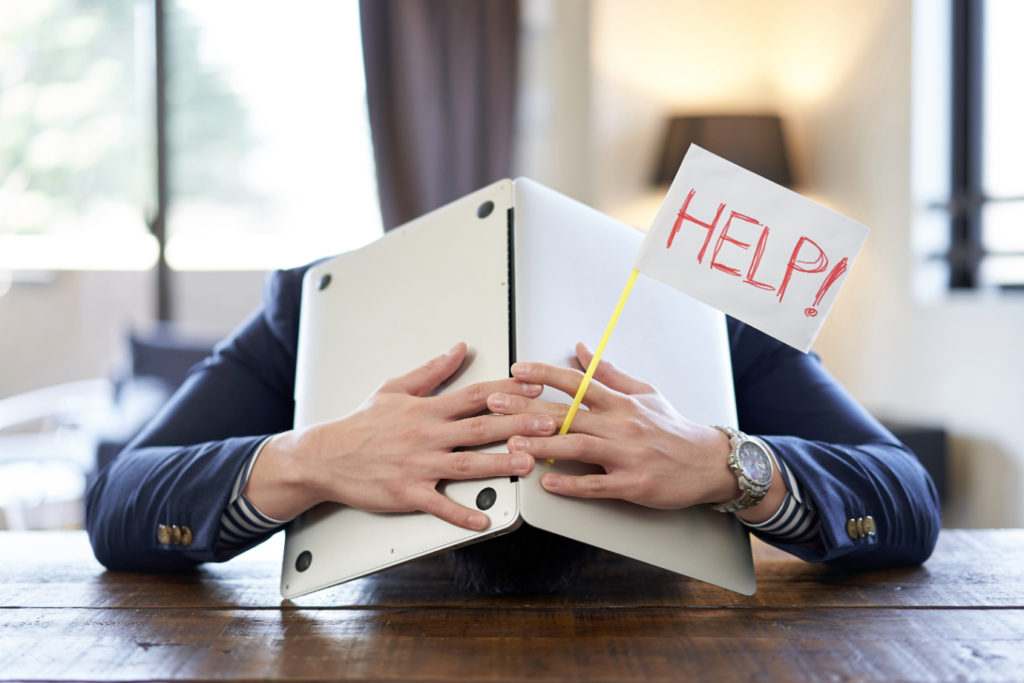
遺産整理や相続に関しては難しいことも多く、特にトラブルが起こった際などにはどうしたら良いかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、専門家の手を借りて遺産整理をしていく際の代表的な相談先について紹介していきます。
専門家によって得意な分野が違うため、問題が起こったときには適切な場所へ相談することが大切です。
信託銀行
信託銀行では、相続財産に関するアドバイスを受けられる他、相続財産を有効活用するためにはどうすれば良いのかなどの相談にも乗ってくれます。
ただし、信託銀行が直接相続の手続きをするわけではなく、実際の手続きに関しては外注が一般的です。
相続手続きの依頼先選びからサポートしてくれるので、できるだけ効率よく相続手続きを進めていきたい方にはおすすめです。
信託銀行で依頼できる業務内容を以下にまとめます。
- 各士業への依頼対応
- 相続手続に関する相談
行政書士
行政書士は、相続手続きに必要な書類の対応一式をサポートしてくれます。
他の専門家に依頼するよりも、依頼費用を抑えられるケースも多いので、できるだけ費用をかけたくない方には向いています。
また、ある程度の相続についての知識があり、必要な書類さえそろえられれば自分で相続手続きを進めることが可能といった方にはおすすめです。
ただし費用については事業所によって差が大きいので、まずは相談して見積もりを出してもらいましょう。
信託銀行で依頼できる業務内容を以下にまとめます。
- 遺言書の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人や相続財産の調査
司法書士
司法書士に相談した場合には、不動産を相続した際の名義変更である相続登記を一任できます。
弁護士と比べると対応できる範囲は限られてきますが、相続トラブルがなく、相続税が発生しないケースでは司法書士に依頼するのがおすすめです。
例えば、不動産の相続を考えている場合や、相続の際に会社に関する商業登記も変更したいケースでは、司法書士に依頼すると良いでしょう。
司法書士に依頼できる業務内容を以下にまとめます。
- 遺言書の検認手続(書類作成の代行のみ可能)
- 遺言書の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続放棄の手続(書類作成の代行のみ可能)
- 相続人や相続財産の調査
- 不動産の名義変更
税理士
税理士は、相続税についての対応が唯一可能です。
相続税が発生するケースだけでなく、相続税についての知識に自信のない方も税理士に相談すると良いでしょう。
税金に関する知識がなく、気づかぬうちに脱税していたようなケースもあるので、少しでも不安がある方は専門家の手を借りることをおすすめします。
税理士に依頼できる業務内容は以下の通りです。
相続人や相続財産の調査
- 相続税の申告
弁護士
相続トラブルで相手が弁護士をつけているケースや、相続トラブルが起きている際に裁判に発展しそうなケースでは、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談するメリットとしては、相続手続きの全般を依頼できる点です。
例えば、遺産分割協議や遺産分割調停、遺産分割審判などの相続トラブルに対応できます。
弁護士は幅広く対応が可能なため、相続を初めてする方でも安心です。
弁護士に依頼可能な業務内容を以下にまとめます。
- 相続トラブルの対応
- 遺言書の検認手続
- 遺言書の作成
- 遺産分割の内容の協議
- 遺産分割協議書の作成
- 相続放棄の手続
- 相続人や相続財産の調査
- 不動産の名義変更(一部可能ですが、基本的には司法書士が対応)
- 預貯金や株式の名義変更
遺産整理を専門家に依頼した場合の費用相場

次に、遺産整理を専門家に依頼したケースでの費用相場について紹介していきます。
信託銀行
信託銀行に遺産整理を依頼した際の費用相場を以下にまとめます。
相続財産の金額によって費用が異なるので注意してください。
- 5,000万円以下:2.200%
- 5,000万円以上1億円以下:1.650%
- 1億円以上2億円以下:1.100%
- 2億円以上3億円以下:0.880%
- 3億円以上5億円以下:0.550%
- 5億円を超える場合:0.440%
行政書士
行政書士は、依頼内容によって費用の相場が異なります。
以下に業務内容と行政書士に対する報酬をまとめます。
- 相続基本報酬:6万円~
- 戸籍や住民票取得:1通あたり1,500円
- 財産目録作成(遺産分割協議用):3万円~
- 遺産分割協議書作成:3万円~
- 金融機関の預貯金の相続手続き:3万円~
- 有価証券の相続手続き:3万5,000円~
- 自動車の相続手続き:3万円~
司法書士
司法書士に土地や家などの名義を変更する「相続登記」を依頼したケースでの相場について紹介していきます。
費用の相場は事務所によって差がありますが、費用の設定のポイントがいくつかあります。
例えば、相続人が複数いるケースや案件が複雑である場合には増額することが多いでしょう。
また、不動産の価値によっても費用相場が異なるようです。
安くて6万6,000円程、高い場合には15万円程となることもあります。
税理士
税理士に遺産整理を依頼した際の費用を以下にまとめます。
- 故人の戸籍謄本類の収集:数万円程度
- 遺産分割協議書の作成:数万円~
- 不動産の名義変更:1物件5万円~数十万円程度
- 未上場株などの手続き:数万円程度
- 家具などの遺品整理:1件分につき20万円~100万円程度
預貯金や上場株式の手続き、会員権などの手続きは経済的な利益の金額によって異なります。
相場は以下の通りです。
- 利益が300万円以下の場合:30万円
- 利益が300万円を超え3,000万円以下の場合:2%+24万円
- 利益が3000万円を超え3億円以下の場合:1%+54万円
- 利益が3億円を超える場合:0.5%+204万円
弁護士
弁護士に遺産整理を依頼した際の費用を以下にまとめます。
- 遺言書検認:10万円~15万円程度
- 遺言書作成:10万円~20万円程度
- 遺産分割協議書作成:10万円程度
- 相続放棄:10万円程度
- 相続人調査:10万円程度
- 相続財産調査:20万円~30万円程度
- 相続財産の名義変更(不動産を除く):10万円程度
相続トラブルを依頼した場合には、着手金の他にも成功度合いによって費用が異なります。
まずは相続トラブルの着手金として、20万円〜200万円以上の費用が必要です。
利益と報酬金については以下の通りになります。
- 利益が300万円以下:16%
- 利益が300万円を超えて3,000万円以下の場合:10%+18万円
- 3,000万円を超えて3億円以下の場合:6%+138万円
- 3億円を超える場合:4%+738万円
遺産整理を専門家に依頼する4つのメリット

依頼できる専門家やその費用相場が理解できたところで次は、専門家に依頼した際のメリットについて紹介していきます。
複雑な戸籍から法定相続人を特定してもらえる
戸籍謄本を調査する際には、戸籍の取得が必要になります。
しかし、この手続きは複雑になりがちです。
なぜなら、戸籍謄本は1カ所から発行を受けることができないためです。
過去の本籍地である全ての市区町村役場に問い合わせをして発行を依頼する必要があります。
また戸籍を取得したあとには、誰が法定相続人になるのかを正確に読み取らなければいけません。
専門家に依頼すれば、手間や判断力が必要になる手続きを専門家が相続人の代わりに行ってくれます。
これが専門家に依頼した場合のメリットの1つです。
相続財産の調査で新たな財産が見つかることも
故人にどのような財産があったのか調べようとしても、素人だと何から調べれば良いのかわからないものです。
それだけでなく、どこに問い合わせれば正しい回答がもらえるのかもわからず、不安を感じている人が多いといえます。
このような場合でも、専門家に依頼すれば専門的な知識や経験をもとに必要なサポートが受けられます。
中には、家族だけでは発見できなかった新たな遺産が見つかるようなケースもあるので、相続人にとってのメリットは大きいといえるでしょう。
相続税対策ができる
遺産を相続した場合には、分割方法によって税額が変わってきます。
そのため分割方法は非常に重要になるのですが、素人では何が最も良い方法なのかわからず、困ってしまうケースもあるでしょう。
税金に対しての知識に不安がある場合には、専門家に頼り、サポートしてもらうことで安心して手続きができます。
専門家に依頼した場合には、相続税対策をしながら最も負担の少ない方法で遺産分割が可能なのです。
複雑な名義変更の代行をしてもらえる
不動産や自動車などの遺産を相続した場合には、名義変更や税務申告が必要になります。
この手続きは難しく、自分で調べて行うと非常に時間がかかり、何度も修正することも少なくありません。
専門家に依頼すれば、司法書士や税理士、行政書士といった専門の士業と連携し、代行してもらえるので安心です。
遺産整理で注意すべきポイント

次に遺産整理で注意すべきポイントについて紹介していきます。
注意点を理解し、トラブルを未然に防いでいきましょう。
相続手続きには期限が設定されている
相続手続きには、それぞれ期限が定められているので注意が必要です。
期限内に手続きを終えなければペナルティを課せられてしまう場合もあるので、期限を守り、手続きを進めていくことが大切になります。
以下に各手続きの期限を紹介するので、参考にしてください。
- 相続放棄・限定承認・単純承認:相続開始を知った日の翌日から3カ月以内
- 故人の所得税の申告・納付:相続開始を知った日の翌日から4カ月以内
- 相続税の申告・納付:相続開始を知った日の翌日から10カ月以内
相続方法によっては借金を抱えることも
相続手続きの方法には、単純承認・限定承認・相続放棄という3種類があります。
選択を間違えると、借金を抱える可能性もあるので注意が必要です。
以下を参考に、どの相続方法が自分に合っているのかを選んでみてください。
単純承認
単純承認とは、故人の遺産をプラスの財産はもちろん、マイナスの財産も含めてすべて相続することです。
この相続方法は最も一般的なものになりますが、借金などの債務があるケースでは注意が必要です。
債務の割合については、相続人の間で自由に決められますが、その割合を債権者に主張することはできません。
例えば、次男が債務の全額を相続したとしても、債権者が次男から借金の全額を回収できなかった場合は、別の相続人から債務を回収する権利が債権者にはあります。
また、故人の財産を相続し、あとから多額の借金が見つかったケースにおいても、この借金も含めて相続しなければいけない点にも注意が必要です。
限定承認
限定承認とは、故人のプラスの財産の範囲内で借金などの債務の弁済義務を負うことです。
この方法では、故人の財産から債務を支払うため、相続人は自分の財産からお金を出す必要はありません。
故人の財産の総額がプラスとマイナスのどちらが多いのかわからないケースで有効な方法になります。
限定承認のメリットは、相続したあとに借金が見つかったとしても、故人のプラスの財産の範囲内で負担をするので、借金を相続する必要がない点です。
この点は相続人にとっては、非常にメリットの大きい方法であるといえるでしょう。
ただし限定承認は、手続きが複雑で手間がかかるため、実際には選択されないケースが多い
ようです。
相続放棄
相続放棄とは、故人の財産をすべて引き継がないものになります。
相続放棄では、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないので、借金がプラスの財産よりも多かったケースなどに有効です。
相続放棄をすると相続権がないことになるので、代襲相続の権利もなくなります。
相続放棄は、相続人の中で1人であっても行うことが可能です。
相続放棄には期限があり、故人の死亡により相続の権利があることを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
この期間内に申し出をしなかった場合には相続放棄は認められなくなり、単純承認をしたとみなされますので注意しましょう。
遺産整理のまとめ

ここまで遺産整理の流れや注意点などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 遺産整理をする際には、まずは遺言書があるのかどうかを確認する
- 遺産整理は複雑な手続きも多いため、専門家に相談するのがおすすめ
- 専門家に遺産整理を依頼すれば、相続税対策をしながら負担の少ない方法でできる
- 弁護士に遺言書検認を依頼した場合、10万円~15万円程度が相場
- 限定承認は故人の財産から債務を補うため自分の財産から負担する必要がない
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
監修者

鎌田 真紀子(かまた まきこ)
国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)
経歴
終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。
相続の関連記事
相続

更新日:2022.06.11
遺族年金が非課税である理由と節税方法・確定申告について紹介
相続

更新日:2024.10.27
遺族と相続人の違いは?定義や順位、割合について解説
相続

更新日:2025.05.20
遺産相続とは?手続きの流れ・相続人の範囲など基礎知識を解説
相続
更新日:2026.01.09
相続のお悩みには最適な専門家を|しきサポの相続をご紹介
相続

更新日:2022.04.27
遺産がいらない場合にはどうすれば良い?相続放棄のやり方を紹介
相続

更新日:2025.06.24
遺産分割トラブル、約4分の3が「遺産額5,000万円以下」…専門家が教える、生前の「財産整理」の重要性



