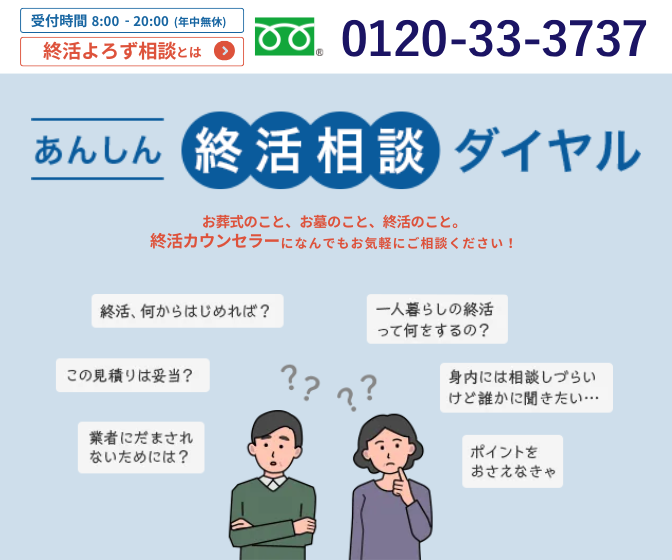終活
遺言書の内容に納得がいかないケースの対応について弁護士が解説
更新日:2025.12.11 公開日:2025.09.12
遺言書は亡くなった人の意思表示として最大限尊重し、その内容に沿って手続きを進めることが原則です。
ところが、本当に本人が自らの意思で作成したのか疑わしい、相続人であるにもかかわらず取り分がほとんど無い内容になっているなど、遺言書を巡って親族間でトラブルに発展するケースも少なくありません。
このようなときであってもなすすべが全くないというわけではなく、以下のような方法があります。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
1.無効を主張する

まずは、遺言書自体が無効であると主張する方法があります。
例えば遺言書を本人以外が記載していたり、日付や押印がないなど、民法で定められた方式に従って作成されていない場合は、方式を満たしていないとして遺言は無効となります。
また、遺言は法律行為にあたるため、遺言書作成時に認知症や精神疾患等による理由で遺言能力がなかったと判断されれば、その遺言書は無効となります。
遺言の無効を主張するには、まず交渉から行う
そのようなときには、地方裁判所に対して「遺言無効確認請求訴訟」を提起し、遺言が無効である旨の判決を得た場合、その遺言は無効となります。
遺言無効判決確定後には、遺言書が存在しない状態と同じになるので、相続人同士による遺産分割協議が必要です。
しかしながら、確認訴訟を起こした後に通常の話し合いを行うことは現実的に難しいため、遺産分割調停(家庭裁判所を通じて相続人間が遺産分割の話し合いを進める手続き)を通じて遺産分割方法を決定することとなるでしょう。
2.遺留分侵害額請求を行う
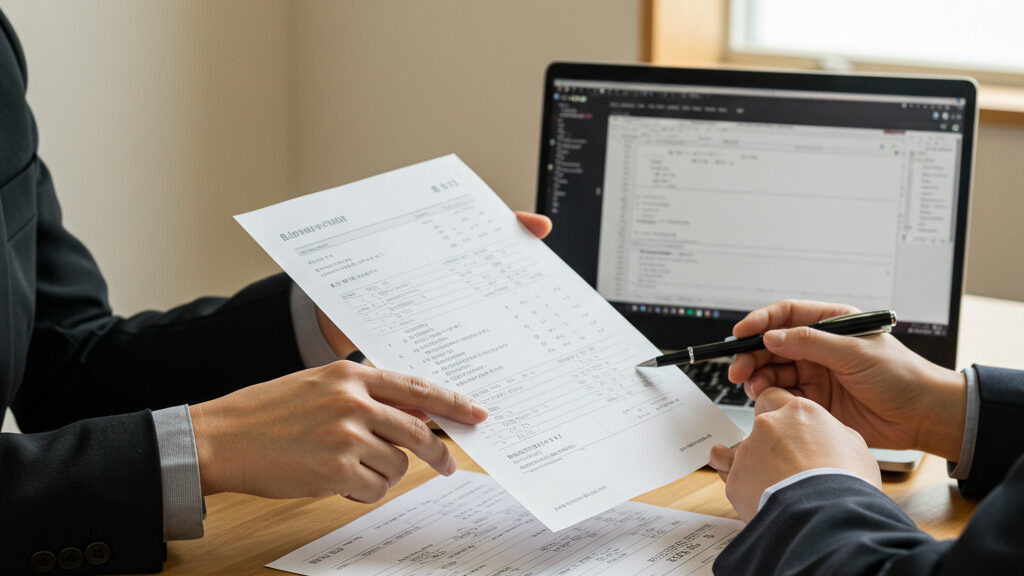
法定相続人には、相続することができると法律で定められている最低限の取り分として遺留分があります。
例えば遺言書の中で「長男に全ての遺産を相続させる」という遺産分割の方針が記されていた際は、他の相続人は自己の遺留分侵害額請求権に基づく請求を検討することとなります。
なお、遺留分侵害額請求は、必ずしも調停や訴訟をしなければならないということではありません。
遺留分を侵害した相手方に、内容証明郵便等で遺留分を侵害された旨の明確な意思表示をしたのち、相続人間の協議で合意がなされれば、穏便な解決に至れます。
相手方が合意に応じなければ、そこから調停ないし訴訟に発展する可能性があります。
いずれの方法にしても、親族間で各々が自己の利益だけを考えて感情的になってしまっては、穏便な解決とはなりません。
お互いが納得できるまで誠実に話し合い、解決できるのが理想ですが、話し合いが平行線のままであったり、全く連絡がとれなくなってしまったりなど、当事者間だけでは到底解決に至れない際には、できるだけ早めに相続トラブルに強い弁護士に相談してみましょう。
【監修】
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 堅田 勇気(神奈川県弁護士会所属)

一橋大学法学部法律学科卒業。相続分野マネージャー、横浜オフィス支店長を務める。相続を中心に、離婚、不動産法務など、幅広く取り扱う。
相続人が30人以上の複雑な案件など、相続に関わる様々な紛争案件の解決実績を持つ。
Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションに掲げ、遺産相続や離婚相談、交通事故をはじめとする個人法務の他、上場企業からスタートアップ企業までを支える企業法務や、建物明渡訴訟などの不動産法務、誹謗中傷対応や刑事事件まで、幅広いリーガルニーズにお応えする総合法律事務所です。
スポンサーリンク
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。