終活
遺影の選び方は?ポイントや注意点をふまえて解説
更新日:2025.03.28 公開日:2022.06.02

記事のポイントを先取り!
- 遺影には故人の人柄が伝わるような写真が選ばれることが多い
- できれば生前から遺影を撮影しておくことがおすすめ
- 写真の修正では故人の服装を変更することができる
大切な人が亡くなった際には遺影が必要になりますが、その選び方をご存じでしょうか。
遺影の写真は何でも良いわけではないので、選び方を知っておきましょう。
そこでこの記事では、遺影の選び方のポイントについて詳しく説明していきます。
この機会に遺影の選び方や注意点について覚えておきましょう。
葬儀後の遺影はどうするのかについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 遺影に適切な写真の選び方
- 遺影は笑っていても良い?
- 遺影に適切な写真がないときはどうする?
- 遺影の加工方法
- 故人の写っている写真がない場合は?
- 遺影選びのタイムリミットは短い
- 生前から遺影を撮影しておきましょう
- 遺影の撮影方法
- 葬儀後の遺影はどうする?
- 遺影の選び方まとめ
- 写真館アワード
遺影に適切な写真の選び方
まずは遺影写真の選び方について紹介していきます。
ひと昔前までは遺影写真には、スーツや和服などのフォーマルな服装で正面から撮った真面目な表情をしているものが良いとされていました。
しかし、実際には遺影の写真に明確な決まりはありません。
そのため、近年では以下のような故人の人柄が伝わるような写真が選ばれることが多くなっています。
- 笑顔などの自然な表情の写真
- 故人の気に入っていた服装をした写真
- 正面ではなく横顔の写真
このような自然な写真が選ばれることが多くなりました。
選ぶ際は、画素数が高く鮮明な写真や、ピントが合い故人の姿が大きく写ったものが良いでしょう。
また、できるだけ最近撮影した新しい写真を選ぶことがおすすめです。
遺影は笑っていても良い?

ひと昔前までは遺影の写真は、真面目な硬い表情のものが多かったため、遺影は笑ってもいいのか疑問に思われる方もいるでしょう。
遺影選びのポイントとしては、故人らしさが伝わるような自然体な姿が感じられる写真がおすすめです。
そのため、遺影は笑っている写真でも問題ありません。
例えば、趣味を楽しんでいるときの写真や旅行先や家族団らんのときの楽しんでいる姿や穏やかな表情などが良いでしょう。
故人の生前の姿が伝わるような写真を選べば、遺族にとっても故人を思い出し懐かしむ良い遺影になります。
遺影に適切な写真がないときはどうする?

次に、遺影に適切な写真がない場合、どのように対応すれば良いのかについて紹介していきます。
例えば、故人が事故などで急死し、生前は写真を撮られることが好きではなく、遺影に使えるような写真がないケースなどが挙げられます。
このようなケースであっても遺影は加工が可能なので、加工することで遺影として使用できる状態に修正することができます。
そのため、適切な写真がなくても問題ありませんのでご安心ください。
遺影の加工方法については次の章で詳しく紹介していきます。
遺影の加工方法
ここからは、どのような写真加工が可能なのかを説明していきますので参考にしてください。
サイズが変更可能
遺影用として選んだ写真はサイズ変更が可能です。
具体的には遺影に使用する写真は、葬儀の際に後ろの席に座っている人からもよく見えるように引き延ばすことが一般的です。
全身が写っている、離れた場所から撮影しているといったような写真しかないケースでも、サイズを拡大することで遺影用の写真に変更ができます。
この際には胸元から上がはっきりと写っていて正面を向いているような写真を選ぶと良いでしょう。
集合写真であっても故人のみを切り取ることが可能
1人で写っている写真がないケースでは、集合写真を活用して故人のみを切り取ることができます。
集合写真は隣の人と重なっているような立ち位置であることもあり得ます。
このような場合でも、背景を変更したり、色合いを変えたり、足りない部分を付け足したりできるので安心してください。
修正を依頼する際には、不足している部分の故人のイメージや服装などを事前に伝えておくと自然な仕上がりに近づきます。
服装を変更することも可能
写真の修正では故人の服装を変更することもできます。
遺影写真を作成する際に本当は、スーツや着物などの正装を希望していたのに、そういった写真がなかったというケースもあるでしょう。
このような場合では、服装を写真加工にて変更依頼することをおすすめします。
お気に入りのスーツや希望する服装があれば事前に伝えることでスムーズに修正することが可能です。
スナップ写真でも可能
遺影写真は、真正面を向いてカメラ目線の必要があると思われる方も多いでしょう。
確かにできればこのような写真であることが望ましいですが、スナップ写真の中から条件に近いものを選んで遺影用として加工することができます。
遺影用に修正する際には、足りない部分を付け加えたり、背景や服装を変更したりすることができるので安心してください。
日常生活で撮ったスナップ写真の方が故人の自然体の姿や柔らかい表情が出やすいメリットがあります。
現像した写真しかない場合でも可能
近年はデジカメやスマホなどで写真を撮影することが多いので、データとして画像が残っているようなケースも少なくありません。
データやネガがないと写真の加工ができないと思われがちですが、これらがなかったとしても問題ありません。
写真をそのまま取り込み、パソコン上で加工作業を行うことが可能です。
写真の傷や汚れがよほどひどくない限りは、遺影として使用することができるようになります。
故人の写っている写真がない場合は?
次に、手元に故人の写っている写真がない場合の対応方法について紹介していきます。
このようなケースでは、親戚に故人の写真がないか確認したり、趣味仲間や地域ネットワークからの写真を探したりすると良いでしょう。
こういった対応をしたとしても、写真が見つからないケースでは、免許証などの証明写真を使っても問題ありません。
この他にも、画家に依頼して肖像画を作成するといったサービスを行っている葬儀社もあります。
遺影選びのタイムリミットは短い
遺影は故人が亡くなってからお通夜までに用意する必要があります。
亡くなってからお通夜や葬儀が執り行われるまでの期間は、2日程度が一般的です。
写真を選択するだけでなく、サイズを調整したり、加工したりする必要があるケースも多いため、早めに遺影を選んでおくことが大切になります。
生前から遺影を撮影しておきましょう

故人が亡くなってから遺影を選ぶと、大変期間が短く慌ててしまうケースも多いでしょう。
そのため、できれば生前から遺影を撮影しておくことをおすすめします。
遺影を生前に撮影し用意をしておけば、遺族に負担をかけることなく、自身にとっても納得のいく写真を準備しやすくなります。
人が亡くなると悲しみや混乱の中でもやるべきことが多く、遺族には非常に負担がかかります。
少しでも負担を減らし、時間に余裕を持って行動できるように事前の準備は大切なことになります。
遺影の撮影方法
次に、遺影の撮影方法について紹介していきます。
どのような方法があるのか以下を参考にしてください。
自分で撮影する
近年はスマホやデジカメなどで気軽に写真を撮ることができます。
写真を撮ることが身近になっている現代では、自分で撮影することに慣れている方も多いでしょう。
「自撮り」と呼ばれる言葉も一般的になり、工夫して撮る方が多いですが、遺影の撮影には三脚などを使用すると安定するのでおすすめです。
自分で撮影するメリットは、費用がかからない点や写真を何度でも納得いくまで撮ることができる点です。
人に撮影を依頼した際には、撮られているという緊張から表情が固くなったり、何度も撮ってもらうことに申し訳なさを感じたりする方も珍しくありません。
しかし、自分で撮影すれば気兼ねなく写真撮影を進めることができ、ストレスもかかりません。
プロに撮影してもらう
プロに撮影してもらうことも遺影の撮影方法の一つです。
撮影場所は写真館やフォトスタジオなどが代表例です。
プロに任せるメリットは、質の高い写真を撮影してもらうことができる点です。
メイクを依頼することができ、衣装もレンタル可能で照明もしっかり当ててもらえるので、きれいに撮影できる環境が整っています。
姿勢や目線などについてもプロのアドバイスを受けられるので、イメージに合うように撮影することが可能です。
プロに依頼した場合には費用はかかってしまいますが、希望通りの写真を残し、納得のいく遺影を残すことができるでしょう。
葬儀後の遺影はどうする?

最後に葬儀後の遺影の取り扱い方法について紹介していきます。
四十九日までは後祭り祭壇に飾る
遺影は葬儀が終了すると後飾り祭壇に安置されることが一般的になります。
この後、飾り祭壇は基本的には四十九日まで飾られることになりますので、遺影も同様に四十九日まで飾られるケースが多くなります。
四十九日後は処分するもしくは飾り続ける
四十九日後は仏壇の近くに遺影を飾るスペースがあれば、そこに先祖代々の遺影と同様に安置されることが多いでしょう。
古くからこうして遺影を飾ることが一般的でしたが、近年では先祖代々の遺影を飾る家も少なくなってきています。
遺影自体には宗教的な意味合いはないので、処分したり、しまっておいたり、小さめの写真をフォトフレームに入れて飾ったりすることが多いようです。
処分をする場合には、家庭ごみとして自宅で破棄しても良いですし、それが心苦しいという方は葬儀社やお寺でお焚き上げをしてもらうのも良いでしょう。
初盆や法事などの仏事の際には遺影を使用することになるため、大切に保管することが必要になります。
遺影の選び方まとめ
ここまで遺影の選び方の情報や注意点などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
遺影には、画素数が高く、鮮明で故人の姿が大きく写ったものが適している
遺影は背景や色合いを変更したり、足りない部分を付け足したりすることができる
プロに撮影依頼をすれば希望通りの納得のいく遺影を残すことが可能である
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
写真館アワード
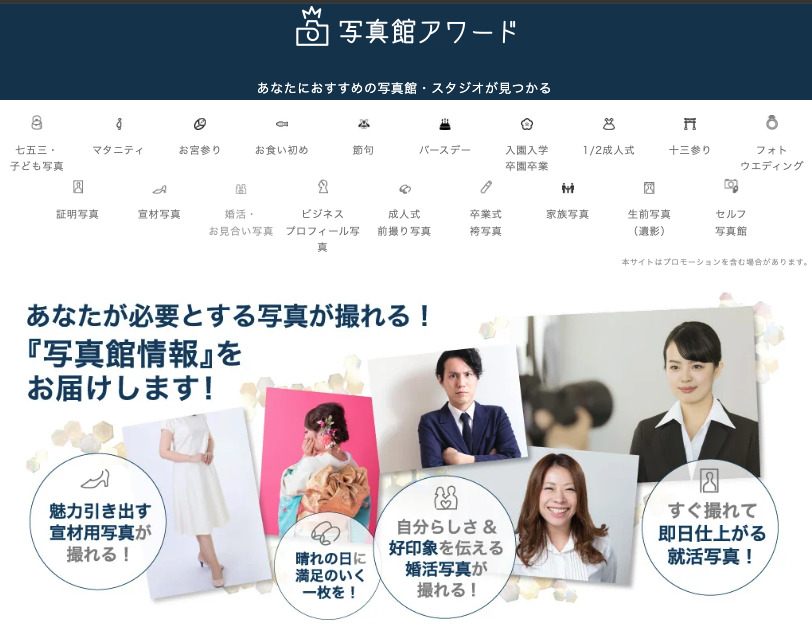
「写真館アワード」には、遺影写真が撮れるおすすめの写真スタジオがまとめられています!エリア別に紹介されているため、自分にぴったりの写真スタジオを見つけることが可能です。
遺影写真を撮影しようと考えている方は、あわせてチェックしてみてください。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
終活の関連記事
終活

更新日:2022.05.03
遺影を選ぶとき笑顔の写真は避けるべき?最適な表情、選び方を解説
終活

更新日:2022.05.17
浄土真宗の遺影の飾り方は?浄土真宗の祭壇やルールを解説!
終活

更新日:2022.05.17
遺影の置き場所はどこがおすすめ?遺影の飾り方についても紹介
終活

更新日:2022.05.17
遺影は自分で作ることができる!作り方の手順や注意点を紹介
終活

更新日:2022.05.17
遺影の飾り方は壁掛けがいいの?現代に合った遺影の扱い方とは
終活

更新日:2022.05.17
葬儀後の遺影はどうするべき?保管方法や処分方法について解説


