法事法要
供養の本質は故人を偲ぶ気持ち|京都博國屋
更新日:2022.03.18 公開日:2022.03.11
「お墓を建ててあげたいが、お墓参りがなかなか行けそうにない。。。どうしたらいいのだろうか。」
「亡くなったことがつらく感じている方がいて、どうしたらいいのだろうか。」
故人の供養の方法は、家族ごとで違うのが当たり前になってきました。
昔は代々一族がお盆やお彼岸などのタイミングで定期的にお墓参りするのが普通でしたが、今は永代供養・散骨・手元供養といった昔では考えられない供養を選択する方が増えています。
供養の本質は故人を偲ぶ気持ち・感謝する気持ちと、京都博國屋代表の山崎譲二氏がおっしゃっていました。
そこで、手元供養品を取り扱っている京都博國屋について紹介していきます。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
京都博國屋とは
京都博國屋とは、清水焼で一品一品丁寧に作る”納骨オブジェ お地蔵”をはじめ、様々な手元供養品を販売しています。
京都博國屋の代表を務めている山崎譲二氏は、手元供養の言葉を作られた方です。
具体的なサービスや始められたきっかけなど、代表 山崎譲二氏にお伺いします。
代表の山崎様にインタビュー
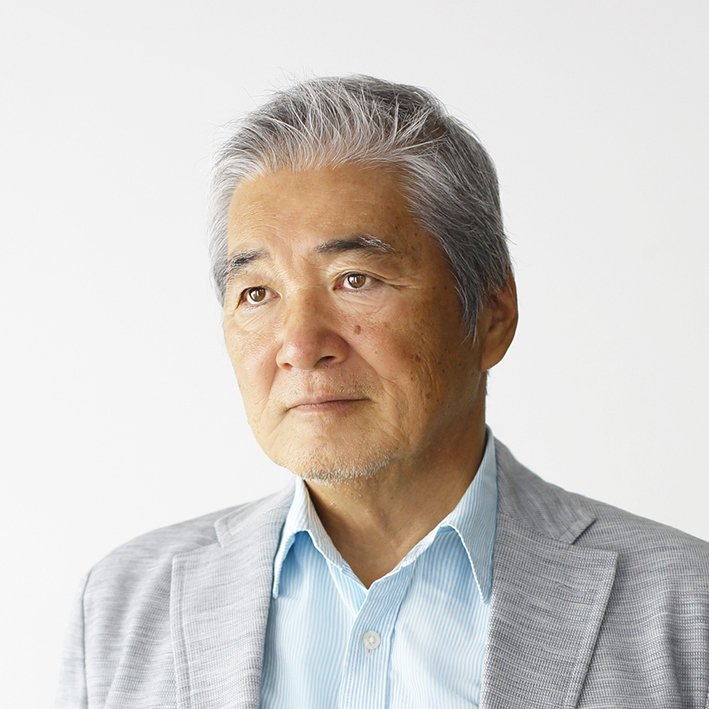
手元供養の確立
選んだ終活: 手元供養を発想したのは山崎様ご自身で、きっかけは山崎様のお父様のがん告知だとお伺いしました。
そこで、手元供養がどのように確立したのかをお伺いしてもよろしいでしょうか?
山崎代表:ちょうど私の大学時代が学園闘争のときでした。
セクト(新左翼党派)は入っていないんだけど、ノンセクト・ラジカル(1960年代に起きた運動)の立場で、いろいろ社会問題に向き合っていました。
そのころ先輩や活動家の皆様が下宿に来たときに、お前たちそんなんでいいのかって言われました(笑)
今じゃ考えられない時代だけど(笑)
まあ、その中で私なりに今の人生哲学というか見方っていうのがですね、社会の今あることが、常識となっているのは必ずしも合理性がなかったり、慣習やしきたりとかに流されて、規制されていることをいろんな方に叩き込まれてきました。
供養っていうのは、基本的にはお墓があって、仏壇があって、お寺さんに供養を頼むことだけど、そこに疑問を感じた。
ようするに、従来の供養の考え方が腑に落ちなかった。
父親が最初肝臓がんを発症したが、最後は脳まで転移してしまった。
父親の生きざまが素晴らしく、男としてすばらしいと思っていて、尊敬しています。
今では、絶対の愛で育ててくれたと感じられるようになっています。
尊敬する父親が肝臓がんを発症してしまい、1年以内に亡くなると医者に言われたときに、ものすごく後悔しました。
とても尊敬している父親だったので、自分なりに供養をしたいと思い、亡くなったあとに、どう感謝をすればいいのかたくさん考えました。
その結果、亡くなったあとの従来のしきたりあるいは世間体の形の供養の仕方は私にはしっくりきませんでした。
そこでいろいろ考え、様々な本を読み漁って、自分なりの供養とはという問いに対する答えが見つかりました。
それは供養の対象をお骨にするということです。
ただし、お骨そのものは供養の形とはなっていないから、お骨を何かの形で手を合わせられるような方法を考えました。
焼き物を手元供養として
選んだ終活:手元供養品として、焼き物を選択された経緯を教えてください。

山崎代表:私はお酒が好きで、おちょこを集めていました。
私が集めていたのは、一品ものの作家が作ったものや古窯で作ったものです。
わりと自由に選んでは、その時の気分でおちょこを選んで日本酒を飲んでいました。
おちょこを選んで日本酒を飲んでいく中で、焼き物は一品一品で違うなと感じました。
つまり、おちょこを作るときに使用する土とか窯の中の置き場所で焼き物が変わると感じました。
おちょこの影響で、親父の手元供養品は焼き物でつくりたいなと感じました。
今は葬祭業界に身を置いていますが、昔はまちづくりとか都市計画の仕事をしていたので、いろんな委員会で、友だちになりました。
京都の清水焼を作る古窯の友人、清水泰博氏を思い出しました。
彼は早稲田の建築出身で、東京藝大大学院ではプロダクトを学び、現在は東京藝大でデザイン科の教授をやっています。
彼は次男坊で、兄が六兵衛九代目をやっています。
彼に、なんとか焼き物の技術を用いて、手元供養を作りたい、それで私は、供養をしたいんだと相談しました。
彼は引き受けてくれて、私がスケッチブックにデザインをし、彼が僕のデザインを実際に形にしてくれました。
それで作ったものがお地蔵さんのオブジェです。
清水泰博氏は清水六兵衛八代目がなくなったときに、私がデザインしたオブジェで手元供養をしています。
大切な人を身近において、偲びたい・感謝したい。
そういう思いで手元供養品を作っていきました。
博國屋の由来
選んだ終活:お店の名前を”博國屋”にした理由をお伺いしてもよろしいでしょうか?
山崎代表:お店の名前を”博國屋”にした理由は、実は手元供養の由来に関係があります。
最初に手元供養の由来から説明します。
まず、新しい葬送の文化を作りたいと思って、色々考えました。
日本人に馴染みがある言葉で思い浮かんだのが供養という言葉です。
さらに、手元に置いて供養するということで手元供養という名前を考えました。
手元供養とは、手元に置いて供養するということだけでなく、手元に置いて元気をもらう意味も込めています。
手元の”元”は元気の”元”です。
実際に私も事務所の机の上に、お地蔵さんの中に両親の骨を入れて置いているけれども、近くで見守られているような気がします。
また、お店の名前の由来なのですが、博は”文化とかひろめる”意味があり、國は文字通り”国そのもの”です。
つまり、”博國屋”という名前は新しい葬送の文化を国にひろめていきたいという思いでつけました。
ちなみに、商品を売ってひろめていくということではなくて、新しい”手元供養”という文化をひろめていきたいという思いもあります。
手元供養を広める際の壁
選んだ終活: 手元供養品を販売していく中で苦労したことがありましたら、教えていただきたいです。
山崎代表:手元供養という言葉を作ったんですけど、その当時は京都の桂坂っていう大きいお屋敷まちのプランニングをやっていました。
まちのプランニングをやっていたときは、マーケティングから商品企画までやっていました。
まちのプランニングと並行で、手元供養について考えていきました。
手元供養の考えはどうだろうと人に聞いてみたことがあります。
僧侶・石屋・樹木葬・散骨・仏壇屋さんのキーマンたちにヒアリングしてみました。
当時はというか、だいぶいまは薄れてきたけど、お寺さんの力が強かったと思います。
だから、お寺さんに遠慮して、なかなか手元供養品をお店ではおけないなと言われてしまいました。
新しい文化なので、なかなか手元供養をしっかりと理解してもらえなかったことに苦労しました。
いまでこそ、手元供養を行う人は10万人と増えてきてはいるけど、あの当時は手元供養を行う人は3000人とか5000人とかそのぐらいでした。
今後の需要
選んだ終活:今後の手元供養の需要について教えてください。
代表:手元供養品というのは、葬儀を行った喪主だけでなく、兄弟や故人が生前お世話になった方とかその人を偲びたいと思う人が対象で、1人が亡くなったからといって、対象が1人というわけではありません。
130万人が亡くなる時代ではありますが、子供2人で手元供養品を1つ所持していると考えたら、手元供養の利用者は10万人ではなく5万人となり、意外と少ないかもしれません。
手元供養はどんどんマーケットとして増えていくのではないかと考えていて、認知される方が増えていってくれたらと思っています。
どういう打ち出し方をすればいいかわからないけれども、需要は10倍、100倍増えていくだろうと考えていますが、なかなか難しい部分もあります。
いっときヒットしたとしても、販売店では、よほど嘆き悲しんでいる人にしか手元供養品を紹介してくれません。
なかなか商品を見せても、手元供養とは分からないから、説明に時間がかかります。
もし単価が10万以下で、歩合制だと、仏壇とか高いものを売ってしまう傾向にあります。
高いものを売るということは、セールスマンは当然の考えです。
ユーザーサイド目線に立つと、特に若い世代は個が本当にばらばらになっています。
今の若い世代は個と個のつながりをもとめていると感じてます。
自分となくなった方のつながり方を考えた時に、手元供養という考えが大事になっています。
京都博國屋は、手作りにこだわった商品ばかりなので、ペットロス・人間ロスになっている方々に対して、偲び方を知ってもらうのが大事だと考えています。
手元供養の商品が様々な形で出てくるのはいいが、お骨を入れるということを重々承知した上で、利用してほしいです。
みんなが選んだ法事法要の電話相談
みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
5万円からご案内!
4万円からご案内!
会社概要
社名 | 有限会社 博國屋 |
| 所在地 | 〒604-0993 京都市中京区寺町通夷川上ル久遠院前町669-1 サンアートビル4F |
理念 | 国内生産にこだわり、特に京都の伝統工芸や最新技術の職人方の技(わざ)をお借りして一品一品にこだわりを込め制作しています。 愛する家族の終のすみかであり、手を合わす対象となる手元供養品ですので素材力や存在感を大切に考えています。 |
事業内容 | 手元供養品の製造販売・葬送関連サービスの提供・講演、セミナー実施等 |
| 設立 | 平成14年8月8日 |
| URL | https://hirokuniya.com/company/(京都博國屋) http://www.temoto-kuyo.org/(NPO手元供養協会) |
実際に取材を行った感想

今回の取材を通して、手元供養がどのようにして確立したのかや、手元供養品を販売していくなかで苦労したことを理解することができました。
皆様もぜひ、京都博國屋の手元供養品を利用されてはいかがでしょうか。
今回は、京都博國屋様を取材させていただきました。
山崎様、お忙しいところ取材に応じてくださり誠にありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。


