相続
遺産相続における不動産の分け方とは?4つの方法を解説
更新日:2025.07.28 公開日:2022.05.11

記事のポイントを先取り!
- 不動産相続の分割方法は4種類
- 相続人と相続財産の調査が必要
- 不動産の共有は避ける
- 評価方法はものによって異なる
遺産を相続する際、相続財産が不動産だった場合の分け方をご存知でしょうか。
相続人一人なら問題ありませんが、不動産を複数の相続人で分ける場合はどのようにして分けたら良いのかわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、遺産相続で不動産を分ける場合の方法について解説します。
不動産は分割できない遺産のため、分ける方法を知っておくことが重要です。
また、相続する不動産の種類別の注意点も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
- 遺産相続で不動産を分けるには?
- 不動産を相続するまでの手続きや流れ
- 不動産の共有はできるだけ避ける
- 相続する不動産の評価方法
- 他の人はこちらも質問
- 相続する不動産の種類ごとの注意点
- 遺産相続における不動産の分け方のまとめ
- りあログ
- 株式会社FUTATABI
- フドログ
遺産相続で不動産を分けるには?
まずは遺産相続において、不動産を複数人で分けなければならない場合に最適な4つの方法をご紹介します。
不動産を分割する際は、以下の方法のいずれかを検討しましょう。
現物分割
現物分割とは、不動産を現物のまま相続する方法です。
一人の場合には、不動産をそのまま単独で相続すれば問題ありません。
しかし、複数の相続人で不動産を相続する場合には、分筆によって分割されます。
分筆とは、土地を複数の人で分けて相続し、登記をそれぞれに行う方法です。
この方法では、土地を法定相続割合と同じ割合で分けます。
ただし、分筆は土地のみ可能となっており、その土地に建っている建物は分筆できないため注意しましょう。
また、条例により、分筆が不可能な場所もあります。
換価分割
換価分割とは、不動産を売却して手に入れた金銭を複数の相続人で分け合う方法です。
不動産を売った金銭は、法定相続割合に応じて各相続人に分けられます。
ただし、売却したお金には所得税と住民税がかかります。
また、売却の手続きには経費も生じるため、その経費を差し引いて、残ったお金が分割の対象です。
売却するまでには時間がかかります。
また、売却を急ぐと安値でしか売れないこともあるため注意が必要です。
代償分割
代償分割とは、不動産を一人が単独で相続し、他の相続人に法定相続割合に応じた代償金を支払うという方法です。
この方法では、建物を分割できない現物分割よりも公平性が高いため、それぞれが満足できる結果になりやすいでしょう。
ただし、代償分割では不動産の評価を行わなければならず、評価方法によって金額が変わるケースもあります。
どの評価方法にするかで、相続人の間で意見が対立する可能性もあるでしょう。
共有
不動産を複数の相続人で共有の財産とするという方法もあります。
不動産を分割するのではなく、そのままにするのが共有です。
相続人は法定相続割合に応じて、共有持分を所有します。
共有持分とは、共有者の所有割合を表すものです。
スポンサーリンク
不動産を相続するまでの手続きや流れ

ここからは、不動産を相続するまでの手続きと流れについて解説します。
以下で、不動産の遺産相続が起こった場合にどういった手続きをすれば良いかをご紹介しましょう。
相続人調査と相続財産調査の実施
相続することになったら、まずは相続人と相続財産の調査を行いましょう。
相続人を調べるには、被相続人の戸籍謄本が必要となります。
生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を見て、相続人を確定させます。
併せて、相続財産を調査します。
預貯金や証券・貴金属・自動車まで、相続財産は多岐に渡ります。
事前に調査を行い、相続後に新しい財産が見つかるなどの事態を避けましょう。
また、借金などのマイナスの財産も相続財産に含まれるため、後から借金が見つからないように先に調べておく必要があります。
まずは相続人と相続財産を全て特定し、相続の実施が可能な状態にする必要があります。
遺言書を確認する
遺言書がある場合には、その内容に従って相続が行われます。
そのため、故人が遺言書を遺していないかを確認しましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
公正証書遺言の場合には、公証役場に遺言書が保管されているため問い合わせてみましょう。
他の2種類に関しては被相続人が保有していると考えられるため、遺品を確認する必要があります。
財産目録の作成
次に、相続人の財産をまとめた財産目録の作成を行います。
不動産が相続に含まれているかを確認するには、固定資産税の納税通知書を確認すると良いでしょう。
また、市区町村の役所で名寄帳を確認すれば不動産を一覧で取得できます。
名寄帳とは、個人が所有する不動産の一覧表のことです。
遺産分割協議を行う
遺言書が存在していたら、基本的にその遺言書の内容に従って遺産相続を行います。
しかし、相続人全員が合意した場合は遺言書の内容に従わず、遺産分割協議で分割内容を決定することが可能です。
また、遺言書が存在していない場合も、遺産分割協議を行うことで、それぞれ何を相続するかを決定します。
相続人全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、それぞれどの遺産を相続するかを詳細に記載しましょう。
相続登記を行う
相続登記とは、不動産などの相続財産の名義を被相続人から相続人に変更することを指します。
相続登記には必要となる書類が複数あるため、事前に準備しておく必要があります。
相続税の申告と納付
相続税の申告と納付には期限があり、その期限を守らなければ特例の適用ができなくなったり、延滞税が発生したりします。
そのため、期限内に忘れずに申告と納付を行いましょう。
相続税の申告は、相続を知った次の日から10ヶ月以内です。
意見が合わなければ遺産分割調停・審判へ
遺産分割協議で相続人全員が合意に至らない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行います。
遺産分割調停とは、調停委員が話し合いに参加することで解決策やアドバイスを提示してくれるものです。
調停でも協議が合意に至らない場合は、審判を行って分割内容を決定することとなります。
審判とは裁判官がそれぞれの言い分を聞いた上で、遺産分割の割合や内容を決定する方法です。
基本的に遺産分割協議は相続人間で決定するのが望ましいですが、もし意見が合わなければ調停や審判も検討することになります。
不動産の共有はできるだけ避ける
不動産を共有した場合、不動産に関する様々な手続きに権利者全員の同意が必要となります。
例えば、不動産のリフォームや売却、建物の建築など、あらゆる手続きを権利者全員が同意しなければなりません。
結局、土地が活用できなくなり、所有しているだけの状態になる可能性もあるため注意が必要です。
基本的に不動産の共有は避けて、他の3つの方法での分割を目指しましょう。
相続する不動産の評価方法
相続する不動産は、どういった方法で評価されるのでしょうか。
土地や家屋など、評価する対象によって異なる評価方法が存在するため、それぞれ詳しく解説します。
土地の評価方法
土地の評価方法は大きく分けて2つ存在しています。
まず1つ目が「路線価方式」です。
これは、路線価と呼ばれる土地の面する道路ごとに設定された価格に応じて評価額を決定する方法です。
国税庁が路線価図を公表しているため、これに沿って計算を行います。
ただし、土地によっては路線価が定められていないケースがあります。
その場合には、2つ目の評価方法である「倍率方式」で評価を行いましょう。
倍率方式とは、固定資産税評価額にその土地で設定されている倍率をかけることで評価額を決定する方法です。
ここで使用される倍率は、国税庁が評価倍率表として公表しているため、それを活用します。
参考:相続税における路線価の重要性と計算方法をわかりやすく解説
家屋の評価方法
家屋の評価方法としては、多くの場合で固定資産税評価額を活用しますが、時価により評価するケースもあります。
時価で評価する場合は、専門家に依頼して再調達価格を調べてもらいます。
再調達価格とは、現在その建物を建てたらいくらかかるかを求めて、経年による減点を行うことで算出する評価額のことです。
他人に賃貸している不動産の評価方法
賃貸にしている不動産では、自用地の評価額から借地権を控除して評価額を算出します。
そのため、自用地よりも評価額が下がるのが特徴です。
またアパートやマンションなど、所有している土地を他人に貸している貸家建付地の評価方法は他の不動産とは変わります。
貸家建付地の評価額は「自用地評価額×(1− 借地権割合 × 借家権割合 )」で算出できます。
他の不動産と違って評価方法が複雑になるため注意しましょう。
他の人はこちらも質問

ここからは不動産の遺産相続に関して、他の人が疑問に思っている点をご紹介します。
質問への回答も記載しているので、ぜひ参考にしてください。
相続 不動産 どうする?
不動産の相続をする場合は、まず不動産に関する書類を集めて相続の対象となる不動産を特定しましょう。
そして被相続人の戸籍謄本で、相続人を特定します。
相続人が特定できたら、全ての相続人を集めて遺産分割協議を行い、どの遺産を誰がどの割合で分割するのかを決めましょう。
遺産分割協議が合意に至ったら、遺産分割協議書にその内容を詳細に記載します。
作成した資料を法務局へ提出し、登記申請を行いましょう。
これで不動産の相続は完了となります。
相続 不動産はどうなる?
不動産は、前述した方法によって相続人で分割するか、単独の相続人が相続します。
また、相続放棄された不動産に関しては国の所有物となります。
相続 不動産 誰に?
不動産の相続は、遺言書がある場合はその遺言に従って相続されるのが通常です。
また、遺言書がない場合は法定相続人が相続します。
1人の場合はその人物が単独で相続しますが、2人以上の場合は遺産分割協議か法定相続で、法定相続人が相続することとなります。
遺産相続 誰がもらえる?
遺産相続には、法定相続と遺言書による相続と遺産分割協議による相続の3種類があります。
法定相続は法律で決められた法定相続人が、遺産を相続する方法です。
また、遺言書による相続では、遺言書に記載された人物が遺産を相続します。
このケースでは、被相続人が法定相続人以外を指定している場合もあります。
遺産分割協議による相続は、法定相続人が集まって、相続人全員で遺産を分割する方法です。
相続する不動産の種類ごとの注意点
ここからは、相続する不動産の種類ごとにどういった注意点があるのかをご紹介します。
土地・戸建て・マンション・収益不動産など、相続する対象に従った注意点を記載するので、参考にしてください。
土地だけを相続する場合
建物がなく土地だけを相続する場合、土地を分割して相続することがあります。
その場合、相続の際に平等に分割したとしても、後から土地の価格が変動して、相続人に不満を抱える人が出てくる可能性に注意しなければなりません。
分割協議ではまず、未来の土地価格の変動も視野に入れて話し合いをして、後からトラブルにならないようにすることが大切です。
戸建てを相続する場合
戸建てを相続しても、他の住宅を所有しているとその戸建てを使用せず空き家になるケースがあります。
そうなると、特定空き家に指定される可能性があり、指定されれば固定資産税が通常の4倍になってしまいます。
固定資産税が高額になれば、持っているだけで毎年大きな出費が発生します。
もし戸建てを相続して長期間空き家になる場合には、売却などを視野に入れましょう。
参考:みやこリフォーム
マンションを相続する場合
マンションを相続した場合、そのマンションに住まないのであれば、賃貸物件として貸し出し、家賃収入を得ることが可能です。
しかし築年数が古い物件は、入居者が来ない可能性があります。
古い物件は築年数が進むほど、入居者の獲得と売却の両方が厳しくなっていきます。
そのため、早めに売却するか、リフォームして賃貸に出すなどの対策が必要となるでしょう。
収益不動産を相続する場合
収益不動産は融資を受けて購入されていることが多く、その場合残債が残っていることがあります。
相続ではこうしたマイナスの遺産も相続対象となることから、残債の金額を確認しておきましょう。
また、収益不動産も相続人間で分割することとなりますが、分割協議中も賃料や土地代は支払われます。
そのお金は誰のものとなるのか、協議中の修繕費や管理費は誰の負担となるのかを事前に決定しておく必要があるでしょう。
遺産相続における不動産の分け方のまとめ

ここまで、遺産相続での不動産の分割方法を中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 不動産相続の分割方法は4種類
- 相続人と相続財産の調査が必要
- 不動産の共有は避ける
- 評価方法はものによって異なる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
りあログ
リフォームや不動産投資に関する情報を提供するブログです。
著者は、不動産業界での豊富な経験を活かし、実体験に基づくリフォームの体験談や実例、不動産投資の体験談を詳しく紹介しています。
特に、築古物件のリフォーム・リノベーションやアパート投資に関する記事が充実しており、これからリフォームや不動産投資を考えている方々にとって有益な情報源となっています。
株式会社FUTATABI

株式会社FUTATABIは相続対策、不動産活用に関するコンサルティングを行っております。
相続や不動産の問題は個別性が高く、皆様それぞれにおいて最適解は異なります。
『不動産を含むご資産の相続対策をしたい方』『ご所有の不動産の活用にお困りの方』
ぜひ一度ご相談くださいませ。
相続対策・不動産取引をサポートするパートナー「株式会社FUTATABI」
スポンサーリンクフドログ
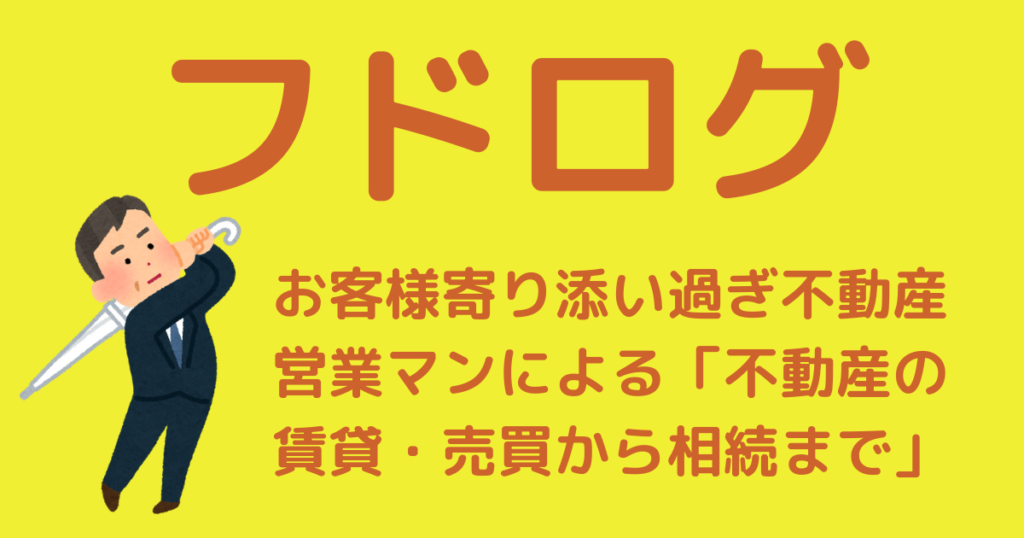
『フドログ』管理人で、お客様に寄り添い過ぎ不動産営業マンのケイヒロと申します。40歳代半ばからこの業界に入り、お陰様で10数年が経ちました。
『フドログ』とは『不動産ブログ』の略語で、不動産の賃貸・売買から相続までを分かりやすく解説しています。
実務経験3年未満の不動産業界の方、また不動産をお持ちだけどその扱いに戸惑われている方、是非お力になれたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
参考:不動産の相続に関するお悩みなら埼玉県さいたま市のMET Design Home株式会社
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
相続の関連記事
相続

更新日:2022.06.11
遺族年金が非課税である理由と節税方法・確定申告について紹介
相続

更新日:2024.10.27
遺族と相続人の違いは?定義や順位、割合について解説
相続

更新日:2025.05.20
遺産相続とは?手続きの流れ・相続人の範囲など基礎知識を解説
相続

更新日:2025.03.16
遺産分割が相続人間で進まない



