相続
配偶者の遺産相続はいくら?配偶者がいない場合についても解説
更新日:2025.01.14 公開日:2022.05.12

記事のポイントを先取り!
- 配偶者は最優先で遺産を受け取れる
- 配偶者の受け取る割合が最も多い
- 遺言書を残せば配偶者のみに相続も可能
自分の妻や夫である配偶者へは、遺産を多く残したいと思うものです。
配偶者がどれくらいの割合で遺産相続できるのかは、気になる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、配偶者がもらえる遺産の割合を詳しく説明していきます。
この機会に、配偶者がいない場合や子供が受け取る割合についても知っておきましょう。
元配偶者や内縁関係の相手が相続人になれるのかについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
- 遺産はどのように配分される?
- 配偶者や子が受け取る遺産の割合
- 配偶者に遺産を全て渡すには
- 配偶者に遺産を渡したくない場合は?
- 配偶者がいない場合はどうなる?
- 元配偶者は相続人になれるの?
- 内縁の相手は相続人になれる?
- 遺産の配偶者まとめ
- 株式会社ベルクライン
遺産はどのように配分される?

民法で定められている遺産の分配割合のことを法定相続分といいます。
この法定相続分が一番多いのが配偶者です。
配偶者はどのような時でも必ず相続人になるため、遺産相続においては最も強い権利を有しています。
しかし遺産を分配する際には、配偶者と子や親などの相続人とが折半して受け取るように定められています。
配偶者以外の相続人は、被相続人(故人)との関係の近さによって優先順位が付けられています。
第1順位 直系卑属(子供)
第2順位 直系尊属(父母)
第3順位 傍系血族(兄弟姉妹)
遺産配分の際は、順位が高い相続人から順に相続する権利を得ます。
配偶者は常に法定相続人
民法で定められた相続人のことを法定相続人といい、被相続人の配偶者はどのような場合でも必ず法定相続人になります。
他の相続人とは違って順位がなく、他の相続人の有無と関係なく必ず法定相続人となるため、相続において最も有利な立場にあります。
ただ、被相続人との関係は法律上の婚姻関係がなくてはならないため、事実婚や内縁関係では相続人と認められない点に注意が必要です。
第1順位
第1順位の相続人は被相続人の直系卑属、つまり子供や孫です。
血族相続人の中で最も優先的に相続を受けられる立場にあります。
もし、第1順位の相続人がすでに亡くなっていたとしても、相続人の子供がいれば代わりに相続できます。
これを代襲相続といいます。
代襲相続は、孫がいなかったらひ孫が、ひ孫がいなかったら玄孫がと、直系卑属が続く限り連続して代襲できます。
第2順位
第2順位の相続人は被相続人の直系尊属、つまり父母や祖父母です。
第2順位の相続人が相続するのは、第1順位の相続人が存在しない場合のみとなります。
直系尊属は親、祖父母、曾祖父母と遡れますが、相続人となるのは被相続人と親等が一番近い存命の人が優先されます。
第3順位
第3順位の相続人は相続人の傍系血族、つまり兄弟姉妹です。
第3順位の相続人が相続するのは第1順位と第2順位がいない場合のみで、第3順位は法定相続人の中で最も低い相続順位となっています。
第3順位の相続人も代襲相続が可能ですが、1世代のみ、つまり甥姪までしか代襲相続はできません。
配偶者や子が受け取る遺産の割合
遺産の法定相続分は、配偶者以外の相続人の人数や被相続人との関係で異なります。
ここでは、配偶者とそれぞれの順位の法定相続人が遺産を相続する場合、どのような割合で遺産を分配するか、具体的に紹介していきます。
配偶者だけの場合
法定相続人が配偶者一人の場合は、当然ながら遺産の全てを配偶者が相続することになります。
配偶者以外の法定相続人である直系卑属、直系尊属、傍系血族のいずれも存在しないので、配偶者が遺産の100%を相続します。
第1順位との場合
法定相続人が配偶者と被相続人の子供の場合は、それぞれ2分の1ずつ相続します。
なお、子供が複数人いる場合は、子供の取り分である2分の1をさらに子供の頭数で等分します。
第2順位との場合
法定相続人が配偶者と被相続人の父母の場合は、配偶者が3分の2、父母が残りの3分の1を相続します。
被相続人の父母が両名とも健在の場合は、父母の取り分の3分の1を二人で等分し、それぞれが6分の1ずつ相続することになります。
第3順位との場合
配偶者と法定相続人の中で最も順位が低い兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続します。
複数の兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹の取り分である4分の1をさらに兄弟の頭数で等分します。
配偶者に遺産を全て渡すには

子供がいない夫婦の場合、配偶者以外に遺産を渡したくないと考える方も多いようです。
しかしなにも対策をしなければ、相続トラブルに巻き込まれてしまうことも珍しくありません。
ここでは、配偶者だけに遺産を全て渡す方法を説明していきます。
遺言書で指名する
遺言書で配偶者だけに遺産を全て相続する旨を書き残せば、配偶者に全ての遺産を相続することは可能です。
民法の規定により法定相続分が定められていますが、遺言書の内容は法定相続分の規定よりも優先されます。
配偶者に遺産の全てを渡したい場合は、遺言書を作成しましょう。
遺言書よりも遺留分が優先される
遺言書に書けば全ての遺産を配偶者に渡せますが、遺留分は遺言書の効果よりも優先されます。
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限取得できる遺産のことです。
遺留分は第1順位と第2順位の相続人に認められているもので、第3順位の相続人には適用されません。
そのため、被相続人に直系卑属や直系尊属がいる場合は、一定の割合の遺産が他の人の手に渡ることは避けられないでしょう。
たとえ遺言書で全ての遺産を配偶者に渡す旨を残したとしても、遺留分の請求には敵いません。
遺留分を請求されれば、一定の遺産が配偶者以外に渡ることについては理解しておきましょう。
ただし遺留分の請求ができるのは、遺留分が侵害されていると知った時から1年間のみです。
遺留分権者が1年以内に遺留分減殺請求をしなければ、遺産の全ては配偶者のものとなります。
配偶者に遺産を渡したくない場合は?

子供だけに遺産を渡したいなど、配偶者に遺産を渡したくない場合も、遺言書に明記すれば可能です。
ただしこの場合も、遺留分で取得されてしまう分については防げません。
配偶者は遺留分権者なので、一定の遺産が配偶者に渡ることは理解しておきましょう。
配偶者がいない場合はどうなる?
近年は生涯未婚率も高くなっており、配偶者がいないまま亡くなるケースも増えてきています。
そのため、配偶者なしで相続が行われることも多くなってきました。
配偶者がいない場合には相続順位の第1順位から、順番に遺産の全額が渡されます。
もし、同じ順位に複数人の相続人がいるなら、相続人全員で等しく分配します。
元配偶者は相続人になれるの?
離婚した元配偶者との相続関係がどのようになるか気になる方は、多いかもしれません。
ここでは、元配偶者や元配偶者との子供が遺産相続でどのように扱われるかを説明していきます。
元配偶者は相続人になれない
元配偶者は、相続人にはなれません。
民法において、法律上の配偶者のみが相続人になれると定められているためです。
離婚が成立した時点で配偶者ではなくなり、親族関係も解消されるので、元配偶者が相続人になることはありません。
元配偶者との子供は相続人になれる
元配偶者との子供は相続人になれます。
元配偶者と離婚したからといって、親子の血縁関係がなくなるわけではありません。
両親が離婚していたとしても、子供は父母両方の相続権を持っています。
また、子供の相続順位や相続分は、どちらの親について行ったかや、親の再婚後に新しい子供ができたなどの理由で変化することはありません。
相続順位は第1順位のままで、相続分も他の子供と等分になります。
内縁の相手は相続人になれる?
近年は、事実婚や内縁関係といったパートナーとの関係を選ぶ方も増えてきています。
そのため、パートナーに遺産を相続できるか心配な方も多いかもしれません。
ここでは、内縁の相手が相続人になれるのか、説明していきます。
内縁関係は相続人になれない
内縁や事実婚の夫婦とは、婚姻届を提出せず法律的には夫婦となっていないが、事実上は結婚生活を送っている人たちのことです。
最近は、手続きなどを経て事実婚でも法律婚と同等の権利が得られる体制ができている自治体も増えてきました。
しかし、相続に関しては民法で相続人の範囲がしっかりと定義されています。
上記で説明したように、法律婚の配偶者と第3順位までの血縁の者しか相続人にはなれません。
婚姻届を提出していない内縁の相手は、法律上は婚姻が成立していないため配偶者とは認められず相続権が発生しません。
法律上遺産を受け取る権利が存在しないので、法定相続人にはなれないのです。
内縁関係でも相続人になる方法
内縁関係の相手は法定相続人にはなれませんが、遺産を相続する方法は存在します。
遺言書で指名をする
遺言書の内容は強い効力を持ち、法定相続より優先されるものです。
遺言書に遺産を譲る旨を記すことで、法律上の婚姻関係が存在しない内縁の相手にも遺産を渡せます。
ただ、遺留分があるので第2順位までの相続人が他にいるのなら、遺言に書き残したとしても全ての遺産を内縁の相手に渡すことはできません。
また、「配偶者に対する相続税額の軽減制度」は受けられないため、配偶者と比べて相続税は2割加算されます。
特別縁故者になる
もし、被相続人に法定相続人がいない場合は、一定の条件を満たすことで内縁相手が特別縁故者と認められれば、遺産を相続できる可能性があります。
■被相続人に相続人がおらず、遺言書もない
■被相続人と生計を同じくしていた
■被相続人の療養看護に努めていた
■被相続人と特別の縁故があった
以上の条件を満たしていれば、裁判所に申し立てることが可能です。
申し立てが認められれば遺産を受け取れますが、「配偶者に対する相続税額の軽減制度」は受けられません。
内縁相手との子供はどうなる?
内縁の子供には相続権がないため、相続人にはなれません。
ただ、父親が子供を認知した場合は、法律上の親子関係が発生するので相続人になれます。
内縁の子供が相続人になった場合は、法律婚の子供である嫡出子(ちゃくしゅつし)と法定相続分は同じです。
以前は、嫡出子の2分の1しか受け取れませんでした。
しかし最高裁の判決で法の下の平等に反すると判決が下された後は、嫡出子と法定相続分を同じとするとされています。
遺産の配偶者まとめ

ここまで遺産相続における配偶者の扱いについての情報を中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 配偶者は遺産を配分する際、必ず相続人となる
- 配偶者の受け取る遺産の割合は相続人の中で最も多い
- 遺言を残せば、配偶者にだけ遺産を渡すことも可能
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
株式会社ベルクライン
株式会社ベルクラインは、依頼者と弁護士を繋ぐ「弁護士ほっとライン」を運営しています。
相談内容ごとに下記6つの分野に強みを持ってる弁護士を探せます。
- 交通事故相談弁護士ほっとライン
- 刑事事件相談弁護士ほっとライン
- 離婚・不倫慰謝料相談弁護士ほっとライン
- 遺産相続相談弁護士ほっとライン
- 債務整理相談弁護士ほっとライン
- 風評・誹謗中傷相談弁護士ほっとライン
また、労働問題の基礎知識を学べる情報サイトも運営していて、退職代行も承ります。
退職代行ほっとライン
スポンサーリンク
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
監修者

鎌田 真紀子(かまた まきこ)
国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)
経歴
終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。
相続の関連記事
相続

更新日:2022.04.23
遺族年金を受け取ったら確定申告は必要?所得控除や節税方法も解説
相続

更新日:2024.06.14
「おひとりさま」の生前整理…血縁者が1人もいないが、死後の財産はどうなる?
未分類
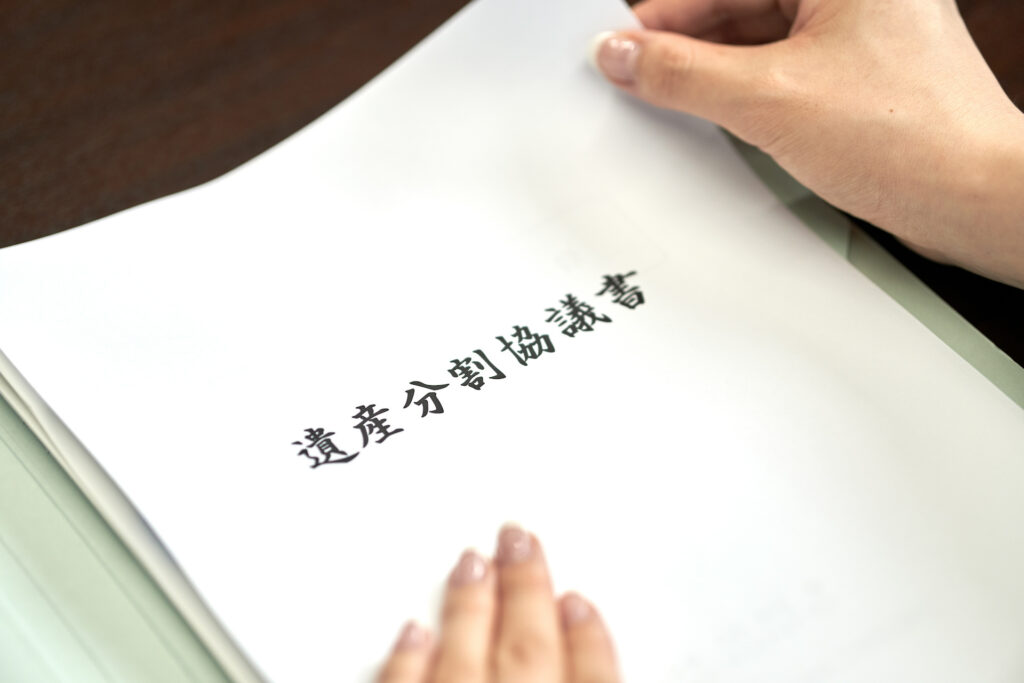
更新日:2025.12.16
他の相続人から不平等な内容の遺産分割方法を提示されたら?






