お墓
分骨とは?分骨の方法・手続き・供養方法や注意点を紹介
更新日:2024.02.03 公開日:2022.04.02

記事のポイントを先取り!
- 分骨とは複数の場所に納骨すること
- 分骨は昔から行われている供養方法/li>
- 分骨のタイミングは火葬の際か納骨後
- 分骨の費用はタイミングによって異なる
分骨とは遺骨を複数箇所に納骨することですが、その方法などについてご存知でしょうか。
分骨の方法や手続き、供養方法などについて覚えておきましょう。
そこでこの記事では、分骨について詳しく説明していきます。
この機会に分骨の費用や注意点なども知っておきましょう。
分骨した遺骨をお墓に戻す方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。
分骨とは
分骨とは、遺骨を複数の場所に別々に納骨することをいいます。
分骨は昔から行われてきた方法です。
現在でも「親族で遺骨を分けたい」「遺骨の一部を手元に置いておきたい」などの理由で分骨が行われています。
分骨はよくないこと?
「分骨は縁起がよくない」と聞いたことがある方がいるかもしれません。
結論から言うと、分骨をすることはまったく問題ありません。
法律で禁止されているわけでもなく、宗教的な問題もありません。
むしろ、分骨は昔から行われてきた慣習です。
以前は「遺骨に魂が宿る」などといわれていたため、分骨をすることで「魂が引き裂かれる」などといわれていました。
しかし近年では、四十九日を過ぎると故人様の魂は成仏するとされているうえ、そもそもお釈迦様の遺骨は世界中に分骨されています。
むしろ分骨には、菩提寺(ぼだいじ)が遠方でも近くで供養できるなどのメリットがあります。
ただし、地域性などによっては分骨を嫌がる方もいますので、分骨をお考えの場合には親族に事前に確認を取ることを忘れないようにしましょう。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
分骨の方法
分骨には、納骨前の火葬場での分骨と、納骨後にお墓から遺骨を取り出して分骨する2回のタイミングがあります。
どちらのタイミングで分骨を行うかによって方法が異なります。
以下に一般的な手順を記載しますので、ぜひ参考にしてください。
火葬場で分骨する場合
- 事前に火葬場へ分骨する旨を伝える
- 分骨する分の骨壷を用意する
- 分骨する数の分だけ分骨証明書、または分骨用の火葬証明書を用意する
- 火葬後、用意した骨壷に遺骨を納める
- 事前に用意しておいた分骨証明書、または分骨用の火葬証明書を分骨をする先の管理人に渡す
- 納骨する
1~3が火葬前に行っておく事前準備で、4~6が実際に分骨をするまでの手順になります。
火葬場に分骨の希望を伝えるのは、自分で直接連絡をしても、葬儀社から伝えてもらってもお好きなほうで問題ありません。
また、遺骨を手元で保管して供養する「手元供養」を行う際にも、将来納骨する可能性を考えて、分骨証明書または分骨用の火葬証明書は発行しておきましょう。
お墓から取り出して分骨する場合
- 寺院や霊園など納骨されている場所の管理者に連絡を取り、遺骨を取り出す日程の段取りと、分骨証明書または分骨用の火葬証明書の発行を依頼する
- 必要分の骨壷を用意する
- 閉眼供養(魂抜き)を行い、遺骨を取り出す
- 開眼供養(魂入れ)を行い、一度取り出した遺骨を再度納骨する
- 分骨した遺骨を納骨する際にも開眼供養(魂入れ)を行ってから納骨する
開眼供養とは、新しいお墓や位牌、仏壇などに魂を入れる法要のことをいいます。
一方、閉眼供養とは、古いお墓などから魂を抜き、ただの石に戻すことです。
この方法での分骨でも、火葬場で分骨する方法と同様に分骨証明書または分骨用の火葬証明書が必要です。分骨する数枚の証明書を、忘れず発行しておきましょう。
分骨の費用

分骨の際にかかる費用は基本的に「骨壷代」と「分骨証明書または分骨用の火葬証明書発行代」のみです。
ただし、分骨の方法によってその他の費用に違いが出てくるので注意してください。
火葬場で分骨する費用
火葬場で分骨する際にかかる費用は、基本的なもの以外に「お墓代」と「墓地や霊園の使用料」です。
ただし、手元に遺骨を置いて供養する手元供養であれば、お墓代や霊園使用料はかかりません。
お墓から取り出して分骨する
お墓から取り出して分骨する場合には、骨壷代と証明書発行代以外に、「遺骨を取り出す費用」と「開眼供養および閉眼供養代」がかかります。
具体的には、遺骨を取り出す費用の相場が2万~3万円、開眼供養の相場が1万~5万、閉眼供養の相場が3万~10万円です。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
分骨時の注意点
分骨の際には、分骨証明書または分骨用火葬許可証があれば良いわけではありません。
ここでは、分骨する際の注意点を説明していきます。
合祀した遺骨は分骨できない
合祀(ごうし)とは、複数人の遺骨をまとめて納骨することをいいます。
永代供養や後述する本山納骨など、合祀して供養する方法はいくつかありますが、一度合祀してしまうと故人様の遺骨を取り出すことはできません。
また分骨の際に合祀と手元供養などを選択した場合、手元供養をした遺骨を紛失したとしても再度分骨はできないので注意が必要です。
遺骨所有者の承諾が必要
遺骨には、「祭祀(さいし)継承者」といわれる遺骨所有者が必要です。
つまり、遺骨やお墓の所有権は、この祭祀継承者にあります。
そのため分骨は、祭祀継承者の許可がないと行えません。
分骨を行いたい場合には、事前に祭祀継承者の同意を得ましょう。
親族からの合意を得たうえで行う
分骨を行う際には、必ず事前に親族からの同意を得ましょう。
分骨は、法律や宗教上は行っても特に問題ないとされていますが、地域の慣習などによっては反対される方もいます。
勝手に分骨を行ってしまうと後々トラブルになりかねませんので、遺骨所有者の同意だけではなく、親族にも同意を得ることが大切です。
分骨後の供養方法
分骨後の供養方法には「本山納骨」「手元供養」「散骨」「複数個所のお墓に納骨」といった方法があります。
ここでは、それぞれの供養方法について説明していきます。
ぜひ、分骨後の供養方法の参考にしてください。
本山納骨
本山納骨とは、その宗派において特別とされている寺院(本山)に遺骨の一部を納めて供養することをいい、宗派を開かれた宗祖に対する敬畏の意味があります。
様々な宗派で行うことが可能ですが、特に浄土真宗では古くから本山納骨の慣習があります。
本山納骨は、本山への申し込み後に法要を行うことでできます。
また、お墓を建てる必要もないため、墓石代やお墓を立てる費用、墓地使用料がかからず、比較的安価に納骨することが可能です。
故人様にとっても、本山での供養は安心感があるといえます。
手元供養
手元供養とは、遺骨を手元つまり自宅に置いて供養することをいい、「自宅供養」とも呼ばれています。
納骨というと、骨壷を連想される方も多いかもしれません。
しかし手元供養の場合は、骨壷でなくてもペンダントや指輪の中に遺骨を入れて持ち歩けます。
もちろん手元供養用のミニ骨壷もあります。
手元供養は遺骨がすぐ側にあるため、故人様を身近に感じられる供養方法です。
近年では、場所を選ばずインテリアに合わせたお洒落な骨壷も多く販売されています。
散骨
散骨とは、遺骨を粉末状にして海などに撒いて供養する方法です。
散骨を行う際には特別な書類は必要なく、業者に頼まなくても個人で行うことも可能です。
お墓代なども必要ないため、安価で簡単な供養方法だと考える方もいるかもしれませんが、実のところそうともいえません。
散骨は、どこでどのように行っても良いというわけではなく、行う場所や行う方法を間違えると他者とのトラブルになりかねません。
個人でも行えますが、散骨に関する知識が豊富な業者に依頼するのが確実です。
また、散骨は近代的な供養方法であるなどの理由から、理解され難い一面もあります。
散骨を希望する場合には勝手に行うようなことはせず、将来的にトラブルにならないよう事前に親族へ相談しましょう。
2箇所のお墓に納骨する
分骨した遺骨は、お墓参りに行きやすい場所に新たにお墓を建てて納骨することも可能です。
しかしその場合には、新たにお墓を建てるのに加えて年間使用料を支払う必要があるなど、高額な費用がかかってしまいます。
そのため、分骨の際にお墓で供養する方の中には「永代供養」を選ばれる方が多くみられます。
永代供養とは、墓地や霊園の管理者が永代的に供養してくれる方法です。
永代供養であれば新たにお墓を建てる必要はなく、ほとんどの場合が年間使用料もかかりません。
費用面では安価に済むほか、墓地や霊園の管理者が永代的に供養をしてくれるため安心です。
ただし、多くの永代供養が本山納骨同様、合祀されています。
一度納骨してしまうと、その後故人様の遺骨だけを取り出すことはできないので注意が必要です。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
一度分骨した遺骨をお墓に戻すことは可能?
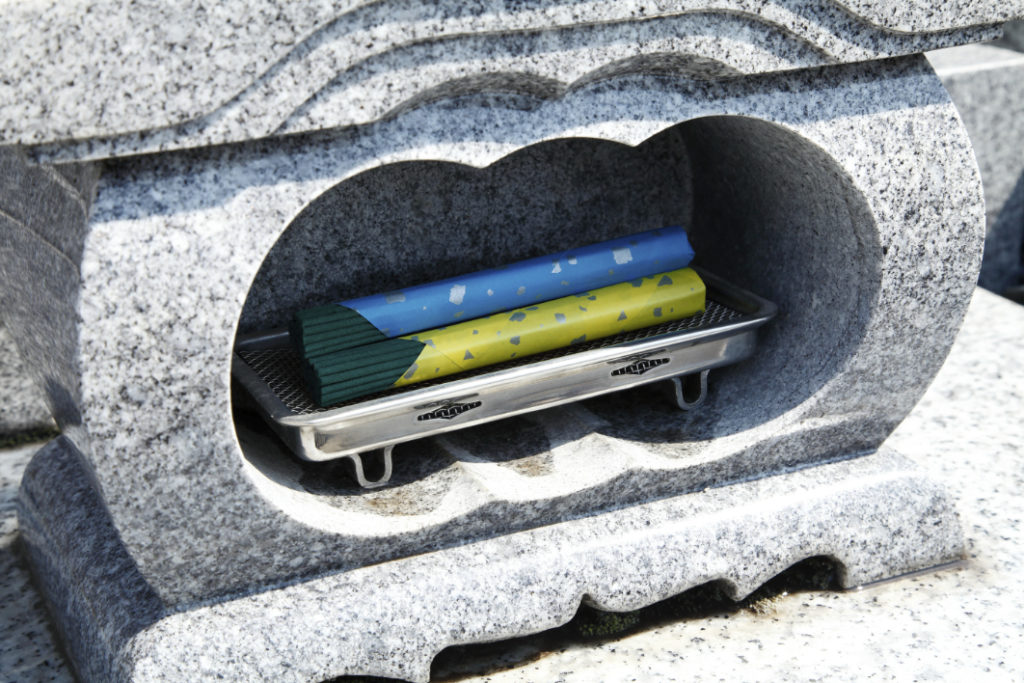
一度分骨した遺骨をお墓に戻すことは、法的にも宗教的にも問題はなく可能です。
ここでは、一度分骨した遺骨をお墓に戻すまでの手順と、お墓に戻すときの注意点について説明していきます。
お墓に戻すまでの流れ
お墓に戻すまでの流れを説明する前に、用意するべき必要な書類について説明します。
分骨した遺骨をお墓に戻すためには、必要となる書類が複数あります。
まずは、分骨証明書または分骨用火葬証明書です。
遺骨に事件性がないことを確認することが目的で、ほとんどの場合に提出を求められます。
紛失してしまった場合には再発行することも可能ですが、再発行には数日かかる場合もあるので早めに用意しておくとよいでしょう。
次に、埋葬許可証です。
こちらは火葬許可証と同じ用紙で、火葬が終わったあと、火葬許可証に印をつけてもらったものになります。
埋葬許可証も分骨証明書同様、遺骨に事件性がないことを確認するために提出を求められる場合がほとんどです。
こちらも再発行が可能ですが、数日かかる場合があるため早めに用意しておきましょう。
書類の準備が終わったら、以下の通り進めていきます。
- 取り出したい遺骨がお墓にある場合は、墓地や霊園の管理者に相談する
- 骨壷や手元供養の容器などから遺骨を取り出し、分骨した遺骨を集める
- 遺骨を確認し、カビなどがある場合にはその部分を切除するため専門の業者に依頼する
- 納骨式などの法要を行う
遺骨を取り出したあとのお墓を完全に撤去してしまう「墓じまい」を行う場合には、最初の相談の際に伝えておきましょう。
また、取り出したい遺骨がお墓に入っていた場合には、閉眼供養を行う場合もあります。
お墓に戻すときの注意点
宗派や地域の考え方によって異なりますが、ほとんどの場合、お墓に遺骨を戻す際には供養が必要になります。
供養の予定を立てるためにも、墓地や霊園の管理者には早めにお墓に遺骨を戻したい旨を伝えておきましょう。
また、遺骨を取り出したお墓への配慮も重要です。
遺骨を取り出したお墓がある墓地や霊園の管理者になんの相談もなく遺骨を取り出すのは、トラブルの原因になります。
とくに、その場所が壇家(だんか)になっている場合にはなおさらです。
墓じまいをするしないに関わらず、お墓から遺骨を取り出すことが決まった時点で一度連絡を入れましょう。
最後に注意しなくてはならない点が、遺骨の状態です。
とくに粉砕した遺骨はカビが生えやすくなっています。
カビが生えた状態の悪い遺骨はそのまま納骨できないため、専門の業者に依頼して取り除いてもらう必要があります。
遺骨を取り出した時点で一度、遺骨の状態を確認しておくことをおすすめします。
また、将来的に遺骨を一つにまとめる可能性がある場合には、脱酸素剤を同封するなどして遺骨の管理を丁寧に行いましょう。
よくある質問
Q:分骨って何?
A:分骨とは遺骨を分けて、納骨や供養することです。
Q:分骨の費用は?
A:火葬場から分骨をする場合は、お墓代と墓地や霊園の使用料のみです。
お墓から取り出す場合は、遺骨を取り出すのに2~3万円と、開眼供養と閉眼供養のお布施が必要です。
開眼供養の費用は1~5万円、閉眼供養は3~10万円です。
Q:火葬許可証は何に必要
A:火葬後、遺骨を納めるのに必要です。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
分骨のまとめ

ここまで分骨の方法や手続き、費用などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 分骨とは複数ヶ所に納骨して供養する方法のこと
- 分骨は法律的にも宗教的にも問題ない
- 分骨のタイミングは、納骨前後の2回ある
- 費用は分骨のタイミングによって異なる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。






