お葬式
霊柩車の利用料金は?霊柩車の値段や霊柩車の種類、車種についても解説
更新日:2023.11.12 公開日:2022.01.30

記事のポイントを先取り!
- 遺体を斎場から火葬場まで運搬する車を、霊柩車という
- 霊柩車の利用料は、霊柩車の種類+走行距離で決まる
- 霊柩車は、基本的に葬儀会社が手配する
出棺時に使われる霊柩車ですが、どのくらいの利用料なのかご存知でしょうか?
霊柩車にかかる値段は一般的にあまり知られておらず、高額ではないかと不安に思っている方も多いのではないかと思います。
そこでこの記事では、霊柩車の値段が葬儀費用に含まれるのか、値段の相場はどのくらいなのか、詳しく説明していきます。
この機会に、霊柩車の利用にかかるおおよその値段を把握しておきましょう。
霊柩車の値段が割引されるケースについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
霊柩車の特徴

霊柩車とは、遺体が納められた棺を火葬場まで運ぶための車です。
現代では洋型(バン型)の霊柩車が多くなりましたが、豪華な泊や飾りが施された立派なお宮が付いた、昔ながらの霊柩車(宮型霊柩車)をイメージされる方も多いでしょう。
いずれの霊柩車も棺を乗せて運べるよう、通常の車と比べて車長が長くなっています。
以下で、霊柩車の特徴をご紹介します。
霊柩車のナンバープレート
霊柩車は通常の車両と違い、前ドアの下に「霊柩限定」や「霊柩」という表記があるのが特徴です。
遺体を運ぶ霊柩車は、車両の種類としても「特種用途自動車」という業務用車(8ナンバー車)に分類されるため、緑色で800番台のナンバープレートが割り当てられます。
霊柩車を使う葬儀会社は、霊柩限定の一般貨物自動車運送事業許可が必要ですが、普通の運転免許(普通自動車第一種運転免許)を持っていれば運転が可能です。
霊柩車の色は、多くが黒色です。
最近では白や紺色、紫、ピンクなどの霊柩車も見られるようになりました。
霊柩車の後部には棺を固定するストッパーなど、特別な装備が施されています。
霊柩車の荷室部分
霊柩車の荷室部分は、棺の専用スペースです。
棺は非常に大きく重いため、スムーズな出し入れが可能となるように、荷室部分には、ローラーやレールが設置されています。
霊柩車が走行している時に、棺が動かないようにするための、固定装置も備えられています。
このような工夫により、霊柩車はご遺体を安全かつ確実に火葬場まで運ぶことができます。
霊柩車の手配方法
霊柩車は葬儀プランにあらかじめ含まれていることが多いため、基本的には葬儀社が手配します。
洋型やバンなど特定の種類の霊柩車を利用したい場合は、前もって葬儀会社に相談することをおすすめします。
また葬儀会社によっては、遺族が霊柩車を手配することもできます。
葬儀社で保有していない霊柩車は、専門業者に手配することになります。
自分で手配したい場合についても、葬儀会社に相談してください。
霊柩車の値段

霊柩車にかかる具体的な値段や相場、霊柩車の運転手に心付けを渡す場合の費用の相場をご紹介します。
霊柩車の値段は葬儀プランに含まれる?
葬儀プランの中に霊柩車の費用が含まれているかは、葬儀社によって違います。
基本プランの中に含まれることが多い「搬送費用」は、病院などの故人が亡くなった場所から安置施設まで搬送する料金を指していることが多いです。
そのため、葬儀プランの中に霊柩車の費用が含まれているか、見積りの際に確認するようにしてください。
また、霊柩車の費用は利用する火葬場で設定していることもあります。
公営の火葬場だと、該当区域の住民であれば市民料金で霊柩車を利用できたり、該当市内であれば費用が無料の火葬場もあります。
一般的に霊柩車の値段は走行距離で決まるため、火葬場と葬儀場の距離も重要になります。
葬儀場を探す際は、近隣の火葬場の情報も調べて霊柩車の費用を確認することをおすすめします。
霊柩車の利用料金
霊柩車の値段は利用する霊柩車の種類と、対象区間の走行距離などによって変化します。
高い霊柩車を利用すれば値段は高くなりますし、長い距離を走らせればその分だけ高くなる仕組みです。
なお料金の対象となる走行区間は、以下の通りです。
- 霊柩車の倉庫〜自宅または斎場まで
- 自宅または斎場〜火葬場まで
走行距離に対する料金相場は、10kmまでで1万2000〜2万円となっています。
以降10kmごとに、2000〜5000円が加算されていきます。
また、霊柩車の値段は各葬儀会社の判断で勝手に決めることができません。
必ず国土交通大臣へ届け出て、その料金が適正であると認められる必要があります。
したがって霊柩車の利用料を無料としているサービスは違法となりますので、万が一見かけた際には注意してください。
霊柩車の心付けの費用相場
霊柩車の運転手への心付けは、一般的に火葬場へ出発する前や火葬場から帰宅した際にお渡しすることがあります。
心付けの金額としては、3,000円~5,000円程度が目安とされています。
心付けは、市販の白無地の封筒や弔事用の半紙を使用して包み、表書きは必要ありません。
ただし、心付けは必ず用意しなければならないものではなく、葬儀社によっては心付けの受け取りを行っていない場合もあります。
また、無理に心付けを渡すと、運転手に負担をかける場合もありますので、事前に葬儀社のスタッフに確認することをおすすめします。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
霊柩車の追加料金と割引

霊柩車は使い方によって、追加運賃や運賃の割引が発生することがあります。
ここからは、どのような場合に追加運賃や割引が発生するのか、具体的に紹介していきます。
霊柩車の値段にオプションが付く場合
霊柩車の料金が割増されるケースは、以下の通りです。
- 早朝割増(5:00~8:00、待機含む)
- 夜間割増(19:00~22:00、待機含む)
- 深夜割増(22:00~5:00、待機含む)
- 冬季割増(冬季割増適用地域を走行した場合)
- 車両留置料金(利用者の都合で30分以上待機した場合)
- 遺骨宅送料(遺骨を自宅に運んだ場合)
- 2名乗務(長距離であるなどの理由で、運転者を途中交代した場合)
- 有料道路料金(高速道路などを利用した場合)
- フェリーボート料金(フェリーを利用した場合)
- その他、通常業務外の作業があった場合の費用
追加運賃が発生するケースとしてもっともわかりやすいのは、時間帯によるものでしょう。
タクシーなどと同様に、遺体を運ぶ霊柩車にも深夜割増や早朝割増があります。
また高速道路やフェリーなどを利用するような場合も、別途その利用料が請求されますので、注意が必要です。
これらの追加運賃は、プラン紹介に書かれていないこともあります。
追加運賃が発生するおそれがあるときは、依頼前に必ず確認しておきましょう。
霊柩車の値段が割引される場合
霊柩車の料金が割引されるケースは、以下の通りです。
- 葬祭扶助を利用した葬儀での搬送(普通車基本額のみ5割引)
- 身元不明の遺体搬送(普通車基本額のみ3割引)
- 行政・司法解剖にともなう搬送(普通車基本額のみ2割引)
- 国公立病院の依頼による献体搬送(普通車基本額のみ2割引以内)
葬儀の利用者に関係してくるのは、葬祭扶助に関する割引でしょう。
葬祭扶助とは、生活保護を受けているなど経済的に苦しく、自力で葬儀が行えない方が利用できる、自治体が支給する葬儀費用の補助金です。
この葬祭扶助を利用した葬儀で霊柩車を利用した場合、霊柩車の基本額が半額になります。
割引を希望する場合は、葬儀会社にあらかじめ相談しておきましょう。
霊柩車の車種
霊柩車と言われて思い浮かぶのは、お城の天守閣が載っているような車ではないでしょうか?
実はあまり目にしていないだけで、その用途によりさまざまなタイプがあります。
ここでは霊柩車の種類についてご説明いたします。
バス型霊柩車
バス型の霊柩車は主に雪国で利用されています。
北海道や東北地方などの雪深い寒冷地域では、移動のために何台もの車を出す事は負担になってしまうからでしょう。
車体脳後部に納棺部が造られ、遺族や参列者と一緒に移動できるようになっています。
マイクロバスや中型など大きさも様々で、同乗できる人数も変わってきます。前もって葬儀社に確認しましょう。
葬儀社によってはバス型を用意できないところもあります。事前の打ち合わせは必須です。
洋型霊柩車
洋型霊柩車は通称リムジン型と呼ばれています。大型のステーションワゴンや高級車を改造して造っていてその形状からつけられた名前です。
最近はこのリムジン型の霊柩車がよくつかわれていますが、洋型とはいうものの、国産高級車を改良している霊柩車も多くみられます。
色も黒に限られてはいません。
パールホワイトやシルバーといった上品な色合いのものもあります。
親族が同乗できるように後部座席が設置してあったり、前列に3人並んで乗れるようなベンチシートタイプの車もあるので、事前に確認しましょう。
宮型霊柩車
霊柩車と言われて最初にイメージする方が多い霊柩車でしょう。
日本のお城を思わせるような納棺部がある車です。
別名を輿型(こしがた)霊柩車とも言われています。
神輿のようにも見えるからでしょう。
車体の天井飾りには仏教を思い浮かばせる極楽浄土や蓮の花が彫刻されています。
元は高級車やピックアップトラックを改造しているものです。
黒と金を基調とした色合いのオーソドックスな霊柩車ですが、最近では洋型の方が使われることが多い様です。
バン型霊柩車(寝台車)
ミニバンやステーションワゴンを改造して造られた霊柩車です。
寝台車として設計されたものでしたが、その使い勝手の良さから霊柩車としての需要が高まりました。
利用料も安く抑えられているのも利用される理由の一つでしょう。
外見は通常のバンと変わりはありません。
後部座席を取り除き、ストレッチャーでご遺体を乗せる台が取り付けられています。
色も黒だけでなく白やシルバーも使われているので、町中を走っていても気づかれないでしょう。
霊柩車で選ばれる車種
近年では特に、バン型霊柩車はその多機能性から選ばれることが増えてきました。
アルファード(トヨタ)やエルグランド(日産)などのミニバンやワゴンタイプが主流となっており、プリウスのように車両後方を延長したモデルも登場しています。
これらの車種は、遺体の搬送だけでなく、遺族の移動にも利用されることも多いです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
霊柩車と寝台車の違い
遺体を運ぶ車としては、霊柩車のほかに寝台車がありますが、用途はそれぞれ異なります。
霊柩車と寝台車の違いをご紹介します。
霊柩車
霊柩車は、故人が棺に安置された状態で、自宅や斎場から火葬場への移送に使用されます。
霊柩車の荷室は、棺の出し入れを容易にするために専用のローラーレールが装備されています。
これにより、棺をスムーズに移動させることができます。
寝台車
寝台車は、故人が亡くなった病院などから、安置場所まで運ぶために使用される車両です。
葬儀の前に遺体を運搬するための専用車として利用されます。
この車両は、故人を迎えに行く場所が病院などであるため、周囲への配慮から寝台車の外観は一般の車両と同様です。
寝台車の荷室は、遺体がのっているストレッチャーの車輪の動きをスムーズにするために、荷室は平らな状態に設計されています。
長距離搬送する場合の値段

家族が県外で亡くなった時などは遺体搬送が長距離になります。
通常、遺体搬送は寝台車で行われますが、離島などの場合は航空機や船を利用します。
それぞれの費用についてご紹介します。
車両の場合
搬送距離で料金は変わるので、県外に搬送する場合は高額になります。
目安を表にしたので参考にしてください。
| 300㎞ | 約11万~13万 |
| 500㎞ | 約15万~20万 |
| 700㎞ | 約25万~32万 |
有料道路を使用する場合は、その料金が別途加算され、状況によって深夜料金が加算されることもあります。
航空機の場合
航空機で遺体搬送をする場合の値段は、遺体と棺の重量で計算されます。
日本国内で搬送であれば、一般的な航空料金は約10万円〜30万円となります。
ただし、空港から自宅まで遺体を運ぶための車両料金は別途必要となります。
それでも、700〜800㎞以上の長距離搬送になると、車両よりも航空機を使用する方が搬送コストを下げることが可能です。
船の場合
本土から離島に遺体を搬送する場合には、フェリーなどの船を利用します。
距離に応じて値段が異なりますが、国内であれば約15万円~25万円が相場です。
また、航空機を用いる場合と同様に、船着場から自宅までの移動は車両により行われます。そのため移動距離に応じた追加料金が必要になります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
霊柩車の変化
霊柩車は、葬儀場や自宅から火葬場まで、故人の遺体を運ぶ特別な車です。
時代と共に、霊柩車のデザインや利用方法は大きく変わってきました。
ここからは、霊柩車の歴史や迷信、近年の霊柩車についてご紹介します。
霊柩車のルーツや歴史
霊柩車のルーツをたどると、ご遺体の埋葬が現代の火葬ではなく土葬が主流だった頃まで遡らなくてはなりません。
土葬時代はご遺体を輿に乗せて、ご親族や参列者の方が墓地へと運ぶことが一般的に行われていました。
この輿を模して造られたものが宮型霊柩車の原型だと言われています。
現在では様々な形がありますが、霊柩車と言われて思い浮かべるのは、この宮型ではないでしょうか。
現代の自動車の霊柩車は、1917年に当時アメリカで普及していた霊柩車を、大阪の葬儀社が輸入した事から全国へと拡大していきました。
日本風にアレンジし、納棺部を輿型へと変えたものが宮型霊柩車です。
霊柩車の普及に伴い、土葬時代の葬列という風習が見られなくなっていったようです。
霊柩車にまつわる迷信
霊柩車に関する迷信で特によく聞かれるのが「霊柩車を見かけたら親指を隠さなくてはならない」と言われているものです。
迷信は地域によっても違いがあり他にも「親の死に目に会えなくなる」や「親に不幸が訪れる」などと伝えられています。
理由は諸説ありますが、親指に関しては江戸時代の「親指から魂が出入りする」という伝承が由来とされています。
昔は亡くなって間もないご遺体は、生きている者の親指から侵入する恐れがあると考えられていました。
このような伝承が、時代とともに今の迷信へと変化したのではないかという説が有力視されています。
近年の霊柩車
古くからの宮型霊柩車は、黒塗りの車体に祭壇のような「輿」が載っており、多くの人々がイメージするものです。
しかし、近年では洋型やバン型、バス型といった多様なデザインの霊柩車が増えてきました。
特に洋型は、高級車をベースにしたシンプルなデザインが特徴で、一見すると普通の車と見分けがつかないこともあります。
また、黒以外の色の霊柩車も増えており、ピンクや白などの明るい色が選ばれることもあります。
時代の変化とともに、霊柩車の形や色、利用方法が多様化してきたことは、葬儀文化の変遷を物語っています。
霊柩車のよくある質問
霊柩車に関してのよくある質問をご紹介します。
霊柩車の値段はいくらですか?
霊柩車の金額は、種類と距離の2つに分けられています。
霊柩車の種類によって金額差が出ますので葬儀社にあらかじめ相談しておくと安心です。
距離に関しては走行区間が大きくかかわってきます。
霊柩車の倉庫から自宅または斎場までと、葬儀後には斎場から火葬場までの合わせた距離から計算されます。
霊柩車は誰が乗りますか?
霊柩車の乗車人数が1名の場合は喪主が乗車することが多いです。
しかし、霊柩車に誰が乗るか明確な決まりはないため、故人の長男長女が喪主を務めていても、故人の配偶者である妻が乗るなど、一番個人に対して思い入れのある方が同乗されるケースもあります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
霊柩車の値段のまとめ

ここまで霊柩車を利用する値段や相場などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 遺体を斎場から火葬場まで運搬する車を、霊柩車という
- 霊柩車の利用料は、霊柩車の種類+走行距離で決まる
- 霊柩車は、基本的に葬儀会社が手配する
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2025.06.17
互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説
お葬式
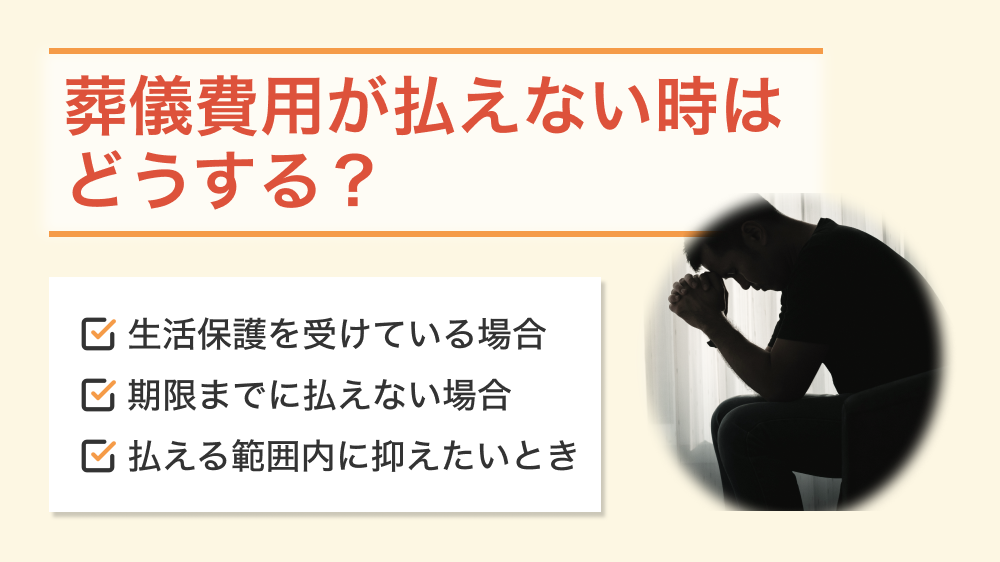
更新日:2025.07.16
葬儀費用が払えない時の対処法は?葬儀費用を安く抑える方法なども解説
お葬式

更新日:2024.02.16
お別れの会とは?種類や費用・流れまでも徹底解説
お葬式

更新日:2023.12.15
社葬の費用相場は?経費処理の仕方や勘定科目、香典の扱い方や個人事業主の方にも解説
お葬式

更新日:2024.01.10
合同葬とは?社葬や一般葬との違いや相場、マナーについて解説
お葬式

更新日:2024.04.11
友人葬でかかる費用は?そもそも創価学会とは?詳しく解説


