お葬式
福祉葬とは?対象条件、流れ、費用、香典の取り扱いや注意点まで詳しく解説
更新日:2023.12.18 公開日:2022.02.23

記事のポイントを先取り!
- 福祉葬は生活保護受給者が対象
- 葬儀は火葬式の形式となる
- 福祉葬の申請は葬儀社が代行
- 福祉葬の申請は葬儀・火葬の前に行う
福祉葬は特定の条件を満たす方々のためのサポート制度として知られていますが、詳しい内容や「福祉葬の対象者」になるための「事前申請」の手順は十分に理解されていないことも多いです。
福祉葬の条件をしっかりと把握しておくことで、必要な時に迅速かつスムーズに手続きを進めることが可能となります。
本記事では、福祉葬の対象者となるための要件や、事前申請の重要性、さらには福祉葬の条件に関する具体的な情報を詳しくご紹介します。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 福祉葬とは
- 福祉葬を行うために葬祭扶助が認められる条件
- 福祉葬を申請できる人
- 福祉葬が認められないケース
- 福祉葬の内容
- 福祉葬の服装
- 福祉葬の費用
- 福祉葬の申請方法
- 福祉葬を申請する際の注意点
- 福祉葬で香典は受け取れる?
- 福祉葬で戒名をつける場合
- 生活保護について
- 生活保護受給者が死亡した際の注意点
- 故人が生活保護受給者だった場合の遺品整理
- 福祉葬のよくある質問
- 福祉葬まとめ
福祉葬とは
福祉葬とは、故人または喪主の同一所帯の方が生活保護を受給している場合に、必要最低限の葬儀が行えるように各自治体からの「葬祭扶助」を受けて行う葬儀のことです。
葬儀の自己負担金はありませんが、原則として火葬式のみでお通夜や告別式は省略されます。
福祉葬を行うために葬祭扶助が認められる条件
次は福祉葬の対象となるのはどのような条件かをご紹介します。
福祉葬の対象となるケースには大きく分けて2種類あります。
喪主の方が生活保護受給者
1つ目は、喪主の方が生活に困窮し、生活保護を受給しているケースです。
喪主と故人が同一世帯で生活保護を受給している場合には、葬祭扶助の対象となるため、福祉葬を行うことが可能となります。
故人が生活保護受給者
故人が生前に生活保護を受給していたケースも、福祉葬の対象となります。
このケースに該当する場合は、故人と生計をともにする人がおらず、葬儀を手配できないことが葬祭扶助の申請可能条件となります。
同一生計の方がおらず、家主や民生委員など第三者が葬儀を手配する必要がある場合には、葬祭扶助を受けて福祉葬を行えます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
福祉葬を申請できる人
福祉葬が受けられる親族はどこまで?
福祉葬は、具体的な支給範囲や条件は自治体によって異なりますが、通常は配偶者や子供、孫などの直系の親族が対象となります。
また、一部の自治体では、兄弟姉妹や祖父母、叔父叔母など、他の親族にも支給される場合があります。
福祉葬を受けるために、申請手続きや必要な書類について、自治体の窓口で詳細を確認しておきましょう。
親族以外で福祉葬を受けたい場合は?
また、親族以外の人でも、故人といっしょに住んでいた場合は福祉葬を申請することが可能です。
親族以外で福祉葬を受給できる人は具体的には以下のとおりです。
- 後見人や補佐人、補助人
- 同居人
- 家主または地主
- 建物または土地の管理者
- 公的設所の長(国立病院など)
福祉葬が認められないケース
次は福祉葬が認められないケースについてご紹介します。
前述した福祉葬の対象となるケースに該当したとしても、以下の内容が当てはまる場合は福祉葬が認められないことがありますのでご注意ください。
生活保護受給者だった故人に十分な資産がある
生活保護を受給していたとしても、葬儀が行えるだけの資産が残されていた場合は、福祉葬が認められないためご注意ください。
また、葬儀に必要な費用が遺産で全て賄えない時には、不足している分だけ葬祭扶助を受けられます。
生活保護受給者だったからといって、全てのケースで福祉葬が認められるわけではないことを覚えておきましょう。
葬儀費用を払える親族がいる
扶養義務者の中に葬儀費用を支払える親族が居た場合には、福祉葬が認められないことがあるためご注意ください。
扶養義務者とは祖父母、父母、個、孫、兄弟姉妹、夫婦のことを指し、これらの親族は民法によって互いに扶養する義務があると定められています。
そのため、葬儀費用を支払える方がいる場合には、葬祭扶助を支給してもらえない場合があるのです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
福祉葬の内容
福祉葬に含まれるサービスや流れなどの内容について説明します。
福祉葬に含まれるサービス
- ご遺体の搬送(病院または自宅から火葬場)
- 必要最低限の葬具
- 火葬の料金
- 安置料
- 死亡診断書(死体検案書)の役所申請手続き
以上のものが福祉葬に含まれています。
葬祭扶助で支給されるものは火葬に最低限必要なもののみとなっています。
僧侶の読経に対するお布施は含まれていません。
葬祭扶助を受ける方の多くは、僧侶による読経を省略しています。
ちなみに、必要最低限の葬具には以下のものがあります。
- 寝台車
- ドライアイス
- 棺、棺用布団
- 枕飾り、仏衣一式
- 骨壺、骨箱
- 白木位牌
福祉葬の流れ
福祉葬の葬儀は火葬式だけを行います。
火葬式とは、直葬と呼ばれる形態で、お通夜や告別式は行わず、火葬のみを行います。
おおまかな流れは以下の通りになります。
遺体の安置
遺体は専用の施設や霊安室に適切に保管され、遺族に対して敬意をもって扱われます。
遺体安置は一般的な葬儀形態を行う場合と特に違いありません。
打ち合わせ・納棺
生活保護受給世帯の方が亡くなり福祉葬を希望する場合には、市役所の福祉課や福祉事務所のケースワーカー、地域の民生委員などに連絡します。
そこから葬儀社へ連絡が行き、故人様を葬儀社が安置場所まで搬送し納棺します。
初めに福祉葬を行いたい旨を伝えておけば、葬儀社が福祉葬として手配してくれます。
出棺・火葬
出棺は故人を最終の安息地へ運ぶ儀式であり、家族や友人が参列します。
火葬は遺体を火にかけ、灰となった遺骨を尊重し、遺族に返すプロセスです。
これらの儀式も一般的な葬儀形態との大きな違いはありません。
骨上げ・散会
福祉葬の葬儀には墓石や納骨費用は含まれていません。
遺骨は遺族または親族が引き取ってお墓に納めたり手元供養・散骨を選択できます。
お墓がないか、血縁者以外の場合は、合葬墓にまとめられることがあります。
福祉葬の服装
福祉葬の場合、一般的な葬儀と同様に喪服が適切な服装とされています。
しかし、生活保護を受給している方々の中には、喪服を持っていない場合や、購入する費用がない場合もあります。
このような場合、黒のスーツやワンピース、アンサンブルなどでも問題ありません。
福祉葬では通常の告別式が行われず、家族や少人数で行われることが一般的です。
そのため、服装に厳密なルールを設ける必要はありませんが、参列者の間で服装が統一されていることが望ましいです。
なるべく地味な服装を選ぶよう心がけましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
福祉葬の費用

続いて福祉葬にかかる費用を解説します。
生活保護を受けていても葬儀はできる?費用は?
生活保護法第18条に「葬祭扶助」の定めがあるように、生活保護を受給している方でも負担額0円で葬儀を執り行うことができます。
葬祭扶助は「検案・死体の運搬・火葬又は埋葬・納骨その他葬祭のために必要なもの」の範囲になる他、故人が生活保護を受給していて身寄りがないことや、喪主が生活保護受給者であることなど条件があります。
出典:e-Govポータル
福祉葬の場合、基本的に自己負担金はないので無料となります。
福祉葬の費用は対象者を通さず、自治体から葬儀社へ直接支払われることになります。
葬祭扶助給付基準額も規定により定められています。
| 故人が12歳未満の場合 | 16万4,000円以内 |
| 故人が12歳以上の場合 | 20万6,000円以内 |
これはあくまで法的な基準額の範囲内であり、これ以外にも自治体ごとに上限額が別途定められています。
故人が住んでいた地域の自治体が定めた上限金額の範囲内で、葬祭費にかかった費用が支給されることになります。
自治体によって、さまざまな規定があるため、お住まいの役所や福祉事務所に確認しましょう。
福祉葬の申請方法
福祉葬の申請方法の流れを説明します。
担当者やケースワーカーへの連絡
生活保護受給者の世帯の方が亡くなったら、まず、担当の民生委員やケースワーカーに連絡します。
ここでは、今後の対応について相談にのってもらえます。
また、このときに葬儀社を紹介してくれる場合もあります。
葬儀社に連絡する際は、福祉葬を検討していることを事前に伝えておきましょう。
生活保護を受給していても、福祉葬の葬祭扶助の条件を認められないケースも考えられるので、生前に相談しておいたほうがよいでしょう。
福祉事務所への葬祭扶助の申請
次に、住まいの管轄の福祉事務所に葬祭扶助の申請を行います。
前もって葬儀社に連絡していれば、申請の手続きなどは葬儀社が代行してくれます。
葬祭扶助を申請する方と故人の住民票が異なる場合、原則として申請者の住民票がある自治体に申請することになります。
故人が生活保護を受給していた場合は、故人の住民票がある自治体にも確認しておいた方がよいでしょう。
葬儀社との打ち合わせ
そのあと、葬儀社と葬儀の場所や日時についての打ち合わせをします。
福祉葬の場合、葬儀の内容がほぼ決まっているため、喪主が決めることはほとんどありません。
葬儀を執り行う
そして葬祭扶助範囲内での葬儀を執り行います。
お通夜や告別式は行わず、必要最低限の火葬式という形式の葬儀となります。
葬儀の費用については、役所から葬儀社に直接支払われるため、喪主を介することは原則ありません。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
福祉葬を申請する際の注意点
福祉葬を申請する際にはいくつかの注意点があります。
ここでは、福祉葬を申請する際の注意点を紹介します。
遺産があると福祉葬は利用できない
故人が生活保護を受給していたとしても、葬儀費用を賄えるだけの預貯金などの遺産があった場合には、福祉葬の対象外となってしまいます。
また、遺産はあるが、葬儀費用の全額が賄えない金額の場合は、不足分のみ葬祭扶助が充てられます。
福祉葬のプラン変更はできない
福祉葬の葬儀内容は決まっているため、自己資金を追加してプランを変更したり、増設したりすることはできません。
喪主や施主の葬儀を執り行う方が葬儀費用を負担できるとみなされてしまい、葬祭扶助は必要ないと判断されてしまうためです。
火葬してからでは申請ができない
福祉葬を希望する場合は、お葬式(火葬)を行う前に市町村に申請する必要があります。
お葬式(火葬)の前に申請していないと適応されませんので注意してください。
納骨まではサポートされない
遺骨は家族や親族が引き取り、お墓に収めたり、手元供養や散骨を行ったりします。
お墓がない場合や血縁者以外であれば合葬墓にまとめられます。
福祉葬の葬儀内容には、墓石の購入や納骨費用は対象外となっています
福祉葬で香典は受け取れる?
生活保護を受給されている方が「葬祭扶助」を受けて行う福祉葬では、一般的な葬儀と変わらず香典を受け取ることができます。
生活保護を受給している方に収入が発生した場合は自治体に報告の必要がありますが、福祉葬で受け取る香典は「収入認定外」とされ、報告の必要がないことが定められています。
しかし、香典に関しての風習として、頂いた香典の3分の1〜半額程度を返礼品としてお返しする「香典返し」というものがあります。
葬祭扶助を受けて行う福祉葬では、香典返しにかかる費用は扶助の対象にならないのでご注意ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
福祉葬で戒名をつける場合
福祉葬を行う場合、戒名料は葬祭扶助制度の対象外です。
そのため、宗教上の理由や遺族の意向により戒名をつける場合、全額を自己負担する必要があります。
菩提寺や葬儀を執り行う住職へ戒名の依頼をする際には、お布施が必要となります。
多くの場合、このお布施は2万円以上の費用がかかりますので、生活に与える影響を考慮しつつ、計画を立てることが重要です。
戒名は、僧侶に依頼するほかに、自分でつけることも可能です。
ただし、戒名には院号、道号、戒名、位号といった4つの要素が含まれており、これらの構成要素を考慮しながらつける必要があります。
また、菩提寺がある場合には、トラブルにならないように、事前に菩提寺や家族への相談を必ず行ってからにしましょう。
スポンサーリンク生活保護について
生活保護制度とは
生活保護制度とは、日常の生活が厳しく、資産や能力を駆使しても最低限の生活が保てない方への支援制度です。
健康かつ文化的な最低限度の生活を保障することを目的としていますが、受けられる条件が定められています。
生活保護の受給条件
生活保護を受けるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 資産の活用:不要な土地、家、宝石などの資産を売却し、生活資金として活用します。
- 能力の活用:労働能力がある場合、求職の取り組みが必須です。
働くことができるのに働かないという選択は受給の対象外となります。
- あらゆるものの活用:年金や公的な支援金など、他の収入がある場合は、それを優先的に使用します。
- 扶養義務者の扶養:親族などの扶養義務者がいる場合は、その支援を受けることが基本となります。
ただし、扶養することで生活が困難になる場合は、生活保護を受けることができる可能性があります。
生活保護の権利
生活保護制度は無差別平等に利用できるものです。この権利として、以下の点が挙げられます。
- 保護の継続:無理由での保護の停止や減額はありません。
- 非課税:受け取った保護費には税金がかかりません。
これらの権利は、受給者としてしっかりと守られます。
生活保護の義務
生活保護を受けるということは、一定の義務も伴います。具体的には、以下の点が挙げられます。
- 生活の努力:財産や能力を最大限に活用し、生活向上の努力をすること。
- 働く努力:労働能力がある場合、就業を目指すこと。
- 福祉事務所の指導・指示に従うこと:不正な申請や、隠し財産が発覚した場合は、不正受給として罰則が適用されることもあります。
生活保護制度は、困難な生活をしている方々の強力な支えとなる制度です。
しかし、受給には一定の条件や義務が伴うため、正確な知識と理解をもって利用することが求められます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
生活保護受給者が死亡した際の注意点
生活保護者が死亡した際の納骨方法や金銭面の注意点について解説します。
納骨方法もいくつか選択できるので家族の考えに合った方法を選択しましょう。
生活保護者が死亡した際の納骨
福祉葬は、骨壺にお骨を入れるまでが対象となっています。
なので、その後どのように納骨をすれば良いのかを早いうちに考えなければなりません。
福祉葬を受けるということは、使えるお金にも限りがあります。
生活保護受給者が亡くなった際の納骨の方法は選択肢に限りがありますが、多くの場合は以下の5つの方法がありますので、納骨の際の参考にしてください。
納骨堂
納骨堂とは、個人単位で骨壺を安置できる建造物で、近年利用が急増しています。
現代は核家族化が進んでいることで、家族で持っていたお墓の継承が難しくなってきたことや、お墓を購入するより安く納骨できることや、街中にある納骨堂もあるのでお参りもしやすいことから人気の納骨方法です。
納骨堂には、寺院にあるものや自治体が運営する公営の納骨堂、法人が運営する民営の納骨堂など、様々な種類があります。
お墓を購入すると100万円ほどと高額になりますが、納骨堂なら数万円で納骨が可能です。
ただ人気の為に抽選になることが多く、しかもかなりの倍率となるのでその辺りの問題も考える必要があります。
遺族が手元で保管
もし遺族が自宅で遺骨を保管しても良いと了承したら、遺骨を自宅に置いておくこともできます。
ちなみに、家の中の仏壇に遺骨をそのまま納めておくのは違法にはなりません。
ただ、遺骨を勝手に裏山や庭などに埋めてしまうのは死体遺棄という犯罪になってしまうので注意しましょう。
遺骨の所有者が将来的に亡くなったり、遺骨をこのまま納めておくのが難しくなる場合になった時の遺骨の行き先は必ず考える必要があります。
いざという時に困ってしまうことのないように、将来的な遺骨の行き先を家族でじっくりと話し合っておきましょう。
散骨
散骨とは、遺骨を砕いて粉にして山や海にまく自然葬です。
近年、納骨の多様性によって散骨に対応している業者も増えてきています。
しかし散骨は、比較的新しい方法なので、現状法律の整備が追いついていません。
埋葬に関する法律にも規程されておらず、国民の意識や感情を意識して、節度を持って行うようにと国も見解を述べています。
なので、散骨をする時は事前に自治体に相談してから行いましょう。
永代供養
お墓を引き継ぐ人がいない時や、子供や孫など後の世代にお墓の管理の負担を軽減させるために、永台供養を選択する人が近年増えてきています。
永台供養をすると、寺院や霊園の関係者が供養と清掃管理を一手に引き受けるサービスを得られるので安心です。
永台供養は、三十三忌の供養が終わったあとで遺骨をまとめて一つの墓に入れる合祀の方が管理費が安いですが、霊園によって異なりますので事前にしっかり確認しましょう。
親族など引き取り手がいない場合
もし遺骨の身寄りが無く、遺族が遺骨の受け取りを拒否したら無縁塚に埋葬されます。
引き取り手が無い場合は、5年間自治体に管理された後に無縁塚に埋葬されますが、もし一度埋葬されたら引き取りに行っても対応することはできませんので注意しましょう。
生活保護者が死亡した際の一時金
生活保護受給者が亡くなり、葬祭費用を払うだけの金銭的余裕が無いという場合、生活保護法によって葬祭扶助が適用となり、最低限の葬祭手続きを行ったりすることはできます。
しかし、生活保護者が亡くなった際に葬祭費を支給することはできますが
「被保護者は、保護を受ける権利を譲りわたすことはできない」
と、生活保護法の59条にも定められていますので、扶養義務者に対する死亡一時金は基本的に支給されません。
また、生活保護を受ける権利は、誰かに譲り渡したり相続することもできない決まりです。
親族などの扶養義務者に対して、何らかのお金が支給されることもありません。
生活保護者死亡後の預金
予め生活保護の受給者が持っていた銀行口座に関しては、通常通り相続の対象になります。
銀行に対し、預金者が亡くなったことを伝え、相続の手続きをすれば預金は相続人へと継がれるので、相続した預金から保護費の返還や葬儀費用を支払うことは可能です。
しかし、相続の前に被相続人の預金をおろしてしまうと、使用目的によって相続承認とみなされるので相続放棄ができない可能性もあります。
スポンサーリンク故人が生活保護受給者だった場合の遺品整理
ここからは生活保護受給者の方が亡くなった場合に、どのように遺品整理を進めればよいかをケース別にご紹介します。
一般的に、生活保護受給者の遺品整理は、親族・連帯保証人・管理会社や大家さんのいずれかが行うこととなります。
親族
故人に親族がいる場合には、親族が遺品整理を行うこととなります。
生活保護は受給者が亡くなるまで有効であり、亡くなってからは自治体からの金銭のサポートはありません。
そのため、親族が対応可能な場合は遺品整理を行わなければなりません。
ただし、生活保護の場合には遺品整理できる親族がいないことも少なくありません。
その場合は、他の方法を検討する必要があります。
賃貸物件の連帯保証人
故人に親族がいなかったり、親族が遺品整理を行うのが難しかったりする場合には、賃貸物件の連帯保証人が遺品整理を行わなければなりません。
生活保護受給者の場合は、賃貸物件を借りる際に連帯保証人が必要となるケースが多いです。
そのため、連帯保証人が遺品整理を可能な場合は連帯保証人に依頼することとなります。
管理会社や大家さん
親族と連帯保証人の両方が遺品整理を行えない場合には、管理会社や賃貸物件の大家さんが、遺品整理を行うこととなります。
この場合、前述したように遺品整理にかかる費用は自治体がサポートしてくれないため、管理会社や大家さんが負担しなければなりません。
通常、遺品整理などの遺産相続に関連する作業は相続人が行わなければならないとされています。
しかし、相続人がいない場合には遺品整理が進まないため、管理会社や大家さんが遺品整理を進めていかなければなりません。
一般的に、遺品整理は親族が行い、それが難しい場合は連帯保証人、連帯保証人も難しい場合は管理会社や大家さんが行うという流れになります。
遺品整理にかかる費用についても、同様の流れとなります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
福祉葬のよくある質問
福祉葬と民生葬の違いは何ですか?
「福祉葬」と「民生葬」は、生活保護を受給している方々の葬儀を支援する制度を指す言葉であり、同じ意味を持ちます。
また同じ意味で、「生活保護葬」とも呼ばれています。
福祉葬の葬儀の種類は何ですか?
福祉葬は、通夜や告別式を行わず火葬のみ行う直葬・火葬式を行います。
火葬を行うまでは、ご遺体を一時的に自宅や安置施設に安置する必要があります。この際に必要なドライアイスの費用も、福祉葬の支給対象となります。
何故、火葬後に福祉葬の希望申請出来ないのでしょうか?
火葬後に書類を提出すると、葬儀費用を先に立て替えることにより、申請が受け付けられない場合があります。
これは、立て替えた行為が葬儀費用を支払う能力があると判断されるためです。
- 故人様と申請者の個人情報
- 故人様と申請者の経済状況
以上の点を指定の書類に記入し、必ず火葬の前に提出しましょう。
福祉葬の費用はどこから支払われているのでしょうか?
福祉葬の費用の全額が自治体の予算から支払われます。
要するに税金です。
福祉葬まとめ

ここまで福祉葬の葬儀内容や申請方法についての情報を中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 福祉葬は生活保護を受給している方に対する葬祭扶助である
- 葬儀内容は決まっており、葬儀は火葬式の形式となる
- 福祉葬の申請は葬儀社が代行してくれることが多い
- 福祉葬は葬儀・火葬前に申請をしないと適用されない
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2025.06.17
互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説
お葬式

更新日:2024.01.10
合同葬とは?社葬や一般葬との違いや相場、マナーについて解説
お葬式

更新日:2023.10.20
湯灌(湯かん)は何をするの?湯灌の目的や費用相場なども紹介
お葬式
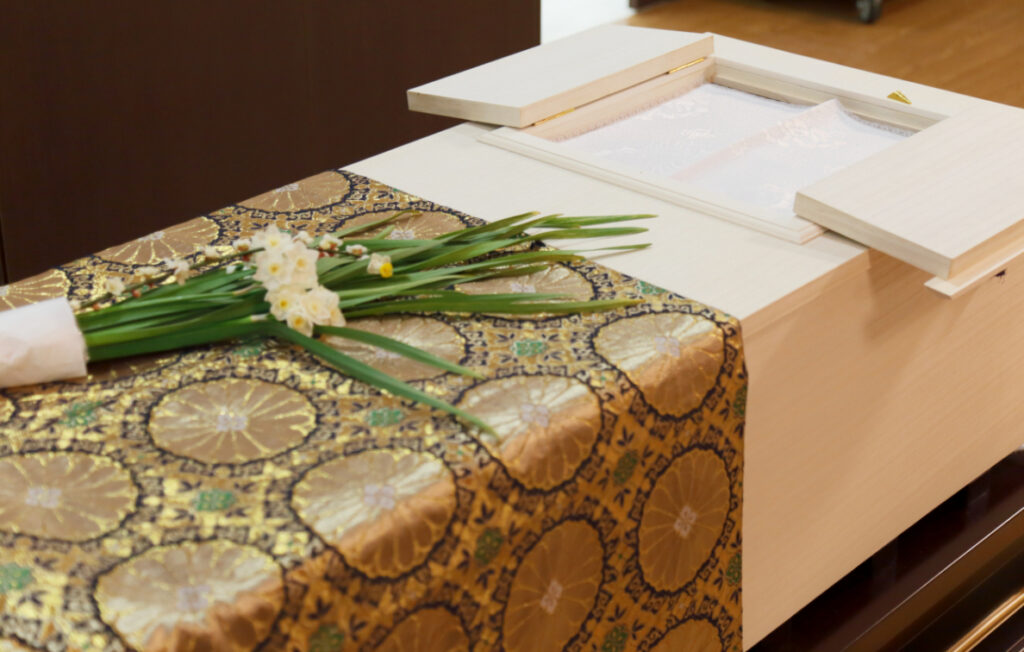
更新日:2024.02.03
遺体搬送車とは?遺体搬送車の車種や霊柩車との違い、搬送料金についても解説
お葬式

更新日:2025.03.20
音楽葬の費用の内訳は?演奏者の派遣料金や著作権、音楽葬の流れも解説


