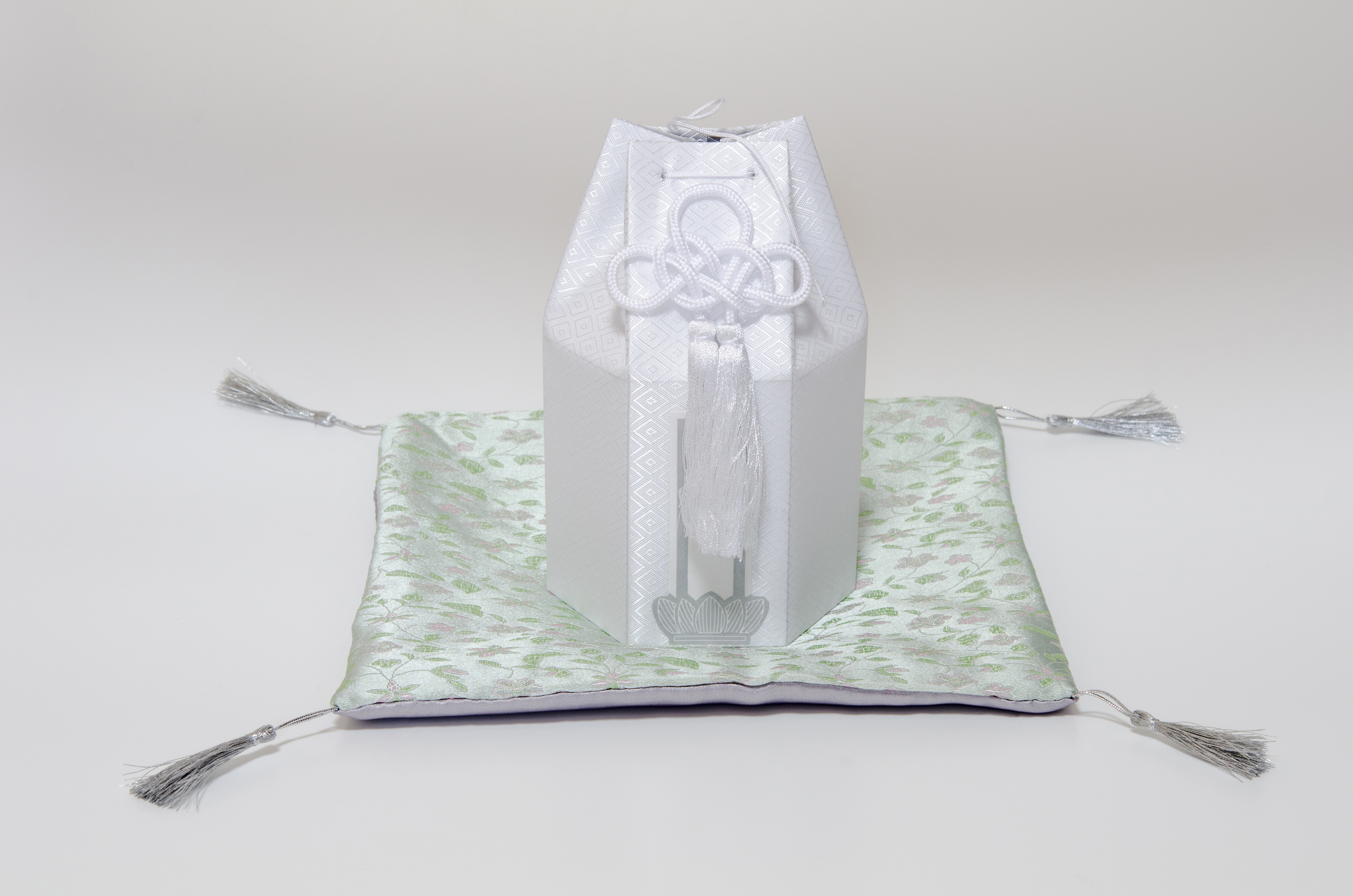お墓
お墓に埋められた骨はどうなる?土や水に還るのか解説
更新日:2024.02.03 公開日:2021.09.29

日本では、人が亡くなった時は遺体を火葬し埋葬する方法がほとんどです。
お墓に埋められた骨は、その後土に還るのか、水に溶けるのか、どのくらいの期間かかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、お墓の骨が土に還る時間はどれくらいかかるのか、骨壺に入れた骨はどうなるのかについて詳しく解説します。
火葬で残った遺骨や遺灰のその後についても説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。
お墓の骨はどうなる?

日本国内の99%は焼骨を埋葬する形です。
骨壺に入れて埋める場合もありますし、遺骨だけ入れて土に還す場合、また袋に入れて納骨することもあり、埋葬方法は霊園や宗教によって様々です。
色々な形で土に埋めますが、お墓の骨は土に埋めた後にどうなるのか、疑問に思う人も多いです。
お墓の骨は土に還るのか、どれくらいの時間がかかるのかについて詳しく説明します。
土に還るまでに数百年かかる?
骨が土に還るという話はよく聞くと思いますが、イメージとしては数年で骨が土に還ると思っている人が多いのではないでしょうか。
実は骨が土に還るまで、とても長い時間がかかります。
火葬した骨は、表面がセラミック状になっていることもあり、完全に土に還るまでに数100年以上かかる場合もあります。
土壌の性質にもよる
火葬の骨が土に還るのに時間がかかるのは、土壌の性質にも左右します。
骨の成分は、主成分はリン酸カルシウムとタンパク質そして少量の水でできています。
火葬することによって骨は高温によって表面が硬化して、土に分解されにくくなります。
骨の成分のリン酸カルシウムは、酸性の水によって少しづつ溶けて、年月をかけて土に還る仕組みです。
土壌によっては酸性ではなく、アルカリ性の土壌もあり骨のリン酸カルシウムが解けない場合もあります。
日本の土地の場合は、酸性の土壌が多いので時間をかけると土に還りますが、その時間が火葬の場合は長くかかります。
また、バクテリアの有無にも影響されます。
土葬ではさらに短い
土葬とは、遺体を焼かずに土の中に埋葬することを言います。
海外では土葬で埋葬することが珍しくないですが、日本では土葬を認めている霊園は全国でほとんど存在せず、大体火葬して埋葬されます。
土葬の場合は、骨が土に還る時間が短く数十年と言われています。
バクテリアの存在、土質によっても期間が変わりますが、土葬の骨は火葬した骨と比べて柔らかい特徴があり土に還る時間も短くなります。
散骨では50年ほど
日本には骨を粉砕して海や山に散骨する業者があります。
粉砕して場所を選定するところまで行ってくれます、費用は一体5万円程度です。
地域によっては骨を粉状にしてお墓に戻すことも散骨と言いますが、散骨すると骨が土に還りやすくなります。
骨の主成分のリン酸カルシウムは、とても水に溶けにくい成分です。
水に溶けやすい塩と比べて18,000倍溶けにくいと言われており、粉砕したとしても完全に土に還るのは単純計算でも50年かかることになります。
お墓の骨壺にある骨はどうなる?

遺骨をお墓に埋葬する場合、多くは骨壺に入れて骨壺ごと埋葬します。
この骨壺に湿気や結露で水がたまります。
蓋を密閉していなくて置いただけのタイプは水がたまりやすく、何十年もたつと蓋近くまでたまっている場合もあります。
この水で遺骨が溶けてしまうのかが気になりますが、実はほとんど溶けることがありません。
骨壺の中の遺灰が若干溶けますが、ほとんどの場合、遺骨はそのまま残っています。
ある程度まで遺灰が解けると飽和状態になり、遺灰もそれ以上は溶けません。
骨壺の水は何?
骨壺の中に水が溜まっていると、骨が解けて水になったと思う方も多いですが、これは骨壺内の結露した水や湿気が骨壺に長年かけてたまったものです。
密閉した骨壺の場合は、長く水がたまらないですが、蓋をのせるだけのタイプは水がたまりやすく、骨壺の形状や素材によっても水のたまり方が違います。
先ほども説明しましたが、水がたまった中に遺骨があったとしてもほとんど溶けずに残ります。
骨壺に水がたまらないようにする方法
骨壺に水がたまると、カビの心配がありますしお墓を移動する時、引越しをする時に面倒なことになります。
ここでは骨壺の水の処理の仕方や、水がたまらないようにする方法を紹介します。
定期的に掃除をする
お墓の中の通気をよくすると結露や湿気も出ないのですが、これは構造上とても難しいです。
そこで水がたまらないように定期的に掃除をするのが大切です。
期間は1年に1度、骨壺にたまった水を捨てて、遺骨と骨壺、カロート内を日光にあてて乾燥させます。
ご先祖様のお墓をきれいにすることで、供養にもなりますし、骨壺内の環境も良くなるため定期的な掃除をおすすめします。
水抜き穴のある骨壺を使用する
お墓が遠い、仕事が忙しいなどの理由で定期的に骨壺まで掃除するのは難しいという人も多いでしょう。
その場合は、水抜き穴のある骨壺を使用するという方法もあります。
色々なタイプがありますが、骨壺の底に貼られている特殊シールが埋葬後に溶け出す仕組みの物もあり、自然と水を排出してくれます。
相場は6000円程度で比較的安価で手に入るので、人気があります。
他にも外部に水分が染み出ていく素材の骨壺なども開発されているため、石材店に相談してみると良いでしょう。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
火葬で残った遺骨や遺灰はどうなる?

火葬した際に、骨壺に入れて埋葬する骨や遺灰は全てが骨壺に収まるわけではありません。
また、地域によって骨を拾う形式が違い、東日本では基本的にすべての遺骨を納めます。
西日本の場合は一部の遺骨だけのため、西日本の火葬は遺骨が多く火葬場に残ります。
火葬の方法によっても、遺骨の残り方が違います。
火葬の方法は2つあり、「ロストル式」と呼ばれる方法では、火葬した際に遺骨が骨受け皿に落ちていきます。
現在ロストル式の火葬場は、全体の1割程度と少なく、ロストル式で火葬した場合、骨が綺麗に残りにくい特徴があります。
もうひとつは「台車式」と呼ばれる火葬方法で、台車と御棺を一緒に焼く方式です。
台車式は、ロストル式と比べると綺麗に遺骨が残ります。
自治体によって処理される
火葬後に残った遺骨は、法的に自治体の所有となります。
砕かれて灰の状態になった遺骨は、不用品もしくは廃棄物として処分することができます。
ただ、遺族にとっては廃棄物として処理されるのは心情的に抵抗がある方も多いでしょう。
そういった事情からも、残った遺骨については自治体が専門の処理業者に依頼して、残骨供養堂や永代供養堂に収められることが多いです。
処理業者では、有機物質の除去、多く混ざっている貴金属のリサイクルを行っている業者もあります。
お墓の骨がどうなるのかまとめ

ここまでお墓の骨がどうなるのかの情報や、骨壺の水についてなどを中心に書いてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- お墓の骨が土に還るまでの時間は数百年かかる
- 骨壺に入れた骨は水に溶けることなく残る
- 骨壺の水は定期的に掃除するか、穴あきの骨壺を使用するとたまらない
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。
お墓の関連記事
お墓

更新日:2022.05.24
墓地の管理者はいったい誰?不明な管理人の探し方なども紹介
お墓

更新日:2022.11.17
塔婆は何回忌まで必要なの?塔婆の依頼方法・処分方法も併せて解説
お墓

更新日:2023.11.21
四十九日に必要な塔婆は?七本塔婆や費用について紹介
お墓

更新日:2023.11.19
お墓の花は枯れたらどうする?対処法や長持ちのコツ、造花についても解説
お墓

更新日:2023.11.21
お墓に関する親族間のトラブルとは?トラブルを避けるための対策を解説
お墓

更新日:2022.11.17
塔婆を立てないのはマナー違反?立てない宗派についても紹介