相続
遺産を独り占めさせないためには?独り占めとなる状況も紹介
更新日:2022.04.26 公開日:2022.05.07

記事のポイントを先取り!
- 基本的に遺産の独り占めはできない
- 独り占めされても遺留分請求で取り返せる
- ケースによっては独り占めできる
- 遺言書の改ざんをすると有罪になる
遺産は亡くなった後分配されますが、独り占めできるのかについてご存知でしょうか。
死後残された遺産は、どの法律が適応され、どのようにして分配されていくのかを知っておきましょう。
そこでこの記事では、遺産の独り占めについて詳しく説明していきます。
この機会に遺産を独り占めさせない方法を覚えておきましょう。
遺言状が偽装されていた場合についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
- 遺産とは
- 遺産は独り占めできない
- 遺産を独り占めされてしまったら
- 遺産をすでに使われていた場合
- 遺産を独り占めさせないための予防策
- 遺産は独り占めできる?
- 終活ノートに遺言が書かれていた場合は?
- もし遺言状が偽造されていた場合は?
- 遺産の独り占めまとめ
遺産とは
遺産とはそもそも何なのでしょうか。
まずは遺産について解説します。
遺産の意味
遺産とは、故人が所有していて、死後残された資産のことです。
家に残されたものや現金、不動産などが遺産のイメージとして思われがちですが、法的な意味での遺産とは、故人の預貯金債権や借金なども指しています。
こうしたものは相続の対象となり、何もしないと借金もすべて相続することになります。
しかし一身専属権という、故人でないと使えないような権利は、相続の対象にはならず、遺産とはいえません。
故人が勤めていた会社での立場や、役職などは一身専属権にあたるため、遺産ではありません。
一身専属権を継承したい場合は、遺産としては扱えないため、跡継ぎといった形で継承しましょう。
遺産の主な対象
遺産になる主なものは、2つに分けられます。
相続する人にとって利益となる遺産と、負債となる遺産です。
特に負債となる遺産には、自分の不利益になるようなものが多く見られます。
利益となる遺産
- 預金
- 不動産
- 仮想通貨
- 知的財産権
負債となる遺産
- 借金
- 未払いになっている経費
- 未払いになっている慰謝料
- 保証債務
遺産は独り占めできない
他の兄弟や親族に遺産を渡したくないという人は、遺産を独り占めできるかどうか気になるのではないでしょうか。
基本的には法律で相続できる人や相続分は決まっているため、遺産の独り占めはできません。
詳しく見ていきましょう。
法定相続分によってできない
遺産は法定相続分に従って分けないといけません。
法定相続分は、故人の家族構成によって変化します。
しかし長男だから多くの遺産がもらえるといったように、兄弟間で法定相続分に違いはありません。
子供がたくさんいても、遺産は均等に分配されます。
たとえ長男で故人の面倒を見ていたからといっても、遺産の独り占めはできないと認識しておきましょう。
遺留分によってできない
遺言書で、一人だけに遺産を渡すと書かれていたとしても、それぞれ相続人には遺留分が決められています。
遺留分とは、最低限もらえる相続財産のことです。
遺言書に、一人だけに遺産を渡すと書かれていて、他の相続人が不服に思うときは、遺留分の請求ができます。
他の相続人が遺留分を請求すると、遺留分を分けないといけません。
遺留分を請求されれば、遺産の独り占めはできなくなります。
遺産を独り占めされてしまったら
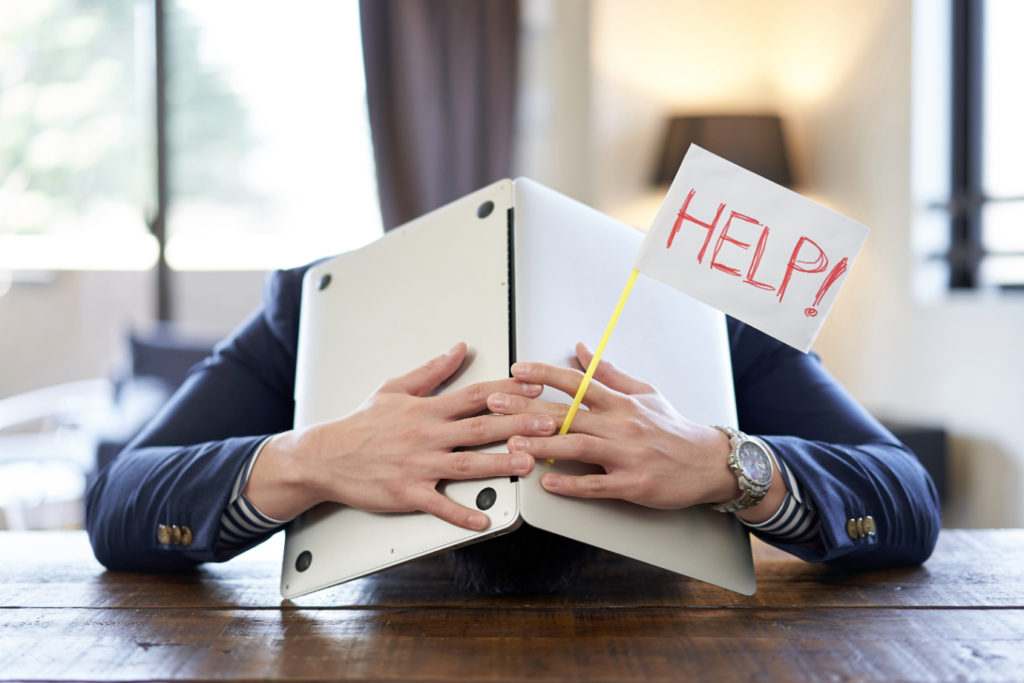
もし遺産を独り占めされてしまったら、どうしたら良いのでしょうか。
遺産を分けてもらうには、二つの方法があります。
遺産分割調停を申し立てる
法定相続分があるといっても、遺産を独り占めして分けてくれない場合もあります。
そのような時には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることができます。
調停を申し立てると、調停委員に相手を説得してもらうことが可能です。
相続人による説得では納得してもらえなかった場合でも、第三者に説得してもらうと素直に同意してくれることもあります。
それでも分けてもらえないようなら、審判を行うことになります。
審判では、裁判官にどうやって遺産を分けるかを決定してもらいます。
審判になると法定相続分によって遺産が分けられるので、独り占めはできません。
遺留分侵害額請求を申請する
遺留分侵害請求を申請することで、遺産を独り占めしている人に対して、侵害額に相当するお金を支払ってもらうよう請求ができます。
これによって、遺留分の遺産をもらえるようになります。
遺留分の請求は、故人の配偶者・子供などの直系卑属、故人の両親などの直系尊属のみができることです。
兄弟・姉妹は請求できないので注意してください。
遺産をすでに使われていた場合
遺産を独り占めされた上に、遺産を使い込まれていることがあります。
使い込まれた遺産は取り戻さないといけません。
その場合、何をすれば良いのでしょうか。
銀行口座を凍結する
遺産が使い込まれていることがわかったら、すぐに銀行口座を凍結してください。
預金を使い込んでいる場合、そのままにしておくと、分けられるはずの遺産がずっと使い込まれて減っていきます。
これ以上使い込まれないためにも、銀行口座を凍結しましょう。
銀行に口座の名義人が死亡したことを伝えれば、口座を凍結してもらえます。
そして、残高証明書を発行してもらいましょう。
残高証明書で、預貯金の残高を銀行から証明してもらえます。
残高証明書のほかに、口座の取引履歴も出してもらってください。
どちらも、本人確認できるものや戸籍謄本などの必要書類をもって金融機関へ行くと発行してもらえます。
取引履歴を見て、故人の死後に出金されていたり、大金がおろされたりしていないか確認して、使い込まれていた証拠を押さえておきましょう。
不当利得返還請求を申請する
話し合って解決できなかったら、地方裁判所で裁判を起こすことになります。
不当利得返還請求を申請して、裁判を起こしましょう。
遺産を使い込まれて、不利益を被った人は利得の返還請求ができます。
場合によっては損害賠償請求をすることになります。
不法行為にもとづく損害賠償請求を申し立てましょう。
相手の行った不法行為で、不利益を被った人が不法行為をした相手へ、損害賠償を求めることができます。
こうした請求をすることで、使い込まれた遺産を取り戻すことが可能です。
不当利益返還請求は使い込みが起こってから10年、損害賠償請求は損害や使い込んでいる人が誰かを知ったときから3年以内に行ってください。
これ以上時間が経ってしまうと、時効となって申請できません。
使い込みがわかったら、素早く対応してください。
遺産を独り占めさせないための予防策

遺産の独り占めを未然に防ぐために、予防策を行っておきましょう。
予防策には、手軽にできるものから、専門家に依頼するものまであります。
自分に合った予防策を行って、独り占めしようとする人がいても、遺産が正しく分配されるようにしてください。
遺言書を用意してもらう
一番良い方法は、故人が亡くなる前に遺言書を用意してもらうことです。
遺言書は、ポイントをおさえれば誰でも書けます。
遺言書があれば故人が亡くなった時、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
ただ、遺産の配分が偏りすぎていると、相続人の間でトラブルが起きてしまうことがあります。
遺留分について考えながら書いてもらうようにしましょう。
遺言書を書くのが難しいという時は、司法書士や弁護士など、専門家に相談するのがおすすめです。
故人に遺言書を書く能力がない頃に書かれた遺言書や、誰かの利益のために誘導されて書かれたような遺言書は、効力がないとされる可能性があるので気をつけてください。
あくまでも、故人の意思で書いてもらいましょう。
親族・相続人と良好な関係を築く
親族や相続人と良い関係を築いておくことも大切です。
遺産を独り占めする理由に、「亡くなるまで故人の世話をしていた」や、「故人と暮らしていた」というものがあります。
そういった理由で遺産を独り占めされないためにも、故人だけではなく、親族や相続人とも仲良くしましょう。
弁護士に相談する
遺産分割は法律が関わってくるため、仕組みがよくわからなくなってくるかもしれません。
混乱する前に、事前に弁護士に相談しておくのも良いでしょう。
弁護士に相談することで、遺産を独り占めする人に先手を打つことができます。
弁護士に、法律のいろいろな方面から支えてもらうというのも、予防策の一つです。
遺産は独り占めできる?
これまで遺産を独り占めできないことについて説明してきましたが、ケースによっては独り占めできることもあります。
しかし、他の相続人がいなかったり、遺言書に書かれていたりと、そのどれもがだいぶ限定的なものです。
遺産を独り占めできるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
遺言書に記載されている場合
遺言書に記載があり、相続人全員が納得するようなら、遺産の独り占めができます。
遺言書に書かれていることは、法的に効力があります。
相続人全員が了承すれば、遺言書の通りに遺産を分けることが可能です。
ただし相続人が一人でも納得せず、遺留分の請求をされたら独り占めすることはできません。
遺言書に、自分だけに遺産を相続するなどと書かれていた場合は、必ず相続人全員の意思を確認しましょう。
他の相続人が相続放棄した場合
遺言書に遺産の分け方が書かれていなくても、独り占めできてしまうケースがあります。
それは、他の相続人が相続放棄した場合です。
自分以外の相続人が相続放棄し、自分しか相続する人がいなければ遺産の独り占めができます。
終活ノートに遺言が書かれていた場合は?
遺言書ではなく、終活ノートに遺言が書かれていた場合は、その内容に従わなければならないのでしょうか。
遺言書は法的な方法に従って書かれているため、法的な効力があります。
しかし終活ノートは法的な方法に従って書かれていないため、法的な効力はありません。
終活ノートに遺言として、遺産の分け方について書かれていたとしても、終活ノートの遺言に法的な効力がないため、その通りに分けることはできません。
基本的に遺産は、法定相続分に従って分割されます。
口約束での遺言も、終活ノートと同じように法的な効力はありません。
遺言は、きちんと遺言書の形式で残しておくようにしましょう。
口約束で遺言を残していても、遺産は法定相続分に従って分割されます。
もし遺言状が偽造されていた場合は?
ごくまれに、遺言書が偽造されている場合があります。
遺言書が他人によって偽造されると、その遺言書は無効になります。
遺産を独り占めするために、偽の遺言書を作ったり、書き換えたりすると、それがバレた時に大きなリスクを負うことになります。
遺言書偽造は犯罪行為
遺言書を偽造することは犯罪行為です。
遺言書を破棄したり、偽造したりした場合、刑事罰に問われることになります。
遺言書を偽造すると、私文書偽造等罪に問われる可能性があります。
私文書偽造等罪は、3か月以上5年以下の懲役です。
遺言書を捨てたり焼いたりして破棄した場合、私用文書等毀棄罪(しようぶんしょとうききざい)に問われる可能性があります。
私用文書毀棄罪は、5年以下の懲役です。
民法では、破棄や偽造、変造や隠ぺいをした人は、相続人としての資格を失うと定められています。
遺言書を改ざんすると、遺産を独り占めするどころか相続すること自体ができなくなります。
遺産を独り占めするための遺言書の改ざんは、相続人の資格を失って罪にも問われる、大きなリスクを伴うことです。
リスクを負う可能性のある遺産の独り占めなどは考えず、法定相続分の遺産を分けてもらうほうが良いといえます。
偽造かどうかの見分け方
遺言書の偽造問題では、本当に故人が直筆で遺言書を書いたのかどうかで、遺言書の効力が判断されます。
遺言書が故人によって書かれたものなのか、偽造されたものなのかを見分けるには専門家に筆跡鑑定を依頼するのが良いでしょう。
筆跡は年齢やその日の体調、筆記具や筆記の姿勢によっても変化するものです。
遺言書の筆跡が故人本人のものなのか、故人の筆跡を真似して他の人が書いたものかを、素人が正確に見分けるのは難しいでしょう。
遺族が直筆だと思っても、実は他の人が故人の筆跡を真似して書いたものだったということもあり得ます。
筆跡鑑定では、故人の書いた手紙などの筆跡と、遺言書の文字の筆跡を比べて、遺言書が直筆のものなのかを見ます。
もちろん、遺言書の筆跡と比べる資料が多ければ多いほど、正確な鑑定が行えます。
もし誰が遺言書を偽造したか分かっている場合、偽造した人の筆跡も鑑定できると、その人が遺言書を偽造したという証拠になります。
ただし筆跡鑑定の鑑定士には、公的な資格が存在する訳ではありません。
筆跡鑑定士の能力はまちまちだということに注意してください。
遺産の独り占めまとめ

ここまで遺産は独り占めできるのかや、独り占めされたときの取り返し方などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 基本的に遺産を独り占めすることはできない
- 遺産を独り占めされても、調停や遺留分請求で取り返せる
- 使い込まれた遺産は、裁判を起こすことで取り返せる
- 遺言書の改ざんや破棄は罪に問われる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
監修者

唐沢 淳(からさわ じゅん)
経歴
業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。
相続の関連記事
相続

更新日:2022.04.23
遺族年金を受け取ったら確定申告は必要?所得控除や節税方法も解説
相続

更新日:2022.04.14
遺産はどうやって分ける?遺産分割の流れ・方法を解説
相続

更新日:2022.04.18
遺産の配分割合はどうなる?法定相続分について解説
相続

更新日:2024.06.14
「おひとりさま」の生前整理…血縁者が1人もいないが、死後の財産はどうなる?






