お墓
お墓にお供えする葉っぱにも種類がある?その用途や役割を解説します
更新日:2024.01.24 公開日:2021.06.29

記事のポイントを先取り!
- お供えする葉っぱには「しきみ」と「さかき」がある
- 「しきみ」は仏教、「さかき」は神道でお供えする
- お墓のお供えする花は、故人が好んでいた花をお供えすると良い
お墓や仏壇、また神社や神棚などに飾られている緑色の「葉っぱ」は、一見すると皆同じように見えます。
しかし、実は用途によって用いられる「葉っぱ」には違いがあります。
今回は、お供えとして用いられているこの「葉っぱ」について、詳しくご紹介します。
ぜひ最後までお読みください。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。
お供えする葉っぱの種類
お供え用として用いられる葉っぱには、「しきみ」と「さかき」があります。
見た目にもよく似ている、この「しきみ」と「さかき」それぞれの特徴について、簡単にご紹介します。
しきみ
「樒(しきみ)」とは、仏教の葬儀や法要などに用いられる葉っぱです。
独特な香りを放つことから、「香の花(こうのはな)」「香芝(こうしば)」などとも呼ばれ、線香や抹香の原材料としても用いられます。
また、しきみには強い毒性があり、その毒は「毒物及び劇物取締法」により劇物と指定されているほどです。
たとえ少量であっても、体内に入ると命を落とす危険性もあります。
葉の特徴は、厚みがあり波打った形状をしています。
さかき
「榊(さかき)」とは、神道と深い関わりがあり、神事や神棚に飾る植物として用いられる葉っぱです。
さかきは別名「ホンサカキ」とも呼ばれています。
葉の特徴は、形が長い楕円形をしており、7~10cm程度の葉が二列相互でついています。
葉の色は濃い緑色で、表面に光沢があるのが特徴です。
お墓には「しきみ」を使おう

お墓にお供えする場合には、「しきみ」を用います。
「しきみ」の放つ独特な香りには、実は大きな役割があります。
ここでは、お墓に「しきみ」をお供えする理由について、ご紹介します。
悪霊除け
しきみは、悪霊除けとして葬儀の飾りにも用いられます。
古くより、しきみの持つ独特の強い香りと猛毒には、邪気を祓う力やお清めの力があると言われてきました。
今でも、関西地方には「葬儀の際には、しきみを立てる」という慣習が残っています。
葬儀会場の入口に「門樒(かどしきみ)」を、祭壇の後ろに「二天樒(にてんしきみ)」を飾ることで、故人を邪気から守る役割があると考えられています。
虫除け
しきみの放つ独特の香りには、虫除け効果のあるサフロールという成分が含まれています。
このサフロールは、殺虫剤や忌避剤にも使用されています。
昔は土葬が主流であったため、お墓には、ハエなどの害虫が群がっていました。
害虫には、疫病の原因になるものもいるため、害虫を寄せ付けないようにしていたと言われています。
火葬が主流となった今では、しきみの虫除け作用により虫でお墓が汚れるのを防ぐという目的もあります。
動物除け
昔は土葬が主流であったため、人里から離れた山中などにご遺体を埋葬していました。
そのため、野生の動物にお墓を荒らされることは、決して珍しいことではありませんでした。
このような野生の動物からご遺体を守るために用いられたのが、しきみです。
お墓の周りに猛毒のあるしきみを植えることで、野生の動物を寄せ付けないようにしていました。
お香として
しきみには、独特の強い香りがあり、線香や抹香などの原材料としても用いられています。
かつては、粉末状の抹香を仏像や仏塔などに塗りこむことによってその香りをまとい、穢れを祓ったと言われています。
しきみの放つその独特な香りには、浄化作用や消臭作用があるとされ、お香としても使用されます。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
しきみは仏事、さかきは神事でお供えする
「しきみ」と「さかき」はよく似た葉っぱですが、それぞれ用途が異なります。
「しきみ」は、お墓や墓地などに植えられていることの多い植物で、主に仏教の葬儀や法要などで用いられる葉っぱです。
また、お墓だけでなく仏壇のお供えとしても用いられます。
しきみの持つ独特の香りと毒性には、お墓や故人を守る役割があります。
一方「さかき」は、神事や神棚に飾る植物として用いられる葉っぱです。
神道の葬儀や法事だけでなく、神棚の飾りや、神社で神主さんが振る「大麻(おおぬさ)」などにも用いられています。
葉っぱと一緒に使うお供え用のお花
お墓や仏壇などにお供えする場合、葉っぱだけでなく花も一緒にお供えします。
ここでは、葉っぱと一緒にお供えする花について、ご紹介します。
一番メジャーな菊
お供え用の花として、最もよく用いられているのが菊です。
なぜ菊の花がお供えとして用いられるのか、次のような説があります。
- 菊の花は皇室の紋章にも用いられており、格調高い花だから。
- 種類が豊富だから。
- 日持ちが良いから。
- 菊の花は「邪気払い」や「無病息災」「長寿をもたらす」など、縁起の良い花と言われているから。
故人が亡くなられてから日が浅い場合には、白色の菊を用いるのが一般的です。
故人の好きな色、好きな花を供える
お供えする花に迷った場合、故人の好きだった花や好きな色の花を参考に選ぶのもおすすめです。
お供え用の花を選ぶ際は花もちが重要なポイントとなりますが、どの花を選んでも特に問題はありません。
先ほどご紹介した菊以外に、よくお供えとして用いられる花には、次のようなものがあります。
- カーネーション
- アイリス
- キンセンカ
- スターチス
お墓や仏壇など、お供えする場所や用途なども考慮し花を選びます。
お墓のお供えに向かない花
お墓にお供えする花には、避けた方が良いと言われるものがあります。
具体的には、次のような花です。
- バラなどのトゲがある花
- 彼岸花・スズランなどの毒性のある花
- ユリ・ウメなどの香りのきつい花
- あさがお・クレマチスなどのツルのある花
トゲは「殺生」をイメージさせるため、トゲや毒性のある花は、お供え用としては避けた方が無難です。
香りがきつい花についても、線香の香りを妨げてしまう可能性があるため、お供え用としては不向きと言われています。
ツルのある花は、自分の家のお墓だけでなく周囲のお墓にも迷惑をかけてしまう可能性があるため、避けるのが無難です。
造花でも問題ない
お供え用の花には生花が望ましいという声も多く聞きますが、造花を用いても特に問題はありません。
一番よくないことは、お供えした生花を枯らしたまま放っておくことです。
毎日お水の入れ替えが難しく、すぐに花を枯らしてしまう場合であれば、造花を用いるのも一つの解決方法といえます。
また、普段は造花を使用し、特別な日には生花をお供えするといった、生花と造花を使い分けをしても問題ありません。
あくまでも大切なことは、故人やご先祖様を供養する気持ちです。
しかし、生花のみと定めている霊園や墓地も存在します。
造花をお供えする際には、管理者に確認をとることをおすすめします。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも 可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
お墓にお供えする葉っぱについてのまとめ

今回は、お墓にお供えする「葉っぱ」についてご紹介してきました。
今回の記事をまとめると、次のようになります。
- お供えする葉っぱには「しきみ」と「さかき」がある。
- 「しきみ」は、仏教と深い関わりがあり、「さかき」は、神道と深い関わりがある。
- お墓のお供えする花は、故人が好んでいた花をお供えすると良い。
ここまでお墓にお供えする「葉っぱ」の種類や用途別の使い分けなどを中心にお伝えしてきました。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。
監修者

鎌田 真紀子(かまた まきこ)
国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)
経歴
終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。
お墓の関連記事
お墓

更新日:2024.01.24
お墓参りではなぜ線香をあげる?意味やマナーを解説します!
お墓

更新日:2022.05.24
お墓参りは花なしでもOK?花を持参しない理由から対処法まで紹介
お墓

更新日:2023.11.24
お墓参りの線香の本数は何本?宗派によって変わるマナーを解説!
お墓
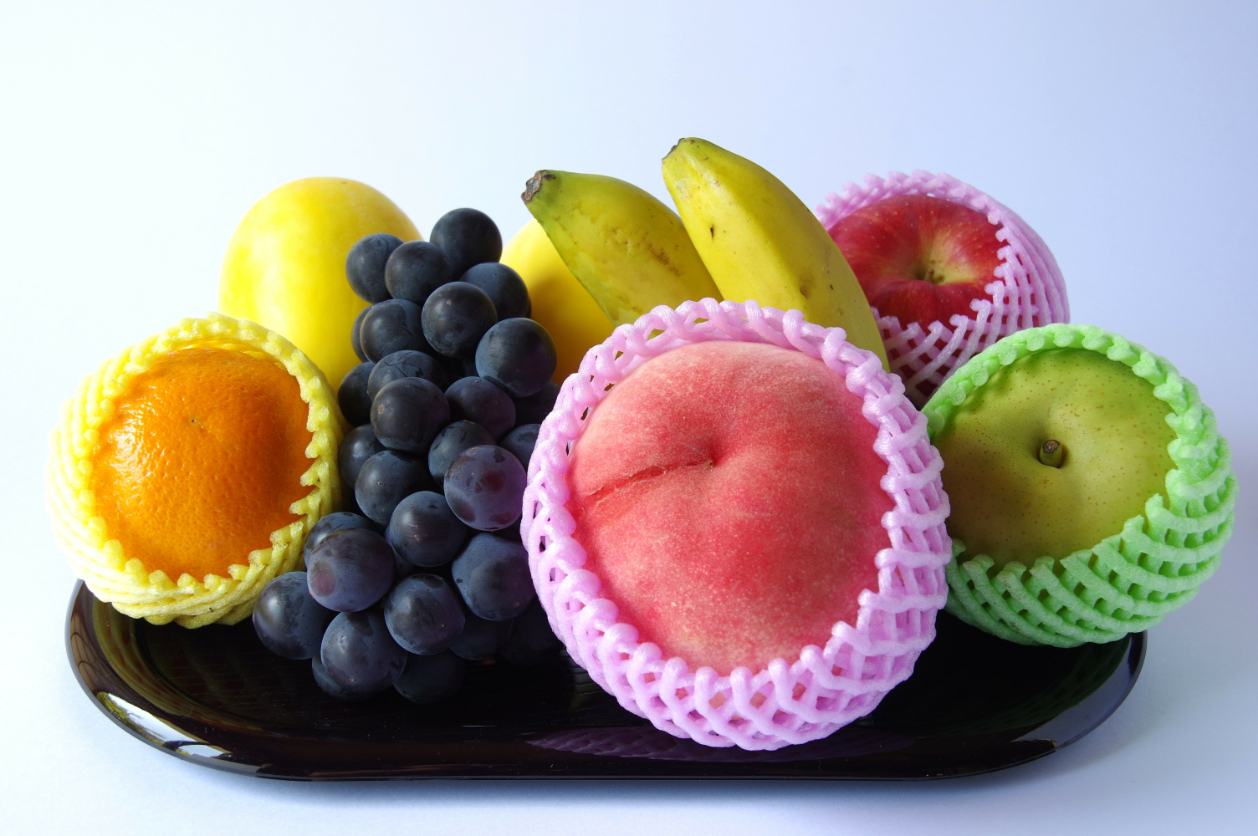
更新日:2024.01.24
お墓参りのお供え物の選び方は?お供え物の置き方も解説
お墓

更新日:2024.02.04
お墓参りは毎月行くべき?適切な時期や月命日に行うことについて解説
お墓

更新日:2022.11.21
お墓にお供えする花の輪ゴムは外す?花の種類やマナーも解説



