終活
遺品を処分する手順とタイミングとは?業者に依頼する注意点も解説
更新日:2025.01.08 公開日:2022.05.05

記事のポイントを先取り!
- 賃貸の遺品処分は退去日までに行う
- 持ち家の遺品処分の時期は様々
- 遺品は大きく3種類に分けると良い
- 業者が遺品処分を代行してくれる
家族や親族が亡くなった時には、故人の遺品を整理して処分する必要があります。
その際、気を付けなければならないのが遺品を処分するタイミングです。
そこでこの記事では、遺品の処分手順やタイミングについて解説します。
この機会に、業者に依頼する際の注意点についても知っておきましょう。
後半では遺品の形見分けはいつするかについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 遺品とは
- 遺品を処分するタイミング
- 遺品を処分するメリット
- 遺品処分を自分でする手順
- 遺品処分を業者に依頼する場合
- 遺品を処分するときの注意点
- 遺品の形見分けはいつする?
- 遺品処分のまとめ
- 遺品整理・出張買取・不用品回収のメイキングワークス
遺品とは
遺品とは、故人が生前に所有していたもの全般のことです。
これには故人の身の回りのものだけでなく、日常生活で使っていた家財や故人が残した遺産も含まれます。
遺品には、遺族にとって必要なものや、形見として取っておくもの、不要なものなど様々なものが混ざっています。
そのため遺品を整理し、取っておくものと処分するものに分ける必要があるのです。
故人が一人暮らしであった場合は家財一式も遺品となるため、不要な場合は処分しなければなりません。
遺品を処分するタイミング
遺品の処分は人生で何度も行うわけではないため、そのタイミングや手順について分からない方も多いでしょう。
処分のタイミングは、故人の住んでいた家に利用制限があるかどうかによって変わってきます。
以下で、利用制限がある場合とない場合に分けて、最適なタイミングについて詳しく説明していきましょう。
賃貸や施設など利用制限がある場合
故人が賃貸住宅や施設などに入居していた場合、退去までの期間が決まっている場合がほとんどです。
そういった場合には、退去日までに物件を原状復帰して明け渡さなければなりません。
そのため遺品は、その期日までに全て他の場所に移すか、処分する必要があります。
利用制限がある場合、故人が亡くなった月か翌月の末まで契約しておき、それまでに遺品の処分を終わらせることがほとんどです。
また、仏教では四十九日までは故人の魂が現世にあると考えられているため、それまでは家をそのまま残しておくこともあります。
どちらにせよ、利用制限がある場合はできるだけ早く遺品を処分する必要があるでしょう。
持ち家などの利用制限がない場合
故人の住む家が持ち家であった場合には利用制限がないため、すぐに遺品を処分する必要はありません。
持ち家で遺品の処分を始めるタイミングとして多いのが、以下の3つになります。
- 四十九日・百か日などの法要がある時
- 死亡後の手続きが全て終わった時
- 精神的に落ち着いた時
重要な法要がある時には親族が集まるため、遺品を処分するのに最適です。
遺品の処分は自分だけで行うと、処分した後でトラブルになる可能性があります。
そのため、できるだけ親族が集まった時に行うのが良いでしょう。
また、死亡後の手続きが終わってから遺品の処分に取り掛かる方も多いです。
遺産相続・保険・年金・住民票・相続税など、故人の死後にしなければならない手続きは多岐にわたります。
期限が近いものも多いため、必要な手続きが全て完了し一段落してから、遺品の処分に取り掛かるのも良いでしょう。
また、遺族の心の傷が癒えたタイミングで遺品の処分を始めることも多くあります。
故人が突然亡くなった場合は特に遺族の動揺が大きく、遺品の処分になかなか手が付かないこともあるでしょう。
そうした方は、急がずに気持ちが落ち着いてから始めても大丈夫です。
利用制限がない場合には、遺品の処分をいつまでにしなければいけないというリミットはありません。
そのためいつから始めても問題ありませんが、ある程度決めておかなければ先延ばしにしてしまう可能性があります。
上記のタイミングを参考にして、いつ頃から始めるか事前に決めておくのが良いでしょう。
遺品を処分するメリット
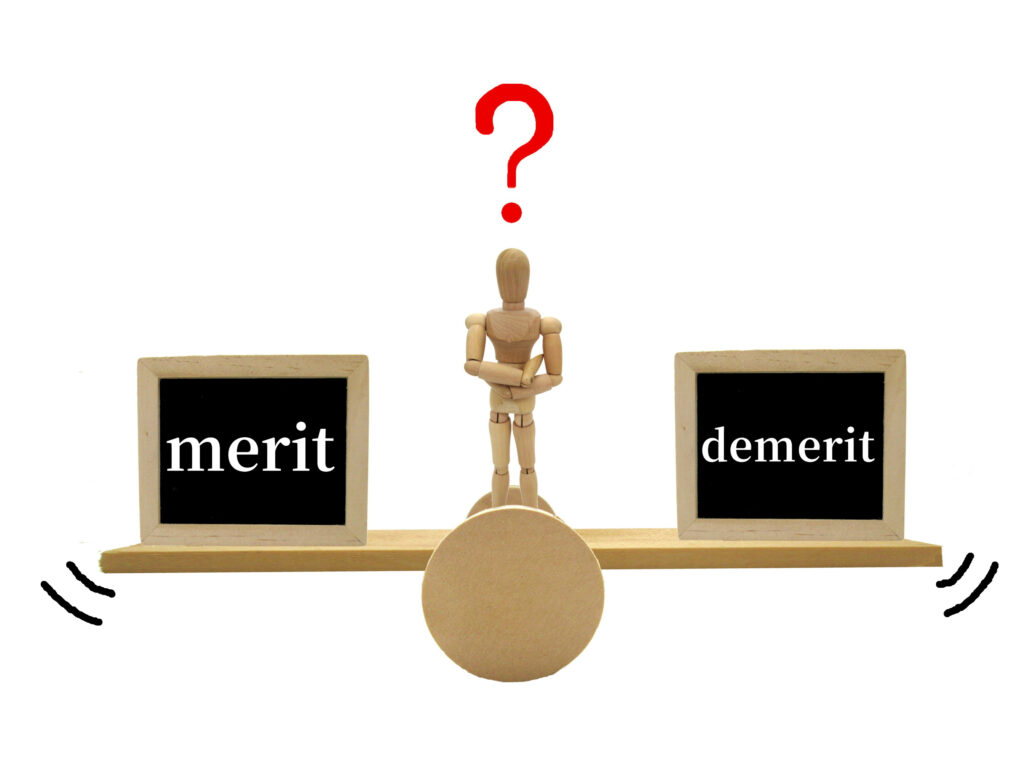
次は、遺品を処分することによって得られるメリットを解説していきます。
遺品の処分を進めていくためにも、どういったメリットがあるか知っておきましょう。
心の整理がつく
遺品を処分するのは心身にかかるストレスが大きく、故人が亡くなってすぐはなかなか取り掛かるのが難しい方も多いでしょう。
しかし、遺品を処分することで心の整理をするきっかけにもなります。
遺品を処分することは、ただ故人の遺品を整理するだけでなく、自分自身と向き合うことにも繋がるのです。
もし心の傷が癒えてきたと思ったら、遺品を処分することでより心の整理をしやすくなるでしょう。
精神的なストレスが減る
遺品には、故人が今まで大切に使ってきたものも含まれています。
そのため、遺品を処分することに対して罪悪感を抱く方も多いでしょう。
遺品の処分が完了するまで、遺品を処分することに関して漠然と考え続けていると精神的なストレスが持続してしまいます。
遺品に関するストレスが大きいと感じる方は、思い切って処分することでそうした精神的ストレスから解放されることもあるのです。
遺品の処分についてストレスを感じているのであれば、思い切って処分することをおすすめします。
遺品処分を自分でする手順

次は、遺品処分を自分で行う際の手順について解説していきます。
以下の手順で行うことで、スムーズに遺品処分を進められるでしょう。
作業しやすい服装を準備する
遺品処分に取り掛かる前に、作業着などの汚れてもいい動きやすい服を用意しましょう。
また、ホコリを吸い込まないようにマスクの準備や、手に怪我をしないように軍手の用意もします。
意図せず物を踏んで怪我しないよう、スリッパを履いて足を守ることも大切です。
また、段ボール・ガムテープ・ゴミ袋・カッターなど、作業を進めるのに必要な道具も忘れず用意しておきましょう。
遺品を仕分けする
準備ができたら、遺品を仕分けしていきます。
その際、まずは故人の家に遺言書がないかチェックしましょう。
遺言書には、相続などに関する重要な情報が記載されている可能性があります。
そのため、遺品を仕分けする前に遺言書の有無を確認する必要があるのです。
遺言書を見つけたら、検認と呼ばれる手続きが必要となるため開封せずにそのまま取っておきましょう。
検認の前に遺言書を開封してしまうと、罰金が課せられる可能性もあるため注意してください。
遺言書の捜索が終わったら、遺品を以下の3種類に仕分けしていきましょう。
- 貴重品・個人情報に関する書類
- リサイクルなど、再利用できるもの
- 処分するもの
この3種類に大まかに分けることで、遺品の仕分けが手際良く進められます。
貴重品や個人情報の書類を探す
まずは、貴重品・個人情報の書類を探します。
貴重品には、以下のものが含まれます。
- 現金
- 通帳
- クレジットカード
- 印鑑
- 不動産に関する書類
- 有価証券
- 借用書
- 生命保険証書
- 遺書
- 宝石・絵画・貴金属類
また、個人情報に関する書類には、以下のものが分類されます。
- パスポート
- 年金手帳
- 健康保険証
- 免許証
これらは、故人が亡くなった後に行う遺産相続や、年金・保険などの手続きに必要となる書類です。
誤って処分してしまうと手続きが行えなくなってしまう可能性があります。
遺品の仕分けを行う際には、最初に必ず探し出して誤って処分しないように別の場所へ保管しておきましょう。
再利用できるものと処分するものに分ける
貴重品・個人情報に関する書類を見つけたら、次は再利用可能なものと処分するものに分けていきましょう。
再利用できるものには家電・家具・衣類などの所有物と、素材が金属・紙・布・プラスチックなどのものが含まれます。
上記の内、まだ使える家電・家具・衣類などの物は親族で形見分けしましょう。
形見分けで余った不要なものに関しては、リサイクルショップなどに売却することも可能です。
また、素材が金属類のものなどは、専門業者にお願いすれば買い取ってもらえる可能性があります。
買い取ってもらうのが難しそうなものに関しては、まとめて処分しましょう。
処分するものは、指定された日にゴミ集積所に出したり粗大ゴミとして回収してもらいましょう。
家電やゴミとして出せないものは、専門業者に依頼して引き取ってもらいます。
また、上記の処分をそれぞれ個別に行うのが大変な場合には、不用品業者に全てまとめて引き取ってもらうことも可能です。
自分にとって最適な方法を選択し、遺品の処分を進めましょう。
処分するもので思い入れがあるものは供養してもらう
処分するものの中で思い入れがあるものに関しては、供養してもらうことをおすすめします。
遺品の供養は、寺院や神社に直接依頼することが可能です。
供養の方法は、自宅まで来てもらい供養する現場供養と、他の方の遺品と一緒に供養する合同供養の2種類です。
寺院・神社の中には、郵送で供養したい遺品を受け付けてくれるところもあります。
自分にとって最適と思える供養方法を選び、遺品の供養を依頼しましょう。
遺品処分を業者に依頼する場合
遺品処分は、専門業者に依頼することも可能です。
ここからは、遺品処分を業者に依頼する場合のサービスの流れやメリットについて解説していきます。
大阪で遺品整理を代行!大阪以外の方も遺品整理が必要な方はご相談ください。お力になります!
サービスの流れ
遺品処分を業者に依頼する場合はまず業者へ問い合わせ、現地調査のスケジュールを押さえましょう。
現地調査では部屋の間取りや大きさ、作業にかかる時間、探す必要のあるものなどについて確認されます。
そして、その情報を基に見積もりが出されるため、見積もりと条件面で合意することで契約完了です。
契約すると業者が作業日に自宅に来てくれるため、遺品の処分作業を代行してもらいましょう。
業者に依頼するメリット
ここからは、業者に依頼することによって得られるメリットを解説していきます。
以下のメリットが魅力的に感じられる方は、業者へ依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
遺品の供養を無料でしてくれる業者もある
業者の中には、遺品を無料で合同供養してくれる業者もあります。
遺品を処分することに対して抵抗を感じる方でも、供養してくれる業者であれば依頼しやすくなるでしょう。
こうしたサービスは、遺族が遺品を処分することに対して感じる精神的ストレスの軽減にも繋がります。
個別供養をしてくれる業者もある
合同供養ではなく、自宅で個別供養の形式で行いたい場合は対応している業者を選べば家に僧侶を手配してくれます。
業者によっては、宗派に合わせた供養の仕方をしてくれたりスケジュールを調整してくれたりします。
形見分けや遺品整理をしてもらえる
遺品の形見分けを親族だけで行うと、誤って処分してしまったり誰が譲り受けるかでトラブルに発展したりする可能性があります。
そんな時、専門的な知識を有する業者に相談に乗ってもらえれば、親族全員が円満に形見分けをできるかもしれません。
また遺品整理も、親族だけで行う場合と比較して専門業者であれば、的確に仕分けしてくれることでしょう。
処分方法に迷った場合も気軽に相談できるため、業者に依頼することで親族の負担が軽減できます。
短期間で処分することができる
専門業者は遺品のプロフェッショナルであるため、仕分けや処分に関しても豊富な知識を有しています。
そのため、業者に依頼すれば短期間で遺品処分を終わらせることが可能です。
遺族だけで遺品処分を行うと処分方法が分からず手間取ることもありますが、業者に依頼すればそうした心配もありません。
遺品を買い取ってくれる業者もある
専門業者の中には、遺品の買い取りなどの対応をしてくれる業者もいます。
そのため、買取可能な業者に依頼すれば遺品の仕分けが終わった後、再度買取業者に依頼する必要がなくなります。
遺品を売却したい場合には、買取にも対応してくれる業者を選ぶと良いでしょう。
良い業者の選び方
良い業者を見分けたい場合は、業者が遺品整理士認定協会が認定する遺品整理士資格を所持しているかどうかを確認しましょう。
遺品整理には、必ずこの資格の取得が必要な訳ではありません。
しかし、資格を取得するには認定試験に合格する必要があります。
そのためこの資格を取得していることが、専門知識を有する業者であることの証明になるのです。
この資格を取得している業者であれば、安心して遺品処分を任せられることでしょう。
また、良い業者の場合にはインターネット上でも、ユーザーの高評価の口コミが見つかるはずです。
遺品業者の情報をまとめているサイトなどを参考にし、高評価の口コミが多い業者を選ぶと良いでしょう。
費用の相場
遺品処分の費用は、部屋の広さによって変わってきます。
費用の相場は以下の通りです。
- 1R〜1DK:3万〜10万円
- 1LDK〜2LDK:8万〜20万円
- 2LDK〜3DK:12万〜25万円
- 3LDK〜4DK:17万〜30万円
また、戸建ての場合であれば30万〜80万円が費用相場になります。
部屋が汚かったり別途特殊清掃が必要だったりする場合には、一般的に上記の相場より高額になります。
業者にかかる費用は、部屋の広さと部屋の状況が大きく関係することを覚えておきましょう。
所要時間の目安
遺品処分には想像以上に時間がかかります。
所要時間の目安は以下の通りです。
- 1R~1DK:1~4時間
- 1LDK~2LDK:3~8時間
- 2LDK~3DK:4~10時間
- 3LDK~4DK:6~12時間
遺品の処分品を活用する方法
遺品の中には故人が生前よく使っていた、思い出深い品物も含まれています。
処分品としてただ捨てるのではなく、何か活用できる方法はないか考えてみましょう。
リメイクする
遺品をそのまま残すのではなく、リメイクすれば形を変えて活用することが可能です。
例えば、ネット上には故人の着ていた服やバッグなどを、ぬいぐるみにリメイクしてくれるサービスもあります。
また、自分でも故人の着物をバッグにリメイクすることは可能です。
家具であれば、解体して別の物に作り変えるといった方法もあります。
思い出深く、捨てるのがもったいないと感じるものがあれば、リメイクも視野に入れてみましょう。
リサイクルショップで買い取ってもらう
ブランド物のバッグや服などは、リサイクルショップに売却すれば高値で買い取ってもらえる可能性があります。
最近では、ネット上から宅配・出張買取を依頼できる業者も増えているため利用しやすくなっています。
またネットオークションやフリマサイトを利用すれば、必要としている方に直接品物を売却することが可能です。
リサイクルショップで買い取ってもらえなかった物でも、それを必要とする人に購入してもらえる場合があります。
遺品を売却することに抵抗のない方は、積極的に活用すると良いでしょう。
寄付する
遺品を不要だから処分しようと考えている方は、必要としている方への寄付も視野に入れましょう。
例えば、衣類や書籍はNPO法人が窓口となって必要な方に届けてくれる場合が多いです。
故人の思い出が詰まった品物をすぐに処分してしまうのではなく、新しい活躍の場を見つけてあげることも考えてみましょう。
遺品を処分するときの注意点

遺品を処分する時には、注意すべきことがあるためご紹介します。
スムーズに処分を進めるためにも、以下の点に気をつけましょう。
親族間でのトラブル
相続人が自分だけでない場合には、相続人全員で遺品の仕分けや処分を行いましょう。
自分だけで遺品を処分してしまうと、形見分けや財産に関してトラブルに発展する可能性があります。
未然にトラブルを防ぐためにも、遺品の処分は相続人全員が立ち合って行いましょう。
手続き書類がある場合は早めに整理する
故人の死後必要となる様々な手続きには期限があります。
年金や保険、相続に関する書類は、期限が過ぎてしまう前にできるだけ早く遺品から探し出し、手続きを進めましょう。
騒音に気を付ける
遺品を仕分けしたり処分したりするときには、思っている以上に騒音が出てしまいます。
そのため、事前に近隣の住宅に事情を説明しておきましょう。
そうすることで騒音トラブルに発展することを避けられます。
また、遅い時間に遺品処分をするのは避けましょう。
予想以上に時間がかかる
遺品を処分するのには、遺品を仕分けたり外に運び出したりといった作業が必要となります。
また、故人の遺品と向き合う精神的なストレスや、運び出す際の肉体的なストレスを感じることが多いです。
親族だけで進める場合、スケジュール通りにいかない可能性もあることを覚えておきましょう。
誤って処分することがある
遺品には、貴金属類や相続に必要な書類なども混ざっています。
そのため、誤って処分すると取り返しのつかないことになる可能性があります。
複数人で作業する時には事前に何を取っておくかなど、ルール化しておくと良いでしょう。
また、判断に迷うものが出てきた場合は取っておいて後から判断することで、誤って処分する可能性がなくなります。
遺品の形見分けはいつする?
次は、遺品の形見分けを行うタイミングについて解説しましょう。
併せて、形見分けの注意点やマナーについてもご紹介します。
遺品の形見分けを行う時期
形見分けを行うのに最適な時期は、信仰する宗教によって異なります。
仏教の場合は、四十九日法要が終わったタイミングがおすすめです。
忌中は故人の死を悼む時期であるため、形見分けは避けた方が無難でしょう。
神道の場合は五十日祭が終わった後、キリスト教の場合は1ヶ月後の命日に行われるミサの後がおすすめです。
上記を参考に、遺品の形見分けをする時期を考えましょう。
遺品の形見分けにおける注意点とマナー
ここからは遺品を形見分けする際の注意点やマナーをご紹介します。
以下の点を守ることで、トラブルを避けて形見分けができるでしょう。
目上の人には贈らない
形見分けは親から子、上司から部下へと渡すのが基本で、目下の人に渡すのがマナーとなっています。
そのため、自分よりも目上の人に形見分けすることはマナー違反となる可能性があるため注意しましょう。
目上の人に形見分けするのは、本人から形見分けして欲しいという要望を受けた場合のみにするのが無難です。
遺品を包装しない
遺品の形見分けはプレゼントではないため、包装して渡すのは避けましょう。
もし包装したい場合には、白い半紙に包むだけにしておきます。
ただし、遺品が汚れたままの状態で渡すことは避けましょう。
遺品を渡す時には、事前に綺麗な状態にして渡すのがマナーです。
また、直接渡せない場合には宅配便で送ります。
その際、中身が形見分けの品であることを手紙として添えましょう。
高価なものを渡さない
遺品を渡す際には、その遺品の価値について事前に知っておく必要があります。
高価なものを形見分けとして渡した場合は相続財産扱いとなり、相手に贈与税を課せられる可能性があります。
高価なものを確認せず渡してしまうと、相手とのトラブルに発展する可能性があるため注意しましょう。
遺品処分のまとめ

ここまで遺品を処分するタイミングや、処分の方法などを中心に解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 賃貸などでは退去日までに処分しなければならない
- 持ち家であれば期限がないので、落ち着いてから処分する
- 遺品処分に困った場合は業者への依頼も検討する
- 形見分けのタイミングは忌明け後に行うと良い
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
遺品整理・出張買取・不用品回収のメイキングワークス

遺品整理・出張買取・不用品回収のメイキングワークス、代表の北池と申します。
故人様の思いの詰まった大切なものを整理し、故人様とのお別れをすることで、ご遺族様の心の整理にもつながる大事な役割を誠心誠意果させて頂きます。
弊社の特徴は整理・処分をするだけではなくリユース、リサイクルも含めて買取をすることが可能なことです。
ご遺族様の金銭面に関しても、少しでもご負担を減らすことで非常に好評を頂いております。
また、リユース品に関しては国内のみならず、海外貿易を通じて必要とされている諸外国へ寄付をさせて頂くSDGsの取り組みも推進しております。
スタッフとの距離が近いのでどんなお困り事も親身になってご相談に乗ります。
お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。







