お葬式
火葬の歴史はいつから?日本の火葬の歴史や火葬の法律、火葬に必要な手続きも紹介
更新日:2024.01.24 公開日:2022.01.01

記事のポイントを先取り!
- 火葬は死後24時間経過してから
- 火葬には火葬許可証が必要
- 近年は火葬のみの直葬も増加
現在の日本の埋葬方法は火葬が一般的ですが、かつては土葬が主流でした。
いつから火葬が日本で主流になったのか、また、火葬の法律では逝去後にいつから火葬が可能になるかをご存じでしょうか。
この記事では、土葬が一般的だった時代から、現代で火葬が広がっていった経緯や火葬の法律をご紹介します。
火葬のみのお葬式、直葬(火葬式)の流れにも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 火葬の歴史はいつから?
- なぜ日本で火葬が行われるのか?
- 火葬はいつからできる?
- 死産児の火葬はいつから?
- 火葬の定義
- 火葬の意味
- 火葬までの間の故人の安置先の手配
- 火葬の流れ
- 火葬にかかる時間
- 日本の「墓地、埋葬等に関する法律」詳細解説
- 火葬式の際のマナー
- 火葬に必要な手続き
- 火葬のみ行う直葬について
- よくある質問
- 火葬はいつからかまとめ
火葬の歴史はいつから?

現在の日本の埋葬方法は火葬が主流で、割合は99.99%に及んでいます。
しかし、かつての日本では火葬よりも土葬が一般的でした。
ここからは、いつから火葬が日本で選ばれるようになったのかご紹介します。
火葬の古代起源
日本での火葬の歴史は古墳時代後期、6世紀に遡ります。
この時期のカマド塚古墳群には火葬の痕跡があり、これが日本での火葬の最初の形跡とされています。
さらに、法相宗の開祖である道昭が700年に火葬されたという記録が「日本書紀」に残されており、これが文献に記録された最初の火葬事例です。
平安時代から鎌倉時代にかけての発展
平安時代になると、火葬は皇族や貴族、僧侶間で広く行われるようになりました。
この時代には、特別な火葬の場所が設けられ、独自の火葬方法が発展しました。
鎌倉時代に入ると、浄土宗や日蓮宗など新興宗教の影響で、火葬は庶民の間にも広まりました。
この時代の火葬は、主に野焼きの形式をとっていました。
江戸時代の火葬場設置とその変遷
江戸時代になると、寺院や墓地に火葬場が設けられ、火葬はさらに広範囲に広まりました。
特に都市部では火葬が一般的になり、火葬場は小屋のような簡易な構造物であったものの、徐々に現代の火葬炉に近い形式に進化していきました。
明治時代の火葬規制と近代化
明治時代に入ると、政府は当初火葬を禁止しましたが、間もなく撤廃され、公衆衛生の観点から火葬が奨励されるようになりました。
この時代に、レンガで作られた最初の火葬炉が登場し、火葬の方法は急速に近代化しました。
現代の火葬率と技術の進歩
現代では、火葬は日本の葬儀文化において中心的な位置を占めるようになりました。
特に都市部では土葬がほぼ行われず、火葬率はほぼ100%に達しています。
火葬炉の技術は進歩し、環境に配慮した無害化や無臭化などが実現されています。
また、都市部では葬斎場や斎場と呼ばれる、通夜や告別式も行える施設が火葬場に併設されるようになり、葬儀の一連の流れが一か所で行えるようになっています。
世界の火葬事情
現在の日本の火葬率は99.99%ですが、世界的にみると火葬は一般的ではありません。
世界的に信者が最も多いキリスト教や、2番目に信者が多いイスラム教では、火葬が原則禁止されています。
そのため土葬が主流です。
特に、教義への執着が強い保守系のカトリックが多い南ヨーロッパ(ギリシャ・イタリアなど)では、現在でも土葬が一般的です。
しかし教義への執着が緩い進歩系のプロテスタントでは、徐々に火葬も増えてきています。
一方インドでは、宗教的な理由などから遺体を重要視しないため、遺体は火葬して川などに流すのが古くからの慣習です。
このように埋葬方法は国や地域の慣習などで異なり、土葬や火葬だけでなく水葬、鳥葬などを行う国もあります。
なぜ日本で火葬が行われるのか?
日本における火葬の普及にはいくつかの重要な理由があります。
まず、日本は伝統的に仏教の影響が強い国であり、仏教では火葬が一般的な儀式とされています。
これが、日本で火葬が広く行われる文化的背景となっています。
加えて、日本の地理的な特性上、土地が限られているため、土葬よりも土地を節約できる火葬が選ばれることが多いです。
さらに、公衆衛生の観点からも、伝染病の拡散を防ぐために火葬が推奨されています。
これらの理由により、日本は世界でも火葬が非常に高い割合で行われる国となっています。
他国でも火葬の文化が広まりつつある中で、日本の火葬率の高さは特筆すべき点です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬はいつからできる?
日本では、逝去後すぐに火葬を行うことはできません。
これは火葬場の空き状況などが理由ではなく「墓地・埋葬等に関する法律」で禁じられているためです。
死後24時間以内はできない
日本の「墓地・埋葬等に関する法律」では、原則として死後24時間以上経過してからでないと火葬してはならないと定められています。
「墓地・埋葬等に関する法律」が制定された昭和23年時点では、日本の医療は未発達でした。
死亡判定も今ほど正確ではなかったため、仮死状態で火葬を行うことを防ぐ目的で制定されたのです。
違反した際の罰則があるわけではありませんが、死後すぐに火葬は行わないようにしましょう。
例外も存在する
日本では、基本的に死後24時間以内の火葬はできませんが、例外的に24時間以内の火葬が認められるケースもあります。
妊娠7カ月未満の死産の場合は蘇生率が低いため、死後24時間以内でも火葬許可を受けることが可能です。
また、感染症で亡くなった方についても、感染拡大を防ぐために24時間以内の火葬が許されます。
ただし、上記のようなケースでも24時間以内の火葬が義務付けられているわけではありません。
死産児の火葬はいつから?
死産とは母胎内で胎児が死亡した状態で出産することです。
死産により亡くなった胎児を死産児と呼びます。
胎児が母胎内で亡くなった場合、胎児の週数や経緯などにより、流産・死産・中絶と呼称が変わります。
死産時の場合、火葬はいつから行うことが可能なのかケース別に解説します。
妊娠12週〜21週
妊娠12週〜22週未満で胎児が母胎内で亡くなったケースを流産と呼びます。
妊娠12週以降の胎児が亡くなった場合、死産を診断した病院で死産証書とともに渡される死産届を7日以内に提出する必要があります。
死産届の提出先は、居住する自治体または分娩した病院がある市町村などの自治体役場の窓口です。
なお、妊娠12週以降の死産児は、火葬または埋葬する必要があります。
妊娠22週以降
妊娠22週以降の死産の場合も、基本的には22週未満の場合と同様に死産届を提出する必要があります。しかし妊娠22週以降の胎児の死産は、母体外での生存の可能性も考えられる時期です。
そのため、死産児の分娩か新生児の早産かによって対応が分かれます。
分娩時に既に亡くなっていた場合は、死産時の分娩と判断され、死産届を提出します。
出産後に赤ちゃんがわずかな時間でも生存していた場合は、死産届ではなく出生届と死亡届の提出が必要です。
また、死産児の分娩と新生児の早産のいずれの場合も、埋葬または火葬が必要となります。
24週以降の死産の場合は、原則通り24時間経過後でなければ火葬を行うことはできません。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬の定義
火葬は遺体を処理する方法の一つで、火葬炉に納められた遺体を強い熱で焼却し遺骨・遺灰にするものです。
火葬の過程は火葬場・火葬室内で行われ、火葬終了後に遺骨を骨壷に納める(収骨)のが一般的な流れになっています。
収骨の際は、遺族が骨上げ箸と呼ばれる箸を使って遺骨を拾い上げることが多いです。
火葬の意味
火葬は、仏教の伝統と深く結びついた文化的慣習であり、遺体を焼いて灰にする行為を「荼毘に付す」と称します。
仏教では、魂は肉体に留まるのではなく、死後には新たな肉体へと輪廻転生するとされています。
この考え方はインドの伝統的な火葬の習慣にも影響を与えており、遺体を完全に灰にして川に流すという文化が存在します。
このように、火葬は単なる遺体の処理方法ではなく、宗教的な意味合いを持つ文化的行為として広く認識されています。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬までの間の故人の安置先の手配
火葬までの故人の安置については、直葬の場合でも故人の死後24時間以上経過する必要があり、火葬場の予約状況によってはさらに時間がかかることもあります。
その間、故人を適切に保管する必要があります。
ここでは、故人を自宅で保管できない場合の対処法、自宅安置時に必要な処置について説明します。
自宅以外での安置方法
故人を病院や自宅以外で安置する場合、葬儀社や遺体安置専門の施設を選ぶことが一般的です。
安置場所の選択は、遺族の住居の場所や利用可能なサービスによって異なります。
ただし、これらの施設を利用する場合は、追加の費用がかかることを覚えておきましょう。
自宅での安置に必要な処置
自宅で遺体を安置する場合、ドライアイスや冷却装置を使って遺体の状態を維持することが重要です。
遺体の保存状態は、周囲の気温や安置期間によって異なります。
葬儀社によっては、高度な冷却システムを提供している場合もあり、そのようなシステムは遺体の凍結を防ぎつつ、適切な状態を保つのに役立ちます。
長期間の安置が必要な場合
火葬までに時間がかかる場合、湯灌(身体を清める儀式)やエンバーミング(防腐処理)といった方法が選択肢となります。
これらの方法は遺体の腐敗を遅らせ、見た目の変化を最小限に抑えるのに効果的です。
湯灌とエンバーミングの料金は、提供するサービスによって大きく異なりますが、一般的に湯灌は数万円、エンバーミングは数十万円の範囲内です。
スポンサーリンク火葬の流れ

通夜・葬儀を行う場合は、葬儀終了時点で死後24時間を超えるケースがほとんどです。
そのため、基本的に葬儀場から出棺された遺体はそのまま火葬場に搬送されます。
葬儀場から出棺されるケースでの火葬までの一般的な流れを以下にご紹介します。
出棺・火葬場への遺体搬送
葬儀場での喪主による出棺の挨拶ののち、遺族や親族のみが火葬場に同行するのが一般的です。
火葬場の受付で火葬許可証を提出すると、火葬終了後に火葬済みの印が押されて返却されます。
この書類が、お墓や永代供養墓・納骨堂などに納骨する際に必要な埋葬許可証です。
炉前での納めの式
火葬場での納めの式は、日本の葬儀の伝統的な一部として重要な役割を果たしています。
まず、棺は告別室や炉前に安置され、式が始まります。
この際、僧侶による読経が行われ、その後に喪主、遺族、親族が順に焼香をします。
全員の焼香が終わった後、一同が合掌して納めの式は終了します。
納めの式が終わると、故人は火葬炉前に運ばれ、参列者は故人との最後のお別れをします。その後、遺体は炉に納められ、火葬が行われます。
火葬の時間は故人の年齢や体型により異なりますが、一般的には1~2時間ほどかかります。
火葬が行われている間、参列者は火葬場の待合室や葬儀場に戻り、待機します。
火葬終了後は係員の指示に従い、故人と縁の深かった方から順に二人一組で遺骨を骨壷に納めます。
これにより、故人への最後の敬意が表され、遺族にとって大切な儀式の一環となります。
収骨(骨上げ)
お骨を拾う時は骨上げ箸(御骨箸)と呼ばれる左右それぞれが竹と白木でつくられた箸を用います。
渡し箸と言って、箸を遺族同士で渡しながら収骨することで故人が無事に三途の川を渡れるよう手助けをする意味があります。
関東地方では遺骨をすべて収骨することが多いですが、関西地方などでは遺骨の一部のみを収骨するのが一般的です。
火葬が終了するまでの時間は多少前後する場合もありますが、おおむね1時間ほどです。
納めの式や参列者による収骨の時間を加味すると、全体では2時間ほどかかります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬にかかる時間
火葬のプロセスは、故人が亡くなってから最低24時間後に始まるとされており、この間には必要な書類の提出や許可証の取得など、多くの手続きが必要です。
日本では、火葬炉の種類によって火葬にかかる時間が異なります。
以下に、現代の火葬炉の主要なタイプとそれぞれにかかる時間について詳しく説明します。
ロストル式火葬炉
ロストル式は、火葬炉内に金属棒を格子状に配置し、その上に棺を置いて焼却する方法です。
この設計により、空気の流れが改善され、効率的な燃焼が可能になります。
ロストル式の火葬場では、火葬に35〜60分程度かかります。
また、この方式では、1日に処理できる火葬の回数が多いため、人口密集地域でよく見られます。
台車式火葬炉
台車式火葬炉では、棺を車輪付きの台車に乗せて炉内に運び込みます。
日本では最も一般的なタイプで、炉内で棺を安定させるための耐火性の高い素材で作られた台車が使用されます。
しかし、ロストル式に比べて火葬には60〜120分程度と時間が長くかかるのが特徴です。
これらの火葬炉の違いは、火葬の時間効率だけでなく、使用する施設の立地や利用頻度にも影響を与えます。
それぞれの火葬方法には独自のメリットとデメリットがあり、選択は多くの場合、地域の文化や習慣、さらには個々のニーズによって決定されます。
スポンサーリンク日本の「墓地、埋葬等に関する法律」詳細解説
日本の「墓地、埋葬等に関する法律をご紹介いたします。
法律の制定背景と目的
「墓地、埋葬等に関する法律」は1948年に制定されました。
この法律の第1章「総則」の第1条では、公衆衛生を守りつつ国民の宗教的感情に配慮することを目的としています。
第2条では、法律で使用される主要な用語の定義が示されています。
火葬に関する重点規定
この法律は特に火葬に焦点を当てています。主要用語として「埋葬」「火葬」「改葬」「墳墓」「墓地」「納骨堂」「火葬場」が定義されており、その中でも「火葬」と「火葬場」に関する言及が多く見られます。
法律内で土葬についての明確な規定は少ないものの、自治体による土葬の規制が実際に行われています。
埋葬場所に関する規定
法律の第2章第4条では、埋葬場所について「墓地以外の区域に、埋葬又は焼骨の埋蔵を行ってはならない」と規定しています。
ここでの「墓地」とは、「都道府県知事の許可を受けた区域」と定義されています。
火葬のタイミングに関する規定
第2章第3条では、火葬は「死亡又は死産後から24時間を経過した後でなければ、行ってはならない」と定められています。
これは仮死の可能性を排除するための措置です。
改葬に関する規定
第2章第5条では改葬について規定し、以前に土葬した遺体を別の場所に移動する場合、厚生労働省の規定に従い、市町村長の許可が必要であるとしています。
改葬が許可されると「改葬許可証」が発行されます。
墓地と納骨堂、火葬場の経営規制
法律では、墓地や納骨堂、火葬場の経営に関しても「都道府県知事の許可を受けなければならない」と定めています。
これは、埋葬施設の適正な管理と公衆衛生の維持を確保するための措置です。
以上の規定により、日本では火葬を含む埋葬方法が厳格に規制されており、その実施には多くの法的要件が伴います。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬式の際のマナー
火葬式の際のマナーをご紹介いたします。
服装に関して
男性は通常、黒または濃紺のスーツを着用します。
ワイシャツは清潔な白を選び、ネクタイ、靴、靴下も黒が望ましいです。
派手な装飾品や光沢のあるアクセサリーは避け、結婚指輪以外は着用しないのが一般的です。
女性の場合、黒や濃紺のスーツやワンピースが適しています。
靴は黒のパンプス、ストッキングも黒を選びます。ヘアアクセサリーやジュエリーは控えめにし、派手なものは避けます。
質素な真珠のネックレスは許容されますが、毛皮や動物革のバッグは避けるべきです。
同行者
基本的に火葬場へは喪主、遺族、親族、故人と親交の深かった友人や知人のみが同行します。
もし同行したい場合は、事前に喪主に確認し、了承を得ることが必要です。
火葬中の過ごし方
火葬が行われる間、参列者は待合室や葬儀場で静かに待機します。
葬儀社が提供する軽食やお茶をいただくことができますが、重い食事や飲酒は控えるべきです。
精進落としの慣習がある地域もありますが、この場合も飲酒は控えめにし、お骨上げに備えることが重要です。
お骨上げ
火葬後、遺骨を骨壷に納める儀式があります。
この際、火葬場の担当者から説明を受け、その指示に従います。
お骨上げは故人との最後の別れの儀式であり、故人と縁の深い人から始めるのが一般的です。
地域や宗派によって異なる場合があるため、担当者の説明に注意を払うことが大切です。
これらのマナーを守ることで、故人への敬意を表し、適切にお別れをすることができます。
火葬式には故人への最後の敬意を示す重要な機会が含まれており、それぞれの行動が大切な意味を持っています。
スポンサーリンク火葬に必要な手続き
火葬を行うためには、死亡届や死亡診断書とともに埋葬・火葬許可証申請書を提出して、火葬許可証を取得する必要があります。
火葬許可証
火葬許可証は、火葬場で提出を求められますので、必ず用意して行く必要があります。
埋葬・火葬許可証申請書は、故人の死亡地や本籍地、届出人の住民登録がある場所のいずれかの自治体に提出します。
自治体役場の窓口などで埋葬・火葬許可証申請書を受け取ったら、必要事項を記入して提出しましょう。
埋葬・火葬許可証申請書が受理されると、火葬許可証が発行されます。
死亡届
人が亡くなった場合、死亡を知った日から7日以内(国外の場合は3カ月以内)に死亡届と死亡診断書を提出する必要があります。
死亡届を提出する際、ついでに火葬許可証の申請も行えば手続きがスムーズです。
死亡届は代理人が提出することも可能で、葬儀社の担当者が提出してくれるケースもあります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬のみ行う直葬について
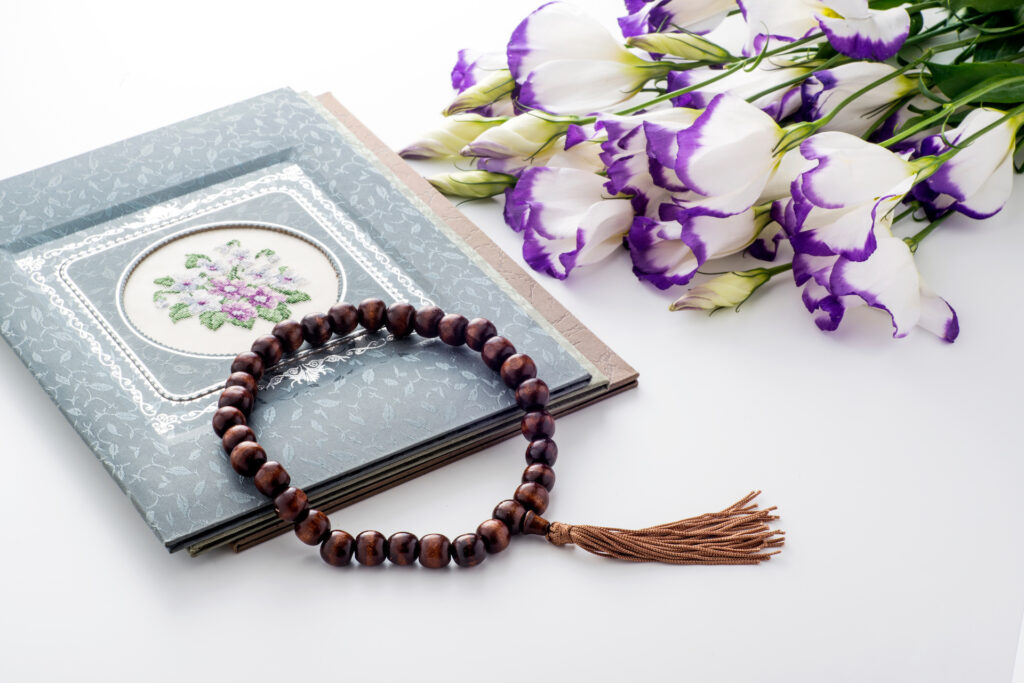
最近では、故人を見送る方法に対する考えもさまざまで、通夜や葬儀を行わない直葬を選択する方も増えています。
直葬とはどのようなものなのか、注意点も含めてご紹介します。
直葬とは
身内に不幸があった場合、通夜・葬儀を行うのが一般的ですが、直葬ではそれらを行いません。
そのため、直葬では火葬のみを行います。
直葬では火葬前に軽く読経などを行うこともできますが、それすら行われないケースも少なくありません。
直葬の注意点
前述した通り、日本では原則として死後24時間経過後でないと火葬はできません。
そのため、直葬を選択した場合も、自宅または葬儀社の安置施設などに遺体を一時的に安置する必要があります。
また、お墓が寺院の霊園にある場合は、相談なしに直葬を行うと納骨を拒否される場合もあります。
菩提寺があって直葬を希望する場合は、あらかじめ菩提寺に相談しておいたほうがよいでしょう。
メリット
直葬では、参列者も家族や近親者のみのケースが多いため、身内だけで故人を見送ることができます。内容も遺体の搬送と火葬のみになるので、故人を見送るための費用を抑えることが可能です。
また、一般的な葬儀では短い期間にさまざまな準備をする必要がありますが、直葬ではほとんど準備が必要ありません。
葬儀の準備は遺族にとって肉体的にも精神的にも大きな負担になりますが、直葬であればそうした負担を軽減できます。
デメリット
直葬では、通夜・葬儀を行わないので、伝統を重んじる方から苦言を呈されるケースもあるようです。直葬を希望する場合は事前に親族などに対して丁寧に説明して、きちんと理解を得ておいたほうが安心です。
また、直葬の場合は安置場所から火葬場に直接向かうので、お別れの時間は短くなります。
火葬炉の前でのお別れの時間も長くは取れないので、慌ただしく終わってしまったと感じる方も少なくありません。
直葬ではゆっくりお別れできないことを心得ておきましょう。
よくある質問
日本で火葬以外の葬儀方法として土葬は可能ですか?
現在日本ではほとんどの葬儀が火葬によって行われていますが、一部地域では土葬が行われている場合もあります。
ただし、土葬を許可している自治体は限られており、土葬を選択することは一般的に容易ではありません。
土葬を行うためには、自治体の規制に従って適切な墓地を見つけ、土葬許可証を取得する必要があります。
感染症のリスクや環境への影響などの理由から、多くの場合火葬が選ばれています。
土葬が根強く残っている地域もありますが、一般的には火葬が主流となっています。
火葬場と斎場の主な違いは何ですか?
火葬場は遺体を火葬するための施設で、火葬炉を設置しています。
公営と民間の火葬場があり、それぞれ火葬費用が異なります。
対して斎場は、通夜や告別式など葬儀全般を行う施設で、民間のホールや会館形式の斎場と公営の斎場が存在します。
公営の斎場には火葬場が併設されていることもあり、地域によっては公営の斎場が多い場所と民間の斎場が多い場所があります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬はいつからかまとめ

ここまで、火葬の歴史や、火葬はいつから可能なのか、火葬の手続きなどの情報を中心にお伝えしました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 火葬は上層階級から徐々に広がった
- 火葬できるのは原則的に死後24時間経過後
- 火葬は出棺・納めの儀式・火葬・収骨の順に行われる
- 火葬を行うためには火葬許可証が必要
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.11.19
近所の人の出棺の見送りへは行くべき?服装の注意点は?
お葬式
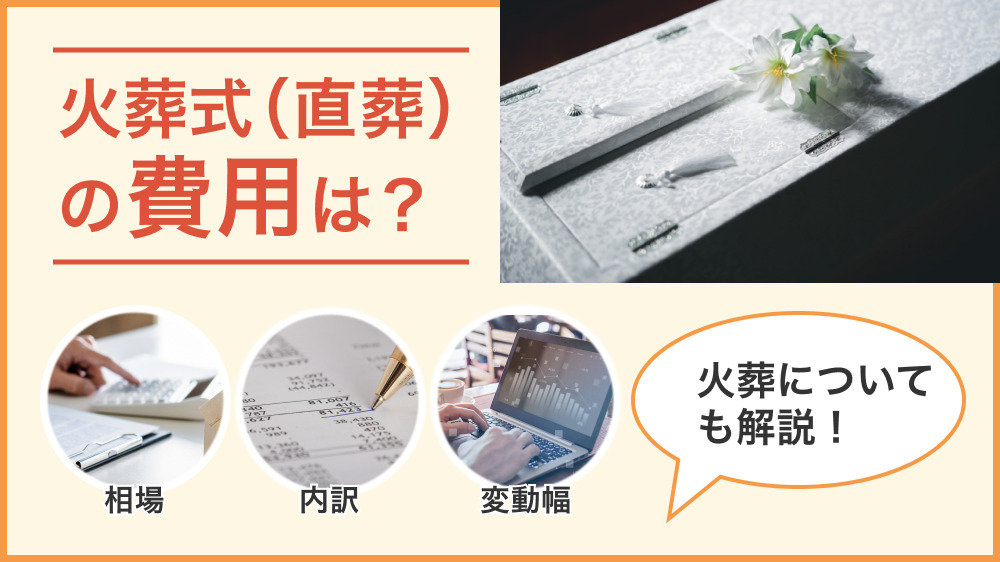
更新日:2025.06.29
葬式なしの火葬費用の相場は?直葬・火葬式の費用を抑える方法についても併せて解説
お葬式

更新日:2024.01.24
火葬の時にピンク色の遺骨があるのはなぜ?収骨拒否についても解説
火葬

更新日:2022.05.11
火葬場で挨拶は必要?喪主の挨拶の注意点と文例を解説
お葬式

更新日:2024.04.02
火葬許可証と埋葬許可証の違いは?紛失した時の再発行の仕方なども紹介
お葬式

更新日:2024.03.13
火葬とは?火葬にかかる費用や時間、流れや仕組みなど解説




