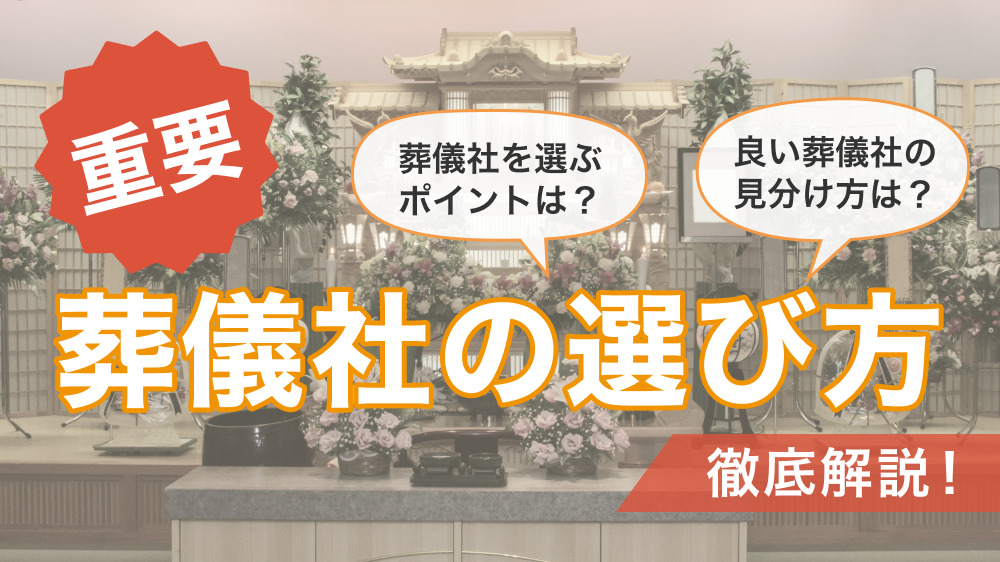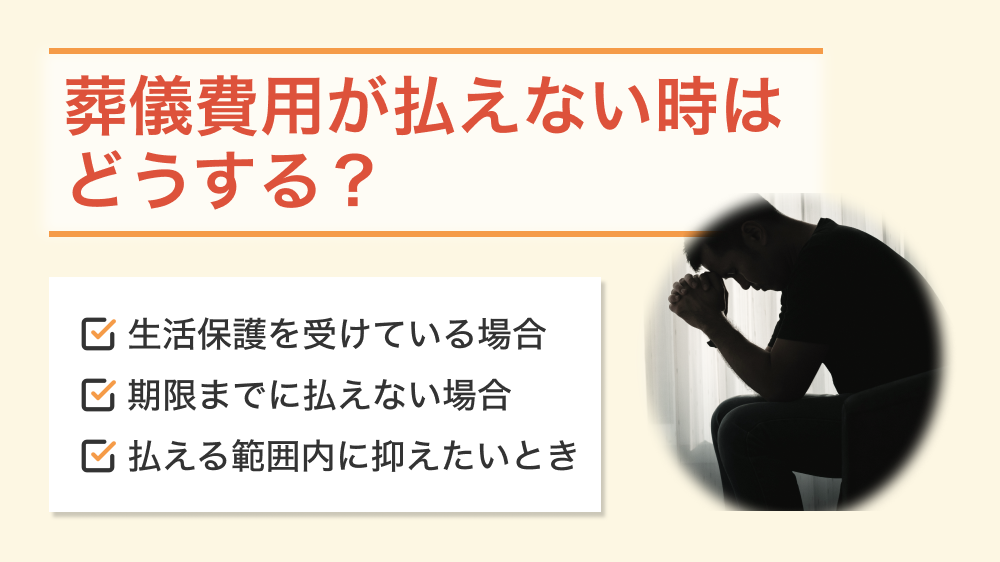死亡後の手続き
突然死した家族への対応は?突然死に救急車は必要?
更新日:2024.01.24 公開日:2022.08.12

記事のポイントを先取り!
- 突然死の判断ができない場合、救急車を呼んでもよい
- 突然死を発見した場合、できるだけ遺体に手を加えない
- 死亡が判断されたら葬儀社へ連絡するのが適切な対応
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
【みんなが選んだお葬式】
突然死で家族が亡くなった場合、その時の対応についてご存じでしょうか。
いざという時に備えて、突然死の対応について知っておくことが大切です。
そこでこの記事では突然死の家族への対応について、解説します。
この機会に突然死で救急車を呼ぶべきかについての事例を見ておきましょう。
後半では突然死の連絡を受けた際の対応についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだ終活では365日24時間葬儀に関するお悩みに対応しています。
葬儀にかかる料金などにも回答しますのでぜひお申し付けください。

都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
突然死とは
突然死とはさまざまな原因によって、健常であるとされる方が短時間のうちに亡くなってしまうことです。
突然死にはWHO(世界保健機構)によって定められた条件が設定されています。
その条件は高所からの転落や交通事故などを除くもので、瞬間的になくなるもしくは原因となった病気を発症し24時間以内で死亡した場合です。
身内や関係者が突然死した場合、家族はどのような対応をとればよいのでしょうか。
資料請求をご希望の方は下記のボタンからお申し込みください。
 スポンサーリンク
スポンサーリンク
突然死した家族への対応
突然死は文字通り、また前述した通り急に訪れるため、家族などの関係者に大きなショックを与えます。
誰にでも訪れる可能性のある突然死ですが、対応方法をあらかじめ把握しておいて冷静に対応したいものです。
不幸にも家族が突然死し、すでに死亡が明らかな場合は死亡診断のために下記の2通りの対応があります。
かかりつけ医がいる場合
突然死した故人にかかりつけ医がいる場合、家族の対応としてはかかりつけ医に連絡します。
かかりつけ医は故人が普段から通っている医者のため、故人の持病などを把握しています。
死因の判断や死亡診断書の作成など、さまざまな要因で適任とされますので、家族の方はかかりつけ医に連絡するのが適切な対応です。
かかりつけ医がいない場合
健常であった故人が突然死し、かかりつけ医がいない場合はご自宅を管轄している警察署に連絡するのが適切な対応です。
警察署に連絡すると、警察官と警察医による調査が行われます。
調査は事件性及び死因の可能性の特定です。
調査後、警察からは死体検案書が発行されます。
事件性の有無を明らかにするためにも、家族としては速やかに警察署へ連絡するという対応が求められます。
資料請求をご希望の方は下記のボタンからお申し込みください。

突然死でも救急車は呼ぶべき?
家族が突然死した場合、救急車は呼ぶべきなのでしょうか。
医療関係者でない一般人であれば、何らかの原因で突然死した方が死んでいるか生きているかを判断するのは難しいでしょう。
また、蘇生できる可能性が残されているかもしれないのにもかかわらず、突然死であると判断するのは適切とは言えません。
そのため明らかに死亡と判断できる場合以外は、家族が救急車を呼ぶことが一部の自治体などで案内されています。
その一方で、明らかに死亡している場合は救急車を呼ばずに警察に連絡することが推奨されています。
その理由は、救急車を呼んでも死亡している場合は救急隊員が警察に連絡するため二度手間になるからです。
さらに、故人にかかりつけ医がいた場合であれば、警察が遺体を調べたり、家族に事件性があるか等の事情聴取されることがないためです。
資料請求をご希望の方は下記のボタンからお申し込みください。
 スポンサーリンク
スポンサーリンク
死亡確認された後の家族の対応
突然死が医者や警察によって確認された後、どのような対応が家族に求められるのでしょうか。
死亡診断書を受け取った後の対応としては、遺体の適切な取扱および安置のために葬儀社に連絡します。
どのような経緯を経てどのような埋葬、供養するにしても専門知識を有した葬儀社と打ち合わせするのが無難です。
故人の遺体を手厚く取り扱う意味でも、速やかにかつ適切に安置所に移送するべきでしょう。
突然死した故人の家族としては葬儀社への連絡が対応として最善と言えます。
また、菩提寺がある場合は、僧侶とも相談して、葬儀の進行を円滑に進めることも大切です。
資料請求をご希望の方は下記のボタンからお申し込みください。

突然死の対応についての注意点
突然死の対応には。前述した手順や手続き以外にも、遺体の取り扱いに注意が必要です。
特に家族は故人の突然死に直面する可能性も高いため事前に把握しておくと、いざというときに慌てずに済むでしょう。
家族が突然死した場合、遺体に触れないことが適切な対応と言えます。
お風呂場で突然死される場合も事例として多くありますが、その場合でも服を着せることは止めておくことが推奨されています。
その理由は警察による事件性の検証において、遺体に触れたり移動させたり衣服を着せたりなどは、不要な疑いの元になるためです。
資料請求をご希望の方は下記のボタンからお申し込みください。

親や家族が亡くなった際の手続き|期限や必要書類、届出先について
スポンサーリンク突然死の知らせを受けた場合の対応
特に大病もせず元気に仕事をしたり生活している方であっても、いつ何が起こるかわからないものです。
その中には突然死のように、事故を除く病症が急な死を招くことも事例としてあることから、誰にでも起きうることが予測できます。
もしもご家族の誰かが突然死やその可能性がある場合、緊急連絡として家族に通知があります。
突然のことに加え、家族の死という大きな出来事は精神的に大きな動揺とショックを受けることでしょう。
しかし大切な家族だからこそ、ご自分で対応すべきことがあります。
そこで突然死の知らせを受けた場合の対応について、基本的な3つの対応をご紹介します。
すぐに連絡先へ向かう
ご家族の方が突然死された場合、主には医療機関や警察関係者からその通知が入ることがほとんどです。
その際には具体的に亡くなったことが告げられないケースもありますが、緊急であることが伝えられるため速やかに連絡先へ向かいましょう。
急いで向かうことになりますが、やむを得ない事情を除き自分で車などを運転して行くことは避けた方が無難です。
気持ちが動揺した状態での運転は危険なため、なるべくタクシーなどを利用するようにしましょう。
持っていくもの
突然死の通知は緊急であるため、何を持っていくべきか冷静な判断ができないことが多いでしょう。
そのため事前に持っていくものを把握しておくことが重要です。
一般的に持っていくものとしては現金や身分証明証、故人の社員証、携帯電話などです。
現金は連絡先までの移動や食費、病院への代金請求に対する支払いで必要になります。
持っていく金額の目安は10万円程度で、それ以上の金額の支払いは後日でも問題ないケースがほとんどです。
病院や警察に身分証明を求められることもあるでしょう。
そのために免許証や保険証も持っていくと、故人との関係性を示せるため話がスムーズです。
また故人の社員証など会社が特定できれば、大きい会社などの総務担当が葬儀を手配してくれるケースもあるようです。
そして親族や関係者に事実を伝えるために、連絡先電話番号が入っている携帯電話は忘れずに持参しましょう。
死因が不明の場合
死因が不明の場合は病院から警察に連絡がいき、その後事情聴取となることを覚えておきましょう。
資料請求をご希望の方は下記のボタンからお申し込みください。

突然死の家族の対応まとめ

ここまで突然死の情報や、家族が行う対応について解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 突然死とは事故以外の病症による、24時間以内の死亡のことを指す
- 突然死した故人にかかりつけ医がいる場合は、まずそこに連絡する
- 突然死の連絡があったら必要なものを持参して、速やかに連絡先へ向かう
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
みんなが選んだ終活では365日24時間葬儀に関するお悩みに対応しています。
葬儀にかかる料金などにも回答しますのでぜひお申し付けください。

都道府県一覧から葬儀社を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀社を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
死亡後の手続きの関連記事
死亡後の手続き

更新日:2024.04.08
死亡診断書は再発行できる?再発行にかかる費用と必要な場面を説明
死亡後の手続き

更新日:2022.11.18
死亡診断書の提出先はどこ?死亡届の書き方についても解説
死亡後の手続き

更新日:2022.04.29
死亡届の書き方を解説。覚えておきたい注意事項とは?
死亡後の手続き

更新日:2022.04.30
警察に遺体が引き取られた場合死亡届はどこでもらえる?流れを解説
死亡後の手続き

更新日:2023.11.21
中絶した場合も死亡届は必要?死産届の手続き方法を解説
死亡後の手続き

更新日:2022.05.01
死亡退職した社員の年末調整の還付金は誰に?計算方法についても解説