終活
自筆証書遺言のメリット・デメリットとは?遺言書の作り方も紹介
更新日:2024.10.18 公開日:2022.05.24

記事のポイントを先取り!
- 自筆証書遺言は遺言者直筆の遺言書/li>
- 自筆証書遺言は自由だが確実性に欠ける/li>
- 書式や用紙などに明確な決まりはない/li>
- 遺言書の種類による優先度はない/li>
遺言書にはいくつかの種類がありますが、自筆証書遺言についてはご存知でしょうか。
自筆証書遺言での遺言書にはどのような利点があるのか知っておきましょう。
そこでこの記事では、自筆証書遺言のメリットやデメリットについて解説します。
この機会に、遺言書の作り方も覚えておきましょう。
後半には自筆証書遺言の有効期限についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 自筆証書遺言とは
- 自筆証書遺言のメリット
- 自筆証書遺言のデメリット
- 遺言書保管制度の導入
- 自筆証書遺言の作り方
- 無効にならないための注意点
- 本人の代わりに弁護士に依頼はできる?
- 公正証書遺言の方が優先度は高い?
- 自筆証書遺言の有効期限は?
- 公正証書遺言のメリット・デメリット
- 自筆証書遺言のメリットとデメリットまとめ
- 遺言書作成に困ったら「Wing堂ヶ芝行政書士事務所」へ
自筆証書遺言とは
遺言書には、基本的に3種類の作成方法があります。
その内のひとつが自筆証書遺言であり、故人が生前に直筆で書いて管理していた遺言書です。
遺言書として必要な情報を記しておけば、死後に見つかった際に遺言書として法的な相続割合などを決めることができます。
もうひとつは公正証書遺言といい、公証人や証人などを交えて作成することで正確な遺言書を作成し、その後の原本を公証役場で管理する遺言書があります。
公正証書遺言は原本を役場が管理する性質上、改ざんや偽造といったトラブルを避ける効果が期待できる作成方法です。
上記以外にも秘密証書遺言というものもあり、遺言書の存在を公的に明らかにしておくための証人は用意するものの、こちらも故人のみが中身を知っている遺言書があります。
遺言書を作成する場合は、手間や費用、その効果の確実性など、いずれの場合でもメリットやデメリットがあるため、目的に合った作成方法を選ぶようにしなければなりません。
自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は生前に直筆で書く遺言書ですが、自筆証書遺言ならではのメリットがあります。
ここでは、他の遺言書と比べて自筆証書遺言にはどのようなメリットがあるのか紹介するので、ぜひ参考にしてください。
好きな時に作成できる
自筆証書遺言は、白紙に直筆で文章を書けばその紙が遺言書になります。
遺言書の内容などを公的に確認する必要はないので、好きなタイミングで作成が可能です。
公正証書遺言や秘密証書遺言では公証人や証人に立ち会ってもらう必要があるため、遺言書を作成するのにどうしても手間がかかります。
難しいことは考えずに遺言を残したい場合は、自筆証書遺言がもっとも容易に作成できる方法です。
作成費費用が不要
自筆証書遺言は手続き等もないうえ、その筆記具にも条件などはありません。
そのため、どこにでもある紙とペンで作成できる遺言書になります。
公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人などに立ち会ってもらうために費用が必要となり、数万円程度を要するケースがほとんどです。
また、費用を必要としない自筆証書遺言であれば、変更点が発生した場合にも遺言書の書き換えが簡単にできます。
破棄や修正が楽
自筆証書遺言は、自分で書いて自分で保管する遺言書です。
自分で好きなタイミングで記入し、誰の目にも入れずに自分で管理する性質から、破棄する場合でも修正する場合でも自分の自由に行えます。
公正証書遺言などは公証人などを交えることから、全員の都合や手間などを考慮したうえで破棄や修正には手間や時間、費用が必要となるでしょう。
最初の遺言書で完成する自信がないのであれば、自筆証書遺言にすることで何度でも修正可能です。
遺言内容を秘密にできる
自筆証書遺言は原本を自分で管理します。
そのため、遺言書の存在を誰にも知らせなければ身近な人にも秘密にできるでしょう。
秘密証書遺言も自分で原本を管理しますが、作成段階では証人が必要です。
公正証書遺言は上記に加えて、管理も公証役場に任せます。
誰にも知らせずに遺言書を作成したい場合は、自筆証書遺言で遺言書を作成しましょう。
ただし、存在自体が知られていない遺言書は発見されないリスクもあります。
そうなってしまえば遺言書の内容はなかったものとなるため、存在を知っている人物がひとりでもいるようにすることをおすすめします。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言はその自由度がメリットとなりますが、反対にデメリットとなる部分もあります。
ここでは、自筆証書遺言で考えられるデメリットについて紹介していきます。
無効になりやすい
遺言書には、最低限記載しなければならない情報があります。
また、書く際の形式にも一部指定があるなど、知識がなければ誤った形式で書いてしまうかもしれません。
最低限の内容が伴っていない場合、遺言書の内容は全面無効になります。
自分ひとりで完成させる自筆証書遺言は、せっかく書いた遺言内容が無効となるケースが多い作成方法といえます。
偽造のリスクがある
自筆証書遺言は、作成から発見されるまで基本的には自分ひとりで管理します。
そのため、もし生前ないし死後に発見された際、発見した人物により内容が改ざんされたり偽造されたりするリスクが伴う作成方法です。
昨今では、遺言書を管理するシステムなども発展してきたため、そうしたシステムを利用することで偽造や紛失の対策も可能となっています。
自分で管理するにせよ、システムを利用するにせよ、大切な遺言書の管理はしっかりと行わなければなりません。
手書きである必要がある
自筆証書遺言は、本人が書いた証明のためにも基本的に直筆でなければなりません。
つまり、パソコンやワープロで作成された遺言書は無効となります。
手が不自由であったり精神障害であったりする方では、そもそも遺言書を残すことすら叶いません。
上記のような方が遺言書を残そうとした場合は、公正証書遺言など、自分以外の人が遺言書の書面を作成する方法でしか用意できません。
開封には家庭裁判所の検認が必要
遺言書は原則、発見したとしても勝手に開封してはいけません。
これは法律で定められているもので、勝手に開封した場合は遺言書が無効になることはないものの、場合によっては罰則が科せられる可能性があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を開封する場合は、参加可能な相続人全員と裁判官などの役員が立ち会って開封する、検認と呼ばれる手順を踏まなければなりません。
検認には時間を要する場合もあるため、遺族にとっても手間のかかる作業となるでしょう。
公正証書遺言であれば検認の手順が不要となっており、開封の際に法的な手段を必要としません。
遺族が検認する必要を避けるのであれば、公正証書遺言の選択も考慮すると良いでしょう。
発見されない可能性がある
自筆証書遺言は、作成から発見までの間は基本的に自分しか遺言書の存在を知りません。
そのため、遺言書があることすら誰にも話していなかった場合には、遺族に発見されずに日の目を見ることさえなくなるケースもあります。
もし遺言書が発見されなければ、遺産分割協議や法定相続分などの方法で処理されるため、自分の望む相続が成されることはありません。
こうしたトラブルを避けるためにも、作成したことだけは誰かに伝えておくと良いでしょう。
公正証書遺言であれば公証役場が管理するため、見つからない可能性は低くなります。
また、秘密証書遺言であれば遺言書の存在自体は公証人や証人になった方が知っています。
必ず発見してほしい場合は、それなりの対策を取っておくと良いでしょう。
遺言書保管制度の導入
遺言書保管制度とは、2020年7月より導入された自筆証書遺言を法務局が管理する制度です。
上述した通り、自筆証書遺言はその管理性質上、紛失や偽造、破棄のリスクがある作成方法になります。
こうしたリスクを最小限に抑えるため、法務局に保管依頼を申請することで自筆証書遺言であっても保管してもらえるようになったのです。
あくまで自筆証書遺言を管理するシステムであるため、作成の段階で証人を必要とすることもなく、作成自体は従来のように手軽に作成可能となっています。
また、手続き時には、法律に則った形式で作成されているかどうか確認してもらえるうえ、開封時の検認も必要ありません。
多少の費用と手続きを要する制度となりますが、遺言書を確実に有効にするためには利用することをおすすめします。
自筆証書遺言の作り方
実際に遺言書を作成する際、自筆証書遺言として作るにはどうすれば良いのかを知っておくことは大切です。
以下で注意点などについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
書式や用紙に決まりはない
大前提として、必要事項などが記載されていればその書式などに明確な決まりはありません。
使用する用紙にも定めはないため、家にあるもので遺言書を作成することもできます。
ただし、必要事項の記載漏れや誤表記など、内容に不備があればその遺言書は無効となるので注意しましょう。
必要事項
遺言書には、必ず記載しなければならない内容があります。
遺言書の内容として必須項目となる事項は以下の通りです。
- 日付…作成年月日を正確に記載
- 氏名…直筆での署名
- 印鑑…実印を署名付近に捺印
作成日は、複数の遺言書が見つかった際の判断項目にもなります。
署名と捺印は本人の意思であることを証明するためのもので、いずれかの表記がなければ遺言書は無効となるので注意しましょう。
記入事項
遺言書に記載するべき文面は、遺言の意思表示とその遺言内容です。
遺言内容は各遺産について、誰にどの遺産をどの程度の割合で相続させるのか明確に記載しましょう。
一般的に遺産として認識される財産は以下の通りです。
- 銀行などの預貯金
- 土地や持ち家
- 有価証券
- 不動産
- 家具家電
- 貴金属類
- 自動車
上記はあくまでごく一部であり、金銭的価値のあるものはすべて遺産として扱われます。
また、ペットなどの引取先を必要とする存在についても遺言書に残しておくことで、自分の思う相続が行われるでしょう。
また各項目については、詳細まで記載するようにしてください。
例えば、預貯金であれば銀行名から口座番号や名義人まで、土地であれば住所から土地の広さまで、といった具合です。
この際、金額まで詳細に記載すると、作成日以降に金額の変化が生じた際に間違った記載と認識されて無効になるケースもあります。
金額については詳細に書きすぎないようにするのがおすすめです。
もし記載内容に不安を覚えるようであれば、弁護士などに相談してみると良いでしょう。
文例
(遺言者氏名)は遺言者として、以下のように遺言します。
一:遺言者は、妻である(妻氏名)(妻生年月日)に以下の財産を相続させる。
1.土地
所在:※県から記載
地番:番地
地目:宅地
地積:㎡
2.家屋
所在:※県から記載
家屋番号:番
種類:居宅
構造:※木造などから何階建てなどまで
床面積:※階ごとの床面積(㎡)
二:遺言者は、長女である(長女氏名)(長女生年月日)に以下の財産を相続させる。
1.預金
所在:※正式な銀行名
支店:※口座の支店名
番号:※口座番号
名義:遺言者名
三:遺言者は、本遺言に記載のない財産についての一切を長男である(長男氏名)(長男生年月日)に相続させる。
四:遺言者は、本遺言の執行者として以下の者を指定する。
事務所:※弁護士などに委託する場合は所属事務所の記載
職業:弁護士
氏名:※弁護士名をフルネームで記載
生年月日:※弁護士の生年月日
五:付言事項
遺族への言葉などがあれば記載
※この項目には法的拘束力はないので注意
令和年月日(作成日)
(遺言者住所)
遺言者 (遺言者名)(印)
※土地などの詳細は、登記に記載されている内容のまま記載してください。
※氏名などについても、戸籍に書かれている正確な名前で記載します。
スポンサーリンク無効にならないための注意点

遺言書を書いたとしても、その内容に不備があれば効力は発生しません。
そのため、遺言書を書く際にはいくつか注意しなければいけない点があります。
以下で特に注意すべき点について解説するので、ぜひ参考にしてください。
内容は明確にする
遺言書に記載する相続内容は、明確に記載するようにしましょう。
遺言者の情報は当然として、相続させる相手についても氏名から生年月日までを明記することで、正確に特定できます。
また、遺産の内容についても詳細まで記載することで明確に特定できるようにしてください。
この記載が曖昧な内容だった場合、誤った相続がなされたり遺言書が無効となったりします。
ひとつでも記載の誤りがあれば遺言書自体の効力がなくなるため、注意して記載してください。
連名にはしない
遺言書は原則として、作成する遺言者は1名でなければなりません。
たとえ夫婦であっても連名での作成はできないため、必要であれば各人で遺言書を作成するようにしてください。
用紙が複数の場合は契印が必要
契印とは、重要書類において複数枚にわたる際に行われる連続している証明の割印です。
作成した遺言書を1枚ずつ少しだけずらして配置し、すべてにかかるように実印を押してください。
こうすることで、仮に書類がバラバラになったとしても印鑑が割印の役割を果たして、連続した書類であることを証明します。
加筆・修正のやり方
遺言書の内容を加筆したり修正したりする際も、正式に定められている方法以外で行うと遺言書が無効となる場合があります。
加筆する場合は、加筆する場所に{を追記して加筆内容を書いてください。
この際、加筆した場所に押印しておきましょう。
修正や削除する場合については、修正または削除する内容を二重線で消したのち、修正内容を追記してください。
二重線で消した部分には加筆時同様に押印しておきましょう。
いずれの場合も、遺言書の枠外に訂正した内容を記載します。
この際の訂正内容は詳細に書く必要があり、どのような内容をどういった内容に訂正したかなど、しっかりと記しておくようにしてください。
本人の代わりに弁護士に依頼はできる?
遺言書の作成はその内容から、どうしても不安に思う方もいるでしょう。
そういった場合には、弁護士に依頼して遺言書を作成することも可能です。
とはいえ、弁護士に依頼する以上は費用が発生するため、金銭面での不安を覚える方もいるのではないでしょうか。
ここでは、依頼した際の利点や費用、弁護士以外への依頼についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
弁護士に作成の依頼はできる
弁護士に遺言書作成依頼を出した場合は、その遺言書が有効になる確立が格段に上がります。
書式や相続内容などを確認したうえで、問題ないかどうか、どのように修正すれば良いかなどについて弁護士が助言してくれるでしょう。
また、自分の財産であっても完全に把握できていないケースは少なくありません。
こうした際にも、弁護士に依頼しておくことで可能な限り調査してくれます。
その他必要な手続きやその準備などについても手助けしてくれるため、安心安全に遺言書を作ろうと思った場合には弁護士に相談することをおすすめします。
作成費用
弁護士に依頼する際、その相談料は多くの事務所で5,000円程度とされています。
無料で相談可能としているところもあるため、事前に調査しておくと良いでしょう。
遺言書作成段階に入った場合は、多くの事務所で10万円〜20万円の依頼費用を要します。
これらの費用はあくまで一般的なものであり、その財産状況や遺言の内容などによってさらに金額が上乗せされる場合もあるので注意してください。
遺言書の保管を依頼した場合は、年間あたり1万円程度の管理費が必要で、遺言の執行を依頼した場合にはその遺産総額から報酬額が定まります。
遺産の数%と固定依頼料の合計額が報酬額として指定されていることが多いため、事前に相談や調査をしておくことをおすすめします。
司法書士や行政書士も依頼可能
弁護士は仕事内容の幅が広く、遺言書作成においてもさまざまな手続きや対応をしてくれます。
しかし、弁護士以外にも、司法書士や行政書士などに遺言書の作成依頼をだせることをご存知でしょうか。
それぞれ依頼費用が8万円程度からとされており、弁護士と比べると費用を抑えられるケースが多くあります。
ただ、それぞれ得意分野があるうえに代理人としての権利はないため、トラブルへの対応などは難しいケースがほとんどです。
行政書士は書類の作成から提出までに関する対応に強く、司法書士は不動産登記などを得意としているため、不動産関連の手続きがスムーズになるでしょう。
どの専門家に依頼するか悩んでいる場合は、自分の目的に合った依頼先を選ぶのも良いかもしれません。
公正証書遺言の方が優先度は高い?
書類の作成段階の観点から、公正証書遺言がもっとも優先順位が高いと思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし、遺言書の種類による優先順位というものはありません。
作成方法がいずれの場合であっても、作成日がもっとも直近で有効なものを最優先するのが遺言書です。
一部例外として、複数の遺言書がある際に、後述の遺言書内に記載のない相続内容が前述のものに記載されている場合に限り、前述の遺言書のその部分のみ有効となります。
また、あくまで有効な遺言書の中でもっとも直近のものであることから、後述の遺言書が無効となった場合には前述の遺言書が有効です。
自筆証書遺言の有効期限は?
自筆証書遺言について、有効期限などがないのか疑問に思う方も少なくないでしょう。
ここでは、自筆証書遺言の有効期限や更新について解説するので、ぜひ参考にしてください。
自筆証書遺言に有効期限はない
自筆証書遺言に限らず、遺言書に明確な期限はありません。
仮に数十年前に書かれた遺言書であっても、その遺言書が見つかって相続が始まった段階で効力が発生します。
これは後から見つかった場合でも例外はなく、遺言書がないまま相続を終えて10年後に遺言書が見つかった場合でも、その遺言書の内容が適用されます。
その際には、可能な範囲で遺言書に従うこととなり、事前の相続内容と照らし合わせて財産の再分割が行われることになります。
とはいえ、遺言書の内容は、相続人全員が合意すれば無効にすることが可能です。
遅くに発見された遺言書は手続きも複雑になるケースが多いため、相続人全員が合意して無効にするのも良いでしょう。
また、古すぎる遺言書というのは無効になるケースも考えられます。
遺言内容にある人物などが死去していた場合などでは、その遺言書の内容すべてが無効になるため、その場合は意味のない遺言書となってしまうでしょう。
遺言書の更新はした方が良い
上述した通り、古すぎる遺言書は内容に問題が生じているケースが多々あります。
そのため、遺言書を作成してからも長く生きた場合は、新しい遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書がない場合はまだしも、一度遺言書を書いてしまった場合は、破棄しない限り見つかった場合に従う必要性が生じます。
そうなれば故人にとっても意図しない相続となるケースもあるため、古い遺言書がある場合には定期的に遺言書の更新をするようにしましょう。
公正証書遺言のメリット・デメリット
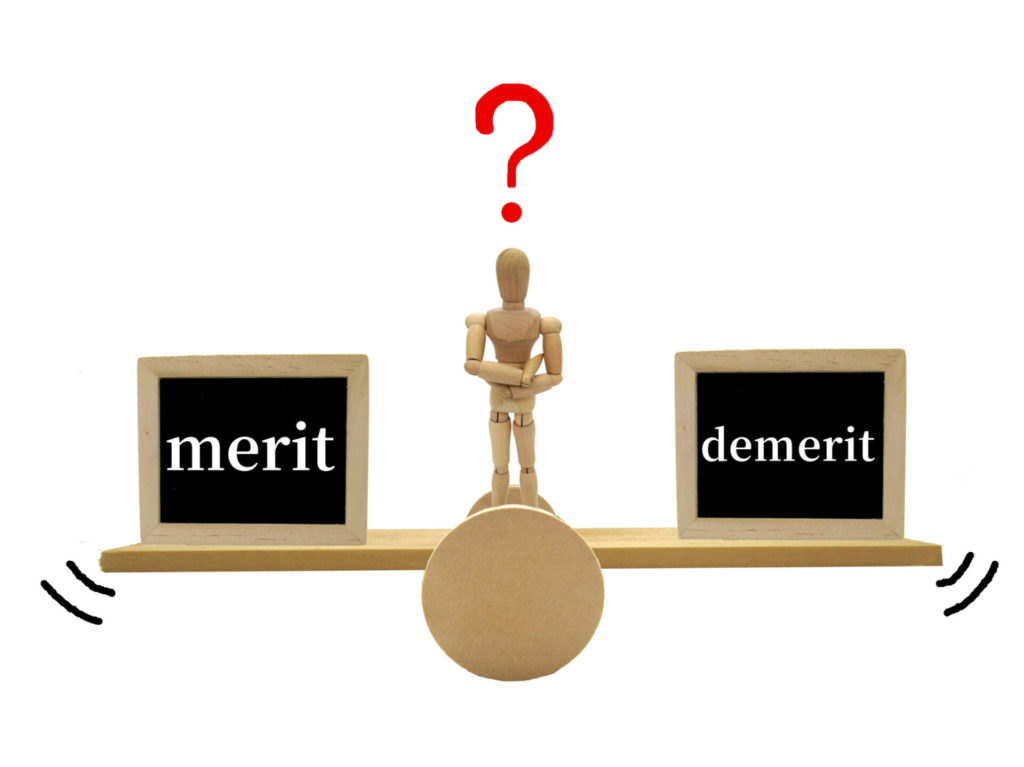
遺言書に関するリスクを最小限に抑えられる公正証書遺言ですが、他にもさまざまなメリットやデメリットがあります。
公正証書遺言での遺言書作成にはどのようなメリットやデメリットがあるのか紹介するので、ぜひ参考にしてください。
メリット
公正証書遺言による一番大きなメリットは、紛失や偽造の心配がないことです。
公正証書遺言は公証役場でその原本を管理するため、よほどの問題が生じない限りはその原本を改ざんしたり破棄したりすることはできません。
遺言書のトラブルの中でももっとも多い、紛失や偽造といったトラブルを避けられるのは大きなメリットといえるでしょう。
また、その作成段階で公証人が関与することから、その作成内容に不備が生じにくいメリットもあります。
遺言書にはちょっとした不備があるだけでも無効となってしまうリスクがあるので、少しでもリスクを抑えられるのは大切なことです。
デメリット
公正証書遺言におけるデメリットは、その手間と費用になります。
公的に作成する性質上、手続きには時間を要するうえに費用が生じてしまいます。
作成にかかる費用はその遺産総額によって変動し、金額が小さければ5,000円〜1万円程度ですが、総額が1億円を超える場合では5万円以上必要です。
作業についても、遺言内容の確認や書面の確認、証人の準備などのさまざまな手間を要します。
上記のようなデメリットを看過できるのであれば、公正証書遺言にて安全な遺言書を作成するのがおすすめです。
自筆証書遺言のメリットとデメリットまとめ

ここまで自筆証書遺言についての情報や、そのメリット・デメリットについて解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 自筆証書遺言は、遺言者当人の直筆の遺言書
- 自筆証書遺言は、自由に作成できるが確実性に欠ける
- 自筆証書遺言は、必要事項が記載されていれば書式に明確な決まりはない
- 弁護士に遺言書の作成依頼を出すことも可能だが費用がかかる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
遺言書作成に困ったら「Wing堂ヶ芝行政書士事務所」へ

Wing堂ヶ芝行政書士事務所の代表行政書士の吉本翼と申します。
行政書士は、許認可手続きや様々な書類を作成する「頼れる街の法律家」です。
当事務所におきましても、お客様のお困りごとに寄り添い、
徹底的にサポートすることを信条としております。
当事務所では開業以来5年以上に渡り遺言、相続の専門家として様々なお客様にご依頼いただき経験を積んでまいりました。
どんな些細なお困りごとにも誠心誠意対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
終活の関連記事
終活

更新日:2023.11.19
遺言書作成の費用はどのくらい?各専門家の費用相場を比較!
終活

更新日:2022.05.01
公正証書遺言は開封しても問題ない?開封のタイミングについても紹介
終活

更新日:2025.03.31
多死社会ニッポン…「孤独死」回避のため、元気なうちから着手したい〈生前対策〉






