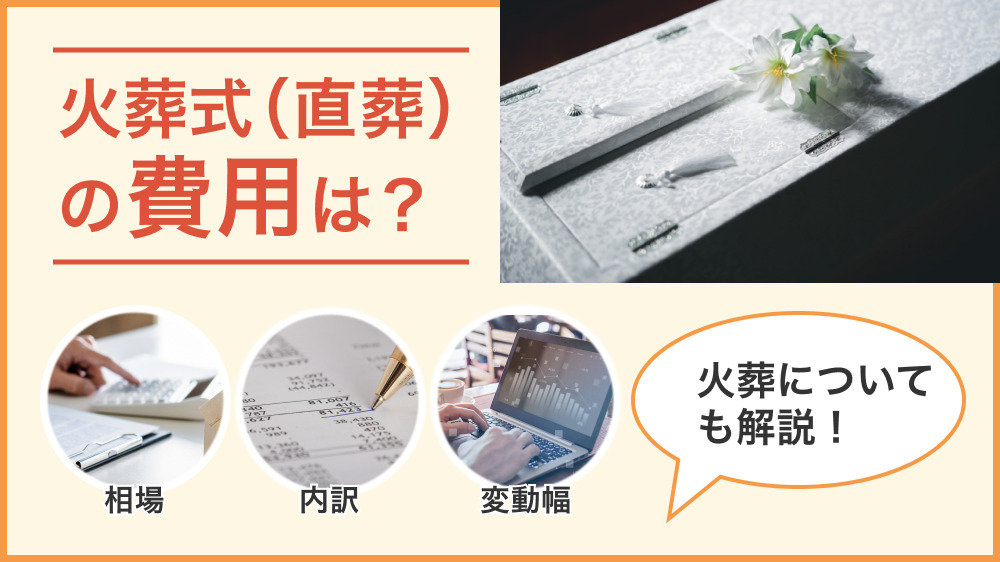お葬式
直葬でお経は必要?読経の流れや相場を解説!
更新日:2024.04.24 公開日:2021.07.29

みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 直葬でのお経について
- 直葬でお経は必要?
- お経の意味とその役割
- 直葬における僧侶の読経依頼の事例とその背景
- お経を読む場所
- 直葬形式での読経のタイミングと方法について
- 直葬の僧侶の手配方法
- 直葬でお経をあげてもらう費用相場
- 直葬の流れ
- 直葬形式での読経を行う際の注意点
- 直葬を行う際の注意点
- 直葬に数珠は持っていく?
- よくある質問
- 直葬でのお経まとめ
直葬でのお経について

直葬とは、火葬だけする形式の葬儀のことをいいます。
火葬だけということになると、お経は必要なのかと思いますよね?
そこでこの記事では以下の3点について主に解説します。
- 直葬でお経が必要か?
- 僧侶の手配方法について
- 直葬におけるお経の相場
是非最後までお読みください。
スポンサーリンク直葬でお経は必要?

直葬の形式が近年増加しています。
これは、一般的な葬儀と異なり、通夜や告別式を省略して火葬だけを行う方法です。
経済的および精神的な負担を軽減するために選ばれることが多いです。
しかし、直葬でもお経をあげる必要があるのか、という疑問が生じます。
結論から言えば、直葬であってもお経をあげることは可能です。
また、お経を省略する選択もあります。
お経をあげない場合、「無宗教」という形をとることになりますが、これは個人または家族の信仰に基づく選択です。
特に、菩提寺がある場合、お経をあげていただかないと納骨できないこともあります。
したがって、直葬を選択する前に、家系の菩提寺の有無を確認することが重要です。
菩提寺とは、家系の先祖代々のお墓があるお寺のことです。
一方で、「お経を唱えないと故人が成仏しないのでは?」と考える方もいらっしゃいます。これは宗教的な観点から見ると、解釈はさまざまです。
仏教では一般的にお経が成仏に必要とされることが多いですが、お経は遺族のためのものと考える立場もあります。
最終的に、遺族と家系の宗教的背景に基づいて、お経の有無を決定することが望ましいでしょう。
そして、直葬形式であっても、必要に応じて僧侶に相談し、お経を読んでもらうことは可能です。
ただし、一般的な葬儀とは異なり、お経をあげるタイミングや方法が異なる可能性があるため、葬儀社とよく相談して決めることが重要です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
お経の意味とその役割
お経には非常に重要な意味があります。
お経は、単なる供養のためのものではなく、覚醒したお釈迦様の教えが含まれています。
この教えを聞いたり読んだりすることで、遺族は悲しみを和らげ、心を落ち着かせることができます。
お経には、故人を思う「供養の心」を表すための役割もあります。
心を静めることで、故人への想いをより深く、より純粋に伝えることが可能になります。
お経を唱えることは、遺族にとって心の平穏をもたらす重要な行為です。
それにより、故人への愛情や敬意を表すことができ、故人の魂に対しても穏やかな気持ちを伝えることができます。
お経は、遺族自身の心の癒しとともに、故人への思いやりを深めるための大切な手段となります。
スポンサーリンク直葬における僧侶の読経依頼の事例とその背景
直葬は本来、儀式を伴わない火葬のみの手続きですが、最近では僧侶による読経を取り入れるケースが増えています。
この傾向には以下の二つの主な理由があります。
菩提寺との関係維持
菩提寺や長年お付き合いのある寺院が関与する場合、直葬でも一定の宗教的儀式を取り入れることが望ましいとされることがあります。
特に、先祖代々の墓が寺院にある場合、火葬後の納骨を寺院の墓地で行うのが自然な流れですが、直葬だけでは納骨を拒否される可能性も考えられます。
このため、直葬を選択する際には事前に寺院にその旨を伝え、必要に応じて最低限の読経を行ってもらうことで、寺院との良好な関係を維持することが重要です。
遺族の精神的な安堵
経済的または体力的な理由から全面的な葬儀を避ける遺族も多いですが、「せめて読経だけはしてあげたい」と考える場合があります。
直葬にもかかわらず、僧侶による読経を取り入れることで、故人への供養としての心のこもったお別れを実現できます。
この折衷案は、遺族にとって「きちんと送り出せた」という心の納得につながり、精神的な安心感を提供します。
これらの理由から、直葬においても僧侶による読経が求められることがあり、故人と遺族に対する思いやりと敬意を形にする重要な要素となっています。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
お経を読む場所

直葬で行う儀式は、火葬場で行う火葬式のみです。
とはいえ、臨終後すぐに火葬することはできません。
亡くなられてから24時間以上安置してから火葬というのが法律でも定められています。
火葬式では、僧侶をお呼びしてお経をあげてもらうことができます。
時間は一般葬より短く、10分ほどです。
直葬形式での読経のタイミングと方法について
直葬形式では、通夜や告別式を行わず、遺体の火葬のみを行うことが多いですが、それでは読経はいつどのように行われるのでしょうか。
直葬では、主に遺体が安置されている場所か、火葬場でのお別れの際に読経を行うことが一般的です。
まず、安置所での読経に関してです。
法律により、人が亡くなってから24時間は火葬や埋葬を行ってはならないため、少なくとも一日間は遺体を安置する必要があります。
この間に、安置所や自宅など遺体を安置している場所で僧侶に読経を依頼することが可能です。
ここでの読経は一般的に10分程度で終わります。
一方、火葬場での読経を希望する場合、僧侶にその旨を伝えて、火葬場での読経を依頼することになります。
火葬場は予約制であり、長時間の滞在が難しいため、読経は通常5分程度と短時間で行われます。
このため、遺族が故人と最後の別れをゆっくりと行いたい場合は、安置所での読経が推奨されます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
直葬の僧侶の手配方法

直葬を行うにあたって読経をしていただく意向がある場合は、僧侶の手配をします。
菩提寺の僧侶にお願いするか、葬儀社に頼むのがおすすめです。
インターネット上に僧侶を派遣してくれるサービスもあります。
僧侶を手配する際は直葬に対して理解のある僧侶を手配することが大事です。
直葬でお経をあげてもらう費用相場

僧侶を火葬式に呼ぶ場合、お布施を支払う必要があります。
直葬でお経をあげてもらう場合のお布施は、5万〜10万円ほどが相場です。
戒名をつけてもらう場合、さらに金額が上がります。
戒名とは、仏弟子となった証明として与えられる名前です。
寺院の檀家になっている場合お墓に納骨する際必要になるので事前に確認しておきましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
直葬の流れ

ここからは、直葬を行うにあたり、火葬炉前でのお経をあげていただく場合の流れをご紹介します。
集合
直葬は、家族などの近親者のみで行われることが多いです。
そのため、皆が集合するのは火葬場へ向かう当日になります。
火葬場で集合でも問題ありません。
お別れ
火葬場に参列者が集合したら、火葬式を行います。
家族や親族、近親者で故人にお別れをします。
直葬は一般の葬儀と違い通夜や告別式を行わないため、短時間になることが多いです。
読経・焼香
火葬する前に僧侶に続経をしていただきます。
そのときに一般の葬儀のときと同じく焼香をします。
この場合も、家族・親族・故人と縁が深かった近親者の順で焼香していきます。
火葬
火葬炉に入る前に、故人の顔を見て最後の挨拶をします。
そして、棺は火葬炉に入ります。
火葬時間は、1時間~1時間30分ほどで終わります。
その間は、火葬場の隣接した場所に飲食できるところがある場合もあります。
そこで故人の思い出話などをしながら、火葬が完了するのを待ちます。
拾骨
火葬が完了したら、葬儀社の方から完了のお声がけをしていただけます。
火葬炉から別室に移されるか、その場でお骨上げ(拾骨)する場合もあります。
骨壺に遺族や親族、親近者が故人のお骨を箸でつまみ上げ骨壺に入れます。
入れる順番は故人がツボの中で座れるように、足のお骨から胴体、頭と入れ、喉仏を最後に入れます。
直葬形式での読経を行う際の注意点
直葬形式での読経には、いくつかの重要な注意点があります。
特にお布施の扱いやお寺との関係について、適切な対応が求められます。
お布施の種類と金額
直葬形式では、「読経料」「戒名料」「お車代」の3つのお布施が主になります。
読経料は僧侶が行う読経に対する感謝の気持ちとして、一般的に火葬場での短いお経には3万円、安置所と火葬場の両方でお経をあげてもらう場合は10万円程度が相場です。
戒名を付けてもらう場合、15万円~20万円が一般的で、高位の戒名には100万円以上が必要なこともあります。
お車代のマナー
お車代は、僧侶が移動する際の交通費です。これはお布施とは別に、適切な額を包むのがマナーです。
遺族が送迎する場合や、僧侶が使うタクシーをチャーターする場合は、お車代は不要です。
菩提寺との関係
先祖から続く菩提寺がある場合は、直葬であっても連絡することが重要です。
納骨のための段取りが必要なため、直葬形式で葬儀を行う際には、僧侶の招聘や戒名の付与について菩提寺と相談することが望ましいです。
菩提寺との良好な関係を維持するためにも、事前の相談は不可欠です。
無宗教葬儀や菩提寺のない場合
菩提寺がない場合や、無宗教葬儀を希望する場合は、葬儀会社に相談して僧侶の手配を依頼するのが一般的です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
直葬を行う際の注意点
直葬を選択する際には、いくつかの重要な注意点があります。
以下に主要なポイントを挙げて説明します。
菩提寺とのトラブルを避ける
「菩提寺」とは、家族や先祖の遺骨を安置するためのお寺のことを指します。
特に、先祖代々続いている菩提寺がある場合、葬儀を行う際にはそのお寺に連絡を入れるのが一般的なエチケットとされています。
直葬、つまり火葬だけを行う形式の場合、僧侶を呼ばないことが一般的ですが、それに伴い菩提寺への連絡を省略するケースも見受けられます。
しかしながら、先祖の墓に遺骨を納めるには、お寺にも準備が必要です。
そのため、菩提寺への相談を怠ると、後に納骨を断られるという事態に陥ることもあります。
直葬を選択した際は、最低限、以下の二点を菩提寺に確認しておくことが推奨されます。「僧侶を招くべきかどうか」「戒名を付ける必要があるかどうか」。
菩提寺とは、葬儀の際だけでなく、法要の度にも関わる重要な存在です。今後も良好な関係を維持するために、事前の相談が非常に重要です。
家族や親族との関係
故人が直葬を望んでいたとしても、家族や親族によってはその選択を受け入れがたい場合もあります。
直葬という葬儀の形態は、現代ではある程度知られていますが、実際にこの方法を選ぶ人は全体の中ではまだ少数です。
特に、伝統的な価値観を大切にする家族や親族がいる場合、直葬に対して反対意見が出ることも想定されます。
また、家族関係が疎遠であったり、普段からあまり連絡を取り合っていない親族がいる場合、故人の死を火葬が完了するまで伝えないこともあります。
直葬は少数の遺族だけで行われるため、葬儀が終わるまで故人の訃報を広めることはありません。
このような状況では、「故人との最後のお別れをしたかった」「もっと早く知らせてほしかった」といったトラブルが生じる可能性も考慮する必要があります。
葬儀の形式を決める際は、家族や親族との十分な話し合いが求められます。
皆が納得できる方法を選択することが、トラブルを避け、故人への敬意を表すためにも重要です。
供花の取り扱い
直葬を選ぶ場合、供花を設置する場所がないことを理解しておく必要があります。
供花は故人の霊前に供え、その霊を慰めるために使用されるもので、通常は葬儀の祭壇や葬儀会場に設置されます。
贈るのは故人の近親者や親しい友人、知人が一般的であり、企業や団体からの送花も多く見られます。
しかし、直葬では葬儀式場を使用しないため、供花を設置するスペースがありません。
遺体は安置室に一時保管された後、火葬場へ搬送されるプロセスが通常です。
このため、祭壇の設置も行われませんし、火葬場には供花を飾るための場所も設けられていません。その結果、直葬の際に供花を飾るのは困難です。
もし故人を偲び、供花を飾りたい場合は、自宅での設置が一つの解決策となります。
自宅なら、枕花やフラワーアレンジメントなどを自由に飾ることができ、故人への敬意を表すことが可能です。
スポンサーリンク直葬に数珠は持っていく?

実は一般の葬儀のときでも数珠は必須ではありません。
数珠は、お経を唱えるときの回数を数えるために僧侶が持つものでした。
そのため参列するだけでしたら、数珠はなくても宗教上は問題ありません。
ただ仏式葬儀の場合、数珠を持参する方がほとんどですので、マナーとしては持って行ったほうが無難でしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
よくある質問
直葬でも故人は成仏できますか?
故人が成仏できるかどうかは、遺族の考え方や信仰によって異なります。
人によって「成仏」の概念は様々です。
例えば、「家族全員での見送りができれば満足」と感じる人もいれば、「宗教的な儀式にはこだわらない」と考える人もいます。
また、生前の意向に基づいて、意図的に直葬を選ぶ人もいるのです。
さらに、直葬を行う際に戒名が必要かどうかという疑問もあります。
戒名は基本的にお墓に納骨する際に必要とされますが、無宗教であれば戒名がなくても納骨は可能です。
ただし、寺院の檀家に属している場合は、戒名がないと納骨できないことがありますので、注意が必要です。
戒名を付けるか否かは、故人の意向と遺族の判断に基づいて決められます。
納骨を行わない予定の人や、無宗教の場合は戒名を付けない選択もあります。
直葬での読経はいつ行うのが適切ですか?
直葬における読経のタイミングは主に二つのパターンがあります。
どちらを選択するかは、遺族の希望や宗教的な慣習によります。
出棺前の安置場所での読経
故人が安置されている場所に僧侶を招き、短い儀式として読経を行う方法です。
この方法では、故人との最後のお別れの時間に精神的な安らぎをもたらし、遺族が直接僧侶と交流できる機会を提供します。
火葬場の炉前での読経
火葬前に火葬場に僧侶を招き、数分間だけ読経をしてもらう方法です。
このタイミングでの読経は、故人を火葬に送る直前に行うため、形式的でありながらも、故人への最終的な祈りとして意義深いものになります。
どちらの方法も、直葬の形式に合わせて選ぶことが可能です。
遺族の心情や故人の宗教的な背景を考慮し、尊重されるべきです。
直葬における読経は、故人への最後の敬意を表す貴重な時間となりますので、事前にしっかりと計画を立てることが大切です。
なぜ読経や戒名なしで葬儀を行いたいのでしょうか?
読経や戒名なしで葬儀を行いたい理由は、主に経済的なものが挙げられます。
お坊さんに支払うお布施は、読経や戒名のお礼を含めるとかなりの金額になることがあります。
葬儀費用を抑えるためには、お坊さんを呼ばない選択が有効です。
しかし、この選択には、菩提寺からの納骨拒否や親戚との関係悪化など、考えられるトラブルも存在します。
そのため、なぜ読経や戒名なしで葬儀を行いたいのかを、ご家族でしっかりと話し合い、全員の理解を得ることが重要です。
このような話し合いを行うことで、葬儀の形式に関する意見や懸念を共有し、最適な選択をすることができます。
お坊さんを呼ばない葬儀にはどのような種類がありますか?
お坊さんを呼ばない葬儀には主に「直葬」と「無宗教葬」の2種類があります。
直葬は、お通夜や葬儀・告別式を行わずに火葬だけを行うスタイルで、身内だけで静かに送りたい方や、簡素で経済的な葬儀を望む方に適しています。
直葬では、火葬炉の前で短い読経を行うこともありますが、必ずしもお坊さんを呼ばなければならないわけではありません。
無宗教葬は、宗教的な儀式を行わない葬儀で、進行している宗教がない方や、個性的な葬儀を望む方に適しています。
無宗教葬では、故人の人柄を反映した音楽や映像を流したり、趣味のアイテムを展示したりすることが可能です。
直葬を選んだ後、どのような後悔が生じる可能性がありますか?
直葬を選択したことにより生じる可能性のある主な後悔には以下のようなものがあります。
周囲の親族からの反対や苦情
直葬は以前、経済的に困難を抱える人や身寄りのない人向けに選ばれることが多かったため、特に高齢者の間では直葬に対する否定的なイメージが根強くあります。
そのため、親族からの反発や苦情が出ることがあり、直葬の選択理由を事前にしっかり説明することが重要です。
故人の意思が確認できていなかったことによる不安
故人が生前に直葬を望んでいた場合は問題ありませんが、その意思を確認していない場合、家族だけで決定すると「本当にこれで良かったのか」という不安や後悔が残ることがあります。
生前に故人の意向を確認し、エンディングノートなどを活用することが推奨されます。
直葬のイメージと実際の差
直葬を希望しても、実際に行われた式が想像していたものと異なる場合、期待外れの感情や後悔が生じることがあります。
これを避けるためには、事前にしっかりと情報を集め、葬儀社との相談を通じて詳細を把握し納得することが大切です。
金銭的事情による選択
本来は故人や家族が望むような形での葬儀を行いたいものの、金銭的制約により直葬を選ぶことになった場合、後悔の感情が残ることがあります。
終活を早期に始め、葬儀費用の計画を立てることで、このような後悔を防ぐことができます。
直葬はそのシンプルさから選ばれることがありますが、家族や親族の意向、故人の意志、費用の問題など、多くの要素を慎重に考慮する必要があります。
直葬でのお経まとめ

ここまで直葬でのお経の情報や、その費用相場などを中心に書いてきました。
この記事のおさらいをすると以下の通りです。
- 直葬でのお経は必須ではなく、考え方によって変わる
- 直葬での僧侶の手配は、菩提寺か葬儀社に依頼するのがおすすめ
- 直葬でお経をあげてもらう費用は、5万~10万円
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2024.01.24
直葬で戒名は必要?戒名料の相場や戒名をつけない場合の納骨方法などを解説!
お葬式

更新日:2024.01.24
直葬(火葬式)に花を贈っても大丈夫?種類・方法・マナーを解説
お葬式

更新日:2023.08.25
ほとんどの人が知らない…後悔のない葬儀に「ご遺体の安置場所」が重要になる理由