終活
公正証書遺言に対して遺留分は請求できる?遺留分対象も紹介
更新日:2024.10.03 公開日:2022.05.19

記事のポイントを先取り!
- 公正証書遺言も遺留分は請求可能
- 遺留分請求できる人は限定的
- 配偶者の兄弟姉妹は請求できない
- ・死亡保険は遺留分に含まれない
公正証書遺言とは遺言形式のひとつで、被相続人の死後、その遺言に従って相続が行われます。
公正証書遺言がある際、その遺言によって自身の遺留分がもらえなくならないか心配な方もいるでしょう。
そこでこの記事では、公正証書遺言がある場合に遺留分が請求できるかどうか解説します。
この機会に、公正証書遺言と遺留分の関係性について理解しましょう。
後半では、死亡保険をもらった場合の遺留分について触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 遺留分とは
- 公正証書遺言であっても遺留分は請求できる
- 遺留分請求の対象者
- 遺留分の計算方法
- 遺留分侵害額請求のやり方
- 死亡保険を貰うと遺留分は減額される?
- 公正証書遺言の遺留分まとめ
- 内容証明の作成に困ったら「内容証明ナビ」へ!
遺留分とは
遺留分とは、相続において相続人が最低限受け取ることのできる、法律で決められた取り分のことです。
また、この遺留分を侵害した相手に対して、遺留分の金額を請求できる権利を遺留分侵害請求といいます。
この権利があることで、法律で決められた取り分の資産を相続できないという事態を防ぐことが可能です。
すべての相続人が受け取れるわけではなく、被相続人との関係性によってもらえるかどうか決まっています。
自分が相続人であるからといって、必ずもらえるわけではない点に注意しましょう。
公正証書遺言であっても遺留分は請求できる
相続財産は基本的に、被相続人の遺言に従って配分されます。
特に公正証書遺言は、公証人と被相続人によって作成されるため、いくつかある遺言の種類の中でも正確性の高いものです。
この公正証書遺言が残されていた場合、内容によっては自分が遺留分を相続できないかもしれないと考える方もいらっしゃいます。
しかし、遺留分は公正証書遺言の内容によらず、請求できるため安心しましょう。
例えば、遺言書の内容によって相続人や受遺者が自分の遺留分を超えて財産を手に入れることがあります。
その場合、自分の遺留分を侵害した相手に対して、遺留分侵害請求を行えます。
これは遺言に書かれた内容に関わらず、遺留分の権利が認められている人であれば誰でも可能です。
ただし、遺留分侵害請求は、遺留分を取得できる相続人が請求するかどうかを決定します。
例えば、自分が遺留分を侵害された場合でも、請求を行わなければ遺留分が手に入ることはありません。
遺留分請求の対象者

ここからは遺留分請求の対象となる人物を紹介します。
前述通り、遺留分はすべての相続人が受け取れるわけではありません。
被相続人との続柄によって権利の有無が変わってくるため、この機会に確認しておきましょう。
遺留分の対象者
遺留分があるのは被相続人の配偶者と、被相続人の子孫(子供・孫)、被相続人の先祖(両親・祖父母)です。
また、遺留分の割合は、それぞれの相続順位によって変わってきます。
遺留分があるのは、相続の第一順位である子供・孫などの下の世代と、第二順位となる両親・祖母などの上の世代です。
遺留分は被相続人亡き後に、生計を共にすることが多い彼らの生活維持を目的として定められたものです。
兄弟には遺留分が存在しない
被相続人の兄弟・姉妹などには遺留分の権利が存在しません。
これには兄弟・姉妹は被相続人と生活を共にしているケースが少ないことも関係しています。
自分が被相続人の兄弟・姉妹だった場合には遺留分侵害請求は行えないため注意しましょう。
離婚や再婚した場合の対象者について
ここからは被相続人と離婚した元配偶者、再婚した配偶者が遺留分を受け取れるかどうかを説明します。
離婚・再婚のケース別に、配偶者は遺留分の対象となるのかを詳しく解説していきます。
元配偶者は遺留分の対象者?
元配偶者は、被相続人と婚姻関係を解消した時点で遺留分請求の権利を失います。
ただし、元配偶者の実子は遺留分の対象者となります。
また、実子が未成年で元配偶者が親権を持っている場合、元配偶者が法定代理人として話し合いに参加することとなります。
元配偶者の実子が相続人の場合、遺産分割協議を実子なしで行うことはできません。
遺産分割協議は相続人全員が揃って行う必要があるため注意しましょう。
再婚者は遺留分の対象者?
再婚者は被相続人と婚姻関係にあるため、遺留分請求の対象者です。
しかし、再婚者に連れ子がいる場合、その子供は対象とならないため注意しましょう。
ただ、連れ子を遺留分の対象者にする方法もあります。
それは被相続人と連れ子が養子縁組を行って、親子関係になることです。
こうすることで、連れ子も相続人になることができ、同時に被相続人の子として扱われるため遺留分の対象者にもなります。
連れ子に対して遺留分の権利を与えたい場合には、養子縁組することを検討しましょう。
遺留分の計算方法

ここからは遺留分の計算方法を紹介しましょう。
遺留分は請求する相続人の人数や、関係性によって金額が変わってきます。
配偶者だけの場合
遺留分を請求するのが配偶者だけだった場合、配偶者が1人で遺留分すべてを受け取ることが可能です。
配偶者が受け取る遺留分は、相続財産全体の1/2です。
例えば、被相続人の相続財産の総額が1,000万円だった場合、その1/2である500万円を受け取れます。
配偶者と子供がいる場合
配偶者と子供がいる場合でも遺留分の請求を行って受け取れる金額は、相続財産全体の1/2です。
そして、その1/2を配偶者と子供でさらに1/2ずつに分けるため、1人あたりの取り分は1/4になります。
例えば、被相続人の相続財産の総額が1,000万円だった場合、配偶者と子供は250万円ずつ遺留分を受け取れます。
配偶者の子供がいない場合
配偶者の子供がいない場合や、子供がすでに亡くなっていて孫もいない場合、遺留分は配偶者と配偶者の両親で分けます。
遺留分は相続財産全体の1/2で、配偶者がその内の2/3、配偶者の両親が1/3ずつ受け取ります。
そのため、それぞれ受け取る遺留分は、配偶者が相続財産全体の1/3、配偶者の両親が1/12ずつとなります。
具体例として、被相続人の相続財産の総額が1,000万円とした場合で説明すると、配偶者は333万円程度、配偶者の両親が83万円程度受け取れます。
配偶者と子供が三人いる場合は?
配偶者と子供が3人いる場合は、遺留分を4人で分けることとなります。
遺留分は相続財産全体の1/2を、配偶者が1/2、子供が3人合わせて1/2を受け取れます。
よって、取り分は配偶者が1/4、子供が1人あたり1/16ずつです。
具体例として被相続人の相続財産の総額が1,000万円とした場合で説明すると、配偶者は250万円、62万5,000円ずつ受け取れます。
順位が同じ人が複数いる場合は?
順位が同じ人が複数人いる場合は、前述した子供3人のケースと同様に、同じ順位の人たちで遺留分を等分することとなります。
例えば、被相続人の両親が両方健在の場合は、両親の間で遺留分を等分します。
また、子供や孫が複数人いる場合は、その人数で遺留分を等分します。
遺留分侵害額請求のやり方
ここからは遺留分侵害額を請求する方法を紹介します。
請求が話し合いで解決できない場合についても紹介しているので、参考にしてください。
遺留分侵害額請求の期限
遺留分の侵害額請求期限は、相続・遺贈を知った時から1年以内です。
これは民法第1048条第1文で定められており、1年を過ぎると請求権利を失効してしまいます。
また、遺留分を侵害する相続・遺贈の存在を知らなかった場合も、10年を超えると時効となり、請求期限が切れてしまいます。
そのため、遺留分侵害を知った場合には、すぐさま手続きを行う必要があるため注意しましょう。
遺産分割協議で話し合う
遺留分侵害額請求は、基本的に内容証明郵便で行います。
ただし、方法は決められているわけではなく、内容証明郵便以外でも請求を行うことは可能です。
しかし、内容証明郵便は出した日付や内容、誰宛に送られたものかなどを証明できるため、請求の証拠にもなります。
期限前に請求を行ったことの証明にもなるため、おすすめの方法です。
また、請求を行った後は、侵害請求する相手と話し合って、合意を得ましょう。
話し合いに応じない場合は?
侵害額請求をする相手との話し合いは、利害が相反するためなかなか応じてもらえないケースも多くあります。
そうした場合には裁判所に請求調停や審判の申し立てを行うことで、第三者が入った状態で侵害額請求が行うことが可能です。
また、内容証明郵便で相手方に遺留分侵害額請求をしたことを証明しておけば、時効になりません。
相手方が支払いに応じないまま時効になることを回避するために、調停を行う前に内容証明郵便で請求を行っておきましょう。
死亡保険を貰うと遺留分は減額される?

死亡保険がもらえる場合、遺留分の金額に影響があるのか心配な方もいるでしょう。
そこで、死亡保険をもらった場合の遺留分について、以下で詳しく説明していきます。
死亡保険は遺留分の対象外
結論を言うと、死亡保険は遺留分には含まれません。
これは、受取人が被相続人ではなく、受取人が自分の財産にすることが可能だからです。
そのため、遺産には含まれないので、死亡保険は遺留分に関係しません。
ただし、死亡保険は相続税の対象となり、相続税の支払いは必要となるので注意しましょう。
遺留分の対象となる場合もある
しかし、すべてのケースで死亡保険が対象外となるわけではありません。
保険金が遺産の大きな割合を占めるほど、莫大な金額であった場合は不公平性を無くすため、遺留分に含まれることがあります。
例えば、被相続人からの相続財産の全額が1,000万円程度しかないにもかかわらず、死亡保険が1億円あった場合、その差は不公平なほど大きいものだと考えられます。
そのため、死亡保険金も、遺留分の対象として、侵害請求できる可能性があるのです。
死亡保険金と遺産にどれだけ差があるのかなど、遺留分の対象になるかどうかはその金額によっても左右されます。
公正証書遺言の遺留分まとめ

ここまで公正証書遺言があった場合の遺留分侵害額請求について解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 公正証書遺言がある場合も遺留分は請求可能
- 遺留分の対象者は被相続人の配偶者・子孫・先祖
- 兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行えない
- 死亡保険を受け取っても遺留分は減額されない
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
内容証明の作成に困ったら「内容証明ナビ」へ!
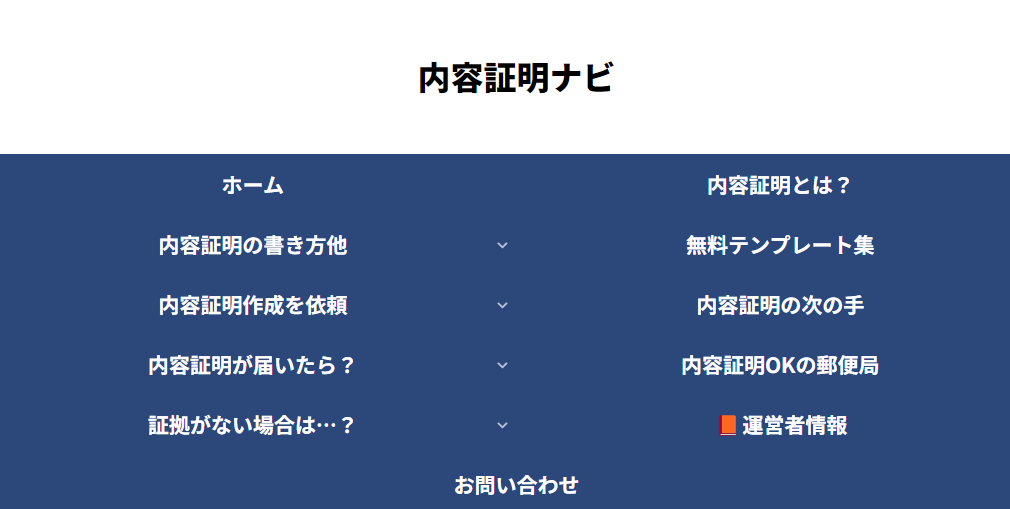
内容証明ナビでは、「そもそも内容証明とは?」という初歩的な疑問から、「具体的にどんな場面で送られているのか?」「逆に送らない方が良いのはどういう時なのか?」といった疑問まで、行政書士がわかりやすく解説しています。
無料テンプレート集や、専門家に依頼するメリットなども紹介。内容証明のことで困ったら、ぜひ「内容証明ナビ」へ。
スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
終活の関連記事
終活

更新日:2023.11.19
遺言書作成の費用はどのくらい?各専門家の費用相場を比較!
終活

更新日:2022.05.01
公正証書遺言は開封しても問題ない?開封のタイミングについても紹介
終活

更新日:2025.03.31
多死社会ニッポン…「孤独死」回避のため、元気なうちから着手したい〈生前対策〉







