お葬式
おひとりさまの死後事務委任契約とは?費用や手続きの仕方、トラブルについて解説
更新日:2024.10.19 公開日:2022.06.07

記事のポイントを先取り!
- 死後事務委任契約は死後の事務を生前に依頼すること
- 内容は死亡届の提出や葬儀について、契約の解約など
- 死後事務委任契約書作成料は30万円が目安
- 死後事務委任契約は基本誰に頼んでもよい
頼れる身内がいないおひとりさまの場合、自分が死んだらその後の事務処理を誰がやってくれるのだろうかと不安になるでしょう。
自分が元気な間に死後の事務を第三者に託しておく、死後事務委任契約をご存じでしょうか。
死後事務委任契約について、どんな契約なのか、何ができるのかを知っておきましょう。
ここでは、おひとりさまが死後事務委任契約を行うメリットや、手続きの仕方、トラブルなどを詳しく説明していきます。
この機会に、死後の事務処理について確認し、死後事務処理委任契約について覚えておきましょう。
死後事務委任契約にかかる費用についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 死後事務委任契約とは?
- 死後事務委任契約でできること
- おひとりさまとは?
- おひとりさまが抱えるリスク
- 死後事務委任契約をする方法
- 死後事務委任契約の手続きの流れ
- 死後事務委任契約にかかる費用
- 死後事務委任契約のお金がないときの対処法
- 死後事務委任契約の契約書の内容
- 死後事務委任契約のトラブル
- 死後事務委任契約のメリット・デメリット
- 死後事務委任契約をする人の特徴
- 死後事務委任契約をするタイミング
- 死後事務委任契約は誰に頼むの?
- 受任者を親族にする場合
- 受任者を専門家や法人にする場合
- 財産管理等委任契約とは
- 死後事務委任契約のよくある質問
- おひとりさまの死後事務委任契約のまとめ
- 京都の終活なら「一般社団法人 高齢者住宅支援連絡会」
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、亡くなってからの煩雑な事務処理を、生存中に誰かに委任するものでおひとりさまが活用すべき制度のことを言います。
死後事務委任契約は、委任者と受任者の間に正式な契約が取り交わされていますので、法的な拘束力があり、確実に死後の意向を事務処理することができます。
受任者は、法的拘束力が発生するので、故人の意向通りに事務を行う義務があります。
死後事務委任契約を結んでおくことで、自分が死んだ後の事務や業務を生前の希望通りに任せることができ、おひとりさまの心配が軽減します。
死後事務委任契約と遺言書との違い
亡くなってから自分の意向を実現させるための死後事務委任と、遺言はどう違うのでしょうか。
どちらも死後に自分の思いが執行されますが、この二つには違いがあります。
基本的に遺言は、財産継承について記載しておくものです。
例えば「○○にある土地は△に相続させる」「預貯金は○に残す」など、財産を誰に残したいかということを決めておきます。
遺言の内容だけを実現するだけしかできませんし、遺言に「葬儀は○○で行ってほしい」「埋葬は樹木葬にして欲しい」などと残しておいたとしても、法的な拘束力はありません。
死後事務委任契約と任意後見契約との違い
任意後見契約とは、将来認知症などになり判断能力が不十分になった場合のために、本人に代わって契約や身上監護、財産管理を信頼できる方に依頼しておく制度です。
基本的に、判断力がある成人ならだれでも任意後見人になることができます。
ただ依頼する場合は、信頼ができる弁護士に委任して行うのが一般的です。
誰しも自分は認知症にならないと思っていますが、おひとりさまの場合、自分で物事を判断する力が衰えた場合、余計な契約をしてしまったり、銀行の暗証番号を忘れてしまったりといったことが出てきます。
いくら、財産を持っていても自分でお金が使えない事態になることを避けるためにも、財産管理に信頼できる人をあらかじめ決めておくと安心でしょう。
任意後見契約の内容は法律に反しない限り、自由に決めることができます。
信頼できる家族が近くにいない方も、元気なうちに信頼できる人を見つけ、契約しておくことが大切です。
死後事務委任契約でできること
実際に死後事務委任契約をしておくことで、どんなことができるのか具体的な内容について紹介します。
行政手続き
亡くなった後には、役所に提出する書類や、届け出など事務的な手続きが様々あります。
例えば、死亡届の提出、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカードの返納、年金の手続きなど。
これらの細かい事務の手続きを、速やかに行ってくれます。
各所への連絡
生前に、自分が亡くなった後に連絡して欲しい箇所を指定しておくことで、訃報の連絡を行います。
契約の解約手続き、費用の清算
電気や水道ガスなど、インフラの契約やスマホや固定電話の契約、ケーブルテレビなどの契約から、クレジットカードなど、様々な契約の解除手続きを行います。
また、支払っていなかった費用の清算、遺品の整理や形見分けの手続きも行います。
葬儀に関する手続き
生前に葬儀、お墓、埋葬について指定しておくことで、亡くなった後は指定通りの葬儀の対応が執行されます。
デジタル遺品に関する手続き
facebookやインスタ、TwitterなどのSNS、増えていくデジタル情報の整理は、本人が亡くなってからでは把握が難しいでしょう。
生前に自分がいなくなった時の対策を考え、伝えておくことで、SNSの退会や報告などデジタル遺品の整理を行います。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
おひとりさまとは?
「おひとりさま」とは、生涯独身の方や配偶者に先立たれ子供がいない方など、同居する人がいない状態のことを言います。
また、子供がいても遠くに住んでいる、疎遠になっているなどで、自分の死後の手続きを任せる方がいない場合も、おひとりさまに含まれます。
おひとりさまが抱えるリスク
おひとりさまの場合、1人で自由気ままに生活するという楽しさがありますが、老後が近づいてくると不安に思うことが多くなるでしょう。
ここでは、おひとりさまが抱えるリスクについて紹介します。
孤独死の危険性
自宅で倒れて意識がなくなったり、怪我で動けなくなった時に、救急車を自分で呼ぶことができずそのまま、衰弱死してしまう例があります。
亡くなってからもしばらく誰にも気づかれずに、孤独死として見つかるリスクもあります。
身元保証人や同意書のサイン
手術や入院が必要になったとしても、同意書にサインをしてくれる人が見当たらずに適切な治療を受けられない可能性があります。
基本的に入院をする場合は、連絡先や保証人などを記載しなければなりません。
子供がいたとしても、すぐに駆け付けられる距離でない場合は、緊急の処置ができないことがあります。
死後の各種手続きの手配
おひとりさまの場合、自分の死後に、お通夜や葬儀の手配をする人がいません。
また、お墓の手配がなく遺骨を引き取る人もいない場合は、遺骨は自治体が一度引き取ることになります。
その後は自治体によっても対応が違いますが、無縁塚などに埋葬されます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
死後事務委任契約をする方法
死後事務委任契約は第三者に依頼します。手続きを行う際は専門家に依頼、もしくは公正証書を残しておけば安心です。
専門家に依頼する場合
死後事務委任契約は弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に依頼するのが一般的です。
専門家に依頼すれば、正しい形式の契約書を用意してもらえるので安心です。
専門家に依頼する場合の流れは以下の通りです。
まずは、死後事務委任契約について専門家に相談します。
最初の専門家からのヒアリングでは、現在の状況やなぜ死後事務委任契約を考えているのかについて聴かれます。
疑問点や不安点等も質問し、納得できれば契約します。
正式な契約の前に、自分の意志が正確に専門家へ伝わり、契約に反映されているかを確認しておきましょう。
専門家によっては、手続きの流れが多少異なる場合もあるため、ご自身でも確認して下さい。
公正証書を作成する場合
死後事務委任契約書は公証役場で、委任者・受任者双方での決定内容を「公正証書」にしてもらえます。
元のままでも有効性に問題はありませんが、公正証書であれば、本人が自分の意思で契約を結んだことが明確となり、本人の死後であっても各種手続きが円滑に進みます。
専門家に依頼する場合は、必ず公正証書を作成して契約を行います。また、専門家以外に依頼する場合でも、作成しておけば安心です。
公証役場で手続きを行えば、早ければ数日中に死後のサポートを受けられる状態になります。
公正証書の作成には、以下のいずれかを公証役場に持参する必要があります。
- 自動車運転免許証と認印
- 印鑑登録証明書(発行後3か月以内)と実印
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
- マイナンバーカードと認印
死後事務委任契約の手続きの流れ
死後事務委任契約の手続きの流れを見てみましょう。
死亡届を提出する
亡くなった人の戸籍を消滅させるための書類である「死亡届」は、故人の本籍地の役所の戸籍課に、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。
委任者は、死後事務委任契約により、受任者に死亡届などの提出を依頼することが可能です。
死亡届の用紙は死亡診断書と同じものですので、受任者は、医師から受け取った死亡診断書に必要事項を追加記入したうえで、役所の戸籍課へ提出します。
死亡診断書を受け取る時、受任者は、死後事務委任契約書を見せて、死亡届の提出を委任されていることを証明しなければなりません。
死亡届の提出時の際は、死体火葬許可申請書も一緒に提出し、役所から火葬許可証を発行してもらい、受領します。
なお、火葬許可証は葬儀社へ渡すようにしましょう。
受任者にたくさんの委任事務があって、忙しくて1人では処理できない場合は、死亡届と死体火葬許可申請書の提出は、葬儀社に代行してもらうこともできます。
葬儀や納骨に関する手続き
受任者は、死後事務委任契約により、葬儀や埋葬の依頼も可能です。
葬儀や埋葬を行う際に、取り決めがなかった細かな点が出てきた場合は、受任者の判断で行うことになります。
葬儀・火葬を行う
委任者にとって葬儀は最も大切なイベントと言えるでしょう。
委任者は、受任者に希望する葬儀内容をしっかりと伝えるとともに、契約しておくことが大切です。
葬儀の費用、葬儀会場の選定、精進落としの料理、香典返しの品などを細かく決めておく方がよいでしょう。
納骨または散骨をする
葬儀と火葬の終了後、菩提寺に納骨を希望する場合は、菩提寺に依頼して墓地や納骨堂に埋葬してもらいます。
その墓地に初めて委任者が眠る場合は、墓石を建てることも委任可能です。
永代供養を希望している場合には、対応している寺院や霊園で手続きが必要になります。
あるいは、委任者が希望していた場所で散骨することもあるでしょう。
寺院の指定や墓石の金額などは、希望を詳細に伝えておいた方が受任者に対して親切です。
行政手続きについて
行政手続きについて解説します。
健康保険の手続きと保険証の返還
健康保険は死亡日の翌日に資格を喪失し、国民健康保険は、死亡後14日以内に資格喪失届を役所に提出して、保険証を返還しなければなりません。
協会けんぽ(全国健康保険協会)は多くのサラリーマンが加入していますが、受任者は事業主へ保険証を返還することのみが委任され、資格喪失届は事業主が提出することになります。
介護保険は、委任者が65歳以上の第1号被保険者であった場合、あるいは、40歳から64歳未満で介護保険の被保険者である第2号被保険者の場合には、資格喪失手続きも同時に行ってもらいます。
委任者が加入している保険や、介護保険の有無については、生前にきちんと受任者へ伝えておかなければなりません。
年金の手続き
年金も、死亡の翌日に被保険者の資格を喪失します。
国民年金の場合、国民健康保険同様、死亡後14日以内に資格喪失届を役所に提出する必要があります。
なお、厚生年金の場合は、資格喪失届は事業主が提出します。
所得税準確定申告
所得税順確定申告と納税は、事業を行っていた委任者が死亡した日の翌日から4カ月以内に、行わなければなりません。
できれば、生前に死後事務委任契約のことを顧問税理士にも伝えておき、受任者を紹介しておくとよいでしょう。
また、収入や費用に関する領収書などの資料が申告の際に必要になるので、前もって受任者に保管場所などを伝えて
おくことをおすすめします。
税金の支払い
住民税や所得税は、委任者が死亡した年度分は支払い義務があるので、受任者が納税することになります。
公共サービスの手続き
公共サービスの手続きも細々としたものがあります。
放置していると、携帯の基本料金などのように無駄な月額費用が発生し続けてしまいます。
受任者の対応が遅れると、遺族から責任を要求される可能性もあります。
公共サービスには以下のものがあります。
- 電気
- ガス
- 水道
- 電話
- 新聞
- インターネットプロバイダ=の解約・使用料金の清算
- スマートフォンアプリ
- クレジットカード
- 運転免許証の返納
- パスポートの失効 など
勤務先での手続き
委任者が勤務していた場合、勤務先での手続きは基本的に勤務先が行い、受任者は死亡の連絡のみを行います。
勤務先での手続きとして代表的なものは、退職手続きと所得税の年末調整です。
退職手続きとして、健康保険、厚生年金、雇用保険などの資格喪失手続きがあり、これらは勤務先が行い、受任者は保険証の返還のみを行います。
年末調整として、亡くなった年の1月1日から死亡日前までに支払われた給与分に対しては、所得税の清算のために、勤務先が年末調整を行います。
死亡日後に支払われる給与は、年末調整の対象とはならず、所得税の対象です。
受任者は、源泉徴収票を受け取り、遺族へ渡します。
源泉徴収票は確定申告の際に必要になるため、受任者は再び遺族から預かります。
しかし、未払い賃金・弔慰金・退職金については、遺族が受領しなければなりません。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
死後事務委任契約にかかる費用
死後事務委任契約にはどのくらいの費用が掛かるのか、相場を解説します。
死後事務委任契約書作成料
死後事務委任契約を行うための契約書の作成を専門家に依頼する場合、おおよそ30万円かかります。
契約書は、委任者の希望を反映した正確なものを作成しなければなりません。
専門家に依頼することで、意向に沿った契約書の作成が可能です。
死後事務委任報酬
死後事務委任報酬とは、亡くなった後の納骨、葬儀、永代供養の手続きを委任する際の費用のことです。
死後事務委任報酬の費用の目安は50万円〜100万円です。
手続きは様々あり、どれを依頼するかによって費用が変わります。
公証役場の手数料
死後事務委任契約書を公正証書として、公証役場で作成するケースもあります。
この場合、公証人に1万1000円の手数料を支払います。
預託金
預託金とは、生前にどのくらいの費用が発生するのか見積もっておいて、死後事務委任契約を結んだ際に、あらかじめ預けておくお金のことを言います。
本人が死亡した後は、銀行などの口座が凍結されお金を引き出すことができなくなります。
死後事務委任契約を結ぶ際には、一般的に100万円〜150万円程度の預託金を預けますが、金額は依頼する内容によって変わります。
死後事務委任契約のお金がないときの対処法
死後事務委任契約のお金がない場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。
死後事務委任契約の項目をしっかり確認する
委任する項目が多いほど死後事務契約の必要な費用も大きくなります。
死後事務委任契約では、委任する項目をしっかり精査したうえで選ぶことが可能です。
そこで、必要のない項目をなるべく省き、本当に必要な作業だけを厳選して委任契約を結ぶことで、費用を節約できます。
業者に対しても、自分でしっかりと委任内容を精査し、丸投げはしないようにしましょう。
複数の死後事務委任契約業者を比較する
死後事務委任契約の費用は、各業者によって差がありますし、契約の範囲も違っています。
死後事務委任契約をする業者と契約する際は、必ず複数の業者を比較検討するようにしましょう。
複数の業者のサービス内容を比較すれば、余計な費用をチェックできます。
また、今後、長い付き合いとなるため、業者が信頼できるかどうかをしっかり見極めることが大切です。
広告に掲載されている業者に連絡してそのまま契約するのではなく、複数の業者に相談して、サービス内容やスタッフの対応からしっかり判断して選定するようにしましょう。
生命保険を利用する
死後事務委任契約の費用の支払いは、生命保険を利用することも可能です。
初期費用は死後事務委任契約の作成料のみですが、毎月の費用は保険の契約によっても違ってきます。
保険会社によって審査条件や保険金額はさまざまですが、まとまったお金が用意できない場合には利用するとよいでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
死後事務委任契約の契約書の内容
死後事務委任契約には決まった形式はなく、口頭でも成立します。
しかし、口頭では約束した内容が記録として残りませんし、死後事務を契約から長い年月が経ってから行うという場
合もあり、記憶が曖昧になってしまう可能性もあります。
死後事務委任契約を確実なものにするためにも、書面による死後事務委任契約書の作成が必要となります。
死後事務委任契約書に記す主な内容は次の通りです。
葬儀や埋葬などの手続き
葬儀場を手配し、火葬許可申請書の提出等の事務手続きを行います。
また、納骨や永代供養等をどのように行うかなど、葬儀に関する事柄を細かく指定できます。
また、現時点で未確定の事項に関して、自身が決められなかった場合に誰に決定権を託すのかを指定できます。
親族や知人への連絡
亡くなった後に連絡して欲しい親族や知人を連絡方法と一緒に記載します。
SNS等でお知らせすることも可能です。
諸費用の計算
亡くなるまでに発生した医療費や老人ホーム等の費用をどのように精算するのかを記載します。
また、死後事務にも費用が発生しますので、その精算方法も一緒に記載します。
死後に家族や親族等へ請求や滞納通知がいくことのないように手配をしておきましょう。
部屋の清掃や家財の整理
居住していた部屋や施設等の清掃や家財の処分等、亡くなった後の整理を行ってもらえるように、権限を委任している旨を記載します。
スポンサーリンク死後事務委任契約のトラブル
死後事務委任契約は、おひとり様にとって死後迷惑をかけないために活用すると良いものですが、トラブルが起きることもあります。
家族の意見の不一致
家族の意見が一致しない事があります。
契約の内容が、家族からすると望まない内容で、希望通りにできない可能性があります。
本人が死後事務委任契約として、葬儀を音楽葬にしようとしても、家族は普通の葬儀にしてほしいと思っていたりします。
葬儀以外にも、納骨せずに海洋散骨をして、永代供養をすると契約をしていても、家族は遺骨をひきとって供養したいと思っていることもあります。
これらは生前に家族とよく話し合って死後事務委任契約を締結できていると回避できるトラブルです。
きちんと相談してから契約すると、家族と自分との意見のズレを少なくすることができます。
しっかり相談していても争いになりそうだという場合は、どうしてそのような委任をしたのか、エンディングノートなどで伝えておきましょう。
エンディングノートは自分の意思を死後家族に伝えるいい方法です。
エンディングノートも活用して、意見の不一致で起きるトラブルを減らしましょう。
受任者の不正
受任者が不正することがあります。
これはよく起こるトラブルです。
死後事務委任契約の受任者には、さまざまな権限が与えられます。
そのため、受任者は委任者の預金にアクセスできるようになります。
この権限を使って、委任者の預金口座に勝手にアクセスし、死後事務委任契約とは違う目的で使い込んでしまうことがあるのです。
その結果、相続人とトラブルになります。
このようなトラブルを避けるために受任者を吟味して選びましょう。
信用できない相手にお願いすると、使い込まれてしまいかねません。
信用でき、いろいろな権利を任せてもよいと思える人に頼みましょう。
弁護士や司法書士などは立場もあるので、受任者に最適だとされています。
受任者と相続者の対立
亡くなったあとの身辺整理では、受任者と相続人が対立することがあります。
死後事務委任契約の規定では、本来は受任者が死後の手続きを行います。
しかし相続人は、委任者の財産を相続する人です。
そのため、相続人も一定の権利を持っています。
事前に相続人にも、死後事務委任契約について話をするとよいでしょう。
相続人にも契約について話をすると、相続人の思いを聞くことができ、自分の思い以外も反映した契約内容にすることができます。
相続人の意見も聞いて、死後事務委任契約の中身を決めておくと、受任者と相続者の対立を防ぐことができます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
死後事務委任契約のメリット・デメリット
死後事務委任契約はどんなことが行えるのか内容を説明してきましたが、メリットやデメリットについても把握しておきましょう。
死後事務委任契約のメリット
死後事務委任契約をしておくことで、生前の希望を叶えられるというメリットがあります。
「自分が死んでから誰かに迷惑をかけるのではないか」「お墓や葬儀はどうなるのか」など、おひとりさまの不安がなくなり、安心して暮らせます。
また、家族や親族などがいる場合でも、死後の面倒な手続きを行わなくてもいいので、負担や迷惑をかけずに済みます。
死後事務委任契約のデメリット
メリットが多い死後事務委任契約ですが、デメリットはあるのでしょうか。
デメリットのひとつは、自分で生前に死後のことを考えて手続きを進めていくのは、大変という点です。
死後の手続きは、専門性が高く素人がいちから考えるのが大変なため、基本的には専門家に相談して契約を進めます。
専門家に依頼するためには、費用が発生するデメリットもあります。
死後事務委任契約をする人の特徴
死後委任契約をする人の特徴にはどういったものがあるのでしょうか。
家族に負担をかけたくない人
家族や、遠方にいる親族などに、死後に行わなければならない事務や整理のことで負担をかけたくないという人がまずあげられるでしょう。
家族が高齢の人
家族が高齢の場合、死後の手続きをまかせるのは不安です。
そういった場合も、死後事務委任契約を締結すると安心でしょう。
おひとりさまの人
葬儀や納骨・その後の財産処分などを決めていない、いわゆる「おひとりさま」の場合、まわりの人や施設などに迷惑をかけてしまう傾向があります。
死後事務委任契約をすることで周囲の人の負担を軽減させることができます。
散骨や樹木葬を検討している人
火葬以外の散骨や樹木葬などを希望している場合、相続人や家族に本人の遺志が反映されないことがあります。
こういった場合も死後委任契約を結んでおくと、死後に自分の希望どおりに散骨や樹木葬などを執り行ってもらえます。
内縁関係のパートナーがいる場合
法律上の夫婦でない内縁関係の場合、パートナーは法定相続人にはなれないため、死後の事務を行うことができません。
死後事務委任契約をしていないと、相続人以外は死後の事務ができません。
お互いに死後事務委任契約するなどの工夫すると良いでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
死後事務委任契約をするタイミング
一般的な契約と同様、死後事務委任契約は、健康や判断能力に問題がない時期が契約するタイミングです。
特に、家族や親戚がいない人で、自分自身の健康も不安になってきた場合は、なるべく早めに契約する方が安心でしょう。
死後事務委任契約は誰に頼むの?
死後事務委任契約を依頼するには誰がいいのかというと、特に制限がありませんので、友人や知人に頼むこともできます。
手続きは、どんなことを依頼するのか契約内容を書面に記載して、依頼者と依頼を受ける側が署名捺印することで成立します。
信頼ができる友人に無償で依頼することもできますし、司法書士や行政書士のような専門家に有償で依頼することも可能です。
本当に執行されるのか不安な方、事務処理が煩雑な場合は、専門家にお願いしておくと安心です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
受任者を親族にする場合
死後事務委任契約で親族を受任者に選ぶ場合、親族は相続などの問題を考えなければいけません。
特に故人を介護していた人など、中心となって身の回りのお世話をしていた人などが相続人となる場合、遺産分割に関するトラブルを防ぐために準備が必要です。
これにはあらかじめ故人が遺言書を作成しておくこと、受任者に支払う報酬の設定などが大切です。
受任者を専門家や法人にする場合
死後事務委任契約の受任者を司法書士等の専門家や法人を選ぶ場合、死後事務は複雑で手間がかかるものも多いため、法的な知識がある司法書士等に頼るのも一つの手段です。
その場合、依頼にかかる費用と委任者の状況の把握が欠かせません。
例えば委任者が一人暮らしの場合、受任者は委任者の状況を把握しておくことで、もし委任者が亡くなった場合死後の手続きを迅速に進めることができ、遺産管理をスムーズに進めることができます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
財産管理等委任契約とは
財務管理委任契約とは、財産の管理やその他の生活上の事務の全部、または一部を、代理権を与える人に委任することです。
この契約は家族でも専門家でも委ねることができ、管理内容も自由に決めることができます。
例えば高齢が理由で財産管理が難しくなった、体の不調で外出が困難になった時などに、一定の法律行為を委任できます。
財産管理だけではなく、生活上の事務も契約対象とすることができるので、おひとりさまで頼る人が近くにいない時に、依頼しておくと安心です。
外出ができない場合でも、契約内容に預貯金の引き出しを含めておくことで、委任者のキャッシュカードで預貯金を引き出し、公共料金などの支払いができます。
死後事務委任契約のよくある質問
死後事務委任契約のよくある質問をご紹介します。
死後事務委任契約 誰に頼む?
死後事務委任契約を頼む人は自由に選択できます。
信頼できる人であれば誰でもよく、特別な資格も不要です。
事情があって親族には頼めない場合や、親族がいない場合は、親族以外の第三者との契約も可能です。
死後の事務手続きは、法律専門家、例えば司法書士などに依頼するという方法もあります。
死後事務委任契約書の作成にしても、死後事務の遂行にしても大変手間がかかり、複雑なものが多いので素人では大変だからです。
死後事務委任契約のデメリットは?
遺言の内容と死後委任契約の規定とが抵触した場合、遺言の内容の方が優先されるおそれがあります。
死後事務委任契約を含む「委任契約」は、民法上で、委任者の死亡によって終了するものと定められています。
そのため、委任者の死亡時に契約が終了してしまうこともあるでしょう。
さらに、委任者の相続人が解除権を行使して、死後事務委任契約を終わらせてしまうことも可能です。
そのような事態を防ぐために、可能な限り相続人と死後委任契約に関する情報を共有して、できる限り解除権を行使しないようにしておくべきでしょう。
死後事務委任契約は解除できるのでしょうか?
死後事務委任契約は、基本的には相続が開始される前に、受任者または委任者のいずれかから契約を解除することが可能です。
さらに、双方の合意による途中での契約解除も選択肢として存在します。
ただし、民法第651条は任意的な規定であるため、契約において解除する権利を制約する条項を設けることもできます。
死後事務委任契約は、委任者と受任者間の信頼関係に基づいて成立するものであり、受任者がいつでも容易に契約を解除できると、委任者にとって不利益が生じる可能性があるため、解除は特定の理由や状況に限定されます。
この点を考慮し、契約の内容を慎重に検討することが大切です。
死後事務委任契約は社会福祉協議会と結ぶことは可能ですか?
死後事務委任契約は、地域の社会福祉協議会とも結ぶことができます。
多くの市区町村には社会福祉協議会が設置されており、これらの組織の中には死後の事務手続きをサポートする部門が存在します。
ただし、社会福祉協議会で取り扱うことができる委任内容は限られており、通常、葬儀の手配、家財道具の処分、公的機関への届け出などが含まれます。
契約方法としては、預託金方式や保険金方式が一般的で、それぞれ異なる特性を持っています。
死後事務委任契約を社会福祉協議会と結ぶ前に、ご自身の居住地の社会福祉協議会に問い合わせを行い、契約の詳細について十分に理解することが大切です。
死後事務委任契約の範囲は?
死後委任契約でできることとして、以下のものがあります。
- 行政手続き
年金手続き、死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納など
なお、死亡届への署名は任意後見契約を締結している人のみ有効です。
- 連絡対応
訃報などの連絡を、事前に指定された連絡先へ行います。
- 葬儀対応
葬儀や埋葬などの執行
- 遺品整理
遺品の整理、形見分け、自宅の家財など
- 病院・施設の退去手続き
施設などの利用の解約、清算、入院費用の清算など。
- 契約の解約、費用の清算
電話契約、クレジットカード、水道・電気・ガスなどの契約、その他生前の契約の解約手・費用の清算など。
- デジタル遺品の整理
サブスクやSNSなど、デジタル情報の整理。
死亡届人とは?
死亡届人とは、故人の死亡を市役所、区役所、町役場に死亡届を届け出る人です。
また死亡届人になることができるのは、故人の親族、同居人、家主、家屋管理人、後見人等です。
成年後見人は、死後事務に関する手続きも担当することができるのでしょうか?
成年後見人は、通常、生前の財産管理や身上監護に関する重要な役割を果たします。
しかし、驚くことに、成年後見人が死後事務に関する手続きを行うこともできます。
ただし、これを実現するためには、『死後事務委任契約』を別途結ぶ必要があります。
任意後見契約を締結する際に、死後事務委任契約も同時に結ぶことができ、生前から死後にかけて、一貫したサポートを受けることが可能となります。
死後事務委任契約の相場は?
死後事務委任契約の費用相場は、契約書作成料が約27万円、死後事務を行うための報酬が50万円~100万円程度です。
また、公証役場の手数料が1万1千円で、預託金は財産の金額や葬儀の内容によって違ってきます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
おひとりさまの死後事務委任契約のまとめ

ここまで、おひとりさまが活用するべき死後事務委任契約について、どんな契約なのか、依頼できる内容などをお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 死後事務委任契約とは生前に死後の事務処理を第三者に依頼するための契約
- 死後事務委任契約の費用は死後事務委任契約書作成料は30万円、死後事務委任報酬は50万円〜100万円
- 死後事務委任契約はおひとりさまの人が多い
- 死後事務委任契約のトラブルは家族との意見の不一致など
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
京都の終活なら「一般社団法人 高齢者住宅支援連絡会」
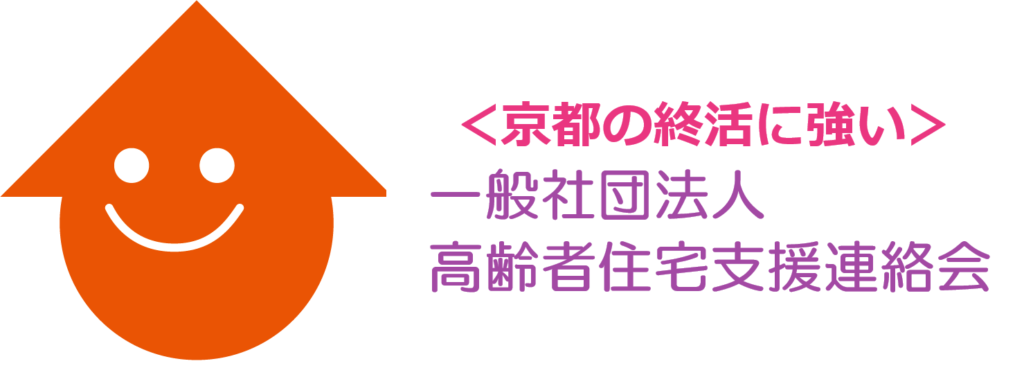
一般社団法人高齢者住宅支援連絡会は、京都のご高齢の方々のお部屋探しと生活支援に長く携わり、終活のサポートにも力を入れてまいりました。
お一人で生前整理や遺言作成など全ての作業を行うのは大変です。「遺言をどうしたらいいのかわからない」「早いうちから身辺整理をしておきたい」といったお悩みに応えるため、生前整理や遺言・遺産のサポート、エンディングノートの作成といった幅広いサービスを手掛け、ご不安を軽減できるよう努めております。
スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2025.06.17
互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説
お葬式

更新日:2023.10.20
湯灌(湯かん)は何をするの?湯灌の目的や費用相場なども紹介
お葬式

更新日:2024.01.10
合同葬とは?社葬や一般葬との違いや相場、マナーについて解説
お葬式
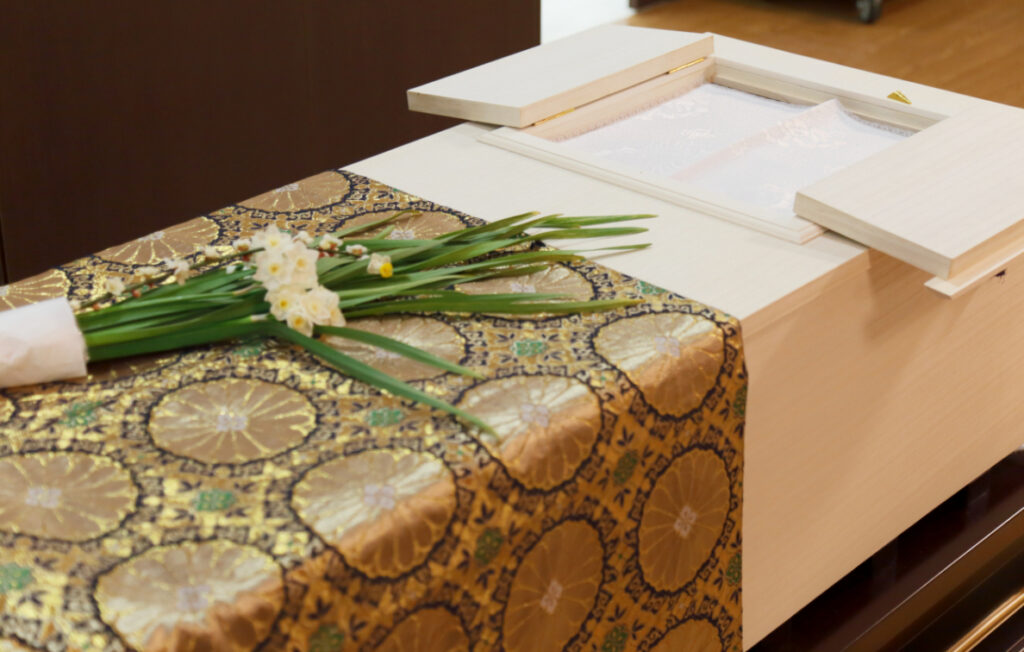
更新日:2024.02.03
遺体搬送車とは?遺体搬送車の車種や霊柩車との違い、搬送料金についても解説
お葬式

更新日:2025.03.20
音楽葬の費用の内訳は?演奏者の派遣料金や著作権、音楽葬の流れも解説


