お葬式
遺体搬送車とは?遺体搬送車の車種や霊柩車との違い、搬送料金についても解説
更新日:2024.02.03 公開日:2022.01.28
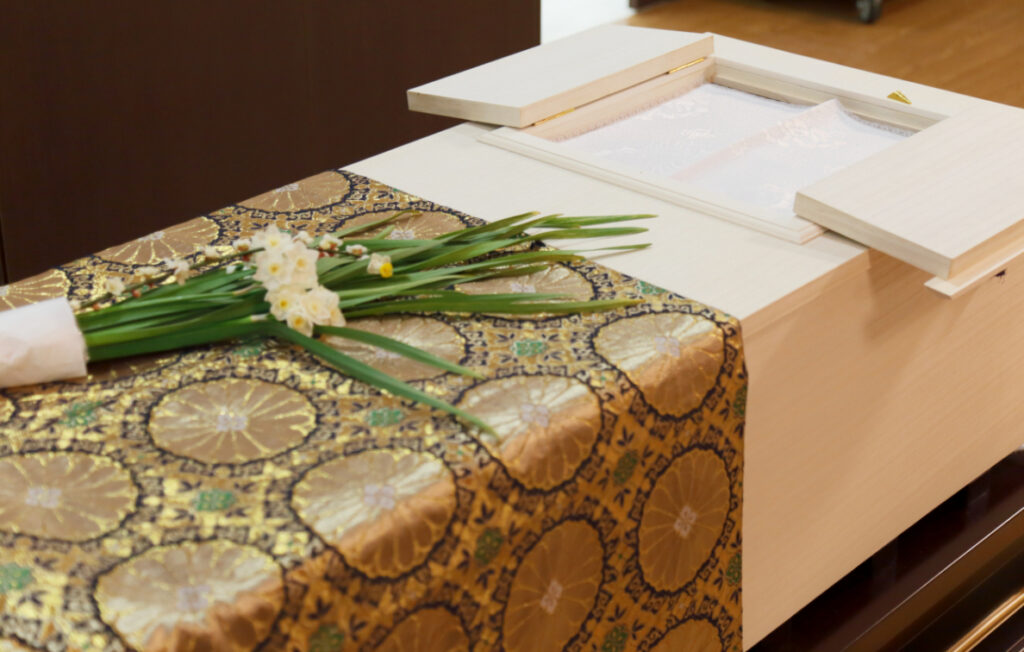
記事のポイントを先取り!
- 自家用車の搬送はリスクが大きい
- 葬儀会社に手配を依頼する
- 海外の搬送には手続きが必要
病院から遺体を運ぶ際、普通の車ではなく遺体搬送車を使うことはご存知でしょうか。
遺体搬送車をスムーズに手配するにはどうしたらいいのかを知っておきましょう。
そこでこの記事では、遺体搬送車の手配について詳しく説明していきます。
遺体搬送車の手配にかかる費用についても解説していきます。
遠方で逝去した場合の遺体の搬送方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
遺体搬送車とは

遺体搬送車とは、故人を亡くなった場所から遺体の安置場所まで搬送する車のことで、寝台車とも呼ばれています。
遺体搬送車には、遺体の出し入れが可能なストレッチャーと、家族が乗るシートがつけられています。
遺体搬送を業務にする場合は認可が必要
金銭の支払いが発生する業務として遺体搬送をする場合は、貨物自動車運送事業法に基づき、霊柩限定の一般貨物自動車運送事業として、国土交通大臣から許可が必要です。
遺体は法律上は貨物の扱いになるため、生きている人を乗せるタクシーやバスでは、業務として遺体を搬送することはできません。
また、遺体搬送に使う車も、専用に認可されたものを使うため、事業者と同じように許可と登録が必要です。
そのため、遺体搬送車には、緑色のナンバープレートが取り付けられています。
搬送費用を受け取って遺体搬送をする場合は、この緑ナンバーの分類番号の始めが8番の車が必要です。
自家用車で遺体搬送は可能
業務での遺体の搬送は、緑ナンバーの認可された遺体搬送車でなければ行えませんが、亡くなった家族を自家用車に乗せて搬送する分には法律上の問題はありません。
しかし、自家用車での搬送にはいくつかのリスクがあります。
まず運搬時に遺体を傷つけてしまう可能性があります。
遺体は生きている人とは違い、重いうえに死後硬直で扱いづらくなっています。
専門の遺体搬送車にはストレッチャーや担架がついており、遺体を固定して搬送することが可能ですが、自家用車にはそういった設備はありません。
そのため、車体の揺れによって遺体を傷つけてしまう可能性があります。
また、安定させようとして遺体を座らせた状態にすると、遺体から体液が漏れることがあります。
体液が漏れると感染症リスクなどが発生します。
遺体搬送車に備えられているような防水シートやマットを用意しておくと、ある程度防ぐこともできますが、設備が不十分な自家用車では完全なリスクの軽減は難しいです。
感染症や不測のトラブルを考慮すると、専門の業者に依頼するほうが安全性が高いといえます。
死亡診断書は必ず携行する
使っているのが自家用車でも遺体搬送車でも、遺体を運んでいることには変わりありません。
自家用車での搬送でも、死亡診断書は必ず携行してください。
また自家用車での搬送はめったにないため、犯罪を疑われる可能性もあります。
家族だと証明できるように、死亡診断書の原本かコピーを提示できるようにしておきましょう。
遺体搬送車と霊柩車

遺体搬送車は一般的に寝台車と呼ばれていますが、寝台車によく似た車に「霊柩車」があります。
ここからは、寝台車と霊柩車の違いと霊柩車の種類をご紹介します。
霊柩車との違い
病院などの亡くなった場所から安置先へ遺体を搬送する車が寝台車ですが、霊柩車は棺に納めた故人を葬儀場から火葬場まで運搬する車両です。
宮型霊柩車などはその形状からすぐにわかりますが、寝台車はワンボックスやステーションワゴンが多く、一見普通車と見分けがつかないことが多いです。
一般普通車とは、緑のナンバープレートがあるかないかで区別できます。
また近年では、寝台車と霊柩車の2つの役割をはたす、多機能車を使用する葬儀社が増えています。
霊柩車の種類
斎場から火葬場まで遺体を運ぶ霊柩車には、いろいろな種類があります。
霊柩車は自動車メーカーではなく、霊柩車専門の業者が製造します。
霊柩車は一般の車両をベースに棺が入るサイズになるよう、ボディーを切断し、パネルを貼って伸ばします。
老朽化するとパネルを貼った部分から劣化していくため、ボディーを伸ばさないノンストレッチの霊柩車も作られています。
宮型
宮型は主として火葬場にご遺体を出棺する際に用いられます。
車の後部に輿のような豪華な装飾が施され、霊柩車のイメージとしてよく挙げられます。
主に仏式や神道の葬儀で使われることが多いです。
洋型
洋型は宮型とは違い、革張りで車体は長く、外見はリムジンのような車です。
パッと見た感じ霊柩車のように見えづらいため、宮型の代わりに使われるようになりました。
一般的に車体は黒ですが、白い洋型霊柩車もあります。
昭和天皇の大喪の礼で使用されたことで広まり、今ではどの宗教の葬儀でも使われます。
バン型
宮型、洋型の霊柩車を使いたくない時は、バン型を使うことができます。
バン型は基本的に搬送車として使われていますが、斎場から火葬場へ遺体を運ぶときにも使われます。
火葬場への出棺のほか、長距離の遺体搬送などにも使われています。
葬祭イベントでもこのバン型霊柩車が展示される程、注目されている型です。
バス型
バス型の霊柩車は、バスの後ろや横の部分に柩を載せられるようになっています。
北海道や東北地方で使われ、参列者と遺体を一緒に運ぶことができます。
通常なら霊柩車の後に続いて、それぞれの車で火葬場まで移動します。
しかし雪の多い地域では火葬場まで安全に向かうために、バス型の霊柩車に発展しました。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
遺体搬送車の車種

遺体搬送車の見た目は、一般の自動車と見分けがつかなくなっていますが、車種によって特長があります。
以下で遺体搬送車の車種ごとの特長をご紹介します。
HONDA オデッセイ
高さ制限にかからない車高と小回りの良さが特長の遺体搬送車です。
見た目が一般の乗用車と変わらないため、車の床が地面と近い、低床設計なので足元が不自由な方も乗り降りがしやすいです。
TOYOTA アルファード
遠方で亡くなり、自宅まで長距離搬送が必要な場合に向いている遺体搬送車です。
セカンドシートとサードシートはどちらもゆったりとした座り心地なため、長距離移動の際の負担を軽減することが可能です。
広々としたスペースと上質な乗り心地により快適に過ごしながら移動ができます。
TOYOTA エスティマ
低床と低重心で揺れの少ない安定した走行が特長です。
また、低床化により生まれた広々とした室内空間により、同乗する際に窮屈さを感じることは少ないです。
ホイールベースが短く小回りがきくため、狭く入り組んだ自宅周辺の道路でもスムーズに移動できます。
TOYOTA ノア
霊柩車と兼用で利用されることが多い遺体搬送車です。
棺台はストレッチャー兼用になっており、前方下収納の棺室は右側スライドドアから乗り降りが可能になっています。
TOYOTA ヴォクシー
広い室内空間と乗り降りしやすい設計が特長の遺体搬送車です。
車内の移動もスムーズに行える工夫がされており、遺族の要望に迅速に対応できる車種となっています。
TOYOTA エスクァイア
家族葬や密葬に適している遺体搬送車です。
お迎えの際にあまり目立たないデザインとなっているため、周囲に知られたくないという遺族の要望にも応えられます。
遺体搬送にかかる費用

遺体搬送の費用は葬儀代金に含まれることがほとんどです。
では、その内訳を見てみましょう。
基本料金+搬送代
基本料金は葬儀会社によってバラツキがあり、10キロメートルまでで大体1万3000円から2万円に設定されています。
搬送の基本料金に加え、距離に応じた搬送代がかかります。
搬送代は距離に応じて10キロメートル単位で金額が決まっています。
割増料金
深夜や早朝の割増料金として、22時から5時の間は30分ごとに時間に応じた割増料金が加えられます。
留置代
車両を指定時刻後に留め置いたり、待機させた場合、留置代が発生します。
留置代も割増料金同様30分ごとに計算します。
備品代
遺体を搬送する際に使う防水シーツやドライアイス、長距離を搬送する時に必要となる交代要員の人件費が含まれます。
追加料金
安置先が自宅の場合、ろうそくや線香を立てるための白木の机など、安置のための費用もかかります。
距離が10キロメートルを超えたり、遺族の事情で搬送の出発の時間が遅くなった場合、冬の時期、深夜、早朝の出発など、多くの要因によって追加料金が発生します。
運転手へ心付けを渡す事もありますが、心付けを受け取らないことにしている葬儀会社もあるので、可能であれば事前に確認しましょう。
依頼すれば自宅の前を通ったり、思い出の場所を通ったりと搬送ルートを変更する事も可能です。
搬送時に高速道路といった有料自動車道、フェリーを使用した際は実費が加算されます。
葬儀費用の平均相場|内訳や葬儀形式別にかかる費用、費用負担を抑える方法について
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
遺体搬送の流れ

遺体搬送はどのような流れで行われるのでしょうか。
以下で説明していきます。
遺体搬送車の手配をする
遺体の搬送は自家用車でも可能ですが、リスクが大きいので葬儀会社へ依頼するのが一般的です。
葬儀会社以外に、遺体の搬送を専門とする会社もあります。
故人の逝去後、すぐに葬儀会社が見つけられない場合は、病院と繋がりのある業者に依頼することもできます。
専門の会社に依頼して遺体搬送をした後、落ち着いてから葬儀会社を決めることも可能なので、自分に合った方法で遺体搬送車の手配をしてください。
遺体の搬送依頼をする際には、遺体がある場所の住所が必要です。
病院の場合は病院名だけでなく、住所も確認してから連絡しておくと安心です。
搬送先を決める
搬送車を手配したら、どこに搬送するかを決める必要があります。
昔は自宅に搬送して安置する人が多く、搬送先は自宅にするのが常でした。
しかし最近は、マンション住まいで遺体を自宅まで運べなかったり、家が狭くて安置できなかったりといった事情があり、自宅以外の場所に搬送する事もあります。
自宅以外で遺体を安置する場所として、遺体安置室や保冷庫などの専用の部屋がある斎場、葬儀会社にある遺体安置室や保冷庫、火葬場の霊安室などがあります。
これらは遺体を一時的に預けておくためのものです。
こうした施設の利用は、依頼する前にきちんと確認しておきましょう。
死亡診断書の発行
搬送車が到着するまでの間に病院へ料金精算をしておきます。
その際、医師に死亡診断書を書いてもらいましょう。
亡くなってから7日以内に、故人が住民登録していた市区町村の役所へ死亡届を出さなければなりません。
このときに死亡診断書が必要となります。
死亡診断書がなければ死亡届も受理されず、火葬・埋葬の許可が出ません。
死亡診断書は必ずもらい、死亡届を出すまで大切に保管してください。
保険金や遺族年金を請求する際にも死亡診断書は必要になります。
あらかじめ2通書いてもらいましょう。
死亡診断書は遺体搬送時に携行することが義務づけられているので、遺体搬送車には死亡診断書を持っている人が必ず同乗するようにしてください。
近親者・菩提寺への連絡
死亡診断書を受け取ったら、まず近親者のみに連絡します。
誰が、いつ亡くなったのか、正確に伝えるようにしましょう。
特に遺体を安置する場所にいくことのできる近親者には、安置先まで来てもらうようにお願いします。
故人の宗教や宗派がわからないような場合は、年配の近親者に連絡する際に確かめておきましょう。
また、いきなりのことで誰に連絡すべきか分からないこともあります。
誰に連絡すべきかをあらかじめリストにしておくと、慌てずにすみます。
檀家となっている菩提寺(ぼだいじ)がある場合は、そのお寺や住職にも連絡します。
このとき、遺体を何処に搬送するのかと到着予定時刻も伝えましょう。
菩提寺の僧侶は檀家の方が亡くなった時、通夜の前に遺体を安置している所で枕経を勤めるからです。
不安ならこのときに、宗教や宗派の情報、その宗教や宗派での遺体安置の作法について確かめておきましょう。
病院から搬送
遺体搬送車が到着したら、病院から安置先へ搬送します。
病院の関係者に挨拶をし、遺体を搬送車に乗せ、安置先へ向かいます。
この時、死亡診断書を持った人が同乗することを忘れないようにしてください。
遠方から遺体搬送をする場合

旅行などで自宅から遠く離れた場所で亡くなった場合の遺体の搬送をご紹介します。
搬送の依頼方法
亡くなった場所と自宅が遠く離れていた場合、遺体の搬送を依頼するのは現地の葬儀会社です。
海を渡る場合は、車だけでなくフェリーなどを使って搬送します。
場所によっては飛行機で搬送することもあります。
病院で亡くなった場合は死亡診断書、事件や事故などに巻き込まれて遺体が警察にある場合は死体検案書が発行されます。
死亡診断書、死体検案書があれば現地の葬儀会社に依頼する事ができます。
搬送方法
陸路で搬送する場合は短距離の時と変わりません。
料金などを葬儀会社に確認しておきましょう。
搬送に空路を使う場合、区分として遺体は貨物扱いになります。
飛行機で遺体を搬送するには、すでに棺に納棺されていなければなりません。
遺体は、葬儀会社に防腐処置をしてもらった後に納棺します。
死亡診断書か死体検案書を、空輸で搬送できる葬儀会社に渡し、出発する空港まで搬送してもらいます。
出発する空港に到着してから、空港貨物所で手続きをして出発します。
搬送する方法は、コンテナを一つ貸し切りにして、そこに棺を固定します。
遠方で亡くなった場合の注意点
遺体と一緒の飛行機に乗って、帰りたいと思う人もいます。
家族が遺体と同じ飛行機に搭乗したい場合は、どの航空便を予約してあるのかを葬儀会社に確認し、自分で搭乗予約と手続きをするのが一般的です。
航空会社側から家族も搭乗するか確認されることもあるため、一緒に乗りたい場合は航空会社にも相談しましょう。
目的地到着後は、目的地の葬儀会社に引き継がれ、安置される場所まで搬送されます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
海外から遺体搬送をする場合
海外旅行中に亡くなり、日本の自宅まで搬送する方法をご紹介します。
海外からの搬送の流れ
海外で亡くなった方は飛行機で搬送されます。
海外で亡くなるとまず、地元警察から日本大使館や日本領事館へ連絡が行き、外務省に情報が伝達されます。
日本にいる遺族へは、外務省から連絡が入ります。
遺体は一旦現地の安置場所へ移動され、遺族は外務省や現地の大使館・領事館と相談しながら、どう搬送するかを決めていきます。
外務省から亡くなったと連絡が来たら、現地に向かう準備をします。
誰が現地に行くかを決め、航空券や宿泊券をすぐに手配して現地に行きましょう。
遺族がパスポートがない場合
航空券や宿泊券は遺族のほうで手配しますが、旅行代理店に手配を依頼することもできます。
この際、パスポートを持っていなくても大丈夫です。
パスポートを持っていない場合は、特例措置として数時間で発行してもらうことができます。
日本に遺体を搬送するための必要な手続きは、国によって変わってきます。
そのため、現地の日本大使館・日本領事館と相談しながら行います。
遺族が現地に行けない場合
遺族が現地へ行けないという場合もあります。
その場合は、現地の大使館・領事館の方が現地の葬儀会社と連携して手続きをするので、大使館、領事館からの指示にしたがいましょう。
海外搬送サービス会社に依頼して、大使館・領事館との連絡から遺体の搬送までを委託することもできます。
必要書類
現地では3種類の書類を用意して、航空会社か旅行代理店にその書類を提出後、航空貨物運送状というものを発行してもらいます。
一つ目は現地の医師の死亡診断に、日本大使館や領事館がサインしたものです。
事故死や自殺、他殺などの事件性があるものの場合は、監察医の死体検案書も用意しなければなりません。
どちらも日本で死亡届を提出する際に必要になります。
二つ目は現地の葬儀会社に作ってもらった、防腐処理証明書です。
飛行機に乗せるには防腐処理が必要です。
きちんと防腐処理がされているという証明が必要になります。
三つめは日本大使館か日本領事館が発行した埋葬許可証です。
日本で遺骨を埋葬する際、この埋葬許可証をお寺などに提出します。
搬送が難しかったり、搬送するのに時間がかかるといったことから、現地で火葬して搬送することもあります。
火葬して搬送する場合は、埋葬許可証が火葬許可証に変わります。
その他に、故人のパスポートも必要になります。
搬送の際の注意点
通関するときに必要な書類も、大使館・領事館の指示にしたがって揃えてください。
現地の空港までは、現地の葬儀会社を荷受人として、棺を空港まで搬送して手続きします。
日本に着いてからは、到着した空港から自宅までの搬送が必要になります。
到着地の葬儀会社か遺体搬送専門会社に依頼しておきましょう。
その時、搭乗予定の便名や日時などを、確実に伝えられるようにしてください。
搬送にかかる金額
海外から遺体を搬送する時にかかる費用は、現地での防腐処理や空港までの搬送費なども含め、100万円から150万円ほどになります。
高額になるため、保険が効くか確認しておきましょう。
旅行保険や、クレジットカードの付帯保険が使えることもあります。
見落としていないか、必ず確認しましょう。
宮型霊柩車の減少理由

霊柩車というと、豪華な細工がされたものや黒くて長いものを思い出す方が多いのではないでしょうか。
金色が特徴的で、豪華な飾りがついたものを宮型霊柩車といいます。
しかし近年では、この宮型霊柩車を見る事は少なくなりました。
宮型霊柩車の減少理由を以下でご紹介します。
家族葬の普及
その理由として、新しい葬儀の形である家族葬の普及があります。
家族葬は親類や近しい友人のみで行われる葬儀です。
こうした葬儀で、豪華な宮型霊柩車を使うのは仰々しくあからさまに霊柩車だと分かってしまうことから、使用が避けられるようになりました。
作り手の減少
また作り手の減少も理由の一つにあります。
宮型霊柩車の、装飾された後部を作ることが出来る宮大工が減ってきているのです。
宮型霊柩車自体、1年に3台か4台しか作ることが出来ないものです。
手間がかかる上に作り手が減少していることで、宮型霊柩車の生産も難しくなってきています。
安全性の問題
宮型霊柩車特有の問題もあります。
国土交通省が自動車の安全性を厳しくしたため、装飾の突起が制限されるのです。
こうしたことから、最近は宮型霊柩車よりも洋型霊柩車を使うことが多いです。
昔よく見かけた宮型霊柩車のシェアは、今では一割未満まで落ち込んでしまいました。
洋型霊柩車は霊柩車らしくなく、宮型霊柩車よりも縁起が悪いイメージを受けないため使われるようになりました。
霊柩車の自由な形態
霊柩車の設備も現代に合わせて変化しています。
霊柩車の色というと黒が定番ですが、今はカラフルな色の霊柩車も登場しています。
車内で音楽を流せるようになっている霊柩車もあります。
故人の好きな色の霊柩車で、故人の好きだった曲を流しながら出棺することができます。
霊柩車自体を使わないということもあります。
霊柩車は、斎場から火葬場まで遺体を運搬する際に使いますが、斎場のすぐ隣に火葬場があるというような場合、霊柩車は必要なくなります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
よくある質問

よくある質問をご紹介します。
霊柩車が発車する時にクラクションを鳴らすのは何故ですか?
霊柩車が出棺の際、クラクションを鳴らすのは、一番鶏(にわとり)の鳴き声の意味があります。
鶏の鳴き声は、闇を払う力があるとされており、かつては、通夜が終わって、朝一番の鶏の鳴き声を聴き、野辺の送りをし、その後葬儀を行っていました。
その名残で、現代では一番鶏の代わりに霊柩車のクラクションを鳴らします。
自宅で亡くなった場合、救急車は呼ぶべきですか?
救急車を呼ぶ基準は、外見から明白に死亡していると判断できない場合です。
そのため、明らかに死亡している状態なら、可能であれば呼ばない方が賢明です。
死亡している場合、救急車で病院に救急搬送されることはなく、救急隊員が警察に連絡し、警察の取り調べを受けることになるからです。
救急車の判断に迷う場合は、「♯7119」(救急相談センター)に連絡して、指示に従うことをおすすめします。
遺体が腐敗するのはなぜですか?
腐敗は、主として細菌やカビ等の微生物の繁殖が原因です。
遺体を栄養源として微生物などは繁殖を続けるため、特に暑い夏の季節は腐敗が早くなります。
そのため腐敗防止対策として、遺体保存用冷蔵庫やドライアイスなどを利用して、遺体の温度を下げることで、細菌などの微生物が繁殖するのをおさえ、腐敗の進行を防止します。
エンバーミングはいくらしますか?
エンバーミングの相場は、遺体の状態によっても違いますが、おおむね15万円~25万円です。
スポンサーリンク遺体搬送車についてのまとめ

ここまで遺体搬送車の手配についての情報や、遺体搬送車の費用などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 遺体搬送車は亡くなった場所から遺体を搬送する車のこと
- 遺体搬送にかかる費用は葬儀代金に含まれ、状況によって追加料金がかかる
- 自家用車での搬送は法律的に問題はないがリスクが大きい
- 遠方で亡くなった場合、飛行機などで搬送することもある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
お葬式の関連記事
お葬式
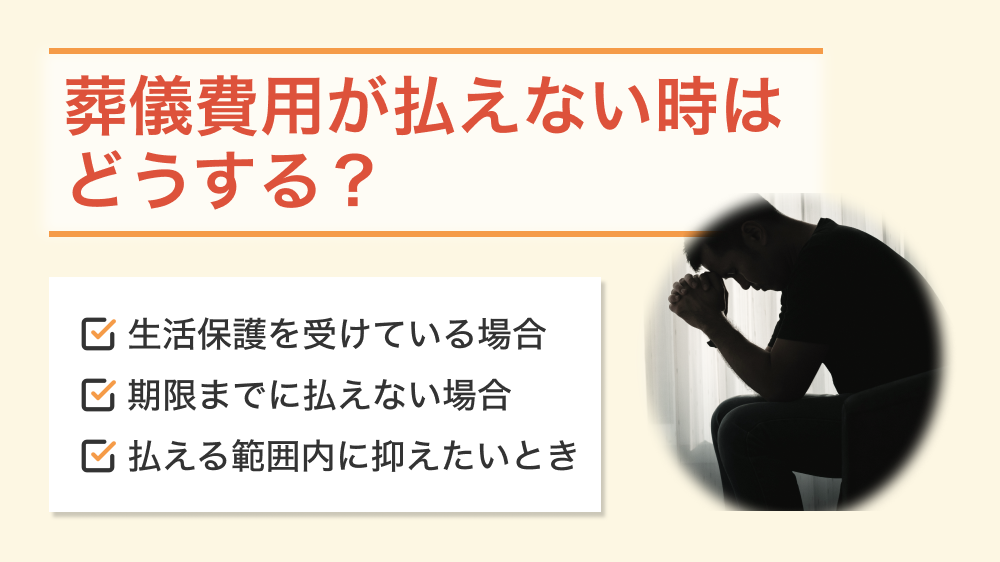
更新日:2025.07.16
葬儀費用が払えない時の対処法は?葬儀費用を安く抑える方法なども解説
お葬式

更新日:2022.11.20
斎場とは?定義や種類、選び方|みんなが選んだお葬式
お葬式

更新日:2025.06.17
互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説




