お葬式
家族葬の訃報連絡方法と近所への対応:内容、タイミング、例文を紹介
更新日:2024.04.05 公開日:2021.09.24

故人が逝去したことを知らせる訃報連絡ですが、一般的な葬儀であれば近親者、親族、故人の友人や知人、会社関係者、近所の方など幅広く連絡します。
しかし、家族葬は故人と近しい人達だけが参列して、少人数で執り行うお葬式です。
そのため、故人との関係性だけでなく、お葬式に参列する人、参列をしない人によって訃報の連絡のタイミングは異なります。
この記事では家族葬の場合の訃報連絡についてご紹介します。
訃報連絡の方法や内容、訃報連絡のタイミング、近隣住民への招待の是非、家族葬後の挨拶方法を関係性ごとに説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 家族葬の訃報連絡の範囲
- 家族葬の訃報連絡のタイミング
- 家族葬の場合の訃報連絡の内容
- 訃報連絡の方法
- 家族葬の場合の訃報連絡の例文
- 家族葬に近隣住民を招待するかどうかの決定ポイント
- 近隣住民からの訃報通知を受けた後の適切な対応
- 家族葬後の近隣への適切な挨拶方法
- 親しくない近所の人から訃報を聞いたときの対処法
- 近所の方から香典をいただいた場合
- 家族葬の訃報連絡のまとめ
家族葬の訃報連絡の範囲

故人が逝去したことを伝える訃報の連絡は、近親者や親族、友人、知人、会社関係者や近所の方に伝えます。
訃報の連絡をする際には、亡くなった日時や状況だけでなく、葬儀の予定も伝えますが、家族葬の場合は、参列者の範囲を限定しているため訃報の連絡は通常の葬儀と異なります。
家族葬を少人数の近親者のみで執り行う場合、参列する方には逝去後すぐ、または葬儀の日程が決まり次第連絡します。
しかし、参列しない方へも同じタイミングで連絡して、招く予定のない方が参列を希望してしまうとトラブルになる可能性があります。
そのため、基本的に家族葬に招かない方には、家族葬が終了してから訃報連絡をすると良いでしょう。
ただし、故人の会社関係者は、家族葬に招く予定が無くとも会社の手続きが必要な場合があるため、早めに連絡します。
家族葬の訃報連絡は、故人との関係性以外に、葬儀に参列する人と参列しない人、会社での手続きが必要かによって連絡する範囲やタイミングが異なります。
家族葬をお知らせする範囲について、以下で詳しく解説しています。
【2023年11月更新】横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区)の斎場情報<火葬場>:家族葬・葬儀の口コミ・費用・アクセス/みんなが選んだお葬式
スポンサーリンク家族葬の訃報連絡のタイミング

家族葬の場合の訃報連絡のタイミングを、関係性ごとにご紹介します。
家族・親族への訃報連絡
訃報は、家族や親族へ最初に連絡しますが、故人と関係性が深い方には危篤の段階でも連絡しておくことが望ましいです。
逝去後すぐに連絡を入れるため、家族や親族へは訃報と一緒に葬儀の日程を伝えることは難しいでしょう。
そのため、訃報の連絡をする際に、葬儀については詳細が決まり次第、再び連絡することを伝えてください。
また、疎遠になっている親族で、家族葬に呼ぶ予定がない場合は、家族葬が終了してから訃報を連絡する場合もあります。
しかし、基本的には三親等以内の親族や親交が深い親族には、故人の逝去後すぐに訃報を伝えるようにすると良いでしょう。
葬儀社や菩提寺への訃報連絡
故人が病院や介護施設で亡くなった場合、自宅や安置施設に搬送して葬儀の日まで安置する必要があります。
家族葬を執り行う葬儀社が決まっている場合は、葬儀社に訃報を連絡して安置施設に搬送してもらいます。
搬送後に葬儀の日程や内容などの打ち合わせを行います。
また、菩提寺などがある場合も家族や親族への訃報連絡が終わったら、優先的に連絡するようにしてください。
家族葬で読経を依頼するには、僧侶のスケジュールを把握してから葬儀社と打ち合わせをすると、スムーズに進められます。
職場への訃報連絡
故人が会社に勤めていた場合は、職場の上司や同僚、人事部への訃報連絡も必要になります。
故人の上司に連絡して、上司から人事部や同僚に伝えてもらうこともできますが、もし故人の上司の連絡先が不明であれば、会社の人事部に連絡してください。
訃報以外に、葬儀は近親者のみの家族葬で執り行うことも伝えると良いでしょう。
また、会社から香典や弔電を送ってくれる場合や、後日の弔問を希望する場合もあるため、辞退の意向があれば訃報の連絡と共に伝えるようにすると会社側も迷わずにすみます。
友人、知人への訃報連絡
友人や知人への訃報連絡は、故人との関係性の深さによって異なります。
故人と特に親しかったり、故人が生前に葬儀への参列を希望している友人であれば、逝去後すぐ、または家族葬の日程が決まってから訃報連絡をします。
一方、家族葬に招かない場合は、家族葬が終了してから連絡すると良いでしょう。
後日の弔問を希望されることもあるため、辞退したい場合は一緒に伝えておくと安心です。
近所の方への訃報連絡
故人が生前に近所の方と親しくしていた場合は、家族葬が終了してから訃報を伝えると良いでしょう。
しかし、近所の方と交流があったことを故人から聞いていても、どの方か分からなかったり、ひとりひとりに伝えるのは大変だったりします。
そのような場合は、自治会や町内会の会長へ連絡して、回覧板を回してもらう方法もあります。
ただし、家族葬を自宅で執り行う場合は、近隣の駐車場を利用するなど近所の方の理解が必要になります。
そのため、葬儀前に自治会や町内会の会長へ訃報を連絡して、自宅で近親者のみの家族葬をすることを伝えておくとトラブルになる可能性を減らせます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
家族葬の場合の訃報連絡の内容

訃報の連絡をする際は、簡潔に要点を伝えます。
故人の名前、逝去日、享年、家族葬の日時や場所、香典や供花の有無、喪主の名前と連絡先、宗教宗派も伝えておくと参列の準備がしやすくなります。
故人の死因を伏せたい場合は、伝えなくても問題ありません。
家族葬は執り行う遺族によって、参列者の範囲や、香典を受け取るか辞退するかが異なります。
香典や供花を辞退したい場合は、訃報の連絡と共に伝えるようにしましょう。
訃報連絡の方法
訃報の連絡方法は、電話やメール、ハガキがあります。
以下で項目ごとにご紹介します。
電話
電話での訃報連絡は、迅速かつ確実に伝えることができるため、家族や親族への連絡に向いています。ただし、連絡する時間帯に注意する必要があります。
近親者への連絡は、早期の連絡が必要なため、時間帯は気にしなくて大丈夫ですが、親族への連絡は早朝や深夜は避けるようにしましょう。
メール
メールでの訃報の連絡は、電話が繋がらなかった人や、時間帯が深夜や早朝で電話での連絡が難しい場合に利用すると良いでしょう。
取り急ぎメールで連絡をし、落ち着いてから再度電話で詳細を伝えてください。
メールのみでは読んでいない可能性もあるため、改めて電話で連絡を入れると行き違いなどを避けることができます。
ハガキ
ハガキでの訃報の連絡は郵送に時間がかかるため、家族葬に参列しない方に事後報告をする際に用いると良いでしょう。
訃報の連絡と葬儀は近親者のみで行ったこと、生前の感謝も伝えるようにしてください。
後日の弔問を希望する方もいるため、辞退の意向がある場合は記載しておくと相手側も配慮してくれます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
家族葬の場合の訃報連絡の例文

訃報連絡を電話でする場合の例文と、家族葬が終了してから訃報を事後報告する場合の例文をご紹介します。
家族葬の範囲や喪主挨拶|弔問や香典の辞退の仕方とは
電話での訃報連絡の例文
電話は早く訃報をお伝えしたい時に、迅速かつ正確に情報をお伝えすることが出来ます。
以下の例文を参考に、事前に必要な情報を整理しましょう。
<例文>
「突然のお電話で申し訳ありません。私、〇〇(故人名)の長男(故人との関係)の、△△と言います。
実は先ほど、〇〇(故人名か、「父」など続柄)が息を引き取りました。
生前、●●(連絡相手の名前)さんには大変お世話になりました、ありがとうございました。
葬儀は父の生前からの意向を尊重して、家族葬で執り行います。
通夜を○月○日○時から、葬儀・告別式は○月○日○時から△△(葬儀場の場所)で執り行い、喪主は私が務めます。
大変失礼とは存じますが、香典や供花、供物、弔電などの一切は辞退させて頂きます。
何かございましたら、私の携帯電話までご連絡賜れば幸いです。
〇〇〇…(電話番号)です。よろしくお願いいたします。」
故人との続柄をしっかり伝え、生前のご厚誼について感謝を述べます。
また、香典や供花、供物、弔電を辞退する意向がある場合は、一緒に伝えると良いでしょう。
葬儀の日程が決まっていない場合は訃報の連絡のみに留め、葬儀の日程が決まり次第、再度連絡することを伝えてください。
家族葬が終了してからの訃報連絡の例文
家族葬に招かなかった方に、葬儀終了後に訃報を連絡する際はハガキで伝えることが一般的です。
訃報の連絡だけでなく、葬儀が近親者のみで終了したこと、生前の感謝も一緒に伝えます。
ハガキでの例文は以下の通りです。
<例文>
「このたび 父〇〇儀
〇年〇月〇日 享年〇〇歳を持って永眠致しました
なお 本人の遺志により葬儀は近親者のみにて相済ませました
ここに謹んでご報告申し上げます
故人が生前賜りましたご厚誼に深く感謝を申し上げ 略儀ながらご挨拶とさせて頂きます
〇年〇月〇日
〇〇(喪主名)親族一同」
近所の方に回覧板で訃報連絡する場合の例文
回覧板には、故人の情報や家族葬である旨をしっかりと記載しましょう。
自治会長や町内会長に直接回覧板の手配について問いあわせると良いでしょう。
以下の例文をご参考ください。
<例文>
「訃報
このたび △△町内会 〇〇様が〇年〇月〇日享年〇歳にて永眠されました
ここに謹んでお悔やみ申し上げます
なお ご本人の遺志により 葬儀は家族葬で執り行われます
ご家族の皆さまより 生前〇〇様に対し△△町内会の皆さまのご厚情に深く感謝申し上げますとのこと
また家族葬という特性上 勝手ながら ご会葬 ご香典 ご供花 お供物 ご弔電などの一切は辞退させて頂きたい旨
皆さまにお伝えいただきたいとのことですので併せてご報告申し上げます
〇年〇月〇日
△△町内会長 ●●」
上記は町内会側で文面を用意していただいた場合です。
故人名や家族葬で執り行う旨を明記し、遺族から生前のご厚情に対する感謝をお伝えします。
家族葬でご会葬やご香典を辞退する場合は、はっきりとその意向を伝えましょう。
家族葬に近隣住民を招待するかどうかの決定ポイント
家族葬は、その名の通り主に家族だけで行う小規模な葬儀のイメージがあります。
しかし、近隣の方々を招待することになった場合、どのような基準で選定するかは、遺族の判断に委ねられます。
以下では、近隣の人々を招待するかどうかを決める際の主な2つのポイントについて解説します。
葬儀の規模に基づいて決定
家族葬と聞くと、ごく少数の参列者で行われると想像するかもしれませんが、実際には30名程度の中規模な葬儀を指す場合もあります。
このような規模が大きめの家族葬では、近隣の方を招待する余地があります。
もし招待する場合は、参列の事実を他言無用であることを伝え、招待されなかった方々の間での不快感を避けましょう。
故人との関係深度を考慮
故人と近隣住民との間の親密さは、招待の可否を判断するうえで重要なポイントです。
たとえば、故人が生前、近隣の方々と頻繁に食事を共にしたり、互いに助け合っていたりした場合は、招待を検討する価値があります。
仮に招待しない場合でも、故人の突然の不在を心配している近隣の方々へは、できるだけ早く訃報を伝えることが望ましいです。
この2つのポイントを参考に、故人の意思を尊重しつつ、遺族の皆様が納得のいく家族葬を実現できるよう、慎重に招待リストを検討してください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
近隣住民からの訃報通知を受けた後の適切な対応
近所の方から訃報を受けた際にどのように対応すべきか、多くの人が悩む状況です。
特に家族葬の場合、遺族が限られた人々のみで故人を偲ぶことを選ぶことがあり、近隣住民としてはどのように遺族の気持ちを尊重しつつ、故人への哀悼の意を表現すれば良いのか迷うことも少なくありません。
ここでは、そんな時に心に留めておきたいポイントを3つに分けてご紹介します。
お悔やみの言葉を伝える
お悔やみの言葉の伝え方から、香典や弔問の検討、遺族への配慮に至るまで、故人と遺族への敬意を形にするためのヒントを探ります。
訃報を受け取り、葬儀が家族のみで行われたことを知らされた際の対応方法は、故人への敬意と遺族への配慮を重視する形で行うべきです。
最も基本的な対応は、心からのお悔やみを表すことです。
この時、一般的に使用される「ご愁傷様です」や「心よりお悔やみ申し上げます」といった表現は、遺族の心情に寄り添う敬意を示すための適切な言葉選びの一例です。
これらの言葉を用いる際は、故人を偲ぶ穏やかな心持ちを忘れずに。
香典や弔問の検討
香典や供物の贈呈については、遺族の意向を尊重することが何よりも大切です。
香典の金額や供物の種類には一定の相場がありますが、遺族が辞退している場合にはそれを強行することは控えましょう。
遺族への追加的な負担を考え、まずは確認を取ることが礼儀です。
特に、故人との親密度に応じた香典の金額設定や、消耗品や故人が好んでいたものを選ぶという心遣いが求められます。
遺族への配慮
また、弔問についても遺族との関係性やタイミングを考慮する必要があります。
葬儀後の遺族は多忙を極めることもあるため、訪問の意向をあらかじめ伝え、了承を得ることがマナーとされています。
弔問の際は、過度に華美でない服装を選び、訪問は短時間に留めるなど、遺族の負担を最小限にする配慮が重要です。
このように、訃報を受けた後の行動は、故人への最後の敬意として、また残された遺族への思いやりとして、慎重に選ぶべきものです。
スポンサーリンク家族葬後の近隣への適切な挨拶方法
家族葬の後、近隣の方々へどのように挨拶回りをすれば良いかは、多くの遺族が直面する疑問の一つです。
家族葬はその性質上、限られた人々のみで行われるため、近所への配慮が特に必要となる場面もあります。
葬儀の際の人の出入りや、それに伴う騒音などで、知らず知らずのうちに近隣住民にご迷惑をおかけしていることもあるでしょう。
このような背景から、葬儀後には適切なタイミングで、心を込めた挨拶回りを行うことが大切です。
以下では、その挨拶回りの適切な方法について、具体的な手順とポイントをご紹介します。これらのステップを踏むことで、今後も良好な近隣関係を維持するための礎を築くことができるでしょう。
挨拶回りの適切なタイミング
家族葬が終わった直後、心は疲れているかもしれませんが、近所への挨拶回りは可能な限り早めに行うことが望ましいです。
理想的には葬儀の翌日から翌々日にかけて訪問し、遅くとも初七日までには終えるよう心がけましょう。
この速やかな対応が、近隣住民への配慮と故人への敬意を示すことにつながります。
事前に電話等で相手の都合を確認し、急な訪問で不便をかけないようにするのが理想的ですが、近所ならではの臨機応変な対応も大切です。
手土産の準備
挨拶回りには、軽い手土産を持参することが一般的です。
この手土産は、葬儀によって近隣におかけした迷惑への謝罪と、これまでのお付き合いへの感謝を表すものです。
菓子折りや小さな贈り物が適しており、2,000円から3,000円程度のものを選ぶのが相場とされています。
また、供花や供物をいただいた場合は、そのお礼として少し高価なものを選ぶと良いでしょう。
挨拶回りの具体的な内容
挨拶をする際は、故人への感謝の気持ち、葬儀に伴うご迷惑のお詫び、そして無事葬儀を終えたことの報告を簡潔に伝えます。
心からの感謝と今後も変わらぬ関係を続けていきたいという意向を表明することが重要です。
挨拶は短時間で、相手の時間を尊重する態度が求められます。
適切な挨拶回りによって、故人への最後の敬意と、近隣との良好な関係が築かれます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
親しくない近所の人から訃報を聞いたときの対処法
近所の方の訃報を受けた際の対応は、状況に応じて異なりますが、基本的には以下のように行動することをお勧めします。
自治会が存在する場合
葬儀前に知った時
自治会からの訃報連絡を受けた場合、自治会の方針に従い、可能であればお通夜や葬儀に参加することを推奨します。
地域の習慣に沿った行動は、後のコミュニティ内での生活をスムーズにします。
お香典の金額や服装について不安があれば自治会長に相談しましょう。
多くの場合、地域に根ざした慣習に従うことが望ましいです。
葬儀後に知った時
葬儀が終了した後で訃報を知った場合でも、自治会関係者に相談してみてください。
適切なアドバイスをもらうことができ、地域の皆さんとの関係性にも影響を与えます。
また、今後自分が自治会長等の役割を担う可能性を考え、学びの機会とするのも良いでしょう。
自治会が存在しない場合
葬儀前に知った時
面識がない場合、特に行動を起こす必要はありませんが、偶然家族と接触した際は、素直な気持ちでお悔やみの言葉を伝えることができます。
「お力になれることがあれば」という言葉を添えると、相手に寄り添った気持ちが伝わります。
葬儀後に知った時
この場合も、特に行動を起こす必要はなく、もし偶然遭遇した際には「少し前にご不幸があったと聞きましたが、お変わりありませんか?」と声をかけることが適切です。
どの状況においても、過度な行動は避け、自然体での対応が最も良いでしょう。
地域社会や習慣に敬意を払いつつ、無理なく自分にできる範囲での配慮が求められます。
面識がない場合に過剰に関わることは、時には反対の効果を生むこともあるため、慎重に判断することが重要です。
スポンサーリンク近所の方から香典をいただいた場合
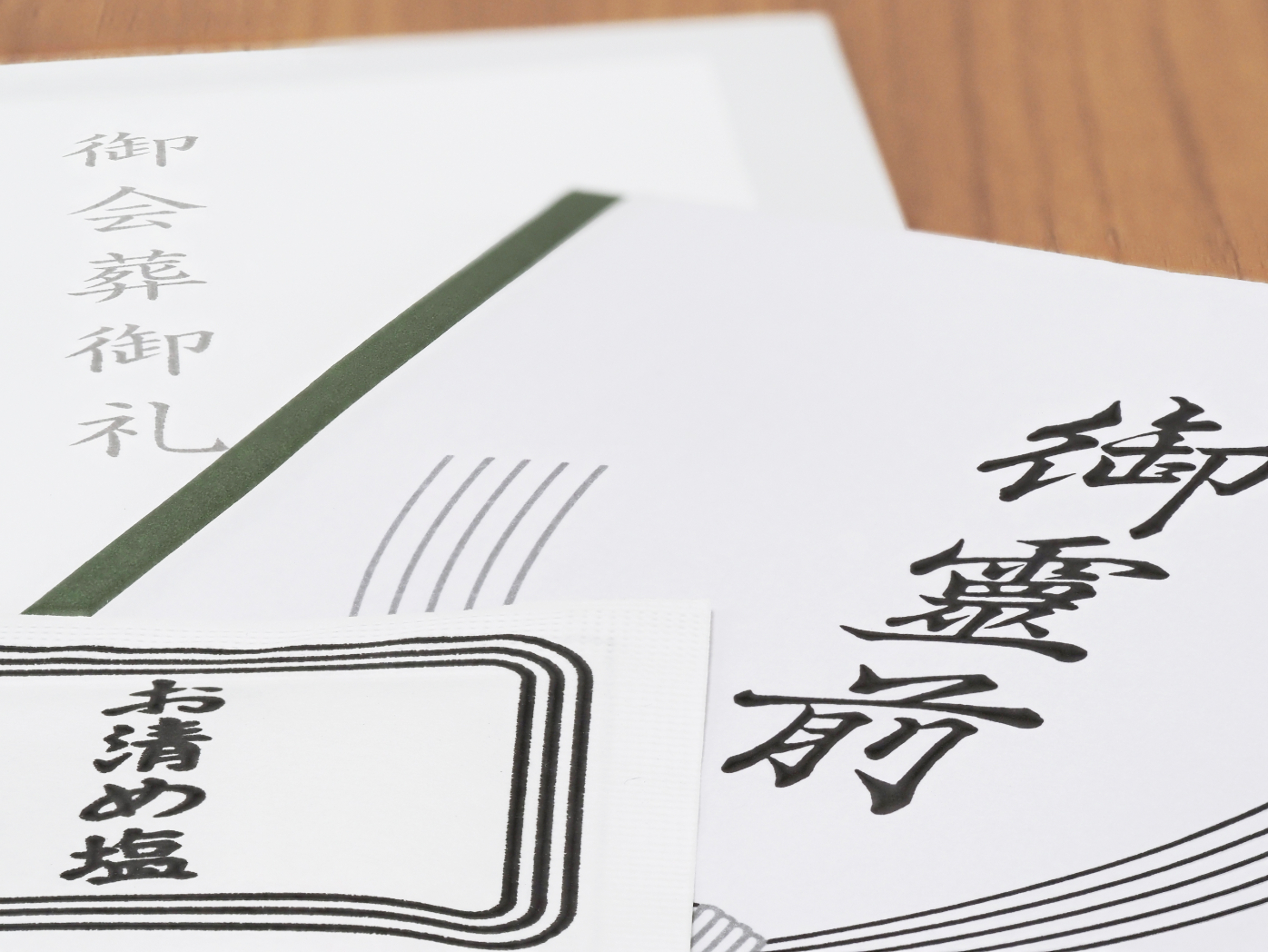
ご会葬やご香典を辞退されている場合でも、近所の方から会葬や香典を頂く場合があります。
事前に辞退の意向を周知している場合は、辞退の旨を改めて伝え、ご理解頂くのが良いでしょう。
弔問については、葬儀まで少し日数がある場合は可能な限り対応なさるご遺族もいらっしゃいます。
葬儀後や四十九日を過ぎて落ち着いているであろう時期をお伝えし、その場はお帰り頂いても良いでしょう。
弔問の流れでご香典を頂きそうになった場合は、改めて丁寧に辞退の意をお伝えします。
何度かお断りしても、どうしてもと御香典を差し出される場合は頂戴し、丁寧にお礼をしましょう。
香典を受け取った場合は、香典返しも忘れないようにしましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
家族葬の訃報連絡のまとめ

これまで、家族葬の場合の訃報連絡を中心にご紹介しました。
この記事のポイントをおさらいすると、以下の通りです。
- 家族葬に参列する人をしない人で訃報連絡のタイミングを変える
- 電話は迅速に訃報を連絡できる
- 事後連絡の場合、トラブルにならないよう配慮する
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
お葬式の関連記事
お葬式
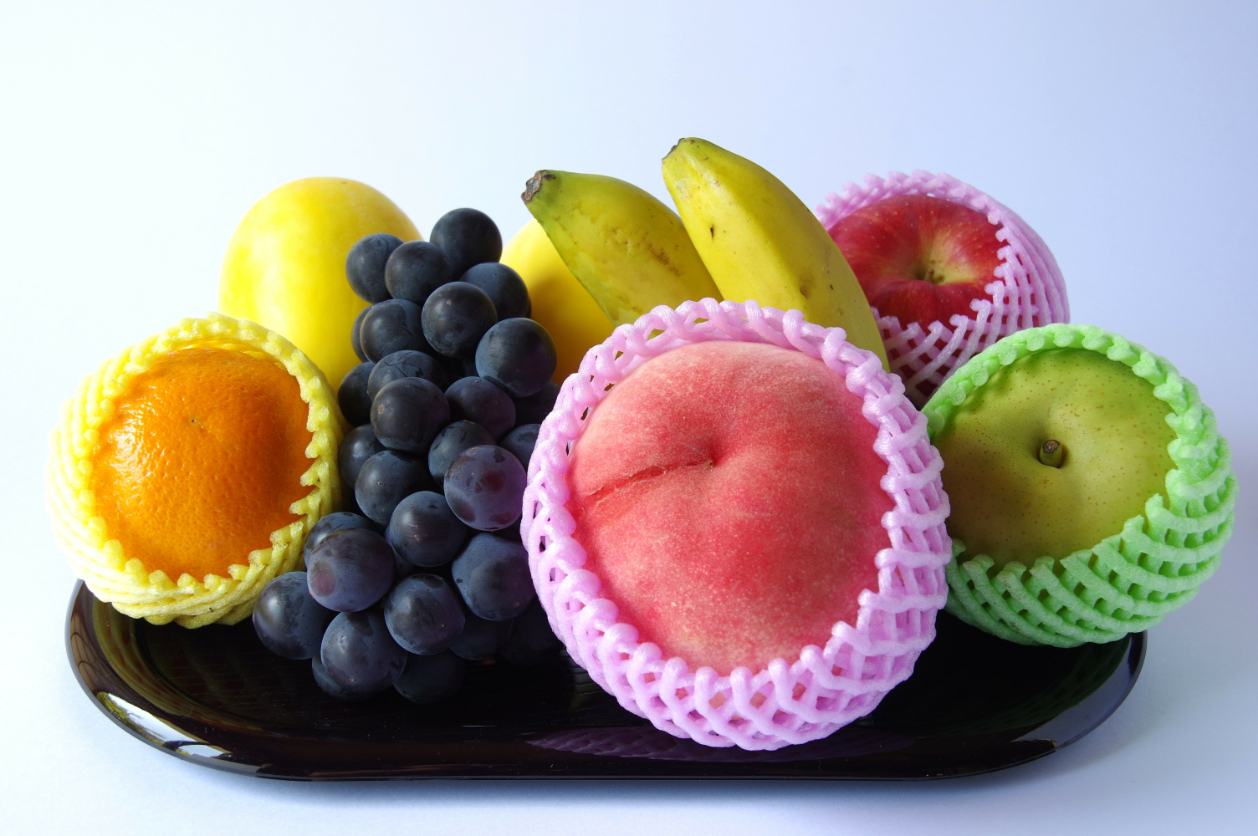
更新日:2024.02.04
家族葬で香典の代わりに贈る品物はなにがいい?マナーや相場を解説!
お葬式

更新日:2024.02.04
家族葬の場合は弔電を送るべきか?弔電を辞退された場合や文例などを解説




