お葬式
箸渡しのマナーとは?箸渡しの意味や流れなどについて解説
更新日:2024.01.24 公開日:2022.07.06

記事のポイントを先取り!
- 箸渡しは故人が無事に三途の河を渡れることを願った儀式
- 箸渡しは2人1組となって実施するのが基本
- 箸渡しは故人と関係の近い親族から順に実施するのが基本
- 理由があれば、箸渡しを実施することを拒否することが可能
箸渡しのマナーについてご存じでしょうか。
そもそも、箸渡しの意味や流れについて知らない方も多いかと思います。
そこでこの記事では、箸渡しのマナーについて解説します。
この機会に、箸渡しに込められた意味も知っておきましょう。
後半では、箸渡しの拒否は可能かどうかについて触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
箸渡しとは

箸渡しとは、遺骨を箸から箸へと渡していき、骨壺に収めていく儀式のことです。
葬儀に参加した人全員が行うのではなく、火葬まで参加した、故人と近しい家族や親戚だけで実施することになります。
これには、そもそも、火葬場に入ることのできる人数が限られていて、そうせざるを得ないという理由があります。
使用する箸の素材は、火葬場によって異なり、そこで準備されているものを使用することになるのが一般的です。
また、こうした箸渡しは、遺体を土に埋めて、基本的に骨を見ることのない土葬では実施されません。
箸渡しに込められた意味
箸渡しの箸は、川などにかかっている橋と発音が同じになります。
そこで、箸渡しには、橋渡しという意味も含まれています。
故人が亡くなったら、あの世で三途の河を渡らなければなりませんが、この橋渡しが無事にできるように、という意味が込められています。
このほかにも、この世とあの世の橋渡しを無事にできるようにという考え方もあります。
また、民俗学的には、故人の遺骨には穢れがまとわりついているとされていて、骨を拾うことで、その穢れを受けてしまうと考えられているようです。
こうしたことにくわえて、東日本では遺骨は全て収骨するのに対し、西日本では、部分収骨といって、一部分しか収骨しない違いがあります。
過去に自分が行った箸渡しの時とやり方や考え方が違っても、それはその地域に根差した大切な文化ですので、おかしいとは思わずに、きちんと理解していくことが重要です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
知っておくべき箸渡しのマナー
箸渡しの際に、マナーを守らずに行動してしまうと、恥ずかしい思いをすることになります。
そこでここでは、知っておくべき箸渡しのマナーについて解説します。
2人1組で行う
箸渡しは、2人1組で実施することが一般的です。
火葬後、故人の遺骨が乗った遺骨台を挟んで向かい合う人同士で、骨を同時に箸でつかみ、骨壺に入れていきます。
ここでは、1人が骨をつかみ、もう1人は骨を箸で支えるようにするスタイルと、同時に骨を箸でつかみながら骨壺へと移動させるスタイルがあります。
あるいは、1人が遺骨を箸でつかみ、もう1人がそれを箸でつかんで受け取り、その後骨壺へ納める、というスタイルもあります。
こうした形は、葬儀社によって指示されるので、それに従うとよいでしょう。
また、男女でペアになる、とされている場合もありますが、男女がそろわない場合は、これに従わなくても、マナー違反とはなりません。
また、一人で遺骨をつかみ、直接骨壺へ納める場合もあるので、こうした内容が指示されたときには、その方法に従います。
関係が深い遺族から行う
箸渡しは、故人から見て、血縁の濃い人から実施するのが基本となっています。
そのため、偶然箸を配っている人のそばにいて、一番に箸をわたされたからといって、
一番初めに遺骨をつかんでしまうのはマナー違反となります。
順番は、一般的には喪主、故人の家族、親戚、という順番が一般的です。
その後、もし知人や友人がいた場合は、故人との親交が深かった順など箸渡しを実施します。
箸渡しを行う回数は1人1回
箸渡しを行うのは、1人1回が原則とされています。
特に指示のない場合、1人で数回箸渡しを実施するのはマナー違反なので避けましょう。
ただし、東日本では、遺骨の全部を拾うような習慣があります。
こうした場合、1人1回では全ての遺骨は拾えませんので、2回目以降の箸渡しを実施する場合もあります。
西日本出身で、1人1度の箸渡しがマナーとして浸透している地域の方でも、葬儀社の職員や遺族などから指示された場合は、それに従うのがマナーです。
場合によっては、数回の箸渡しが実施された後、急いで骨を骨壺に納めるよう指示される場合もありますが、驚くことなく、大切な文化だということを理解して臨みましょう。
長さ・素材の違う箸を左右一組にする
箸渡しに使用する箸は、葬儀社が用意しているものを使用することになります。
多くの葬儀場では、長さや素材の違う箸を一組として、用意しています。
また、左右で長さが不揃いの箸が用意されているケースもあります。
これは、突然の葬儀のため、箸が揃っていないことにも気づかないほどあわてていた、という意味を持たせているとされています。
足の骨から徐々に上の骨を拾う
箸渡しの際に、遺骨は足の方の骨から順に体の上部に向かって拾っていくのがマナーとなっています。
頭の方に自分が立っていたとしても、近くの骨を拾うのはマナー違反になりますので、移動して足の方から拾うようにしなければなりません。
上部にいく順番は、足、腰、上半身、喉仏の順になります。
最後に頭蓋骨を納めると、箸渡しは終わります。
喉仏は、特に別の骨壺が用意されている場合もありますので、拾わないように指示があった場合は、それに従いましょう。
また、場合によっては、喉仏が最後に骨壺に納められる場合もあります。
箸渡しを行う流れ

ここでは、箸渡しを行う際の大まかな流れについて解説します。
遺骨の周りに集合する
火葬が終わったら、葬儀社や火葬場の職員により、その旨が知らされます。
職員の指示に従い、喪主や遺族・参列者は、火葬台の周りに集合します。
2人1組になる
箸渡しは、2人1組で実施することが一般的です。
火葬後、故人の遺骨が乗った遺骨台を挟んで向かい合う人同士で、骨を同時に箸でつかみ、骨壺に入れていきます。
1人が骨をつかみ、もう1人は骨を箸で支えるようにするスタイルと、同時に骨を箸でつかみながら骨壺へと移動させるスタイルがあります。
あるいは、1人が遺骨を箸でつかみ、もう1人がそれを箸でつかんで受け取り、その後骨壺へ納める、というスタイルもあります。
こうした形は、葬儀社によって指示されますので、それに従うとよいでしょう。
また、男女でペアになる、とされている場合もありますが、男女がそろわない場合は、これに従わなくても、マナー違反とはなりません。
また、一人で遺骨をつかみ、直接骨壺へ納める場合もあるので、こうした内容が支持されたときには、その方法に従います。
故人と関係が深い人から遺骨を骨壺へ納める
箸渡しは、故人から見て、血縁の濃い人から実施するのが基本となっています。
そのため、偶然箸を配っている人のそばにいて、一番に箸をわたされたからといって、
一番初めに遺骨をつかんでしまうのはマナー違反となります。
納める順番は、喪主、故人の家族、親戚、という順になります。
その後、もし知人や友人がいた場合は、故人との親交が深かった順など箸渡しを実施します。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
箸渡しは拒否することも可能

箸渡しをすることに対して事情がある場合は、拒否することも可能です。
こうした場合、喪主や葬儀の代表者にその旨を伝えて、火葬に参加せずに、火葬施設の前で待ったり、葬儀会場で待ったりすることもできます。
特に、遺骨となった故人を見るのが怖いという感情は、自然なものです。
そのほか、故人と仲が悪かった、というような理由もあります。
喪主や代表者など、遺族に本音を伝えてしまうと、あまりよい印象を持たれない理由のある場合は、葬儀社の担当者などに伝えておくことをおすすめします。
その場合、理由は遺族に伝えないでほしいと伝えておけば、ある程度プライバシーを守って、参加しないことを承知してくれる場合があります。
子供の場合
子どもが幼い場合、遺骨を見てショックを受け箸渡しを前に泣き出してしまう場合や、箸渡しを拒んでしまう場合があります。
この場合、子どもが箸渡しで泣いている理由が悲しみからなのか、恐怖からなのかをきちんと把握する必要があります。
遺骨を前にした恐怖の感情は、子どもの場合は自然なものですので、いくら遺骨となった故人が大切な人であったからといって叱ることはしないでください。
また、こうした場合、無理に箸渡しをさせず喪主や代表者に丁寧に説明し、場合によっては遺骨の見えない場所に子どもを連れ出すことも必要です。
正当な理由がある場合は、無理に箸渡しには参加しなくても、きちんと理由が説明できればマナー違反にはなりません。
また西日本では部分収骨の文化があり、場合によっては収骨自体を実施しないという選択肢を取ることができる自治体もあります。
こうした場合、遺骨は自治体で供養されていくことになります。
箸渡しについてよくある質問
箸渡しについてのよくある質問をご紹介します。
食事中に箸渡しがダメな理由は何故ですか?
食事の席で箸から箸へ料理を渡す「箸渡し」がマナー違反とされるのは、火葬場で故人の骨上を行う時に同じ動作をするためです。
不幸ごとを避けるために、葬儀で行われる慣習は日常の生活では行わないようにしてください。
箸渡し中に遺骨を落としてしまった場合はどうすればいいですか?
箸渡しは普段の生活で行う動作ではないので遺骨を落としてしまうこともあります。
落としてしまったときは慌てずに係員に伝えてください。
箸渡し中に遺骨を落としてしまってもやり直すことが可能です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
箸渡しのマナーのまとめ

ここまで箸渡しのマナーについて解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 箸渡しは故人が無事に三途の河を渡れることを願った儀式
- 箸渡しは2人1組となって実施するのが基本
- 箸渡しは故人と近い親族から順に足の方の骨から上方に向かって拾う
- 理由のある場合は、箸渡しをすることを拒否できる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.11.19
近所の人の出棺の見送りへは行くべき?服装の注意点は?
お葬式
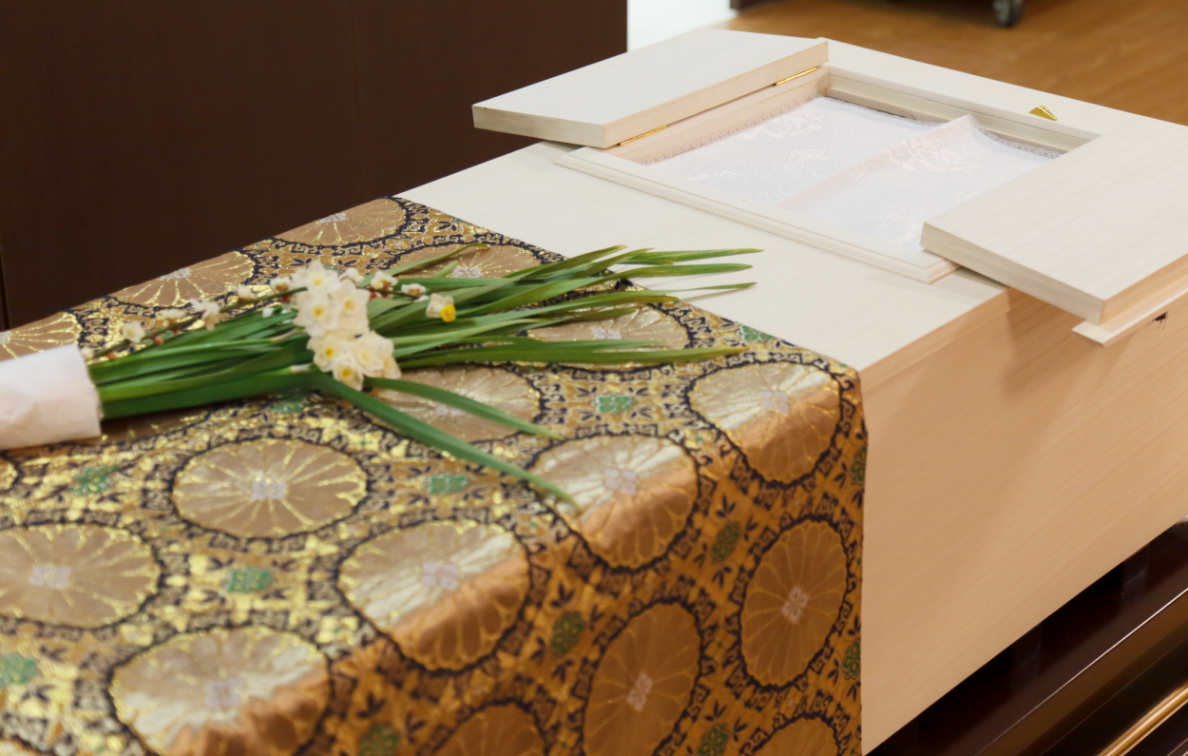
更新日:2025.06.17
孤独死とは?発見から葬儀までの流れや費用、これからできる対策についても解説
お葬式

更新日:2022.11.17
骨上げをしない事は可能?しなかった場合、遺骨はどうなる?
お葬式

更新日:2024.03.13
火葬とは?火葬にかかる費用や時間、流れや仕組みなど解説
お葬式

更新日:2024.01.24
「荼毘に付す(だびにふす)とは?意味や使い方、例題でわかりやすく
お葬式
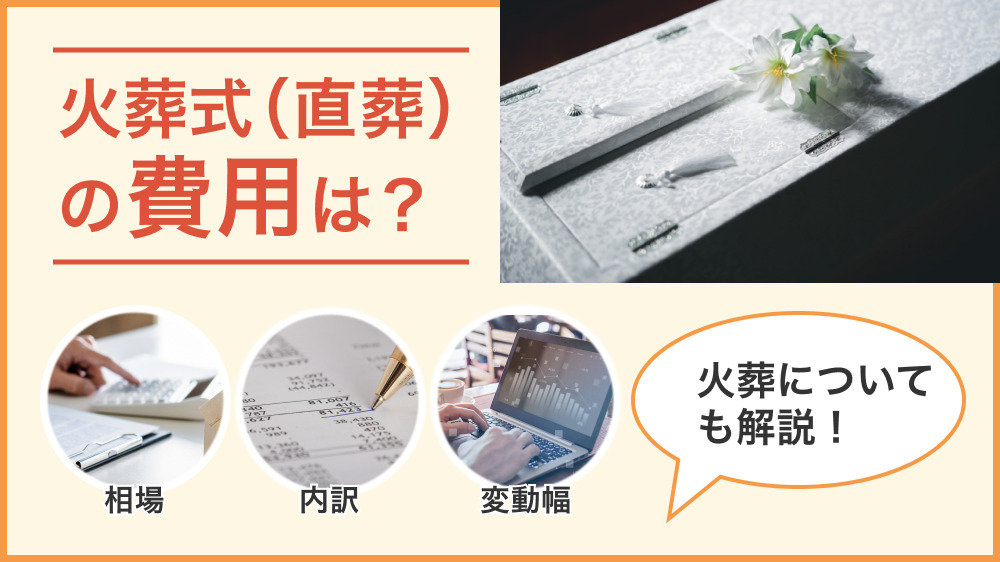
更新日:2025.06.29
葬式なしの火葬費用の相場は?直葬・火葬式の費用を抑える方法についても併せて解説




