お墓
火葬後すぐ納骨してもいい?納骨にふさわしいタイミングを解説
更新日:2022.05.18 公開日:2021.11.27

記事のポイントを先取り!
- 火葬後すぐに納骨することは可能
- 四十九日法要と同時に納骨するのが一般的
- 火葬後すぐに納骨する場合は時間に注意
納骨は、時代の移り変わりや地域の風習によって納骨するタイミングが変わってきます。
そこで、この記事では納骨にふさわしいタイミングについて解説していきます。
火葬後すぐに納骨する地域についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。
納骨にふさわしいタイミング

結論からお伝えすると、納骨のタイミングに決まりはありません。
法律などできちんと決められたものがないからです。
とはいえ多くの場合が、下記のときに納骨されることが多いです。
- 火葬後すぐ納骨する
- 四十九日法要の後納骨する
- 百か日法要の後納骨する
- 一周忌で納骨する
- 三回忌で納骨する
それぞれの場合に分けて、順番に解説していきます。
火葬後すぐ納骨する
葬儀をして、火葬後すぐに納骨するというパターンも多いようです。
これはお墓がすでにある状況が前提ですが、1日で葬儀から納骨までできるのが大きなメリットといえます。
しかし、朝から夜まで慌ただしく、亡くなったことを悲しむ間もなく1日が過ぎてしまうため、後悔してしまう場合もあるようです。
気持ちの整理がつき、火葬後数日経ってから納骨という場合もあるようです。
四十九日法要の後納骨する
四十九日法要の後に納骨することが最も一般的です。
四十九日法要は、故人が亡くなって四十九日に行う法要で、仏教において「故人が浄土に行ける日」とされています。
この法要の意味合いは、遺族が集まりきちんと浄土にいけるよう供養をするというものがあります。
そのため、遺族が集まる四十九日法要に納骨されることが多いです。
こちらも納骨できるお墓がすでにあることが前提になってきます。
百か日法要の後納骨する
百か日法要は、故人が亡くなって100日後に行われる法要のことです。
大切な人が亡くなったその悲しみから、徐々に立ち直って元の生活に戻らなければいけません。
その区切りとして行う法要でもあります。
四十九日法要と同じように遺族や関係者が集まるときなので、このタイミングも納骨するのによい時期だといえます。
お墓がなかった方も、この時期にお墓ができる場合が多いです。
もし、はじめて納骨される場合はこのタイミングで納骨できることを目標にしておくとよいでしょう。
一周忌で納骨する
遺族や近親者が喪に服すことから区切りをつけるべきタイミングなのが、この一周忌になります。
喪中では正月や結婚式などの祭事を行わないようにする風習がありますが、一周忌を迎えると喪に服す期間は終わり、一区切りつける時期だとされています。
亡くなった悲しい現実をなかなか受け入れられなかった人も、一周忌を迎え少しずつ心の整理がつく頃です。
この機会に納骨を考えてもよいかもしれません。
三回忌で納骨する
最初に納骨をする時期に決まりはないとお伝えしましたが、遺族にも心配されてしまうので、遅くても三回忌あたりまでには納骨を済ませるようにしましょう。
お墓はいわゆる亡くなった方のための「家」になります。
悲しみから立ち直る意味合いも含め、納骨できるようにするとよいでしょう。
火葬後すぐに納骨するときの注意点
次に、火葬後すぐに納骨するときの注意点を解説していきます。
火葬の時間に注意が必要
まず火葬後すぐに納骨するときの注意点として、火葬を行う時間に注意が必要です。
例えば、火葬する時間が14時30分頃になってしまうと、納骨するタイミングは18時前後になってしまいます。
夏場ならよいかもしれませんが、冬場などは真っ暗な状況の中、納骨をしなければいけません。
そのため、火葬の時間はなるべく早くできるように注意が必要です。
墓地への確認が必要
上記のように、薄暗くなる時間になってしまうと納骨できない場合もあるので、事前に墓地への確認をする必要があります。
たとえば寺院の境内墓地の場合は、前もって連絡しておけば納骨することもできます。
霊園などは閉門の時間も厳しいため、事前に問い合わせを行いましょう。
そして、その日の何時くらいに納骨ができるかをきちんと調べておくようにしましょう。
みんなが選んだお墓の電話相談
みんなが選んだお墓ではお墓選びのご相談に対応しております。 お客様のご希望予算と地域に応じた霊園をご提示することも可能ですので遠慮なくお申し付け下さい。24時間365日無料相談
電話をかける
後悔しないお墓選びのためにプロのお墓ディレクター
を無料でご紹介いたします。
沖縄では火葬後すぐに納骨する?

供養や納骨の方法などは、地域などによっても様々です。
特に沖縄では、他の地域では見ることができない、仏教と合わさった沖縄独自の風習があります。
沖縄では遺骨を自宅に持ち帰ってはいけない
沖縄では死を「穢れ」と考えられているため、遺骨を自宅に持ち帰ってはいけないという風習があります。
遺骨を自宅へ持ち帰ると、悪霊がついてきたり、故人が家に住み着いたりしてしまうと考えられています。
そのため、火葬場から故人の遺骨を自宅に持って帰ることはタブーとされてきました。
沖縄の納骨の慣習
死をケガレだと考えているため、納骨前、お墓に移動するときは黒い傘を遺骨にさすこととされています。
また、納骨の帰り道は来た道と違う道を通ることが通例です。
これは帰り道に「悪霊がついてこないように」という意味が込められています。
納骨後7日間は毎日お墓参りをする
沖縄の独特な風習として、「ナーチャミー」と呼ばれるものもあります。
それは、亡くなったすぐ納骨した方のお墓に、7日間は毎日お墓参りをするものがあります。
以前は、若い人が亡くなった場合に墓の周りで宴会を行っていました。
火葬後すぐの納骨まとめ
ここまで火葬後すぐの納骨についての情報を中心に書いてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 納骨は火葬後すぐに行うのに加え、法要のタイミングで納骨することもある
- 火葬の時間と墓地への確認を取ることに注意する
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

4つの質問で見つかる!
ぴったりお墓診断
Q.お墓は代々ついで行きたいですか?
都道府県一覧からお墓を探す
こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。

こちらでご希望のエリアからお墓を検索できます。
監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。
お墓の関連記事
お墓

更新日:2024.01.24
家族のみで納骨するには?納骨する流れや注意点も紹介
お墓
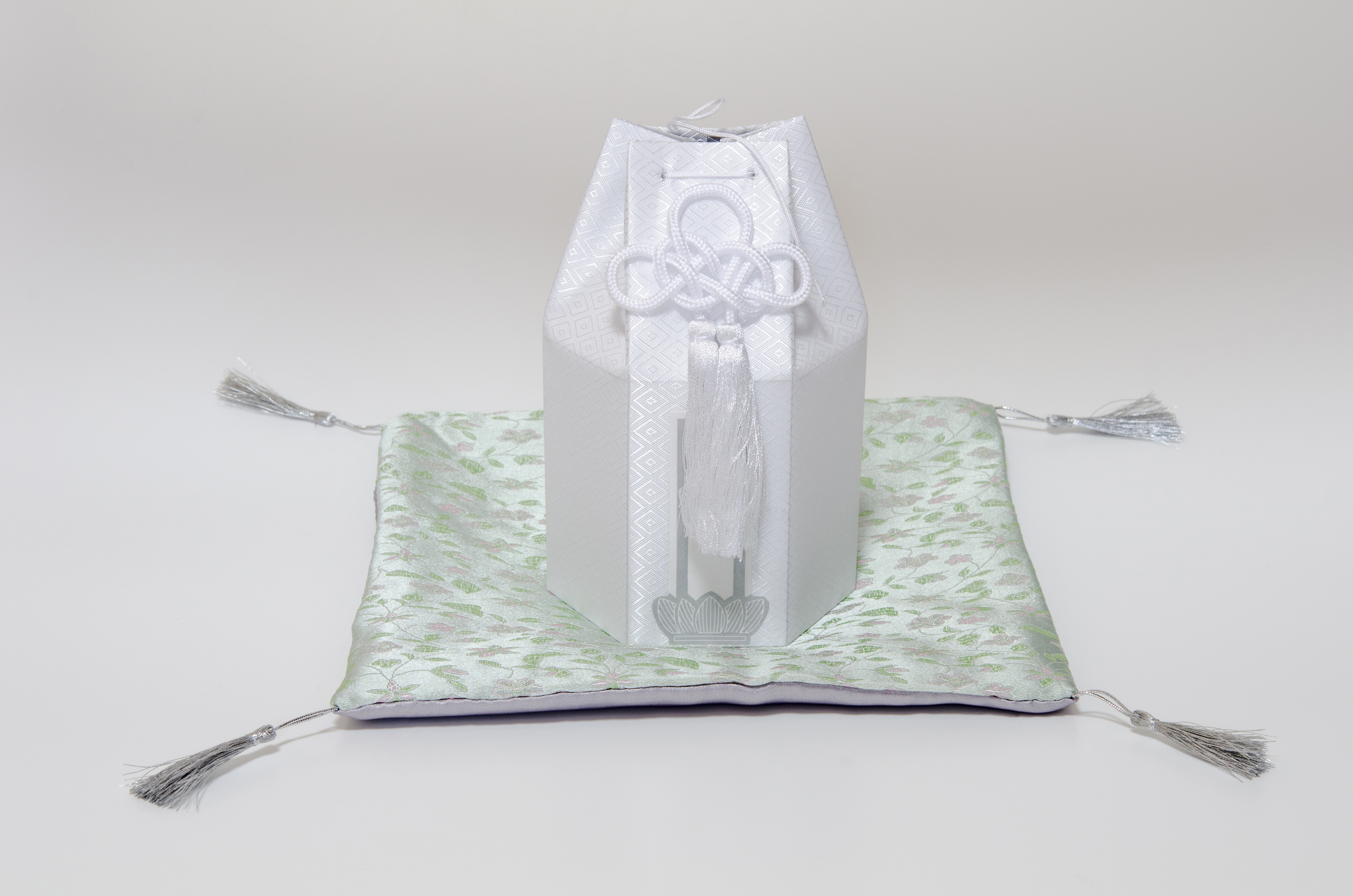
更新日:2022.11.20
お墓への骨の入れ方は?自分で行ってよいのか解説
お墓

更新日:2022.05.18
納骨式には遺影が必要?納骨式の持ち物を解説!
お墓

更新日:2022.11.08
納骨時に石材店に支払う費用は?納骨費用・彫刻料などを解説
お墓

更新日:2022.05.18
戒名なしで納骨はできる?戒名のいらないお墓の種類を徹底解説!
お墓

更新日:2024.01.24
納骨式でおすすめの花は?花選びの注意点や造花についても紹介



