お葬式
出棺とは?出棺から火葬までの流れや挨拶について解説
更新日:2024.02.04 公開日:2021.12.24

記事のポイントを先取り!
- 出棺は遺体を火葬場へ送り出す事
- 火葬許可証を忘れずに持参する
- 出棺時の挨拶は簡潔にまとめる
故人のご遺体を納めた棺を霊柩車に乗せて、葬儀場から火葬場は送り出すことを出棺といいます。
出棺は故人との最後のお別れの時間になりますが、どのような流れで行われるかご存知でしょうか。
この記事では仏式の出棺の流れだけでなく、神式とキリスト教の出棺式についても紹介しています。
出棺の注意点や地域ごとの違い、出棺時の挨拶にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 出棺の流れ
- 仏式以外の出棺の儀式
- 出棺の注意点
- 出棺時の挨拶
- 出棺の儀式が終わった後の流れ
- 火葬場で必要な持ち物
- 出棺時参列者が気を付けるべきマナー
- 地域によって異なる出棺で行われる儀式
- 出棺についてのよくある質問
- 出棺まとめ
出棺の流れ

出棺の流れについて解説します。
別れ花
葬儀・告別式を行った後、祭壇から棺をおろし、故人と向き合える最後の時間を過ごします。
このときに、ご遺体の周りに短く切った供花を一人一輪づつ飾り、故人に別れを告げる儀式を「別れ花」といいます。
喪主から、喪主の妻や夫・親や兄弟・子供・孫と血縁の濃い順番に行います。
また、遺族の希望があれば、一般の参列者も別れの花を捧げる場合もあります。
釘打ち
「別れ花」が終わった後に執り行われる儀式です。
「釘打ち」とは、棺に蓋をし、まず葬儀社のスタッフが棺の四隅に釘を浅く打ちます。
その後、故人との縁が深い人から順に釘を打ち、蓋を開かなくすることです。
釘を打ちつけることで、故人が帰らぬ人であることを遺族が認識し、けじめをつけてお別れをする儀式でもあります。
最近ではこの釘打ちの儀式が、遺族の心情への配慮や釘が燃え残ってしまうなど、省略されることも多くなっています。
出棺
「別れ花」や「釘打ち」などの儀式が終わった後、棺は霊柩車へ運ばれます。
ご遺体が入った棺はかなりの重量があるので、遺族を中心に男性数人で運びます。
このとき、運ぶときも乗せるときも、どちらが正しいということはありませんが、ご遺体の足側が前にくるように運ぶことが一般的です。
仏式以外の出棺の儀式

仏式以外の出棺の儀式を紹介します。
神式
神式の出棺式は発柩祭(はっきゅうさい)と呼ばれます。
発柩祭では、斉主による発柩祭詞の奏上のあと、喪主や参列者が玉串拝礼を行い、神前に供え物をします。
基本的に神式では、自宅から葬儀会場に向かう際に出棺の儀式を執り行うため、自宅が葬儀会場の場合は出棺の儀式は省略されます。
一方、民間のセレモニーホールで葬儀をする場合は、葬儀後に家族や参列者が故人とのお別れと棺に釘打ちをする出棺式を行い、火葬場に向かいます。
また、上記で紹介した儀式を省略して霊柩車の後方を清めるだけの場合もあり、地域ごとに出棺の儀式は異なります。
キリスト教
キリスト教の出棺式も神式と同様に、基本的には自宅から葬儀会場の教会へ向かう際に出棺式を行います。
しかし、近年では葬儀を教会で行ってから出棺式をする場合も増えてきています。
出棺式では、カトリックの場合は神父、プロテスタントの場合は牧師が祈りを捧げたあと、家族や参列者が故人との最後のお別れを行い、花を棺に納めます。
出棺式を終えたら棺を教会へ運びますが、葬儀後に出棺式をする場合は、火葬場へ向かいます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
出棺の注意点

出棺は、葬儀や告別式が終わった後に故人を火葬場へ運ぶ過程です。
ここでは、出棺時の注意点に焦点を当て、火葬場の予約から逆算して出棺の時間を決める方法、火葬の同行者を事前にお願いする重要性、そして地域の風習について親族やお寺と確認しておくべき事項についてご紹介します。
事前に火葬場の予約を忘れない
火葬場を利用する際は、事前の予約が必要なため忘れずに行いましょう。
予約の際に、葬儀社に相談しておくと円滑に予約をとりやすくなります。
出棺の時間は火葬場の予約から逆算する
火葬場の予約時間は、出棺の時間を決定する際に重要なことです。
特に都市部では、火葬場が混雑している場合が多く、希望する日に予約が取れないこともあります。
そのため、火葬場の予約状況を早めに確認し、それに基づいて出棺の時間を逆算することが重要です。
また、故人が生前に愛した場所に立ち寄るといった要望がある場合は、それも考慮に入れて時間を設定する必要があります。
火葬の同行は事前にお願いする
火葬場へは通常、遺族と親族、それに故人と特に親しい関係にあった人々が同行します。
そのため、火葬の同行者は事前に遺族から依頼されることが一般的です。
この依頼に対する返答は速やかに行うべきです。
また、無理に同行することは避け、遺族の意向と計画に従うことがマナーとされています。
地域の風習を親族やお寺に確認しておく
日本には地域ごとに独自の葬儀や出棺に関する風習が存在します。
例えば、「火葬場への行き帰りは同じ道を通らない」といった風習がある地域もあります。
そのため、地域の風習については、事前に親族やお寺、または葬儀社に確認しておくことが推奨されています。
こうしておくことで、不必要な混乱や手間を省くことができます。
副葬品は火葬場に確認する
出棺の際に棺に花を納めますが、花以外にも故人が生前に大切にしていた思い出の品を一緒に納めてお見送りをしたい参列者もいると思います。
花以外に棺に納める品物を「副葬品」といいますが、棺の中に納められる副葬品は火葬場によって異なります。
基本的に、ご遺体や火葬炉を傷つける可能性のあるビニールや金属などの不燃物や、ライターやスプレーなどの爆発の恐れがある副葬品は、大半の火葬場で禁止しています。
一方で、副葬品自体をご遠慮いただいている火葬場も存在します。
これは、火葬場が保有している火葬炉の種類によって、故障の危険に繋がる副葬品が異なるためです。
したがって、棺に納めたい副葬品がある場合は火葬場への確認が大切になります。
出棺時の挨拶

出棺の際、喪主は参列者に対し、会葬してくださった感謝の気持ちや故人がお世話になったことへのお礼の挨拶を述べます。
このときに、忌み言葉(再び、重ね重ねなど)や「九」や「四」などの死を連想させる数字は使わないようにしましょう。
また、挨拶ができるかどうか不安なときは、メモを用意し読み上げることも可能です。
参列者が立ったまま屋外で見送りすることを考慮し、簡潔な挨拶にとどめ手短にまとめることが大切です。
出棺の挨拶例文
ここでは出棺時の挨拶の例文を紹介します。
下記に挨拶の例をあげましたので、ぜひ参考にしてください。
「本日はお忙しい中、父〇〇の葬儀にご参列くださいまして、誠にありがとうございます。
このように大勢の方にお見送りいただき、故人もさぞかし喜んでいることと思います。
ここに生前のご厚誼に対し、深くお礼申し上げます。
残された私どもは未熟ではございますが、故人同様今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。」
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
出棺の儀式が終わった後の流れ

出棺の儀式が終わった後、多くの人々は何をすればよいのか、どのような手続きや儀式が続くのかについて不明瞭であることが多いです。
ここでは、出棺の儀式が終わった後の流れについて詳しく解説します。
火葬場へ移動
出棺の儀式が終わった後、次に行うのは火葬場への移動です。
この際、遺族と特に関係が深い人々だけが火葬場に同行することが一般的です。
移動手段は霊柩車が主であり、その他の参列者は自家用車や公共交通機関を利用し向かいます。
火葬場への移動には、事前にスケジュールをしっかりと組む必要があります。
また、移動中に特定の場所に立ち寄る場合、その時間も考慮に入れる必要があります。
骨上げ
火葬が終わった後、次に行うのは骨上げです。
この儀式では、遺族や親しい人々が特製の箸を使用して、故人の骨を骨壷に納めます。
この際、骨を納める順番や方法には特定のマナーが存在するため、事前に確認しておくことが重要です。
還骨法要・繰り上げ初七日
骨上げが終わった後は、還骨法要と呼ばれる儀式です。
この儀式では、遺骨を祭壇に安置し、僧侶が読経を行います。
また、繰り上げ初七日という儀式もこのタイミングで行われることがあります。
これは、葬儀当日に初七日法要を行う形式で、遺骨法要と同時に行われることが多いです。
精進落し
最後に行うのが精進落しです。
この儀式では、僧侶や世話役、参列者に対して、葬儀が無事に終わったことの報告と感謝の意を込めて料理を振る舞います。
この際、参加人数に応じて料理の量を調整する必要があります。
火葬場で必要な持ち物
火葬場での儀式は、故人との最後のお別れの場となります。
火葬場に何を持って行くべきかは、多くの人にとって疑問と不安の一つです。
ここでは、火葬場で必要な持ち物とその理由、さらにはマナーや注意点についてご紹介します。
火葬許可証
火葬許可証を忘れずに持参しましょう。
許可なく遺体を火葬することは、法律で禁止されています。
火葬許可証は地方自治で発行していますので、死亡届と同時に火葬許可申請書を出すのが通例となっています。
心付け
心付けとは、葬式でお世話になった方へのお礼として渡すお金です。
この慣習は義務ではありませんが、一般的には行われています。
火葬場のスタッフには、通常3,000円から5,000円を小さい不祝儀袋や無地の封筒に入れて渡します。
ただし、葬儀社や火葬場によっては、心付けの受け取りが禁止されている場合もあります。
そのため、事前に確認しておくことが重要です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
出棺時参列者が気を付けるべきマナー

出棺時のマナーとして、参列者側にも配慮しなければならないことがあります。
出棺時に参列者が守るべきマナーは次の通りです。
霊柩車が見えなくなるまで一礼や合掌をする
棺を霊柩車に乗せ見送ることまでが、出棺の儀式です。
霊柩車が出発した後は一礼をし、霊柩車が見えなくなるまで合掌や黙礼しましょう。
霊柩車が出発した途端に、緊張が緩んで話し始めたりするのはマナー違反となりますので、静かに故人の冥福を祈り最後まで見送りましょう。
寒くても出棺中はコートを着ない
出棺は屋外で行うことがほとんどですが、出棺時には身なりをきちんと整えましょう。
寒くてもコートを脱ぎ、腕にかけるなどして見送ります。
一方、真夏の時期では、上着を脱ぎたくなりますが、出棺時にはきちんと上着を着用しボタンもしっかり留めましょう。
ただし寒さの厳しい地域では、コートを着る事を許される場合もあるかと思います。
その地域ごとの出棺時のマナーを把握しておくことが良いでしょう。
雨天時傘は黒や紺色のものを使用する
葬儀や告別式のときに雨が降っている場合でも、出棺の儀式は屋外で行われます。
出棺時に傘をさすことはマナー違反ではありませんが、赤や黄色、ピンクなどの派手な色のものは避けましょう。
できるだけ地味な、黒や紺の傘をさすのが無難ですが、コンビニや100円ショップで販売されているビニール傘を使用することも問題はありません。
地域によって異なる出棺で行われる儀式
出棺の儀式は、故人との最後のお別れの場となる瞬間です。
しかし、この儀式は地域や宗教によって異なる場合があり、その多様性が日本の葬儀文化の一つの特徴とも言えます。
ここでは、地域によって異なる・出棺で行われる儀式についてご紹介します。
別れ花
別れ花(花入れ)の儀式は、ほとんどの葬儀で行われる一般的な儀式です。
この儀式では、故人の周りに生花を飾り、最後のお別れをします。
花を飾る順番は、故人に近い立場の人から始まり、遺族や親族、縁のある人が続きます。
また、故人が愛用していた品物も副葬品として棺に収めることがあります。
釘打ちの儀式
釘打ちの儀式は、地域によっては行われない場合もあります。
この儀式では、棺の蓋を閉め、釘を打ち込む作業がです。
通常、葬儀社の担当者が半分釘を打ち込み、残りは石を使って打ち込む場合もあります。
この儀式には、「無事にあの世へ渡れるように」という願いが込められています。
茶碗割り
茶碗割りの儀式は、地域や宗教によって行われる特色ある儀式です。
この儀式では、故人が使っていた茶碗を割り、故人がこの世に未練を残さないようにするとともに、遺族の気持ちを整理する意味があります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
出棺についてのよくある質問

出棺についてのよくある質問をご紹介します。
出棺のとき入れるもの
出棺時に柩の中に入れる副葬品は、一般的に、故人が生前愛用していたものや、故人の性格や趣味を反映する品物が選ばれます。
例えば、お気に入りの着物、手紙、または特定のお菓子などが該当します。
また火葬に影響を与えないように、燃えやすい素材のものを選ぶことが基本です。
金属やガラス、燃えにくい素材は避けるべきです。
また、燃焼時に有毒ガスを発生させる可能性のあるものも避けましょう。
地域や葬儀場によっては、副葬品に関する独自のルールや制限がある場合もありますので、事前に確認して、後で問題にならないようにしましょう。
出棺の時何故クラクションを鳴らすの?
出棺の際にクラクションを鳴らす習慣の一つは、故人を弔うという意味があります。
この音は、故人が最後の旅に出る際の合図ともされ、多くの人がこの瞬間に耳を傾けます。
また、クラクションの音は邪気を払うとも言われています。
一方で、「特に意味がない」という説も存在します。
この習慣がどのように始まったのか、その起源ははっきりしていません。
火葬場まで同行する人と留守番をする人の違い
火葬場まで同行する人は通常、喪主や直接の親族が担当します。
一方で、留守番をする人は遠縁の親族や友人がなることが多いです。
喪主は位牌を、次につながりの深い親族は遺影写真を持ち、棺を運ぶのは通常、男性6人程度が担当します。
この選定には、故人との関係性や地域の風習も影響を与えるため、事前によく確認しておくことが重要です。
出棺まとめ

ここまで出棺についての情報や、その時の注意点などを中心に解説してきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 出棺とは、ご遺体を霊柩車に乗せて火葬場まで送り出すこと。
- 出棺時の喪主側の注意点は火葬許可証を忘れないことなど
- 参列者はマナー違反な服装をしない
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.11.19
近所の人の出棺の見送りへは行くべき?服装の注意点は?
火葬

更新日:2022.05.11
火葬場で挨拶は必要?喪主の挨拶の注意点と文例を解説
お葬式
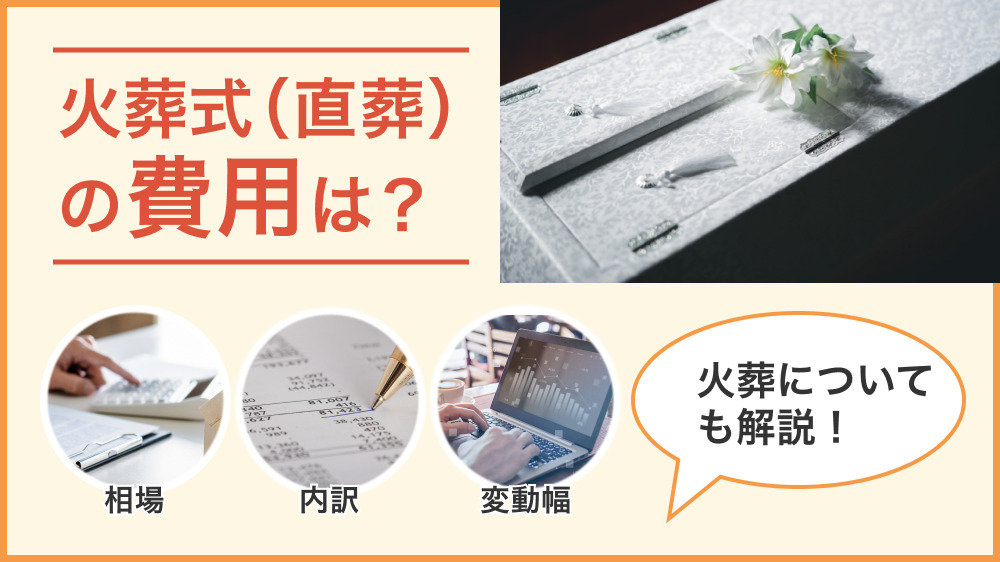
更新日:2025.06.29
葬式なしの火葬費用の相場は?直葬・火葬式の費用を抑える方法についても併せて解説




