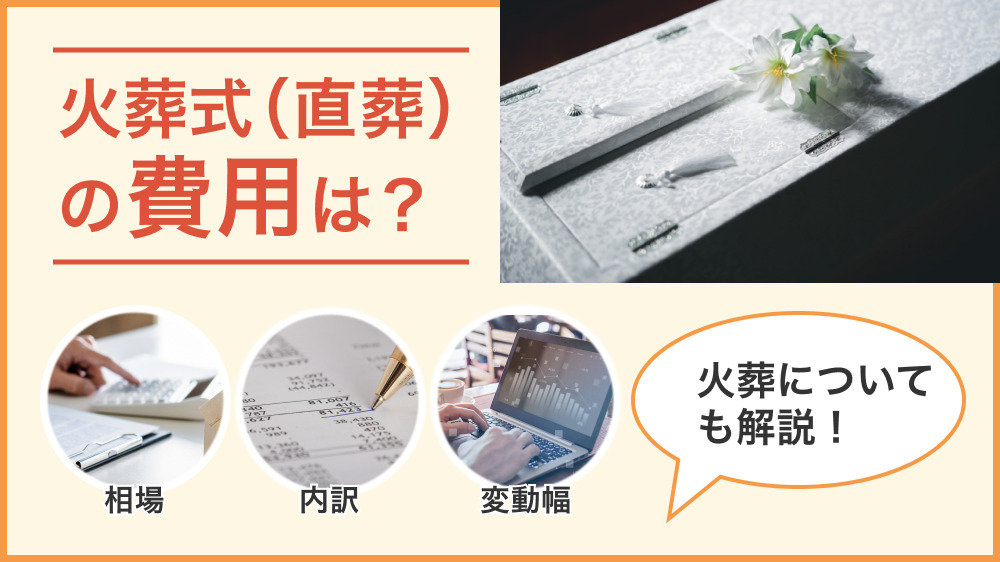お葬式
葬儀会場の種類の特徴は?葬儀会場の選び方や斎場と火葬場の違いについても解説
更新日:2024.03.16 公開日:2021.08.29

葬儀を行える会場は複数ありますが、具体的にどのような施設があるかご存知でしょうか。
公営斎場、民営斎場、寺院や教会、ホテル、自宅、公民館や集会所など近年の葬儀会場は多岐に渡ります。
そこでこの記事では、公営斎場と民営斎場の違いや、葬儀場の種類ごとの特徴をご紹介します。
後半では葬儀会場の選び方や内見についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 斎場とは
- 葬儀会場と公営・民営の違い
- 葬儀会場の利用の仕方
- 公営斎場の特徴
- 民営斎場の特徴
- 寺院や教会が葬儀会場の場合の特徴
- ホテルが葬儀会場の場合の特徴
- 自宅が葬儀解除の場合の特徴
- 公民館や集会所が葬儀会場の場合の特徴
- 斎場のサービスとその特徴
- 葬儀会場の選び方の基礎知識
- 葬儀会場の内見について
- 葬儀会場での写真撮影は可能?
- 葬儀会場で参列者は着替えられない?
- 葬儀会場の聞き方
- 葬儀会場についてのよくある質問
- 葬儀会場のまとめ
斎場とは
斎場とは、お通夜・葬儀式・告別式などの葬儀の儀式全般を行う場所を言います。
施設によってできる範囲は様々で、遺体の安置や葬儀後の会食、遺族の宿泊などが可能な施設もあります。
主に市町村が運営する公営の斎場と、葬儀者や組合が運営する民営の斎場があります。
本来、「斎」は神道に由来する言葉で心身を清めて神に仕えることを意味します。
そして、斎場は、神を祀る場所という意味があります。
斎場は、他にも葬儀場や、葬儀会館、セレモニーホール、聖苑などとも呼ばれています。
従来は、自宅で葬儀を行う自宅葬が主流でしたが、親類縁者との関係が希薄になったことや住宅事情などにより、今では斎場で葬儀を行うのが一般的になっています。
葬儀場との違い
斎場は、葬儀場とも呼ばれており、明確な違いはありません。
ただし、葬儀場というと火葬場を併設していない施設を差す場合が多く、葬儀・告別式の後、火葬場に移動するのが一般的です。
葬儀会館、セレモニーホールなどと呼ばれることもあります。
火葬場との違い
火葬場は、火葬炉があり、火葬をするための設備が整った場所を言います。
待合室や霊安室などの設備が併設されているところもあります。
火葬場の運営には、都道府県知事の許可が必要です。
多くは地方自治体が運営しておりますが、東京の都心部では民間企業が運営しているところが多くあります。
一方、斎場の運営には法的な規制はありません。
火葬場を併設している葬儀場は、「斎場」という名前がついていることが多く、斎場といえば火葬場のある葬儀場という認識が広まっています。
火葬場が併設されている斎場
以前は、火葬場と葬儀会場は別になっている場所が多く、告別式の後、火葬場へ遺体を霊柩車で搬送し、参列者もマイクロバスなどで移動する必要がありました。
しかし、近年では火葬場が併設された斎場が増えており、その場合、移動の負担なく1箇所でお通夜、葬儀、告別式から火葬まで執り行うことができるのがメリットと言えるでしょう。
葬儀会場と公営・民営の違い

葬儀会場には自治体が運営する公営斎場と、民間企業が運営する民営斎場があります。
葬儀には法的な制約がないので、故人の希望や予算などに応じて自由に選択できます。
この章では、公営斎場と民営斎場の違いや特徴を大まかに解説していきます。
公営は費用が安い
公営斎場は、民営斎場よりも葬儀費用が安く設定されています。
しかし葬儀費用が安いので人気が高く、待ち時間が1週間から10日程度と予約が取りにくいです。
一部使用条件がありますので、条件を満たしているか確認も必要になります。
民営は予約が取りやすい
民営斎場は葬儀会場の保有数が圧倒的に多く、日程調整など柔軟な対応ができます。
ご遺族のご要望を尊重した日程での予約も取りやすいです。
ただし葬儀を取り仕切る葬儀社のプランにもよりますが、葬儀費用は高くなることが多いです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀会場の利用の仕方
公営斎場と民営斎場は、それぞれ会場の利用方法が異なります。
公営斎場は、市区町村が運営しており、◯◯市営斎場・◯◯町営斎場などと施設名に自治体名や地名が入っている場合が多いでしょう。
ただし、市区町村は、貸斎場として場所の提供をするのみとなります。実際葬儀を執り行う場合の実務は、葬儀社を別に探して依頼する必要があります。
葬儀社に心当たりがあれば、直接問い合わせて確認してみましょう。
わからなければ、斎場の名前をインターネットで検索すると、その斎場で葬儀の手配が可能な葬儀社を見つけることができます。
民営斎場は、葬儀社などの民間企業が運営している斎場です。
そのため、民営斎場を選んだ場合、葬儀社も必然的に決まるかたちになります。
直接、運営している葬儀社に問い合わせましょう。
公営斎場の特徴

公営斎場には様々な特徴があります。
以下で詳しくご説明します。
公営斎場の使用料
公営斎場の使用料は、会場の大きさや形態などによって変動します。
火葬のみの直葬でも、遺体の搬送や納棺などのために葬儀社に依頼する必要があります。
もっともシンプルな直葬でも総額5万〜10万円になるでしょう。
安すぎるプランを提示された場合、必要最低限の内容も含まれていない場合があるので、内容をきちんと確認する必要があります。
公営斎場の葬儀の流れ
公営斎場では、通夜、葬儀、会食(精進落とし)、火葬が一連の流れになります。
火葬場が併設された斎場では、移動の負担なく火葬まで行うことができます。
しかし、初七日法要を同一日に行う場合は、基本的に別の会場に移動する必要があります。
公営斎場のメリット
公営斎場のメリットは以下の通りです。
- ほとんどの斎場に火葬場があり、葬儀の進行がスムーズ
- 火葬場が併設されている場合、出棺時の運搬車両の手配が不要
- 葬儀社や宗教・宗派の制限がない
施設使用料の相場は3万~5万円程度と安く、 葬儀社や宗教・宗派の制限がないため葬儀費用を柔軟に抑えることができます。
また火葬場が併設されていることも多く、葬儀から火葬までの流れがスムーズなうえ出棺の際の車の手配が不要なこともメリットの1つです。
公営斎場のデメリット
公営斎場は、故人もしくは喪主がその自治体の住民でないと利用できない場合があります。
一部、住民ではなくても利用できる場合もありますが、料金が割高になるのが一般的です。
また、民営に比べて数が少なく、費用も安いことから、予約が取りづらくなっています。
そして、費用を抑えられるぶん、こだわりの強い葬儀には対応できない場合もあります。
例えば、故人の好きな音楽をかけるなどの葬儀演出ができない場合が多いです。
さらに、居住区域から離れた火葬場と併設されているため、アクセスしにくい場所にある場合も多い傾向にあります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
民営斎場の特徴

民営斎場にも様々な特徴があります。
以下で詳しくご説明します。
民営斎場の使用料
民営斎場は、会場費は無料で、葬儀の規模に応じて葬儀費用のプランを提示しているところが多いです。
相場は、公営斎場の2、3倍かかる場合が多く、最もシンプルなプランで2万〜4万円程です。規模が大きくなったり、祭壇を豪華にしたり、オリジナルの企画などをしたりすると、100万〜150万円を越える場合もあります。
民営斎場の葬儀の流れ
民営斎場では、通夜、葬儀・告別式、初七日法要、会食(精進落とし)、火葬という流れが可能です。
火葬場が併設されていない斎場の場合、初七日法要後に、火葬場へ移動し、火葬場近隣のレストランなどで火葬中もしくは火葬後に会食を行うのが一般的です。
もしくは、通夜、葬儀、告別式を終えた後、火葬場に移動し、火葬後、斎場に戻って初七日法要と会食をするという流れもあります。
民営斎場のメリット
民営斎場のメリットは以下の通りです。
- 葬儀会場の設備が充実しており、葬儀演出などにも対応可能
- 比較的交通の便の良い場所にあり、会葬者の参列にもアクセスが良い
- 葬儀会場を多数保有する葬儀社の場合、規模やアクセス面を考慮した会場を選べる
- 葬儀会場が貸会場の場合、葬儀を取り仕切る葬儀社の制限がない
- 故人の安置が可能で、家族の宿泊施設や参列者への食事の提供ができる
故人の趣味趣向を反映した葬儀の演出が、ご遺族の要望を満たした形で行えます。
また故人を1日~3日間安置するスペースがあり、葬儀までのブランクも安心です。
葬儀まで故人の近くに居たいご遺族の宿泊施設を備えた会場もあり、遺族の心情に柔軟に寄り添えます。
民営斎場のデメリット
民営斎場の場合、公営斎場と比べて割高になる事が多いです。
また、火葬場が併設されていない斎場では、別途予約が必要になり、料金も上乗せされる場合もあります。
葬儀会場を運営する法人が葬儀社の場合には、予め葬儀社が決められている為、自分で葬儀社は選べません。
また宗教法人が葬儀会場を運営する場合には、宗教的な制限がかかるケースが多いです。
寺院が所有している斎場に依頼すると、宗旨宗派が問われる場合もあるので注意が必要です。
寺院や教会が葬儀会場の場合の特徴

昨今、寺院や教会でも葬儀が出来るケースが増えています。
寺院や教会での葬儀のメリットとデメリットそれぞれについて分かりやすくお伝えします。
メリット
寺院や教会での葬儀のメリットとして以下のものがあります。
- 寺院や教会で格式の高い葬儀が行える
- 故人の思い入れのある菩提寺で葬儀を営める
- アクセスが良く葬儀会葬者が参列しやすいことが多い
- 祭壇が必要ない場合もある
寺院や教会は格式が高く、落ち着いた雰囲気で故人を送ることができます。
また祭壇を用意する必要がなく、葬儀費用を抑えることができる場合もあります。
故人と馴染みのある寺院・教会で葬儀を営むことができ、参列者のアクセスも便利なことが多いです。
デメリット
寺院や教会での葬儀のデメリットとして以下のものがあります。
- 檀家・信徒でない場合は利用できないことが多い
- 故人の趣味趣向などを反映した演出ができないことが多い
檀家・信徒であることが利用条件となっていることがほとんどで、演出にも制限があることが多いです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
ホテルが葬儀会場の場合の特徴

最近では豪華なセレモニーとしてホテルでの葬儀ホテル葬も注目されています。
焼香を禁止されている場合でも、火葬を先に行う骨葬や密葬の後の「お別れ会」として利用される場合が多いようです。
メリット
ホテルでの葬儀のメリットは以下の通りです。
- 豪華で設備の整った会場で葬儀ができる
- 最寄駅からのアクセスが良く参列しやすいことが多い
- 会場から離れた地域の参列者が宿泊できる
- バラエティーに富んだ料理をセレクトできる
一般的に有名人が利用することが多く、豪華で高級感のある葬儀スタイルです。
故人を偲ぶための「偲ぶ会」や故人とのお別れをする「お別れ会」のスタイルが多いです。
デメリット
ホテルでの葬儀のデメリットは以下の通りです。
- 葬儀費用がかなり高額
- ご遺体が持ち込めないことが多い
- ご焼香など一般的な葬儀ができないことが多い
葬儀費用が高額で、ご遺体の安置やご焼香など一般的な葬儀ができない場合が多いです。
スポンサーリンク自宅が葬儀解除の場合の特徴

自宅での葬儀の場合にも、最低限の条件がそろわないとできないことが多いです。
自宅で葬儀を執り行う際のメリットとデメリットをお伝えします。
メリット
自宅での葬儀のメリットは以下の通りです。
- 葬儀会場使用料金がかからない
- 時間や利用条件の心配がいらない
- 故人の思い出の詰まった自宅で葬儀ができる
自宅での葬儀は会場費用がかからず、時間や利用条件を気にせず故人を送ることができます。
デメリット
自宅での葬儀のデメリットは以下の通りです。
- 棺や祭壇を設営するスペースを確保できる広い部屋が必要
- 霊柩車や弔問客の駐車スペースが必要
- 複数の人が自宅へ出入りするため準備が必要
- 近所迷惑にならないよう注意が必要
弔問客の人数にもよりますが、祭壇や棺を置き、参列できる広い部屋が必要になります。
不特定多数の人が出入りするのでお出迎えする準備も必要です。
霊柩車など葬儀関係車両の駐車場確保や、騒音対策にも気が抜けないという難点があります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
公民館や集会所が葬儀会場の場合の特徴

地域の公民館やマンションの集会所は、習い事や講習会、展示会などの他に冠婚葬祭の会場として利用できる場合があります。
公民館や集会所を葬儀会場として利用した場合のメリットとデメリットをご紹介します。
メリット
公民館や集会所を葬儀会場として利用するメリットには、会場費用の安さが挙げられます。
公営斎場の利用料金の相場は5万〜10万円ほどになっていますが、公民館や集会所の大半は数千円で利用できます。
マンションの集会所では、居住者は無料で利用できる場合もあります。
自宅を葬儀会場にした場合も利用料は無料ですが、公民館や集会所は自宅よりも広い会場です。
したがって、広い会場を安価で利用できる点はメリットといえるでしょう。
また、習い事や講習会、展示会などに利用できる会場でもあるため、音響設備や映像設備の貸し出しや、公民館によっては祭壇を貸し出しています。
自由度の高い葬儀を行える点もメリットのひとつです。
デメリット
公民館や集会所は葬儀専門の会場ではなく、さまざまな行事での利用が想定されている会場です。
そのため、公営斎場や民営斎場のように葬儀に適した施設の造りにはなっていません。
葬儀の設営は利用者が行う必要があり、控室などの設備が足りない会場もあります。
また、規約によっては葬儀での利用ができない可能性もあり、すべての公民館や集会所を葬儀会場として利用できるとは限りません。
利用申請ができるのも地域住民やマンションの居住者に限られている会場が大半です。
ただし、公民館や集会所の設営に関しては、葬儀社が対応してくれる場合があります。
したがって、設営を行ってくれる葬儀社を探すと、公民館や集会所を葬儀会場として利用しやすくなるでしょう。
斎場のサービスとその特徴
現代の斎場は、公営斎場でも民営斎場でも、遺族の願いを最優先に考え、さまざまなプランを提供しています。
また、遺族や弔問客が快適に過ごせるように、様々な設備が整えられています。ここでは、斎場で提供される主なサービスとその特徴について詳しくご紹介します。
家族葬
近年、少人数の身内だけで行われる「家族葬」の需要が増えています。
そのため、斎場も少人数向けのプランを提供しており、弔問客が10人以下の場合でも快適に行うことができます。
公営斎場は多くが火葬場と併設されており、アクセスが便利なのが特徴です。
家族葬は公営斎場でも民営斎場でも行うことができ、費用と時間を抑えたい方に最適です。
無宗教での葬儀
宗教的な要素を排除した「無宗教葬儀」も、多くの斎場で実施されています。
故人や遺族の意向に合わせ、宗教にとらわれずに葬儀を行うことができます。
読経や焼香を行わず、音楽演奏や映像上映などの要素を取り入れることが一般的です。
ただし、斎場によって提供できるサービスが異なるため、無宗教葬儀を検討する際には事前に確認が必要です。
法要などの会食施設
広々としたスペースを持つ斎場では、通夜や初七日法要、精進落としなどの宴席を行えます。
特に宴席会場が斎場内にある場合、参列者の移動が不要で便利です。
初七日法要は故人の命日から7日目に行う法要であり、葬儀の日に一緒に行うこともあります。
また、精進落としは僧侶や関係者を招いて行うお食事会で、感謝の意を示す大切な儀式です。
参列者への宿泊設備
一部の斎場では、遠方からの弔問客や参列者のために宿泊設備を提供しています。
特に斎場周辺に宿泊施設が限られている場合、このサービスは大変便利です。
遠くから来る方々が安心して参列できる環境を整えることで、故人を偲ぶひとときをゆっくりと過ごすことができます。
斎場は、個々の希望やニーズに合わせて葬儀や告別式を行う場所として、多様なサービスを提供しています。
どのサービスも、故人への最後の思いを大切にしながら、遺族や参列者の心に残る瞬間を提供することを目指しています。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀会場の選び方の基礎知識

葬儀会場を選ぶ際には、葬儀会場の利用費用が予算内に収まるかなどの確認が大切です。
また遺族の要望を満たした葬儀を執り行うため、収容人数など葬儀会場の規模も重要となります。
参列者が足を運びやすいアクセスの良さも判断材料となります。
葬儀会場の費用の確認
故人の希望を満たした葬儀会場の費用にいくらかかるのか確認が大切です。
公営斎場や民営斎場などさまざまな葬儀スタイルから自身に合った費用プランを選びます。
公営斎場の場合、施設使用料と葬儀社への支払総額が10万円を超すことが多いです。
民営斎場の場合、プランにより費用が違うので葬儀社と打ち合わせが必要です。
予算を踏まえたうえで自分たちの望む葬儀が可能か、葬儀社を比較して検討しましょう。
葬儀会場の規模が参列者数に見合っているか
葬儀に参列する人数を、事前に把握することも大切になります。
葬儀が親族だけで営む家族葬であれば葬儀会場の規模は小さくてすみます。
大勢の弔問客が見込まれる一般葬では、参列者が窮屈に感じない広い会場が必要です。
自分たちが望む葬儀スタイルや参列者数を明確化し、希望に見合った会場に決めましょう。
葬儀会場までのアクセスの良さ
葬儀会場までのアクセスの良さはとても大切です。
自宅から距離のある葬儀会場や火葬場の場合には、移動費用も嵩(かさ)んでしまいます。
参列される人の交通手段を考慮し、駐車場の有無や最寄駅からの利便性も確認が必要です。
火葬場までのアクセスが悪いと出棺の時間が早まり、お別れの時間が満足のいかないものになることも考えられます。
遺族や参列者がアクセスしやすい葬儀会場を選ぶようにしましょう。
葬儀会場の安置施設や宿泊設備の有無
多くの葬儀会場では、通夜や葬儀・告別式までご遺体を安置できる場所が整っている場合が多いですが、設備がない場合もあります。その場合、どこでご遺体を安置するのか葬儀会社と相談して決める必要があります。
また、お葬式まで故人と一緒に過ごしたいと思っても、宿泊が可能なところと、そうでないところがあります。
宿泊可能なところでも、人数制限があったり、設備の充実度合いも施設によって様々です。こちらもチェックするようにしましょう。
葬儀会場の内見について

葬儀会場を見極める際、会場の内見は有効な手段です。
施設の広さや設備などを体験できる内覧会のチェックポイントについてお伝えします。
葬儀会場の内覧会に参加する
葬儀社が運営する葬儀会場では、施設を無料で見学できる内覧会を催しています。
内覧会に参加することで、施設の設備や会場の雰囲気などを体感できます。
中には精進落としとして出される料理が試食できるケースもあるようです。
他にも仏事の相談コーナーや、葬儀の見積もりをしてくれる葬儀社もあります。
インターネットの普及により、葬儀社運営サイトから内覧会の申し込みも簡単です。
葬儀会場の内覧会参加時のチェックポイント
内覧会に参加した際にチェックすべきポイントを見ていきます。
- 式場の広さ・明るさ・音響効果
- 祭壇・棺・供花などの展示物の品質と価格
- 控室のセキュリティー対策
- 水回り器具が清潔か
- 宿泊施設があるか
- 参列者にふるまう料理・返礼品のバリエーションと価格
- 葬儀スタッフの対応
- 駐車場への侵入経路や駐車可能台数・送迎バスの有無
内覧会のチェックポイントの中で一番大切なものは、葬儀スタッフの接客対応です。
会場設備の掃除が行き届いているかなどから、葬儀社の仕事の質を判断できます。
葬儀は大切な故人を送る一度きりの儀式ですので、信頼できる葬儀社であるかが肝要です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀会場での写真撮影は可能?
故人様との最後のお別れを、思い出として写真に残したい人は多いと思います。
葬儀会場での写真撮影は、遺族と葬儀社の許可が得られれば、撮影しても問題ありません。
ただし、許可が得られなかった場合は、遺族や葬儀会場の方々の意向に従い、撮影を控えるようにしましょう。
葬儀会場で撮影許可を得た場合のマナー
葬儀会場で許可を得て、写真撮影をする場合は、葬儀進行の妨げになったり、迷惑行為にならないように、シャッター音やフラッシュは消すようにしましょう。
また、祭壇に背を向けての撮影は、故人に失礼なので、撮影位置に注意し、撮影した写真はプライバシーに配慮し、不特定多数が見るSNSに載せないようにしましょう。
葬儀会場で参列者は着替えられない?
葬儀に遠方から参列する時に、葬儀の会場で喪服に着替えたいと考える方もいるかもしれませんが、一般的には葬儀会場での着替えは親族に限られます。
葬儀会場では通常、参列者が使用する控え室は設けられておらず、親族の方々が利用することが一般的です。
そのため、参列者が葬儀会場での着替えをすることはできません。
したがって、遠方での葬儀に参列する場合、最初から喪服を着て行くか、私服で向かい、葬儀場の近くのトイレや駅などの利用する場所で着替えることが望ましいです。
もしくは、葬儀場に車で行く場合は、車内で着替えてから葬儀場に入るのがいいでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀会場の聞き方
故人との親しい関係がある場合でも、遺族の方と面識がなく、葬儀会場の連絡先を得られない場合があります。
このような場合、葬儀会場の場所を尋ねることは失礼には当たりません。
葬儀会場の場所を聞く時は、電話で尋ねるのが確実です。
まず、自分の名前を名乗り、故人との関係を簡潔に伝えましょう。
次に、お悔やみの言葉を伝えてから、お別れに参列したい旨と、葬儀の日程について尋ねることが適切です。
重要な点として、用件に入る前にお悔やみの言葉を伝えることを忘れないようにしてください。
用件に直ちに入ることは非常に失礼とされます。
また、死因を尋ねたり、忌み言葉や生死に関する直接的な表現を使用することは、マナー違反ですので避けましょう。
葬儀会場の場所を尋ねる際には、遺族の方の気持ちに寄り添った言葉選びを心がけることが重要です。
葬儀会場についてのよくある質問

葬儀会場についてのよくある質問をご紹介します。
葬儀はどこで行えばいいですか?
葬儀を行う場所にはいろいろな選択肢があります。
斎場などの葬儀専門の施設、寺院、教会などの宗教施設、集会所などの自治体の施設、自宅、ホテルなど、それぞれに特徴が異なります。
ご希望の形や、予算なども考慮し、最適な場所で行えるようそれぞれの特徴を把握しておきましょう。
葬儀会場を調べる方法は?
葬儀のことがわからない状態で信頼できる葬儀社を見つけるのは難しいことです。
インターネットで葬儀社比較サイトを利用して複数の葬儀社から要望に合った葬儀社を探すのが便利です。
葬儀社ごとの特徴をくらべることができ、相見積もりをとって比較検討することができます。
葬祭場とはどういう意味ですか?
葬祭場とは、葬式や火葬、会食、法事などを行う場所のことです。
葬儀会館、セレモニーホールなどと呼ばれることもあります。
ただし、葬祭場といっても、火葬も含めてすべてのことができる所は限られており、施設によって設備や規模は異なります。
お葬式を行う場所には規定はある?
日本には「墓地、埋葬に関する法律」において、お葬式に関する明確な規定は存在しません。
つまり、法的な制約がないため、お葬式の場所は自由に選ぶことができます。
近年では自宅でお葬式をする慣習が減少しており、会場を借りて行うケースが一般的となっています。
したがって、お葬式を行う場所を選ぶ際には、故人や遺族の希望やニーズを尊重することが重要です。
会場選びは、故人を偲びつつ心に残る形でお別れするための大切な要素です。
規定がないからこそ、自由な発想でお葬式を計画し、大切な人を偲ぶ場を創り上げることができるのです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀会場のまとめ

これまで葬儀会場の選び方の情報や、公営・民営斎場の違いと内見について解説しました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 公営斎場は自治体が運営し、民営斎場は葬儀社や宗教法人が運営
- 公営斎場は葬儀費用が安く、民営斎場は予約が取りやすい
- 会場選びは望む葬儀プランに見合った予算ででき、アクセスの良い会場がポイント
- 内覧会のポイントは葬儀社スタッフの信用度と、設備の清潔さ
この情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.11.21
町内会の回覧板で訃報のお知らせをするには?文例や注意点を紹介!
お葬式

更新日:2024.03.30
離婚した父の葬儀で喪主は誰がやる?参列の可否や香典の扱いについても解説
お葬式

更新日:2022.11.18
なぜご遺体の手を組む必要があるの?手を組む理由や注意点も紹介
お葬式

更新日:2022.11.18
会葬御礼は郵送した方が良い?弔問客や代理参列者の対応も説明
お葬式

更新日:2022.11.21
供花を頂いたらお礼はするべき?お礼状の書き方や例文も紹介
お葬式

更新日:2022.11.17
枕飾りのご飯(枕飯)とは?いつまでお供えすればいいの?