お葬式
喪中だけど初詣に行きたい!参拝可能な場所や時期・初詣マナーも解説
更新日:2022.06.17 公開日:2021.10.19

記事のポイントを先取り!
- 忌明けなら初詣もOK
- 忌中は49日までの期間のこと
家族を亡くした方が喪中になることは知っていても、その意味や期間についてまでは詳しく知らないこともあるでしょう。
そして喪中の場合に年始の初詣は行っていいのかお困りではありませんか。
そこで喪中の初詣について、本記事では以下の内容を網羅的に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
喪中に初詣に行ってもいい?
結論から述べますと、喪中に初詣でお寺・神社へ参拝することは可能です。
しかし、神社へ初詣するのであれば忌明けじゃなければならないという条件があります。
忌明けは通常故人が亡くなってから49日までのことを指します。
お寺は仏教の教えによって営まれており、仏教では亡くなった方の供養が推奨されているため定期的な法要も行われます。
そのためお寺への参拝は、故人やご先祖さまへの挨拶という主旨になります。
また、仏教の宗派の一つである浄土真宗では喪中という考え方がありませんので、初詣に制限がありません。
神社は神様がいる場所のため、神聖な領域とされています。
神社の考え方は神道によるもので、人の死は穢れ(けがれ)とされています。
そのため近いうちに家族を亡くした人は、神社への初詣などで参拝することは推奨されません。
忌明けまで待ってから参拝するとよいでしょう。
忌中と喪中の違い
忌中と喪中という2つの言葉には違いがあります。
喪中は命日からおおよそ1年間で、一周忌をもって喪が明けるという考えが一般的です。
それに対し忌中は仏教と神道で期間が異なります。
仏教では四十九日法要までが忌中の目安となっています。
この49日間の間、亡くなった人は極楽へ辿り着くための道中にあり、同時に修行期間ともされています。
四十九日法要を終えて、無事に極楽へ辿り着くタイミングと同時に忌明けとする考えです。
その一方で神道の忌明けは最も長い忌中が、両親を亡くした場合で50日間です。
忌明けの目安は命日から50日の五十日祭をもって忌明けとするケースが多く見られます。
これらの期間は、かつて明確に期日が決まっていたとされていますが、現在では目安程度になっています。
期間中はお祝い事やお祭りを控え、故人を偲び静かに生活するという考えが基本にあります。
喪中の初詣に対するお寺と神社の考え
お寺と神社では死への考え方が異なります。
仏教の教えを守るお寺は、神社よりも死への考え方が肯定的です。
故人は死んだ後もお墓に祀られ、お盆には毎年帰ってくるものとされており、家族はそれを迎え入れます。
人は死んでもなお遺族や関係者に影響を与えるため、残された方々も定期的に故人を供養する行為が良しとされています。
その一方で神社では穢れの概念があるため、喪中の初詣は控える必要があります。
神道では死ぬことは穢れとされ、「穢れ」は「気枯れ」とも書きます。
亡くなった方の穢れに限らず、家族を亡くした方も悲しみの中で気持ちが滅入り、気枯れているとされます。
そのため喪中では神聖な領域である神社への初詣を含む参拝が不適切とされています。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
喪中の初詣のマナーとは?

実際に喪中の初詣に行く際は、守るべきマナーが存在します。
以下でそれぞれ解説しますので、ぜひ参考にしてください。
お守りやお札の購入は忌明けに行う
せっかくの初詣で心機一転、気持ちを新たにお守りやお札を購入したい方も多いかと思います。
しかし、忌中にある場合はお守りやお札を購入するために神社に参拝することは不適切です。
穢れの時期を過ぎた忌明けを待って、その後に購入するべきでしょう。
派手な着物は控える
喪中の期間は基本的に「静かに生活する」という考えがあります。
初詣は禁止ではありませんが、晴れ着のような派手な着物は喪中に適切とは言えません。
忌中を過ぎていれば鳥居をくぐっても問題ない
神社の鳥居は忌中を過ぎていればくぐっても問題ありません。
では忌中に鳥居をくぐらずに避けて参拝すれば問題ないかというと、それは違います。
まず忌中に神社を参拝することは避けるべきであり、鳥居をくぐらずに参拝するという行為も不適切です。
忌明けであればおみくじを引くことも可能
参拝したらおみくじを引くのが楽しみの一つという方もいらっしゃると思います。
ですが、やはり忌中におみくじを引くことはよくありません。
忌明けであれば問題ありませんので、忌明けの日を待ってからおみくじを引いてください。
喪中の正月はどう過ごせばいい?
喪中の場合、どのような正月を過ごせば良いのでしょうか。
喪中の正月の過ごし方を注意点とともにご紹介します。
喪中の正月飾りは控える
喪中の正月飾りは控えるべきです。
なぜなら正月飾りはおめでたい意味合いがあるためで、一周忌を迎えるまでは避けた方がよいとされているからです。
おせち料理を食べることも避ける
年始には家族親戚が集まっておせち料理を囲むのが正月の風物詩といえます。
しかし喪中期間においては、お節料理を食べることも避けた方が無難です。
その理由は、おせち料理は新年を祝うための料理だからです。
喪中はがきを出して年賀状は遠慮する
喪中期間の年賀状を控えることは一般的に広く知られていると思います。
そのために事前の段取りとして、11〜12月中旬までに喪中はがきを出します。
早い段階で喪中の知らせが届けば、相手側が年賀状を控えることができるからです。
喪中はがきの書き方
喪中はがきを書く際には、守るべきマナーがあることをご存知でしょうか。
ここからは喪中はがきを書く際に気をつけるべき点をご紹介します。
喪中はがきを書く際は、まず年賀欠礼の挨拶を忘れないようにしましょう。
年賀欠礼とは近親者に不幸があったため喪に服し、新年の挨拶を行わないことを知らせることです。
「喪中のため、新年のご挨拶は失礼いたしました」などと書き、相手にそのことが伝わるようにしましょう。
また、故人についても必ず書きましょう。
「誰が、いつ、何歳で亡くなったのか」を相手が分かりやすいように記載します。
また、故人との続柄を書くことで、あなたとの関係も分かりやすくなるため、こちらも忘れず記載しましょう。
「◯月◯日 父〇〇が◯◯歳で永眠いたしました」といった形で書くのが一般的です。
次に、故人が生前お世話になったことや日頃の付き合いの感謝を述べます。
続けて、今後も変わらずにお付き合いを願う言葉も加えます。
例えば、「生前のご厚情に深く御礼申し上げます」「明年も変わらぬご厚誼を賜りますようお願いいたします」といった形です。
最後に日付と差出人名を記したら、喪中はがきは完成です。
喪中はがきを書く際は、年賀欠礼についてのみ書き、他のことを書くのは避けましょう。
他に報告などがある場合は、同じはがきに書くのではなく、その用件についてはがきを作り、別に出すのがマナーです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
忌中に神社に行ってしまったらどうすべき?
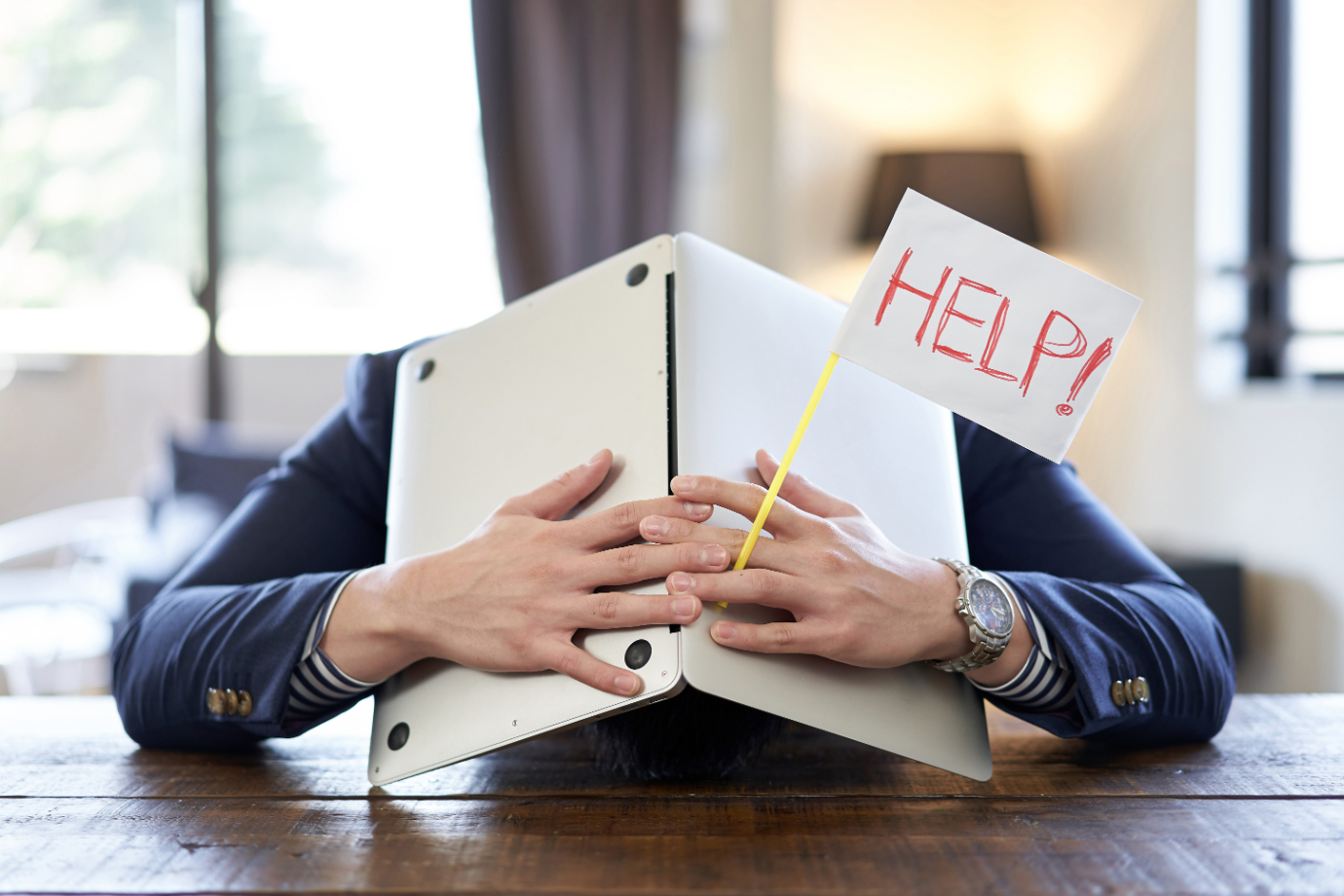
忌中に神社に行ってしまうこともあるでしょう。
もしも忌中に神社に行ってしまったらどうすべきなのでしょうか。
適切な段取りがありますので、参考にしてください。
まずは神主への相談
まずは神社を管理している神主へ相談してください。
気がついた時点で可能な限り早い段階で相談するべきです。
おおまかな事情だけを簡潔に述べて、あとは神主からの質問に答えて適切な指示をもらいます。
日本には多くの神社がありますので各神社、地域ごとに作法やしきたりが変わることがあります。
必要な場合はお祓いを受ける
さまざまな状況から神主が適切な方法を判断してくれます。
場合によってはお祓いが必要になるケースもありえます。
必要に応じて神主の指示に従いお祓いを受けてください。
神社でお祓いを受けることは、めずらしいことではありません。
事実、忌明け払いというお祓いがあり、穢れをはらうことで参拝が許されるケースもあります。
ただし、忌明け払いをしたからといって多くの人が参拝する神社に行くことは推奨されません。
人によってはお祓いをしていたとしても、穢れの期間にある人を快く思わない人もいるからです。
忌中後にお詫びをしておく
忌中後にお詫びをすることも大切です。
神道の決まりごとに関わらず、不適切な行為をお詫びすることに宗教は関係ありません。
お詫びするタイミングは必ず忌中後としてください。
よくある質問
ここからは喪中に関して、インターネット上でよくされている質問をご紹介します。
以下の内容を参考に、よくある疑問を解消してください。
Q:喪中の初詣で厄払いをしてもらうことは可能?
喪中で初詣をした時に、厄払いをしてもらうことは可能です。
ただし神社の場合、忌中は厄払いができません。
忌中とは、四十九日までのことで、神社は人の死によって遺族にも穢れがもたらされると考えています。
そのため、四十九日までは喪に服す期間としてお参りなども控えるのが神道の考え方です。
一方、お寺での厄払いは忌明け前でも問題なく行なえます。
忌中に厄払いすることを検討している方は、お寺で厄払いをしてみてはいかがでしょうか。
Q:喪中の初詣でお札やお守りを収めることは可能?
喪中の初詣であっても、お札やお守りを納めても問題ありません。
ただし、前述のように忌中の場合は神社に行ってはいけないため、お札やお守りを納めることはできません。
その場合はお札やお守りを親戚に納めてもらうか、忌中が明けてから自分で行くか、郵送でお願いするかの3択となります。
ただし、郵送は神社によっては対応していないことがあるため、あらかじめ確認が必要です。
忌中の場合は、自分にとって都合の良い方法でお札やお守りを納めるようにしましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
喪中の初詣まとめ

ここまで喪中の情報や、喪中の初詣などを中心にお伝えしてきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 忌中での神社への初詣は控えるべきだが、お寺への参拝は問題なし
- 喪中は命日から1年間、忌中は仏教で四十九日まで神道で五十日間のことをいう
- 正月飾りやおせち料理は控え、事前に喪中はがきを出す
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.05.15
喪中だけど誕生日は祝ってもいいの?友人が喪中の場合についても解説
お葬式

更新日:2022.11.17
厄払いにはどんなマナーがあるの?服装や祈祷料などのマナーを紹介
お葬式

更新日:2025.05.15
【公務員の忌引き休暇】忌引き日数は?忌引き申請の方法や非常勤の公務員の取得についても紹介
お葬式

更新日:2022.06.17
喪中の対象はどこまで?喪中に注意するべきことについても解説
お葬式

更新日:2025.05.19
喪中はがきの宛名は薄墨で書くの?薄墨の理由や書体などを紹介
お葬式

更新日:2025.04.24
喪中期間に飲み会へ参加していいの?喪中にしてはいけないことや喪中と忌中の違いまで解説


