お葬式
自宅葬にはどんなメリットがある?注意点や葬儀の流れについても解説
更新日:2023.12.15 公開日:2022.01.22

記事のポイントを先取り!
- 自宅葬は費用が抑えられる
- 自宅葬は遺族の負担が大きい
- 近隣住民への配慮が必要
- 自宅葬なら住み慣れた家で故人を見送ることができる
- 自宅葬なら式場使用料がかからず、費用の負担も軽減できる
- 自宅葬を行う場合は、近所への配慮、管理会社への確認が必須
- 自宅葬の祭壇は葬儀社と相談して引き取ってもらう
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
自宅葬について
自宅で葬儀を行う自宅葬は現代では減少傾向でしたが、昨今再び注目を集めているのをご存知でしょうか。
自宅葬にはメリットもあれば、注意すべき点もあり、それらを知っておくことで自宅葬をするかどうか適切に判断が出来ます。
そこでこの記事では、自宅葬について詳しく説明していきます。
この記事を読んで、自宅葬を行う選択肢も検討してみましょう。
自宅葬の際は祭壇をいつまでだしておくかについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
自宅葬とは
自宅葬とは、その名の通り自宅で行う葬儀のことを言います。
自宅で葬儀を行う自宅葬は、昔であれば一般的な葬儀を行う手段でした。
しかし1980年代以降、住宅事情が変化したことや近所との関係が希薄化したこと、葬儀専門の式場建設が進んだことなどにより、自宅で葬儀を行う人が大幅に減少しました。
現在では自宅で葬儀を行う方は1割にも満たないほどです。
一方、家族や近しい方々のみで行う家族葬が増えたことで、自宅葬の価値が見直されています。
家族だけで自由にゆっくり見送るのに、自宅を選ばれる方が増えているのです。
自宅葬を行うには、メリット・デメリット、注意すべき点があります。
それぞれ紹介していきますので、確認しておきましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
自宅葬のメリット・デメリット
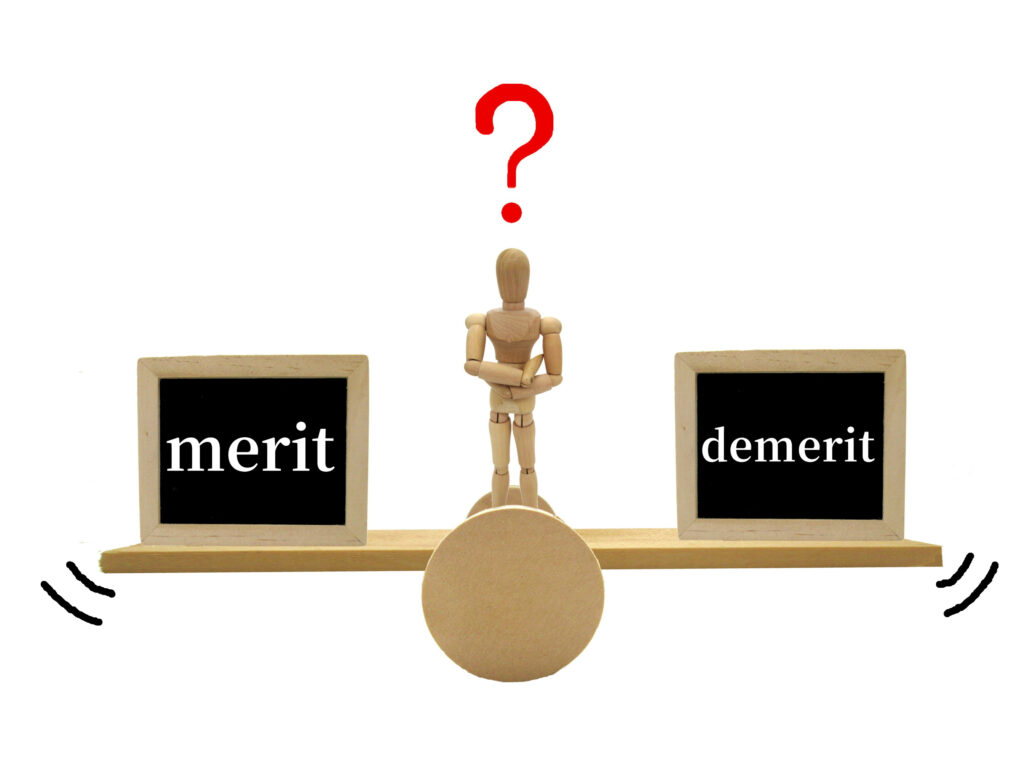
メリット
それではまず自宅葬のメリットをご紹介します。
住み慣れた自宅で最期を迎えることが出来る
故人や家族が過ごした思い出の多い自宅で最後のお別れができるのが、自宅葬の最大のメリットです。
入院生活が長かったり、施設に入所していたりした故人が「自宅に帰りたい」と希望していたとしたら、その希望も叶えることができます。
時間を気にせずお別れが出来る
斎場や寺院を借りる場合、時間的な制約が設けられていることがほとんどです。
準備を始める時間や撤収をする時間も決められており、その範囲内で葬儀を行う必要があります。
しかし、自宅であればそのような制限はないため、時間を気にせず自由に葬儀を行うことができます。
費用の負担が減る
葬儀費用の負担を少しでも軽減したいという場合でも自宅葬はおすすめです。
なぜなら、斎場や寺院を借りないためその式場使用料がかからないからです。
式場使用料は場所によっても大きく異なり数万円から数十万円かかる場合もありますが、自宅葬ではその費用が一切かかりません。
費用の負担が減るため、その分祭壇のお花を増やしたり、棺や骨壺を豪華にしたりするなど他の部分にこだわることもできます。
葬儀の費用について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
デメリット
次にデメリットをご紹介します。
準備が大変
自宅葬では、自宅に祭壇を飾ったり棺を置いたり、参列者が座るスペースを確保しなければなりません。
スペースを確保するために家具を動かしたりする必要がある場合には、遺族が中心となって行います。
また遺族以外の参列者を招く場合には、そのもてなしのための準備や片付けなども遺族が行う必要があるため、遺族の負担が大きくなります。
ご近所への配慮が必要
自宅で葬儀を行う場合には、葬儀社や棺の出入りがあったりお経の音がしたりと、どうしても多少は騒々しくなってしまうところがあります。
事前に近所へ話しておかないとトラブルになることも考えられますので、自宅葬を行う場合には事前に近所の方にお話をしておきましょう。
また事前に話しておくことにより、葬儀の準備や当日の駐車場の手配などの際に協力をしてもらえるかもしれません。
自宅葬の注意点

自宅葬を行うにあたって、事前に確認しておくべき注意点が5つあります。
それぞれ確認しておきましょう。
棺を運び入れるスペースはあるか?
棺を運び入れるスペースがあるかどうかを確認しておきましょう。
戸建てであれば玄関から葬儀を行う場所まで棺を運べるかどうか、マンションやアパートであればエレベーターに棺が入るか、階段を棺が通れるかなどを確認します。
葬儀社によっても、どのくらいのスペースがあれば運べるかという判断基準が異なってくるため、基本的には葬儀社に自宅の確認を促し判断してもらった方が確実です。
マンションの場合には通常使用するエレベーターとは別に、荷物の搬送用の大きなエレベーターが用意されていることがあるので、管理会社に確認をしてみましょう。
駐車場を確保できるか?
車でお越しになる参列者がいる場合や、僧侶が車でいらっしゃる場合には駐車場を確保しなければなりません。
近くにパーキングがあるかなどを確認したり、近所の方に自宅葬を行うことを報告する際に駐車場を貸してもらえないかを聞いてみてもいいかもしれません。
片付けに立ち会い人が必要
自宅から火葬場に出棺した後で、自宅の片付けを行います。
基本的には葬儀社が行いますが、その間家に誰もいないわけにはいきません。
家族が誰かしら立ち会う必要があるので、誰が片付けに立ち会うかを決めておきましょう。
電気容量を確保できるか?
自宅葬では飾りのための照明などで、通常時よりも多くの電気を使う可能性があります。
通夜や葬儀の途中でブレーカーが落ちてしまうということがないように、電気容量を確認しておきましょう。
もし足りなそうな場合には電力会社に連絡をして、一時的に容量をあげてもらえるように手配します。
マンションなどの場合、管理人に確認する
マンションの場合、規約などにより葬儀を行えない場合があります。
そのため、必ず管理人に確認しておきましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
自宅葬の流れ

次に自宅葬の流れを紹介します。
自宅葬は葬儀を行う場所が自宅になる以外は、斎場で葬儀を行う場合と大きくは変わりません。
死亡時刻の確認から葬式の手配
医師による死亡時刻や死因の確認後、死亡診断書を受け取ります。
死亡診断書を受け取ったら、葬儀社に連絡します。
自宅葬を行いたい場合には、最初の連絡の段階でその旨を葬儀社に伝えておきましょう。
葬儀社に連絡をしたら、葬儀社が亡くなった場所まで迎えに来て、安置場所まで搬送をします。
安置場所は自宅か安置施設かを選ぶことができますが、自宅葬を行う場合には自宅に安置することが一般的です。
故人を安置したら、葬儀に関する打合せを行います。
打合せでは、どんな祭壇を飾るか、料理や返礼品はどうするか、当日の流れなどを中心に葬儀の内容を決めていきます。
通夜当日
通夜当日のお昼頃から、打合せした内容を元に自宅に祭壇などを飾りつけます。
飾りつけが終了したら、故人を棺に収めて開始の時間を待ち、通夜式を開始します。
通夜式では、仏式で行う場合は僧侶の読経を中心に、焼香を行います。
葬儀・告別式当日
葬儀・告別式当日は僧侶による読経、焼香後、故人との最後のお別れの時間が設けられます。
お別れの時間には、棺に花や故人の愛用品などを収めて棺の蓋を閉じます。
蓋を閉じたら、火葬場に向けて出棺です。
出棺をしたあとには葬儀社が自宅の片付けを行うので、家族の誰かが立ち会ってください。
火葬場では、火葬が終了したら骨壺に収骨します。
火葬の時間が1~2時間ほどかかるため、その間に精進落としとして料理を召し上がることが多いです。
収骨後自宅に戻ったら、後飾りを設営して自宅葬は終了となります。
自宅葬の場合、祭壇はいつまで出しておく?
斎場や寺院などで葬儀を行う場合には撤収の時間が決められており、葬儀が終了したら祭壇などの飾り付けはすぐに撤収をしなければなりません。
しかし自宅葬の場合はそのような制限がありません。
それでは自宅葬の場合、祭壇はいつまで出しておくものなのでしょうか?
葬儀社に相談する
自宅葬の場合には、すぐに片付けなければならないという決まりは特にありません。
葬儀社との打合せ次第で決めることができます。
基本的に通夜・葬儀・告別式で使用する祭壇は、葬儀社の備品を使って貸し出しの形で飾られているためいつまでも飾っておくわけにもいかないものです。
そのため、葬儀社と相談をして撤収するタイミングを決めましょう。
後飾り祭壇を配置してもらうことが多い
一般的には出棺後に葬儀で利用した祭壇は片付け、後飾り祭壇や自宅飾りと呼ばれる小さな祭壇を設置してもらうことが多いです。
通夜・葬儀・告別式で使用する祭壇は先ほども説明した通り、葬儀社の備品を使用することが一般的です。
そして大きな祭壇をずっと飾っておくと自宅が手狭になってしまうため、別の小さな後飾り祭壇を設置することになります。
後飾り祭壇は四十九日までの間飾っておき、葬儀後に弔問にいらした方がいればそこで線香やお焼香をしてもらったり、お供え物を置いたりします。
後飾り祭壇は一般的に買い取りになりますので、四十九日が終了して納骨を行ったら遺族が解体して処分をしましょう。
処分の際には、自治体のごみのルールに従って処分をするよう注意してください。
もし処分をする方法が分からない場合などには、葬儀社に連絡をして教えてもらうか、葬儀社によっては引き取りに来てくれることもあります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
自宅葬のまとめ

ここまで自宅葬のメリット・デメリットについてや、注意点などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると下記のとおりです。
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。





