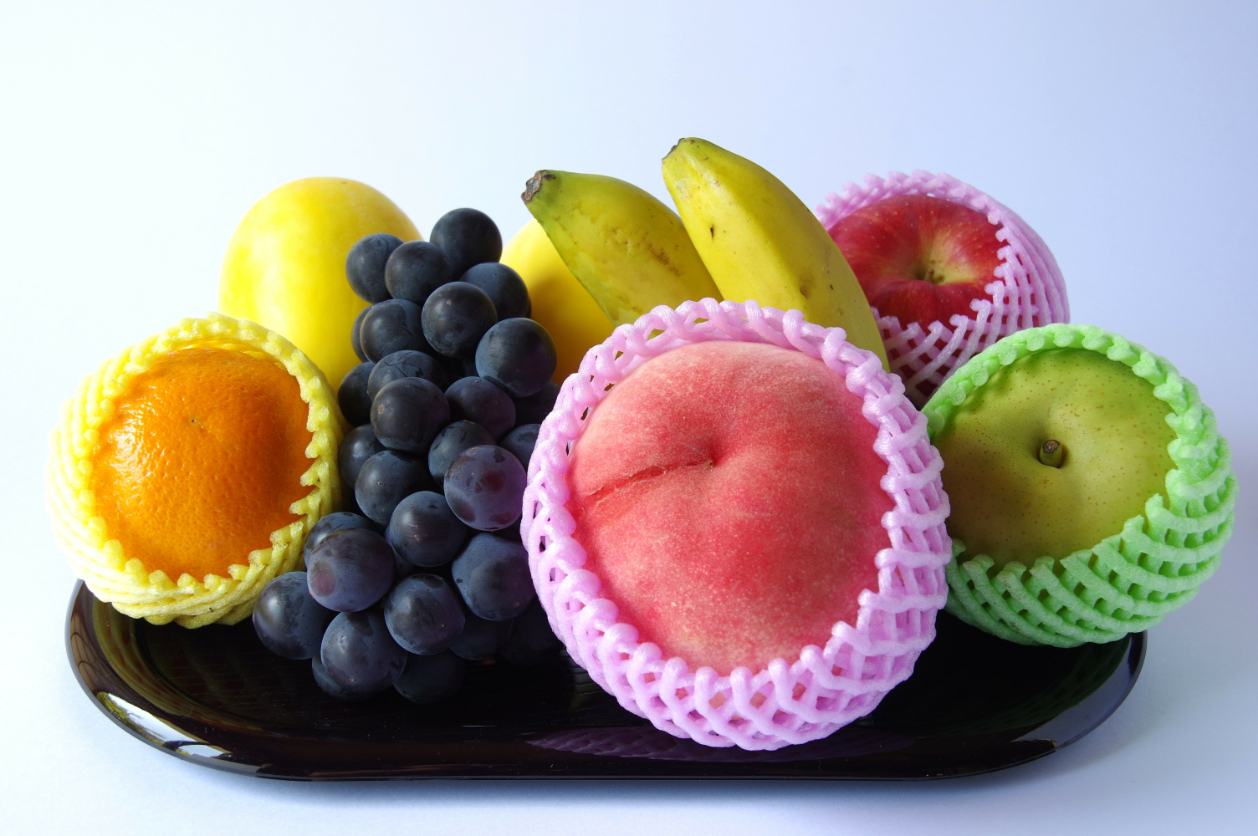お葬式
後飾り祭壇の自宅での並べ方は?祭壇の設置場所や処分方法も紹介
更新日:2022.11.19 公開日:2021.12.03

記事のポイントを先取り!
- 祭壇の並べ方は宗教で異なる
- 祭壇は可燃ごみで処分してもよい
- 祭壇は無理に用意しなくてもよい
納骨を行うまでの間、自宅には後飾り祭壇を飾る必要があります。
しかし、後飾り祭壇の並べ方には様々な決まり事があります。
そこでこの記事では、自宅での後飾り祭壇の並べ方について紹介し、その上で四十九日法要後の処分方法についてご紹介します。
後飾り祭壇の必要性についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
自宅で用意する祭壇とは
葬儀後には、自宅でも祭壇が必要となります。
この祭壇のことを後飾り祭壇といいますが、何故この祭壇が必要となるのか知らないという方もいるのではないでしょうか。
ここでは、後飾り祭壇を飾る目的や祭壇を用意する方法について解説していきます。
祭壇の目的
葬儀を終えてから忌明けして納骨するまでの期間、遺骨は自宅に安置しておくことになります。
この遺骨を安置する場所のことを「後飾り祭壇」や「中陰壇(ちゅういんだん)」と呼びます。
忌明けを迎えて納骨するまでの期間、自宅に後飾り祭壇を設置して故人を弔い、冥福を祈るのです。
葬儀と火葬が終わってから忌明けとなる日まで、後飾り祭壇の上に遺骨と仮位牌を安置します。
忌明けとなるタイミングは宗教によって異なるため、注意が必要です。
忌明けのタイミングは、仏教では四十九日法要、神道では五十日祭となります。
キリスト教の忌明けはカトリックであれば死後30日目に行う追悼ミサ、プロテスタントであれば一か月後に行う召天記念日となります。
納骨するための仏壇やお墓の購入が間に合わなかったら、忌明け後も祭壇を残すこともあります。
後飾り祭壇は、火葬から忌明けを迎えるまでの間に使用する仮の祭壇です。
また後飾り祭壇を自宅に設けることで、弔問客が故人へ祈る場となります。
後飾り祭壇は、弔問客が故人を想う場としても大切な役割を担っているのです。
用意する方法は?
いざ後飾り祭壇を用意しなければならないとなった時は、どのようにして用意すればよいのでしょうか。
後飾り祭壇を手に入れる方法としては、レンタルと購入の2つが挙げられます。
葬儀会社の中には、葬儀プランの中に後飾り祭壇一式をレンタルまたは購入する形で含んでいることもあります。
この方法は、元から葬儀会社に用意してもらえるため、自分で祭壇を用意する必要がないという利点があります。
ただしどの葬儀会社でもやっている訳ではないため、事前に確認が必要となります。
葬儀会社のプランに含まれていない場合には、自分で購入する必要があります。
仏具店やインターネットで、後飾り祭壇を購入することが可能です。
また、段ボールでできた後飾り祭壇のキットも存在しています。
こうしたキットを使用すれば、自分自身で後飾り祭壇を作るということも可能です。
通常の祭壇では置き場所がない場合や、祭壇の購入予算に余裕がないという方は、こうしたキットを利用するのも良いでしょう。
スポンサーリンク後飾り祭壇の設置場所
後飾り祭壇を設置する場所は、自宅であればどこでも良い訳ではありません。
一般的に家に仏壇がある場合には、その仏壇の前に後飾り祭壇を設置します。
もし仏壇がない場合には、部屋の北側か西側に設置するのが良いとされています。
また弔問客が後飾り祭壇に祈りを捧げることも考慮して、お客様が入りやすい場所に置くと良いでしょう。
祭壇に日が当たると遺骨や位牌の劣化が進んでしまうため、直射日光を避けて設置することをおすすめします。
キッチンやお風呂場の近くも湿気が多くなってしまい、劣化を招いてしまうため要注意です。
もし日当たりや湿気などの関係で部屋の北側・西側に設置するのが難しい場合には、弔問客や家族が祈りを捧げやすいかどうかを基準に場所を決めると良いでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
後飾り祭壇の並べ方
ここからは、後飾り祭壇の並べ方について解説します。
祭壇の並べ方は宗教によって異なるため、注意が必要です。
飾る仏具は基本的に仏壇と同じものを使用するため、すでに自宅に仏壇がある方は新しく用意する必要はありません。
仏式の場合
以下で仏式の場合の並べ方をご紹介します。
上段
後飾り祭壇の棚は基本的に2段か3段のものが一般的です。
3段の場合、上段には故人の遺影と遺骨を隠岐ます。
また、2段の場合にはこれらと一緒に仮位牌を置く場合もあります。
中段
3段で、中段がある場合にはここに仮位牌を置きます。
下段
下段には香炉・蝋燭台・線香台・お鈴・花立て・お供え物を置きます。
お供え物として、故人が生前好きだったものなどを置いても構いません。
神式の場合
次に、神式の場合の後飾り祭壇の並べ方について解説します。
神式の祭壇は八足祭壇と呼ばれる、足が8つあるものを使用します。
また、神式の場合には仏式と違い、仏具は使いません。
上段
上段には仏式と同様に遺影と遺骨を置きます。
中段
中段には霊璽(れいじ)と榊(さかき)を飾ります。
霊璽とは仏式の場合の位牌にあたるもので、故人の御霊を祀るためのものです。
下段
下段には三方(さんぼう)と呼ばれる台の上に徳利(酒を入れる)・水玉(水を入れる)・皿(洗米と塩を入れる)などを置きます。
また、玉串とお供え物もこの段に置きます。
キリスト教式の場合
キリスト教式では、テーブルの上に白い布を被せて祭壇を作るのが一般的です。
キリスト教にはもともと祭壇を飾る文化はありません。
そのため、後飾り祭壇の並べ方のルールも細かく決められている訳ではありません。
以下で一般的な例をご紹介します。
上段
上段には仏式や神式とは違い、遺影や遺骨を置くのではなく十字架を置きます。
中段
中段には遺影と遺骨を置きます。
下段
下段には生花・聖書などを置くのが一般的です。
スポンサーリンク祭壇のお供え物
ここからは、後飾り祭壇に置くお供え物についてご紹介します。
お供え物は、宗教ごとにどういったものを供えるべきかが細かく変わってきます。
一般的なお供え物を、宗教ごとに具体例を挙げてご紹介していきましょう。
仏式
仏式の後飾り祭壇には以下のようなものをお供えするのが一般的とされています。
- 茶
- 水
- 果物
- お菓子
- 生花
- 仏飯
仏飯(ぶっぱん)とは、仏前にお供えするご飯のことを指します。
これと水は毎日取り替え、お供えするようにしましょう。
お供えしたものの中でも果物やお菓子などは、賞味期限が切れる前に仏前から下げ、家族で召し上がるようにします。
この他にも、故人が生前好きだったものをお供えしても問題ありません。
神式
神式の場合のお供え物として定番のものは以下の4つです。
- 洗米
- 神酒
- 水
- 塩
これらは祭壇上では三方の中に置かれるもので、神式における正式なお供え物となっています。
仏式とは違い、線香・蝋燭などは使わないため、神前にお供えする物として不適当です。
仏式と神式の違いをしっかりと確認しておきましょう。
この他にも故人が好きだった果物などをお供えしてもいいでしょう。
キリスト教式
キリスト教式の場合は、お供え物の概念がないためルールも定まってはいません。
ただ、故人に生花を捧げることが多いです。
キリストの肉であるとされる、パンをお供え物として捧げることも多いです。
そのほかにも、故人が好きだったものをお供えしても問題ありません。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
後飾り祭壇の処分方法
ここからは、自宅に置いた後飾り祭壇の処分の方法についてご紹介していきます。
後飾り祭壇は忌明けになると処分することになります。
しかしながら、この記事をご覧になっている方の中には後飾り祭壇の処分方法をどうしようかと困っている方もいるでしょう。
具体的な処分方法について以下で解説していきます。
祭壇をゴミとして処分する
忌明けとなり自宅の後飾り祭壇が不要になった場合には、祭壇をゴミとして処分することができます。
自治体によってゴミ収集のルールは異なるため、決められたルールに従って祭壇を処分しましょう。
多くの場合、祭壇は可燃ごみとなります。
しかし、人によっては故人を想って祈りを捧げてきた祭壇をゴミに出すことが嫌だという方もいることでしょう。
そのような場合には、葬儀社や寺院などに祭壇の処分方法について相談してみることをおすすめします。
祭壇を引き取ってもらえたり、良い処分方法を教えてくれるでしょう。
残しておいても良い
祭壇は必ず処分しなければならないという訳ではありません。
ゴミとして処分せずに、そのまま自宅に残しておいても問題ありません。
祭壇は年忌法要などの節目の儀式で使用することが可能な他、仏具は仏壇用のものと同じであるため仏壇で使用することができます。
そのため、自宅に場所を確保できるのであれば、後飾り祭壇を残しておいても良いでしょう。
白木位牌はどうすれば良い?
後飾り祭壇に置く仮位牌である白木位牌は、どのようにして処分すればよいのでしょうか。
これはその名の通り仮のものであるため、四十九日を迎えると本位牌に故人の魂を移します。
そのため白木位牌も後飾り祭壇と共に不要となりますが、こちらは後飾り祭壇と違いゴミに出すことはおすすめしません。
白木位牌は、菩提寺などに相談をして忌明けにお焚き上げしてもらうことをおすすめします。
また、本位牌は忌明けを迎える前までに用意しておく必要があるため注意しましょう。
スポンサーリンク浄土真宗の後飾り祭壇について
後飾り祭壇は、宗派によっても並べ方が異なります。
前述した仏式の並べ方と、浄土真宗の並べ方は異なるため注意が必要です。
具体的にどういった部分が異なるのか、以下に箇条書きでまとめます。
- 浄土真宗では祭壇の上に遺影・遺骨・位牌の3つのみを置く
- 線香や蝋燭、生花は祭壇ではなく仏壇に置く
- 読経や供花も仏壇に置く
- 水・お茶・御膳のお供えはしない
- 華瓶(けびょう)を仏壇に置き、樒(しきみ)を飾る
浄土真宗では後飾り祭壇の上には最低限のものしか置かず、ほとんどの物を仏壇の上に置きます。
他の宗派では祭壇の上に並べるものも、浄土真宗では仏壇に置くことが多いため注意しましょう。
また浄土真宗ならではの仏具として、華瓶とそこに生ける樒という植物があります。
樒は浄土真宗では魔除けになるとされており、故人のことを守ってくれるとされています。
そのため、これを仏壇に置くことで故人をお守りするという意味があります。
浄土真宗の後飾り祭壇は独特なルールが多いため、上記の内容を参考にしてしっかりと事前に確認しておくと良いでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
後飾り祭壇はなくても大丈夫?
後飾り祭壇は、必ず用意しなくてはならないものではありません。
置き場所がない場合には、無理に祭壇を用意する必要はありません。
祭壇が自宅になかったり、新たに用意するのが難しかったりする場合には、机や段ボールなどに白い布を被せて即席で作ることもできます。
布で覆ってしまえば、中身がどうなっているかは分からないため、あり合わせのもので祭壇を作ってしまっても問題ありません。
自分たちなりに故人への弔いの気持ちを示せる形で、遺影や遺骨を飾れば基本的には問題ありません。
自宅の祭壇の並べ方まとめ

ここまで後飾り祭壇の自宅での並べ方についての情報や、後飾り祭壇の処分方法などを中心に書いてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 自宅の後飾り祭壇の並べ方や並べる物は宗教によって異なる
- 祭壇はゴミとして処分しても、残しておいても問題ない
- 白木位牌は忌明けになったらお寺にお焚き上げしてもらう
- 浄土真宗では通常の仏式の並べ方とは異なるため注意
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2024.03.30
離婚した父の葬儀で喪主は誰がやる?参列の可否や香典の扱いについても解説
お葬式

更新日:2022.11.21
町内会の回覧板で訃報のお知らせをするには?文例や注意点を紹介!
お葬式

更新日:2025.06.14
葬儀場での宿泊は可能?宿泊できる人、費用や準備品についてわかりやすく解説!
お葬式

更新日:2022.11.18
なぜご遺体の手を組む必要があるの?手を組む理由や注意点も紹介
お葬式

更新日:2022.11.21
供花を頂いたらお礼はするべき?お礼状の書き方や例文も紹介
お葬式

更新日:2022.11.21
忌引きの連絡はメールでも良い?書き方や文例なども紹介