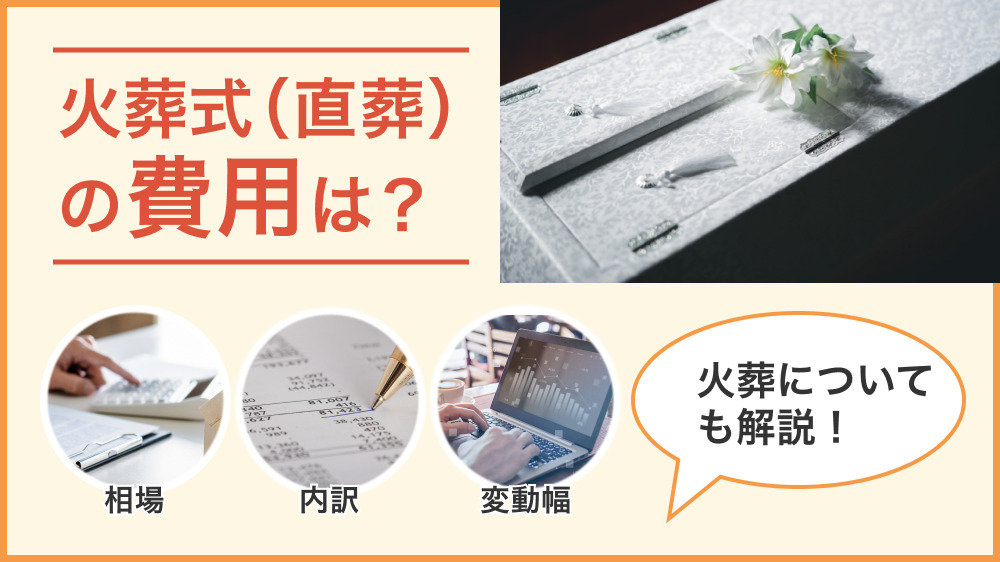お葬式
箸渡しの意味とは?恥をかかないためのマナーを解説
更新日:2024.01.24 公開日:2022.07.17

記事のポイントを先取り!
- 箸渡しとは遺骨を箸で運ぶ儀式
- 箸渡しは2人1組で行う
- 箸渡しは喪主に言えば辞退できる
- 箸渡しがタブーなのは日本のみ
日本では、火葬で行われる儀式のひとつとして、箸渡しと呼ばれるものがあります。
箸渡しを行う際には、守るべきマナーがあることをご存知でしょうか。
そこでこの記事では、箸渡しの意味やマナーについて解説します。
この機会に、箸渡しに込められたマナーについて知っておきましょう。
後半では、子どもは箸渡しに参加できるのかについて触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
箸渡しとは
箸渡しは、故人を火葬したあと、骨上げの際に行われる儀式です。
遺骨は入れ物に入れなければ持ち帰れないため、骨壷に入れて持ち帰ることとなります。
この儀式は、親族や参列者が二人一組となって、一緒にお骨を持ち上げて骨壷の中へと移動させるというものです。
ただし、箸渡しですべての遺骨を骨壷に入れるわけではなく、遺族が拾骨するのはその一部分となっています。
このとき、男女でペアになって行うことがあるなど、宗教や地域などの関係でやり方が異なります。
箸渡しは日本特有の作法
箸渡しは、同音異義語である「橋渡し」とかけて行われる儀式です。
仏教儀式の一種ですが、中国ではこの儀式が行われておらず、日本特有のものだとされています。
もともとは遺骨を箸で掴んだら、それを遺族が順番に渡していって、骨壷に入れるという儀式であったようです。
それが時代とともに、箸を持って遺骨の一部を運ぶという儀式へと変わっていきました。
また、箸渡しは火葬が始まってから行われるようになったものです。
火葬がなく、土葬が一般的だった明治初期までは、この儀式は存在しませんでした。
現在でも、地域によっては箸渡しが行われない場合があります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
箸渡しの意味

前述したように、箸渡しは「橋渡し」とかけて行われるものです。
この橋渡しは、故人が死後訪れるとされる三途の川と関係しています。
三途の川とは、あの世とこの世の間に流れているとされる川のことです。
亡くなった方はこの三途の川を渡って、あの世へと向かいます。
箸渡しでは、故人がこの川を無事に越えて、あの世へ行けるように橋をかけてあげるという意味があります。
上記のことから分かる通り、こちらの儀式は故人を供養する儀式の一種として行われるものです。
箸渡しのマナー
ここからは、箸渡しする際の具体的なマナーを紹介します。
箸渡しは地域や宗教によってもやり方が異なるため、以下では一般的なものを取り上げて説明していきます。
原則2名1組で行う
箸渡しは、基本的に2名1組で行います。
箸渡しが2名1組で行われるのには、故人の霊が1人に取り憑くのを避け、故人の死を一緒に悲しむためという理由があります。
箸渡しの行い方は複数あり、代表的なのが、1人が箸で遺骨を持ち上げて、もう1人がそれを受け取って骨壷に入れるというものです。
他にも、男女が2人1組になって2人で同時に遺骨を持ち上げて、骨壷に運ぶというのもよく行われます。
また、2名1組で行われないケースもあります。
その代表的な例が、参列者が一列に並んで、最初の人が持ち上げた遺骨を箸で隣の人に順番に骨を渡していくというものです。
この場合は、最後の人が遺骨を受け取ったらその人が骨壷に遺骨を入れます。
もし、どういった方法で行うのか分からない場合は、火葬場スタッフの指示に従いましょう。
関係が深い遺族から行う
遺骨は、故人と関係が深い遺族から順番に行うのがマナーです。
そのため、喪主から順番に箸渡しを行います。
喪主が終わったら、遺族、親族、友人、知人といった順番で行っていきます。
自分が故人と友人や知人の関係である場合は、遺族よりも先に橋渡しをしないよう注意しましょう。
箸渡しを行う回数は1人1回
箸渡しは原則として、1人1回ずつ行うのが作法だとされています。
ただし、参加している人の人数が少ない場合には、喪主や遺族などの血縁関係が深い人がもう1度遺骨を拾うこともあります。
その場合は、火葬場のスタッフの指示に従いましょう。
長さ・素材の違う箸を左右一組にする
箸渡しで使われる箸は、普段使われるのと同じようなものではなく、箸渡し用の骨上げ箸を使います。
この骨上げ箸は、左右で長さと素材が異なっており、一般的に竹と木でできた箸を使います。
このように専用の箸を使うのは、日常的に使う箸を骨上げで使うのは縁起が悪いとされているためです。
また、不揃いの箸を使用することで、箸を揃えることもできないほど気が動転していると意思表示できます。
ちなみに、葬儀などでは「逆さごと」といい、普段とは逆の物を使うことが良くあります。
箸渡しも普通は揃っている箸を不揃いで使うことから「逆さごと」の一種だと捉えられています。
足の骨から徐々に上の骨を拾う
骨上げでは、下の方の骨から順番に拾って行くのがマナーです。
これは足の方から拾っていくことで、故人が骨壷に入ったときも生前となるべく同じ姿にしたい、という思いが込められているとされます。
一般的に足の骨を最初に拾い、最後に喉仏を拾います。
頭の骨ではなく喉仏が最後なのは、喉仏の形が座禅を組んだ仏様が合掌しているように見えるためです。
そのため、仏教の儀式の一種である骨上げでは、この喉仏の骨を重要視しています。
骨を拾う順番にもルールがあり、どこから拾っても良いわけではないため注意しましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
箸渡しを拒否することは可能なのか?

骨上げや箸渡しが行われる際、何らかの事情により参加したくないという場合もあるでしょう。
人によっては故人の遺骨を見ることが難しかったり、故人と生前の関係が良好でなかったりすることがあります。
もし箸渡しをやりたくない場合には、拒否することも可能です。
箸渡しを拒否したい場合は、喪主に伝えて骨上げに参加しない旨を伝えましょう。
ただし、基本的に拾骨は行わなければいけない儀式であるため、骨上げ自体を行わないということはできません。
原則、お骨は誰かが持ち帰ることになるため、その点だけ留意しましょう。
子供は箸渡しに参加できる?

子供であっても、箸渡しに参加することは可能です。
ただし、まだ5歳前後の小さい子供であった場合、手元がおぼつかず、骨上げはなかなか難しいかもしれません。
その場合は、親が手伝って一緒に行うようにしましょう。
子供が箸渡しに参加する場合は、事前に火葬場スタッフに話を通しておくとより良いでしょう。
ただし、子供によっては骨上げが精神的に大きなストレスとなる場合があります。
例えば、思春期の子供や小さな子供は、精神的に不安定な場合が多く、悪影響になる可能性もあります。
そのため、本人が嫌がる場合は、骨上げに参加しないという選択肢もあることを覚えておきましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
食事の際、箸渡しがタブーなのは日本だけ
日本では、食事をする際に、箸渡しをするのはタブーとされています。
これは、葬式での箸渡しを連想させるためです。
食事の場では「移し箸」や「合わせ箸」などとも呼ばれますが、誤って食事の場でこれを行わないよう注意しましょう。
また、ひとつの料理を二人で同時に掴む「二人箸」も、同様に箸渡しを連想するためマナー違反です。
上記に加えて、箸が片方ずつ違うものを使うのも「竹木箸」と言って、箸渡しで使う箸を連想することから、マナー違反となります。
ただし、韓国では火葬の際に箸渡しの儀式がないため、食事の場でも普通に箸渡しすることがあります。
食事の際に箸渡ししていけないのは、日本特有のマナーだという点を理解しておきましょう。
箸渡しのまとめ

ここまで、箸渡しの意味や箸渡しを行う際のマナーについて解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 箸渡しは骨上げの際に行うもので、故人の遺骨を箸で骨壷に入れる儀式のこと
- 箸渡しは、故人が無事に三途の川を渡れるようにという意味がある
- 2人1組で、故人と関係の深い人から順番に行う
- 箸渡しをしたくない場合は、喪主に伝えて辞退する
- 箸渡しがタブーなのは日本のみで、韓国ではマナー違反にならない
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.11.19
近所の人の出棺の見送りへは行くべき?服装の注意点は?
お葬式

更新日:2024.04.02
火葬許可証と埋葬許可証の違いは?紛失した時の再発行の仕方なども紹介
お葬式

更新日:2024.02.18
亡くなってから火葬までの流れは?火葬の段取りについて解説