法事法要
お盆の迎え火をする日時や時間帯は?やり方や送り火についても解説
更新日:2022.05.17 公開日:2021.11.07

記事のポイントを先取り!
- 迎え火行う時間帯は夕方が多い
- 迎え火は玄関先で行うことが多い
- 迎え火は提灯で代用できる
お盆ではご先祖様のために迎え火を焚きます。
迎え火はいつ、何時ごろに焚けばいいのかをご存知でしょうか?
今回は迎え火と送り火の意味を踏まえつつ、それぞれ焚くといい時間帯など詳細をお伝えします。
また、迎え火と送り火を焚く流れについても詳しくご説明します。
ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
お盆に行われる行事「迎え火」とは?
お盆に行う迎え火という行事にはそもそもどんな意味があるのでしょうか?
迎え火はどんな行事か
迎え火とは、お盆にご先祖様を迎えるために焚く火のことです。
昔はお墓参りをした後、ロウソクの火を提灯に移して消えないように持ち帰りました。
そして、その提灯の火を火種として迎え火を焚いていました。
現代では、玄関先で火をつけて焚くやり方が主流になりました。
迎え火を燃やす燃料となるのがオガラです。
オガラとは麻の茎の皮を剥いだものです。
オガラがない場合は松明やバカラという白樺の木の皮で代用できます。
送り火は玄関先や庭などで焚くのが一般的ですが、都会のマンション住まいで迎え火や送り火の儀式をするのは難しいでしょう。
玄関先やベランダで火を焚くのは近所迷惑にもなってしまいます。
もし、迎え火を焚けない場合は提灯をお供えすることをおすすめします。
近年は、LED電球を使用したタイプの盆提灯が販売されています。
火事の心配もありませんし、お盆のお供えとしても最適なアイテムといえます。
迎え火と送り火をする意味
迎え火とは、お盆に帰ってこられるご先祖様が道に迷わないよう祈りを込めて焚くものです。
迎え火の煙に乗ってご先祖様が帰ってこられるという説もあります。
また、ご先祖様は昔の記憶をなくしているといわれています。
そのため、迎え火から立ち昇る煙を目印に帰ってくるという説もあるようです。
送り火はお盆の最終日、ご先祖様をお見送りするときに焚くものです。
ご先祖様があの世へ帰られる際の道を明るく照らす役割があります。
また、送り火を焚くことで悪霊を追い払う効果があるとされています。
焚いた送り火が燃え尽きると、ご先祖様があの世へ到着した合図であるといわれています。
お盆に迎え火と送り火を行う時間帯

迎え火と送り火を行う時間は決まっているのでしょうか?
それぞれ何時から焚くのかをお伝えします。
迎え火・送り火それぞれの時間帯
迎え火を焚くのは8月13日(新の盆は7月13日)の夕方17時くらいの時間です。
実は迎え火を焚く時間は厳密に決められているわけではありません。
一般的には13日ですが、お盆の前日である12日の夕方頃に焚く家もあります。
家族の仕事が終わる時間や親戚の集まる時間に合わせて迎え火を焚いても問題ありません。
送り火を焚くのは8月16日(新の盆は8月16日)の夕方17時くらいの時間です。
迎え火と同様、送り火の時間も定められていません。
17時くらいから19時くらいまで2時間ほど焚く家が多いようです。
一般的にはご先祖様がお帰りになるとされるお盆最終日に合わせて焚きます。
8月17日までがお盆期間の地域は17日に焚きましょう。
迎え火・送り火を行う時間帯の理由
霊が動き始めるのは薄暗くなってきてからといわれています。
そのため、迎え火も送り火も辺りが薄暗くなる夕方くらいの時間帯から焚き始めるのが一般的です。
また、通常のお盆の流れから迎え火の時間が夕方になってしまうという理由もあります。
お盆の初日である13日の流れとして、午前中にお墓の掃除を行い、午後からお墓参りへ行きます。
お墓参りの際、盆提灯にロウソクの火を移して持ち帰り、迎え火を焚くころにはちょうど夕方の時間となります。
送り火は少しでもご先祖様に長く滞在してもらいたいという願いから、夕方に焚くことが多くなりました。
みんなが選んだ法事法要の電話相談
みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
5万円からご案内!
4万円からご案内!
迎え火と送り火の流れ
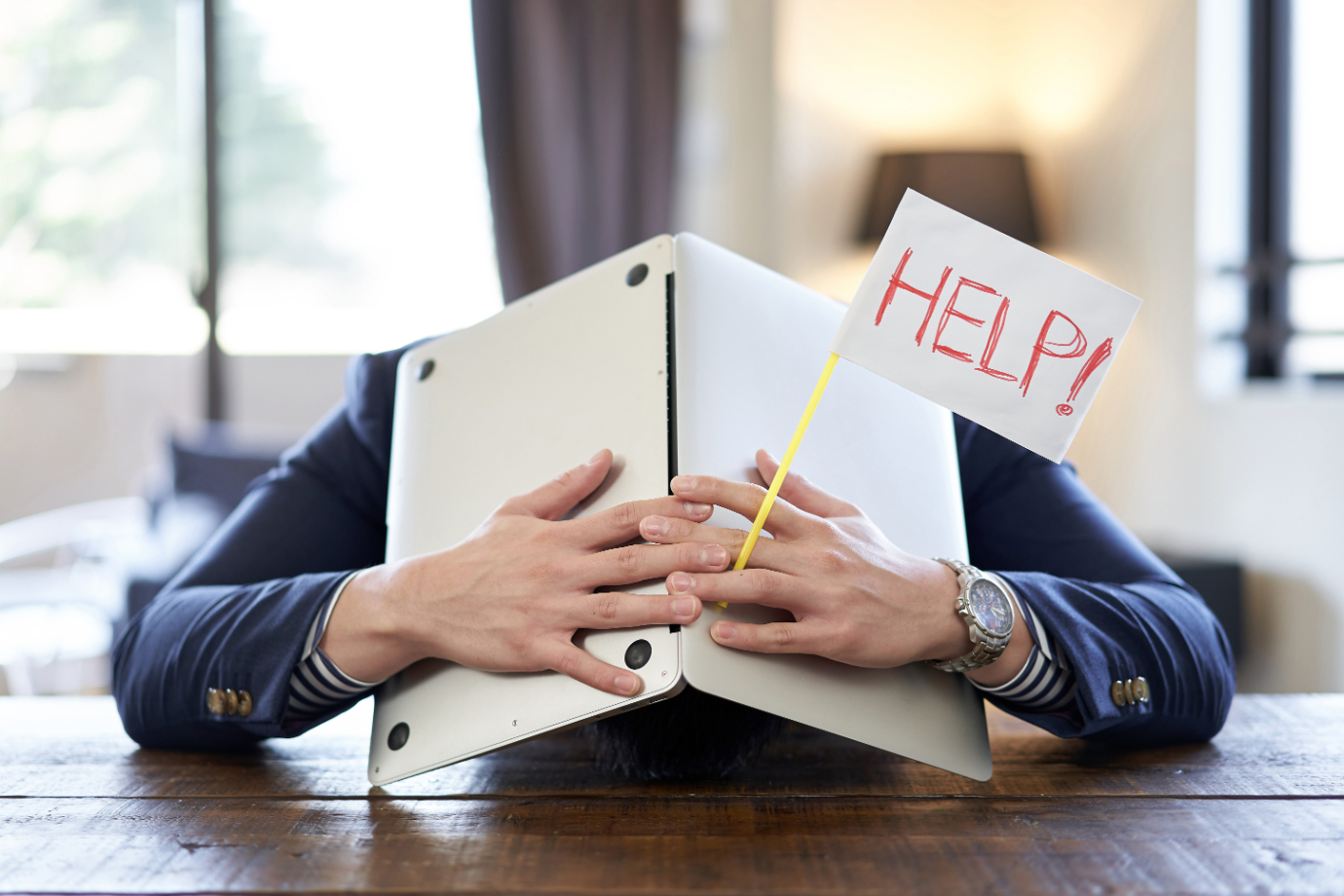
迎え火と送り火、それぞれの流れについて詳しくお伝えします。
送り火と迎え火に必要なもの
送り火と迎え火に必要なものは以下の通りです。
- 焙烙(ほうろく)
焙烙とは素焼きの平たいお皿のことです。
なければ小さめの灰皿などでも構いません。
- オガラ
麻の茎の皮を剝いだものです。
スーパーや花屋、ホームセンターなどでも購入できます。
オガラがない場合は松明やバカラという白樺の木の皮を代用します。
稲藁を使用する地域もあるようです。
いずれも焙烙に乗るくらいの短めにカットしておきます。
- 新聞紙
オガラに直接火が付きづらいため、種火用として新聞紙を使用します。
小さめにちぎったものを用意しておきます。
- ライター
着火用にライターかマッチを用意します。
お盆の時期になると、迎え火・送り火のセットがスーパーなどでも販売されるようです。
もちろんネットでも購入できます。
それぞれの流れ
迎え火と送り火の焚き方についてご説明します。
迎え火
- 焙烙の上にカットしたオガラをのせる
オガラは手でも簡単に折れます。
焙烙からはみ出ていると火種が落ちる原因となるため短めにカットしましょう。
オガラはキャンプファイヤーのように四角く交互に積んでいく木組みを作ります。 - 火をつける
ライターで新聞紙に火をつけ、木組みの真ん中に落とします。 - オガラが燃え尽きるまで見守る
火の粉が飛ぶと火事の原因となるため燃やし始めたら目を離さないようにします。
送り火
やり方は迎え火と同様になります。
オガラが燃え尽きたときにご先祖様が到着するといわれているため、送り火の時もしっかり見守ります。
お盆飾りである、野菜で作った精霊馬や精霊牛もこのとき一緒に燃やす地域もあるようです。
また新盆の場合、ご先祖様を迎えるために白提灯を用意します。
この白提灯も送り火を焚くときに一緒に燃やすのが一般的なようです。
燃やし終わった灰は一般ごみとして廃棄してOKです。
庭で燃やした場合は埋めてもいいでしょう。
送り火と迎え火に使われるオガラとは
オガラは「麻幹」と漢字で表すことからもわかるように植物の麻のことです。
麻の茎部分の皮を剥いで乾燥させたものがオガラです。
迎え火と送り火を焚く燃料として使用されるオガラですが、実はお盆のお供物にも活用されています。
お盆には精霊棚(しょうりょうだな)というお供え物を置く棚を作ります。
精霊棚は帰ってきたご先祖様が休んでいる場所とされる大切な棚です。
精霊棚にはキュウリやナスで作った精霊馬や精霊牛などの盆飾りも備えます。
この精霊馬や精霊牛の足部分をオガラで作る地域があります。
精霊馬についてもっと詳しく知りてい方は「お盆に飾る精霊馬とは?作り方や詳しい意味まで解説」をご覧ください。
また、麻幹箸(おがらばし)という箸や、7段もしくは13段のオガラのはしごをお供えする地域もあります。
岐阜県神戸市で行われる火祭りでは、オガラを松明として利用しています。
もともと麻は清浄な植物として親しまれていたので、悪い例を追い払い、辺りを清らかな空気にするといわれています。
よって、オガラは迎え火や送り火、お祭りなどの儀式に最適な植物といえます。
お盆に大活躍するオガラですが、儀式やお祭り以外にも沢山の活用方法があるのをご存知でしょうか。
オガラは天然の消臭剤と呼ばれるほど消臭効果のある植物です。
トイレのアンモニア臭をなくしてくれる効果もあるそうです。
短くカットしてガラス容器などに入れておけば、インテリア兼消臭剤の役割を果たしてくれます。
また、日本では古くから茅葺き屋根の下地材として利用されていました。
オガラは中が空洞で軽く、調湿や温度調整ができるため建築材としても優秀です。
近年、ヨーロッパではオガラと石灰を混ぜたヘンプクリートが注目されています。
フランスではオガラの調湿性と温度調整の特性を生かし、ブロック状のヘンプクリートでワイナリーを作っているようです。
他にも家畜の飼料やペレットなどオガラは幅広い用途で使用できる植物です。
みんなが選んだ法事法要の電話相談
みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
5万円からご案内!
4万円からご案内!
送り火の種類

迎え火や送り火はご先祖さまの無事を祈るための大切な儀式です。
しかし、送り火とはオガラを燃やして火を焚くだけではありません。
お盆の時期にニュースなどで見かける灯籠流しも送り火と同様の意味を持っています。
精霊流しともいいますが、そもそも精霊とはご先祖様の霊のことです。
船に見立てた灯籠に火を灯し、川や海へご先祖様の霊を送り出すのが本来の意味となります。
夏に行われるイベントは、実はお盆と深く関わっている行事です。
地域によってはお盆行事を大々的なイベントとして取り扱う地域もあります。
例えば京都の五山送り火は有名なお盆行事のひとつです。
発祥時期は定かではありませんが、平安時代から室町時代に始まったものとされています。
京都を囲む山々に送り火を灯すことで死者の霊であるお精霊(おしょらい)さんを極楽へ送り届ける行事です。
その中の五山送り火で護摩木に氏名や年齢、性別を書いて焚いてもらうと厄除けになるとされています。
また、燃え残った灰を包んで水引きをつけ、家の戸口にかけると疫病避けになるそうです。
ほかにもお盆行事として長崎県の精霊流し(しょうろうながし)が有名です。
精霊流しは初盆(故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のこと)の遺族がおこなうものです。
竹や藁で骨組みを作った船形に、花や果物で装飾したものを担いで町を練り歩きます。
船の先端の水押(みよし)と呼ばれる部分には町名や家紋が表されており迫力があります。
爆竹を鳴らしながら進んでいくのも精霊流しの特徴です。
お盆の迎え火の時間まとめ
ここまで、お盆に迎え火を焚く時間についての情報を中心にお伝えしました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りになります。
- 迎え火と送り火はお盆にご先祖様を無事にお迎え・お見送りするための儀式
- 迎え火の時間は13日の17時ころから、送り火は16日の17時ころから焚き始めるのが一般的
- マンション住まいなどで火を焚くのが難しい場合は盆提灯を灯してお供えする
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
法事法要の関連記事
法事法要

更新日:2022.05.17
お盆に用意する真菰(まこも)とは?使い方や購入方法なども紹介
法事法要

更新日:2022.05.16
お盆のほおずきにはどんな意味があるの?飾り方や片付け方も紹介
法事法要

更新日:2022.05.17
お盆のお膳の中身はどうする?お膳の並べ方やお供えする期間も紹介
法事法要

更新日:2022.06.06
お盆では何をお供えする?初盆法要のお供え物について紹介
法事法要

更新日:2022.05.17
お盆の提灯の飾り方とは?飾る時期や盆提灯の種類も紹介
法事法要

更新日:2022.09.06
お寺で行う初盆法要のマナーは?初盆のお布施の相場や書き方も解説







