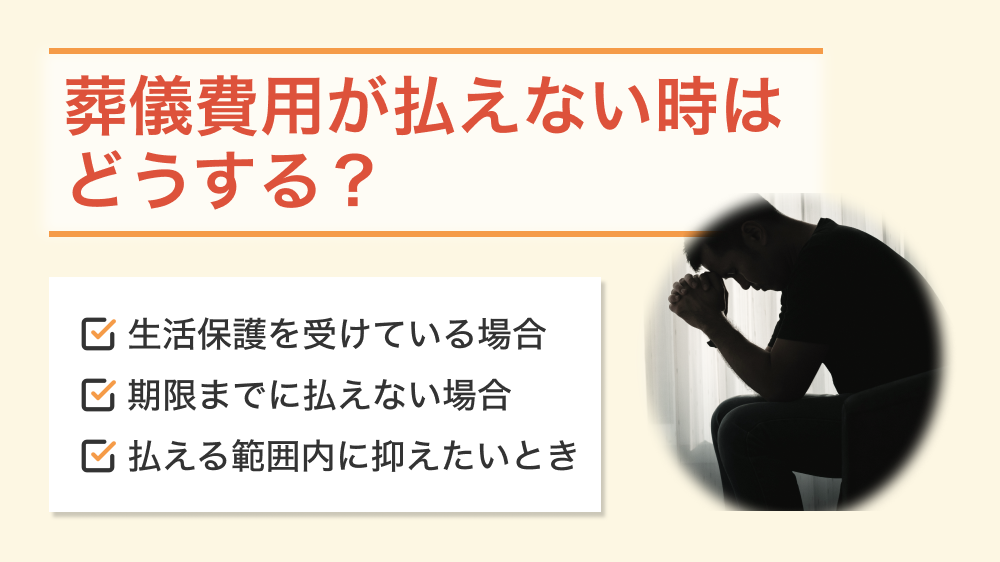お葬式
葬儀費用って誰が負担するの?トラブルを避けるために知っておくべきこと
更新日:2024.02.22 公開日:2021.06.18

記事のポイントを先取り!
- 葬儀費用は喪主の負担が一般的
- 必ずしも喪主が負担する必要はない
- 遺産から葬儀費用を出すことも多い
親の葬儀などの際は、葬儀費用をだれが払うのかを話し合う必要があります。
いざそういう場面になった時、誰が負担するべきなのか分かりませんよね。
そこでこの記事では、葬儀費用の負担のしかたについて解説いたします。
この機会に葬儀の負担を誰がするのかなどについて確認しておきましょう。
葬儀費用を抑える方法についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 葬儀費用は喪主が支払うのが一般的
- 喪主が全額払えない場合は施主に支払ってもらうことも
- 喪主の決め方
- 遺言書などが残されていた場合
- 香典を葬儀費用に充てることは可能?
- 葬儀費用の支払いについて
- 葬儀費用について知っておくべきこと
- 葬儀費用の負担について争う方法
- 葬儀費用を安くするには
- 兄弟間での葬儀費用トラブルを防ぐ方法
- よくある質問
- 葬儀費用についてのまとめ
葬儀費用は喪主が支払うのが一般的

葬儀の費用は、喪主が負担するのが一般的とされています。
喪主をはじめ葬儀を執り行う人たちは個人の親族であることがほとんどです。
親族は個人の遺産を受け取ることが多いため、故人の遺産は葬儀の費用負担に大きく影響します。
喪主とは
喪主は、遺族の代表者として葬儀や葬式を主催します。
喪主の役割は葬儀内容のとりまとめや弔問客や僧侶への対応など様々あります。
葬儀全体を取り仕切る存在であるため、スムーズに葬儀を行うためにとても重要な役割を担っています。
一般的には個人の配偶者や子供など、血縁の近い親族が喪主を務めることが多いです。
法律では誰が払うか定められていない
喪主が葬儀費用を負担するというのは、あくまで慣例です。
実は、葬儀費用を誰が負担するかについては、民法やその他の法律では定められていません。
そのため、必ずしも喪主ばかりが葬儀費用を負担する必要はないのです。
喪主一人では支払いが難しい場合、親戚や共同相続人が一部または全額を負担する場合もあります。
喪主が全額払えない場合は施主に支払ってもらうことも

故人の配偶者が喪主となっており、高齢で葬儀費用を負担する余裕がない場合など、喪主が葬儀費用を全額負担できないこともあります。
このような場合、施主に支払ってもらうことも多いです。
では、そもそも施主にはどのような役割があるのでしょうか。
施主とは
お葬式で中心となる喪主と施主ですが、喪主と施主には異なった役割があります。
施主にはお布施をする人という意味があり、葬儀の費用を担う人であるといわれています。
たとえば、世帯主が亡くなり、喪主は息子で施主が妻というケースがあります。
その場合、息子はお葬式を主催し、妻は葬儀費用を支払うという役割になります。
ちなみに施主の決め方は血縁関係の深い順に決めていくことが一般的とされていますが、同居する家族構成などに合わせても問題ありません。
一般的には喪主=施主と考えられることが多く、同じ人物が施主と喪主の役割をすることが多いです。
相続人で分担する場合
葬儀費用は相続人で分担することも可能です。
その場合、故人の両親や兄弟・姉妹などの親族に費用を分割で負担することになります。
一般的に分割時の負担割合は年齢や年収などをふまえて決めていきます。
相続財産から支払うことも可能
故人の遺産がある場合、故人の相続財産から支払うことも可能とされています。
相続財政から支払うことは相続税の計算もその分を差し引いて行うことになるので、節税対策にもなります。
通夜や告別式、火葬、埋葬にかかる費用やお布施も相続税の控除対象になるため、相続財産がある場合はそこから支払うのがおすすめです。
香典返しや墓石の費用、初七日、四十九日法要にかかる費用は相続財産から支払うことができないので注意しましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
喪主の決め方
喪主を選ぶ際、最も影響力を持つものは故人が残した遺言です。
もし、遺言の中で喪主が指定されていれば、それに従って決めていくことができます。
しかし遺言に指定がなければ以下の基準で決定することになります。
一般的な慣習
昔は故人の後継者が喪主となっていましたが、現在はその意識が弱まってきていることから、故人の配偶者が喪主を務めることが一般的となっています。
ただし、地域の慣習によって異なる場合もあるため、迷ったら親戚などに相談するようにしましょう。
血縁関係
もしも配偶者が高齢であったり、病気であったりした場合、喪主を務めることは困難でしょう。
そのため配偶者を除く、血縁関係の深い順に(長男→長男→次男以降の直径男子→長女→亡くなった方の両親→亡くなった方の兄弟・姉妹)喪主が決定されます。
知人・友人など
故人に配偶者や血縁者がいなかった場合、故人の知人や友人が喪主となる場合もあります。
また、入所していた介護施設の代表者に喪主をお願いすることもあります。
この場合、「友人代表」「世話人代表」と呼ぶようになります。
複数人で行うことも
喪主を1人に決定できない場合もあるでしょう。
そのような時は無理に1人に決める必要はありません。
法律上では「祭祀継承者は1人」と定めていますが、喪主は複数でも問題ないといわれています。
遺言書などが残されていた場合

遺言書には喪主や葬儀費用の支払い方法などについて記載されていることも多いです。
故人が遺言書を残していた場合、相続財産の処分方法は故人の遺志が優先されます。
遺言書の内容を無視して遺族が相続財産を運用してはいけません。
遺族が勝手に遺言書を開封することは違法行為のため気を付けましょう。
基本的には家庭裁判所に提出し、内容の検認を請求することが必要となります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
香典を葬儀費用に充てることは可能?
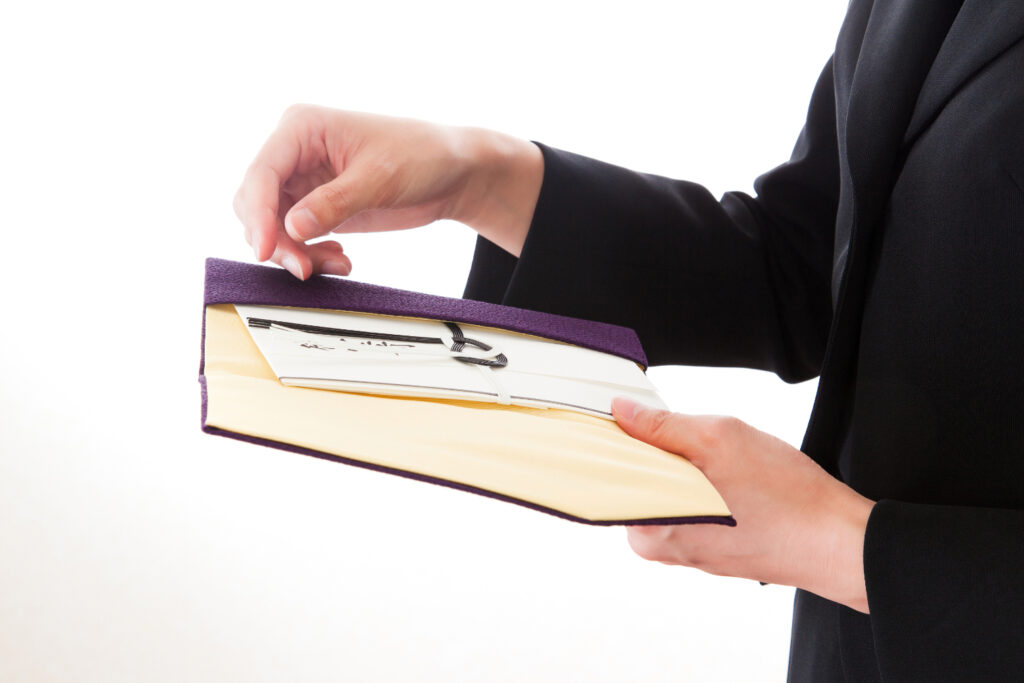
葬儀では、参列者から香典として金銭を受け取ります。
この香典は葬儀費用に充てることは可能なのでしょうか。
香典によって発生する相続人同士でのトラブルについても説明していきます。
香典とは
香典は喪主が通夜や告別式の参列者からいただくもので、故人の霊前に供える金品という意味があります。
葬儀費用の足しにしてくださいという意味もあります。
このことから香典は葬儀費用に充てても問題ありません。
香典は喪主のものになる
基本的には香典をもらうのは喪主です。
香典は亡くなった方を供養するためのものという考え方がありますが、一般的には喪主の負担を軽くし、葬儀費用に充ててもらうための贈り物とされているからです。
余剰分の香典も一般的には喪主のものになりますが、喪主とその他の相続人で分けるケースもあります。
この場合、喪主が多くもらうことが一般的ですが、中には他の相続人が不満を抱き、トラブルに繋がったケースあります。
トラブルを回避するためにも頂いた香典や香典返しは細かく記録しておくと良いでしょう。
葬儀費用の支払いについて
葬儀費用の支払いに関して、故人の遺志を尊重することは非常に重要です。
特に、遺言書、生前契約、そして遺言信託という三つの要素を確認することが、故人の最後の意向を反映させる上で欠かせません。
遺言書の確認
故人が残した遺言書は、相続財産の処分において故人の意志が最優先されるべきです。
遺言書が存在する場合、その内容に従って葬儀費用を支払うことが法的に要求されます。
遺言書の存在を確認し、その内容を家庭裁判所で検認する手続きを踏むことが必要ですが、無断での開封は法律違反になるため注意が必要です。
生前契約の検討
終活の一環として、故人が葬儀社と結んだ生前契約があるかどうかも確認することが重要です。
この契約には、葬儀の内容や費用の支払い方法が明記されており、故人の意向が具体的に反映されています。
故人が別の葬儀社と生前契約を結んでいた場合、その契約内容を無視して葬儀を行うことは、故人の遺志に反する行為となり得ます。
遺言信託の利用
遺言書が自宅になくても、故人が遺言信託サービスを利用している可能性があります。
これは、信託銀行や信託会社に遺言の作成、保管、執行を一任するもので、故人の死亡後に速やかに遺言の執行が行われます。
故人が遺言信託を利用していた場合、その事実を生前に家族に伝えていることが多く、故人の意向を明確にする手がかりとなります。
これら三つの要素を葬儀費用の支払い前に確認することで、故人の遺志に沿った形で葬儀を執り行うことができます。
故人の意向を尊重し、適切な手続きを踏むことが、故人への最後の敬意を表すことに繋がります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀費用について知っておくべきこと
葬儀を計画する際には、費用の面でどのような点を考慮すべきでしょうか?
一般的に、葬儀の平均費用は150万円から200万円とされていますが、実際の費用は葬儀の規模や地域、選択するサービスによって大きく異なります。
ここでは、葬儀費用を構成する主な要素について解説します。
葬儀自体の費用
葬儀の基本費用には、斎場の使用料、祭壇の設置費用、生花の装飾などが含まれます。
斎場の使用料は、選択する斎場の規模や立地によって異なります。
祭壇に関しても、選ぶランクやデザインによって価格が変わります。
格調高い白木祭壇から、故人の趣味を反映した個性的な祭壇まで、選択肢は多岐にわたります。
飲食費用
お通夜や法要後に提供される飲食にかかる費用も、葬儀費用の大きな部分を占めます。
通夜振る舞いや精進落としの内容は、予算内で調整可能ですが、参列者が足りなくならないように配慮が必要です。
葬儀社によって提供できる食事の内容や価格が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
寺院への費用
葬儀で僧侶に来てもらい、読経をしてもらう際にはお布施を用意します。
また、戒名を授けてもらう場合のお布施も必要で、その額は戒名のランクによって異なります。
お布施のほかに、僧侶の交通費(お車代)や食事代(御膳料)も考慮する必要があります。
葬儀費用を把握し、計画的に準備を進めることで、故人にふさわしい葬儀を実現しつつ、無理のない費用計画を立てることができます。
葬儀の規模や内容を決める際には、これらの費用の内訳を参考にして、適切な選択を行いましょう。
葬儀の費用について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
葬儀費用の負担について争う方法
葬儀費用の負担に関するトラブルはどのように解決されるのでしょうか?
これは複雑な問題であり、感情的な対立を招きやすいため、注意が必要です。
葬儀費用の負担者については一般に明確な法的規定がないため、争いが生じることがあります。
訴訟による解決
理論的には、葬儀費用の負担に関する争いは裁判所での訴訟を通じて解決されます。
葬儀費用は相続財産とは別に扱われ、その支払いを巡る問題は通常、遺産分割の範囲外と考えられるためです。
しかし、実際には訴訟に発展することは稀です。
調停による話し合い
実際のところ、葬儀費用の負担に関する問題は遺産分割調停の場で話し合われることが多いです。
調停では、中立的な立場の調停委員が関与し、双方の意見を聞きながら合意に至るよう仲介します。
葬儀費用の負担は遺産分割問題と密接に関連しているため、これらの問題を調停で一括して解決する方が実務上都合が良いとされます。
原則として相続財産には含まれないものの、相続人同士の合意があれば葬儀費用も遺産分割の対象に含めることが可能です。
多くの場合、葬儀費用以外にも相続に関する諸問題が存在するため、これらを調停で総合的に話し合い、解決を図ることが望ましいと考えられます。
葬儀費用の負担について争いが生じた場合、訴訟よりも調停を通じた話し合いによる解決が推奨されます。
これにより、双方が納得のいく解決を目指すことができるでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀費用を安くするには

葬儀費用の相場は150万~200万と説明しましたが、できるだけ安くしたいという方もいらっしゃるでしょう。
葬儀費用を安くするための方法、以下3つを紹介していきます。
公営の施設で行う
公営の葬儀を行う施設は、一般的には公営斎場と呼ばれます。
公営斎場は市区町村などの自治体が設置しており、税金などの公費で運営されています。
そのため価格が安く、火葬場が併設されていることが多いといった点で利便性が高いです。
葬儀を小規模にする
参加者が少ない場合は葬儀の規模を小規模にすることで金額を抑えることが可能です。
たとえば、葬儀会場を小さくしたり、会場費や葬儀運営スタッフ費などの費用を抑えたりすると費用を抑えることができます。
また通常だと2日間で執り行う葬儀ですが、通夜を行わずに1日で葬儀・告別式を行う一日葬でさらに費用を抑えることができます。
相見積もりをとる
複数の葬儀社から相見積もりを取ることも重要です。
葬儀にかかる費用は葬儀社によって様々です。
そのため、複数の会社から相見積もりを取ることで極力費用を抑えることにつながります。
また、葬儀社によっては見積書に乗っていない費用が後から追加されることもあります。
費用が無駄にかさむことがないよう、見積もりの内容についてもしっかりと目を通しておきましょう。
葬祭費補助金制度の利用
葬祭費補助金制度は、故人が加入していた保険種別に応じて異なる支援を受けられる仕組みです。
国民健康保険加入者の場合、自治体に申請することで葬祭費を受け取ることが可能で、金額は自治体によって異なりますが一般的には約5万円程度です。
一方、社会保険や共済保険加入者は「埋葬料」または「埋葬費」として、同様に上限5万円までの支援を受けることができます。
これにより、葬儀を執り行った人、主に喪主が支援金を受け取ることになります。
ただし、支給を受けるには申請後に1〜2ヶ月程度の時間が必要であり、葬儀費用の直接的な支払いには即時充当できない点に注意が必要です。
申請には故人の保険証、死亡証明書、葬儀の領収書などが必要で、故人の死亡から2年以内に行う必要があります。
保険によって細かな申請条件が異なるため、葬儀の際には保険内容を再確認し、必要な書類を準備することがスムーズな補助金受け取りに繋がります。
市民葬・区民葬の利用
市民葬や区民葬は、一部の市区町村で提供されている公的な葬儀サービスです。
これらのサービスを利用すると、民間の葬儀社が提供する葬儀と比べて費用を大幅に抑えることが可能になります。
たとえば、一般葬儀の相場が約200万円であるのに対し、市民葬や区民葬では50万円以内で葬儀を行うことができます。
ただし、プランの選択肢が限られていたり、簡素な葬儀になることが多いため、利用可能かつ望ましいかどうかは、地域や個人のニーズによって異なります。
現代では多様な葬儀プランを提供する民間の葬儀社も増えており、比較検討する価値があります。
市民葬や区民葬の利用方法については、市区町村役場での死亡届提出時に確認するのが一般的です。
福祉葬の利用
生活保護受給者の方が亡くなった際には、福祉葬(葬祭扶助制度)を利用することが可能です。
この制度は、経済的に困難な家庭に対して、自治体が葬儀費用の一部または全額を負担し、最低限度の葬儀を行うことを支援するものです。
対象となるのは直葬や小規模な火葬など、簡素な葬儀に限られます。
福祉葬を利用する際は、事前に生活保護を受けていた自治体の福祉事務所や、地域の民生委員に相談し、葬儀前に葬祭扶助の申請を行うことが重要です。
立替払いをしてしまうと、葬儀費用の支払い能力があると見なされ、扶助の対象外となる恐れがあるため、注意が必要です。
また、扶助額に自己資金を加えることはできず、申請は故人が居住していた自治体で行う必要があります。
申請には、故人の死亡診断書や申請者の収入を証明する書類(預金通帳や給与明細など)が必要です。
手続きの過程で必要書類を忘れることがないよう、また申請手順を正確に守ることで、スムーズな申請と承認を目指しましょう。
スポンサーリンク兄弟間での葬儀費用トラブルを防ぐ方法
葬儀費用の負担に関する兄弟間のトラブルは、事前の準備と明確なコミュニケーションによって避けることが可能です。
以下の4つの対策を講じることで、平和的な解決が期待できます。
遺言書による負担割合の明示
目的
生前に遺言書を用いて葬儀費用の負担割合を定めることで、将来的なトラブルを回避します。
注意点
- 遺言書に記載された葬儀費用の指示は法的な拘束力はありませんが、故人の意志として尊重されるべきです。
- 遺言書が葬儀前に開封されるとは限らないため、生前に家族間で意思疎通を図ることが重要です。
相続人同士の事前協議
目的
相続人間で葬儀の内容や費用について事前に協議し、理解し合うことで、トラブルを未然に防ぎます。
実践
故人が亡くなる前に、葬儀の形態や予算について話し合い、共通の理解を形成しておくことが望ましいです。
葬儀費用の公平な分担
目的
葬儀費用や香典の金額を相続人間で公開し、公平に分担することで、争いを避けます。
方法
香典の金額を含めた葬儀全体の費用を相続人が法定相続分に応じて負担し、必要に応じて領収証の開示を行います。
銀行預貯金からの葬儀費用払戻し
目的
2019年7月の民法改正により、故人の銀行口座から直接葬儀費用を引き出すことが可能となりました。
これにより、相続人間での合意形成の手間を省くことができます。
実施方法
引き出し可能な上限額は金融機関ごとに異なるため、具体的な手続きや必要書類については、事前に金融機関に確認が必要です。
これらの対策を事前に講じることで、兄弟間での葬儀費用に関するトラブルを効果的に防ぐことができ、故人を穏やかに送り出すことに集中できるでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
よくある質問
葬儀費用の支払いが困難な場合、どのような対処法がありますか?
葬儀費用の支払いが困難な場合、葬儀ローンを利用することが一つの解決策となります。
葬儀費用は通常、葬儀後に一定期間内に一括で支払う必要がありますが、すぐに必要な資金を用意できない場合があります。
このような状況で葬儀ローンを活用すると、10万円から500万円程度までの範囲で資金を借り入れ、分割払いで葬儀費用を支払うことが可能です。
これにより、すぐに手元に資金がない場合でも、適切な規模の葬儀を執り行うことができます。
自分の葬儀費用を自分で準備する方法はありますか?
自分の葬儀費用を事前に準備するには、葬儀保険への加入や葬儀の生前契約が有効な手段です。
葬儀保険の加入
葬儀保険に加入することで、保険料の支払いを通じて葬儀費用を事前に用意することが可能です。
保険料は比較的手頃であり、持病がある方や高齢者でも加入しやすいプランが多くあります。
ただし、解約時に返金がないなどのデメリットも考慮する必要があります。
特に「遺族に負担をかけたくない」と考えている高齢者に適しています。
葬儀の生前契約
生前契約を結ぶことで、自分が生きている間に葬儀の詳細を決定し、契約しておくことができます。
これにより、故人の意向に沿った葬儀を確実に行うことができる上、遺族の手間や心配を軽減することができます。
ただし、契約先の企業が倒産するリスクなど、注意すべき点もあります。
自分の葬儀について自分で決定したい方や、遺族の負担を軽減したい方におすすめです。
葬儀費用は遺産から支払うべきですか、それとも相続人全員で負担すべきですか?
葬儀費用の支払いに関しては、一般的には「喪主」が負担することが原則です。
過去には葬儀費用を相続財産から支出する裁判例もありましたが、葬儀費用が故人の生前の債務ではなく、故人の死後に喪主に発生する債務であるとする見解が主流となっています。
そのため、葬儀費用は基本的には相続財産ではなく、相続の対象外とされます。
しかしながら、相続人全員の合意があれば、遺産分割の過程で葬儀費用を相続財産から支出することも可能です。
実際に多くの場合、葬儀の費用は一旦喪主が支払った後、相続財産から精算する手続きを取ることが一般的です。
この方法では、相続人間での合意が必要となるため、葬儀前に相続人間で十分な話し合いを行うことが重要です。
スポンサーリンク葬儀費用についてのまとめ

今回は葬儀費用について説明してきました。
- 葬儀費用は150~200万で、一般的には喪主が負担する。
- 葬儀費用を喪主が払えない場合、施主や相続人で分担する、相続財産から支払うことも可能。
- 香典は喪主のものとなり、一般的に葬儀費用に充てられる。
- 葬儀費用を安くするには、公営斎場で行うことや小規模で葬儀を行う
いずれもトラブルにならないように相続人同士でしっかりと話合うことが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

鎌田 真紀子(かまた まきこ)
国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)
経歴
終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2025.06.17
互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説
お葬式

更新日:2023.12.18
福祉葬とは?対象条件、流れ、費用、香典の取り扱いや注意点まで詳しく解説