お葬式
火葬炉の仕組みや種類の違いは?火葬炉ごとの温度や火葬時間も解説
更新日:2024.03.19 公開日:2021.08.25

記事のポイントを先取り!
- 火葬炉は2種類ある
- 火葬にかかる時間は40~60分程度
- 葬儀場内に火葬場があることが多い
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
【みんなが選んだお葬式】
火葬炉は、ご遺体を丁寧に焼くために専門の技術を導入した設備として作られます。
火葬炉にも種類があることを知っていますか?
火葬炉の内部や仕組みについても、種類によって様々な違いがあります。
そこでこの記事では、以下のことを中心に紹介します。
- 火葬炉の種類
- 各火葬炉のメリットデメリット
- 火葬時間・火葬の温度
是非最後までご覧ください。

みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 火葬炉とは
- 火葬場の歴史
- 日本:世界における火葬文化のリーダー
- 火葬炉の大きさ
- 火葬炉の種類・仕組み
- 火葬炉の種類別メリットデメリット
- 火葬にかかる時間
- 火葬炉の温度
- 火葬炉の旧式と最新式を比較
- 炉前の意味
- 火葬で骨のみが残る理由
- 火葬の流れ
- 火葬中にすること
- 火葬の費用相場
- 火葬場にある施設
- 火葬の際に棺に入れてよいもの・入れてはいけないもの
- 子供の火葬に適した火葬炉について
- ペットの火葬に適した火葬炉について
- 火葬場では撮影が禁止
- 火葬炉の寿命は10~25年
- 火葬炉のある葬儀場に関するおすすめ記事
- 火葬炉のよくある質問
- 火葬炉まとめ
火葬炉とは

火葬炉とは人の遺体を骨上げができるよう、丁寧に焼却する火葬場の設備です。
大きく分けて二種類あり、メーカーごとに仕組みや構造が異なります。
火葬場にはその他に骨上げのための収骨室や、故人とお別れをするための告別室があります。
また、大きな火葬場になると軽く食事ができるスペースなどもあります。
火葬場の歴史
火葬場の起源と進化は、長い歴史の中でさまざまな文化や宗教的影響を受けてきました。
紀元700年頃、中国から帰国した高僧の遺命に従って行われた火葬が、日本での火葬の始まりとされています。
平安時代には、僧侶間で火葬が一般的になり、やがて武士や庶民の間にも広がりを見せました。
江戸時代には、一部で火葬が禁じられる時期もありましたが、人口密集地域では土地の限られた埋葬地に対処する手段として火葬が選ばれることが多くなりました。
明治時代には、公衆衛生の観点から火葬が奨励されるようになり、各地に公営の火葬場が設置されることになりました。
技術の進歩とともに、火葬の方法も自然の場や簡易な設備から、近代的な火葬場へと進化していきました。
今日では、公営と民営の火葬場があり、それぞれが地域のニーズに応じたサービスを提供しています。
火葬炉の技術も台車式やロストル式など多様化し、それぞれの方式には特徴があります。
このように、火葬場とその技術は時代と共に発展し、今日では多くの地域で衛生的で尊厳ある故人の送り方として認識されています。
火葬は、故人を偲び、尊重する文化の一環として、私たちの生活に深く根ざしているのです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
日本:世界における火葬文化のリーダー
日本では、遺体の埋葬方法として火葬が圧倒的に多く、その割合は約99%に達しています。
この高い火葬率は、日本が世界でも類を見ない火葬大国であることを示しています。
日本国内では火葬が一般的な埋葬方法として広く受け入れられているため、国内にいると遺体を火葬することが当たり前と感じられるかもしれません。
しかし、世界を見渡すと、火葬を行わない国や地域も多数存在しています。
日本が火葬を好む理由の一つに、仏教の影響が挙げられます。
仏教の教えに基づく火葬の習慣は、日本独自の文化や宗教観に根ざしています。
しかし、仏教国であっても、火葬の取り扱いは国によって異なります。
例えば、中国では火葬が70%程度とされ、依然として土葬の習慣が残る地域が多いことが知られています。
これは、仏教の解釈や宗教的習慣が地域によって異なるためです。
さらに、日本では国土が狭く、土地の有効活用が重要な課題となっていることも、火葬が広く行われる大きな理由の一つです。
土葬に比べて火葬は土地を節約でき、都市部を中心に限られた空間で多くの人々の埋葬を可能にします。
このように、日本の火葬文化は、宗教的背景と実用的な必要性が複雑に絡み合って形成されているのです。
スポンサーリンク火葬炉の大きさ

火葬炉は、故人をお送りするための最終段階で使用される設備であり、そのサイズは主に三つのカテゴリーに分けられます。
これらのカテゴリーは、故人の体格や特定のニーズに応じて選択され、火葬場によって設置されている火葬炉の種類は異なります。
以下に、それぞれの火葬炉の大きさと使用される棺の標準的なサイズを詳しく紹介します。
標準炉
- 用途:一般的な成人用
- 棺のサイズ:長さ195~220cm、幅55~65cm、高さ50~60cm
- 特徴:大多数の火葬場に設置されており、平均的な成人の体格を想定した設計です。
大型炉
- 用途:高身長や大柄な成人用
- 棺のサイズ:長さ220cm以上、幅60cm以上、高さ60~70cm
- 特徴:標準炉よりも大きなサイズで、特に大柄な人や高身長の人の火葬に適しています。
大型炉はすべての火葬場に設置されているわけではないため、使用を希望する場合は事前の確認が必要です。
小型炉
- 用途:子供、胎児、体の一部用
- 棺のサイズ:長さ195cm未満、幅50~60cm、高さ40~50cm
- 特徴:小型で低温での焼却が可能な設計となっており、子供や胎児の火葬に適しています。
この炉は、軟らかい骨が焼き切らずに残るように特別に設定されている点が大きな特徴です。
火葬炉の選択は、故人の体格や特定の要望に応じて行われます。
火葬を行う際には、故人に合った炉を選ぶことで、敬意を持って最後の送りを行うことができます。
事前に火葬場にどの種類の炉が設置されているかを確認し、適切な準備を行うことが重要です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬炉の種類・仕組み

日本国内で運用されている火葬炉は、大きく分けて2種類に分かれます。
それぞれの特徴について、詳しく解説します。
ロストル式
ロストルとは、オランダ語で「火格子」といいます。
現物は鋳物で作られた棺の置台のことを意味します。
ご遺体の入った棺は、火葬炉に入炉するとこのロストルの上に丁寧に設置されます。
この時、炉の下部と棺が直接設置しないように、ロストルが用いられます。
ロストルが生み出す隙間によって、炉内の火が四方八方から棺を包み込みます。
そのため、焼きムラが出ることなく、短い時間でご遺体を火葬することができます。
ロストル式の火葬炉の火葬場はかなり少なく、日本国内でも全体の10%程度です。
台車式
耐熱煉瓦等で作られた台車の上に棺を設置します。
台車ごと火葬炉に入炉して火葬する方法を台車式と呼びます。
日本国内の火葬炉は、台車式が主流で、国内の火葬場の約90%が台車式を採用しています。
台車式は、棺と台車が下部で密着しています。
そのため側面と上面から火力を与えてご遺体を火葬します。
台車式の構造上、遺骨の形をそのまま残しながら火葬することができます。
よって骨上げの時に主要な部分のお骨を見つけやすいです。
火葬炉の種類別メリットデメリット

火葬炉を種類別に考察して、メリットとデメリットをまとめてみました。
メリット
まず、それぞれの火葬炉のメリットから考察します。
ロストル式
- 火葬時間が短い
- 使用料が安い
四方から火力を集中するため、火葬時間が約40分程度で済みます。
そのため、火葬場で待たされる時間が少なくて済みます。
また、ロストル式は運営コストが安価な設備のため、遺族の金銭的負担が軽減されます。
台車式
- 遺体の形が崩れにくい
- 有害ガスや異臭が出にくい
遺体の形がその姿のまま残るので、骨上げの際に遺族が迷うことがありません。
また、台車式は「副燃 焼炉」と2種類の設備を使用します。
ご遺体を有害ガスが出ないように火葬することができます。
台車式の火葬炉であれば、周辺住民の理解も得やすいとされています。
デメリット
次にそれぞれの火葬炉ごとに存在するデメリットも確認します。
ロストル式
- 遺体の形が崩れやすい
- 火葬音が起きい
- 異臭が出る
燃焼中に遺骨が崩れやすく、骨上げの時に遺骨が乱雑になってしまうことがあります。
喉仏などの大事な部分のお骨を拾うときにすぐに見つけられない場合も出てしまいます。
また、急激に火力を上げて燃焼させることで、体液が染み出すことがあります。
その際に嫌なにおいが出ることも多いです。
台車式
- 火葬時間が長い
- 使用料が高い
ロストル式に比べて火葬時間が長いです。
そのため葬儀の時間が長くなってしまうことがあります。
また、設備が複雑で、運営コストもロストル式と比べるとかかります。
火葬場の使用料もロストル式に比べると高くなりがちです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬にかかる時間

ロストル式、台車式で一般的に火葬にかかる時間は、次の時間とされています。
- ロストル式 約40分
- 台車式 約60分
これは、身長170㎝程度の一般的な体形のご遺体(成人男性)を火葬した時の想定です。
実際、身長や体重が大きければ大きいほど、火葬時間に影響を与えます。
例えば、肥満体系の男性の場合、内臓脂肪が多いために火力調節が難しいです。
内臓脂肪に着火して火力が強まってしまいます。
最悪の場合遺骨が燃え尽きてしまう場合があります。
この場合、火葬場の職員は、火力の調節を丁寧に行うため、目視しながら火葬を行います。
この調節にかかる時間が影響して、通常の火葬時間にプラス30分程度の時間がかかることもあります。
子どもや乳幼児の火葬の場合、脂肪の多い大人よりもさらに火葬時間がかかります。
子どもの骨が小さいため、火力が強いと骨まですべて燃えてしまう可能性があるからです。
火葬場の職員は目視しながら時間をかけて火葬を行います。
火葬炉の温度
故人のご遺体を焼き、ご遺骨にするためには火葬炉が必要です。
火葬炉は、その温度を800度以上にするよう、国によって決められています。
これは800度以上にすることで、ダイオキシンなどの有害物質の発生を抑えるためです。
低温でご遺体を焼くと、ダイオキシンなどの有害物質が発生し、大気汚染の原因となります。
ただし、火葬炉の温度が高すぎるとご遺骨まで燃えてしまい、灰になってしまう可能性があります。
反対に、火葬炉の温度が低すぎても、ご遺骨が大きい状態で残ってしまい、骨壷に入り切らないということになりかねません。
そのため、火葬炉の温度は800度から1200度の間に設定されています。
旧式の火葬炉の温度は800〜950度でしたが、新型では900〜1,200度と温度が向上しました。
これにより、火葬にかかる時間を短縮することを可能としました。
旧式では2〜3時間程度は火葬にかかっていましたが、現在では新型が普及し、1時間10分程度で終わるようになりました。
技術の進化と共に、火葬にかかる時間も短縮されているのです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬炉の旧式と最新式を比較
| 火葬時間 | 燃料 | 煙突 | 温度 | |
| 旧式 | 2~3時間程 | 石炭、薪、重油 | 有 | 800~950度 |
| 最新式 | 1時間程 | 都市ガス、液化石油 | 無 | 900~1200度 |
最新式の火葬炉の特徴
最新式の火葬炉の特徴は、無煙、無臭、無塵、低騒音を追求し周辺環境に配慮した、無公害の施設への取り組みがされていることです。
また、コンピューターによる温度調節を行うことができるようになったところも、火葬技師が必要だった旧式の火葬炉とは違うところです。
最新式の火葬炉を使う火葬場には煙突が無い
火葬炉がある火葬場は、亡くなった方とお別れをする場所ですが、一方で立ち上る黒煙や臭いの影響により、嫌悪されていた場所でもあります。
最新式の火葬炉では、嫌悪の対象であった、煙突がないものが増えています。
最新式の火葬炉は高温で火葬を行うことが可能なので、旧式と違い燃焼を促す煙突が不要になったからです。
また、近年ではダイオキシンが発生しにくいとされる、800度以上で火葬するようになっています。
再燃焼炉の使用や、コンピューターによる排ガスのコントロールによって、最新式の火葬炉では煙突が不要になっています。
炉前の意味

火葬場では、火葬炉の扉の前のことを炉前と呼びます。
炉前は、遺族にとって印象に残る場所となります。
そして炉前では、故人との最後のお別れの場として、さまざまな儀式が行われます。
納め式
故人の顔を最後に見ることのできる場所です。
火葬炉の扉を閉めることで、旅立ったことを実感する場所でもあるからです。
そのため僧侶による読経、遺族によるお別れや焼香などが行われるのが一般的です。
地域によっては、これらを納め式と呼びます。
最近増加傾向の直葬で火葬する場合、炉前のお別れを火葬式と呼ぶことがあります。
お布施の相場
僧侶を招いて読経を依頼すれば、それに対してお布施を支払うことになります。
相場は3万円から10万円程度です。
しかし菩提寺として付き合いがあるお寺の場合、多少金額を抑えてもらえるようです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬で骨のみが残る理由
火葬によって遺骨のみが残る理由は、専門的な技術と炉の精密な温度管理によるものです。
ここでは、火葬プロセスにおける骨だけが残る背景を、専門家の役割と現代技術の観点から詳しく解説します。
専門家による温度と時間の調整
火葬技師の役割
火葬技師、または火夫と呼ばれるスタッフは、火葬炉の温度や火葬の時間を細かく調節します。
これらの専門家は、火葬プロセスに必要な訓練と知識を有しており、故人の体格や年齢、病歴に応じた適切な火葬方法を選択します。
個別の調整が必要な理由
故人の骨密度や体脂肪の量、副葬品の存在などによって、火葬の条件を個別に調整する必要があります。
高齢者や骨粗鬆症の影響を受けた故人の場合、骨が完全に灰になりやすいため、特に注意深い管理が求められます。
コンピューターによる温度管理
技術の進化
近年の火葬場では、コンピューターを利用して炉内の温度を制御するシステムが導入されています。
これにより、火葬技師が直接温度や時間を管理する従来の方法に代わり、より一貫した火葬プロセスが可能となりました。
一定品質の火葬を実現
コンピューター制御により、故人の特性に応じた最適な火葬条件を設定し、一貫した品質での火葬を実現しています。
これにより、遺骨のみを残すという火葬の目的を、より精度高く達成することが可能になっています。
火葬で骨だけが残るのは、これらの専門家による細やかな管理と、最新の技術による温度制御の結果です。
火葬技師が炉内の様子を観察し、適切な火葬が行われるよう調整すること、そしてコンピューターによる精密な温度管理が、遺骨を適切に残すための鍵となります。
スポンサーリンク火葬の流れ
火葬におけるプロセスは、遺族と故人を送るための大切な儀式の連続です。
参列者は、故人の最後の旅立ちを尊重し、その過程を慎重に進めます。
以下に火葬の基本的な流れと、特に注意を要する骨上げの儀式について詳しく説明します。
火葬の基本的な流れ
出棺(しゅっきゅう)
葬儀が行われた場所から、故人を納めた棺を火葬場へと運びます。
この時、故人を最後の旅立ちに送る重要な一歩となります。
読経と焼香
火葬場にて、僧侶が読経を行い、参列者は順に焼香します。
この儀式は、故人への最終的なお別れの意味を持ち、故人の冥福を祈ります。
火葬
故人を納めた棺は火葬炉へと運ばれ、火葬が行われます。
火葬の間、遺族や参列者は休憩室で待機し、故人の平安を心から祈ります。
骨上げ(こつあげ)
火葬が終わった後、特別に用意された箸を使用して遺骨を骨壺に納めます。
この儀式は、故人への最後の奉仕であり、故人の魂を尊重する行為です。
骨上げの儀式
骨上げの方法
遺骨は2人1組で箸を使って持ち上げ、骨壺へ納めます。通常は足の骨から始め、順に上半身へと進みます。
特に、喪主が喉仏の骨を納めることには深い意味があります。
地域差と方法
骨上げには地域や宗派によって異なる方法があります。
一部の地域では、1人で骨を持ち上げる方法や、特定の遺骨のみを選んで納める習慣があります。
実施にあたっては、その地域の慣習や宗派の指示に従うことが大切です。
火葬と骨上げのプロセスは、故人を敬うための厳粛な儀式です。
この一連の流れを理解し、参加することで、遺族や参列者は故人との最後の瞬間を尊重し、心の中で故人を送り出すことができます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬中にすること

火葬中、火葬炉は自動制御で火力調整や風力調整が行われます。
火葬場の職員が炉内の様子を確認します。
遺骨が残るように焼きムラを抑えながら火葬していきます。
その間、遺族は待合室で骨上げが始まるのを待つことになります。
火葬場によっては、遺族単位で使用できる個別の待合室が使用できます。
しかし共用の待合スペースで他の遺族と一緒に骨上げを待つ場合もあります。
また、火葬場には自動販売機や売店などの設備が設けられていることもあります。
小腹を満たしたりコーヒーを飲む程度のことができる火葬場もあります。
なお、火葬中には宗教的な儀式も行われません。
疲れている人は仮眠を取ってもよいですし、食事を摂ることも問題ありません。
火葬の費用相場
ここからは火葬を行う際の費用相場をご紹介します。
火葬にかかる費用は、行う火葬場の種類や地域によって変わってきます。
以下で紹介する費用相場を参考にして、最適な火葬場を選びましょう。
民営か公営かで異なる
火葬にかかる費用は、民営か公営かによって異なります。
基本的に公営の方が民営よりも費用が安いケースが多いと考えられます。
公営の相場は、数千円程度から5万円程度です。
ただし、公営の場合はその火葬場がある場所の市民でなければ、市外料金がかかります。
市外料金は5万円〜10万円が相場とされており、市民よりも1.5倍〜2倍ほど高額になります。
これは公営の火葬場はその自治体内の税金で運営していることが関係しています。
その自治体に属していない人は税金を負担していないため、火葬場を利用する際その自治体に居住する人より費用が高額になるのです。
何らかの特別な事情がない限り、居住する地域の火葬場を使いましょう。
民営の相場は5万円〜15万円程度と金額に幅がありますが、大体において公営に比べて高額な費用となります。
地域によって異なる
火葬の費用相場は上述したように公営か民営かによっても左右されますが、その他に火葬する地域によっても相場が変動します。
地域によっては市民が無料で火葬を行える公営の施設が存在する場合もありますが、市民でも利用料が必要となるケースもあります。
これには上述したように、公営の火葬場がその自治体の税金によって運営されていることが関係しています。
自治体の財政状況や方針によって、相場に差が生じているのです。
そのため、あらかじめ自分の地域の相場や、公営の施設の利用料がどのくらいかを調べておく必要があります。
その地域の火葬の費用相場を調べる際は、インターネットの検索エンジンでの検索が便利です。
例えば「〇〇(地域名) 火葬場 費用」などといった形で検索すれば、その地域の費用相場が調べやすいでしょう。
予算を抑えたい方は事前のリサーチを怠らず、どの火葬場に依頼するかを考えておきましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬場にある施設
ここからは火葬場にある施設についてご紹介します。
実際に火葬を行う場合には、火葬前や火葬の待ち時間などで施設を利用することがあります。
以下で各施設がどういった場所であるか、どのような時に使うのかを知っておきましょう。
告別室
告別室は故人との最後のお別れを行う部屋です。
火葬を行う前の故人の姿を最後に見られる場所で、棺の小窓を開けて故人の顔を見ることもできます。
葬儀や告別式を終えて故人とお別れする場で、遺族が最後のお別れのために気持ちの整理をする場所でもあります。
火葬の順番などの関係から15分程度などと使用できる時間が決められています。
控え室
控室は故人との最後の別れを済ませてから火葬が終わるまでの間、遺族や僧侶が待つための場所です。
遺族はお菓子やお茶などを用意し、参列者が火葬場に同行している場合は待っている間は接待を行います。
何もせずに過ごすと時間が長く感じ、気持ちも落ち着かなかったり、悲しくなったりする可能性があります。
そのため、遺族で故人の思い出話をして過ごすのが一般的です。
気持ちを落ち着けるためにも、遺族でお話をして待ちましょう。
炉前室(前室)
炉前室は、火葬炉の前にある部屋です。
遺族が少人数である場合は、告別室の代わりに炉前室で故人との最後のお別れをします。
ここでは最後に故人の冥福を祈って焼香をしたり、僧侶が読経を行ったりします。
ただし、火葬場によっては時間の都合から、炉前室での読経が行えないケースもあります。
事前に故人との最後のお別れでどれだけ時間が取れるか、炉前室で読経を行うことは可能かなど確認しておくと良いでしょう。
また、地域によっては僧侶が火葬場へ付いていくのが一般的ではないことがあり、その場合は炉前での読経はしません。
炉前室は故人との本当の別れの場所です。
後から後悔がないように、しっかりと故人とお別れをしましょう。
火葬の際に棺に入れてよいもの・入れてはいけないもの
火葬に際して棺に添える副葬品は、故人への最後の敬意として重要な役割を果たします。
副葬品を選ぶ際には、故人との想い出を形にすると同時に、火葬の過程における安全性や適切性も考慮する必要があります。
ここでは、火葬時に棺に入れることが推奨される品物と避けるべき品物について解説します。
棺に入れてよい副葬品
棺の中に入れることができる副葬品は、燃焼しやすく、かつ有害物質を放出しないものが適しています。
以下に、その代表例を挙げます。
- 手紙や絵:故人への想いを綴った手紙や絵は、感情的な価値が高く推奨されます。
- お菓子:故人が生前好んでいたお菓子は、親しい人々の想い出とともに棺に入れられます。
- 生花:お花は自然に帰るため、火葬時に有害な物質を発生させる心配がありません。
- 写真:故人や愛するペットの写真は、故人の思い出として棺に添えることができます。
- 愛用の衣服:故人が特に気に入っていた衣類も、身に着けることがなくなった故人との思い出を共有するために適しています。
棺に入れてはいけないもの
一方で、火葬中に有害なガスを発生させたり、火葬炉に損傷を与えたりする可能性があるため、以下のような物品は避けるべきです。
- 金属製品(腕時計、指輪、入れ歯など):火葬時に溶け出し、火葬炉を損傷する原因となります。
- プラスチック製品(メガネ、ビニール製品など):燃焼時に有害なガスを発生させる可能性があります。
- 缶ジュースや水分の多い果物:内容物が熱で膨張し、事故の原因になる恐れがあります。
- 分厚い本:燃焼しにくく、火葬の過程を妨げる場合があります。
火葬時に棺に入れる副葬品を選ぶ際には、これらのガイドラインを参考にして、故人への想いを尊重しながらも、安全かつ適切な選択を心がけることが大切です。
故人との最後のお別れの時に、遺族の想いを込めた副葬品が、故人の旅立ちをより意味深いものにします。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
子供の火葬に適した火葬炉について
子供の火葬では、大きさに適した小型炉、または胎児専用の火葬炉を利用する必要があります。
赤ちゃんの骨はとても小さく、一般的な火葬炉で火葬を行った場合には遺骨が残らないことが多いためです。
もちろん、必ず遺骨が残るとは言い切れませんが、その方が確率が一気に上がります。
ただし、胎児用の火葬炉は通常のものよりも利用料金が高額になることが多いためご注意ください。
スポンサーリンクペットの火葬に適した火葬炉について
ペットの火葬炉となると、もちろん人間用の火葬炉とは全く異なります。ペットと一括りにしても大きさが種類によって大きく異なるため、火葬炉も細かく分けると様々な種類が存在します。
今回は「室内型」と「室外型」の大きく2種類に絞ってご説明します。
屋内型火葬炉
こちらは「室内型」「室外型」に分ける最大の特徴である火葬炉の入口がお別れをする部屋に設置されています。
しっかりとお別れをした後、飼い主さんの前で火葬炉にペットを入れます。
メリットとしては、できるだけ長く、最後までペットと一緒にいることのできる点が挙げられます。
拾骨は火葬炉から出てきたそのままの状態で収骨する場合やトレイに移してから収骨する場合など様々です。
屋外型火葬炉
屋外型のタイプは火葬炉の入口がないため、基本的には飼い主さんが立ち会えるのはお別れのお時間までです。
その後は、霊園スタッフがペットを運び出し、火葬に入ることになります。
拾骨は霊園スタッフがお骨をトレイに移し、お別れをしたお部屋での拾骨になることが多いです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬場では撮影が禁止

火葬場では、写真や動画の撮影が禁止されている場合が多いです。
これは個人情報の漏洩を防ぐことを目的にしています。
最近のご時世、故人が亡くなったことを公言したくない事情もあります。
写真や動画の撮影で遺族も含めて個人情報が漏洩するきっかけを作らないためです。
また、火葬場職員の個人情報を保護する意味もあります。
火葬場という場所は、まだまだ忌避感を持って受け止められています。
そこで働く職員への職業差別を防ぐための予防的措置でもあります。
火葬炉の寿命は10~25年
火葬炉は高熱で稼働する機械であることから、使い続けていればいずれ改修しなくてはなりません。
この改修までの期間は火葬場や使用頻度によっても大きくことなりますが、一般的な寿命となる期間はあります。
上越市議会定例会の資料によると、『火葬炉設備については、参考文献では各機器・部品により耐用年数が異なるが10~25年とされる』と言われています。
そのため、火葬炉の平均的な寿命は10~25年と言えます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬炉のある葬儀場に関するおすすめ記事
火葬炉を備えている火葬場の中には、葬儀場としての設備を揃えているところも多いです。
以下の記事から火葬炉のある葬儀場を参照できるので、ぜひご活用ください。
火葬炉のよくある質問
火葬炉と焼却炉の違いは何ですか?
火葬炉とは遺体だけを焼却する施設で、焼却炉は廃棄物を処理する施設です。
火葬炉では、1体ずつ遺体の焼却を行い、遺骨だけをきれいに残すことができます。
火葬して骨だけ残るのは何故ですか?
火葬炉の温度を骨が残るように調節しているからです。
旧式の火葬炉では火葬技師の技術で調節していましたが、最新式の火葬炉ではコンピューターによる温度調節が可能になっています。
火葬場が混んでいるのは何故ですか?
1日の火葬の上限を超えて行われていることが多いことと、火葬の時間をお昼にしたい方が多いため混んでいます。
そのため、朝や夕方ですと予約に空きがあることが多いです。
火葬中に遺体が動くことは本当ですか?
火葬中に遺体がある程度の動きを見せることは実際にありますが、これは遺体が「蘇生」することではありません。
人体は大部分が水分で構成されており、火葬の過程で高温にさらされると、この水分が蒸発します。
水分の蒸発や熱による筋肉の収縮などが原因で、遺体が動くように見える現象が発生することがあります。
この動きは自然な化学反応と物理的変化によるもので、遺体が生き返るということではないため、誤解を恐れずに理解することが重要です。
ペット火葬と人間の火葬では温度に違いはありますか?
ペット火葬における温度範囲は、一般的に800度から1200度となっており、これは人間の火葬で用いられる温度範囲とほとんど変わりません。
ただし、ペットの種類や大きさによっては、火葬の過程で最適な温度に調整する必要があります。
例えば、小型犬や猫などの小さなペットでは、比較的低い温度設定で火葬が行われる場合があります
一方で、大型犬などの体重が重いペットの場合は、より高温での火葬が必要になることもあります。
このように、ペットの火葬ではそのサイズに応じて温度を適切に調節することが重要です。
火葬中の様子を見ることはできますか?
一般的に、火葬中の様子を直接見ることができるのは火葬技師だけです。
火葬のプロセスは高度に管理された環境下で行われ、火葬技師が炉内の様子を確認しながら、遺体が適切に焼却されるように監視しています。
このため、遺族や一般の参列者が火葬炉内部を直接見ることは通常はありません。
火葬技師は遺体が適切に処理され、尊厳を持って扱われるよう、温度や時間の調整を行う専門のプロフェッショナルです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬炉まとめ

火葬炉の種類が違うだけで、火葬時間の際や悪臭の有無も異なります。
そして火葬場の利用者にさまざまな影響が出ることがわかりました。
- 火葬炉にはロストル式と台車式がある
- ロストル式のメリットは火葬時間が短く、費用が安いことで、台車式のメリットは遺体の形が綺麗に残りやすく、衛生的によいこと
- ロストル式のデメリットは遺体の形が崩れやすく、異臭が出やすいことで、台車式のデメリットは火葬時間が長く、費用が高いこと
- ロストル式の火葬時間は40分程度、台車式は60分程度
ここまで火葬炉の構造や、構造別のメリット・デメリットについてお伝えしてきました。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
お葬式の関連記事
火葬

更新日:2022.05.11
火葬場で挨拶は必要?喪主の挨拶の注意点と文例を解説
お葬式

更新日:2022.11.19
近所の人の出棺の見送りへは行くべき?服装の注意点は?
お葬式

更新日:2024.01.24
火葬式(直葬)時の服装は?他葬儀との違いや持ち物のマナーも解説
お葬式
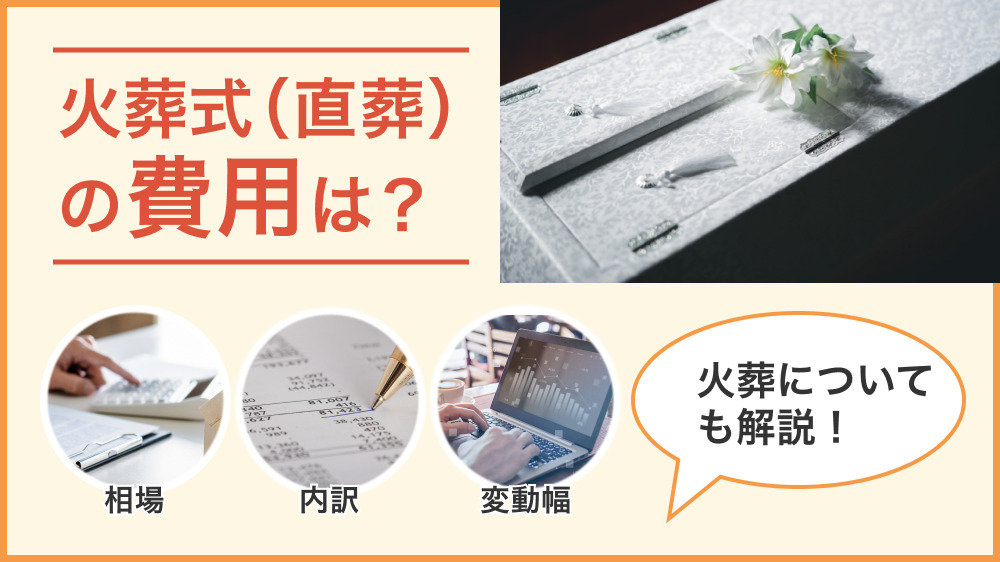
更新日:2025.06.29
葬式なしの火葬費用の相場は?直葬・火葬式の費用を抑える方法についても併せて解説






