お葬式
葬儀費用の支払いはどうすればいい?葬儀費用を分割にする場合は?
更新日:2024.04.10 公開日:2021.09.10

葬儀を執り行うには相応の費用がかかります。
しかし、葬儀の支払方法を把握していない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、
- 葬儀費用の支払いの方法
- 葬儀費用を支払うタイミング
- 支払えない時の対処方法
を中心に解説していきます。
生前に支払う方法についても解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 葬儀費用の支払い方法
- 葬儀費用の支払いの際に注意すること
- 葬儀費用の支払いのタイミング
- 葬儀費用は誰が払う?
- 葬儀費用の相場と内訳
- 葬儀費用の支払いができない場合は補助金を申請
- 葬儀費用を故人の口座から支払うことはできる?
- 葬儀費用の見積もりを取ることが大事
- 葬儀費用の支払い時の注意点
- 葬儀費用の支払いについてのよくある質問
- 葬儀費用の支払いまとめ
葬儀費用の支払い方法

葬儀費用の支払い方法は大きく分けて4つあります。
現金振込
もっとも一般的な方法が現金振込です。
コンビニエンスストアでも振り込むことができます。
一括で支払える場合は現金払いが一番便利です。
借金を背負わないので、精神的な圧迫もありません。
クレジットカード払い
クレジットカード払いも受け付けている葬儀社は多いです。
支払い方法には、一括、分割、ボーナス払い、リボ払いがあります。
その中から、自分に適した選択肢を選ぶことができます。
しかし、分割やリボ払いの場合、利息がかかることもあります。
そのため最終的には現金払いよりも多くの額を支払う事になるかもしれません。
また利用限度額にも注意が必要です。
ローン支払い
葬儀の費用をまとめて準備するのが難しい場合、葬儀社と信販会社が提携している「葬儀ローン」の利用が一つの解決策です。
金融機関が提供する葬儀ローンもあります。
一般的には、返済は「1回~36回」の分割で選べます。
分割払いでは利息が発生するため、返済計画の立案が重要です。
ローン申込みには審査がありますが、即日審査が可能な場合も多いので、手続きは迅速です。
詳細については葬儀社に相談しましょう。
葬儀ローンのメリット
葬儀費用は高額になることが多く、一括払いが難しい場合もあります。
ローンを利用すれば、一時的に資金を用立てることができます。
分割払いにより、収入状況に応じた無理のない支払いが可能になります。
葬儀社提供のローンであれば、手続きもスムーズです。
葬儀の準備に追われる中で、資金の手配が容易になります。
葬儀ローンのデメリット
金融商品の利用では利息が発生し、総支払額が借入額より増えることがあります。
信販会社や銀行、クレジットカード会社によって利息は異なります。
また、審査を通過しなければ利用できません。
審査では申込者の属性や勤続年数、年収などが考慮されます。
融資までの時間も確認が必要です。
僧侶への御布施や戒名料などは現金で支払う必要があり、ローンに組み込むことはできません。
現金の手渡し
現金による支払いは、葬儀の費用を支払う際に最も一般的な方法です。
葬儀社への支払いは、直接訪問して手渡しするか、銀行振り込みを利用します。
しかし、葬儀以外にも法事や墓地の費用、病院への支払い、遺品整理など、様々な出費が発生することがあります。
そのため、将来の計画も考慮に入れて支払い方法を選ぶことが重要です。
現金手渡しの場合、特別な封筒に入れる必要はなく、簡単に手続きが行えるので安心してください。
コンビニエンスストアで支払い
最近では、コンビニエンスストアで葬儀費用の支払いができる葬儀社が増えています。
全ての葬儀社がこの方法を採用しているわけではありませんが、特に大規模でWebサービスに対応している葬儀社では、コンビニでの支払いが可能なことが多いです。
支払い用紙が到着してから支払い期限まで、通常7日から10日程度の猶予があり、現金を準備する余裕が生まれます。
コンビニでの支払いには複数のメリットがあります。
一つは、24時間いつでも自分の都合に合わせて支払いができる点です。
銀行での支払いでは窓口の営業時間内に行く必要がありますが、コンビニなら時間を気にせずに支払いが可能です。
ただし、デメリットとしては、一度に大きな金額を用意しなければならないことが挙げられます。
コンビニでの支払いは、特に急な葬儀の場合や時間的な余裕がない場合に便利です。
しかし、この支払い方法を採用しているかどうかは、事前に葬儀社に確認することが重要です。
葬儀の準備は多くの面で大変ですが、支払い方法の選択肢が増えることで、少しでもその負担を軽減できればと思います。
葬儀費用の支払いの際に注意すること
葬儀費用の支払い方法は、多くの人にとって一度きりの経験であり、知識が乏しいために失敗するケースが少なくありません。
主な支払い方法は現金、クレジットカード、葬儀ローンの3つです。
現金は一般的ですが、大量の現金を用意するリスクがあります。
クレジットカードは便利ですが、分割払いにすると利息が発生します。
葬儀ローンは審査が必要で、利息もかかります。
また、支払いタイミングは葬儀後の1週間から10日が一般的ですが、葬儀社によっては前金が必要な場合もあります。
これらのポイントを把握して、事前にしっかりと計画を立てましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀費用の支払いのタイミング

支払いが必要な葬儀費用には、葬儀社に支払う費用と火葬場に支払う費用、そして宗教者に渡すお布施などの費用があります。
それぞれに支払うタイミングが異なるため、以下で説明します。
葬儀社への支払い
葬儀社への支払いは、葬儀後1週間から10日以内を期限に設定している葬儀社が大半です。
しかし、葬儀社によっては支払期限が3日以内であったり、1ヵ月以内であったりする場合もあるため、見積りの際に確認しておきましょう。
葬儀費用の支払い方法には、現金の手渡しや銀行振込、クレジットカードでの支払い、葬儀ローンなどさまざまですが、故人の生命保険金で支払う場合は注意が必要です。
生命保険金の支払いは、基本的に手続きの書類が保険会社に届いた日の翌営業日から5営業日以内に設定されています。
営業日で計算されるため、休日を間に挟んでいると保険金の受取りに1週間ほどかかる可能性もあります。
万が一、葬儀社への支払い期日に間に合わない場合は、葬儀社に連絡して支払い予定日を伝えるようにしましょう。
火葬場への支払い
民間の葬儀社は葬儀式場のみを所有している場合が多く、火葬は公営の火葬場へ移動して行われます。そのため、火葬の費用は葬儀社ではなく火葬場へ直接支払う必要があります。
火葬場への支払いは、火葬当日に現金での手渡しで支払う方法が大半のため、事前に火葬場への費用を確認して準備しておくようにしましょう。
宗教者へのお布施などの費用
読経や戒名へのお礼を包んだお布施の費用や、葬儀場までの交通費を包んだお車代は葬儀社ではなく、宗教者へ直接手渡します。
お布施などを渡すタイミングに明確な規定はありませんが、基本的には宗教者が葬儀場に到着して挨拶をする際に渡すと良いでしょう。
また、葬儀当日は喪主はやることが多く余裕がないため、葬儀社のスタッフに相談してお布施などを渡すタイミングを作ってもらうことも大切です。
葬儀費用の支払いは生前に済ませることもできる
近年では、存命の内に葬儀を予約される方も増えてきました。
亡くなった後、残された親族の負担を減らしたいという思いからです。
生前予約なら葬儀費用も生前に支払うことができます。
そのため遺族に経済的な負担がかかりません。
生前予約の場合でも、支払いを事後支払いにすることはできます。
葬儀費用は誰が払う?
葬儀費用は誰が払うのか、という疑問は多くの人が抱く一つです。
ここでは喪主が葬儀費用を払う場合と喪主以外が払う場合についてご紹介します。
葬儀費用を喪主が払う場合とその理由
葬儀費用は誰が払うのか、一般的には喪主が担当します。
喪主は故人と最も近い関係にある人物であり、葬儀の全体的な手配と費用の管理を担当します。
通常、葬儀費用は葬儀が終了してから10日以内に支払われることが多いです。
支払い方法としては、現金、クレジットカード、または葬儀ローンが選べます。
また前金が必要な場合もあるため、その点も念入りにチェックが必要です。
親の葬儀費用を喪主・施主以外が支払う場合とその理由
親の葬儀で喪主や施主以外が費用を支払う場合もあります。
これは、喪主が経済的に困難な状況にある場合や、複数の兄弟姉妹が費用を分担する場合などが考えられます。
親の葬儀費用を喪主以外が支払う場合、その費用は後で相続財産から差し引かれる可能性があります。そのため、事前に家族間でしっかりと話し合い、合意を得ることが重要です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀費用の相場と内訳
葬儀費用に関する情報は、多くの人にとって重要な知識です。
喪主が主に負担することが多いですが、費用の内訳は多岐にわたります。
一般的な相場は、葬儀一式で約140万円、飲食接待費が約41万円、寺院費用が約55万円とされています。
葬儀費用を安く抑えるポイント
葬儀の規模を小さくする: 葬儀の規模が大きいほど費用も増加します。
不必要なサービスを省くことで、費用を抑えることが可能です。
- 生前契約・葬儀保険の活用する。
葬儀社との生前契約や葬儀保険に加入することで、費用を大幅に削減できます。 - 葬祭費の補助・扶助制度を利用する。
保険や組合の補助が受けられる場合もあります。 - 生活保護受給者は葬祭扶助制度が利用可能です。
行政が一部の費用を負担する制度があります。
葬儀費用の準備の仕方
葬儀費用の準備は、遺産や保険金、さらには特定の補助・扶助制度を活用することで、スムーズに行えます。
遺言書や遺言代理信託がある場合は、それに従って手続きを進めることが重要です。
葬儀全体にかかる費用はどれくらい?
葬儀全体にかかる費用は、一般的には200万円~300万円程度です。
しかし、これは一例であり、多くの要因で変動する可能性があります。
相続税の控除対象となる費用もありますので、領収書や明細書はしっかりと保管しておくことが推奨されます。
葬儀の費用について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
葬儀費用の支払いができない場合は補助金を申請

葬儀は急に執り行われることが多いです。
費用が足りないこともあるかと思います。
これから紹介する補助金制度については葬儀費用を全て賄えるわけわないので注意してください。
葬祭費補助金制度を利用する方法もあります。
以下でケース別に詳しく解説します。
公的健康保険に加入している場合
故人が公的健康保険やそれ以外の健康保険に加入していた場合、以下の制度が利用できます。
- 国民健康保険
- 国民健康保険組合
- 後期高齢者医療制度
公的保険の制度は地方自治体によって異なります。
埋葬費は基本的に3万~7万円程度が支給されます。
葬儀終了後、自治体へ申請することで受給することができます。
社会保険に加入している場合
故人が勤務先などで社会保険に加入していた場合は以下の制度を利用できます。
- 所轄の社会保険事務所
- 勤務先の健康保険組合
この場合、埋葬料として5万円が支給されます。
埋葬料は蔡葬費と異なり、埋葬するまでにかかった費用が対象となります。
具体的には霊柩車や火葬費用・僧侶への謝礼があげられます。
申請期限は、故人が亡くなった翌日から2年間です。
生活保護受給者の場合
故人あるいは申請者が生活保護受給者の場合は蔡祭扶助が支給されます。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 故人が生活保護受給者で、遺族以外の第三者が葬祭を執り行う場合
- 遺族や喪主が生活保護受給者である場合
この場合の申請先は、故人が居住していた市町村になります。
また、蔡祭前の事前申請が必要です。
補助金制度について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀費用を故人の口座から支払うことはできる?

故人の銀行口座から葬儀費用を払おうとした場合、かなり手間がかかります。
なぜなら、故人が亡くなった時点で凍結されるのではなく、死亡届が役所に提出されたのちに凍結されるためです。
故人の凍結された口座から、お金を引き出すには、相続人全員の同意が必要になります。
また、戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書の提出書類なども必要です。
口座の凍結や故人の資産について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
葬儀費用の見積もりを取ることが大事

葬儀費用の支払いは、見積りが肝要です。
葬儀に関連して掛かる費用の内訳は以下の3つがあげられます。
- 基本葬儀料
- オプション料
- 葬儀社以外への費用
基本葬儀料とは、祭壇、葬儀の運営、人件費などを指します。
オプション料とはお棺、礼状、礼品など地域によって変動する費用です。
葬儀社以外への費用は、宗教者への謝礼、火葬料など葬儀社を介さずに直接支払う費用です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀費用の支払い時の注意点
急な葬儀の際、喪主はしばしば混乱し、慌てることがあります。
葬儀費用を支払う際には、以下の点に注意し、冷静に対処しましょう。
総額の見積もりを事前に確認
葬儀後に思いがけず高額な請求が来ると、家族は困惑することがあります。
このような事態を避けるためにも、葬儀社には事前に総額の見積もりを依頼しましょう。
見積もりには、葬儀の基本料金のみならず、追加で発生しうる費用(花輪、返礼品、会食費用など)についても確認が必要です。
これらの詳細をメモしておくことで、後でのトラブルを防げます。
互助会・共済会についての情報共有
互助会や共済会に加入している場合、その情報は故人だけでなく、家族全員で共有することが重要です。
万が一、加入していることを家族が知らないまま別の葬儀社を利用すると、積立てた金額を利用することができません。
また、積立金は葬儀費用の一部をカバーするもので、すべての費用を賄うことはできないため、返礼品や会食、宗教者へのお布施などの費用についても別途計画を立てる必要があります。
故人の預金口座の凍結への対応
金融機関は故人の死亡を知ると、口座を凍結することが一般的です。
これは、相続争いや不正利用を防ぐための措置です。
凍結された口座からお金を引き出すには、相続人全員の同意が必要で、戸籍謄本や死亡診断書などの書類が求められます。
この手続きは複雑で時間がかかることがあるため、故人の口座から葬儀費用を支払う予定の方は、事前に必要な書類を準備し、手続きの流れを理解しておくことが大切です。
また、故人の預金口座から引き出せる金額には制限があります。
一般的には「預金残高×1/3×1/相続人数の合計」で計算され、1口座あたり最大150万円までとなっています。
その他の支払い方法についても考慮
葬儀費用の支払い方法としては、互助会や共済会の他にも、葬儀ローンや故人が加入していた生命保険の利用などが考えられます。
これらの方法を選択する際にも、それぞれのメリットとデメリットを理解し、家族で十分に話し合って決定することが重要です。
葬儀の準備は心情的にも、経済的にも大きな負担となりがちです。
しかし、これらのポイントを押さえ、計画的に対応することで、精神的なストレスを軽減し、スムーズに手続きを進めることが可能となります。
以上を踏まえた見積もりを複数の葬儀社から取って、葬儀社を選ぶのがおすすめです。
葬儀費用の支払いについてのよくある質問

葬儀費用の支払いについてのよくある質問をご紹介します。
香典の費用には贈与税がかかりますか?
香典は故人を偲ぶ際に贈るお金であり、その性質は一般的に「贈与」とされます。
このため、一定額以上の香典を贈る場合、贈与税が発生する可能性が高く、贈与税の申告が必要になった場合を考慮して領収書をしっかりと保管することが推奨されます。
ただし、夫婦間での贈与は一定額まで非課税とされています。
葬儀費用の支払いで起こるトラブルはありますか?
葬儀費用の支払いで起こる可能性のあるトラブルには、追加料金の発生が考えられます。
葬儀費用の内訳が不明瞭な葬儀社の場合、見積もり段階で聞いていた費用に追加費用が発生して金額が予定よりも高額になってしまう事例があります。
このような状況を避けるためには、事前に葬儀社との契約内容をしっかり確認することが必要です。
また、葬儀社とのトラブルだけでなく、葬儀費用を誰が支払うかで相続人と揉める場合もあります。
葬儀費用の負担が不均等だと不満が発生する可能性があるため、事前に家族間で葬儀費用の分担について話し合い、明確な合意を得るようにしましょう。
故人の預貯金から葬儀費用を捻出する場合は、凍結した口座から葬儀費用を引き出す旨を事前に伝えておくとトラブルになる可能性を減らせます。
相続財産から葬式費用を支払うことは可能ですか?
はい、相続財産がある場合、その資産から葬式費用を支払うことは可能です。
葬式費用は大きな支出となるため、喪主が自己の資金で全額をカバーするのが難しい場合があります。
そうした状況では、相続財産を使って葬式費用を支払うことが一般的です。
ただし、故人の預金口座が凍結される前に現金を引き出しておく必要があります。
預金口座がいったん凍結されると、相続手続きが完了するまで引き出しはできません。
引き出しには故人のキャッシュカードと暗証番号が必要です。
一部の金融機関では、凍結された口座から葬儀費用を引き出すことを許可している場合もありますが、これは例外的なケースです。
通常は口座が凍結された後は、相続財産を葬式費用に使うことは困難になりますので、早めの対応が必要です。
葬式費用や香典に関するトラブルを避けるにはどうすればいいですか?
葬式費用や香典は金銭トラブルの原因となりやすいので、事前の話し合いと適切な管理が重要です。
特に葬儀費用に関しては、負担者や分担割合について家族や親族間でしっかりと話し合い、明確に決めておくことが大切です。
金銭の負担をする人たちの間で帳簿を作成し、領収書や明細書を共有することで、支払いの透明性を保ち、トラブルを未然に防ぐことができます。
香典については、相続財産には含まれず、基本的に喪主への贈与となります。
しかし、想定以上に多額の香典が集まった場合、その扱いを巡ってトラブルが生じることがあります。
香典の分配についても、家族や親族で事前に話し合い、合意に至ることが重要です。
遺産分割とは異なる扱いなので、喪主としては、集まった香典の扱いについても透明性を持って対応することが求められます。
香典の相場について、親族、友人、仕事関係などのケース別にどのような違いがありますか?
香典の相場は、故人との関係性や参列者の年齢によって異なります。
親族の場合、遠い親戚は3,000円から1万円、おじおばなどは1万円から3万円が一般的です。
兄弟姉妹や親の場合は、年齢や親密さに応じて3万円から10万円程度になります。
友人の場合は、3,000円から1万円が相場で、特に親しい友人は5,000円から1万円程度が多いです。
仕事関係では、同僚や部下には3,000円から1万円、上司には5,000円から1万円が適切とされています。
また、取引先の場合、故人の役職に応じて1万円から10万円の範囲で調整します。
これらの相場はあくまで目安であり、自分の財政状況や故人との関係を考慮して適切な額を決めることが重要です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀費用の支払いまとめ

ここまで、葬儀の支払方法や、葬儀費用の支払いのタイミングを中心に書いてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 一括で支払える場合は現金払いが一般的
- 支払いのタイミングは、葬儀後1週間程度
- 一括が無理なら葬儀ローンや補助金制度が利用できる
これらの情報が少しでも皆様の役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2025.06.17
互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説
お葬式

更新日:2024.01.10
合同葬とは?社葬や一般葬との違いや相場、マナーについて解説
お葬式

更新日:2023.10.20
湯灌(湯かん)は何をするの?湯灌の目的や費用相場なども紹介
お葬式
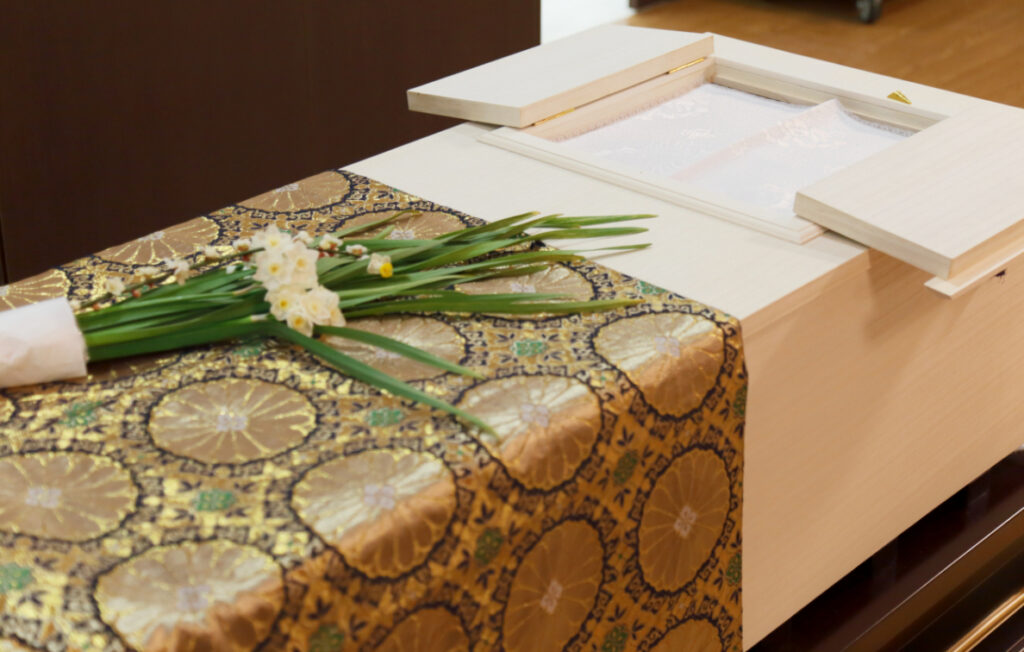
更新日:2024.02.03
遺体搬送車とは?遺体搬送車の車種や霊柩車との違い、搬送料金についても解説
お葬式

更新日:2023.11.12
霊柩車の利用料金は?霊柩車の値段や霊柩車の種類、車種についても解説



