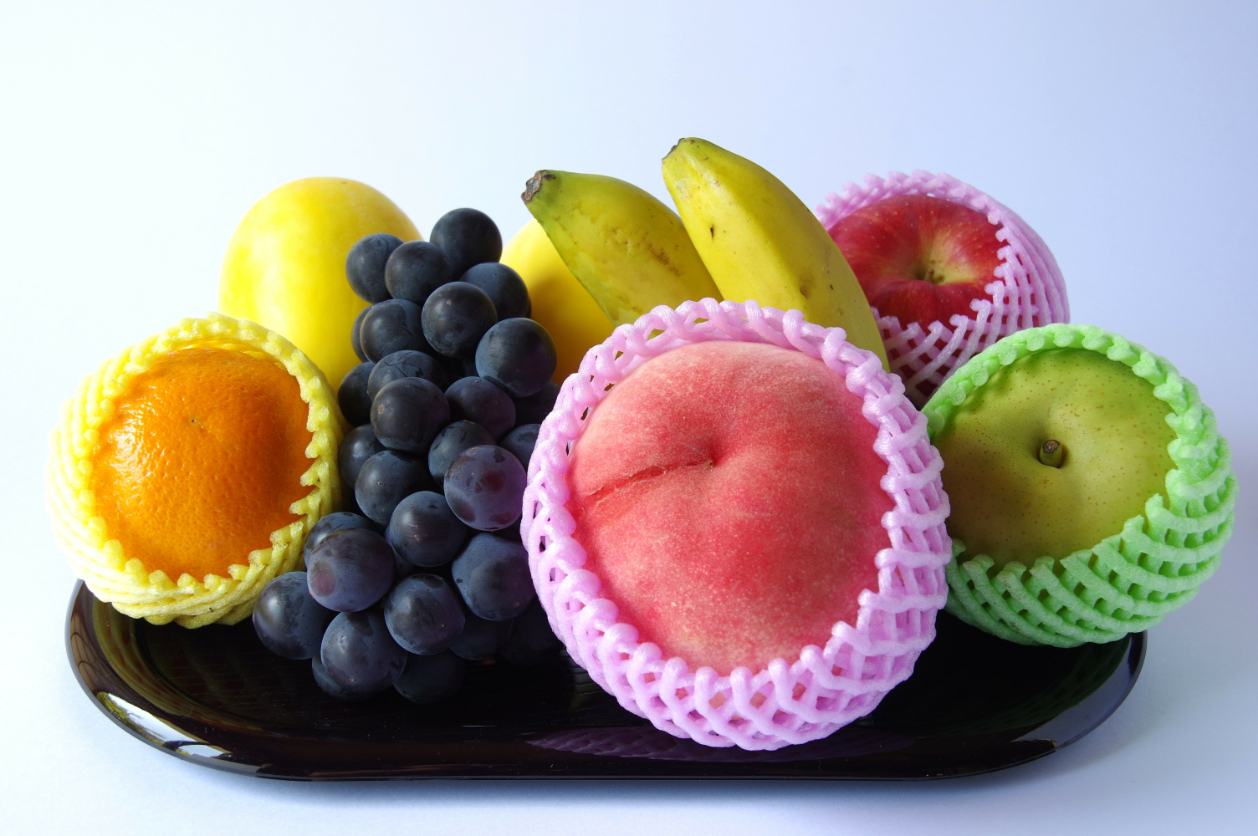法事法要
お墓の魂入れのお布施とは?相場や表書きの書き方まで解説
更新日:2022.09.04 公開日:2021.11.27

記事のポイントを先取り!
- 魂入れとは、故人の魂をお墓や仏壇に宿す儀式
- 魂入れのお布施の相場は1万円〜3万円
- 魂入れのみの場合はお祝い事だが、納骨を伴う場合は弔事
お墓を初めて購入した後、「魂入れ」をする必要があることをご存じですか?
魂入れや儀式の内容について知らない方も多いと思います。
この記事では、魂入れとはどのような儀式なのか、魂入れのお布施について説明します。
ぜひ、最後までご覧ください。
みんなが選んだ終活では無料の電話相談を実施しています。
魂入れのお布施についてお悩みの方はお気軽にお電話ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
魂入れとは
魂入れとは、「開眼法要」とも呼ばれ、僧侶の読経を通して故人の魂をお墓に宿し、礼拝の対象とする儀式のことです。
新しくお墓を建てたり、お墓の移動やリフォームをしたりする時に行う法要です。
魂入れを行う前の墓石は、霊が宿っていないただの石とみなされます。
他にも「お性根入れ」「入魂式」「霊入れ」など様々な呼び名があります。
ただし、浄土真宗では「魂」という概念がないため、魂入れや開眼法要は行いません。
「御移徙法要(おわたましほうよう)」や「遷仏法要」がそれにあたります。
こちらの記事では、お墓の開眼供養について詳しく解説しています。
開眼供養でお悩みの方はぜひこちらもご覧ください。
お墓の魂入れの依頼先
魂入れは菩提寺に依頼するのが一般的です。
菩提寺とは、先祖代々のお墓があるお寺のことを言います。
菩提寺がない場合、もしくは近くにない場合は、葬儀やお墓をお願いしたお寺に相談してみましょう。
詳しくないから魂入れを忘れるのではないか。と心配される方もいると思います。
仏壇仏具店の多くは、購入者に対して魂入れについて説明してくれます。
そのため心配する必要はありません。
不安なことも多いと思いますので、まずはお寺や葬儀会社に相談してみましょう。
みんなが選んだ終活では無料の電話相談を実施しています。
お墓の魂入れの依頼先にお困りの方はお気軽にお電話ください。

みんなが選んだ法事法要の電話相談
みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
5万円からご案内!
4万円からご案内!
お墓の魂入れのお布施

魂入れをお寺に依頼する場合、僧侶に渡すお布施を準備しておく必要があります。
お布施は、お墓に来てお経を上げてもらったお礼として渡します。
魂入れのお布施の金額
また、お布施以外にも、お車代や、御膳料も渡すのが一般的です。
以下がお布施、お車代、御膳料の費用相場です。
- 魂入れのお布施:1万〜3万円程度
- お車代:5000円〜1万円程度
- 御膳料:5000円〜1万円程度
また、魂入れと同じ日に納骨式を行うこともできます。
その場合は、1.5~2倍程度の金額を包むことが一般的です。
御膳料は、僧侶が会食に同席する場合は渡す必要がありません。
ただし、親族が集まる会食に僧侶が同席することはほとんどないため、御膳料としてお渡しする場合が多いようです。
会食に同席されるかどうかは、魂入れの日程の相談と合わせて確認しておくと良いでしょう。
加えて、石材店や施設管理業者の方など、お世話になった方達にお礼を包む人もいます。
目安は5000円〜1万円程度ですが、提示された料金をすでに支払っている場合は必要ありません。
お布施の金額については、特に決まった金額がありません。
わからないときは僧侶やお寺に直接確認しても問題ありません。
その際は、「他の檀家さんはどのくらい包んでいらっしゃいますか?」と間接的に確認するようにしましょう。
魂入れのお布施袋の書き方・水引
お布施の袋の書き方は、弔事と慶事によって分かれます。
以下で詳しく見ていきましょう。
納骨も一緒に行う場合は弔事
新しく納骨するためにお墓を建てたのであれば、魂入れと納骨法要は同時となり、不祝儀になります。
表書きは「御布施」とし、奉書紙に包むか、無地の白封筒などに入れます。
地域によっては、黒白または双銀の結び切りの水引を使う場合もあります。
魂入れのみなら慶事
生前にお墓を建てた場合など、魂入れのみを行う場合は慶事と捉えられます。
生前にお墓を建てることは長生きや子孫繁栄、家内円満を導き、縁起が良いとされているためです。
表書きは「御布施」や「御礼」とし、奉書紙または無地の白封筒に包みます。
また、赤白結び切りの水引で、のしがついていない祝儀袋を使います。
ただし、多くの祝儀袋の右上についているのしは、あわびをあらわしています。
仏教では生臭いものを嫌うので、慶事でも、のしがついていないものを使いましょう。
みんなが選んだ終活では無料の電話相談を実施しています。
魂入れのお布施にお悩みの方はお気軽にお電話ください。

お墓の魂入れのお返し
友人や知人、親族からお祝いをいただいた場合は、お返しをする必要があります。
基本的にはいただいた額の半分相当の品物をお返しします。
品物は、お菓子やタオルなどの消耗品を贈ることが一般的です。
そのほかに、カタログギフトをお返しとして贈る人も増えています。
表書きは「御礼」、「内祝い」、「建立内祝い」と書くようにしてください。
納骨式を一緒に行う場合でも同様に、いただいた金額の半分相当の品物を贈ります。
みんなが選んだ法事法要の電話相談
みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
5万円からご案内!
4万円からご案内!
魂入れは仏壇を購入した際にも行う

魂入れは、お墓だけではなく仏壇を購入、リフォームしたときにも行います。
仏壇の魂入れは仏壇に対して行われると思われる方も多いですが、御本尊、掛け軸、ご位牌に対して行うものです。
魂入れを行うまでは御本尊もご位牌もただの木彫りでしかなく、魂入れをしてはじめて礼拝の対象となります。
仏壇の魂入れは菩提寺にお願いするのが一般的ですが、菩提寺が無い場合や疎遠である場合、インターネットから手配してくれるサービスもあります。
仏壇の魂入れで包むお布施の金額の相場は3万〜5万円が相場です。
お墓と仏壇の魂入れは同時に行うこともできます。
その場合は、お布施は2回分ではなく、1回分の金額に少し多く包むといいでしょう。
こちらの記事で仏壇の開眼供養について解説しているので、ぜひご覧ください。
魂入れに招かれた場合はどうする?
参列者として魂入れや開眼供養に招かれたときは、お供え物またはお祝いを持参します。
魂入れのご祝儀の表書きや金額
魂入れのみの場合や生前に建立された場合は、紅白の水引で「建碑御祝」「建立御礼」「祝建碑」「御供養料」とします。
納骨法要を伴う場合は、黒白の水引で表書きは四十九日以前は「御霊前」四十九日以降なら「御仏前」と書きましょう。
会食付きの魂入れのご祝儀の相場は、親族は2万円程度、友人は1万円程度です。
会食のない場合、親族は1万円程、友人は5000円程度包みます。
こちらの記事で開眼供養に必要なお供え物について解説しているので、ぜひご覧ください。
服装について
魂入れを行うのが故人の四十九日以内なら喪服が必要ですが、それ以降は喪服の着用は必要ありません。
魂入れのみ行う場合は、地味な服装で結構です。
男性はダークスーツ、女性はフォーマルなワンピースなどがあたります。
魂入れのみの場合は施主に「おめでとうございます」と声がけをしますが、法要と一緒に行われる際はお悔やみの言葉をいいます。
みんなが選んだ法事法要の電話相談
みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
5万円からご案内!
4万円からご案内!
お墓の魂入れの流れ
「魂入れ」は別の呼び方で「開眼法要」「開眼供養」「お性根入れ」などの呼び方があります。
新しいお墓を建てた時やお墓を移動する時に行う儀式で、故人の魂をお墓に宿らせることをいいます。
お墓の準備
墓地と墓石の購入が済んだら、お墓の清掃とその周辺も綺麗にしましょう。
魂入れまで時間がある場合は、白い布を巻いて墓石が汚れないようにしておきます。
故人の戒名を彫ったり、祭壇の準備についてはお墓を建立した石材店が担ってくれることがほとんどです。
遺骨がある場合は先に納骨を済ませておくことも可能です。
祭壇には故人が好きだった食べ物や飲み物などを用意する場合が多いです。
お供え物には特に決まりはないので、法要してくれるお寺に事前に確認しておくと良いでしょう。
こちらの記事でお墓の開眼供養のお供えについて解説しているので、ぜひご覧ください。
僧侶の手配
魂入れでは菩提寺の僧侶から読経を行ってもらう必要があります。
菩提寺とは先祖代々のお墓が祀られているお寺のことです。
葬式や法事などを依頼するお寺でもあり、仏事でわからないことがあった場合、相談に乗ってもらえる場所でもあります。
近年では「そもそも菩提寺がない」「菩提寺はあるが疎遠で頼むのが難しい」などの理由も多く見受けられています。
その場合、インターネットで複数の宗教宗派に対応した僧侶を派遣してくれるサービスなども提供されています。
魂入れは魂を宿らせる大切な儀式のひとつなので、なるべく行うべきです。
人数確認
魂入れに参加される方を確認したら、土曜、日曜、祝祭日に設定し参加しやすい日程で組みましょう。
通夜、告別式ほどの規模ではなく、親しかった友人や親族が参加するのが一般的です。
人数にもよりますが、日時やアクセスマップ、会食会場などが記載されている案内状の作成や郵送も必要となります。
ゴールデンウィークやお盆などの大型連休は、参列される方が旅行に出かけてしまう場合もあります。
また、僧侶もお盆やお彼岸時は多忙なため、都合をつけることが難しい可能性が高いです。
早めの連絡を心がけましょう。
会食の手配
法要後は僧侶と参列者を会食の席に招きます。
お料理はお寿司や仕出し料理、懐石料理を用意するのが一般的とされています。
墓地や霊園、お寺にある施設を主に利用することが多いですが、ホテルや料亭、自宅などでも行うことがあります。
また会場が墓地から離れている場合、移動時にバスやタクシーの手配が必要となります。
事前に交通手段は確認しておき、当日はスムーズに移動できるようにしましょう。
お布施の用意
魂入れではお布施の準備が必要です。
お布施とは、葬儀や法要の時に僧侶へ謝礼として渡すお金のことです。
あくまでも謝礼として渡すものなので読経の対価として払う料金ではありません。
お布施の金額は地域や宗教、執り行う儀式によって金額は異なります。
封筒の中に入れるお金は新札、古札どちらでも構いません。
香典の場合は古札を使用しますが、お布施は謝礼として渡すものなので新札で用意されたほうがよいでしょう。
また封筒の水引は不要で、白い無地のものを使用することが多いです。
封筒は市販のもので構いません。「お布施」や「御布施」と印刷された封筒を用意しましょう。
こちらの記事でお布施の水引について解説しているので、ぜひご覧ください。
引出し物を用意
魂入れは新しく建てたお墓を祝う儀式のため、引き出物を用意するときは、消え物ではないタオルや日用品を準備するとよいでしょう。
魂入れと納骨式を同時に行う場合は、香典返しや法事のお返しと同様、お茶や海苔、お菓子などの消え物を準備しましょう。
また、お返しはどのようなものを用意したらよいかわからない場合は、カタログギフトを利用される方も近年増えてきています。
選定するのに迷ったらカタログギフトを利用されるとよいでしょう。
こちらの記事で法事のお返しについて解説しているので、ぜひご覧ください。
服装の準備
特に決まりはありませんが、派手な服装や貴金属類は控えましょう。
黒やグレーなど落ち着いた色の服装であれば問題ないです。
中には礼服を着用される方もいます。
男性の場合は礼服に白ネクタイ、女性の場合は礼服や無地の着物で参列されることが一般的です。
礼服ですが、一般的とされているだけで必ず身につける必要はありません。
ただし納骨式も行う場合は、施主側、参列側ともに喪服で参列しましょう。
こちらの記事で法事の服装について解説しているので、ぜひご覧ください。
お墓の魂入れのお布施についてのまとめ

ここまで魂入れのお布施について詳しく説明してきました。
まとめると以下の通りです。
- 魂入れは、お墓や仏壇に故人の魂を入れて礼拝の対象にしてもらうこと
- 魂入れのお布施の相場は1万円〜3万円
- お布施の表書きは「お布施」とし、奉書紙または白無地の封筒に入れる
- 魂入れに招かれた場合の香典は、親族は1万円〜2万円、友人は5000円〜1万円程度
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
みんなが選んだ終活では無料の電話相談を実施しています。
8:00~20:00の年中無休で専門の相談員が対応いたします。
お墓の魂入れについてお困りの方はお気軽にお電話ください。

都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
法事法要の関連記事
法事法要

更新日:2022.12.24
厄払い・厄祓いで初穂料の封筒は何を使う?書き方や包み方、相場も解説
法事法要

更新日:2024.01.24
三十三回忌のお布施の相場は?お布施の書き方・包み方・渡し方も解説
法事法要

更新日:2022.05.19
50回忌法要のお布施はどのくらい?弔い上げをする場合は?
法事法要

更新日:2022.05.24
お墓を移動させるときにお布施は必要?お墓の移動について詳しく解説
法事法要

更新日:2022.11.11
浄土真宗のお布施の相場は?お布施の書き方や宗派ごとの相場も解説
法事法要

更新日:2022.12.24
檀家のお布施はいくら必要?入檀料や離檀料の相場についても解説