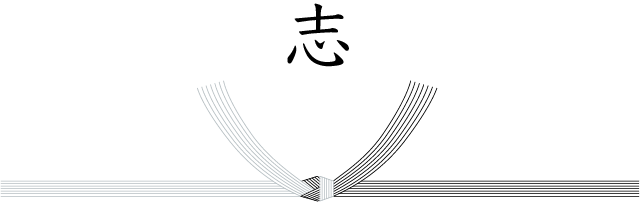法事法要
一周忌のお返しにオススメの品を紹介!渡すタイミングやマナーは?
更新日:2022.02.08 公開日:2022.02.07

記事のポイントを先取り!
- 一周忌のお返しには消え物以外の残る品物でもOK
- 一周忌のお返しの目安は御仏前の半額~7割程度
- 一周忌のお返しの「のし」には「志」や「粗供養」と書く
故人が亡くなってから1年後の祥月命日には、一周忌を行います。
一周忌でいただいた御仏前には引き出物をお返ししますが、どんな品物を選べば良いのかご存知でしょうか?
そこで、この記事では一周忌のお返しについて詳しく解説します。
この機会に、一周忌におけるお返しマナーについても知っておきましょう。
一周忌のお返しでよくある間違いについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
一周忌とは
一周忌とは、故人が亡くなってちょうど1年目の同月同日(祥月命日)に執り行われる法要のことです。
遺族にとっては1年間の服喪期間の空ける節目の日でもあります。
一周忌には親族のほか、故人と縁の深かった友人にも参列してもらうのが一般的です。
法要の中でも比較的規模の大きい部類に入るといえるでしょう。
本来は祥月命日に行う法要ですが、命日が平日だった場合は、参列者の休みを考慮して手前の土日に行われることが多いようです。
一周忌のお返しで選ばれる定番の品
一周忌のお返しでよく選ばれる定番の品物をご紹介します。
葬儀時の香典返しではお茶やコーヒーなど、後に残らない「消え物」が基本です。
しかし、一周忌のお返しでは食器や茶器など形に残るものを選んでも良いとされています。
引き出物は基本的に軽くて小さめの品物を選びましょう。
重くてかさばる品物は遠方からいらっしゃる参列者の負担となります。
乾物の詰め合わせ
乾物の詰め合わせは弔事のお返しの定番といえるでしょう。
椎茸や鰹節の詰め合わせや海苔とお茶漬けのセット、京都のお吸い物セットなどがあります。
日持ちもよく、老若男女問わず好まれる品物でおすすめです。
引き菓子
お菓子も幅広い年代の方に受け入れられるお返しといえます。
引菓子は和菓子と洋菓子、どちらでも大丈夫です。
洋菓子ならクッキーやマドレーヌ、和菓子なら羊羹やおかき・カステラが人気です。
夏場であればゼリーでもいいでしょう。
お菓子は個別に包装されているタイプがおすすめです。
地域によっては引き菓子を単品で渡すことがマナー違反となるところもあります。
そのような場合は、単品の引菓子よりも安価のものをいくつか組み合わせます。
生前、故人が好きだったお菓子を引き菓子として、親しい方に渡すのもおすすめです。
故人の思い出話などもできて供養になるでしょう。
カタログギフト
近年、お返しの品として人気があるのがカタログギフトです。
遺族側がお返しの品物を選んで手配するのは手間がかかります。
カタログギフトは参列者が好みの品物を選べますし、持ち帰る際も荷物になりません。
品物ですと落として割れたりする心配がありますが、カタログなら安心です。
ただし、品物の発注が参列者の負担になる点と、手元に届くまで時間がかかる点は留意してください。
みんなが選んだ法事法要の電話相談
みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
5万円からご案内!
4万円からご案内!
一周忌のお返しのマナー
一周忌のお返しで注意するポイントについてお伝えします。
葬儀後の香典返しとは異なりますので、相違点を確認しておきましょう。
のし
一周忌の引き出物に使用する「のし」の書き方についてご説明します
表書き
表書きは「志」と記すのが一般的です。
ほかには「粗供養(そくよう)」や「御礼」の表書きも使われます。
通夜や葬儀では薄墨を使用しますが、一周忌の表書きは濃墨色で書いてください。
薄墨を使用するのは「悲しみで墨が薄まった」という意味や「墨をする間もなく駆けつけた」という意味が含まれています。
一周忌はあらかじめ予定されている法要ですので薄墨は使用しません。
表書きの下には施主の苗字、もしくは「○○家」と家名を書きます。
水引
水引は黒白か双銀の結び切りを使用します。
関西や北陸地方では黄白の結び切りを使用する場合もあります。
近年は、もともと水引が印刷された包装紙がよく用いられます。
渡すタイミング
引き出物を渡すタイミングは、法要が終わったあとです。
法要後にお斎がある場合は、会食が終わったあとに渡すことになります。
お斎をレストランなどで行うのであれば、あらかじめスタッフに伝えておくことで参列者が席を立つ前に渡してもらえます。
お斎がない場合は、折詰やお酒を持ち帰ってもらいますが、そのときに引き出物も一緒に渡します。
お供えのみを頂いた場合
一周忌法要に参列できず、御仏前のみ郵送でいただくこともあります。
この場合はお礼状と一緒に引き出物を送りましょう。
法要後1カ月以内に送ることができるように手配します。
参列していただいた方と同じ品物を送る場合と、お斎の代わりにもう一品を追加して送る場合があります。
地域ごとに異なるため、わからない場合は親族や葬儀社のスタッフに相談しましょう。
スポンサーリンク一周忌にお礼状は必要?
一周忌の引き出物にはお礼状を付けると丁寧です。
参列した方へは直接お礼を述べられますが、さらに引き出物の中にも礼状が入っていることで印象も良くなります。
一周忌に参列できずに御仏前だけ送っていただいた方へは、必ずお礼状を付けてお返しを送りましょう。
御仏前をいただいた感謝の気持ちと、一周忌法要が滞りなく済んだ報告、さらに手紙で略儀のお礼になってしまったことをお詫びします。
お礼状は縦書きが基本です。
亡くなった方の敬称は、施主から見た故人との関係で書きましょう。
「亡祖父○○儀」や「故○○儀」のように表します。
文面では句読点を使用せずに空白や改行を用いてバランスよく書きます。
「度々」や「ますます」などの重ね言葉は、「不幸を繰り返す」とされる縁起の悪い言葉なので使用しません。
また、「もう一度」や「引き続き」なども「不幸が再び訪れる」、「不幸が続く」などを連想する忌み言葉にあたるので避けてください。
「四」や「九」の数字も縁起が悪いため使用しません。
以下は礼状の例文です。
【参列した方へ渡す礼状】
拝啓
亡祖父○○の一周忌の法要につきまして ご多用中のところ はるばるお越しいただき誠にありがとうございました
皆様にはこの1年 温かく励ましていただき ようやく前向きに生活を営んでいけるようになりました
無事に法要を終えることができましたこと 厚く御礼申し上げます
略儀ではございますが 書中にてお礼の挨拶とさせていただきます
敬具
【参列されなかった方へのお礼状】
拝啓
この度は 亡祖父○○の一周忌につきまして ご鄭重なるご厚志を賜りまして 誠にありがとうございます
去る△月△日、無事法要を終えることができました
謹んでここにお知らせさせていただきます
簡単ではございますが 書中にてお礼のご挨拶とさせていただきます
敬具
みんなが選んだ法事法要の電話相談
みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
5万円からご案内!
4万円からご案内!
一周忌のお返しでよくある間違い
一周忌のお返しと、葬儀時のお返しを混同していないでしょうか?
お返しする額や熨斗の書き方で間違いやすい点についてお伝えします。
半返し
一周忌のお返しの基本は、「お斎+引き出物」です。
いただいた御仏前の半分〜7割ほどになるよう準備しましょう。
地域によっては7割〜同額以上のところもあるので確認が必要です。
葬儀時の香典返しの場合はいただいた香典の3分の1〜半額程度が一般的ですが、一周忌法要では異なりますので注意してください。
例えば御仏前が2万円でお斎が5,000円だった場合、引き出物の金額は5,000〜7,000円程度と考えます。
お斎がない場合は、「持ち帰り用の折詰とお酒+引き出物」となります。
夫婦で来られた場合も、引き出物は1世帯につき1つお渡しするのが一般的です。
お斎(折詰)と引き出物は、遺族側があらかじめ準備しなければなりません。
予想よりも多く御仏前を包んできた方へは、後日追加分の品物を郵送します。
薄墨の使用
通夜や葬儀では薄墨で香典を書きますが、一周忌では薄墨を使用しません。
御仏前やお返しの品物の表書きは濃墨色で書くようにしましょう。
薄墨を使用する意味は「悲しみの涙で墨の色が薄くなってしまった」や「墨をする間もなく駆けつけた」というものです。
一周忌法要はあらかじめ予定されている法要ですので、薄墨で書く必要はありません。
薄墨で表書きを書くのは通夜・葬儀のみとするのが一般的です。
ちなみに京都では、通夜や葬儀でも薄墨を使用しない地域が多いようです。
スポンサーリンク一周忌のお返しのまとめ

ここまで、一周忌のお返しの詳細や注意点についてを中心にお伝えしました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りになります。
- 一周忌のお返しは御仏前の半額~7割程度を目安にする
- 一周忌のお返しで人気なのは乾物やお菓子・カタログなど
- 一周忌のお返しを渡すタイミングは法要後、もしくはお斎後
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
法事法要の関連記事
法事法要

更新日:2024.01.24
四十九日が過ぎるまで遊びに行くのはダメ?他にもNGな行動を紹介
法事法要

更新日:2022.11.21
法事で食事なしはマナー違反?食事の代わりやおすすめの引き出物を紹介
法事法要

更新日:2022.11.18
四十九日の献杯ではどんな挨拶をする?挨拶のポイントや文例を紹介
法事法要

更新日:2022.05.17
弔い上げ(三十三回忌)をしないという選択について
法事法要

更新日:2022.02.19
一周忌の法要は欠席しても大丈夫?欠席する場合のマナーを解説
法事法要

更新日:2022.08.21
七回忌のお供えには何を用意すれば良い?相場やNGな物も紹介