お葬式
火葬許可証と埋葬許可証の違いは?紛失した時の再発行の仕方なども紹介
更新日:2024.04.02 公開日:2022.02.20

記事のポイントを先取り!
- 火葬許可証の発行は死亡届が必要
- 埋葬許可証の発行は火葬場が行う
- 埋葬許可証の再発行は可能
故人を埋葬するうえで火葬許可証と埋葬許可証が必要になりますが、その2つの違いについてはご存知でしょうか。
いつか大切な方が亡くなった時、安らかに眠ってもらうためにも知っておくべきでしょう。
そこで、この記事では火葬許可証と埋葬許可証について、詳しく説明していきます。
この機会に発行場所や死亡届出人の条件についても覚えておきましょう。
万が一、無くして再発行が必要になった場合についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 火葬許可証と埋葬許可証の違い
- 埋葬とは
- 埋葬の種類
- 火葬許可証と埋葬許可証の発行
- 火葬許可証と埋葬許可証の提出先
- 埋葬許可証を紛失した場合
- 埋葬許可証を保管する方法
- 埋葬許可証の保管期間
- 埋葬する際にもらえる給付金
- 火葬許可証の申請手続きは誰でもできる?
- 火葬許可証で書くこと
- 分骨と散骨の埋葬許可証
- お墓のお引越しに必要な改葬許可証
- 納骨までの流れ
- 火葬の流れ
- よくある質問
- 火葬許可証・埋葬許可証のまとめ
火葬許可証と埋葬許可証の違い
人は亡くなると葬儀を経て火葬され、お墓などに埋葬されるのが一般的です。
日本において人の死や遺体の取扱いは、間違いがあってはならないこととして明確な手順に則って進められます。
その手順の中には、公的な効力を持った2つの許可証が存在し、社会的秩序が守られています。
火葬許可証とは
火葬許可証とは、故人の遺体を火葬する許可を証明する書類です。
火葬許可証は葬儀の前に必ず取得する必要があります。
火葬許可証を取得しなかったり、火葬場に提出できなければ火葬を執り行うことができないからです。
埋葬許可証とは
埋葬許可証とは、火葬後の遺骨をお墓や納骨堂に埋葬する許可を証明する書類です。
火葬場に提出した火葬許可証は遺骨とともに返却されます。
火葬場から返却された火葬許可証が埋葬許可証です。
書類自体は同じもの
火葬許可証と埋葬許可証は、多くの場合同じ書類です。
火葬場に提出するまでの名称が「火葬許可証」で、火葬後に返却されたものが「埋葬許可証」になります。
火葬場は火葬が正規の手順で行われると、火葬許可証に印を押します。
この印は遺体を火葬したことを証明し、埋葬許可証として返ってくるのです。
火葬場の印があるかないかの違いはありますが、同じ書類が火葬許可証と埋葬許可証を兼ねているのです。
スポンサーリンク埋葬とは
埋葬についての理解を深めるためには、その歴史的背景や法的な側面、さらには安置方法についての知識が必要です。
以下では埋葬に関連する基本情報を簡潔に紹介します。
埋葬の歴史背景
日本では江戸時代まで土葬と火葬が併用されていましたが、明治時代に入ると葬儀方法に大きな変化がありました。
明治3年に寺院墓地の国有化が行われ、明治5年には自葬祭が禁止され、葬儀は神主や僧侶が行うものとされました。
火葬禁止令が出された時期もありましたが、その後火葬の有用性が認められ、今日では衛生面を考慮して主流となっています。
法的解釈
昭和23年には「墓地、埋葬等に関する法律」が制定され、土葬や埋葬のルールが整備されました。
この法律により、遺骨を骨壺に納める場合、指定された区域外での埋葬や自宅土地への埋葬が禁止されています。
ただし、遺骨を自宅に安置する行為については違法ではありません。
埋葬と納骨の区別
埋葬は遺体や遺骨をお墓に納める行為全般を指し、納骨は火葬後の遺骨を骨壺に入れてお墓や霊園、納骨堂に安置することを意味します。
現代日本においては、火葬後の遺骨を骨壺に納めることが一般的な方法となっています。
土葬するための許可証が「埋葬許可証」
土葬は、故人を大地に還す伝統的な葬送方法として、我が国の一部地域で今も守られている貴重な風習です。
法律により、埋葬と定義される「死体を土中に葬る行為」を実施する際には、「埋葬許可証」が必要とされます。
この許可証は、土葬を行うための公的な証明書であり、土葬の風習が残る地域でのみ、その本来の用途で用いられます。
現代日本では火葬が葬儀の主流を占めていますが、文化的・宗教的な理由で土葬を選ぶ地域や家族も存在します。
これらの地域では、埋葬許可証が土葬を行う上で欠かせない書類となります。
土葬を選択する場合、適切な手続きを経て埋葬許可証を取得することが、故人を尊重し、伝統を守る上で重要です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
埋葬の種類
現代社会では、葬儀や死に関する考え方が多様化し、それに伴い様々な埋葬方法が選択されています。
以下では、代表的な埋葬方法をいくつか紹介します。
お墓への埋葬
最も伝統的な埋葬方法として、遺骨をお墓に納める方式があります。
これには、先祖代々のお墓を使用する場合と、新たに墓石を設置してその下のカロートに骨壺を納める場合が含まれます。
先祖継承のお墓では、戒名が墓石に刻まれ、家族の歴史や絆を感じさせます。
納骨堂の活用
納骨堂は、個人や家族単位で遺骨を収納できる施設です。
都市部などの限られたスペースでも建設可能であり、屋内にあるため、天候に左右されずに訪れることができます。
その便利さから、多くの人に選ばれるようになっています。
永代供養の選択
永代供養は、寺院や霊園に遺骨を預け、代わりに永続的な管理と供養を行ってもらう方法です。
この選択肢は、お墓の継承者がいない場合や、お墓の準備と維持にかかる費用負担を軽減したい場合に特に有効です。
スポンサーリンク火葬許可証と埋葬許可証の発行
故人の遺体の取扱いにおいて、強い効力を持つ火葬許可証と埋葬許可証はどこでどのように発行されるのでしょうか。
火葬許可証の発行
火葬許可証の発行には、市町村役場の窓口にある死亡届出が必要です。
必要事項を記入して提出し、受理されることで火葬許可証が発行されます。
埋葬許可証の発行
埋葬許可証の発行は火葬場が行います。
先ほどもお伝えしましたが、遺体とともに訪れた火葬場に火葬許可証を提出し、火葬を終えたことが認められると「火葬済み」の印が押されます。
遺体が遺骨になって遺族に引き渡される際、印が押された火葬許可証が埋葬許可証として発行されます。
死亡届の提出期限
日本の法律では、死亡届を提出する期限が設けられており、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があります。
もし国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヵ月以内に届け出る必要があります。
死亡届を提出できる役所は、故人の本籍地か死亡地、または届出人の居住地の市区町村役場です。
死亡届は、「死亡診断書」と同じ用紙を使用します。
病院で亡くなった場合は、臨終を確認した医師が作成し、家庭で持病が原因で亡くなった場合はかかりつけ医に依頼して作成します。
もし不慮の事故や変死、自宅で亡くなった場合で死因が明らかでない場合は、所轄の警察署に連絡し、監察医による検案を受ける必要があります。
この場合は、「死亡診断書」は「死体検案書」となります。
死亡届の提出は、親族、同居人、後見人、本人が借りていた不動産の家主や地主などが行うことができます。
埋葬許可証を出さなかった場合
埋葬許可証は、遺骨をお墓や納骨堂に納める際に必要な重要書類です。
埋葬許可証を出さずに故人の遺体を納骨する行為は「墓地、埋葬等に関する法律」で禁止されています。
もし埋葬許可証なしで埋葬を行ってしまった場合、罰則が科される可能性があります。
また、「死体破壊・遺棄罪」として罪に問われることもあります。
そのため、墓地や納骨堂の場所を確保していても、埋葬許可証を取得することが不可欠です。
必ず火葬後に火葬執行済の印が押された火葬許可証を受け取るようにしましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬許可証と埋葬許可証の提出先
火葬許可証と埋葬許可証のおおまかな概要と流れについて解説しました。
以下では、それぞれの提出先についてご紹介します。
火葬許可証の提出先
火葬許可証の提出先は、火葬当日の火葬場の受付や事務所です。
棺に入った遺体とともに、火葬場に到着したタイミングで火葬許可証が必要になります。
埋葬許可証の提出先
埋葬許可証は遺骨を納める場所へ納骨するタイミングで必要になります。
契約した墓地や霊園で、納骨当日に管理者や受付担当者に提出します。
共同墓地の場合
埋葬許可証は墓地の管理者に提出します。
共同墓地は大きく分けて2種類あり、ひとつのお墓に複数の遺骨を納めることができる合祀墓、合葬墓と呼ばれる共同墓地は、そのお墓がある霊園や寺院が管理者です。
一方、墓地の使用者や地域のコミュニティーなどで管理や運営している場合の共同墓地の責任者は区によって違い、区長や衛生長などの役員が担当することもあります。
地域の共同墓地は墓地専任の役員ではなく兼任されている場合があるので注意が必要です。
火葬許可証や埋葬許可証はコピーでも可能?
分骨における埋葬許可証の取り扱いは、葬儀や納骨の手続きにおいて重要なポイントとなります。
特に、遺骨を複数の場所に分けて納骨する場合、それぞれの納骨場所に対して埋葬許可証が必要になることがあります。
これは、墓地や霊園の管理者に対して正式な手続きを行うための公的な証明として求められるためです。
火葬が完了した段階で、分骨が予定されている場合や、分骨先が既に決定している場合は、火葬場の担当者に事前に相談することが重要です。
多くの場合、必要な埋葬許可証を事前に準備してもらうことが可能です。
また、複数の場所に分骨する際には、「分骨証明書」という形で埋葬許可証が発行されることも一般的です。
一方で、火葬許可証や埋葬許可証は公的な文書であるため、原則としてコピーではなく原本の提出が必要です。
万が一、これらの文書を紛失した場合は、再発行の手続きを行う必要があります。分骨に関連して複数の埋葬許可証が必要な状況では、その旨を明確にして、必要な数の文書を発行してもらうようにしましょう。
このように、分骨や納骨をスムーズに行うためには、事前の準備と適切な手続きが不可欠です。
埋葬許可証の取り扱いについて正確な情報を把握し、必要な書類を適切に準備することが、故人を敬う過程における大切な一歩となります。
スポンサーリンク埋葬許可証を紛失した場合
火葬済みの印が押された埋葬許可証を誤って紛失してしまった場合、正しい手順を踏めば再発行することができます。
多くの場合、四十九日法要と同時に納骨される方がほとんどです。
しかし火葬後の遺骨を、お墓などに埋葬するタイミングに決まりはありません。
そのため人によっては、自宅で長期間保管する方もいるようです。
火葬から四十九日までの間に、埋葬許可証を無くしてしまうこともあるかもしれません。
何年も長期間にわたって自宅で遺骨を保管していれば、紛失する可能性も高くなりがちです。
実は埋葬許可証の再発行には、火葬から埋葬までの期間によって2通りの条件があります。
それぞれについて以下でご紹介します。
火葬許可証の発行から5年未満の場合
火葬許可証の発行日から5年未満であれば、発行した市区町村役場で再発行が可能です。
市区町村役場は、火葬許可証の保管期間を5年間と定めているからです。
火葬許可証の発行から5年以上の場合
火葬許可証の発行から5年以上が経過している場合、「火葬証明書」という書類が必要です。
市区町村役場では、5年が経過しているため再発行ができません。
しかし火葬場は火葬後30年の間、火葬の記録保持が義務付けられています。
そのため5年が経過していても、記録を元に火葬場で「火葬証明書」を発行してもらえます。
その火葬証明書を市区町村役場に届けると、火葬許可証の再発行申請を行えます。
民営の火葬場の再発行は相談が必要
日本では、亡くなった方を火葬する場所として「公営の火葬場」が多く存在します。
特に地方自治体によって運営されていることが一般的ですが、東京23区のように公営の火葬場が少なく、民営の火葬場を利用するケースも見られます。
民営の火葬場で火葬を行い、もし埋葬許可証を紛失してしまった場合は、直接その火葬場に相談することが重要です。
公営の火葬場では火葬記録を30年間保存することが義務づけられていますが、民営の場合はその保管期間が施設によって異なるため、各施設の方針に沿った対応が必要になります。
埋葬許可証の再発行の料金
埋葬許可証の再発行には、自治体によって異なりますが約300〜400円程度の手数料がかかります。
再発行が必要な場合には、事前に料金や手続き方法を確認し、準備しておくようにしてください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
埋葬許可証を保管する方法
埋葬許可証は、火葬後に骨壺を入れた袋の中に、火葬場の職員が入れることが多いため、紛失した場合はまずその場所を確認することが推奨されます。
また、墓地の管理者は法律で埋葬許可証を5年間保管する義務があるため、必要に応じて管理者に保管状況を確認することも大切です。
スポンサーリンク埋葬許可証の保管期間
埋葬許可証は、故人を埋葬する際に不可欠な書類です。
その保管方法と期間は、場所によって異なります。
以下で、主な保管場所ごとの保管期間とそれに伴う注意点を詳しく解説します。
墓地・霊園の管理者による保管
墓地や霊園の管理者は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、遺族から提出された埋葬許可証を5年間保管する義務があります。
この期間内にお墓の移動などが発生した場合、遺族は埋葬許可証の提示を求められることがあるため、管理者への問い合わせが推奨されます。
自治体による保管
市区町村の役所では、一般に死亡後5年以内は埋葬許可証を保管しています。
ただし、自治体によっては保管期間が異なる場合があるため、具体的な保管期間については、居住地の自治体に直接問い合わせることが重要です。
埋葬許可証を紛失した場合には、この保管期間内であれば再発行を受けられる可能性があります。
自宅での保管
納骨せずに手元供養を選択する場合や、将来的に納骨を検討している場合には、埋葬許可証の自宅での保管が必要になります。
この書類は、将来的に納骨や分骨を行う際に必要となるため、紛失しないように注意が必要です。
保管の際は、骨壷と共に保管することで忘れにくくなり、推奨される方法です。
これらの点を踏まえ、埋葬許可証の保管には、提出先や自宅での保管を含め、適切な管理が求められます。
遺族は、これらの保管期間と注意点を理解し、埋葬許可証の大切な役割を果たすために、慎重に対応することが望まれます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
埋葬する際にもらえる給付金
埋葬時に受け取れる給付金には、「葬祭費」と「埋葬料」の二種類があります。
これらは、故人が生前加入していた健康保険から支給されるもので、埋葬の際に経済的な支援となります。
葬祭費
葬祭費は国民健康保険加入者のための給付金で、支給額は自治体によって異なります。
一般的には5万円が基本ですが、都市部では7万円、その他の市町村では3万円から7万円の範囲で設定されています。
葬祭を行った人が申請することにより受け取ることが可能です。
埋葬料
埋葬料は故人が加入していた健康保険種類に応じて申請方法が異なり、支給額は一律5万円です。
加入していた健康保険組合によっては、基本の給付金に加えて追加の給付がある場合もあります。
申請できるのは、故人と生計を一にしていた人が行う埋葬の際です。
これらの給付金を利用することで、埋葬にかかる経済的負担を少しでも軽減することができます。
スポンサーリンク火葬許可証の申請手続きは誰でもできる?

火葬許可証の申請は多くの場合、故人の家族が行います。
しかし、家庭や人の事情はさまざまで複雑なものです。
昔と比べて家族を持たず子供もいない独り身の方も増えています。
婚姻届を出さずに同居している方やシェアハウスの同居人が故人の葬儀から埋葬を執り行うこともありえます。
もしも、家族がいない人が亡くなった場合、家族以外でも火葬許可証の申請手続きはできるのでしょうか。
そこで家族以外でも火葬許可証の申請はできるのか、どのような条件があるのかを以下でご紹介します。
特定の人に限られる
火葬許可証の申請には「死亡届出人」が必要です。
死亡届出人は特定の方に限られているため、以下の条件を満たす必要があります。
家族や親族以外では、同居人や家主、地主、家や土地の管理者、後見人、保佐人、補助人、委任後見人とされています。
必要な書類
火葬許可証の取得に関する手続きは、喪失の瞬間から私たちが直面する実務の一部です。
この許可証を入手するには、主に3つの重要な書類が必要になります。
それぞれの書類は、そのプロセスの特定のステップを満たすために不可欠です。
まず、「死亡診断書(死体検案書)」は、患者の死亡を確認し、その原因を公式に記録するものです。
この書類は、臨終に立ち会った医師や遺体を検案した医師によって作成されます。
病院や自宅での死亡が確認された場合、この診断書を医師から受け取ることになります。
次に、「死亡届」があります。
この書類は、死亡診断書と一体化しており、通常はA3用紙の左側に配置されています。
死亡届の提出は、故人の死亡を法的に記録し、公的な手続きを進めるために必要です。
最後に、「火葬許可申請書(死体埋火葬許可申請書)」が必要です。
この申請書は、地方自治体の市区町村役場で入手することができ、一部の自治体ではオンラインでダウンロードすることも可能です。
火葬許可証の申請にあたり、これらの書類を準備し、提出する必要があります。
死亡届の提出については、誰が行っても制限はありません。
実際には、多くの場合、葬儀社がこの手続きを代行してくれるため、遺族の負担を軽減することができます。
火葬許可証をスムーズに取得するためには、これらの書類の準備と提出が重要であることを理解し、必要な手続きを迅速に進めることが求められます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬許可証で書くこと
火葬許可証の書き方が分からないと不安な方もいるかもしれません。
ですが、こちらは難しく考えなくても問題ありません。
大きく分けて以下の項目を記入します。
- 申請者の本籍・住所・続柄
- 故人の本籍・住所・死亡日時
- 火葬を行う場所
死亡診断書に記入した内容と必ず一致するようにしましょう。
分骨と散骨の埋葬許可証
分骨や散骨を行う場合の埋葬許可証についてご紹介します。
分骨を行う場合
遺骨を墓地に埋葬する際には埋葬許可証の提出が必要ですが、ひとつの遺骨につき1枚しか発行されません。
埋葬許可証はコピーでの提出は認められておらず、埋葬許可証なしでの遺骨の埋葬は死体遺棄とみなされてしまいます。
そのため、分骨を行う場合は分骨証明書が必要になります。
分骨証明書もコピーでの提出は認められていないので、分骨を希望する人数分の証明書が必要になります。
火葬前に分骨が予定されている場合は火葬場の職員に分骨の意向を伝えると、分骨証明書を発行してもらえます。
もし火葬場での手続きを忘れた場合は、地方自治体の役所で分骨証明書を取得でき、紛失してしまった場合も、自治体の役所で再発行することが可能です。
既にお墓に納骨した後で分骨を行いたい場合には、墓地の管理者に相談し立会いのもとで遺骨を取り出し、分骨証明書を発行してもらいます。
散骨を行う場合
散骨を行う際には、公的機関への書類申請や手続きは法律で義務付けられていません。
ただし、散骨を業者に依頼する場合には埋葬許可証が必要な場合があります。
埋葬許可証の提示がない場合、事件性の疑いがある可能性が否定できないと判断され、散骨が拒否されることがあるからです。
また、埋葬許可証は散骨後も処分しないことをおすすめします。
埋葬許可証は、故人のご遺骨に関する公的な文書です。
ご遺骨の一部を納骨する場合や、少量の遺骨を手元に保管したい場合には、埋葬許可証を大切に保管しておくようにしてください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
お墓のお引越しに必要な改葬許可証
墓じまいやお墓の引っ越しをする場合、許可なしに移動できません。
そのため、遺骨を埋葬している自治体に「改葬許可申請書」を提出し「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。
また改葬許可証は、遺骨ごとに申請書を記入する必要があります。
お墓に先祖の遺骨が複数ある場合は、遺骨の数に合わせて申請してください。
納骨までの流れ
納骨を行う際には、以下の手順に従って進めることが一般的です。
納骨時期の決定
まず、納骨の時期を決めます。これは寺院や家族、親族との相談によって決定されます。
日本においては「死後〇年以内に納骨しなければならない」といった法律は存在しないため、納骨は任意のタイミングで行うことが可能です。
石材店への連絡
次に、石材店へ連絡を行います。お墓に新たに文字を入れる場合や、お墓のタイプによっては納骨室を開けるために石材店の協力が必要になることがあります。
このため、納骨に関する詳細や必要な手続きについても事前に相談しておくと良いでしょう。
納骨の実施
納骨当日には、埋葬許可証や墓地使用許可書、印鑑などの必要書類を準備します。
これらの書類は納骨をスムーズに行うために必要となりますので、事前に墓地管理者に確認し、準備しておくことが大切です。
これらの手順に沿って納骨を行うことで、故人を敬うとともに、遺族としての責任を果たすことができます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬の流れ
火葬の流れをご紹介します。
火葬場の予約方法
火葬場の予約は、葬儀の計画を立てる際の最初のステップとなります。
亡くなった直後に、まずは火葬場の空き状況を確認します。
これは、火葬場が限られている地域では特に重要で、葬儀の日程は火葬場の利用可能日に基づいて決定されることが一般的です。
空き状況を確認し、適切な日程で火葬場を予約することが必須となります。
火葬当日の手続き
火葬当日には、事前に役場で受け取った火葬許可証を忘れずに火葬場へ持参します。
この許可証は火葬を行うための必須書類であり、火葬場の管理事務所に提出します。
火葬が完了し、遺骨を収めた後には、火葬許可証に「火葬執行済」の印が押され、これをもって正式な手続きが完了します。
遺骨とともに許可証を受け取ることを忘れないようにしてください。
これらの手順を正しく実行することで、故人に対する最後の責任を果たすことができます。
火葬許可証の取り扱いに注意し、葬儀業者や火葬場の指示に従って、手続きを進めましょう。
出棺・火葬場への移動
葬儀が終了すると、出棺の時間が訪れます。
故人を最終的な安息の地へと運ぶため、棺を霊柩車に載せ、火葬場へと移動します。
この際、棺を霊柩車まで運ぶためには6名の担ぎ手が必要となり、故人と親しかった家族や友人にこの役割をお願いするのが一般的です。
霊柩車の移動に際しては、遺影を持った方が助手席に座り、位牌も忘れずに携帯します。
納めの式
火葬場に到着したら、火葬の前に納めの式を行います。
この儀式は、棺が炉の前に到着した時に実施され、焼香を伴います。
僧侶が同行している場合は、読経が行われ、参列者は一人ずつ焼香をします。
この時、喪主が最初に焼香し、その後遺族や親族が続きます。
精進落とし
火葬中には、精進落としの食事が提供されることがあります。
これは火葬後に行われることが伝統的ですが、現代では火葬の間に行うケースも増えています。
精進落としは、火葬の疲れを癒やし、故人を偲ぶ時間として、参列者や僧侶への感謝を表す機会となります。
お酒も提供されることがありますが、飲み過ぎに注意し、故人を偲ぶ静かな時間を過ごしましょう。
骨上げ
火葬が終了すると、骨上げの儀式が行われます。
通常、2名一組で遺骨を丁寧に骨壺に納めます。最初に骨を拾うのは喪主で、その後は家族や親族が血縁の順に参加します。
地域や宗教によって順番に違いがあるため、葬儀社のスタッフの指示に従うことが大切です。
骨上げは、故人との最後の身体的な接触となるため、深い敬意を持って行われます。
これらのステップを踏むことで、故人への最後の送りとしての火葬式が完結します。
適切な準備と尊重をもってこれらの儀式を行うことが、故人への敬意となります。
スポンサーリンクよくある質問
火葬許可証あるいは埋葬許可証についてのよくある質問に答えていきます。
火葬許可証の取得と再発行の方法は?
火葬許可証は、地方自治体の役所窓口で受け取ることができます。
多くの場合、死亡届を提出した際に窓口から直接渡され、自治体によっては死亡届が受理されると同時に発行されます。
また、一部の市区町村では公式ホームページからダウンロードすることも可能です。
火葬許可証の再発行が必要な場合は、死亡届を提出した役所でのみ行うことができます。
再発行を希望する場合は、故人の戸籍謄本に記載されている「死亡事項」から、該当する役所を特定してください。
埋葬許可証はどこでもらえますか?
埋葬許可証は、通常は火葬場で発行されます。
市区町村役場が運営する火葬場では、役場で発行されることもあります。
埋葬許可証には「火葬埋葬許可証」や「死亡届・火葬許可証」と記載されることがありますが、火葬を実施したことを認める認印があれば、埋葬許可証としての効力を持ちます。
火葬許可証は納骨後に返却されますか?
はい、火葬が完了し遺骨を骨壺に納めた後、火葬場の管理者は火葬許可証に「火葬済み」の印を押し、それを遺族に返却します。
この「火葬済み」の印が押された火葬許可証は、その後の埋葬許可証としての役割を果たします。
そのため、遺骨を墓地や納骨堂に納骨する際には、この捺印された火葬許可証を持参する必要があります。
適切な手続きを経て遺骨を納骨することで、故人を慎重に供養することができます。
埋葬許可証の保管期間はどのくらいですか?
「墓地、埋葬等に関する法律」では、埋葬許可証を受理した日から5年間保存するように記述されています。
埋葬許可証は誰に渡しますか?
埋葬許可証は、墓地や霊園、納骨堂の管理者に渡します。
散骨の場合は、散骨を依頼した業者から埋葬許可証の提出を要求されることがあります。
納骨を行う時に、骨壺と共に許可証を忘れずに持って行くようにしてください。
海洋散骨の際、埋葬許可証は必要ですか?
法律上、海洋散骨を行う場合に埋葬許可証の提出は必ずしも必要ではありません。
なぜなら、埋葬許可証は主に遺骨を墓地に埋葬する際に求められる書類であり、海洋散骨はその範囲に含まれないからです。
しかし、実際には海洋散骨を実施する業者の中には、事件性のないことを証明するために埋葬許可証の確認や提出を要求する場合があります。
そのため、海洋散骨を予定している場合でも、埋葬許可証を大切に保管しておくことが推奨されます。
特に、散骨後にも遺骨の一部を手元に残す予定がある場合や、将来的に納骨を検討している場合は、埋葬許可証が必要になる可能性があるため、手元に保持しておくと安心です。
海洋散骨の計画を進める際には、この点を念頭に置き、必要な書類を確実に準備しておくことが大切です。
火葬証明書と火葬許可証はどう違いますか?
火葬証明書と火葬許可証は、共に納骨の際に必要とされる重要な書類ですが、その発行目的と取得方法には明確な違いがあります。
これらの違いを理解することは、火葬に関わる手続きをスムーズに進めるために不可欠です。
火葬証明書は、火葬が行われた証明として発行される書類です。
具体的には、火葬許可証を紛失した場合に、火葬場または役所で発行を受けることができます。
この書類は、火葬が正式に行われたことを証明する重要な役割を果たします。
一方、火葬許可証は、死亡届を提出した際に、火葬を行うために役所から発行される書類です。
火葬場で火葬が完了した後、火葬済みの押印を受けることで、火葬証明書や埋葬許可証と同様の機能を果たします。
万が一、この書類を紛失しても、発行から5年以内であれば再発行を受けることが可能です。
これら二つの書類は、それぞれが独立した目的と機能を持っており、火葬に関する手続きを適切に進めるためには、その違いを正確に理解しておくことが重要です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬許可証・埋葬許可証のまとめ

ここまで、火葬許可証と埋葬許可証の情報や、発行方法を中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 火葬許可証と埋葬許可証は、もともと同じ書類
- 火葬後に「火葬済み」の印が押されたものが埋葬許可証という
- 火葬許可証の再発行は、5年未満か5年以降で条件が異なる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
スポンサーリンク都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
お葬式の関連記事
火葬

更新日:2022.05.11
火葬場で挨拶は必要?喪主の挨拶の注意点と文例を解説
お葬式

更新日:2024.01.24
火葬式(直葬)時の服装は?他葬儀との違いや持ち物のマナーも解説
お葬式

更新日:2024.01.24
火葬の歴史はいつから?日本の火葬の歴史や火葬の法律、火葬に必要な手続きも紹介
お葬式
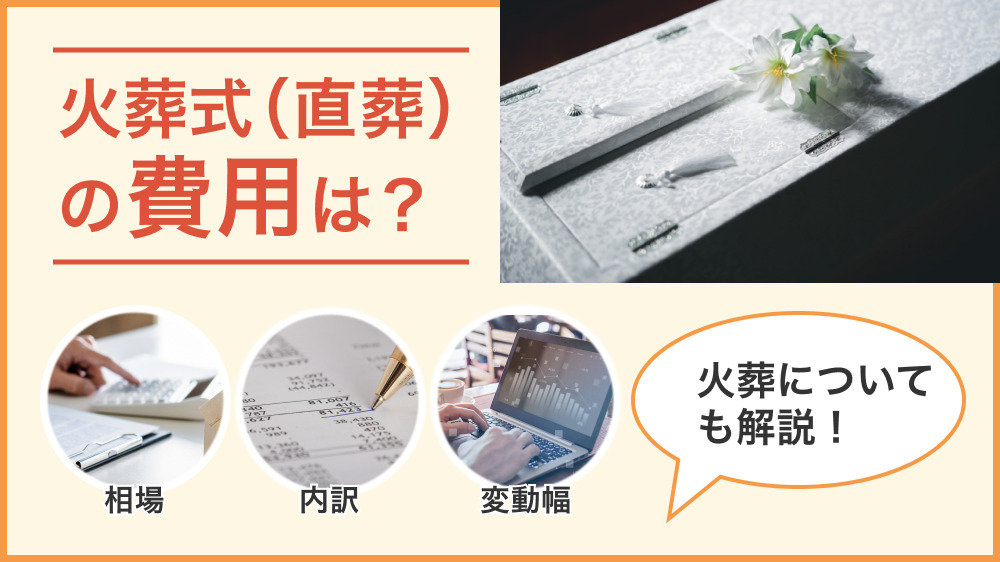
更新日:2025.06.29
葬式なしの火葬費用の相場は?直葬・火葬式の費用を抑える方法についても併せて解説





