お葬式
火葬の流れやマナーは?火葬場の費用や持ち物についても解説
更新日:2024.01.24 公開日:2022.05.22

記事のポイントを先取り!
- 葬儀後に火葬するのが一般的
- 火葬前には納めの式を行う
- 火葬には火葬許可証が必要
- 民営火葬場は5万円〜10万円が相場
日本では現在、亡くなるとほとんどの人が火葬を行いますが、火葬の流れやマナーについてはご存じでしょうか。
スムーズに手続きを行うためにも、火葬について知っておきましょう。
そこでこの記事では、火葬のマナーや流れについて詳しく説明していきます。
この機会に、火葬場の費用や持ち物についても覚えておきましょう。
火葬場の仕組みについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 火葬とは
- 火葬に参列する人
- 火葬を行うタイミング
- 火葬の流れ
- 火葬に必要な持ち物
- 火葬にかかる費用相場
- 火葬に必要な書類や手続き
- 火葬のマナー
- 火葬場の仕組み
- 台車式のメリット・デメリット
- ロストル式のメリット・デメリット
- 火葬についてのまとめ
火葬とは
火葬とは、現在の日本において代表的な葬法の1つで、ご遺体を焼却して残ったご遺骨を弔う方法です。
残ったご遺骨は火葬後に骨上げの儀式を行い、骨壷に納められます。
日本では、亡くなるとそのほとんどが火葬されます。
日本で火葬が主流になったのには、どういった背景があるのでしょうか。
日本の火葬率は99.9%以上
ご遺体の弔い方法は、宗教や地域、文化によって異なります。
例えば欧米ではほとんどの方がキリスト教徒であり、多くは土葬されます。
一方で日本では、火葬を選択するケースがほとんどです。
日本でも土葬は認められていますが、自治体の条例によっては土葬禁止地域を定めていることが多く、土葬の許可が下りにくい現状があります。
日本は、国土が非常に狭い割に人口が多い国です。
火葬をすることで限られた土地を有効利用できるうえ、衛生面から見ても安全性が高いため、火葬が主流になっていると考えられるでしょう。
日本における火葬の割合は、今では99.9%以上にも上っています。
火葬が日本で主流になった背景
火葬が一般的になったのは比較的新しく、明治時代以降といわれています。
それ以前の日本では、貴族や公家などの身分が高い人のみが火葬されていました。
一方で庶民は火葬されずに土葬されることが、この時代では一般的だったようです。
しかし伝染病の流行により、明治30年に伝染病予防法で都市部の土葬が禁止されました。
この法令が制定されたことで、火葬炉が作られることになったのが火葬の始まりだとされています。
衛生面から見ても火葬は安全性が高く、日本の国土環境にもマッチしたことで広く普及することとなったようです。
火葬に参列する人
葬儀や告別式が終了すると、花を入れた棺に蓋をして火葬場へ出棺することになります。
火葬場に参列するのは、葬儀や告別式に参列した人全員ではなく、喪主や親族、親しかった友人など、故人と関係が深かった人たちのみです。
その他の参列者は葬儀会場にて出棺のお見送りをして、そこで解散となります。
どうしても火葬場に同行したい方は、事前に遺族に確認して了承を得る必要があります。
なお、火葬場へ移動する際は、位牌を持った喪主が霊柩車に乗りますが、定員によってはその他の親族も同乗することがあります。
それ以外の方々は、用意されていたマイクロバスなどで火葬場へ移動することが一般的です。
地域によって火葬場へ行く人や霊柩車の同乗者は異なるので、詳しくは周囲の方に確認することをおすすめします。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬を行うタイミング
火葬は、どのタイミングで行うのでしょうか。
ここでは、火葬を行うタイミングについて紹介していきます。
葬儀・告別式の後が一般的
火葬を行うタイミングは地域によって異なりますが、葬儀や告別式の後が最も一般的です。
これを「後火葬」と呼びます。
亡くなられた翌日の夕方からお通夜を行い、その次の日の午前中に葬儀や告別式を行った後火葬するのが基本的な流れになります。
地域によっては通夜や葬儀の前に行う
地域によっては、お通夜や葬儀の前に火葬をすることがあります。
これを「前火葬」や「骨葬」と呼び、このような場合ではご遺骨を祭壇に置いて供養することになります。
この風習は、主に東北地方などでよく見られます。
雪深いこの地域では交通が発達していなかった頃、親族が亡くなってもすぐに駆けつけることが難しい状況でした。
親族が集まるのを待っている間にご遺体の腐敗が進んでしまうため、先に火葬してから葬儀や告別式を行うことが通例となったようです。
この名残から、現在も地域によっては前火葬が行われています。
死後24時間以上経過しないと火葬できない
日本では法律で、死亡後24時間以内は火葬できないことが定められています。
昔は現代のように医療技術が進んでいなかったため、死亡の診断が的確ではなく、中には死亡の診断をした後に蘇生するケースもありました。
そのため、確実に死亡が確認できる24時間が経過してから火葬を行うことが定められたのです。
ただし、指定された感染症で亡くなられた方や、妊娠7カ月に満たない死産の場合にはこの法律は当てはまりません。
火葬の流れ

次に、一般的な火葬の流れについて紹介していきます。
スムーズに手続きを行うためにも、火葬の流れについて知っておきましょう。
出棺
葬儀や告別式を終えると、葬儀会場から火葬場までご遺体を搬送するために出棺をします。
出棺の際には、遺族や葬儀社のスタッフ6〜8人で棺を担いで、霊柩車や寝台車に乗せます。
地域によっては、故人が自宅に帰ってこないようにといった思いから、足側から乗せる風習があるようです
出棺時には喪主が位牌を持ち、喪主の次に故人と縁が深かった親族が位牌を手にします。
火葬場に同行しない方とはここでお別れになるので、喪主から参列者にお礼のあいさつをして出棺となります。
火葬場へ移動
ご遺体は、霊柩車もしくは寝台車にて火葬場へ搬送されます。
同行する方々はマイクロバスやハイヤー、タクシー、自家用車などで後を追って火葬場へ向かいます。
霊柩車には葬儀社のスタッフや、位牌を手にした喪主が同乗するケースがほとんどです。
また、故人が帰ってこないようにといった願いから、火葬場へ向かう行きと帰りのルートを変えるような風習をもつ地域もあります。
火葬許可証を提出
火葬する際には、市町村役場などの自治体が発行する「火葬許可証」が必要になります。
亡くなった後、死亡届を提出するときに「火葬許可申請書」に記入して一緒に申請するとスムーズです。
火葬許可証がなければ火葬はできないので、失くさないように大切に保管しましょう。
火葬場に到着したら、火葬許可証をスタッフに渡します。
このやりとりは葬儀社が代行してくれることがほとんどのため、葬儀社に最初に火葬許可証を提出する形になることも多いようです。
納めの式
ご遺体を火葬する前には、火葬炉の前で「納めの式」と呼ばれる故人とのお別れの儀式を行います。
火葬炉の前に棺を置いたら、設置されている祭壇の上に持参した位牌や遺影を飾ります。
納めの式の流れについては以下の章にまとめますので、参考にしてください。
納めの式の流れ
1.火葬炉の前に棺が安置されると、線香台が用意されます。
2.僧侶が火葬場に同行している場合には読経が始まります。
※僧侶に対するお布施を忘れないようにしましょう。
3.喪主、遺族、親族、故人の知人・友人の順にお焼香を行います。
4.火葬炉の前で棺の顔部分の窓を開けて最後のお別れをします。
※火葬場によってはお別れ用の別室が設けられているところもあります。
5.合掌しながら、火葬炉に棺を納めるところを参列者全員で見届けます。
6.火葬炉に棺が納められたら、火葬開始となります。
焼香を行わない宗派の場合
次に、焼香を行わない宗派の納めの式について紹介します。
神道は玉串を捧げる
神道では、玉串を捧げます。
玉串案という台の上に神職から受け取った玉串を置き、音を立てない偲手(しのびて)で二礼二拍一礼をします。
火葬場によっては玉串案が用意されているところもあるので、持参する必要がないケースもあります。
念のため、事前に火葬場に確認しておくと安心です。
キリスト教は献花を行う
キリスト教では、献花が行われます。
献花台の上にお花を置き、故人を送り出します。
なお、玉串や献花の際に用いる花は、葬儀社によって用意されているケースが多いようです。
火葬
棺が火葬炉の中に納まると、ご遺体は火葬されます。
火葬の時間は、故人の状態や副葬品などによって変わりますが、40分〜2時間半程度かかるとされています。
火葬が終了するまで親族や参列者は、控室に移動して過ごすことになります。
参列者にお茶やお茶菓子を振る舞いながら、火葬が終わるのを待ちます。
特に、火葬場まで同行していただいた僧侶に対しては、お礼の気持ちを伝えて、手厚くもてなすようにしましょう。
ただし葬儀場によっては、飲食類を持ち込むことが禁止されているところもあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
地域によっては、葬儀場に一旦戻って精進上げをしてから収骨のために火葬場へ戻るといった風習もあるようです。
収骨・骨上げ
火葬終了のアナウンスがあったら、参列者全員で拾骨室に移動します。
ご遺骨を骨壷に移していく際には「骨上げ」と呼ばれる儀式を行います。
二人一組となり、長い箸で1つのお骨を拾い上げ、骨壷へと納めていくのが骨上げの儀式です。
これには、故人が三途の川を無事に渡れるように箸渡し(橋渡し)するといった意味合いがあります。
骨上げするには順番があり、足→腰→胸→背→腕→のど仏→頭と、骨壷の中で立っていることをイメージして納めていきます。
なお、のど仏は故人と最も縁が深かった人が納めることが一般的です。
頭骨を納めたら蓋を閉めて終了となります。
ご遺骨を納めるのにも種類があり、全てのご遺骨を納める「全拾骨」と一部のご遺骨のみを納める「部分拾骨」に分かれます。
地域によってどちらを選択するかは異なります。
東日本は全拾骨、西日本は部分拾骨が多いとされています。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬に必要な持ち物
ここでは、火葬に必要な持ち物について紹介していきます。
必要なものをあらかじめ把握して、当日困らないように準備しておきましょう。
火葬許可証
火葬許可証がないと火葬を行うことができません。
火葬許可証は市区町村役場などの自治体にて発行してもらえるので、事前に準備して当日必ず持参するようにしましょう。
位牌
仏式の場合には位牌を火葬場に持っていくことが一般的です。
位牌には故人の魂が宿るとされているので、故人だと思って丁寧に扱いましょう。
神式では、位牌の代わりになる「霊璽(れいじ)」と呼ばれるものがあります。
位牌とは異なり、霊璽は火葬場へは持参しないので覚えておきましょう。
遺影
遺影は葬儀の際に祭壇に飾られる故人の写真のことです。
位牌と共に火葬場へ持っていくことが一般的です。
火葬にかかる費用相場

火葬には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
民営と公営とでは費用の相場が異なることを知っておきましょう。
民営の火葬場の費用相場
民営の火葬場の費用は公営と比べると高くなる傾向にあり、5万円〜10万円程度が相場です。
内訳としては、火葬料が4万円〜10万円程度、待合室の利用料が2万円程度、骨壷料金が1万円前後となります。
公営の火葬場とは異なり、民営の火葬場は地域やグレードによって金額の差が大きい傾向にあります。
民営であっても公営と同じ程度の金額で利用できるところもあるので、費用の目安を考えて探してみましょう。
公営の火葬場の費用相場
公営の火葬場の費用は、無料〜6万円程度が相場です。
費用の内訳としては、火葬料が無料〜5万円程度となります。
公営の火葬場は市区町村役場などの地方自治体が運営しているので、故人が住民票登録をしていれば、無料で利用できるところもあります。
住民票を登録している自治体以外の火葬場も利用できますが、利用の費用は割高になる傾向にあります。
待合室の使用料は、無料〜1万円程度、骨壷は4,000円前後のケースが多いようです。
火葬にかかる費用内訳
次に、火葬にかかる費用の内訳を解説します。
火葬料
火葬料とは、ご遺体を火葬する際に必要となる費用のことです。
火葬料については、火葬場が公営か民営かでも異なり、故人の年齢によっても費用が前後します。
待合室の使用料
待合室の使用料とは、火葬を待っている間に待合室を使用する際に必要となる費用のことです。
待合室では参列者同士が故人を偲び、団らんして過ごすことが多くなります。
骨壷代
骨壷代とは、ご遺骨を納める骨壷の費用のことです。
骨壷は素材や大きさによって金額が前後します。
中には火葬料に含まれているケースもあります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬に必要な書類や手続き
ここからは、火葬に必要な書類や手続きについて詳しく紹介していきます。
死亡届を死後7日以内に提出する
死亡届と死亡診断書は、セットになっています。
左側が死亡届で、右側が死亡診断書です。
病院から死亡診断書を受け取ったら、死亡届に必要事項を記載して市町村役場に提出します。
この死亡届には提出期限があり、死亡の事実を知ってから7日以内に提出する必要があります。
ただし例外もあり、国外で亡くなられた場合には、死亡の事実を知った日から3カ月以内となっています。
火葬をするには火葬許可証が必要
火葬するときには火葬許可証が必要になります。
市区町村役場に死亡届や死亡診断書を提出するときには火葬許可申請証も一緒に提出して、火葬許可証を発行してもらいましょう。
受け取った際には内容に不備がないか、市区町村役場の押印がきちんとあるかなどを確認しておくと安心です。
火葬後に提出した火葬許可証を受け取る
火葬が終了すると日時が記入され、火葬場の証印が押されて火葬許可証が返却されます。
返却された火葬許可証は埋葬の際に必要となるので、失くさずに大切に保管しましょう。
自治体によってはこの火葬許可証が「埋葬許可証」という名称になっているケースもあります。
最近では、死亡届の提出から火葬許可証の受け取り、火葬場の手配まで葬儀社が代行してくれるケースが多いようです。
火葬のマナー
ここでは、火葬のマナーについて紹介していきます。
失礼のない対応をするためにも、マナーについて知っておきましょう。
火葬場の職員には心付けは渡さない
心付けとは、お礼の気持ちを込めて包むお金のことを指します。
火葬場では送迎バスのドライバーや、火葬炉や控室のスタッフに渡すことが一般的です。
渡す際には不祝儀袋や、シンプルな白い封筒などに包んで渡すと良いでしょう。
公営の火葬場の場合には、公務員に金品を渡したことで賄賂とみなされてしまうリスクがあるので注意が必要です。
民営であったとしても、金銭は受け取らないといった方針の火葬場もあるので、断られた際には無理に渡さずに、お礼の気持ちだけ伝えることをおすすめします。
火葬に同行するには喪主の許可を得る
火葬場へは、誰でも同行できるわけではありません。
一般的には、故人とより関係が深かった方が同行することになります。
もしも同行を希望する場合には、喪主の許可を得るようにしましょう。
直前に申し出ても調整できないケースもあるので、早い段階で喪主に伝えることが大切です。
火葬場での服装
ここでは、火葬場での服装のマナーについてまとめました。
葬儀後に火葬場へ行くことがほとんどのため、基本的に葬儀での服装マナーと同じです。
男性と女性に分けて詳しく説明していきます。
男性の服装のマナー
男性の場合、基本的にはブラックフォーマルやブラックスーツを身に着けていれば問題ありません。
ブラックであっても、サテンなどの光沢のある素材は避けるのがマナーです。
上着はシングル、ダブルのどちらでも大丈夫ですが、パンツの裾はシングルが適しています。
中に着用するワイシャツは白一色のものにし、光沢のある生地やボタンダウンのタイプは避けましょう。
ネクタイは黒一色にし、光る素材のものは避けます。
なお、ネクタイの結び目にくぼみを作るディンプルは、お通夜や葬儀の場ではマナー違反になるので注意が必要です。
基本的にピアスやネックレスなどのアクセサリー類は避けます。
身に着ける場合は、光らないブラックのカフスのみにしましょう。
ベルトや靴も黒にし、ワイシャツ以外は全身を黒一色でコーディネートするのが基本です。
素材としては、スエードやエナメルのものは避け、靴下も黒のものを用意してください。
またバックルが派手なベルトは避け、金具が付いている靴も避けるのが無難です。
子どもや学生は、制服を着用するのが良いでしょう。
靴はローファーでもマナー違反にはなりませんが、成人男性の場合にはローファーはタブーになるので注意してください。
女性の服装のマナー
女性の場合も男性と同様に、ブラックフォーマルやブラックスーツを着用します。
ワンピースやパンツ、スカートなどのタイプがありますが、好きなものを選んで着用して問題ありません。
ジャケットの中にブラウスを着る場合には、白一色のものを選びましょう。
バッグや靴は黒で統一し、光る素材や金具の付いているものは避けるのがマナーです。
ストッキングは肌色のものか、黒であれば30デニール以下の薄いものが適しています。
リブ入りや網タイツ、カラータイツ、柄入りのものは避けましょう。
足元はパンプスなど、シンプルなデザインの布製や革製のものを着用します。
ヒールは3cm程度のものを選び、ヒールが高すぎるものやミュールやサンダルは避けてください。
派手なアクセサリーやネイルはマナー違反です。
急に駆けつけた場合などでネイルを取ることができなかった場合には、手袋を着用するなどして対応しましょう。
なお、パールのネックレスやイヤリングにおいては着けても問題ありません。
真珠のネックレスは、2連のものは「不幸が重なる」とされ縁起が悪いため、1連のものを選択します。
メイクは控えめのナチュラルメイクにし、つけまつげや派手なチーク、グロスは避けましょう。
棺に入れられるのは可燃物
故人を火葬するときには、副葬品として棺の中に故人の思い入れのあった品を一緒に入れて火葬することが多いようです。
ただし、何でも副葬品として棺に入れられるわけではないので注意しましょう。
棺に入れられるのは、基本的に可燃物のみになります。
よく見られるのは、写真や手紙、花などです。
ビニール製のものや革製品は燃えにくく、溶けた際にご遺骨を損傷させる可能性があるので、入れることはできません。
メガネや指輪などのガラス製や金属製のものも不燃物のため、入れられないことがほとんどです。
また、生きている人の写真などを一緒に入れると縁起が悪いとされているので、避けることをおすすめします。
骨壷を保管する場所
火葬後、骨壷は自宅で保管しても問題ありませんが、保管する場所については配慮が必要です。
湿気の高いところで保管するとカビが生えてしまうことがあるので、風通しが良く、直射日光が当たらないところに保管しましょう。
手元供養などで長期間自宅に安置する場合は、骨壷は完全密閉可能な容器を選ぶと安心です。
また、骨壷が大きくてスペースを取り保管場所に困るケースでは、遺骨を細かく粉砕したり、分骨したりなどの対応方法があります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
火葬場の仕組み

火葬場の火葬炉には、台車式とロストル式の2種類があります。
ここでは、火葬場の仕組みについて詳しく紹介していきます。
台車式の仕組み
近年主流となっている火葬炉が台車式です。
普及率は非常に高く、日本では現在約90%以上が台車式を使用しています。
台車式による火葬ではまず、主燃料炉と呼ばれる場所へ台車に乗せた棺を運びます。
その後、バーナーで棺を台車ごと一緒に焼く仕組みになっています。
台車式は火葬炉への出し入れが簡単で、タイヤの数が多いため脱線しにくい特徴があります。
また、台車式火葬炉の多くは、バーナーの設置場所が2層構造となっています。
台車式では、ご遺体の焼却炉と、焼却した際に出るガスを無害にする炉が設置されているのが一般的です。
中には、さらに有害ガスの漏洩を防げる3層構造になっているものもあります。
ちなみに3層構造は、2層構造のものよりも構造が複雑です。
ロストル式の仕組み
ロストル式とは、棺を「ロストル」と呼ばれる格子の上に置いてバーナーで焼いていく仕組みのことです。
ロストルとは、オランダ語で「火格子」といった意味合いがあります。
ロストル式は、棺を置くロストルの下に骨受け皿があるだけのシンプルな構造です。
ロストルには網のようにすき間があいているため、焼いていくうちにご遺骨が骨受け皿に入る仕組みになっています。
台車式のメリット・デメリット
現在主流となっている台車式にはメリットもありますが、デメリットもあります。
以下で詳しく紹介していきます。
台車式のメリット
台車式のメリットとしては以下のことが挙げられます。
- 台車に乗せて火葬するためご遺骨がきれいな状態で残る
- 炉内の熱気や臭気が待機ホールに漏れ出す心配がない
- 不完全燃焼のリスクが小さい
- 前室扉を閉じれば参列者に見られずに副葬品を取り除ける
ご遺骨をきれいな状態に保ちながら火葬できるので、どこの骨なのかがわかりやすい状態で残ります。
遺族からしても、大切な故人のご遺骨がきれいに人型に残っていた方が心の安定につながるでしょう。
また悪臭が少なく、衛生的な面もメリットとされています。
台車式のデメリット
台車式のデメリットとしては以下のことが挙げられます。
- 燃焼時間が長い
- 設備コストが高い
- 燃料のガスや重油によるコストがかかる
台車式はロストル式と比べると構造が複雑なので、その分費用が高くなります。
また、焼却時間も長くかかる傾向にあります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
ロストル式のメリット・デメリット
ロストル式にもメリットとデメリットがあるので紹介しましょう。
ロストル式のメリット
ロストル式のメリットとしては以下のことが挙げられます。
- 設備費用が安く済む
- 燃焼効率が良い
- 火葬時間が短くなる
ロストル式では、ご遺骨の燃焼が終了するまでにかかる時間が非常に短いのがメリットです。
また、シンプルな構造のため、製造する際にかかる費用の負担が非常に少ない点もメリットといえます。
ロストル式のデメリット
ロストル式のメリットとしては以下のことが挙げられます。
- ご遺体の形状が維持できない
- 臭気や熱気が待機ホールに漏れ出す
- 故障したときには火葬炉を止める必要がある
ロストル式ではご遺骨が下に落下する仕組みとなっているので、原形をとどめることが難しくなります。
また、燃焼する際にはご遺体の体液などによって悪臭が発生するため、衛生面の管理が難しいこともデメリットです。
以上のようなデメリットから現在、ロストル式を使用している火葬場は10%未満となっています。
火葬についてのまとめ

ここまで火葬の流れやマナー、費用相場などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 火葬を行うタイミングは、葬儀・告別式後が一般的
- 遺体の火葬前には最後のお別れである「納めの式」を行い、読経・焼香をする
- 火葬するときには「火葬許可証」を葬儀場に提出する必要がある
- 民営の火葬場の費用相場は5万円〜10万円程度
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.11.19
近所の人の出棺の見送りへは行くべき?服装の注意点は?
お葬式
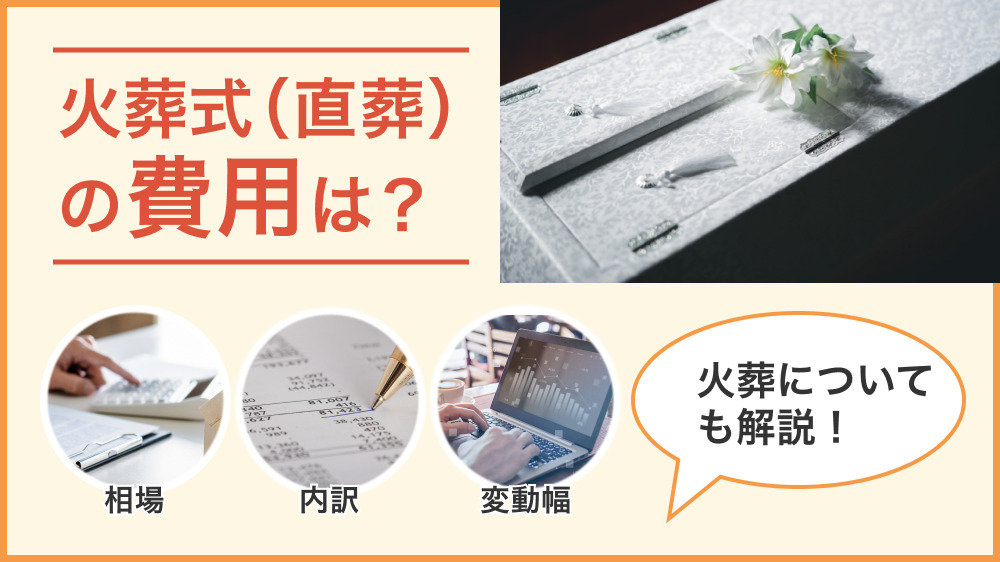
更新日:2025.06.29
葬式なしの火葬費用の相場は?直葬・火葬式の費用を抑える方法についても併せて解説
お葬式

更新日:2024.01.24
火葬の時にピンク色の遺骨があるのはなぜ?収骨拒否についても解説
火葬

更新日:2022.05.11
火葬場で挨拶は必要?喪主の挨拶の注意点と文例を解説
お葬式

更新日:2024.04.02
火葬許可証と埋葬許可証の違いは?紛失した時の再発行の仕方なども紹介
お葬式

更新日:2024.03.13
火葬とは?火葬にかかる費用や時間、流れや仕組みなど解説





