お葬式
故人の凍結口座の払い戻し方法は?医療費の払い戻しまで解説
更新日:2024.01.23 公開日:2021.10.11

記事のポイントを先取り!
- 金融機関に死亡を伝えると故人の口座は凍結される
- 書類を揃えれば医療費の払い戻しが行える
- 申請後、自治体から葬祭費と埋葬料の支給がある
高額な葬儀費用の捻出に悩む遺族の方は多いと思います。
そのような場合に、故人の口座から葬儀費用が引き出せる「相続預金の払い戻し制度」はご存じでしょうか。
故人の逝去後に凍結される口座から、預金を払い戻すことで葬儀費用を補填できます。
そこでこの記事では、相続預金の払い戻し制度の内容や手続きに必要な書類、故人の存命中にかかった高額な医療費の払い戻し制度について解説します。
葬儀費用の捻出に困らないように、生前に利用できる葬儀保険や互助会についても紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
葬儀費用の相場

葬儀費用の相場は、208万円といわれており高額です。
火葬場や式場使用料、スタッフの人件費などのお葬式費用の相場が119万円、飲食接待費用相場が31万円、返礼品費用相場が34万円、お布施などの寺院に支払う費用相場が24万円になっています。
参列者の人数や戒名のランク、通夜の有無や、火葬のみの直葬・火葬式を選択する場合など希望するお葬式の内容によって葬儀費用は変動します。
しかし、相場よりも抑えることができても、経済状況によっては葬儀費用の捻出は遺族の悩みのひとつになります。
そのため、遺族の資産だけでなく、故人の預貯金の口座から払い戻しを行い葬儀費用を捻出する方法や、葬儀後に利用できる補助金の制度の知識が大切です。
遺産分割前の相続預金の払い戻し制度
故人名義の口座がある金融機関に、故人の死亡を伝えると口座は凍結され、葬儀費用を引き出すことができなくなります。
凍結された口座は遺産分割が終了するまで利用できませんが「相続預金の払い戻し制度」の手続きをすると、故人の口座から葬儀費用のための金額を払い戻すことが可能です。
以下で、払い戻しができる金額や必要な書類、口座凍結前に預金を引き出した場合のリスクをご紹介します。
払い戻しができる金額
相続預金の払い戻し制度を利用して、単独で払い戻しができる金額は「相続開始時の口座残高×1/3×払い戻しをする法定相続人の相続分」になります。
ただし、払い戻しができる金額には上限があり、同一の金融機関で150万円までです。
葬儀費用の平均相場が208万円であることを考えると、払い戻しができる金額で葬儀費用を全額賄うことは難しいですが、補填することは可能です。
口座の凍結や故人の資産について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
亡くなった人の口座凍結や遺族年金の相続|故人の資産の取扱いについて
払い戻しに必要な書類
相続預金の払戻し制度に必要な書類は以下の通りです。
- 故人の出生から死亡までを記録した除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 払い戻しを希望する相続人の印鑑証明
上記の書類を故人の口座がある金融機関に提出しますが、金融機関によって必要な書類が異なる可能性があるため、事前に確認しておくと手続きがスムーズに進められます。
口座凍結前に葬儀費用を引き出さない
相続預金の払い戻し制度を利用すると、凍結後の口座から葬儀費用を引き出せますが、手続きが面倒で、凍結前に預金を引き出したいと考える方もいると思います。
しかし、故人名義の口座が凍結する前に預金を引き出してから、金融機関に故人の死亡を連絡すると、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。
相続は預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、相続放棄ができなくなると困る場合があります。
相続放棄ができない以外にも、他の相続人とトラブルになる可能性もあるため、葬儀費用を故人の口座から引き出す場合は、故人の存命中に行うと良いでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
医療費の払い戻し

葬儀費用は高額なため、故人の逝去後でも払い戻しができる金額があれば、手続きをすることをおすすめします。
以下で、故人の逝去後に払い戻しが可能な医療費について説明するので、参考にしてください。
高額療養費制度
故人が病気で亡くなった場合、長期間の入院による高額な医療費を払い戻せる「高額療養費制度」があります。
医療費は毎月1日から末日までの1ヶ月間で負担額が決まっており、上限を超えた場合に払い戻しが可能です。
年齢や所得ごとに限度額は異なりますが、故人の逝去後も請求ができ、時効は2年です。
本来は、故人が生前に受け取る金額のため、相続税の対象になりますが、払い戻しが可能な費用のひとつとして覚えておくと良いでしょう。
払い戻しの対象
高額療養費制度は、国民健康保険や後期高齢者医療制度、各種健康保険の加入者が対象です。
払い戻しの金額は、健康保険が適用される医療費のため、治療費と入院基本料のみが対象です。
入院中の食事や個室を希望した場合の差額ベッド代、テレビ視聴カードや入浴セットなどの消耗品代は含まれません。
故人が70歳以上であった場合、医療費の自己負担限度額は低額のため、払い戻しの対象になる可能性が高くなります。
払い戻しの対象か不明の場合は、各自治体に相談することをおすすめします。
高額療養費の申請方法
高額療養費の申請は各自治体や健康保険組合で行います。
必要な書類は以下の通りです。
- 高額療養費支給申請書
- 医療費の領収書など
- 故人との関係が記載された戸籍謄本など
- 本人確認書類(身分証明書やマイナンバーカードなど)
- 相続人全員の印鑑証明
必要書類は申請先の自治体や健康保険組合によって異なるため、事前に問い合わせてから手続きをすると良いでしょう。
また、相続税が関わってきて不安がある場合は、委任状があれば専門家が代行することも可能なため相談することをおすすめします。
生前に葬儀費用を準備する方法

葬儀費用の捻出に悩む遺族の方は多いと思います。
万が一に備えて、生前から葬儀費用を準備する方法に、葬儀保険や互助会を利用する方法があります。
以下で、それぞれの内容と注意点をご紹介します。
葬儀保険に加入する
葬儀保険とは、葬儀代を保険金で補う目的の保険で、少額短期保険に含まれます。
生命保険よりも保険料が安く、加入時に医師の診断書が不要という手軽さが最大の魅力です。
また、加入できる年齢の範囲が広く保険金が早く支払われるため、葬儀費用が急遽必要になった場合に対応できる保険になっています。
葬儀保険の注意点
葬儀保険に入るときは、加入時の年齢が高いほど保険料も高額になります。
長期間の加入の場合ですと他の方法と比べて高くなってしまう可能性がありますが、他の保険に比べて保険料が少なめとなっています。
期間や年齢によってプランが異なるため、よく確認するとよいでしょう。
しかし、掛捨型の保険なので解約返戻金がないことや、保険加入後は一定期間は保障されないといったデメリットがあります。
互助会を利用する
互助会とは民間の保険サービスで正式名称は冠婚葬祭互助会といいます。
互助会の大半が毎月2,000円程度の少額からでも入会できます。
持病がある方や高齢者の方、年金で生活している方も問題なく積み立て可能です。
積み立ての途中で契約者が逝去した場合でも、残額を納めることで互助会のサービスを受けられます。
また、加入したときの契約が何年後も保証されていることも魅力の1つです。
互助会によっては映画鑑賞や観劇、旅行券のサービスがある場合があります。
互助会の加入は冠婚葬祭などに向けての積み立てが目的です。
ただ、その他のポイントも確認してお得に使いましょう。
互助会の注意点
互助会を利用する際は葬儀の規模や料金に気をつけましょう。
規模が大きすぎると互助会の払い戻しでは不足してしまいます。
逆に小さい規模の葬儀を行っても余分な費用が返ってくるわけではありません。
ですので小規模の葬儀を行う場合は互助会の利用は損をしてしまう可能性があります。
また、互助会は解約手数料の発生や指定された葬儀場しか使えないといったデメリットがあります。
互助会で積み立てをしていることを家族が知らずに指定されていない葬儀社で葬儀を行ってしまうケースもあるそうです。
その場合でも掛金は返ってこないので、互助会への入会は家族に知らせておきましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
生前贈与の注意点
故人が長くはないと悟った時に、葬儀代や手続きの負担、相続税を心配して生前に生前贈与の提案をするケースも少なくありません。
しかし、金額に注意する必要があります。
贈与税の基本控除額は1年間で110万円と決められていて、超えてしまうと申請の必要が発生するからです。
数年に分けて贈与、または贈与する人数を増やす等の工夫することで税金がかからずに済みます。
葬儀後に申請できる給付金
葬儀社に支払った葬儀費用が払い戻されることはありませんが、葬儀後に喪主が自治体などに申請することで支給される給付金があります。
以下で、葬祭費と埋葬料について説明します。
葬祭費
葬祭費とは、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた故人の葬儀を執り行った喪主が申請すると支給される給付金です。
支給される金額は自治体によって異なりますが、基本的には3万〜5万円が支給されます。
申請には、本人確認書類や振り込みの口座以外に、葬儀費用が分かる領収書などが必要なため失くさないようにしましょう。
申請期限は2年となっています。
埋葬料
故人が生前に会社に勤めており、協会けんぽの健康保険に加入していた場合は、故人の埋葬をした方に埋葬料として5万円が支給されます。
埋葬料が申請できるのは、故人に生計を維持されていた方が対象で、それ以外の方が故人の埋葬をした場合は「埋葬費」が支給されます。
埋葬費は、実際に埋葬にかかった費用である、霊柩車などで遺体の運搬にかかった費用、霊前供物代、火葬の費用、僧侶の謝礼などが5万円の範囲内で支払われます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀費用の払い戻しまとめ

ここまで葬儀費用の払い戻しの方法や注意点を中心に書いてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 故人の預金を葬儀費用に充てる際は相続預金の払戻し制度を利用する
- 故人の死亡後も自己負担額を超えた医療費の払い戻しが可能
- 生前に葬儀費用を準備するには葬儀保険や互助会を検討する
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2025.06.17
互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説
お葬式

更新日:2024.01.10
合同葬とは?社葬や一般葬との違いや相場、マナーについて解説
お葬式

更新日:2023.10.20
湯灌(湯かん)は何をするの?湯灌の目的や費用相場なども紹介
お葬式
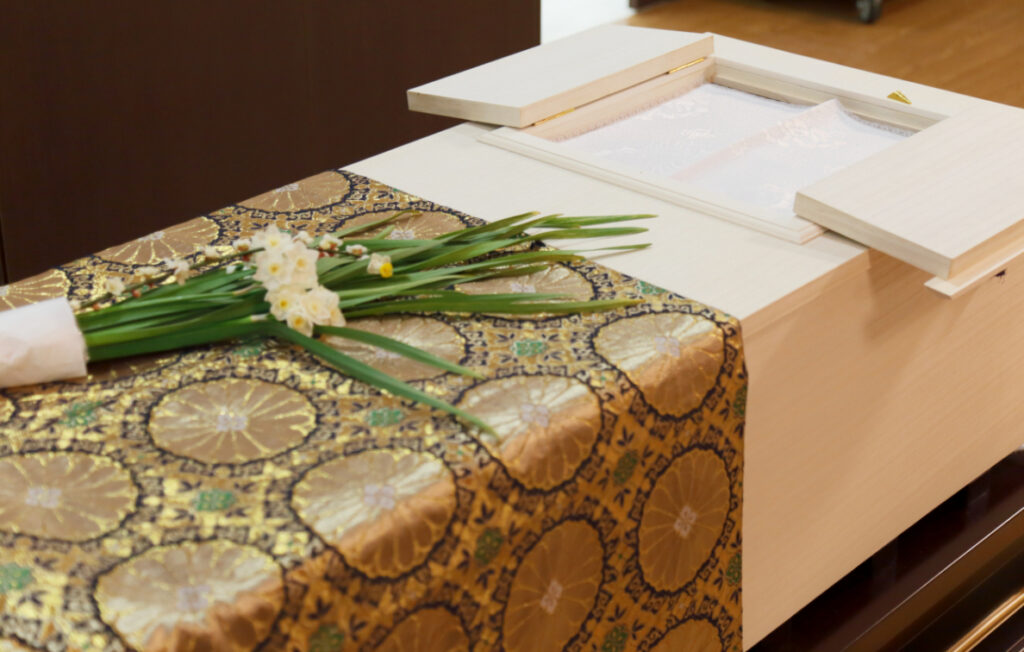
更新日:2024.02.03
遺体搬送車とは?遺体搬送車の車種や霊柩車との違い、搬送料金についても解説
お葬式

更新日:2023.11.12
霊柩車の利用料金は?霊柩車の値段や霊柩車の種類、車種についても解説






