お葬式
孤独死とは?発見から葬儀までの流れや費用、これからできる対策についても解説
更新日:2025.06.17 公開日:2021.07.04
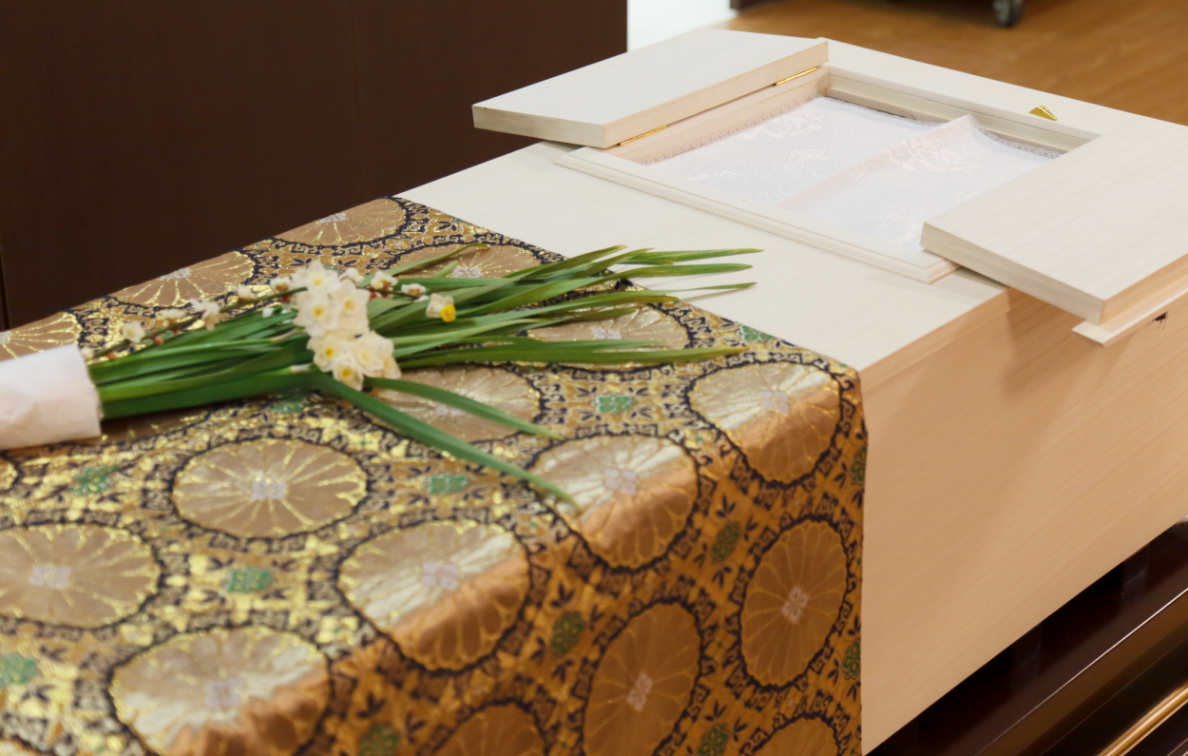
記事のポイントを先取り!
- 遺族がいる場合、遺族が遺体を引き取り葬儀・埋葬を行う
- 遺族がいない場合、葬儀費用は自治体が負担する
- 自治体で火葬した場合、一定期間遺骨を保管した後に無縁墓に納骨される
孤独死とは、誰にも看取られることなく一人で亡くなることを指しますが、高齢化や核家族化が進んでいる近年では、孤独死の割合も増加傾向にあります。
万が一孤独死した場合、遺体の発見から葬儀の手続きの流れはご存じでしょうか。
この記事では、孤独死を発見した場合の流れや、孤独死した場合の葬儀を遺族がいる場合といない場合に分けて説明しています。
孤独死の葬儀後の手続きや、身寄りがない場合の生前準備についても紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 孤独死とは
- 孤独死を発見した際の流れ
- 遺族がいる孤独死の葬儀
- 遺族がいない孤独死の葬儀
- 孤独死した故人が生活保護受給者だった場合
- 活用できる葬儀費用の補助金制度
- 孤独死を避けるために今からできること
- 身寄りがない方が生前にやっておくべき準備
- 孤独死の葬儀後にする手続き
- 孤独死のよくある質問
- 孤独死の葬儀についてのまとめ
孤独死とは

孤独死は、平成24年の内閣府の「高齢者の健康に関する意識調査」において、誰にも看取られず亡くなったあとに発見される死と定義されています。
以下で、孤独死に似た孤立死との違いや、高齢者の独居世帯の増加についてご紹介します。
孤独死と孤立死の違い
孤独死と同じく、誰にも看取られずに1人で亡くなることを指す言葉に「孤立死」があります。
孤独死と孤立死の違いは、社会との関わりがあったかどうかになります。
孤独死は家族や親族、友人との交流が普段からある状態でありながら、さまざまな要因が重なって自宅などで1人で亡くなってしまうことを指します。
一方で、孤立死は他者との交流がなく、自宅で1人で亡くなることを指しているため、死後長期間放置されてしまう可能性が高くなっています。
高齢者の独居世帯は増え続けている
2013年のデータによれば、全体の世帯数の中で65歳以上の単身高齢者が占める割合は、33年前から比べると約6倍に拡大しています。
高齢者の独居世帯の増加は、必ずしも家族がいないからというわけではなく、さまざまな事情で単身で生活している人たちが増えていることを示唆しています。
65歳以上の単身で生活している高齢者の増加が、誰にも看取られずに1人で亡くなる孤独死が増加している背景となっている側面も否めません。
孤独死を発見した際の流れ

孤独死は何らかの要因で、自宅などで1人で亡くなってしまうため、事件性がないか警察による現場検証が必要になります。
そのため、家族に看取られながら亡くなる場合とは流れが異なります。
以下で孤独死が発見されてからの流れを説明します。
孤独死を発見した場合
亡くなった人の腐敗臭から近所の人が気付いたり、家族が訪問したことがきっかけで孤独死の遺体が発見されることが多いです。
発見者は、亡くなっているかどうか分からない時は救急車を、あきらかに亡くなっている場合は警察に連絡します。
警察が到着すると、すぐに検死と現場検証が行われます。
警察による現場検証
孤独死の死因に事件性がないかを調べるために、警察による現場検証が行われます。
この時すべての金品は押収され、誰も現場の家に入ることは出来ません。
現場検証の結果、病気が原因の死亡と判断された場合には、かかりつけ医から死亡診断書が発行されますが、事故などの可能性がある場合は警察が検視のために遺体を引き取ります。
検視は、原則として遺族であっても拒否できません。
警察による検視
警察による検視が行われると、死体検案書を作成するまでは遺体を引き取ることができません。
検視の結果、事件性がないと判断された場合は、医師が死因や死後経過時間を判断し、死体検案書が作成されます。
死体検案書は死亡診断書と同様の役割を持つ書類なので、役所へ提出すると埋火葬許可証が発行され葬儀が行えます。
しかし、事件性があると判断された場合は司法解剖となり、事件性はないものの死因がはっきりしない場合は行政解剖となります。
孤独死が発見されてから遺体を引き取るまでには、事件性がない場合で半日から数日程度、検視が行われる場合は10日~2週間程度かかります。
遺体の損傷が激しいなどで身元の確認ができず、DNA鑑定によって個人を特定する場合は、1カ月程度引き取ることができないこともあります。
検視が終了すると遺族に連絡が行き、遺体を安置施設に移す必要があるため、検視が行われている間に葬儀社を決めておくと引き取りから葬儀までスムーズに行えます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
遺族がいる孤独死の葬儀
孤独死した故人に遺族がいる場合、遺体を引き取った後の葬儀は通常と同じ流れで行われますが、警察から遺体を引き取るまでに手続きが必要です。
以下で、警察から連絡を受けてからの手続きを説明します。
警察署で説明を受ける
身内が孤独死したという警察署からの連絡を受けたら、管轄する警察署へ出向き、死亡時の状況などについて説明を受けます。
身元確認時や遺体の引き取り時に必要となる「身分証明書と印鑑」を持参することを忘れないようにし、故人の身分証明書が手元にあれば持っていきます。
故人との関係性が分かる戸籍謄本や住民票も取っておけば、手続きがスムーズになります。
警察署で身元確認する時は、遺体は霊安室に安置されています。
霊安室は、遺体の腐敗を防ぐために室温を低く設定していますので、防寒着を用意しておいた方がいいでしょう。
スマホはバッテリーを充電しておき、充電器を持っていくことをおすすめします。
警察からの連絡が突然入って来るだけでなく、遺体を引き取った後には、親族への連絡、葬儀社の選定や依頼、特殊清掃業者への依頼など、スマホが必要な場面が多くなるからです。
自宅から現地まで長距離の場所にある時には、着替えだけでなく、必要に応じて喪服も用意しておけば、現地での葬儀や火葬にも対応できます。
遺体引き取り時にかかる費用
孤独死によって警察が遺体の搬送や保管、行政解剖などを行った場合の費用は、遺族が負担することになります。
孤独死した現場から警察署や解剖場所まで搬送した場合の搬送費用は、搬送距離で料金が変わり10㎞までは1万2,000円〜2万円といわれています。
警察が解剖が必要だと判断した場合に行われる司法解剖の費用は国が負担しますが、孤独死の死因を究明する行政解剖は8万円〜12万円が相場になっています。
さらに、遺体保管料が1日あたり2,000円×日数と死体検案書の発行料が5,000円〜1万円ほどかかります。
ただし、これらの費用はあくまで目安で自治体によって金額は前後します。
葬儀の打合せ
遺体が引き渡されるまでの間に、葬儀をどのような形で行うかを決め、葬儀社との打ち合わせをしておきたいです。
孤独死であっても、喪主を決めて葬儀を行うという一般的な流れは同じですが、通夜・告別式を行うか、火葬だけの直葬にするかは遺族の判断に委ねられます。
火葬については、故人の住民票がある自治体で行うのが一般的で、他の地域で火葬する場合には搬送料がかかりますので、注意してください。
葬儀社によっては、孤独死の葬儀を断る事業者もありますので、トラブルにならないよう最初の段階で孤独死であることを伝えておく必要があります。
特別清掃の専門業者の選定
孤独死した家族の発見が遅れた場合、腐敗臭や害虫の問題などが発生している可能性があります。
そのような場合、通常の清掃業者では部屋の原状回復をするのは困難な場合が多いため「特殊清掃業者」に依頼します。
特別清掃業者は、孤独死の現場を人が再び住める状態に復旧させるための技術やノウハウを持っています。
そのため、孤独死の発見が遅れた場合は、葬儀の手続きだけでなく特別清掃業者の選定も考慮に入れることをおすすめします。
遺族がいない孤独死の葬儀
孤立死して、身元が不明な場合は自治体にて火葬を行い、遺骨は自治体にて保管されます。
保管期間は自治体によりますが大抵は5年ほどで、保管中に遺族を探し、遺族がいない場合は身寄りのない方たちの埋葬される無縁墓に納骨されます。
多くの身寄りのない方たちの骨と一緒に埋葬されるので、その後に遺族が見つかっても骨を取り出すことは出来ません。
一方、故人が遺族はいなくても近隣住民と親しかった場合は、遺族の代わりに近隣住民が葬儀、埋葬をするケースもあります。
葬儀費用は一時的に近隣住民が負担しますが、後ほど相続管理人から返却されます。
相続管理人とは家庭裁判所が、検察官や故人の大家さんなどから請求を受けて、故人の財産を管理するために選んだ人のことで、弁護士が選ばれることが一般的です。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
孤独死した故人が生活保護受給者だった場合
孤独死した故人が生活保護受給者だった場合の葬儀費用は、相続人が負担しなければなりません。
一般的に生活保護を受けている人は、近くに頼れる親族がいない場合が多く、亡くなった時に初めて自分が相続人であると知らされるケースもあるでしょう。
法定相続人は民法によって定められていますが、相続したくない場合は相続放棄をすることもできます。
遺族以外が葬儀をする場合には「葬祭扶助」を事前に申請すれば、自治体からの給付を受けて葬儀ができます。
葬祭扶助での葬儀は、火葬のみの直葬となります。
活用できる葬儀費用の補助金制度

孤独死した人の葬儀をする場合、公的制度や健康保険制度のなかで葬儀費用を補助できるものがあるため、ご紹介します。
葬祭費
葬祭費は、故人が国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度に加入していた場合、喪主に対して支給されるものです。
受給額は自治体によって異なり、首都圏の場合は3万円〜7万円で、亡くなった翌日から2年までの間に自治体窓口で手続きを行います。
ただし、通夜や告別式をしない火葬のみの直葬は、対象外となる場合がありますので注意が必要です。
埋葬料
埋葬料は、故人が国民健康保険以外の健康保険または全国健康保険協会に加入しており、申請者が故人の収入で生活していた場合、申請により受給できます。
受給額は5万円で、亡くなった翌日から2年までの間に社会保険事務所か健康保険組合に申請します。
申請者が故人によって生計を維持していない場合は、埋葬料ではなく「埋葬費」として申請をすることになります。
受給額は上限5万円で、亡くなった翌日から2年までの間に申請します。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
孤独死を避けるために今からできること
孤独死は避けるために、一人暮らしの方が今からできることをご紹介します。
一人暮らしの方は周囲の人とのコミュニケーションが重要
一人暮らしをしている高齢者の男女比をみると、女性の割合が高いのですが、孤独死で発見されるのは男性の方が多いとされています。
女性は近所や友人などとのコミュニケーション能力が高いのに対し、男性は仕事を退職してしまうと、一人で活動しがちであることも起因しています。
普段から周囲の人とコミュニケーションが取れていれば、何か起きた時に気づいてもらえる可能性が高くなりますので、コミュニケーションは重要です。
訪問サービスの利用
孤独死を防ぐためには、自治体、社会福祉法人、民間を問わず、さまざまな訪問系のサービスを利用するという手もあります。
訪問介護、日用品の宅配、配食サービスなど、自宅に来てもらえるサービスを通し、サービススタッフと日頃からかかわりを持っておけば、いざという時にも安心です。
身寄りがない方が生前にやっておくべき準備

一人暮らしで、周囲に頼れる親族や知人がいない方にとっての心配事の一つが「自分が亡くなった時の後始末」です。
体も心も元気なうちに、万が一への備えをしておきましょう。
葬儀の事前相談と準備
自分が望むような最期にしたい、他者に負担をかけたくないという方は、「葬儀の生前契約」を検討してみてはいかがでしょうか。
どんな葬儀をしたいのか、誰を呼びたいのか、納骨はどうするのかなど、希望するプランを事前に契約し、亡くなった時にはプランに従って葬儀をしてもらうものです。
菩提寺がある場合は、生前契約の中で納骨先に指定しておき、住職には生前契約を結んでいることを伝えておけば、スムーズな供養につながります。
さらに葬儀だけでなく、死後の年金や公共料金などの手続き、自宅の遺品整理などもやってもらいたいという方は、死後事務委任契約書の作成をおすすめします。
遺言書やエンディングノートの作成
身寄りのない方には、遺言書やエンディングノートは必要ないと考えがちですが、自分の葬儀や財産などについて、文書に残しておくのは大切なことです。
相続人のない方に財産があった場合、遺言書などで財産の処分方法が指定されていなければ、最終的には国庫に入ってしまいます。
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、法律に従って財産分与などについての遺言者の意向を記しておき、死亡後に効力を発揮します。
遺言書の内容を実行する遺言執行者の指定もでき、身寄りのない方であれば、友人や知人を選ぶことも可能です。
エンディングノートは、終活を進めていく際、自分のことを記録しておくために作成するものです。
自分の身の回りの人のこと、不動産を含む財産のことをはじめ、受けたい終末期医療や希望する葬儀の方法、さらには「伝えたい思い」まで書き記しておきます。
自分が元気で、判断能力があるうちに、エンディングノートを作成しておくようお勧めします。
遺品整理業者と相談
遺品整理業者は、身寄りのない方が亡くなった時、所有物だった家財道具を処分する業務を請け負います。
業者の中には、遺品整理について生前契約のサービスを行っているところもありますので、希望する方や不安のある方は相談してみるといいでしょう。
生前契約の方法は、業者スタッフがご自宅を訪問し、家の間取りや家財道具などを見て、引っ越し時と同様に見積もりをします。
家財道具が多いと感じたのであれば、生前のうちに整理をしておくようにします。
アパートなど貸家に住んでいる方は、遺品整理業者と生前契約を結んでおけば、万が一の際にもオーナーや持ち主にご迷惑をかけずに済むというメリットがあります。
成年後見制度の利用
任意後見制度は、判断能力が衰える前に、自らの意志で将来の財産管理や身上監護を任せることができる制度です。
高齢者と任意後見受任者が「任意後見契約」を締結することで成立します。
この契約は公証役場で公正証書として取り交わされ、高齢者の意志に基づいて内容を設定することができるため、任意後見受任者として法律専門家との契約が推奨されています。
また、死後の手続きをスムーズに進めたい場合は、遺品の整理や葬儀の手配など、具体的な内容を契約で定める「死後事務委任契約」も考慮すると良いでしょう。
成年後見制度に関するさらなる情報や相談を希望する場合は、法務省民事局の公式サイトの参照や地域の行政機関や法律専門家にも相談することが可能です。
適切な契約を締結し、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、安心した高齢期を迎えることができます。
福祉事務所等を利用する
孤立している高齢者や身寄りのない方が生活の中で困ったことや疑問を抱えたときに相談できる場所として、福祉事務所が設けられています。
福祉事務所は、市区町村役場の福祉課や地域包括支援センター、福祉相談窓口として機能しています。
地域包括支援センターには、保健師やケアマネージャーなどのプロフェッショナルが常駐し医療から介護、さらには日常生活の福祉に関するアドバイスや情報提供を行っています。
専門スタッフが家庭訪問や、個別の面接を通じて生活状況や資産を把握することで生活指導を行っているため、一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートが可能になっています。
このような施設や窓口を活用することで、孤独や不安を感じる高齢者でも、地域社会とのつながりを保ちながら安心して生活することができるようになります。
どの施設が近くにあるのか、どのようなサービスが受けられるのか、知らない方は最寄りの市区町村役場に一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
地域の福祉サポートを最大限に活用し、より豊かな日常を手に入れる手助けとなることでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
孤独死の葬儀後にする手続き

孤独死の遺体を引き受けた遺族は、葬儀後にも多くのすべき事があります。
契約しているものの名義変更手続き
葬儀後、故人が契約していたものの名義変更手続きをしなくてはなりません。
主に次の物の名義変更手続きが必要です。
- 公共料金…主に電気、ガス、水道です。それぞれの営業センターなどに電話して、手続きを行います。故人名義の口座で引き落としになっている場合は預金口座の変更手続きも行います。
- 携帯電話…大手キャリアの場合、店頭で手続きを行います。
- クレジットカード…名義変更は出来ません。解約手続きを行います。
カード会社によって、死亡の確認書類や解約申請書類の提出が必要な場合があります。
相続についての話し合い
遠い親戚で孤独死した人のことを知らなかったとしても、相続人になる資格者は相続手続きをしなくてはなりません。
まず、相続するか、放棄するかを決めるため、故人の財産を調査します。
相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に、申立てする必要があるので、すみやかに行います。
故人に借金があり、相続放棄する前に支払ってしまうと相続放棄ができなくなるので要注意です。
また、不動産の相続は、自己所有でも賃貸でも事故物件として価値が大きく下がるため、売却が難しいのが現状です。
賃貸物件の場合、オーナーから損害賠償を受ける可能性があることも知っておきましょう。
それでも相続することを決めたら、手続きを開始します。
相続の申告と確定申告には期限があるので注意が必要です。
遺品整理
相続する場合、早急に遺品整理を行わなくてはなりません。
相続放棄する場合は、遺品整理をしてしまうと放棄できなくなるので、注意が必要です。
遺品整理業者に依頼する
遺族が故人の身辺整理をする際、生前どんな暮らしをしていたのかがわからず、とくに手続きが必要な契約関係がどうなっているのか、把握できないというケースが考えられます。
遺品整理業者は、依頼された遺族に代わって遺品の仕分け、片付け、処分、買い取りなどをします。
遺品整理中の業者が、契約関係の書面や領収書を探し出してくれますので、それをもとに遺族が手続きを行えば安心です。
遺品整理を担う特殊清掃業者もありますので、特殊清掃が必要な時は併せて相談してみるのもいいでしょう。
遺品整理業者の選び方
遺品整理業者の中には、遺品を不法投棄したり、高額な料金を請求したりする悪質業者もいますので、慎重に見極めて選ぶ必要があります。
ただ、普段の生活で遺品整理業者とかかわることがないため、どんな基準で選べばいいのか分からないという方も多いでしょう。
問い合わせをした際の電話応対の雰囲気やホームページの分かりやすさを参考にし、訪問見積もりの有無や業務に必要な許可・届出をしているかどうかを確認しておきます。
見積もりをした段階では、見積書の作業内容と料金が明確かどうか、追加料金についての記載があるかどうかをチェックし、複数の業者の見積もりを比較検討するといいでしょう。
孤独死の状況次第では特殊清掃を依頼する
孤独死が発生すると、部屋内は遺体の腐敗臭が充満し、発見が遅れた場合、害虫や害獣の侵入の可能性も高まります。
これにより、病原菌やウィルスが急増し、部屋の空気には感染リスクが伴うため、事故物件を原状回復する専門の特殊清掃業者への依頼が必要になります。
特殊清掃業者は、特別な方法や薬剤を使った部屋の消臭と消毒、害虫駆除などを行い、会社によってはリフォームや家の解体にも応じています。
賃貸物件の場合は、まずは大家さんや住宅管理会社に対応方法を相談することから始め、警察の入室許可が下りたところで、速やかに特殊清掃をしてもらうようにします。
特殊清掃業者の中には、高額な料金を請求してくるところもありますので、最初から明確な料金を提示するなど、優良な業者かどうかを見極めることも大事です。
相続についてもこちらで詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
孤独死のよくある質問
孤独死のよくある質問をご紹介します。
孤独死した際、住んでいた家が賃貸住宅だった場合、契約はどうなるのか?
1. 大家・管理会社へ連絡
まずは遺族や関係者、あるいは警察などが孤独死を確認した際、大家さん(貸主)や管理会社に連絡します。
2. 賃貸借契約の解除
亡くなった時点で、賃貸契約は「契約者死亡による終了」として扱われるのが原則です。
ただし、保証人がいる場合には、保証人が契約解除の手続きを行ったり、残置物の撤去などの責任を負うことがあります。
3. 室内の特殊清掃
孤独死の状況(時間経過や発見の遅れ)によっては、部屋が腐敗臭や汚染によって通常の清掃では対応できない場合が多いです。そのため、特殊清掃業者が入り、消臭・清掃作業が行われます。
この費用は一般的に故人の遺産(預金など)や保証人が負担することになりますが、残置物処理費用や修繕費の一部をめぐってトラブルになることもあります。
4. 賃貸物件のその後
事故物件として扱われるかどうかは、孤独死の状況(事件性の有無や死後の時間経過、清掃の程度など)によって判断されます。事件性がない自然死であっても、孤独死というだけで心理的瑕疵物件として告知義務が発生するケースが多いです。
(宅地建物取引業法で告知義務があるとされるのは、概ね次の入居者の募集時までです。)
5. 残置物の処理
部屋に残された家具や荷物は、原則として遺族や相続人が引き取ります。
相続放棄された場合などは、貸主側で一定の手続きを経て処分されることがあります(相続人不存在の場合は家庭裁判所の手続きが必要)。
孤独死した場合の火葬代はいくらですか?
孤独死は、警察への対応や部屋の特殊清掃などで費用が掛かるケースが多いため、火葬のみを選ぶ遺族がほとんどです。
火葬のみの場合の費用相場は、20万円~30万円程度となっています。
孤独死した場合の葬儀費用は誰が払いますか?
一般的に葬儀の費用は、葬儀を執り行った喪主が支払います。
喪主は、故人の子供や配偶者、親族が就くことになります。
親族がいない場合は、法定相続人や扶養義務者に請求されたり、故人の遺産から支払われたりすることもあります。
孤独死はどうやって発見されますか?
多くの場合、遺体が腐敗して起こる悪臭に近隣の人などが気づいて発見されています。
また、郵便受けに新聞や手紙がたまっていることから、不審に思われて発見されることもあります。
孤独死した遺体はいつ火葬しますか?
孤独死した人々の遺体は多くの場合、現地で火葬されることが一般的です。
これは、遺体が腐敗している可能性が高く、公衆衛生に影響を与えるためです。
公営の火葬施設を利用する際には、住民登録している自治体での手続きが費用面で有利とされています。
身元不明や遺族が存在しないケースでは、地元の自治体が「無縁塚」に埋葬することもあります。
このような措置は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づいて行われます。
また、遺体の搬送には一般車両は使用できず、専用の霊柩車を手配する必要があり、特に遠距離の場合、その費用はさらに高額になります。
親族の孤独死に関する対応とは?
親族から孤独死の知らせを警察経由で受けた場合、何を始めにすべきか心配です。
まずは遺体を迅速に自宅や専門の安置施設に搬送する必要があります。
孤独死の際、遺体は現地で火葬されることが多く、お骨の形で返されることが一般的となっています。
適切な手続きを進めるための知識を持つことが大切です。
孤独死時、親族が遺骨を引き取らない場合、どうなるの?
孤独死を迎えた方の遺骨の行方は、多くの方が気になるところでしょう。
もし親族が存在していても、さまざまな理由で遺骨の引き取りを拒否する場合があります。
親族が存在しない場合や、遺骨の引き取りを拒否された場合、その遺骨や遺品の管理は自治体が担当します。
しかし、自治体が永遠に遺骨を保管するわけではありません。
大抵の自治体では、遺骨の保管期間が設けられており、その期間は自治体によって異なるものの、多くは約5年程度とされています。
この期間を超えると、その遺骨は「無縁塚(むえんづか)」にまとめて埋葬されます。
無縁塚は身寄りのない方の遺骨が集められる場所で、後から個別に取り出すことは不可能です。
ただし、きちんとした埋葬の手続きが行われるので、故人の魂の安息を願う意味でも、適切な処置が施されていると言えます。
身内が孤独死した場合、遺体の受け取りを拒否すると、どのような法的・財産的影響が生じるのでしょうか?
身内が孤独死した場合、遺体の受け取りは法的に義務付けられていません。
受け取りを拒否することは可能です。
ただし、受け取りを拒否した故人は「行旅死亡人」として扱われ、自治体により直葬されることとなります。
この葬儀の費用は、故人の遺産から支払われることになります。
財産が不足している場合、遺族が費用を負担することもあります。
また、遺体の受け取り拒否と相続放棄は異なるので、相続権は依然として存在します。
そのため、故人の借金や負の遺産を相続するリスクも考慮しなければなりません。
遺体受け取りや相続に関する疑問や不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
不審死とは?
不審死は、死亡の状況が異常、不詳、または死因が不明または特定できない死を指します。
具体的には、目撃者が不在で一人で亡くなった場合や発見段階で死因が明確でない場合などに「不審死」として扱われます。
特に、孤独死のシチュエーションでも、基本的には不審死としての手続きや処理が行われることが多いです。
遺体を引き取る遺族や身元が不明の場合、遺体はどのように取り扱われますか?
遺体に関して遺族が存在しない場合や身元が全く不明である場合には、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という特定の法律に基づき、地元の自治体が責任をもって火葬を実施します。
また、遺骨に対しても引き取る方がいない場合、一定の保管期間後に「無縁塚」と呼ばれる場所に埋葬される手続きが行われます。
夏場と冬場、遺体がどのように腐敗し、臭いを放つのかの違いは何ですか?
遺体の腐敗と臭いの発生は季節や気温に大きく影響されます。夏場、特に梅雨が明けた後、気温が急激に上昇すると、遺体の腐敗が加速します。
部屋の中は40℃~50℃にも達することがあり、これにより発酵が早まり、ウジも湧きやすくなります。結果として、夏場は死後約2日で強烈な死臭を放つことが一般的です。
対照的に冬場は、気温が低いため、また部屋が冷蔵状態になるケースもあり、腐敗の進行が遅れます。
しかし、冬でもハエなどが遺体に卵を産み付けることはあり、これが孵化することで臭いが発生します。
通常、冬場は死後約2週間くらいで強烈な死臭を発するようになります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
孤独死の葬儀についてのまとめ

ここまで孤独死の葬儀の流れや、孤独死の葬儀費用の負担は誰がするのかについてお伝えしてきました。
孤独死の葬儀の流れは次のとおりです。
- 孤独死の流れは、発見→警察による現場検証→遺族に連絡→遺体引き渡し→遺族による葬儀→埋葬
- 遺族がいない場合は自治体で葬儀、埋葬
- 孤独死の葬儀の費用は遺族が負担して、遺族がいない場合は自治体が負担します。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から火葬対応の葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.11.19
近所の人の出棺の見送りへは行くべき?服装の注意点は?
お葬式

更新日:2024.01.24
「荼毘に付す(だびにふす)とは?意味や使い方、例題でわかりやすく
お葬式

更新日:2024.01.24
火葬の時にピンク色の遺骨があるのはなぜ?収骨拒否についても解説
火葬

更新日:2022.05.11
火葬場で挨拶は必要?喪主の挨拶の注意点と文例を解説
お葬式

更新日:2024.01.24
箸渡しのマナーとは?箸渡しの意味や流れなどについて解説
お葬式
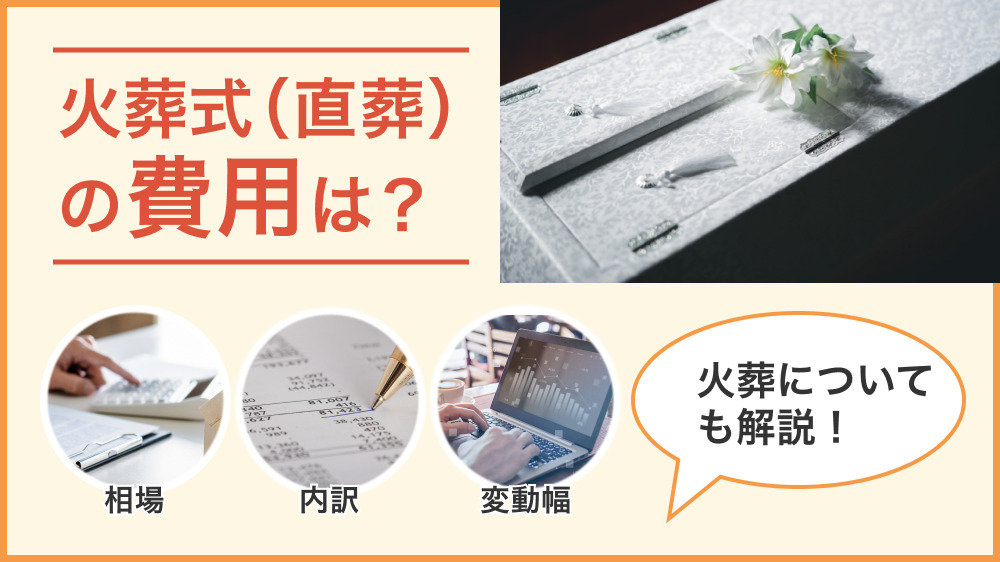
更新日:2025.06.29
葬式なしの火葬費用の相場は?直葬・火葬式の費用を抑える方法についても併せて解説





