法事法要
年忌法要はいつまで続ける?年忌法要のやめ方についても紹介
更新日:2023.11.19 公開日:2022.07.24
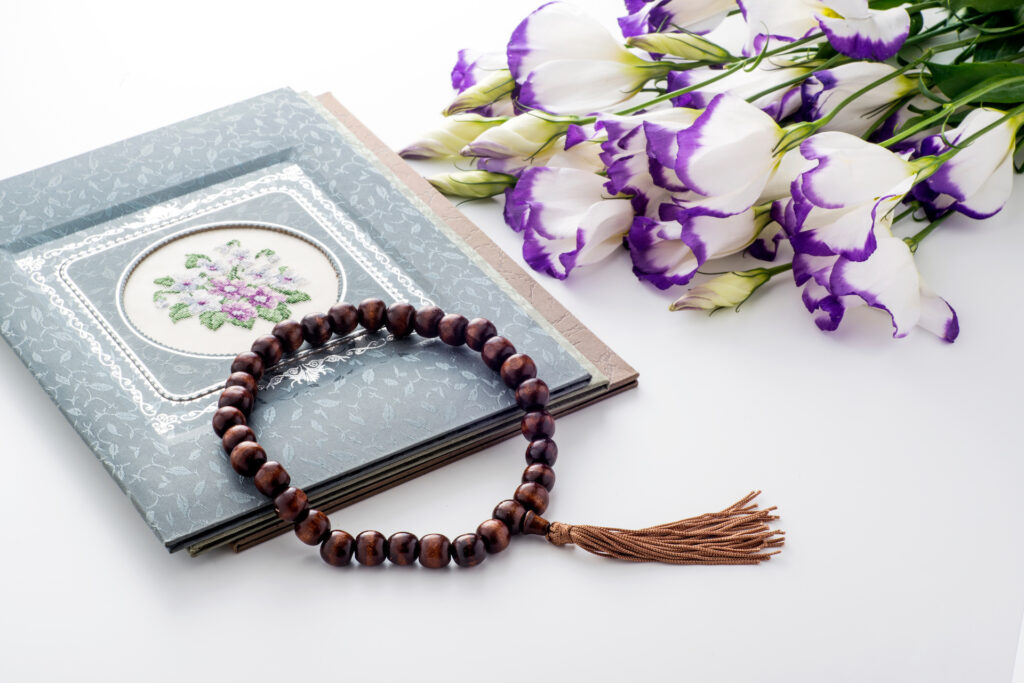
記事のポイントを先取り!
- 年忌法要は三十三回忌で弔い上げする場合が多い
- 弔い上げのタイミングや考え方は宗派によって異なる
- 弔い上げのお布施は3万〜5万円程度が相場である
年忌法要は故人の供養のための大切な儀式ですが、いつまで続けるべきなのかはご存知でしょうか。
年忌法要の正しい情報を知ることで、故人の供養にもつながります。
そこでこの記事では、年忌法要をやめるタイミングについて詳しく説明していきます。
この機会に年忌法要のやめ方についても知っておきましょう。
宗派や宗教ごとの弔い上げのタイミングについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
年忌法要とは
まずはそもそも年忌法要とはどういったものなのか紹介していきます。
年忌法要とは、故人が亡くなられた月や亡くなられた日に執り行われる供養のための仏事になります。
親族が集まり、僧侶の読経やお墓参りにて故人を偲びます。
年忌法要は三回忌や七回忌などの決まった年数で行われることが一般的です。
年忌法要を執り行うことで、追悼供養となり故人が成仏することにつながるとされています。
なお、年忌法要の規模や意味合いは地域や寺院、宗派によって違ってきます。
主な年忌法要一覧
次に年忌法要の計算方法や一覧を紹介していきます。
以下で詳しく説明していきますので参考にしてください。
年忌法要の計算式
一周忌は故人が亡くなってから初めての年忌法要で、亡くなった翌年に執り行われます。
三回忌以降の計算方法は以下の通りです。
回忌数-1=何年目に行うか
例)三回忌は何年目に行うのか?
3(回忌)-1=2年目
これらのことから三回忌は故人が亡くなってから2年目に執り行うということがわかります。
この式に当てはめれば、簡単に何年目に行うのかわかります。
年忌法要一覧
年忌法要の一覧を以下にまとめます。
- 一周忌(いっしゅうき):亡くなってから満1年目の命日
- 三回忌(さんかいき):満2年目の命日
- 七回忌(ななかいき):満6年目の命日
- 十三回忌(じゅうさんかいき):満12年目の命日
- 十七回忌(じゅうななかいき):満16年目の命日
- 二十三回忌(にじゅうさんかいき):満22年目の命日
- 二十七回忌(にじゅうななかいき):満26年目の命日
- 三十三回忌(さんじゅうさんかいき):満32年目の命日
- 三十七回忌(さんじゅうななかいき):満36年目の命日
みんなが選んだ法事法要の電話相談
みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
5万円からご案内!
4万円からご案内!
年忌法要はいつまでやるの?

次に年忌法要はいつまでやるべきなのか紹介していきます。
以下で詳しく説明していきますので参考にしてください。
一般的には三十三回忌でやめる
三十三回忌を最後として法要を終えることが一般的です。
この理由として、仏教では三十三回忌を過ぎれば、故人はご先祖様の仲間入りをして仏様になるとされているためです。
また、死後30年程経過すると世代も代わるため、故人のことを知っている人もかなり少なくなることも理由の1つです。
これは永代供養墓であっても同様で、多くの場合、個別で供養していたとしても三十三回忌を過ぎると、合祀墓での管理に変わります。
三十三回忌前にやめる場合もある
三十三回忌で法要を終えることが多いのですが、やめる時期は地域や宗派によって違います。
最近では核家族化によって遠方で親族が生活しているケースも多いので、法要の回数を減らす傾向にあります。
また、共働き世帯が年々増えており、仕事や子育てなどから忙しく生活する中で、なかなか親族で集まれなくなったことも影響しています。
このように、さまざまな理由から四十九日を最後にする家庭もあります。
年忌法要のやめ方
年忌法要を最後にするときには、「弔い上げ」をすることが一般的になります。
ここからは弔い上げについて詳しく説明していきます。
費用の相場、位牌や仏壇の取り扱い方などを紹介しますので、以下を参考にしてください。
やめる際には弔い上げをする
法要に区切りをつけるときには、最後の法要を「弔い上げ」と呼び、盛大に執り行うことが一般的です。
弔い上げは別名、「問い上げ」や「上げ法要」、「揚げ斎(あげどき)」などと呼ばれることもあります。
弔い上げをすることで、長年の法要で供養してきた故人の魂は成仏して極楽浄土に行けるとしております。
弔い上げの費用
弔い上げをする際には、僧侶にて読経していただく形になりますので、僧侶に関してお礼の気持ちを込めてお布施を渡すことがマナーになります。
弔い上げでは普段よりも念入りに供養するので、お布施も一般的な法要よりも多く包むことが一般的です。
相場としては3万〜5万円程度になりますが、お布施はあくまでも気持ちになりますので、明確に決まっているわけではありません。
位牌や仏壇はどうすれば良い?
法要を最後として弔い上げした場合には、位牌や仏壇はどうすれば良いのか疑問に思われる方もいるかと思います。
位牌は魂抜きをしてからお焚き上げすることをおすすめします。
寺院に依頼するケースが多いですが、仏具店や葬儀社でも引き受けてくれることがあるので、確認してみるといいでしょう。
故人の位牌は先祖位牌にまとめることで、その後も供養していけます。
仏壇については、そのまま使用できますので安心してください。
みんなが選んだ法事法要の電話相談
みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
5万円からご案内!
4万円からご案内!
宗派ごとの弔い上げのタイミング
次に宗派ごとの弔い上げのタイミングについて紹介していきます。
三十三回忌で弔い上げとする宗派が多く、具体的には真言宗や曹洞宗、臨済宗、日蓮宗、浄土真宗などが挙げられます。
真言宗では三十三回忌が終わったあとも五十回忌や百回忌、百五十回忌まで執り行われるケースがあります。
曹洞宗では五十回忌法要まで執り行われることが多いようです。
日蓮宗や浄土真宗では、弔い上げの概念がそもそもありません。
この理由として浄土真宗では、成仏するといった考え方はなく、人は亡くなるとすぐに成仏して極楽浄土に行けるとされているためです。
宗教ごとの弔い上げのタイミング
次に宗教ごとの弔い上げのタイミングについて紹介していきます。
以下で神道とキリスト教について詳しく説明していきますので参考にしてください。
神道の場合
神道では、人は亡くなると遺族や子孫にとっての守護神になると考えられております。
仏教と同じように死後1年、3年などの節目ごとに「霊祭」と呼ばれる儀式が行われます。
神道では三十年祭に「荒御霊(あらみたま)」が温厚な「和御霊(にぎみたま)」になるとされ、これを区切りに弔い上げが執り行われることが一般的になります。
キリスト教の場合
キリスト教で「死」は、仏教のように不幸なことであるとは考えず、祝福すべきことであるとされています。
そのため、仏教のように長い年月を法要などで供養するといった概念はありません。
キリスト教では追悼の儀式が行われますが、これは成仏することを祈るのではなく、故人に感謝するために行われるものになります。
死後1年である命日に盛大な祭りが執り行われ、これが一周忌にあたります。
キリスト教においては、一周忌以降の儀式に明確な決まりはなく、弔い上げといった概念はありません。
みんなが選んだ法事法要の電話相談
みんなが選んだ法事法要では葬儀や法事法要のご相談に対応しております。 お悩みにある方はご相談ください。
24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
5万円からご案内!
4万円からご案内!
忌日法要とは
最後に、忌日法要(きにちほうよう)について紹介していきます。
忌日法要の意味合いについて以下で説明していきますので参考にしてください。
忌日から7日ごとに行われる法要
忌日法要とは、故人の命日から7日ごとに執り行われる法要のことです。
法要のタイミングを以下にまとめます。
- 初七日(7日目)
- 二七日(14日目)
- 三七日(21日目)
- 四七日(28日目)
- 五七日(35日目)
- 六七日(42日目)
- 七七日(49日目)・満中陰
- 百カ日(100日目)・卒哭忌
百箇日とは
百箇日(ひゃっかにち)とは、故人が亡くなられてから100日目のことを指します。
このときに執り行われる法要のことを「百箇日法要」と呼びます。
仏教では百箇日に平等王(びょうどうおう)による再審が行われるとされており、この日に法要することで故人が良い方向に進むことを後押しすると考えられています。
年忌法要はいつまでまとめ

ここまで年忌法要はいつまで続けるべきなのかを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 年忌法要とは、故人が亡くなられた月日に執り行われる供養のための仏事のこと
- ライフスタイルの変化から年忌法要の回数は年々減らす傾向にある
- 忌日法要とは、故人の命日から7日ごとに執り行われる法要のことである
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
法事法要の関連記事
法事法要

更新日:2022.02.19
一周忌の法要は欠席しても大丈夫?欠席する場合のマナーを解説
法事法要

更新日:2024.01.24
四十九日が過ぎるまで遊びに行くのはダメ?他にもNGな行動を紹介
法事法要

更新日:2022.05.17
弔い上げ(三十三回忌)をしないという選択について
法事法要

更新日:2025.03.20
会食なしの法事でも御膳料は必要?相場や書き方についても解説
法事法要

更新日:2022.11.21
法事で食事なしはマナー違反?食事の代わりやおすすめの引き出物を紹介
法事法要

更新日:2022.08.21
七回忌のお供えには何を用意すれば良い?相場やNGな物も紹介







